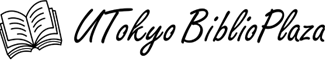大学入試に漢文を課す大学は、今やすっかり少なくなりましたが、それでも毎年共通テストの時期になると、「古文・漢文不要論」がネット (の一部) で盛り上がります。本書は、正面からその話題を扱ったのではありませんが、近代日本の高等教育とりわけその中心であった東京 (帝国) 大学において、学問としての「漢学」がどのように取り扱われ、議論され、生き延びてきたのかを論じました。
江戸時代まで普通、「学問」と言えば漢学、とりわけ儒教を指しました。国学や蘭学 (洋学) もあっただろうと思われるかもしれませんが、たとえば各藩にあった藩校、江戸の中枢にあった徳川政権直轄の「昌平坂学問所」で教えられていた「学問」とは基本的に漢学、とりわけ儒教でした。寺子屋で一通りの手習を終えた子供たちが更に「学問」を学びたいと思ったら、次は四書五経の素読を教わるのが普通でしたし、国学者や蘭学者も、まずは幼少期に「学問」のスタンダードとしての漢学を通過してから、「そうではない」学問としての国学や蘭学などへ転じていったのです。
明治維新を経て、この大前提が大幅に崩れました。「学問」と言えば西洋の学問を指す時代が到来したのです。明治初期においては漢学塾もなお命脈を保ちましたが、小学校から始まり大学に至る近代学制が整備されるに従って、漢学を学ぶ環境は大幅に縮小していきました。
このことは、東京大学において顕著かつ象徴的に現れています。明治10 (1877) 年に設立された東京大学は、東京開成学校と東京医学校の書類上の合併によって生まれた大学です (明治19年に帝国大学、明治30年に東京帝国大学と名前を変えます)。東京開成学校は主として英米人が英語で英米法や自然科学を教える学校であり、東京医学校はドイツ人がドイツ語で医学を教える学校でした。それらが合併して生まれた東京大学は、草創期においては特に「西洋人が西洋語で西洋の学問を教える学校」であって、この学校が、やがて近代学制の頂点として位置付けられることになります。
困ったのは漢学者たちでした。創設まもない東京大学においても漢学は細々と教えられてはいましたが、従来の慣習を改められない、あるいは手探り状態の漢学者達は、次第に「学問」のあるべき姿がすっかり変わってしまった現実に直面せざるを得なくなります。時代に相応しい新たな漢学の姿を探ろうとする者たち、漢学の伝統を守ろうとする者たち、あるいは漢学に破壊的改革を要求する、旧来の漢学からは自由な新時代の人々、その中で次第に立ち上がって来る、現在の「中国思想史」「中国哲学」という学問に繋がる「支那哲学」の姿。
かつて覇権を握った伝統学術が、大きな時代の変革に直面し、その存在意義を真剣に問われた時、それはどのように揺さぶられ、また生き残ろうとしたのか。その中心的な現場であった東京 (帝国) 大学を舞台として描こうとしたのが本書です。
(紹介文執筆者: 水野 博太 / 2024年12月25日)
本の目次
1 本書の問題意識と分析範囲
2 先行研究とその課題ならびに本書の新規性
3 本書の構成
第1章 漢学から「支那哲学」へ――草創期の東京大学および前身校における漢学の位置と展開
はじめに
1 東京開成学校における漢学の位置づけ
2 草創期の東京大学における漢学の位置づけ
3 草創期の東京大学における漢学講師の人選
4 草創期の東京大学における漢学教育の実態
5 漢学の転換
おわりに
第2章 漢学から「日本哲学」へ――井上哲次郎による世界発信の挑戦とその挫折
はじめに
1 日本人に哲学は可能か
2 「東洋哲学」「日本哲学」の模索
3 「日本哲学」はあるか
おわりに
第3章 漢学から「実用支那学」へ――井上(楢原)陳政を中心とした明治期の漢学改革論
はじめに
1 重野安繹の漢学改革論
2 井上(楢原)陳政の漢学改革論
3 帝国大学周辺の漢学改革論
4 島田重礼の漢学および「支那哲学」観
おわりに
第4章 「孔子教」の前提――島田重礼と服部宇之吉
はじめに
1 島田重礼について
2 初期服部宇之吉の学風
3 服部の留学と周辺人脈
おわりに
第5章 漢学から「孔子教」へ
はじめに
1 服部のドイツ留学とKonfucius
2 Konfuciusにおける「天命」(Schicksal)
3 もうひとりの「孔子教」論者――大西祝との視点の差異
4 辛亥革命と「孔子教」論の形成
5 論敵の確定と「孔子教」論の形成
6 方法としての古典とその限界
7 「孔子教」の到達点
おわりに
終章 中心と周縁
関連情報
第5回東京大学而立賞受賞 (東京大学 2024年)
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/research/systems-data/n03_kankojosei.html
書評:
中川未来 (愛媛大学法文学部准教授) 評 (『日本思想史学』第57号 2025年)
http://www.perikansha.co.jp/Search.cgi?mode=SHOW&code=1000001986
苅部直 (政治学者・東京大教授) 評「国際的交流・対話の成果」 (本よみうり堂|読売新聞オンライン 2025年2月14日)
https://www.yomiuri.co.jp/culture/book/reviews/20250210-OYT8T50074/