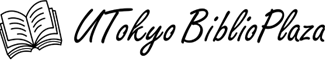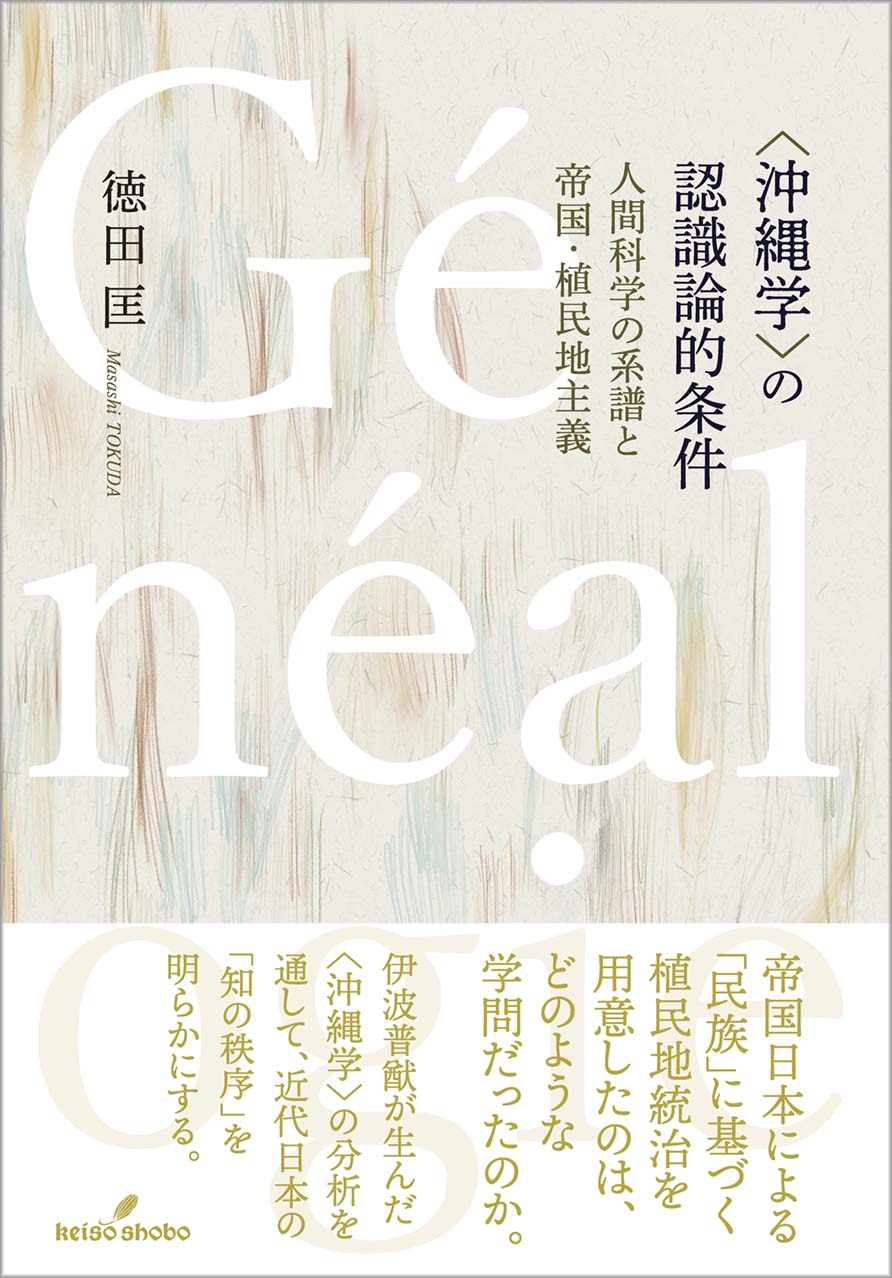
書籍名
〈沖縄学〉の認識論的条件 人間科学の系譜と帝国・植民地主義
判型など
432ページ、A5判
言語
日本語
発行年月日
2024年10月
ISBN コード
978-4-326-20067-2
出版社
勁草書房
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
この本は、以下のような問いに関心を持つ方におすすめです。「人種・民族・ネーションなどが『歴史』を持つとはどういうことか?」「人種・民族を『統治する』とはどういうことか?」。
本書は、二〇世紀初頭の比較言語学者である伊波普猷の言説を生み出した認識論的条件である近代日本の人間諸科学と、さらにはその背景にある同時代の帝国・植民地関係のなかで現れる〈民族〉や〈民族性〉の関係について考察しています。タイトルにある認識論的条件とは、ミシェル・フーコーの「エピステーメー」概念を指し、「物とそれらを類別して知にさしだす秩序」を意味しています。
フーコーは一九世紀以降の人間諸科学の成立によって、その考察対象である「人間」が新たに構成されたと論じました (『言葉と物』)。つまり「人間」を知にさしだす秩序が当の「人間」を認識可能にするのです。のちにフーコーは、こうした考えを、人口 (人間集団) にまで広げ、人口を通じた近代の「統治性」を論じました。
この統治性概念を、帝国・植民地関係に応用したのが、近年ポストコロニアル研究で議論されている「植民地統治性」の概念です。本書は、それを念頭に、近代日本における植民地統治の対象である「民族・民族性」(ある性質を持った集合体=人口) が、何のために必要で、どのように作り出されたのか、という問いを探究しています。
具体的には伊波普猷の「日琉同祖論」を含む諸言説に焦点を当てています。その理由は、彼の言説が〈民族〉という近代特有の〈歴史主体〉を描き出したこと、そしてそれが近代日本の人間諸科学の成立と密接に関わっているからです。
本書が扱う近代日本の人間諸科学とは、比較言語学、形質人類学、生物学、社会学、歴史学、郷土史、優生学、精神分析、民族心理学、植民政策学など多岐にわたる分野が含まれます。すべてを解説するのは難しいですが、ごく簡単に本書の内容をまとめると次のようになります。
比較言語学は「音声」という言語の自然性を分析し、言語の歴史を明らかにすることで言語と民族を分離する一方、形質人類学との結びつきによって民族を〈歴史主体〉として位置づけました。この考え方は当時の国体論や民権論と相容れないものでしたが、生物学を基盤とする社会有機体論とも響き合いながら、〈統治〉のための言説を形成していきました。その統治の対象である民族の身体には優生学や民族衛生学が、精神には郷土史や精神分析がそれぞれの矯正や治療の手段として適用され、植民地統治の実践へとつながっていきました。
本書は複雑な内容を扱っていますが、「人種」「民族」「統治」という問題に関心がある方にとって、有益なヒントや視座を与える一冊となるはずです。
(紹介文執筆者: 徳田 匡 / 2024年12月4日)
本の目次
1 はじめに
2 問題の所在
3 本書の分析方法
4 伊波普猷に関する先行研究について
5 本書の構成
第一章 言語と歴史
1 はじめに
2 日琉相似論
3 人種論と比較言語学
4 〈言語そのものの歴史〉
5 人間の「歴史化」
6 言語の歴史と君主権力
7 「P音考」
8 言語の「開放性」
9 言語の伝達可能性
10 古形の保存
11 まとめ
第二章 身体と歴史
1 はじめに
2 分類としての人類学
3 初期人類学の「人種交替説」
4 チェンバレンと上田万年にとっての神話
5 ベルツ説――現在の身体
6 鳥居龍蔵と坪井正五郎
7 計測と歴史
8 形質人類学と比較言語学の循環論法
9 戦後における言語と形質の関係
10 まとめ
第三章 生物学と社会学――有機体論の系譜
1 はじめに
2 生物学――相似から法則へ
3 細胞
4 進化論
5 コント社会学
6 スペンサー社会学
7 「法」と「社会有機体論」
8 まとめ
第四章 人種交替説
1 はじめに
2 旧来的な「歴史」の機能
3 国学者と主権論
4 国民論と天皇論
5 〈歴史〉の浸透
6 「日琉同祖論」と「人種交替説」
第五章 新式の統治法
1 はじめに
2 「古琉球の政教一致」
3 伊波の歴史分析の特徴
4 〈民族〉の政治的本能
5 「新式の統治法」
6 統治法の現在性
7 「現在性」と「規範」
第六章 優生学と精神分析――「民族衛生」と「郷土史」
1 はじめに
2 人種改良と優生学
3 「衛生」という思想
4 社会主義と優生学
5 人種主義
6 「人口」と「旧慣」
7 「進化論より観たる琉球の廃藩置県」
8 民族衛生講話
9 精神分析
10 遺伝と環境
11 まとめ
第七章 帝国と植民地
1 はじめに
2 「生物学の原則」
3 原敬の「内地延長主義」
4 日本の植民政策学の展開
5 「植民」の最終目的
6 「民族自決」と「能力」
7 植民地統治の試金石としての「琉球・沖縄」
8 伊波普猷と「自治能力」
9 補遺――社会化と生政治
終章 知と権力
あとがき
引用・参考文献一覧
関連情報
第5回東京大学而立賞受賞 (東京大学 2024年)
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/research/systems-data/n03_kankojosei.html
書籍紹介:
あとがきたちよみ『〈沖縄学〉の認識論的条件――人間科学の系譜と帝国・植民地主義』 (けいそうビブリオフィル 2024年10月30日)
https://keisobiblio.com/2024/10/30/atogakitachiyomi_okinawagakunoninnshikiron/