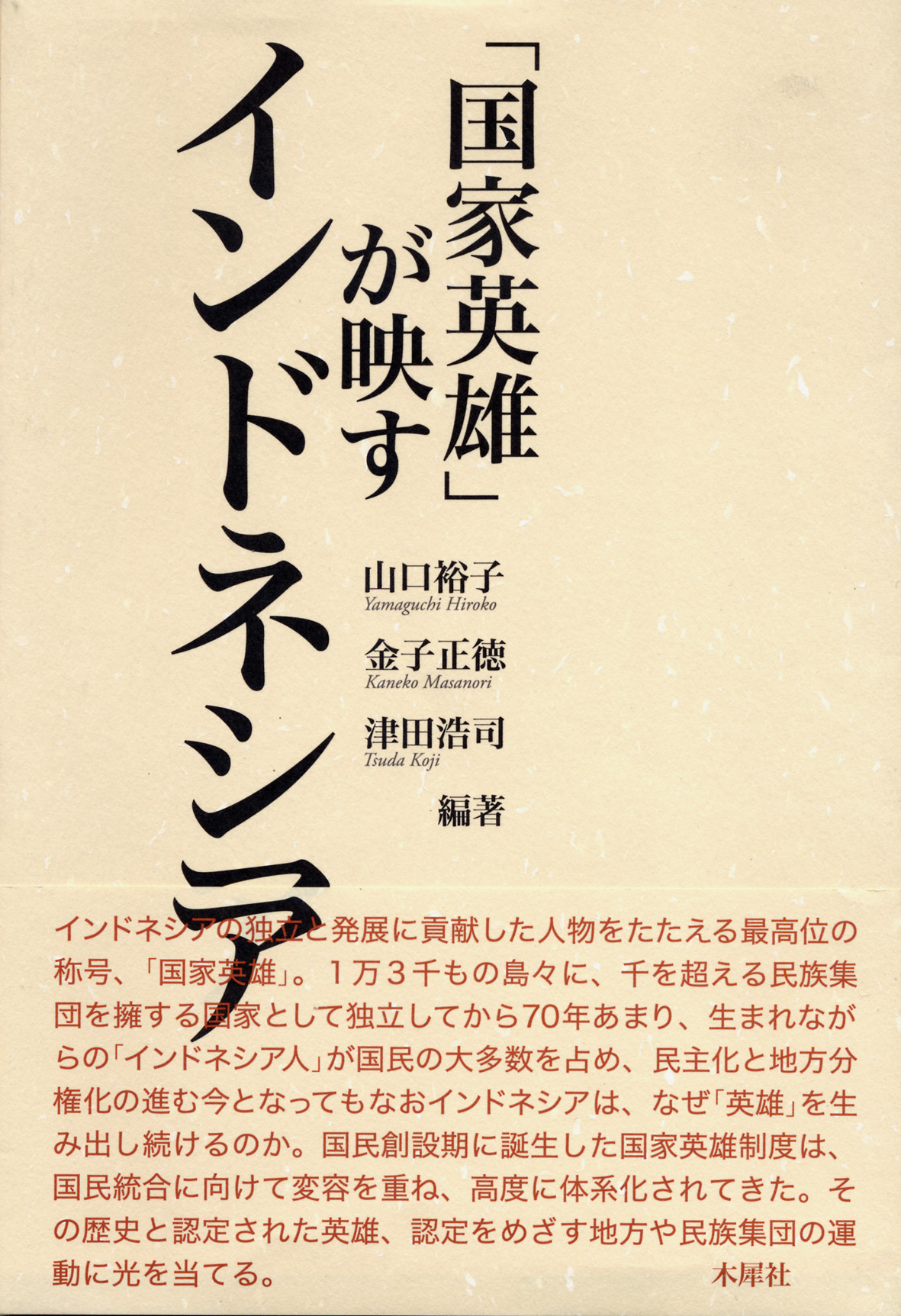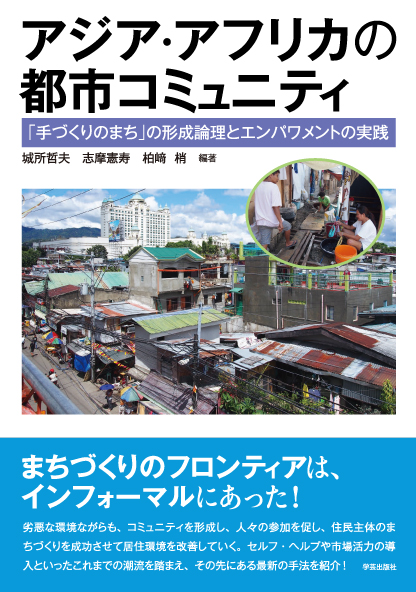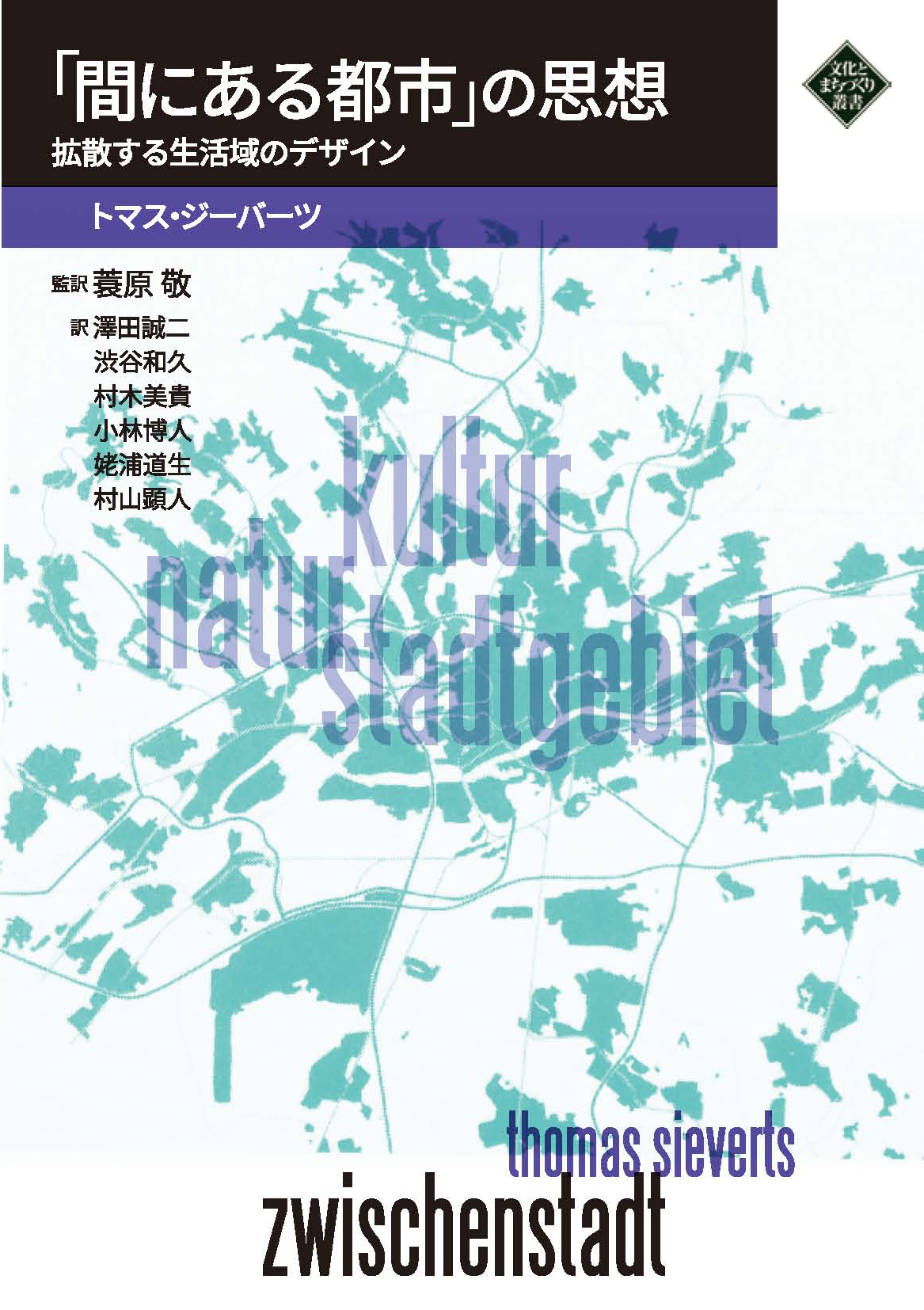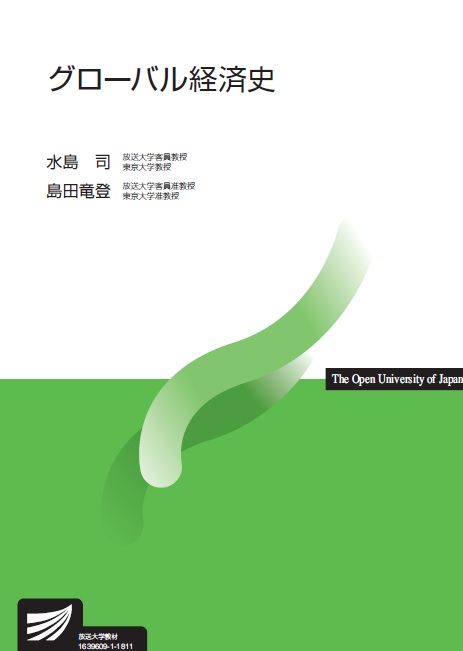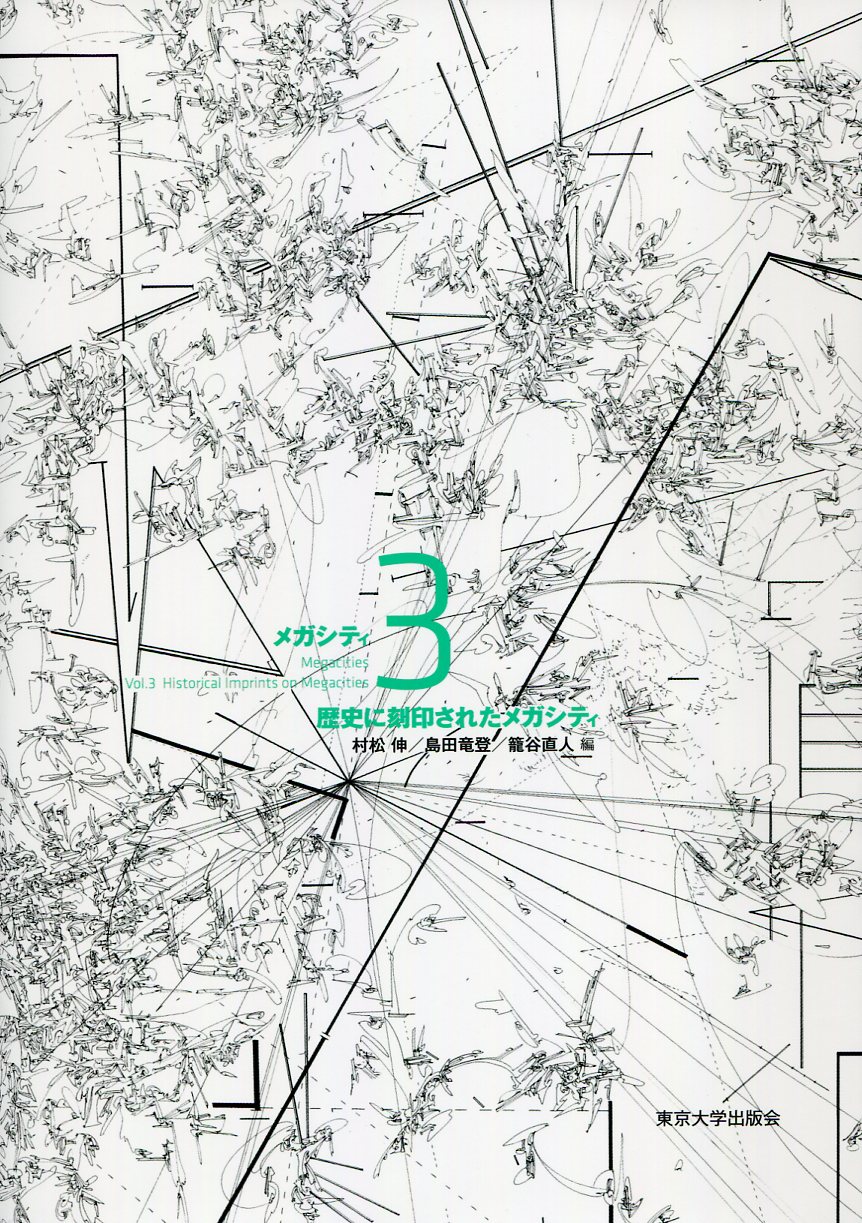
書籍名
メガシティ 3 歴史に刻印されたメガシティ
判型など
272ページ、A5判
言語
日本語
発行年月日
2016年8月23日
ISBN コード
978-4-13-065153-0
出版社
東京大学出版会
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
歴史家はつねに後ろ向きで、過去ばかりを調べている。都市を再生するためには歴史学などは役に立たないのだろうか。そもそも歴史学とはいったい何のためにあるのだろうか。
本書は京都にある総合地球環境学研究所のプロジェクト「メガシティが地球環境に及ぼすインパクト: そのメカニズム解明と未来可能性に向けた都市圏モデルの提案」の研究成果である。全6巻のうちの第3巻目にあたり、ジャカルタの都市開発の歴史を特に自然環境面などから分析する。
熱帯のメガシティであるジャカルタを題材に、都市を住みよいものとするため、そして地球環境にも優しい都市とするために、2010年、このプロジェクトは本格始動した。プロジェクトリーダーは東京大学生産技術研究所の村松伸教授。私はこのプロジェクトで歴史分析を担当した。
ジャカルタはかつてバタヴィアと呼ばれ、17世紀から20世紀半ばにかけてオランダが支配者として創出した近世植民都市である。現在はインドネシアの首都として膨大な人口を抱える。17世紀、オランダ東インド会社がこの地を手に入れたのは、強力な軍隊を持っていたからだけではない。当時、現地の人々があまり顧みることもない、自然環境上あまりよろしくない土地だったのだ。水はけが悪く、洪水は毎年起こる。ジャカルタを訪れたことがある人は知っているだろう。どこまでも続く渋滞、雨期の洪水、あちらこちらのゴミの山。もちろん河川は悪臭が漂う。ジャカルタに住む人に聞いてみればいい。たいてい、ジャカルタは好きではないという。好きではないのに住まなければならないジャカルタって?
この嫌われ者の都市を再生する手掛かりはあるのだろうか。そして歴史学はいかなる貢献が可能なのだろうか。歴史を紐解くと、この都市は、多民族共生の場であり、平和共存につとめた都市であったことが分かる。熱帯都市特有の環境問題にも、様々な知恵が活かされ、その知恵自体も発展してきた。プロジェクト研究に従事して、ある時、私は気づいた。ジャカルタが歴史的に体得してきた様々な知恵を明確にすれば、オリジナリティあふれる都市に改良する手がかりとなるのではないかと。その知恵の集合体としての歴史書が本書の目指すところである。
もし本書を手にする機会があれば、なにより一読願いたいのは巻末の座談会記録である。文理融合とは聞こえがいいが、実際には、プロジェクト開始直後から苦痛の連続であった。それぞれの分野で抱える問題意識や研究手法は異なっており、しかも挨拶の仕方や電子メールの書き方まで違うのである。それがまた国際共同研究となるので、ジレンマは数倍にまで膨れ上がる。プロジェクト内部で班別の研究グループをつくったが、各グループの連携を取るべく、毎月、コアメンバー会議を開いていた。殴り合い寸前にまで議論は白熱し、ときに日本人の文系メンバーだけで会議後、近くの蕎麦屋で愚痴を言い合っていた。プロジェクトが終了し、本書を刊行してしばらくたち、座談会記録を読み返すと、今ようやく、あの熱気が懐かしく思い出される。
(紹介文執筆者: 人文社会系研究科・文学部 准教授 島田 竜登 / 2018)
本の目次
第2章 ジャカルタの国際的契機:マニラ,マカオ,マラッカ,そして日本
第3章 歴史からみたジャカルタの自然と都市空間
第4章 会社のつくった都市バタヴィア:オランダ東インド会社時代,1619-1799年
第5章 オランダ領東インドの中心都市としてのバタヴィア,1800-1949年
第6章 メガシティ化するジャカルタ――独立後の変容
第7章 計画されたジャカルタ――空間計画の枠組みとその実現を支える技術をめぐって
<座談会> ジャカルタはなぜメガシティになったのか



 書籍検索
書籍検索