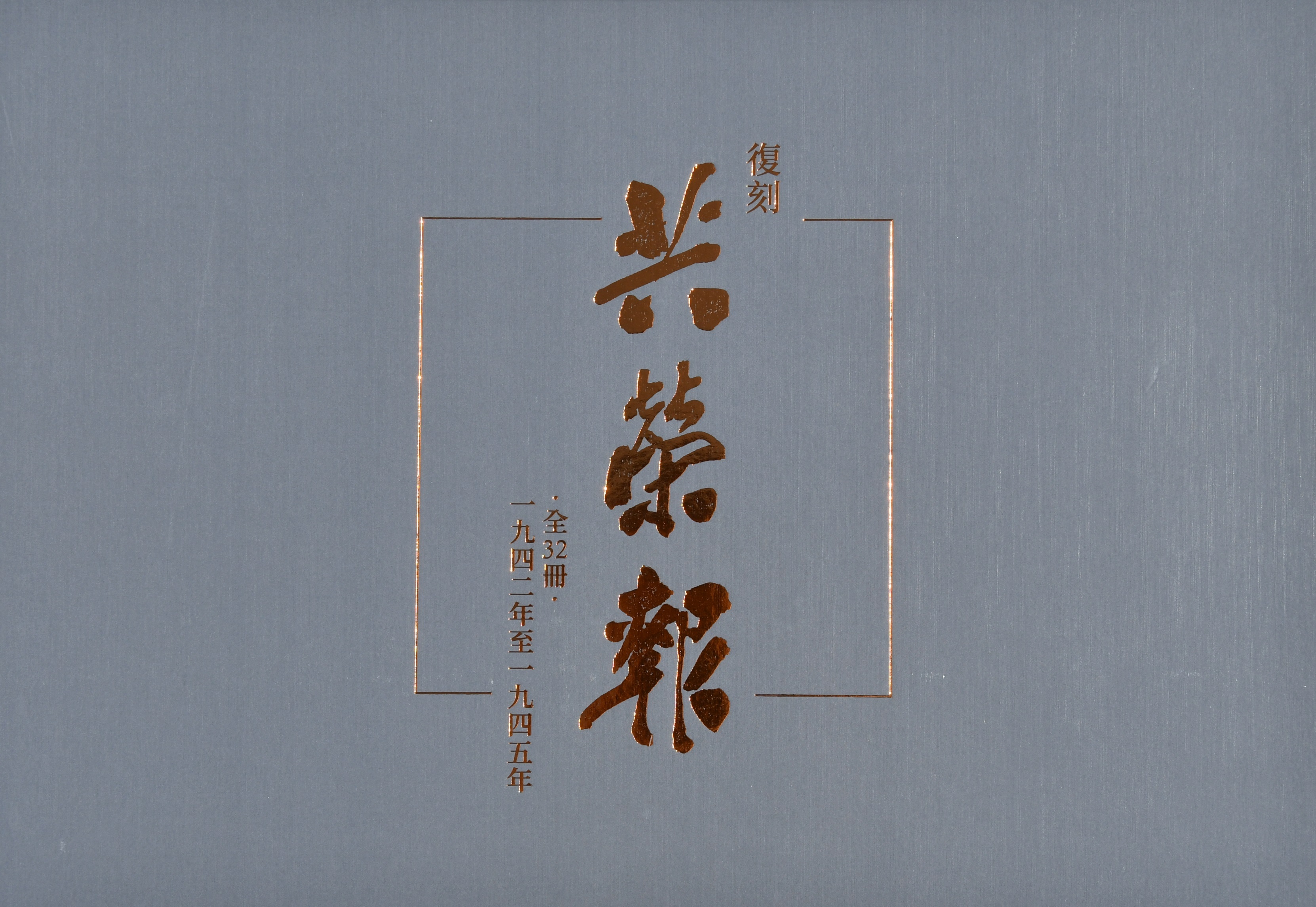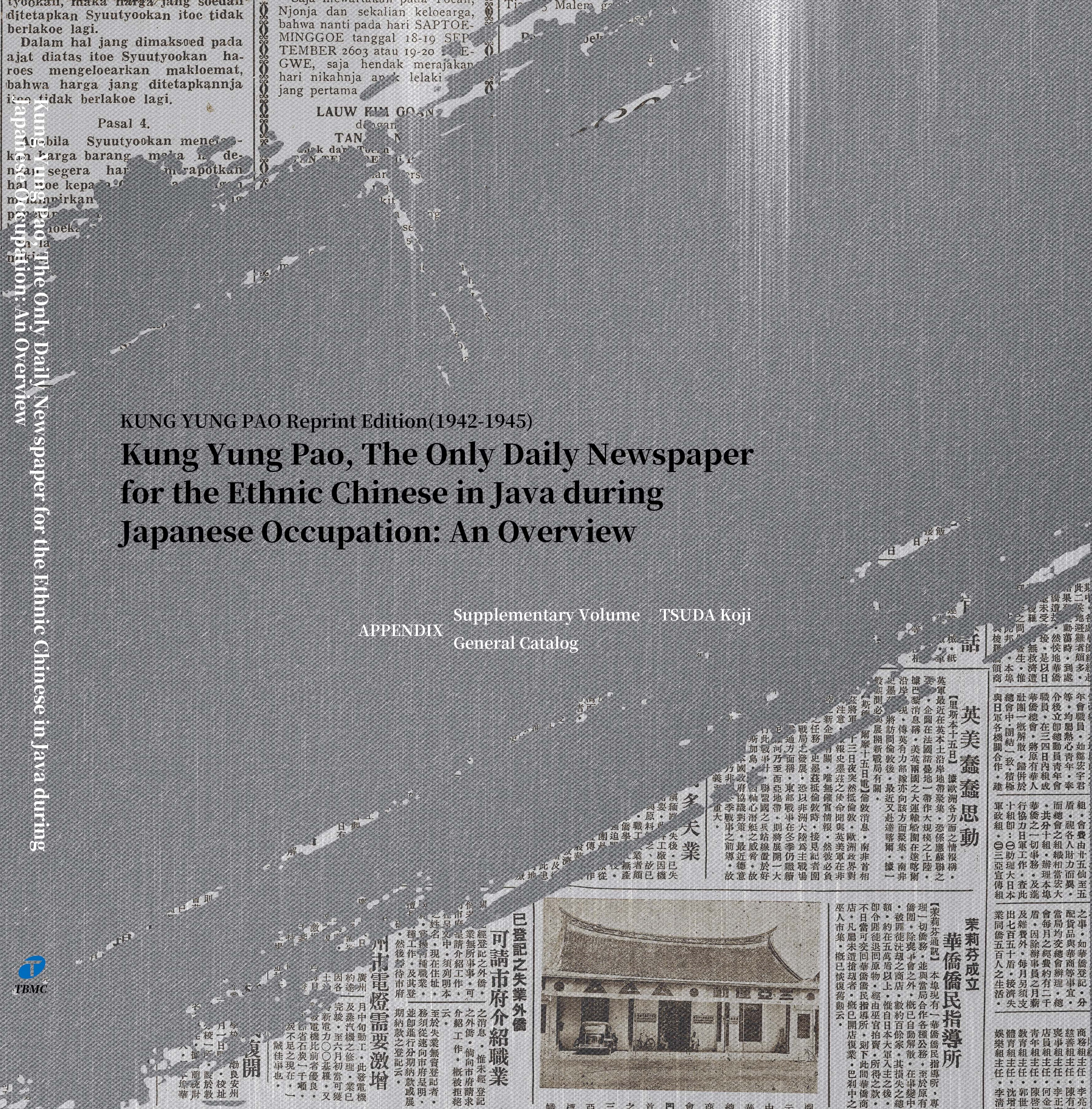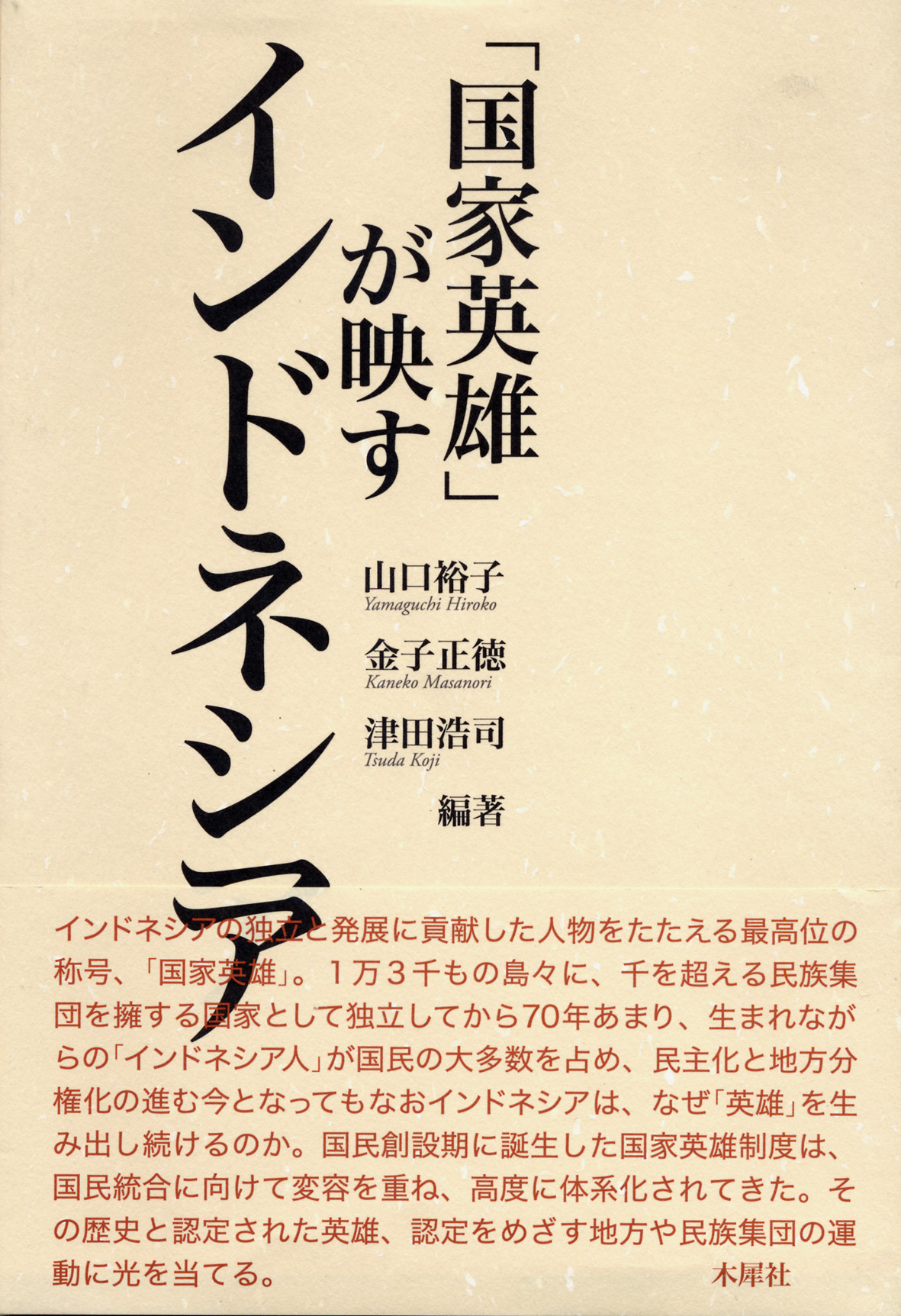
書籍名
「国家英雄」が映すインドネシア
判型など
333ページ、A5判
言語
日本語
発行年月日
2017年3月31日
ISBN コード
978-4-89618-066-4
出版社
木犀社
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
大抵の国には、「建国の父/母」などと呼ばれる存在がいる。日本の場合、今日に連なる国家としての日本の成立の契機をどこに設定するかにより、神武天皇、明治の元勲たち、あるいは戦後民主主義の担い手たちなどと、意見が分かれるところだろう。さらに対象を、社会にとって英雄的とされる人物へと広げ、たとえば戦中期の「軍神」と、戦後の「国民栄誉賞」受賞者の面々とを対比させてみれば、日本社会の性格や価値観の変化もまた見て取れるだろう。このように、英雄というものを考えることで、それを取り巻く社会のあり方や社会そのもののイメージが浮かび上がってくる。
本書が対象とするのは、無数の島々と多数の民族集団から成る東南アジアの大国、インドネシアの英雄たちである。しかもそれは単なる英雄ではなく、インドネシアの国家・国民 (=ネイション) のために尽くした人物を国が公的に認定するという制度によって顕彰された、「国家英雄 (Pahlawan Nasional)」と呼ばれる人たちである。この「国家英雄」たちを焦点として、彼らを英雄として祀り上げようとする社会の側のダイナミズムを見ていこう、というのが本書の趣旨である。
インドネシアは1945年8月に独立宣言をし、その後再植民地化を目論むオランダとの間で4年余りのゲリラ戦・外交戦を展開し独立を勝ち取った。その後1950年代後半に上述の「国家英雄」制度が創設されたのだが、以来今日までに、この同国最高位の称号を授与された人物は何と160名を超えており (!)、その数は今なお毎年増え続けている。
この「国家英雄」の最も典型的なイメージは、独立宣言に至るまでのインドネシア・ナショナリズム運動、そして日本軍政を挟みその後続いた独立戦争において、指導的立場を担って世を去った政治家・軍人である。このコアな英雄像は今なお変わっていないが、しかしその後半世紀以上にわたる同国の社会や政治の変化を反映し、ノミネートされる英雄像も幾分変遷を辿った。
さらに90年代末以降、インドネシアで民主化・地方分権化が進むと、様々な地域や民族集団 (この中には、従来国家の枠組み内で周辺化されてきたような存在も含まれる)、あるいはローカルな文脈で台頭しつつある政治エリートなどが、こぞって「自分たち」の存在を代表するような過去の人物を掘り起こしては、この「国家英雄」のラインナップに加え入れようと、推戴運動を起こし始めているのである。
では、インドネシアはこの「国家英雄」制度を通じいかなる自画像を描いてきたのだろうか。また、もはや新興国家というには十分に安定・成熟しつつある今日もなお、ネイション・ビルディングの英雄が模索され続けているというのはいかなる事態なのだろうか。とりわけ、この「国家英雄」制度に則りつつ、現在盛んに「自分たち」の存在をシンボリックに示そうと画策している地域や民族集団、その他利害集団による動きは、インドネシア社会内部のいかなる変化・対立を反映しているのだろうか。そして、それらの主張が「国家英雄」制度を通してなされることで、どのような可能性 / 制約が生じるのだろうか。
本書は、文化人類学、地域研究、歴史学などの立場から、インドネシア各地で実地研究を進めてきた研究者が、それぞれの地で沸き起こっている英雄推戴運動の諸相を丁寧に描き出すことを通じ、現代インドネシアで展開している社会の動態を活写するとともに、人々が英雄を通していかなる価値や歴史を担うものとして「自分たち」を提示しようとしているのかを、明らかにしている。
(紹介文執筆者: 総合文化研究科・教養学部 准教授 津田 浩司 / 2017)
本の目次
I 未完のファミリー・アルバム――東南スラウェシ州の、ふたつの英雄推戴運動 (山口裕子)
II 新たな英雄が生まれるとき――国家英雄制度と西ティモールの現在 (森田良成)
III 民族集団のしがらみを超えて――ランプン州における地域称号制度と、地域社会の課題 (金子正徳)
IV 「創られた英雄」と、そのゆくえ――スハルトと一九四九年三月一日の総攻撃 (横山豪志)
V 偉大なるインドネシアという理想――ムハマッド・ヤミン、タラウィの村からジャワの宮廷まで (ファジャール・イブヌ・トゥファイル、荒木 亮 訳)
VI 「歴史をまっすぐに正す」ことを求めて―― 国家英雄制度をとおした、ある歴史家の挑戦 (津田浩司)
VII 「国家英雄」以前――「祖国」の創出と名づけをめぐって (加藤 剛)
あとがき



 書籍検索
書籍検索