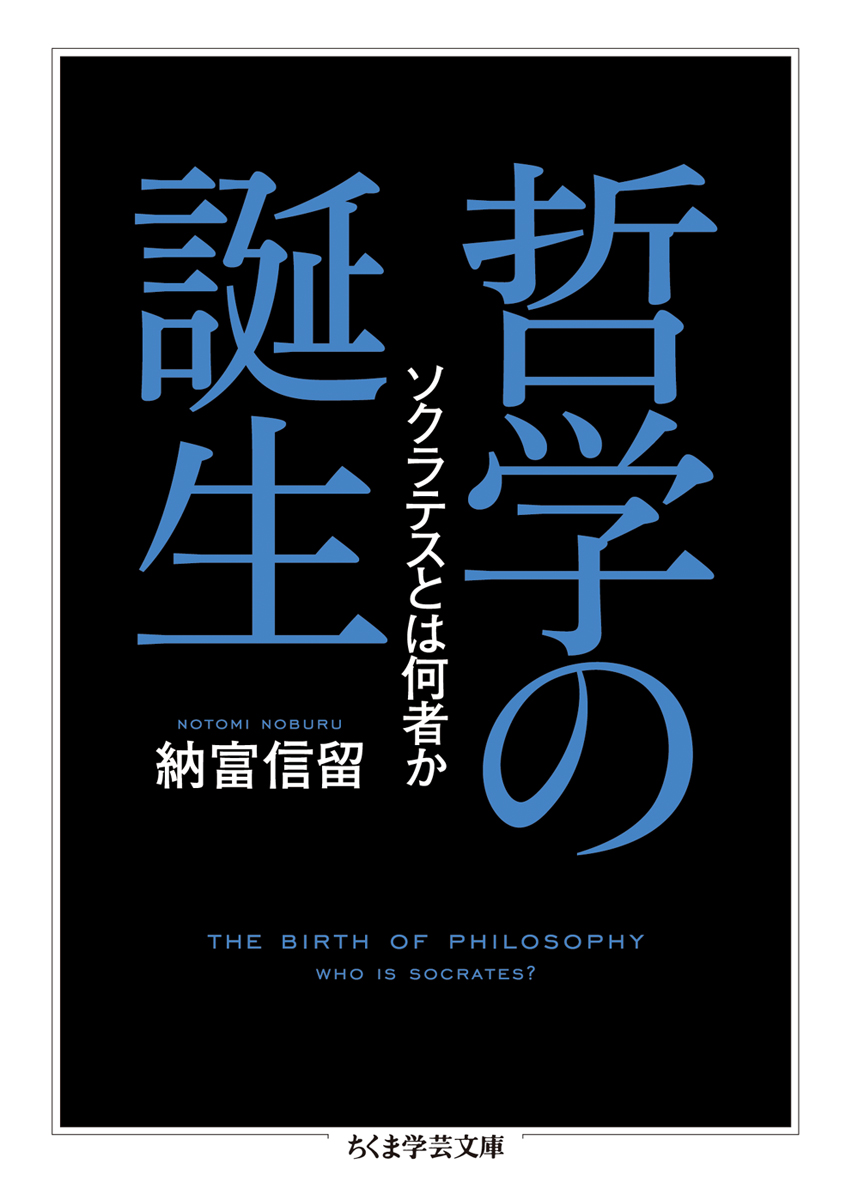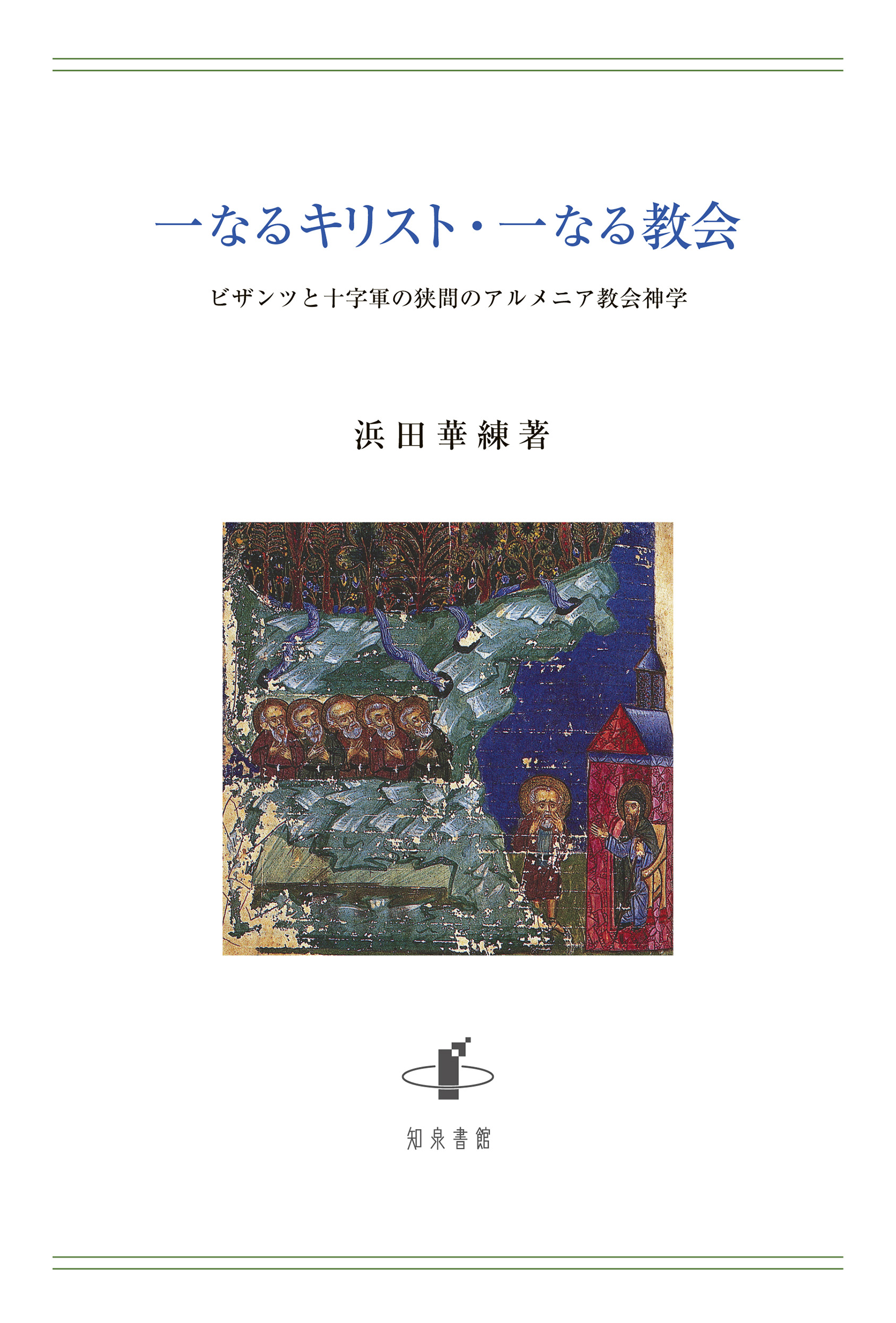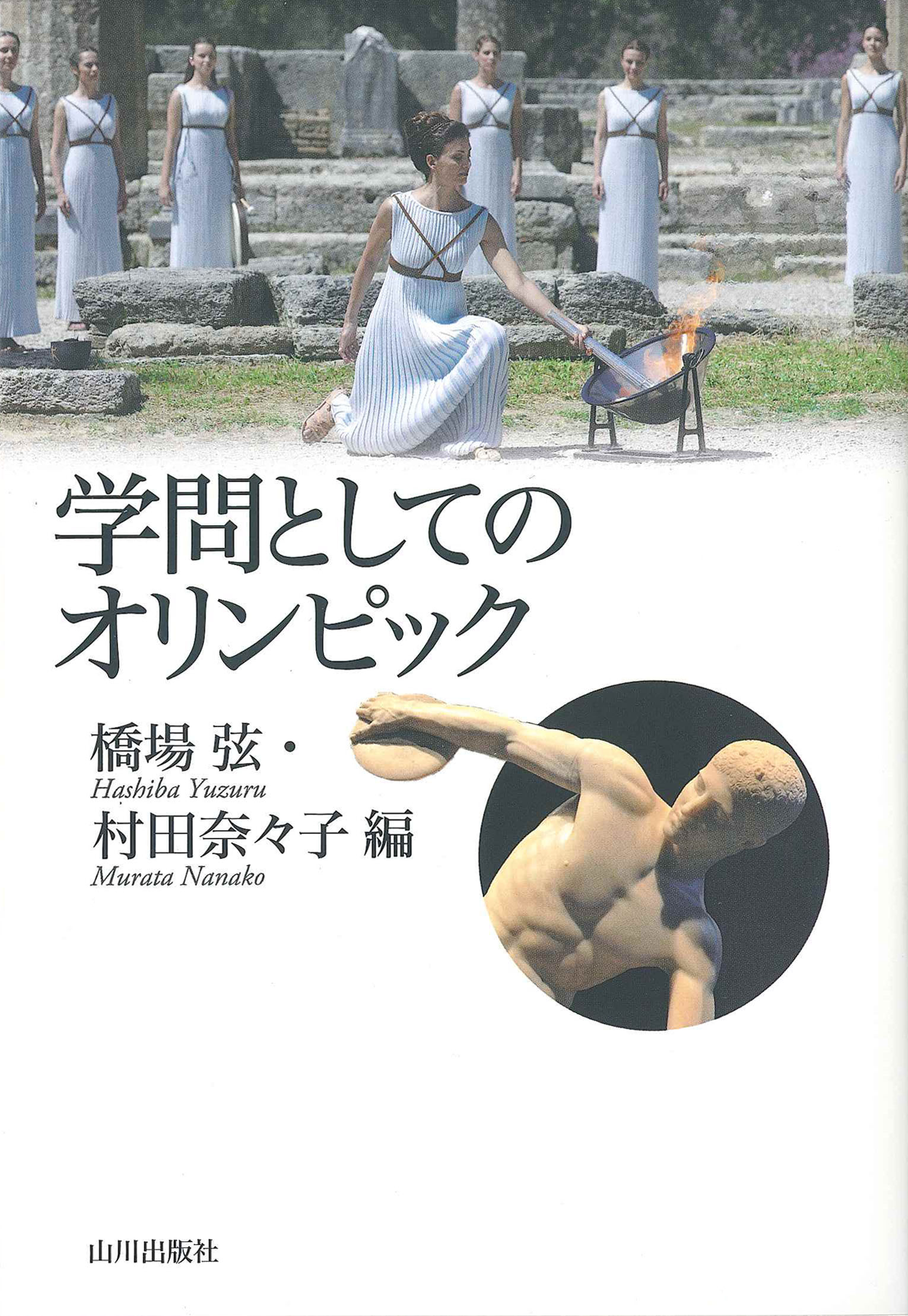西洋哲学において「光」という概念はどのような哲学的・宗教的・文学的役割を果たしたのか。『創世記』で神が「光あれ」という言葉とともに世界を創造したように、光は、言葉 (ロゴス) や存在と合わせて、万物の秩序の始原とされた。本書は、東京大学文学部哲学研究室の出身で現在は慶應義塾大学文学部で教鞭をとる山内志朗教授を中心に、私を含む11名の研究者がそれぞれの専門分野や問題関心から共通テーマを論じた論文集であり、慶應義塾大学言語文化研究所 (かつて井筒俊彦が研究に従事した) で行われた共同研究の成果である。そのテーマが、「光の形而上学」が西洋古代から中世近世にかけてどう展開されたか、である。
西洋古代でプラトンに始まった「光」の哲学には、『ポリテイア』の「太陽の比喩」が原型イメージを与える (納富論文)。「存在の彼方」とされる善のイデアは太陽に喩えられ、その光が存在をもたらす。その強烈な形而上学イメージは、プラトンの哲学をうけつぐプロティノスら新プラトン主義で展開され (樋笠論文)、初期ギリシア教父では神の姿に重ねられていく (土橋論文)。
キリスト教をアリストテレス哲学で理論化した中世の哲学では「光」という契機は一見重要ではないが、この伝統を中世哲学でどう捉えるかが、山内論文と上枝論文で論じられる。また、13世紀の神学者ロバート・グロステストによる「太陽光の熱さ」の議論 (神崎論文) や、ルネサンスの美術作品に描かれる「光と影」(遠山論文) がこの角度で扱われる。
東方キリスト教世界では、新プラトン主義の影響がつよく「光」を体験的に語る伝統が維持された (谷論文)。また、中世の神秘主義宗教家や文学では、光をめぐる言説が顕著であった (香田論文)。ギリシアの伝統を受け入れたイスラームでも、神や預言者やイマームにおいて「光」がテーマとなった様子が、10世紀のスィジスターニーの著作の翻訳と解説をつうじて示される (野元論文)。
本書に収められた論考は、それぞれ特定の問題から共通テーマに光をあてるもので、必ずしもすべての領域を覆うものではない。だが、それら特徴的な考察が全体として「光の形而上学」という伝統の光と影を照らし出してくれる。いくつかの重要文書が翻訳され解説されている点も特徴である。狭い哲学にかぎらない、精神史への興味深いアプローチとして一読をお勧めしたい。
(紹介文執筆者: 人文社会系研究科・文学部 教授 納富 信留 / 2018)
本の目次
はじめに 山内志朗
第 I 部 古代の光
プラトン「太陽」の比喩 納富信留
光の超越性と遍在性
初期ギリシア教父における光とロゴスをめぐって 土橋茂樹
プロティノスにおける光と言語の形而上学 樋笠勝士
第 II 部 中世における展開と発展
中世存在論における唯名論
実体論批判としての唯名論 山内志朗
トマス・アクィナスにおける「光の形而上学」の可能性 上枝美典
太陽の光はなぜ熱いのか
ロバート・グロステストの『太陽の熱について』 神崎忠昭
15世紀シエナ美術における光と影
サッセッタ作〈聖痕を受ける聖フランチェスコ〉の場合 遠山公一
第 III 部 伝統の継承と刷新
東方キリスト教圏の光に関する体験的言説とその特質 谷 寿美
弾む御言 (みことば)、差し込める光
中世ドイツの宗教と世俗文学に現れた光をめぐる言説 香田芳樹
神の光、そして預言者とイマームたちの光
イスマーイール派によるクルアーン「光の節」の解釈
(スィジスターニー『神的王領の鍵の書』第52章の翻訳と解題) 野元 晋
同一性と指示詞に基づく論理体系 藁谷敏晴
あとがき 山内志朗



 書籍検索
書籍検索