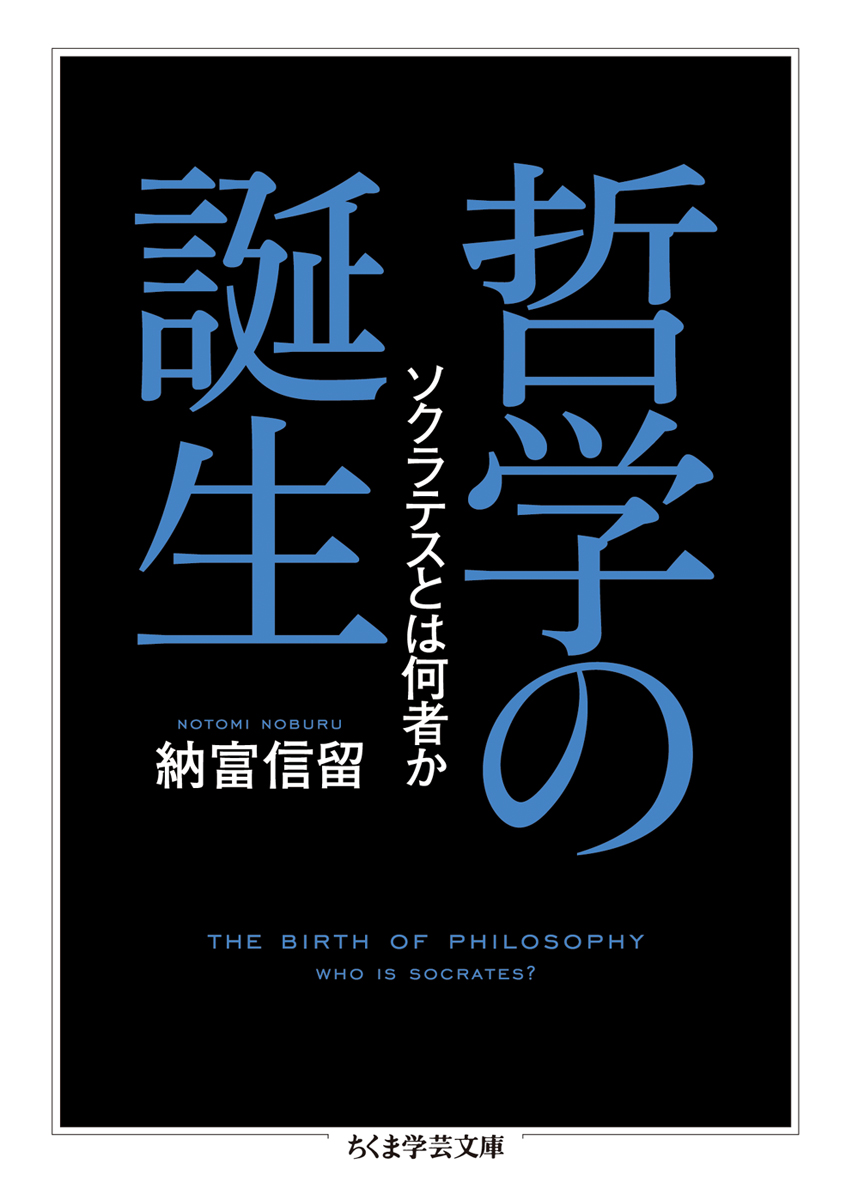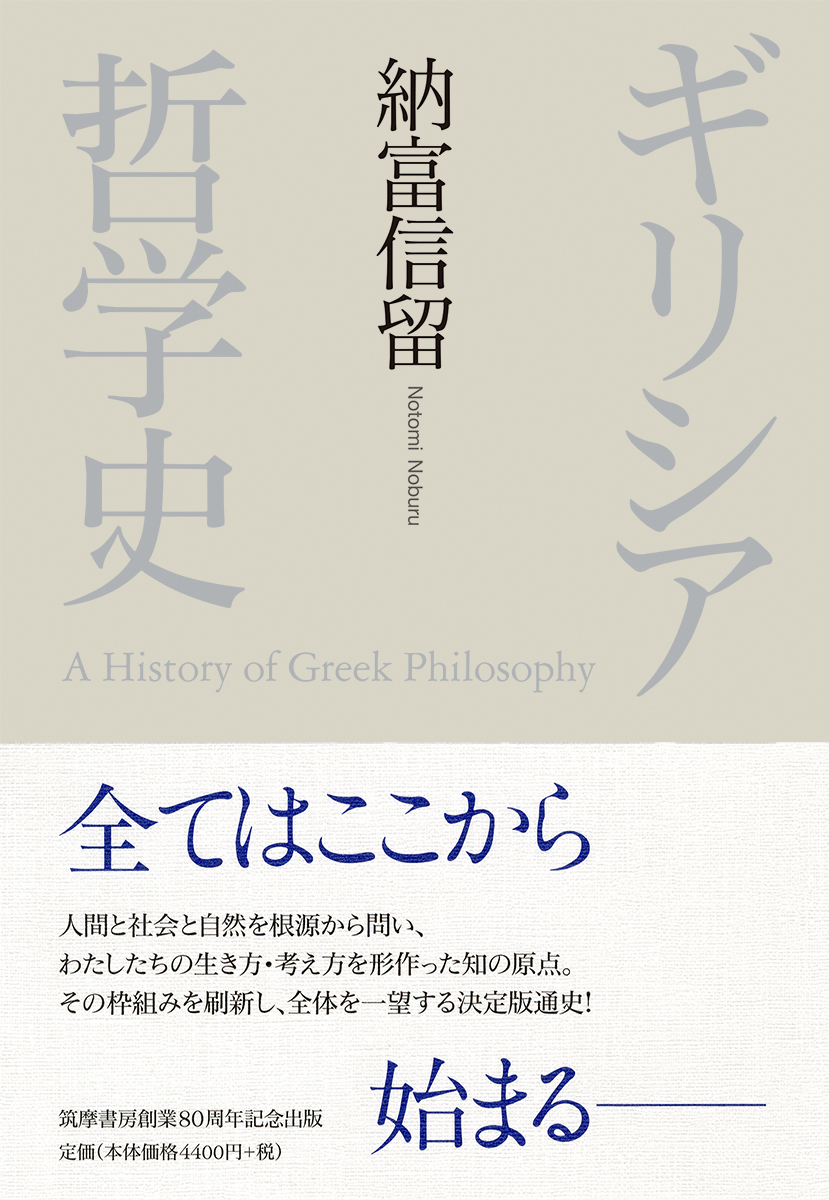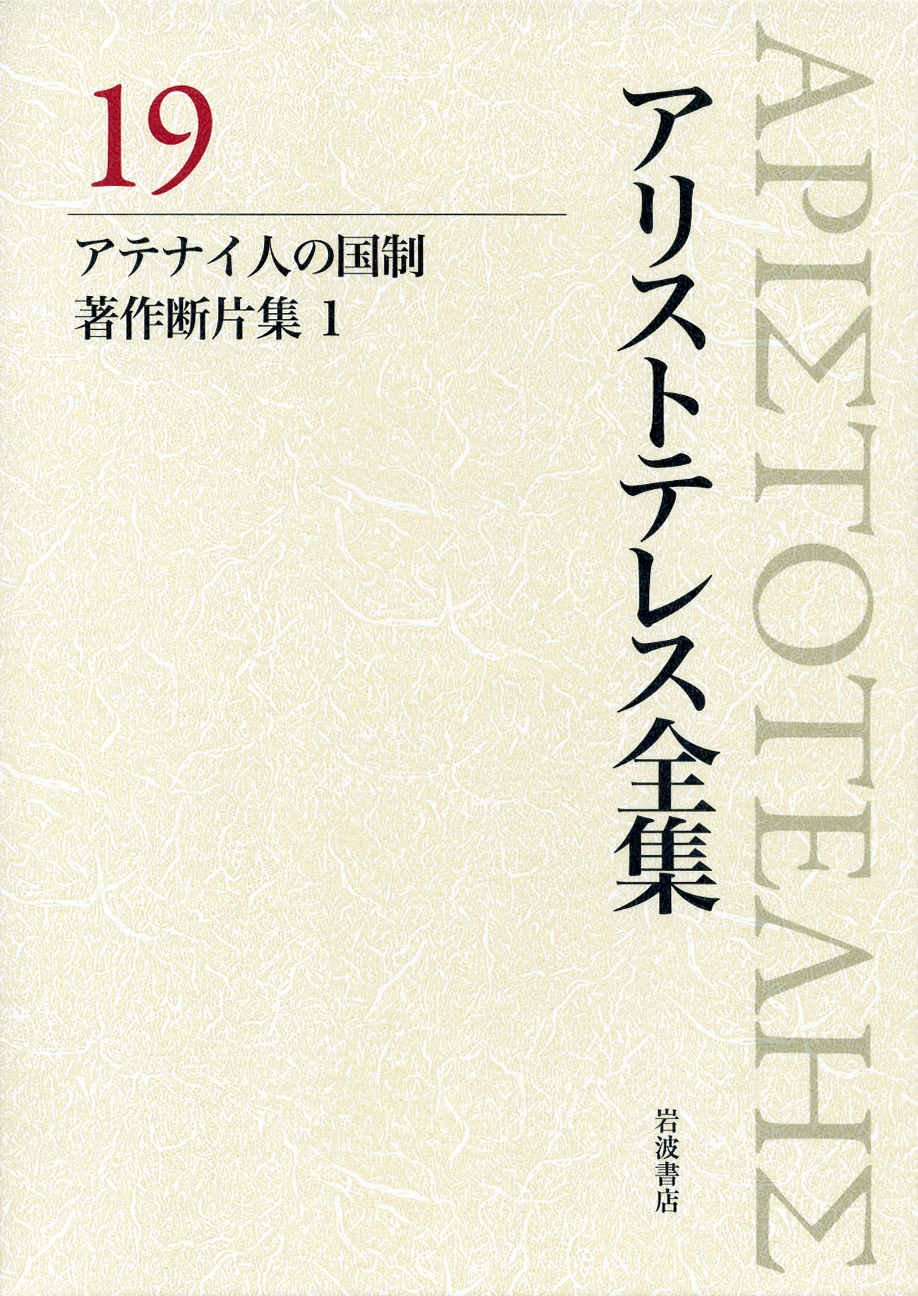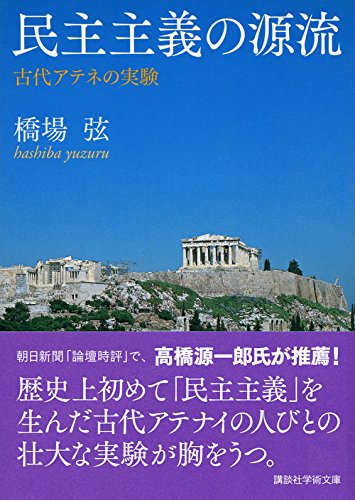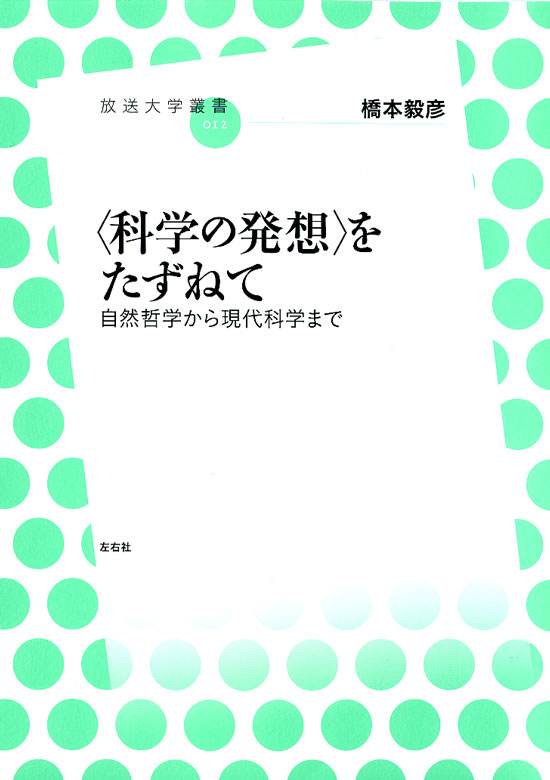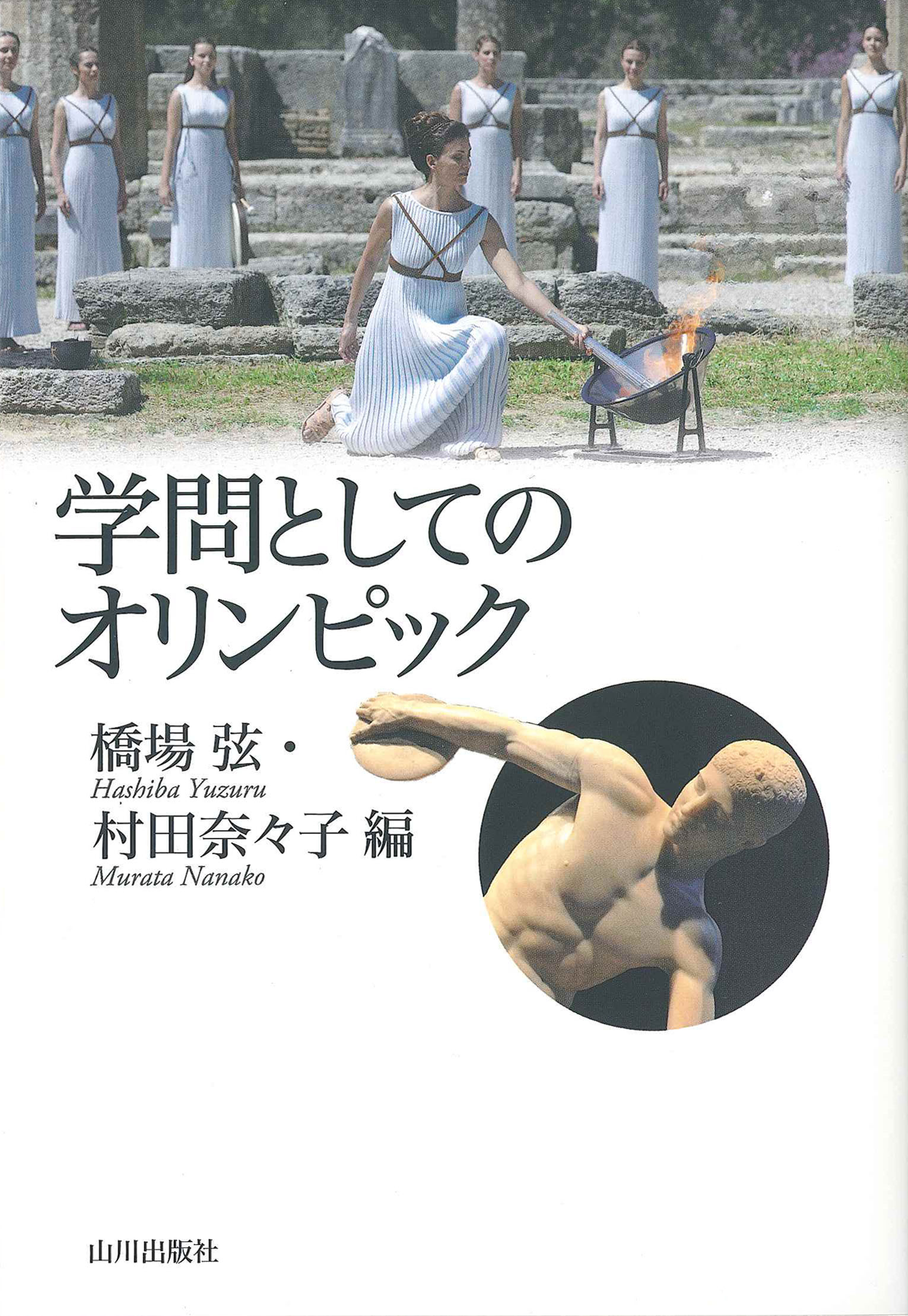哲学は前5世紀後半、ソクラテスとともに始まったとされてきた。だが、何も著作を残さなかったソクラテスが、なぜ最初の哲学者とされるのか。その事情とそこに込められた哲学的問題を、ソクラテスを主人公にした多彩な「ソクラテス文学」から読み解くのが本書である。この主題では日本で唯一の研究書であるが、一般向けの読み物としても楽しんでもらえる。
ギリシアにおける哲学の誕生を、ソクラテスとその弟子のプラトン、アリストテレスという3人の天才による奇跡的な達成と考える従来の哲学史観では、致命的に見落とされたものがある。それは、ソクラテスが何者だったかをめぐり、同時代の緊張のなかで多士済々の思想家たちが繰り広げた論争から真に哲学が形成されていく動的なプロセスである。前399年にアテナイの法廷で「不敬神」の罪状で死刑となったソクラテスをめぐっては、彼を批判する勢力と、その生き方を擁護する人々との間で論争が巻き起こった。その中で、前4世紀前半には弟子たちによって二百もの「ソクラテス対話篇」が公刊され、「ソクラテス文学」というジャンルが成立した。そこには、プラトンの全対話篇を始め、現存するクセノフォンの4つのソクラテス著作も含まれる。現在ではタイトルや断片だけで残る作品も含めて、それらの言論とその背景から、多様なソクラテス像が浮かび上がる。
まず、プラトンの代表作『パイドン』が描く「ソクラテスの死」が手がかりとなり、プラトンがその語りに何を込めたのかが解き明かされる。また、「ソクラテス文学」で焦点となったのは、弟子であった寡頭派政権の中心人物クリティアス、及び、奔放な政治活動で全ギリシアとペルシアを翻弄した奇才アルキビアデスとソクラテスの関係であった。それぞれの著者が「対話篇」という文学形態に仮託したソクラテス哲学の評価が、読み解かれるべき内容となる。間テクスト的な読解をつうじて、2400年前、古代ギリシアで哲学が生まれるその有り様が次第に明らかとなる。最終章ではソクラテスが明治以来の日本でどう受容されてきたかをたどり、日本で流布する「無知の知」という標語が歴史の歪みから発生した誤解であることを証明する。
ソフィストと哲学者の関係を再検討した補論を収録した、『哲学者の誕生―ソクラテスをめぐる人々』(ちくま新書、2005年) の増補改訂版である。新書版後の世界での研究状況について、著者による「文庫版あとがき」が解説を加える。
(紹介文執筆者: 人文社会系研究科・文学部 教授 納富 信留 / 2017)
本の目次
第1章 ソクラテスの死―プラトン『パイドン』の語り
第2章 ソクラテスと哲学の始まり
第3章 ソクラテスの記憶
第4章 ソクラテス裁判をめぐる攻防
第5章 アルキビアデスの誘惑
第6章 「無知の知」を退けて―日本に渡ったソクラテス
補論 「ソクラテス対ソフィスト」はプラトンの創作か
あとがき



 書籍検索
書籍検索