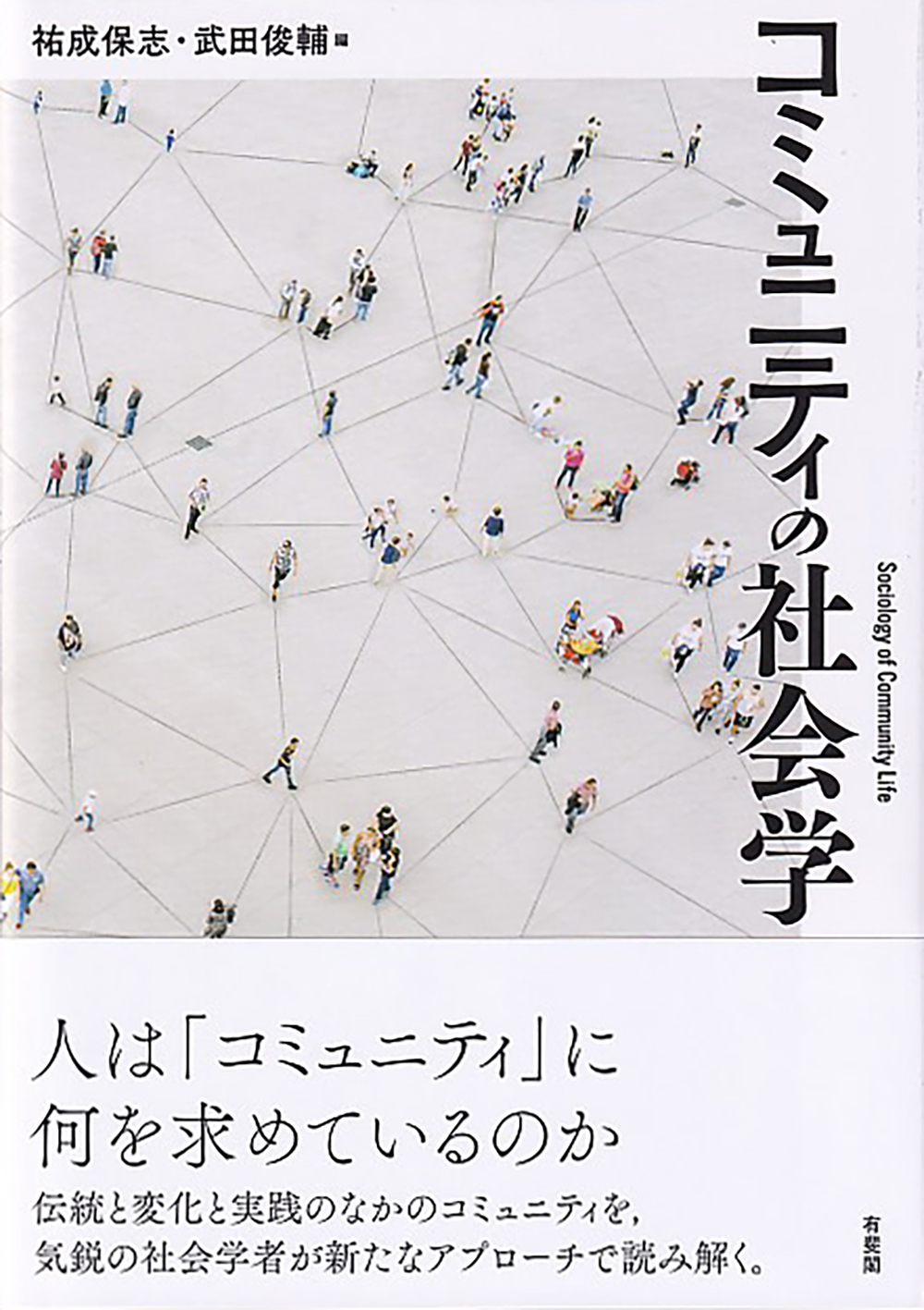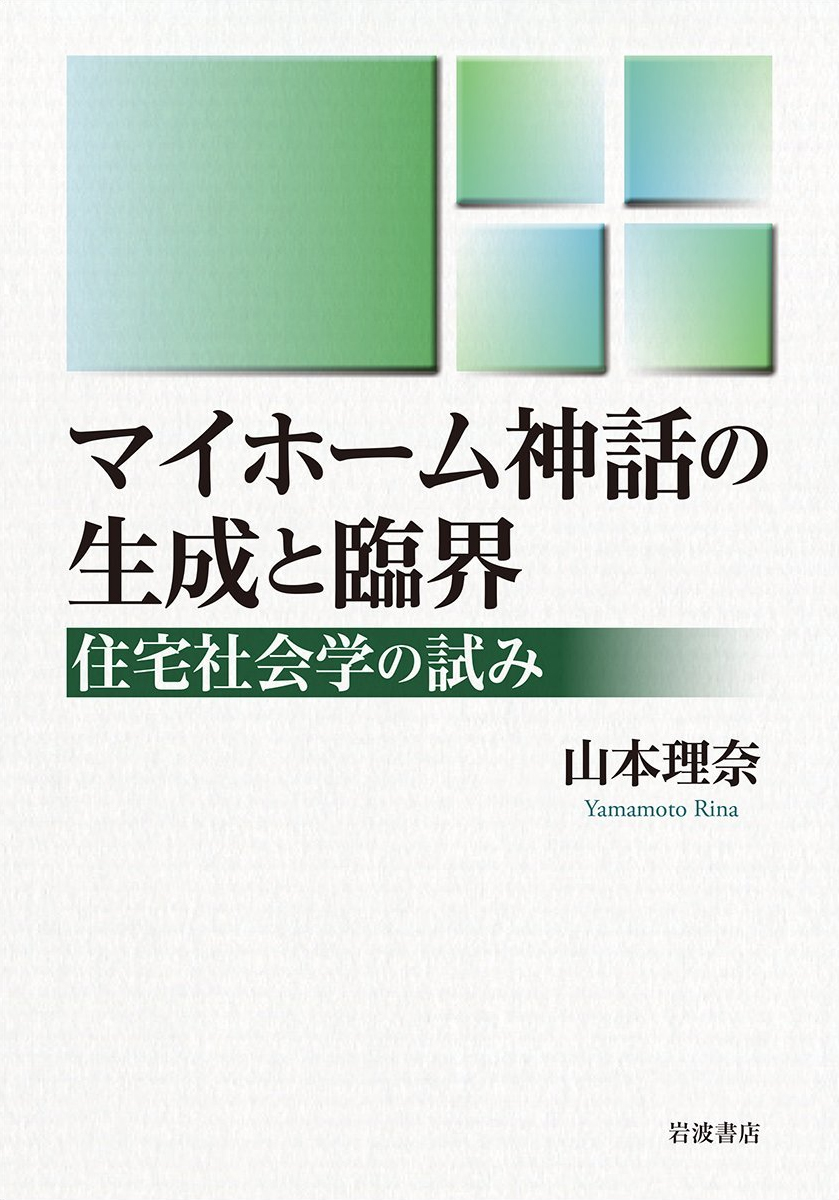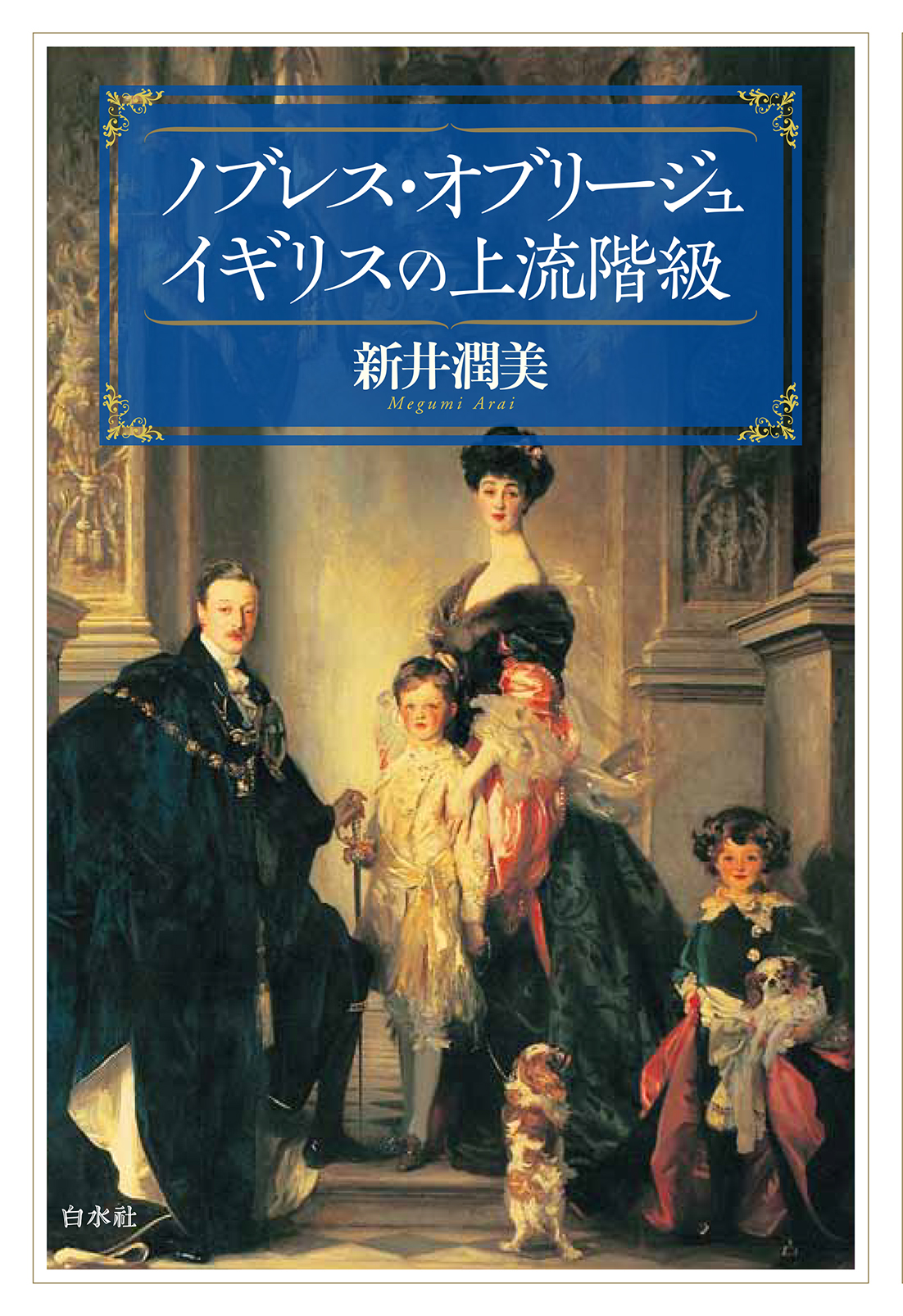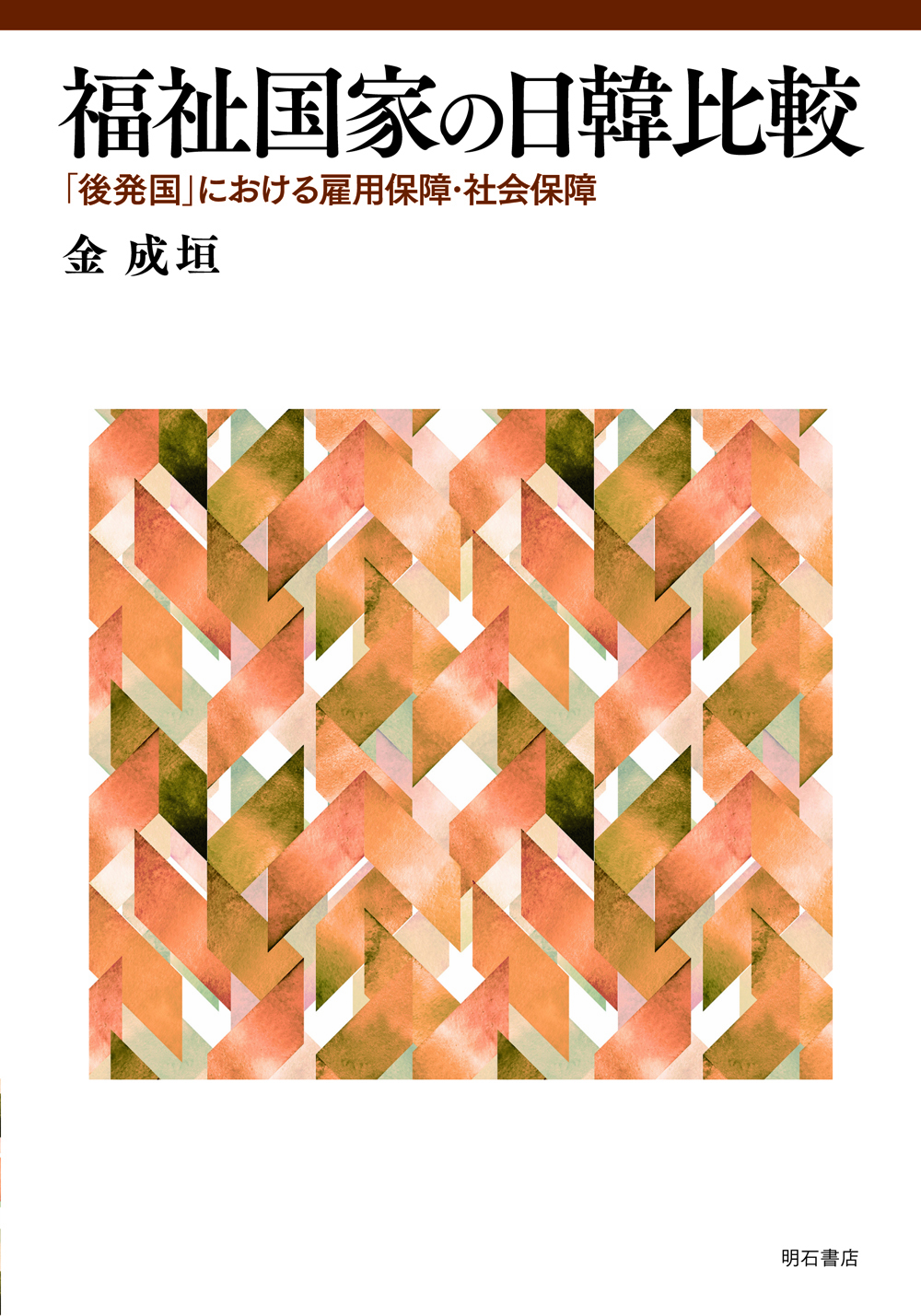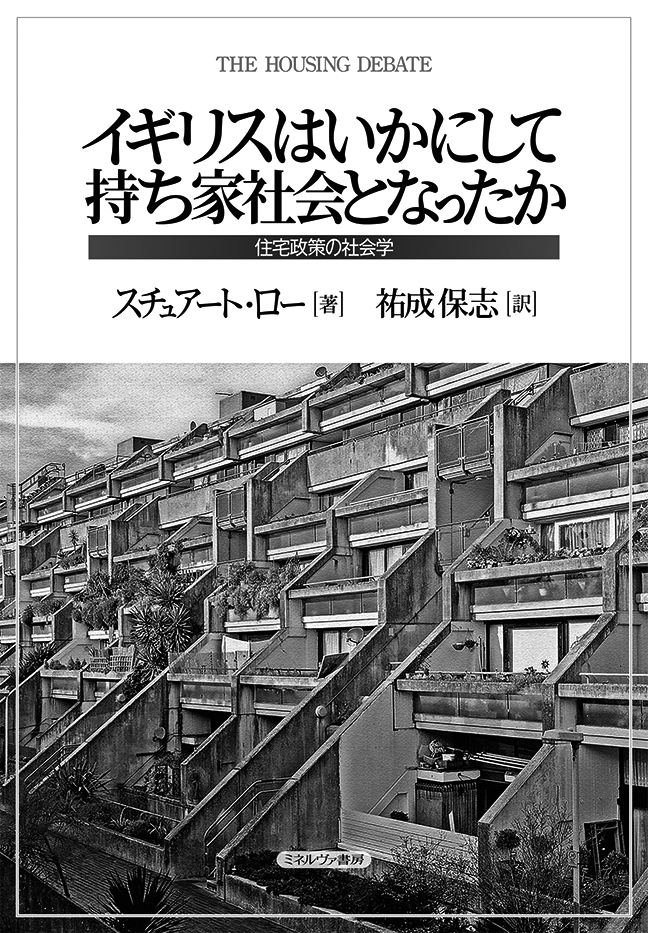
書籍名
イギリスはいかにして持ち家社会となったか 住宅政策の社会学
判型など
336ページ、A5判
言語
日本語
発行年月日
2017年9月10日
ISBN コード
9784623079100
出版社
ミネルヴァ書房
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
1980年代以降、欧州を中心に社会科学の分野で発展してきた住宅研究 (housing studies) は、2007年のサブプライム住宅ローンの問題に端を発する世界金融危機以降、にわかに注目を集める領域となった。近年、研究の蓄積を反映して、相次いで充実した概説書・入門書が出版されている。今回翻訳したStuart Lowe, 2011, The Housing Debate, Policy Pressは、そのなかの一つである。
本書に先立って、筆者は2014年にJim Kemeny, 1992, Housing and Social Theory, Routledgeの翻訳を刊行した (『ハウジングと福祉国家』新曜社)。ケメニーの本は住宅研究の世界では必読とされる古典であり、専門家向けの理論書である。一方、本書が想定する読者は学部や修士課程の学生である。本書を読んで興味をもたれた方は、ケメニーに読み進んでほしい。そうすれば住宅研究の要諦がつかめると思う。
さて、本書には次のような特長がある。(1) 住宅を社会現象として分析するための理論的な概念を導入したこと。(2) 住宅政策を幅広い社会政策、さらには福祉国家のなかに位置づけたこと。(3) 国際比較のなかで英国の特徴を見いだしたこと。そのうえで、著者自身が「物語」とも述べるように、英国の住宅政策がたどった歩みを、起伏に富んだストーリーとしてえがいている。
入門書らしい気配りが本書の随所にみられるが、その一方で、福祉国家と住宅の関係についての著者独自の主張が真正面から展開されており、ページを繰るうちに論争に巻き込まれる感覚が味わえる。
福祉国家を構成する諸制度 (医療、年金、教育、住宅など) のなかで、住宅は「ぐらついた柱 (wobbly pillar)」とか「弱い柱」と呼ばれてきた。制度には、それぞれ特有の論理がある。例えば、医療と同じ論理が住宅に適用できるわけではない。もっとも、そのように言うだけでは、住宅は、研究対象のリストには挙がっても、優先順位の低いテーマという位置にとどまる。
ローはもう一歩進んで、「柱」の比喩そのものに疑問を投げかける。住宅は、「福祉国家の重要な柱のひとつであるだけでなく、いわば土台をなしている」(36頁) というのだ。この指摘の秀逸なところは、ハウジングが、福祉国家の土台・基礎をなしているからこそ、周縁的であるかのように見えるという、われわれの認識上の罠を喝破した点にある。
本書が明らかにするのは、住宅政策において「時間」がもつ重みである。居住空間は、長期にわたって、多様な主体によって、さまざまな資源を用いながら形成される。積み上げられたストックは、徐々にしか更新されない。それゆえ、住宅問題の由来と影響を理解するためには、長期にわたるプロセスを見わたす必要がある。ローは本書で、歴史を把握すること、とくに「はじまり」の時期に着目することの意義をくり返し説いている。
短い時間幅で観察するだけでは、出来事の本当の意味は分からない。このことは住宅という制度の見過ごされやすさにもつながるのだが、住宅が社会の基礎部分にあることと密接にかかわっている。住宅を社会科学の対象に据えられるかどうか。そこでは、われわれの観察力と構想力が試されているのである。
(紹介文執筆者: 人文社会系研究科・文学部 准教授 祐成 保志 / 2018)
本の目次
第2章 住宅政策という発想――ヴィクトリア朝後期の住宅市場危機
第3章 持ち家社会の誕生――1918~39年の戦間期
第4章 持ち家社会の成長――1945~75年の戦後期
第5章 経済のポスト工業化とハウジング
第6章 ハウジングと福祉国家
第7章 住宅ローン市場のグローバル化
第8章 アセット・ベース型福祉国家に向けて
第9章 結論
訳者解説
関連情報
元木周二 (住宅金融支援機構) 評 (『都市住宅学』100号 2018年1月)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/uhs/2018/100/2018_209/_article/-char/ja
平山洋介 評 (『大原社会問題研究所雑誌』717号 2018年7月)
https://hosei.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=21411&item_no=1&page_id=13&block_id=21



 書籍検索
書籍検索