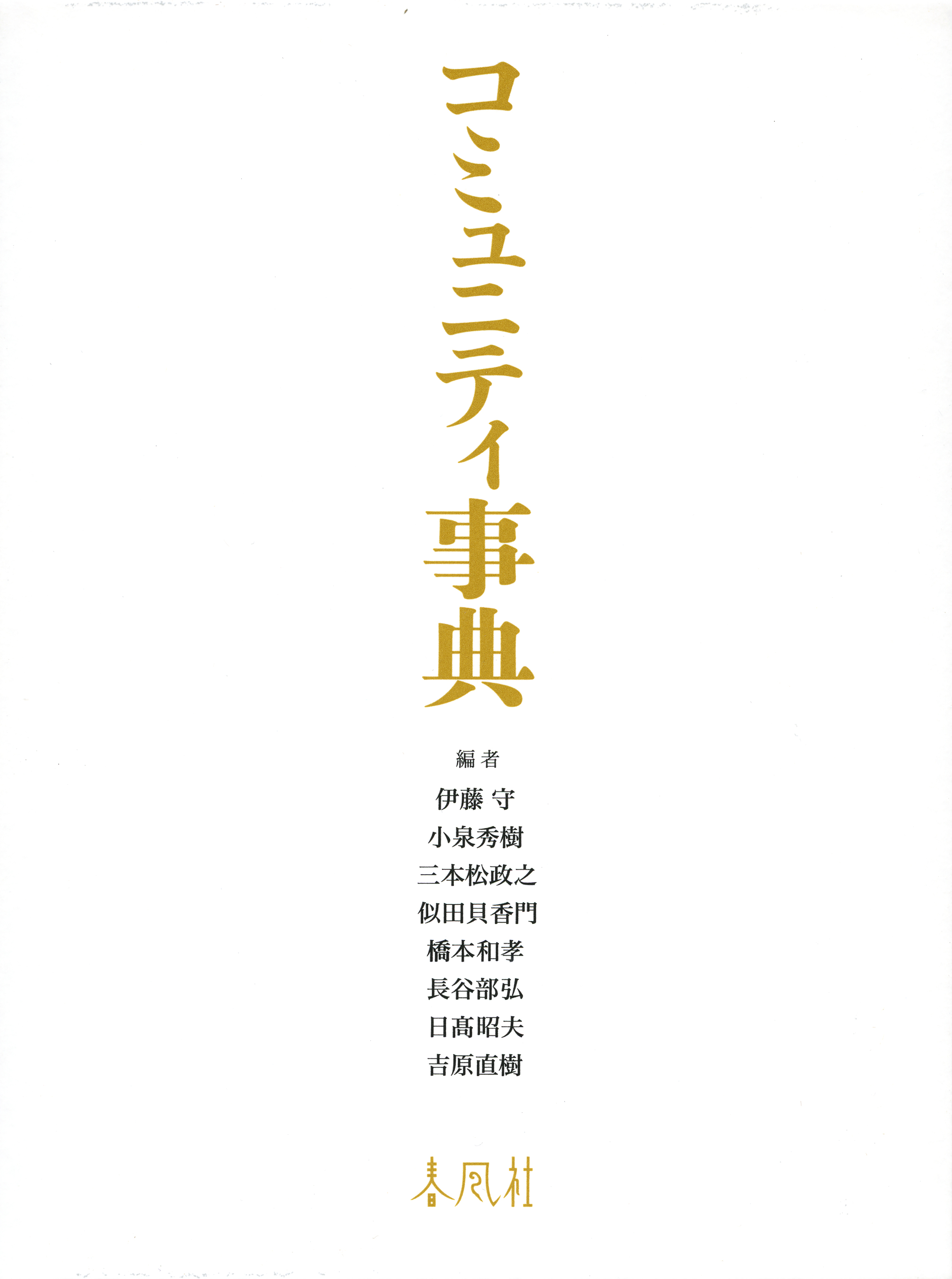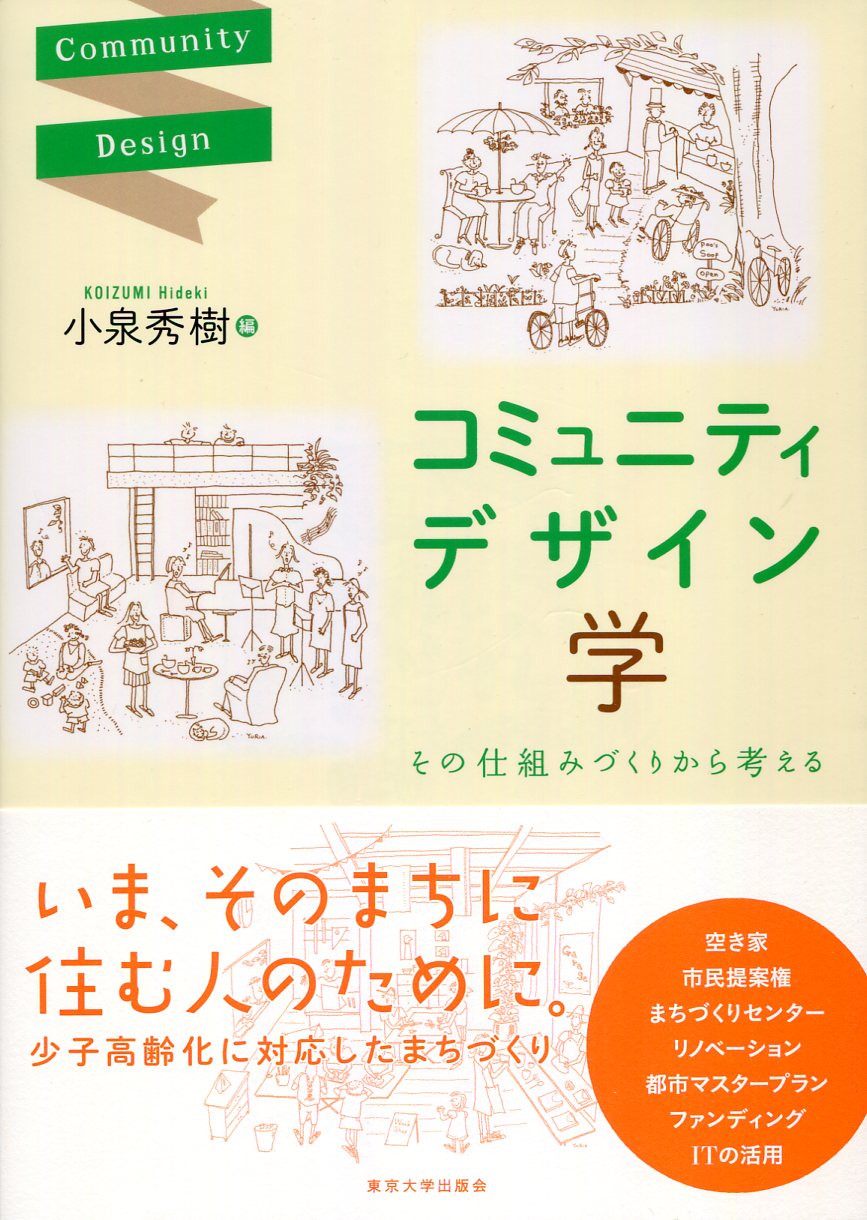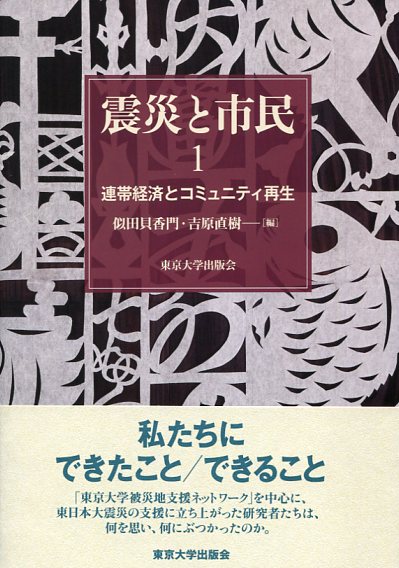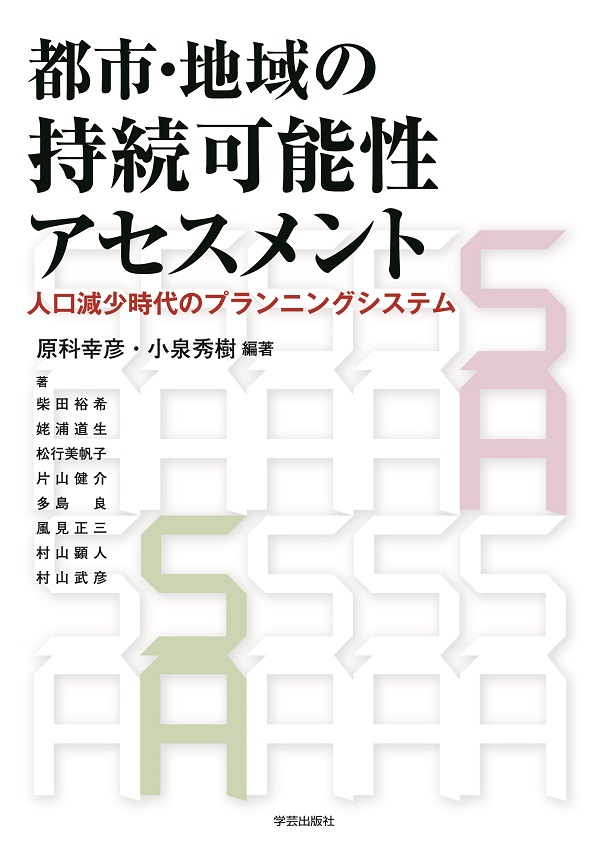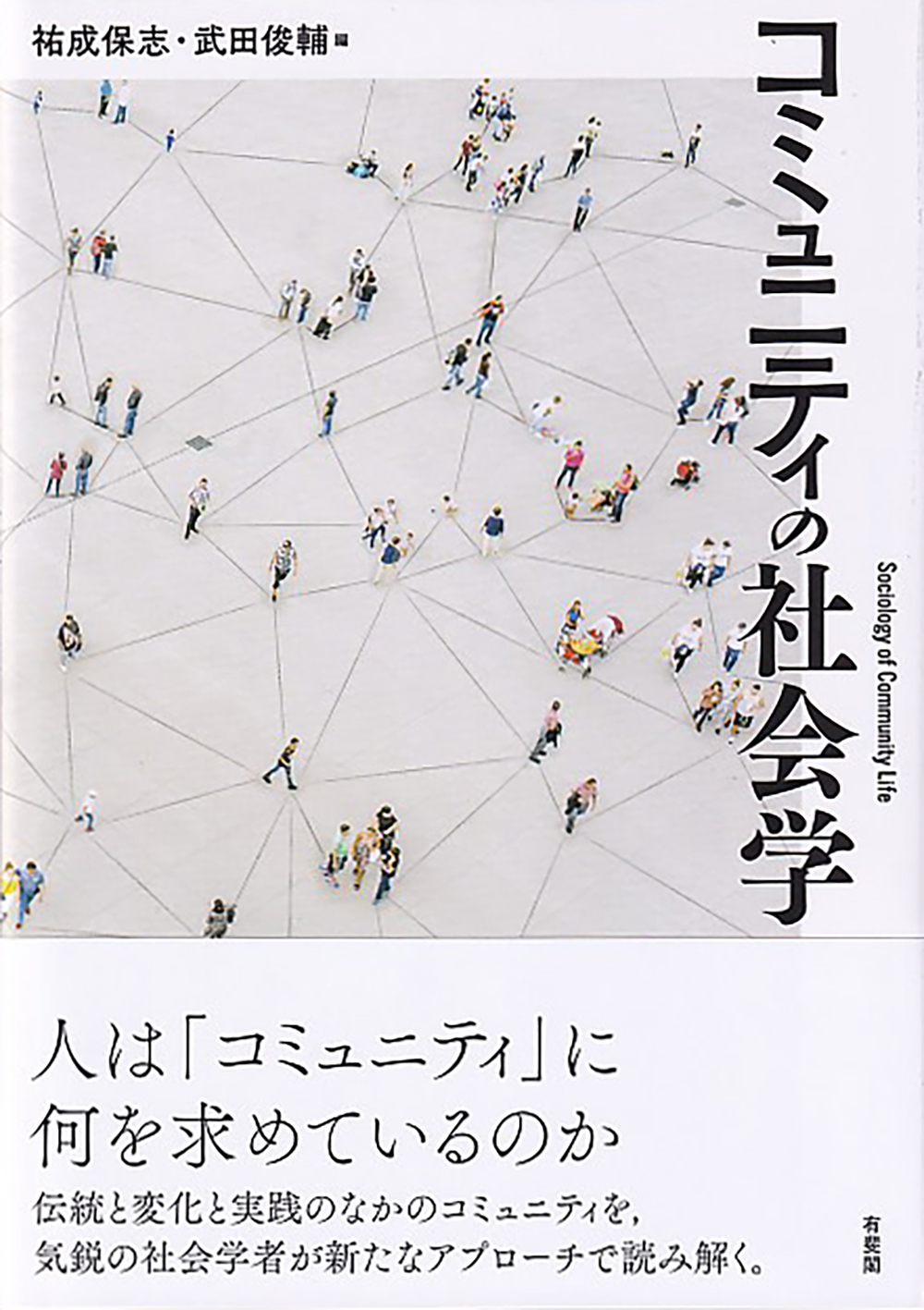グローバライゼーションのなかで国家の役割は変容し、市民、個人の立ち位置も変化しつつある。そして、現代都市では、一人ひとりが競争的な状況に置かれていて、「だれが勝って、だれが負けるか」という局面に日々接することが多くなっている。
災害時に「セーフティネット」がはがれていったとき、むき出しの個人になってしまうのか、それとも集団的に助け合う方法をつくり出していくのか。それによって、復興の筋道は、大きく変わる。また、子育ての環境にしても、社会や経済システムのなかに組み込まれてしまい、自分たちで自分たちの周りの環境をつくることが困難になっている。加えて、都市開発は、地域の住民、地元の自治体の意思ではなく、グローバルな投資や大資本の意思で決まる場合もある。「自分たちの暮らし」を、自分たちで決めることができない様相が、広がり、深まりつつある。
しかし、自分が病気になる、子どもを持つ、親が死んでいくなどの経験を通して、「勝ち続けることはあり得ない」「生物としてのヒトは、むき出しの個という考え方だけでは成り立たない」ことに気がつく。
都市はコミュニティを脆弱にしてきたし、重視してこなかった。都市は、個人主義を是として経済的な活動をする場になっており、「私化」「わたくし化」「個人主義」が浸透し、生物としての人間ヒトが求めている「場」が、うまく形成できない状況にある。そして、いま、科学技術、ICTやAIなどの先端的技術が普及した都市や社会のあり方も、問われている。ICTが浸透することによってプラットフォーム型の事業が展開し、いろいろなリソースを融通して仲間内で支えることが容易にできるようになっている一方で、自動運転などの仕組みは、「わたくし化」を進める。どちらに転ぶのかわからないような状況にある。
グローバリゼーションが進行し、ICTやAIなどの先端的な技術が急速に普及する都市社会において、人がヒトとして生活を営むために、必須となるのが、人々を包摂する中間領域としてのコミュニティの再構築だろう。
現代は、まさにコミュニティ自体が問われている時代と言え、そういう時代に、さまざまな学術分野、そして多様な歴史的側面から光を当て、現代的なイシューをも含んだ、まさに総合的な観点でコミュニティをとらえるような『事典』ができたというのは、非常に意義がある。『コミュニティ事典』は、コミュニティのありよう、モデル的なものを、極めて描きにくい時代だからこそ必要とされている書と言えるだろう。
本書には、コミュニティに関して「学ぶ」項目も多数あるが、実践としてのコミュニティ再生に役立つ項目も多数含まれている。多様化する現代のコミュニティの文脈のなかで非常に役立つ『事典』である、とも言えるだろう。
註 本稿は、図書新聞における「コミュニティ事典 | 評者 鼎談 吉原直樹×似田貝香門×小秀樹」の筆者発言部分をもとに再構成、大幅加筆したものである。
(紹介文執筆者: 工学系研究科 教授 小泉 秀樹 / 2020)
本の目次
2 総論 国家・地方制度のなかのコミュニティ
3 総論 近代日本社会とコミュニティ
4 総論 ボランティア、NPO、NGOとコミュニティ
5 総論 グローバル化とネット・コミュニティ
6 総論 変容するエスニック・コミュニティ
7 各論 まちづくりとコミュニティ
8 各論 社会計画・社会開発とコミュニティ
9 各論 福祉とコミュニティ
10 各論 安全・安心とコミュニティ
11 各論 災害・復興とコミュニティ
12 各論 アジアのコミュニティ
13 各論 欧米のコミュニティ
14 各論 コミュニティ・プランニングの対象と方法
15 各論 コミュニティ・スタディーズの対象と方法
関連情報
【Interview1】オープン・イノベーションには 「人」が集まる「場」が必要 (CityLab TOKYO 2018年12月5日)
https://citylabtokyo.jp/2018/12/05/report-vol1/
書評:
(『ガバナンス』11月号 2017年11月)
https://shop.gyosei.jp/products/detail/9562
今村 都南雄 (中央大学名誉教授) 評 (地方自治総合研究所ホームページ 2017年10月)
http://jichisoken.jp/column/2017/column201710.htm
「コミュニティ事典 |評者 鼎談 吉原直樹×似田貝香門×小秀樹」 (『図書新聞』 会員のみ閲覧可)
http://www.toshoshimbun.com/books_newspaper/week_description.php?shinbunno=3310&syosekino=10567



 書籍検索
書籍検索