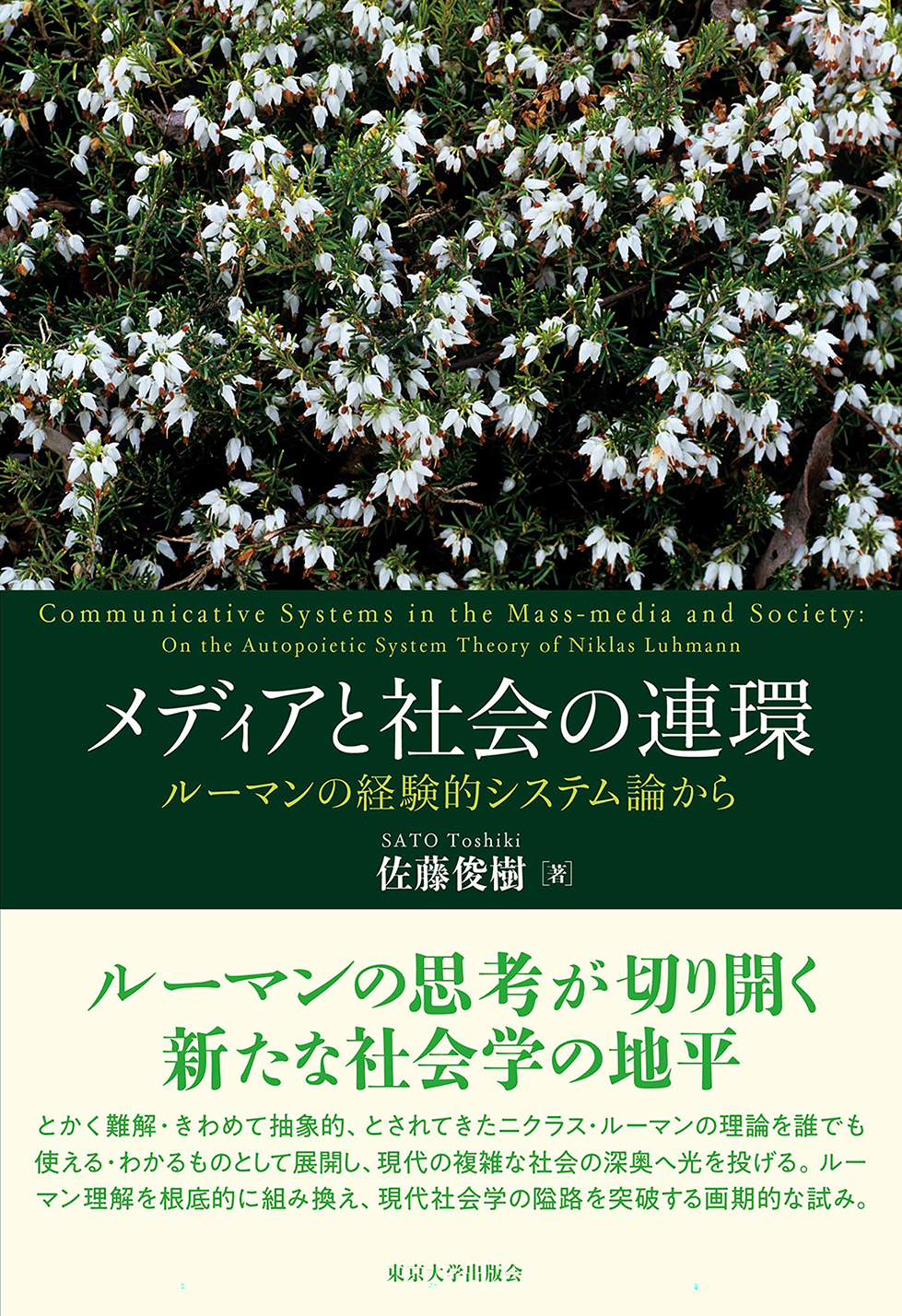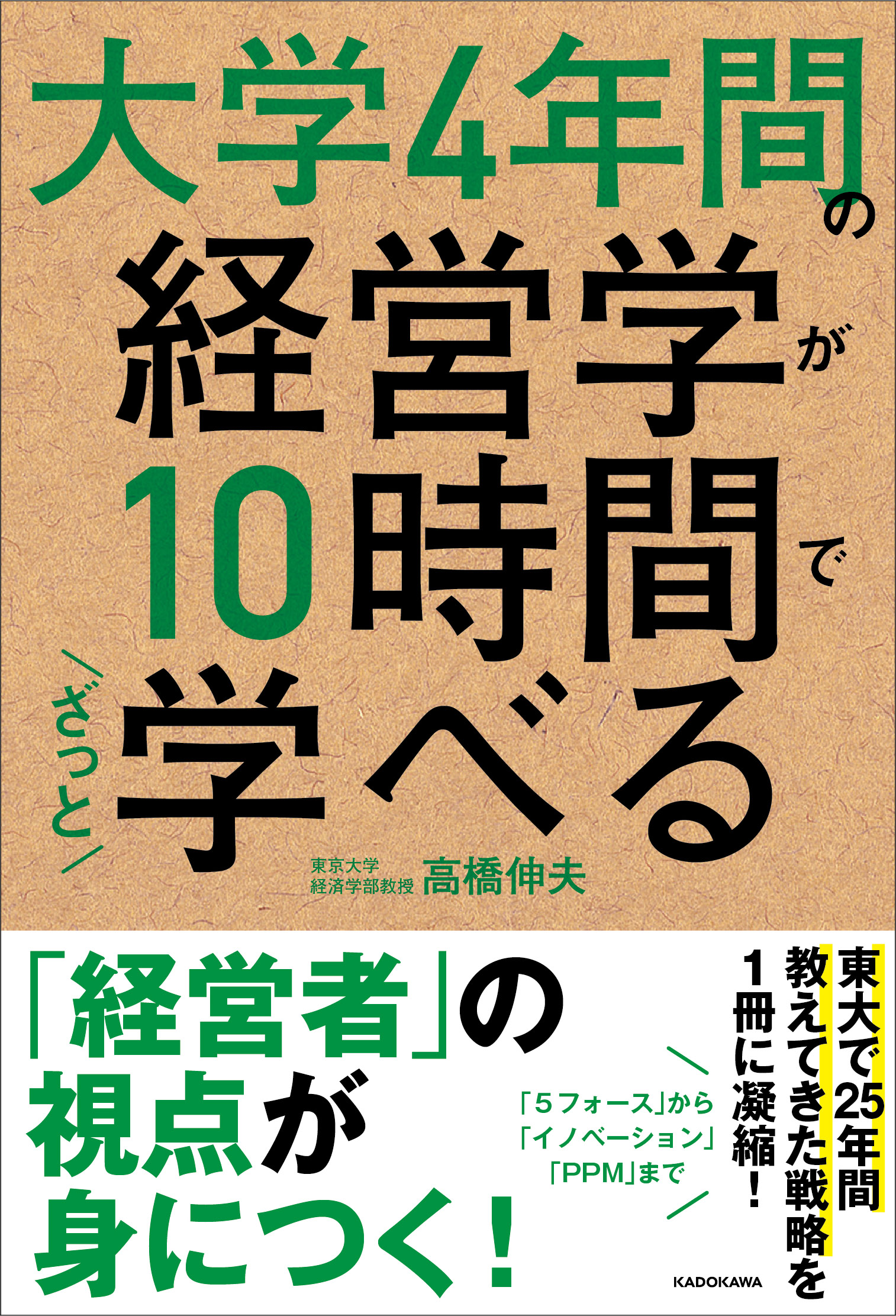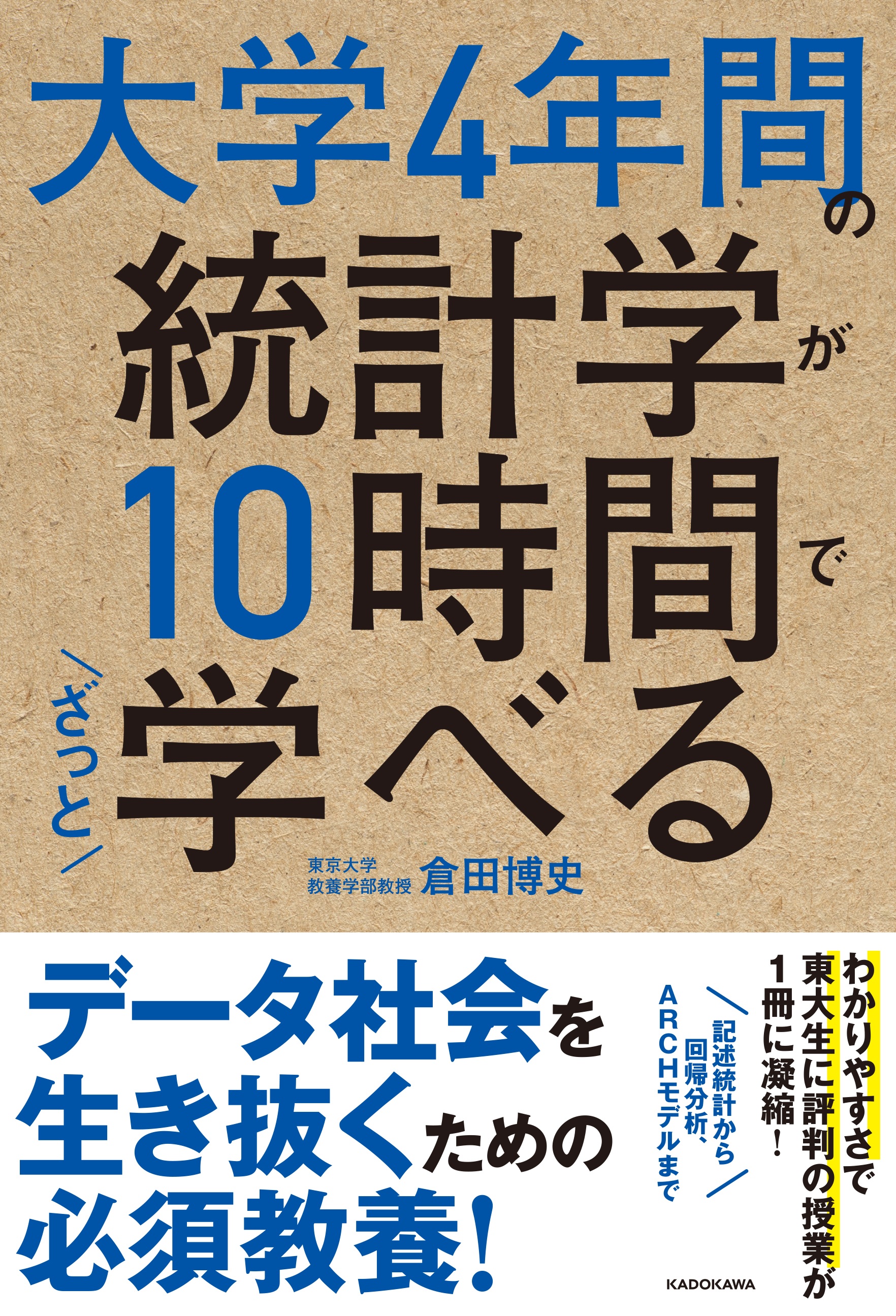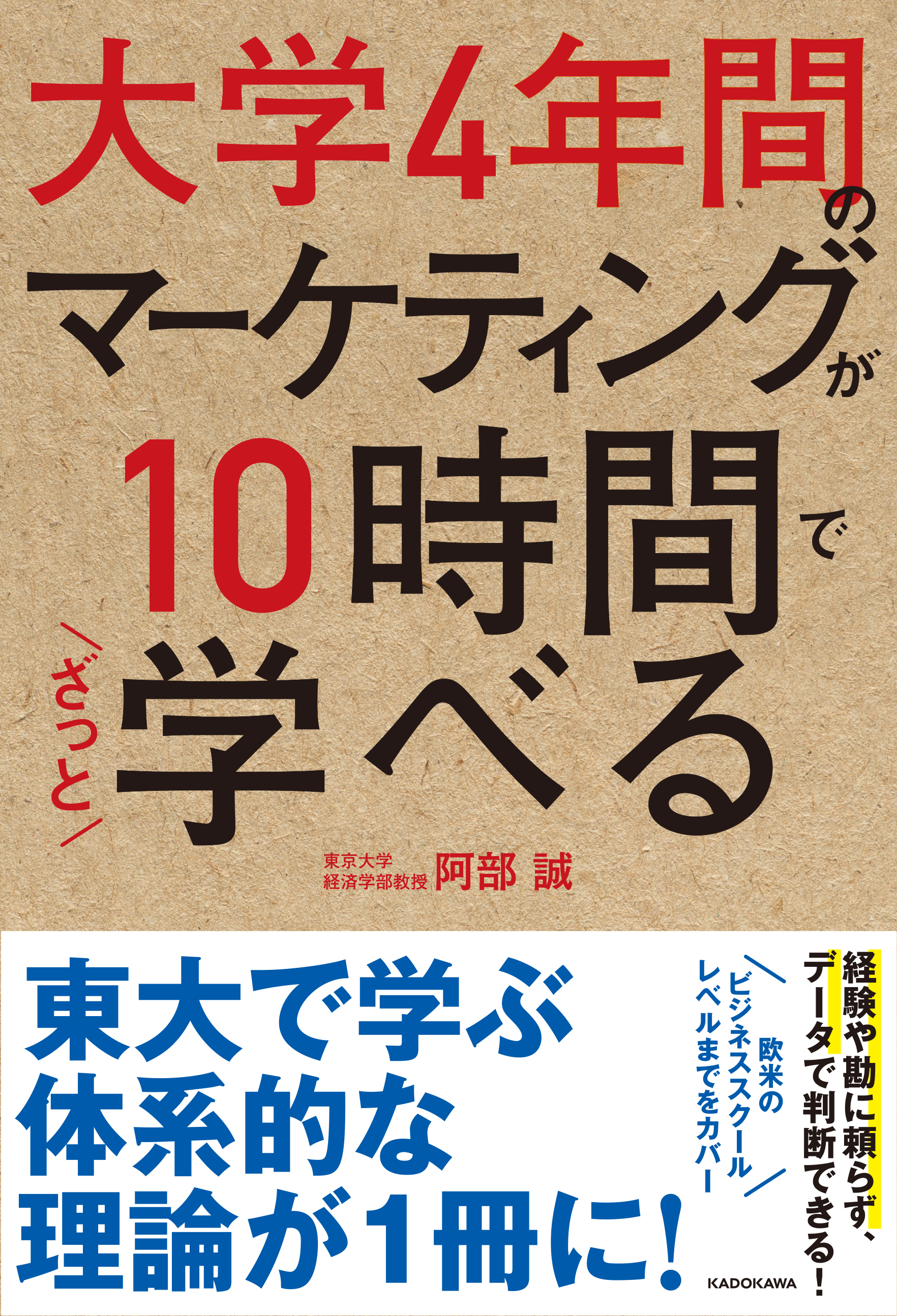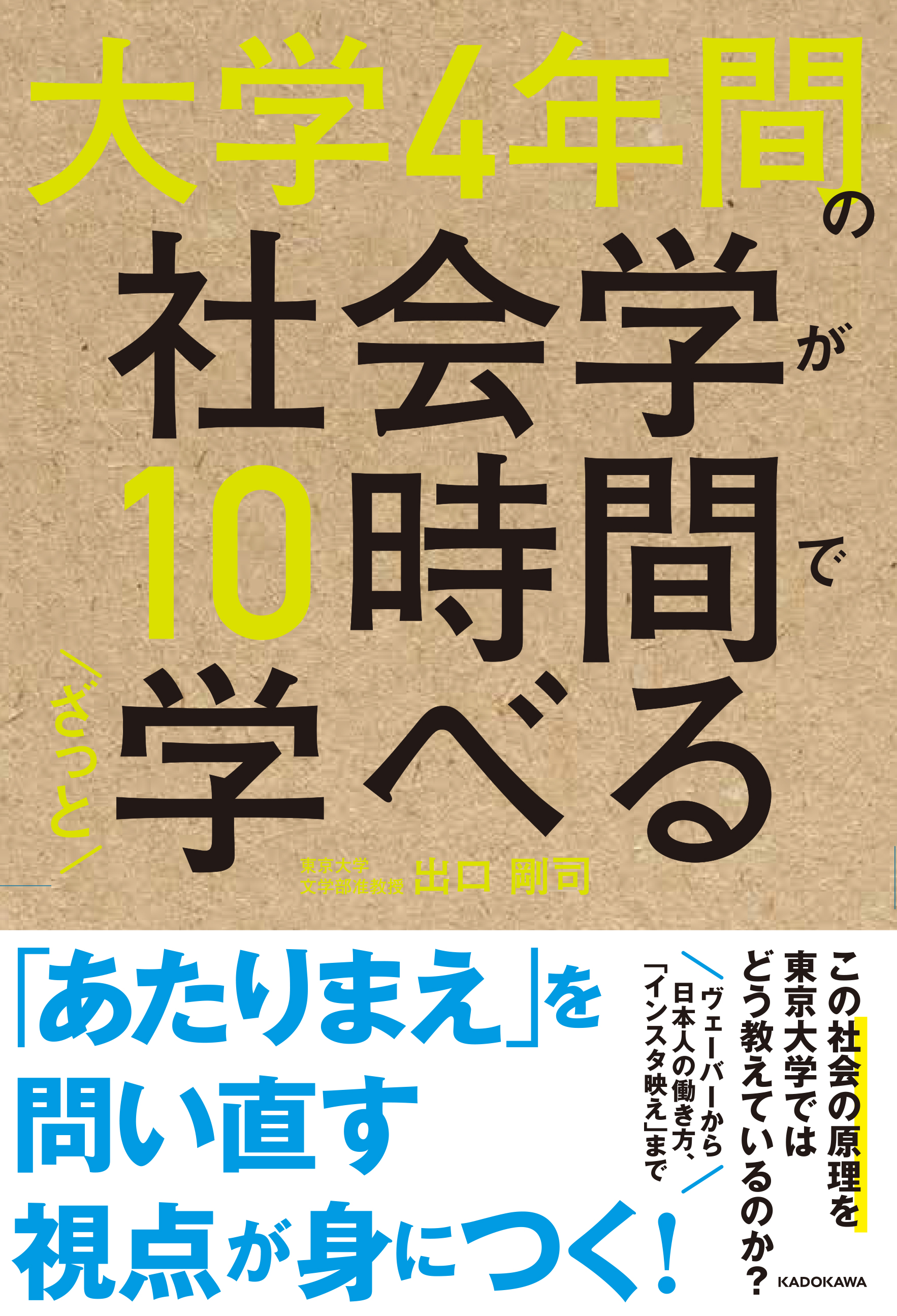
書籍名
大学4年間の社会学が10時間でざっと学べる
判型など
232ページ、四六判
言語
日本語
発行年月日
2019年2月1日
ISBN コード
9784046019905
出版社
株式会社KADOKAWA
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
社会学とはどのような学問だろうか? 「社会」について研究している学問だ、ということは容易に想像できます。しかし、その中身を具体的にイメージするのはとても難しい。その理由は、研究対象である「社会」がつかみどころのない、空気のような存在だからです。同じ社会科学の中でも、経済学や政治学に対して、何を研究しているのか分からない、という印象をもつ人はほとんどいないでしょう。それに引き換え、社会学が研究の対象としている「社会」はあまりにも巨大で、漠然としすぎています。
しかし、動物と異なる人間の特徴は、「社会」をつくって生きていることにあります。たしかにアリや羊も集団を作って生活していますが、それは個体が単なる「群れ」を作っているにすぎません。私たち人間は、ものの感じ方、考え方、そして他人とコミュニケーションをとったり、高度な思索を支える言語に至るまで「社会」の中で作られ、生まれてから死ぬまで「社会」の中で「社会」を学習し、反復し、新たに作り直しつづけるのです。そして一人になっても、こうした「社会」のチカラから逃れることはできません。「社会」とは空気のような存在で、私たちはそれにしらずしらずのうちに取り込まれ、ときに抑圧され、生きづらさを感じるのです。また逆に、こうした空気のような社会によって生かされてもいるのです。しかし問題は、こうした「社会」という空気を目で見たり、触ったりすることができないという点にあります。社会学とはまさに、こうした空気を「見える化」し、その仕組みを解明する学問なのです。
本書は5部構成で、最初の第1部が社会学理論、最後の第5部が社会学史になっています。この二つの部から社会学の基本的な考え方と歴史について学ぶことができます。真ん中の第2部から第4部は身近な日常世界から日常から異質な非日常的な世界へとテーマが拡大していきます。第2部では私たちの生活の場である家族や地域社会を取り扱い、第3部では産業・労働を通して私たちの働き方について考えます。第4部はそうした日常の外にある消費、宗教、政治、国際社会について論じていきます。冒頭から順番に読み進めると、社会学の考え方が身に着き、それをもとに身近な世界から出発し、日常の外部にあって日常を外から支配する社会の仕組みを理解することができます。そして最後に社会学の偉大な歴史を垣間見ることができます。本書を執筆するにあたって、とくに心がけたことは、「立ったままで読める」ことです。本書を手にとった読者は、おそらく、「社会」や「社会学」を理解する手がかりを本書に求めているのだと思います。本書はそうした読者が「社会はこんなふうになっているのか」「社会学とはこういう学問だったのか」と「腑に落ちる」ことを目指しています。
社会学の勉強をさらに専門的に深めたい人のために、本書の最後に簡単な読書案内をつけています。これから社会学を学ぼうとする人、社会学に興味があるがイメージがつかめない人、すでに社会学を学んだけれども、もう一度学びなおしたい人、そして最後に、今生きている「社会」を違った形で経験してみたい人に本書はおすすめです。
(紹介文執筆者: 人文社会系研究科・文学部 准教授 出口 剛司 / 2020)
本の目次
第1章 <社会> の謎と正体を探る (1)
01 (社会名目論) <社会> は何からできている?
02 (資本主義の成立) <社会> は個人から説明できる
03 (創発特性) しかし <社会> は個人を裏切る!
04 (社会システム論) <社会> が維持されるメカニズム
≪コラム≫ 社会学の最重要課題とは?
第2章 <社会> の謎と正体を探る (2)
01 (社会実在論) 今度は <社会> からはじめよう!
02 (自殺の原因解明) <社会> に翻弄される個人
03 (役割取得と役割距離) 個人は <社会> の裏をかく
04 (合理的選択理論) それでも人は合理的に行動する
≪コラム≫ 構造の二重性
第3章 社会学の流儀
01 (理解と説明[1]) 理解という方法で <社会> を研究する
02 (理解と説明[2]) <社会> に対するさまざまな説明
03 (理解と説明[3]) 理解と説明を組み合わせる
04 (機能分析) 存在理由を知れば納得する
≪コラム≫ 実在論と構築主義
第4章 <社会> を知るためには集団を見よ
01 (ゲマインシャフトとゲゼルシャフト) 時代と共に変化する個人・関係・社会
02 (官僚制) 人を縛る鉄の檻
03 (準拠集団) 集団は個人に判断基準を提供する
04 (内集団と外集団) 偏見と敵意は集団が育む
≪コラム≫ 個人も社会も存在しない!
第2部 身近な世界から出発しよう
第5章 家族の作り方
01 (生産 / 再生産と公的領域 / 私的領域) 社会に走る見えない線引き
02 (近代家族) 私たちの家族は特別
03 (性別役割分業とM字型就労) 男性と女性の役割はなぜ違う?
04 (ロマンティック・ラブ) 愛しているのは君だけ、あなただけ
≪コラム≫ <子ども> の誕生
第6章 性愛と親密な関係
01 (純粋な関係性) 実は危ういピュアな関係
02 セックス、ジェンダー、セクシュアリティ) 性を表すさまざまな表現
03 (ヘゲモニックな男性性) 男の中の上下関係
04 (多様化する共同性) 新しい家族のカタチ
≪コラム≫ 性の解放と社会学
第7章 都市と地域社会
01 (都市の類型学) 都市の空気は自由にする
02 (都市と無関心) 満員電車は人を個性的にする
03 (人間生態学) 都市はこうして発展する
04 (都市の生活様式と文化) 都市は生活と文化の発信源
≪コラム≫ パサージュとファンタスマゴリー
第8章 変容する都市空間
01 (グローバル・シティ) 国家を超える都市の形成
02 (インナーシティ問題とジェントリフィケーション) 都市の再生をめざして
03 (ゲーティド・コミュニティ) 中世に逆戻りする都市
04 (情報ネットワーク社会の形成) 都市はネットの中に溶解する?
≪コラム≫ 無縁社会
第3部 働き方と職場の人間関係
第9章 人が働く / 働かせる方法
01 (資本主義の誕生) 資本主義はこうして生まれた?
02 (資本主義と格差) 資本主義が生み出す平等と不平等
03 (テイラー主義とフォーディズム) こうして豊かな社会が誕生した
04 (ポスト・フォーディズムとトヨティズム) 世界に冠たるトヨタ
≪コラム≫ サービス業と感情労働
第10章 日本人の働き方
01 (日本的経営) 日本的経営と三種の神器
02 (ジョブ型とメンバーシップ型) 日本人はこうして仕事を回す
03 (新卒一括採用) 就活という日本独自の現象
04 (長期安定雇用と年功賃金) 一つの会社で長く働く理由
≪コラム≫ 日本的経営と日本型近代家族
第11章 働き方を見直す
01 (過労死) 死ぬまで働くのは勤勉だから?
02 (同一労働・同一賃金) 即戦力か、潜在的能力の蓄積か
03 (外国人労働者) 移民がやってくる理由
04 (セカンドシフト) 女性は仕事のあとにまた仕事
≪コラム≫ 資本主義の新しい精神
第12章 集団とネットワーク
01 (弱い紐帯の強さ) 本当に役立つのは薄い人間関係
02 (構造的な空隙) 漁夫の利はどこに存在する?
03 (社会関係資本) つながり自体がもつ力
04 (アクターネットワーク理論) 人とモノとのハイブリッドなネットワーク
≪コラム≫ ポスト・ヒューマン社会の到来
第4部 日常と非日常のインターフェイス
第13章 神話世界としての消費空間
01 (誇示的消費) 消費するのは何のため?
02 (依存効果) 売れる商品とは?
03 (記号消費) 私たちがモノを買う理由
04 (マクドナルド化と消費の殿堂) 消費の合理化と再魔術化
≪コラム≫ ディズニーランドと現代社会
第14章 宗教と社会
01 (社会の脱魔術化) 合理化する社会のゆくえ
02 (聖と俗) 社会とは宗教そのもの
03 (聖なる天蓋) リアリティを安定させる機能
04 (市民宗教) 宣誓式で、アメリカ大統領はなぜ聖書に手をのせる?
≪コラム≫ 「日本人は無宗教」は本当か?
第15章 政治という非日常
01 (支配の三類型) 暴力だけでは治まらない
02 (公共圏) 民主主義の始まりはカフェにあり
03 (権力) 権力は抑圧するだけではない
04 (社会問題の構築主義) 最初から解決すべき問題があるのではない
≪コラム≫ 疑似環境という疑似問題
第16章 グローバル化する世界と日本
01 (世界システム論)「世界は一つ♪」なのか
02 (想像の共同体) 世界の果てで日本人に会うと
03 (世界リスク社会) 富の分配からリスクの分配へ
04 (象徴的通標と専門家システム) 時間と空間が分離する世界で生き抜くには
≪コラム≫ 安心と信頼
第5部 社会学物語
第17章 社会の発展法則を解明せよ!
01 (コントと社会学の始まり) めざすは秩序と進歩の調和
02 (スペンサーと社会進化論) 明治の知識人も愛したイギリス人
03 (マルクスと革命思想) 社会学最大のライバル
04 (世態学から社会学へ) 日本の社会学はこうして始まった
≪コラム≫ コントの情熱と人類愛
第18章 危機の時代にこそ、社会学を!
01 (闘う社会学者・デュルケム) 第三共和制を守り抜け
02 (市民階級の守護神・ヴェーバー) 社会を動かす主体たれ
03 (生粋のベルリン子・ジンメル) 不遇の社会学者ジンメルの夢
04 (知識社会学と批判理論) 独裁が生じる理由
≪コラム≫ 転換期の社会理論
第19章 社会の秩序はこうしてできている
01 (パーソンズと秩序問題) 規範を共有し、社会秩序を維持せよ
02 (マートンと中範囲の理論) 社会の仕組みを経験的にとらえろ!
03 (ブルーマーとゴフマン) 社会は相互行為からできている
04 (ガーフィンケルとシュッツ) 日常生活を問い直せ
≪コラム≫ 問い合わせ 伝説の社会学者
第20章 現代社会学への道
01 (ハーバーマスとルーマン) 社会はシステムとして作動する
02 (ブルデューとフーコー) 自由な主体、そんなものは存在しない
03 (ギデンズ) 第二の近代化、あるいは終わらない近代
04 (バウマンとベック) 液状化する社会とリスク化する世界
≪コラム≫ 21世紀社会学のキーワード



 書籍検索
書籍検索