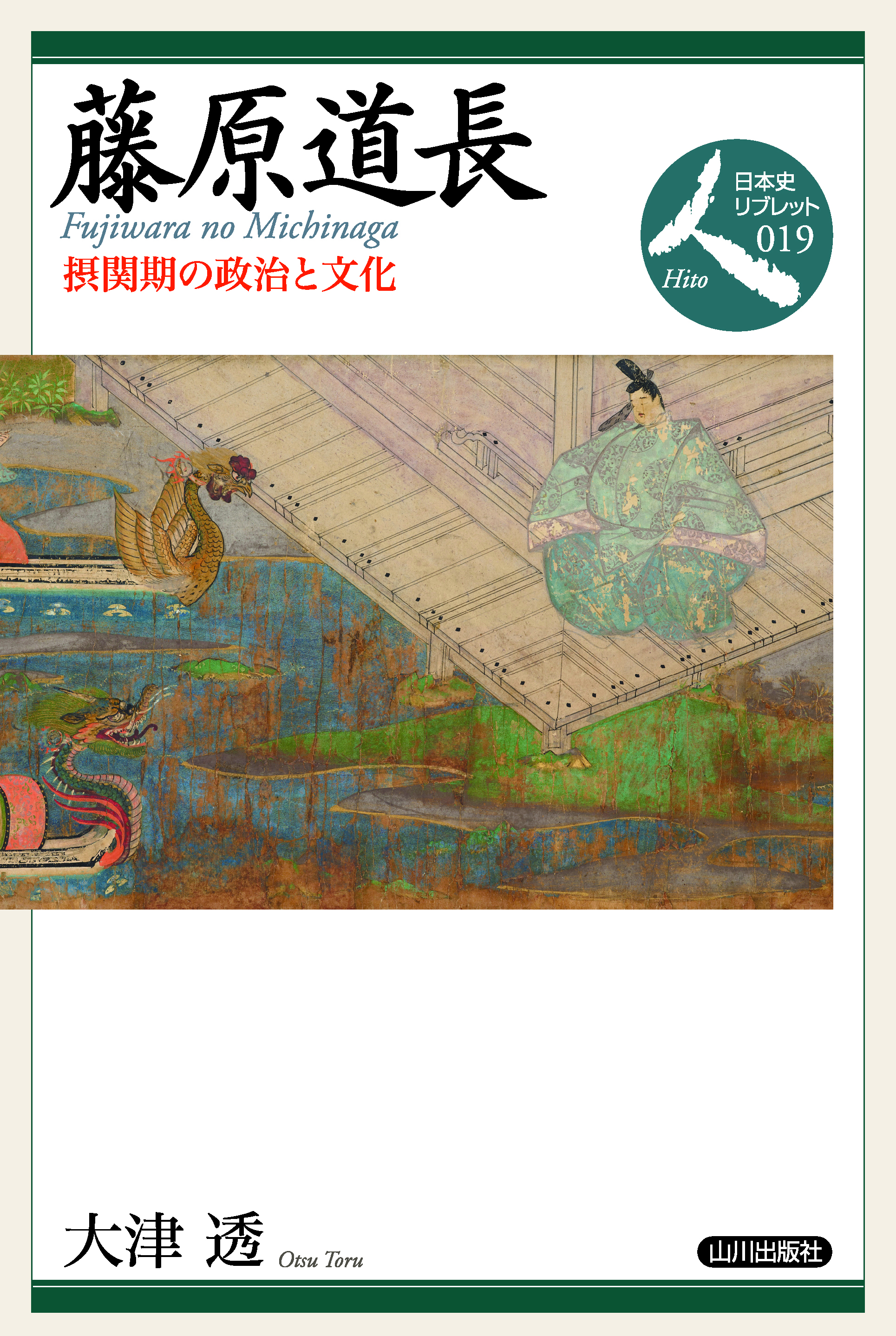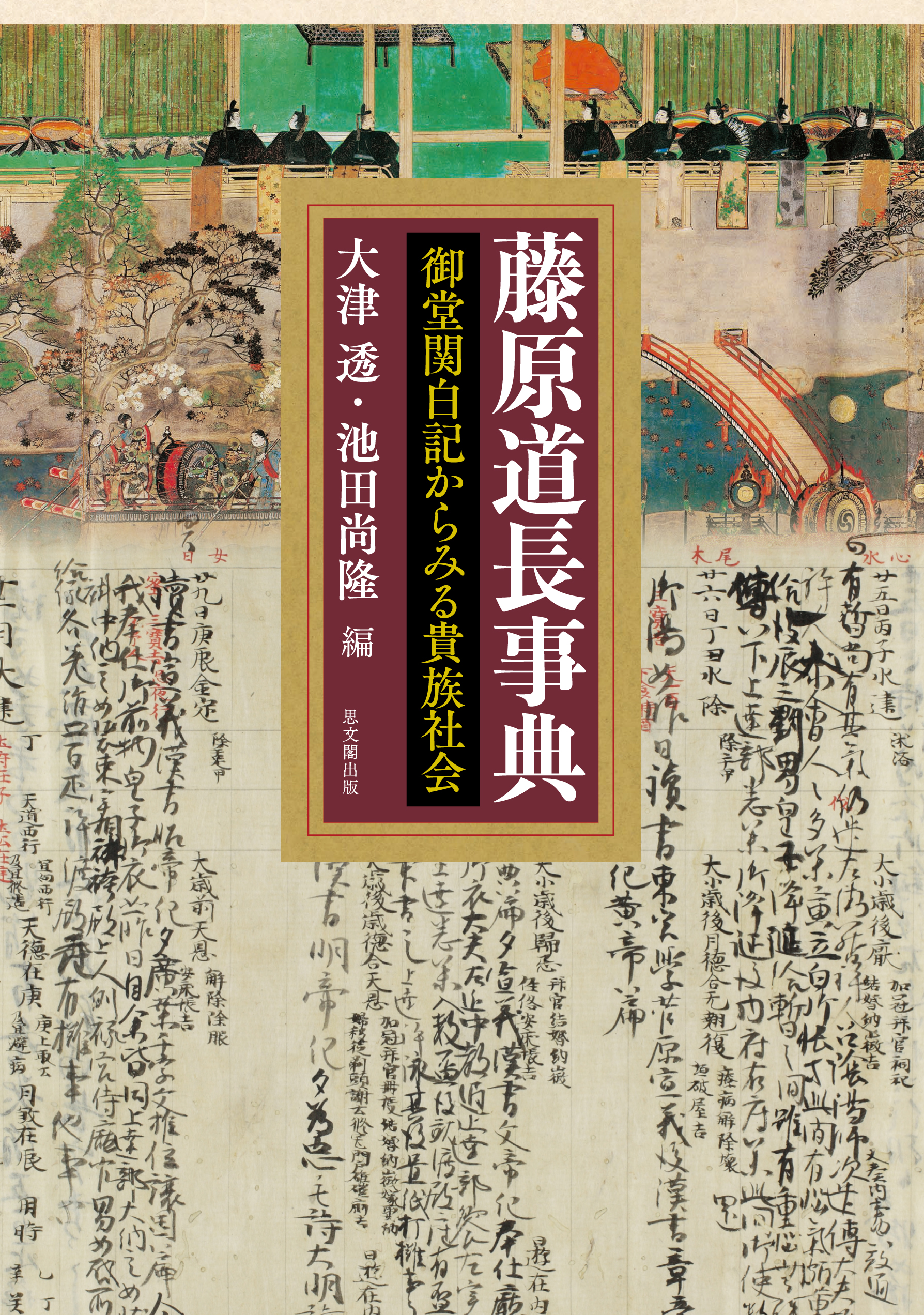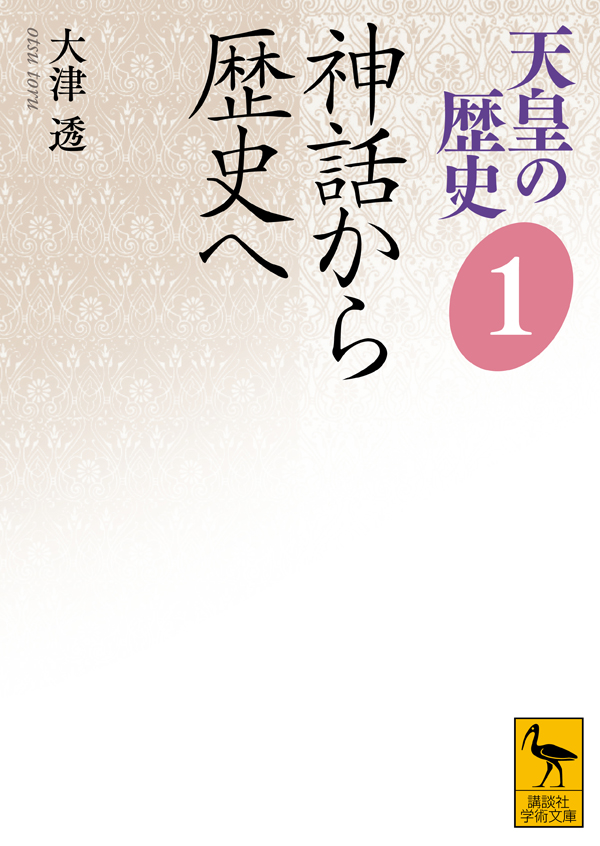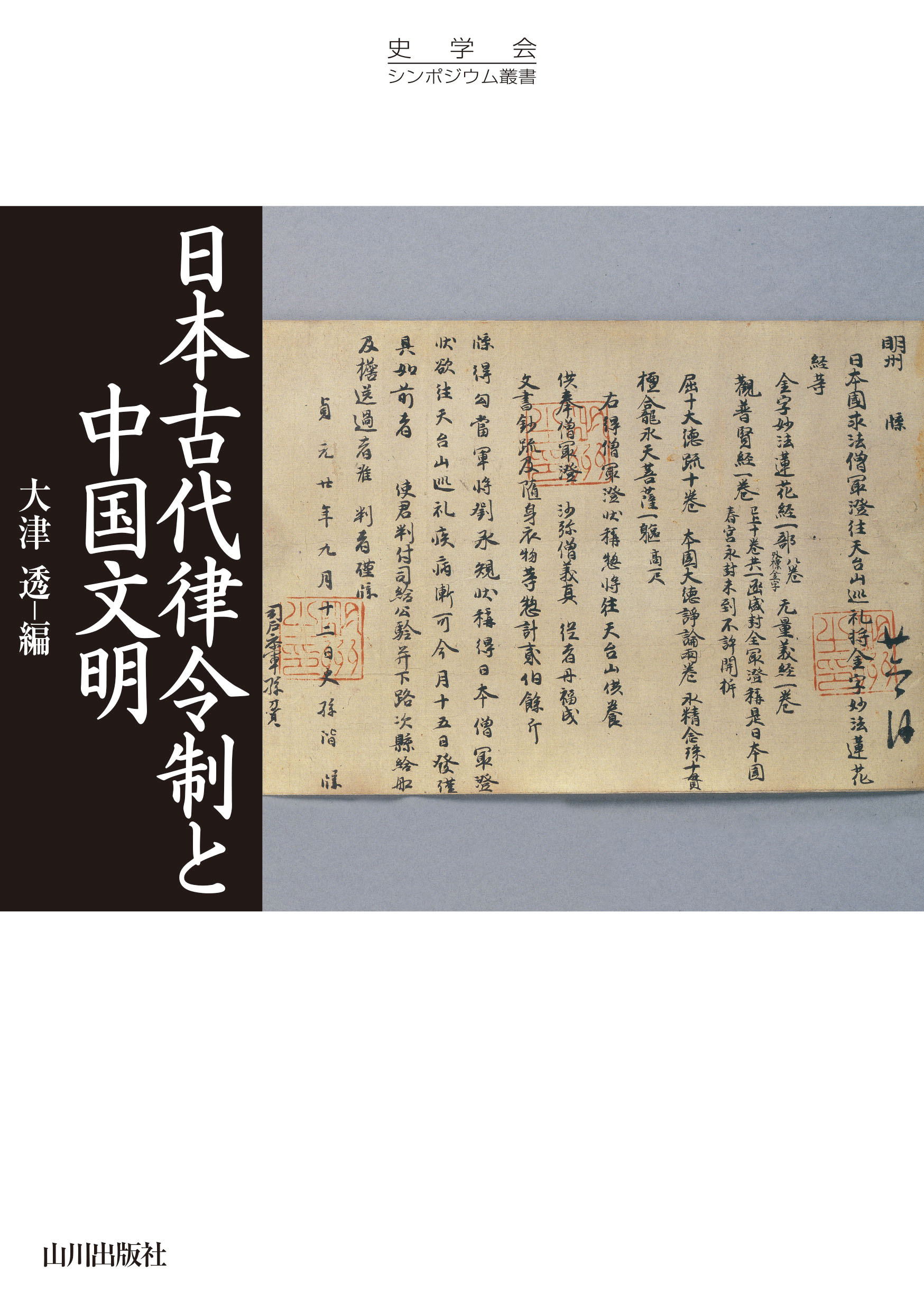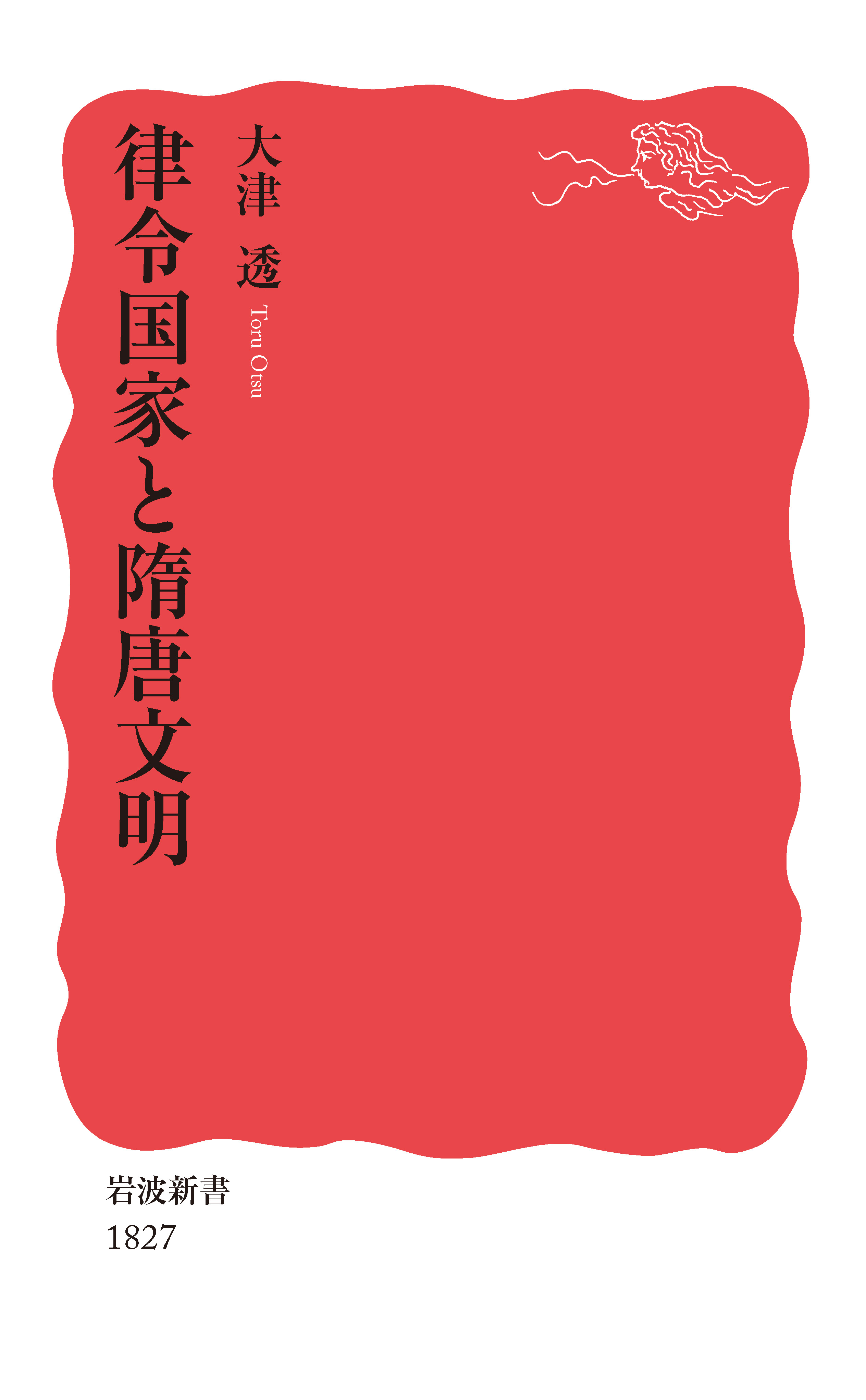本書は、摂関期を代表する権力者である藤原道長をとりあげて、前半ではその生涯を叙述しその実像に迫り、後半では彼が行った政治のあり方の特色を明らかにし、また彼が中心となって推進した仏教や文芸などの文化的達成をとりあげた。藤原道長と摂関期の政治や文化を古代国家の歴史の中に位置づけることをめざした。
かつて、摂関政治は、貴族は先例だけを守り儀式作法に意を注ぎ、実質的な政治は無いとされていたが、国家政治の中心は太政官にあり、平安時代中期の政治制度の実証的研究が進んだ。受領についても地方官として徴税を請け負っていたことが明らかになった。こうした国家の中に藤原道長の政治を位置づけた。
藤原道長は摂関政治の頂点にいると考えられるが、実際には孫の後一条天皇が即位したわずか1年間摂政になっただけであり、三条天皇が即位したときに関白就任の要請があったが辞退し、もっぱら内覧と一上左大臣の地位を保った。政治史的には三条天皇との対立が有名で、後一条の即位をめざして天皇に陰湿に退位をせまった専制的権力者というイメージが強いが、実際には三条天皇に問題が多く、道長が貴族社会全体の利益を統合し代弁していることを述べた。また生涯後半には仏教への奉仕を強め、金峯山詣や出家後の法性寺の造営など大きな達成であるが、出家後も「大殿」として大きな政治力をもったことは、摂関政治をゆがめた面がある。
政治のあり方としては、公卿が集まって合議する「定」、陣定が大きな意味をもったことで、道長はそれに左大臣として参加して議論を主導したことが特色である。陣定は、改元定、罪名定など国家的重要議題で開かれたほか、諸国申請雑事定、造宮定、受領功過定など地方行政、つまり受領の統制に関する議題で開催された。とくに任期終了後の受領の成績を審査する受領功過定では、調庸制の再編を受けてあらたに審査項目をふやすことで財源の確保をめざし、例外的に全員一致の結論が出るまで繰り返された。一方で中納言以上の公卿は、上卿として「政」において諸司諸国からの申請を決裁し、また様々な行事の執行も上卿として担当した。こうした公卿の合議と分担を一上と内覧として統括したのが道長の政治の特色であり、公卿連合の太政官政治の上に権力を築いたことは、古代国家の伝統の到達点と評価できる。
文化史上では仏教への貢献が大きく、法華経信仰を広め、晩年無量寿院・法成寺を造営した。そこで仏師康尚・定朝を登用し、定朝様の古典的と呼ぶべき美を生みだしたことに大きな意義がある。みずから漢詩の作詠や書籍の蒐集につとめ、一条朝の漢文学の興隆に大きな貢献をしたが、さらに『紫式部日記』の執筆や『源氏物語』の流布にも大きく関与し、屏風歌の作成などを通じて和歌など女性中心の文化を歴史の表舞台に取り込み、文化の基盤を広げた。
(紹介文執筆者: 人文社会系研究科・文学部 教授 大津 透 / 2023)
本の目次
1. 道長の登場
2. 道長と一条天皇
3. 三条天皇との対立と外孫の即位
4. 道長の政治
5. 道長の文化
おわりに 『御堂関白記』と『栄花物語』
関連情報
NEW 第14回東京大学文学部公開講座 「天皇号と日本国号の成立と意味」 (東京大学人文社会系研究科・文学部 2024年6月22日)
https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/events/z0105_00042.html



 書籍検索
書籍検索