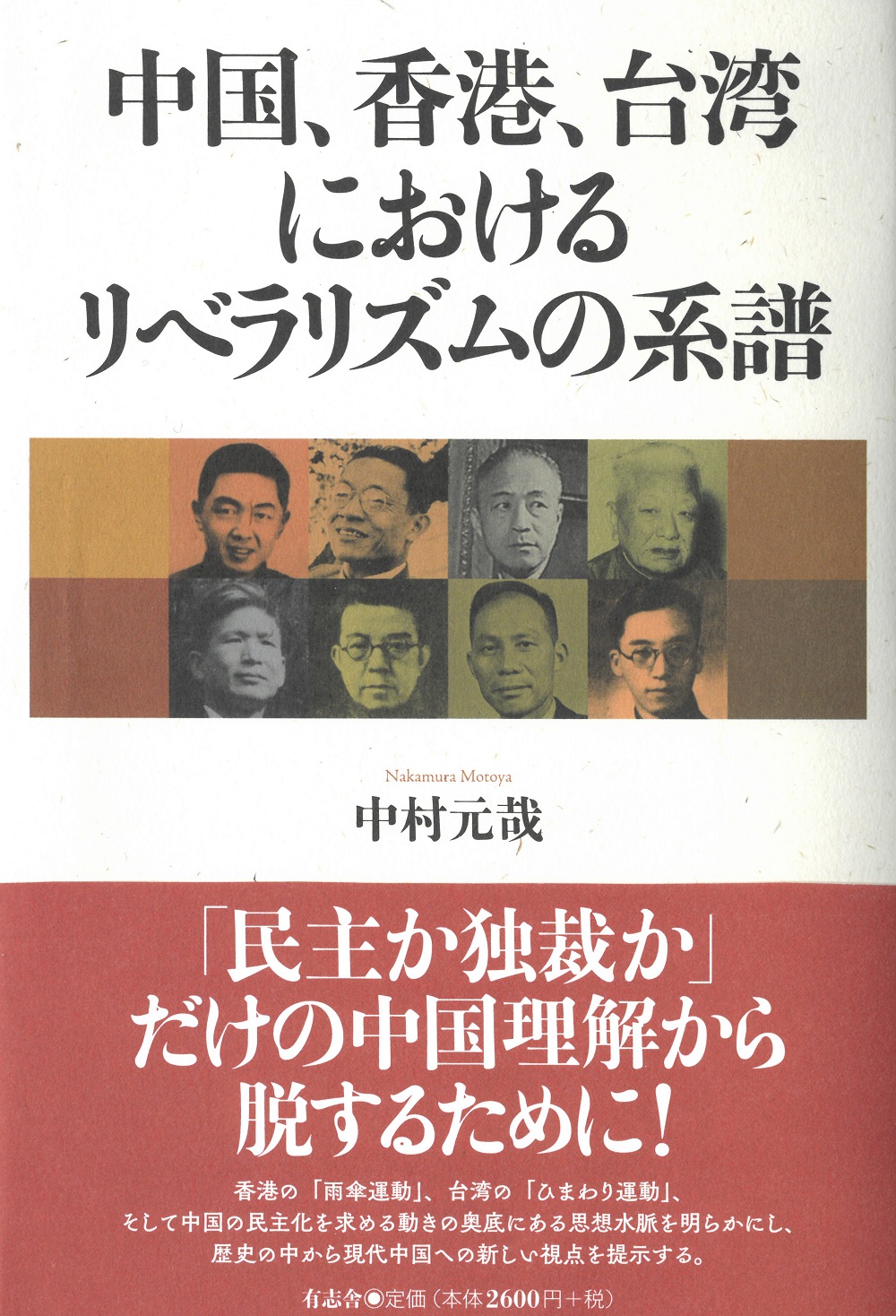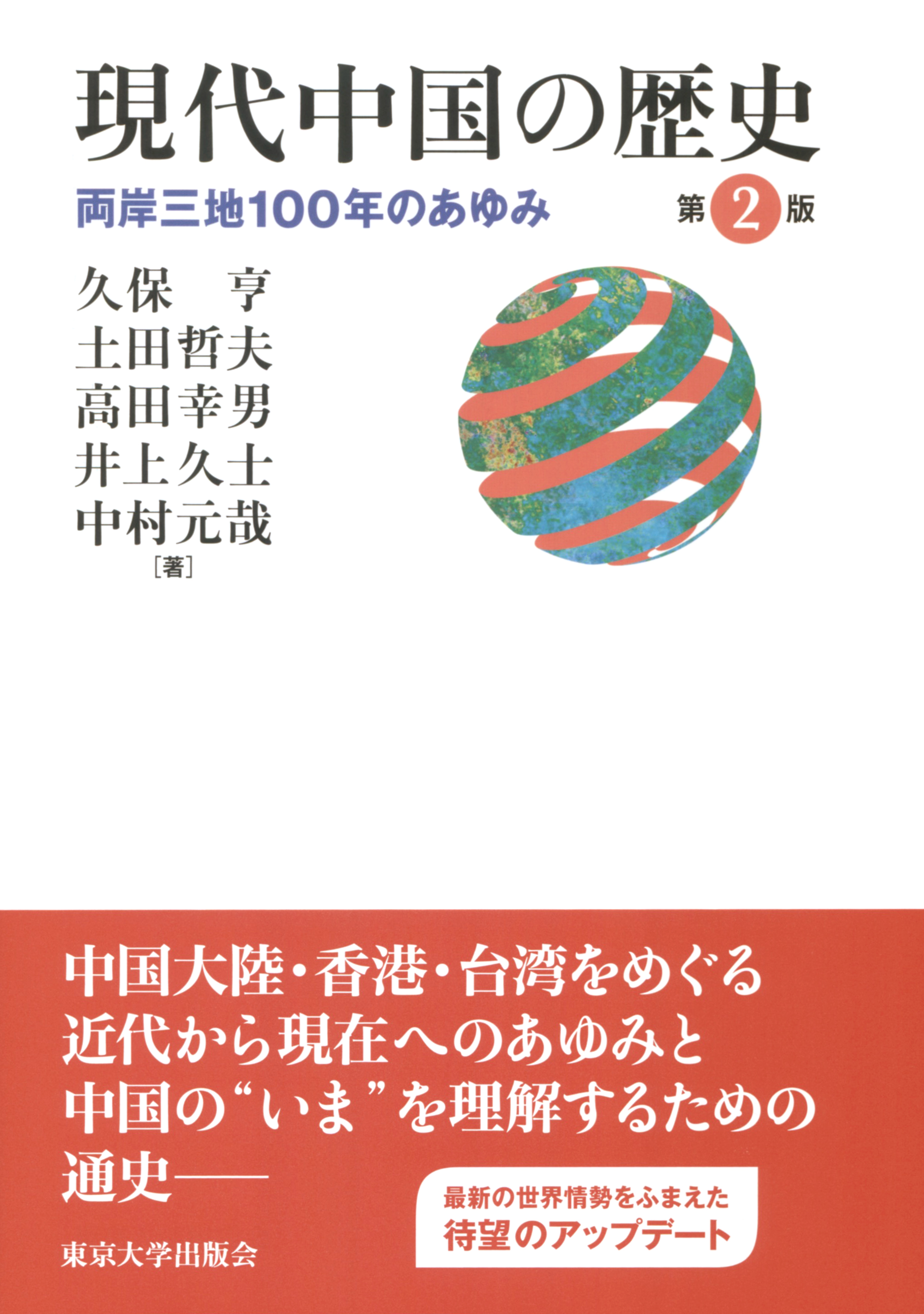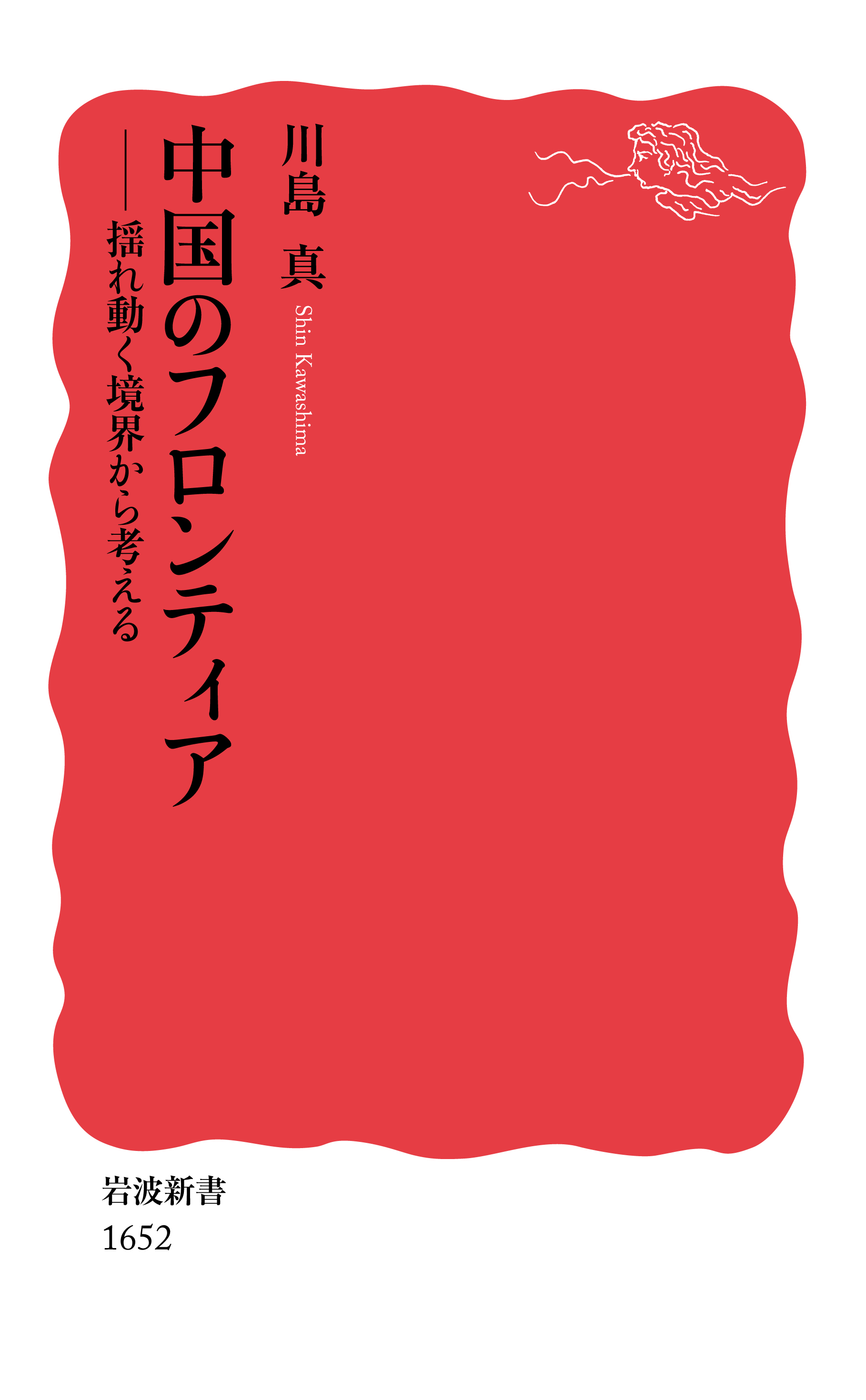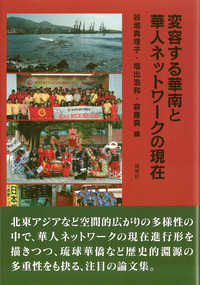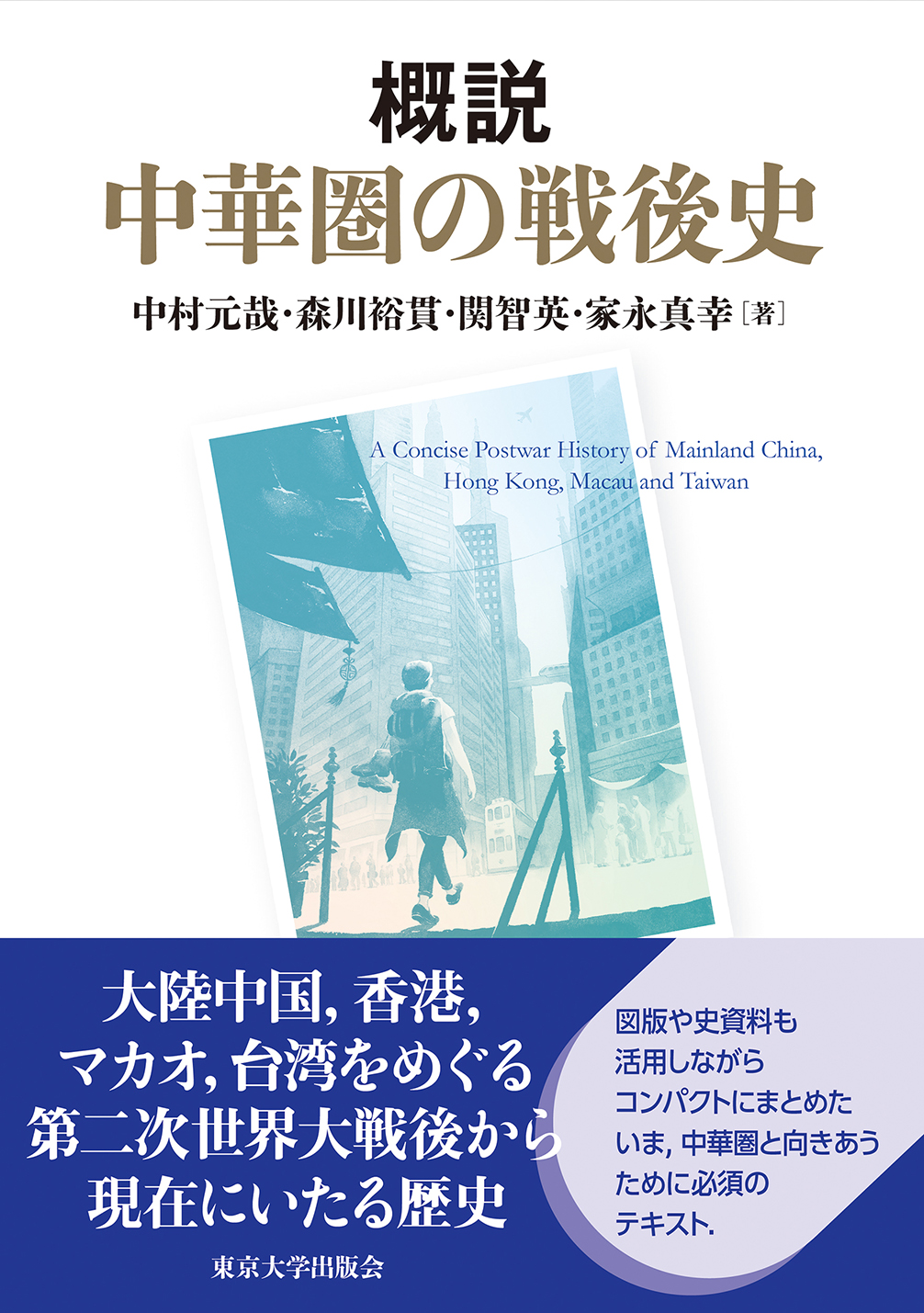
書籍名
概説 中華圏の戦後史
判型など
276ページ、A5判
言語
日本語
発行年月日
2022年10月26日
ISBN コード
978-4-13-022028-6
出版社
東京大学出版会
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
民主化をめぐる香港の社会運動が、2010年代に、中国と香港との間で新たな摩擦を生んだ。そして、その余波が、民主化した台湾にも広がった。こうした中国と香港と台湾をめぐる現状に対して、日本に住む多くの人たちは、これらの地域との心理的距離が近い分だけ、世界のどの国よりも高い関心を示している。ところが、日本では、中国と香港と台湾がそれぞれに解説されることはあっても、これらの地域の歴史的関係性を踏まえて各地域の歩みを手軽に解説した本は、これまで無かった。本書は、こうした社会的・教育的ニーズに応えようとした概説書である。
しかし、本書が刊行されるにあたり、二つの難題が立ちはだかった。
一つ目の難題は、「中国や台湾という呼称を国家概念として使用するのか否か」という政治問題を回避しながら、対象とする地域を学術書としてどのように記すのか、ということだった。本来ならば、「両岸四地」 (大陸中国・香港・マカオ・台湾) という表記が、現状では最もしっくりくる。なぜなら、「一つの中国」を原則とする中国共産党政権は「両岸四地」の使用を禁止するようになり、他方で、自らの独自性を重視しつつある台湾社会は「両岸四地」という概念を必ずしも受け入れていないからである。つまり、消去法的発想ではあるが、「両岸四地」は現状では最も中立性のある概念だと考えられる。ところが、「両岸四地」という表記は日本語にはない。そのため、代わりの日本語表記が必要になってくる。そこで、マカオを含めた中国語圏の地域を暫定的に「中華圏」と記すことにした。
二つ目の難題は、歴史的関係性を踏まえるとはいっても、「両岸四地」の現状につながる歴史性を重視して、その一つのまとまった時代をどのように呼称するのか、という問題だった。私たちは、熟考の末、戦後史という概念を選択した。その理由は、「両岸四地」の現在の関係性の根底には、日本の敗戦による各地域の再編と中国分断と呼ばれる国制の分裂があり、それらはいずれも戦後直後の歴史と深くかかわっているからである。現代史という表記の可能性も十分にあり得たが、戦後史という表記のほうが現在へとつながる「両岸四地」の歴史的深みを表せる、と判断した。
もちろん、本書の「中華圏」という見せ方をめぐっては、様ざまな立場からの様ざまな批判があるだろう。それだけ、「両岸四地」は激動の真っただ中にあるということである。また、本書の「戦後史」という見せ方をめぐっても、様ざまな立場からの様ざまな批判があるだろう。確かに、戦後史という呼称は、もはや世界の歴史学界では通用しない。日本社会は、自らが戦後ととらえてきた約80年の年月を、そろそろ適切に総括しなければならない。
本書の企画と出版は、まさに「火中の栗を拾う」かのようなものだった。それでも、誰かが「戦後史」に起因する「両岸四地」の歴史性と相互の関連性を最新の学術成果の知見に基づいてまとめなければ、日本の「両岸四地」に対する見方は更新されないだろう。このような書き手の熱意を汲み取って下されば幸いである。
(紹介文執筆者: 総合文化研究科・教養学部 教授 中村 元哉 / 2023)
本の目次
序 章 近代国家中国のあゆみ──変革の時代 (1900年代-40年代)
1. 文明と近代と革命という時代性
2. 第二次世界大戦後の風景──出発点としての1945年
3. 中国国民党から中国共産党への政権交代
[史料解読1] 胡適「近代西洋文明に対する吾人の態度」
第一章 大陸中国─建設と混乱の時代 (1950年代-70年代)
1. 毛沢東体制の始動と展開
[図版解説1] 政治運動に動員された人びと
[史料解読2] 日本人が観察した「大躍進」
2. 毛沢東体制の動揺と終焉
[図版解説2] 筆を執る毛沢東
[史料解読3] 鄧小平「どのようにして農業生産を回復させるか」
3. 混迷のなかの知識人
[図版解説3] 壁新聞
[史料解読4] 巴金「胡風を偲ぶ」
[コラム1] 人民解放軍の歴史
第二章 大陸中国──発展と強国の時代 (1970年代-)
1. 対外開放と体制改革
[史料解読5] 1982年憲法の主な部分改正
[史料解読6] 趙紫陽「中国の特色のある社会主義の道に沿って前進しよう」
2. 経済成長の光と影
[図版解説4] 改革開放と経済成長率
[史料解読7] 「復興の道」展を参観した際の習近平による講話
3. 多様化する思想文化と管理される社会
[図版解説5] 中国共産党と『中国青年報』
[史料解読8] 胡平「言論の自由を論ず」
[コラム2] 人民共和国期の映画史
第三章 香港・マカオ──中国と世界の狭間 (1950年代-)
1. 植民地としての展開と矛盾
[図版解説6] 日本軍票の交換を求める老人
[図版解説7] 九龍石硤尾の新興集合住宅
[図版解説8] 香港の映画雑誌
2. 返還への動きと社会の変容
[図版解説9] マカオ半島にあるホテルリスボアとビル群
[コラム3] オリンピックの代表権
第四章 台湾──民主化の成熟 (1950代-)
1. 中国国民党一党体制の確立と展開
[図版解説10] 国立故宮博物院 (台北)
[史料解読9] 彭明敏・謝聰敏・魏廷朝「台湾人民自救運動宣言」
2. 体制の動揺と民主化
[図版解説11] 金門包丁
[史料解読10] 李登輝「Always in My Heart」
3. 中華文化の優勢から多元社会の尊重へ
[図版解説12] ひまわり学生運動
[史料解読11] 李筱峰「台湾史は中国史の一部分なのか?」
[コラム4] 中華圏のジェンダー
終 章 中華圏と中華文明のゆくえ
文献案内
中華圏を知るための年表
関連情報
倉田徹 (立教大学法学部教授) 評 (『中国研究月報』第908号 2023年10月号)
https://www.institute-of-chinese-affairs.com/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%9C%88%E5%A0%B1
倉田徹 (立教大学法学部教授) 評 (『史学雑誌』第132編第6号 2023年6月)
http://www.shigakukai.or.jp/journal/index/vol132-2023/
関連研究:
基盤研究 (C)「中華圏におけるナショナリズムとリベラリズム:連関する大陸中国・台湾・香港」 (2017年4月-2021年3月)
https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-17K02040/



 書籍検索
書籍検索


 eBook
eBook