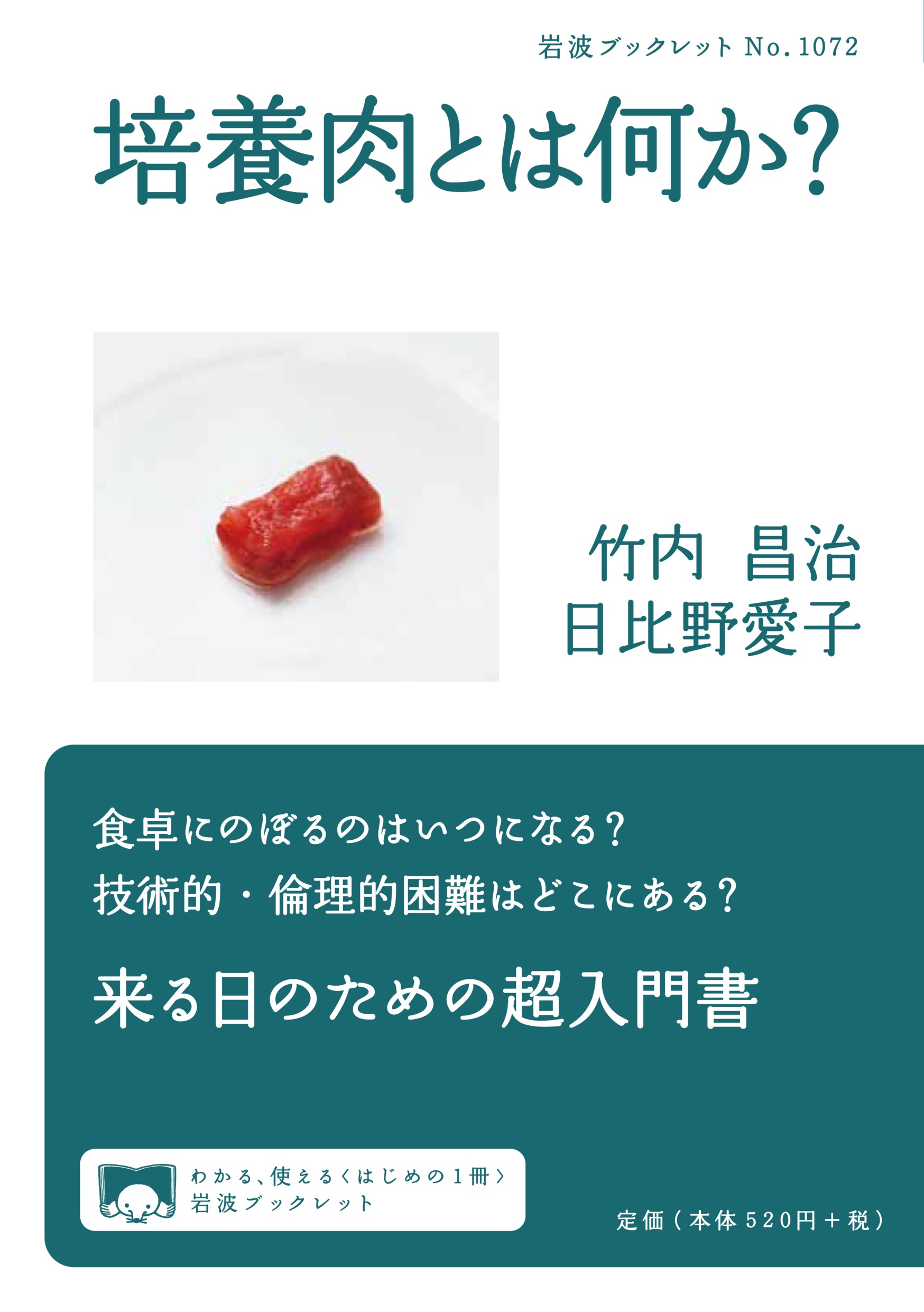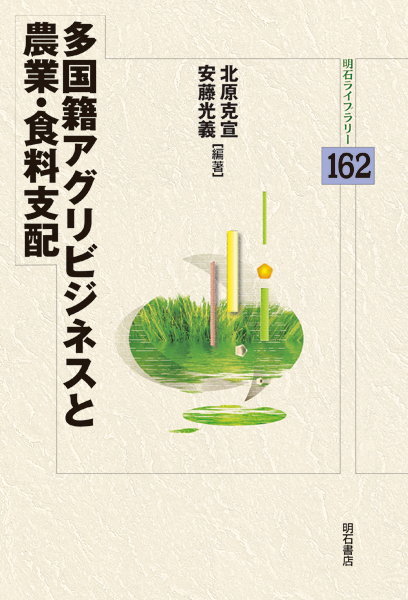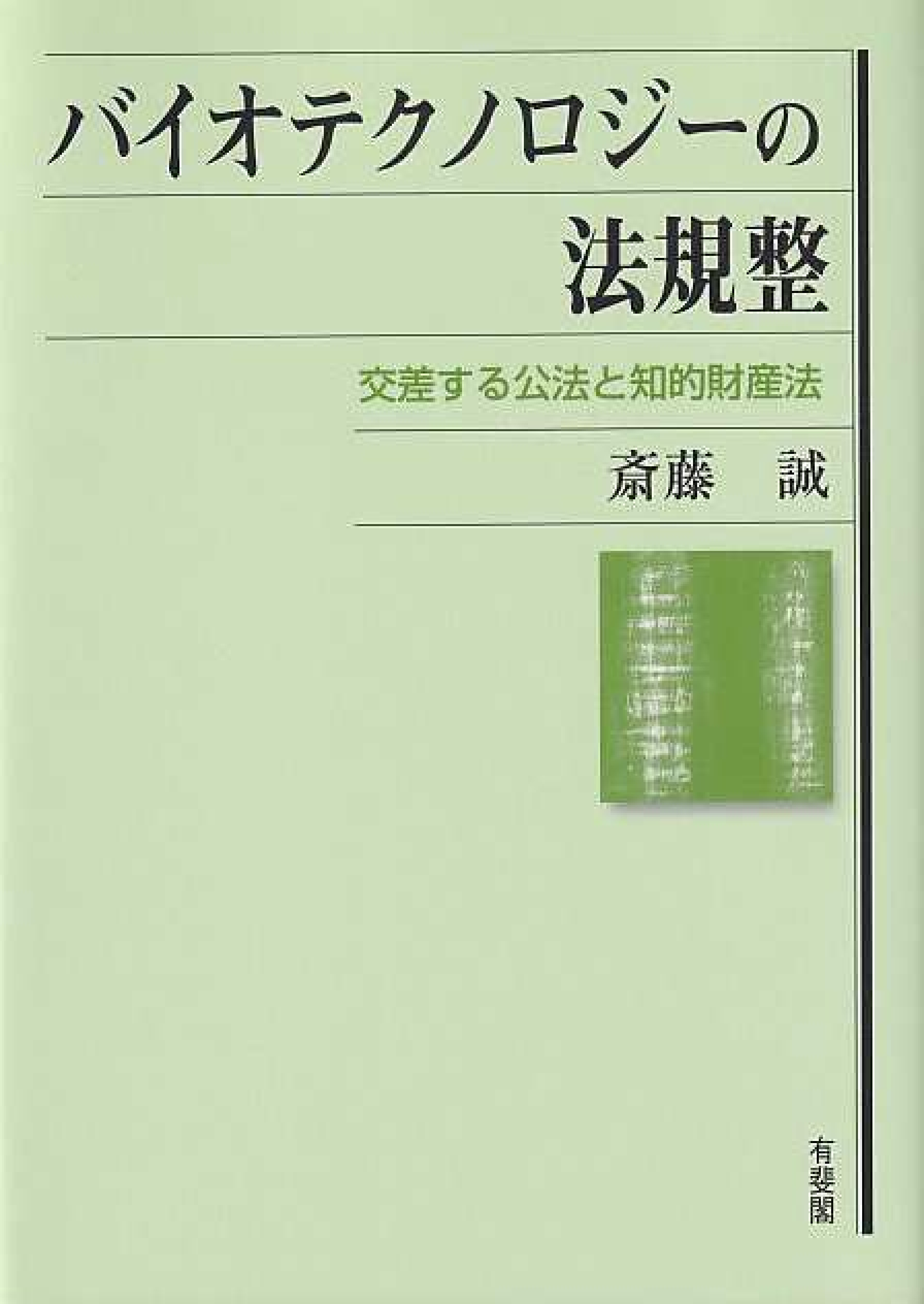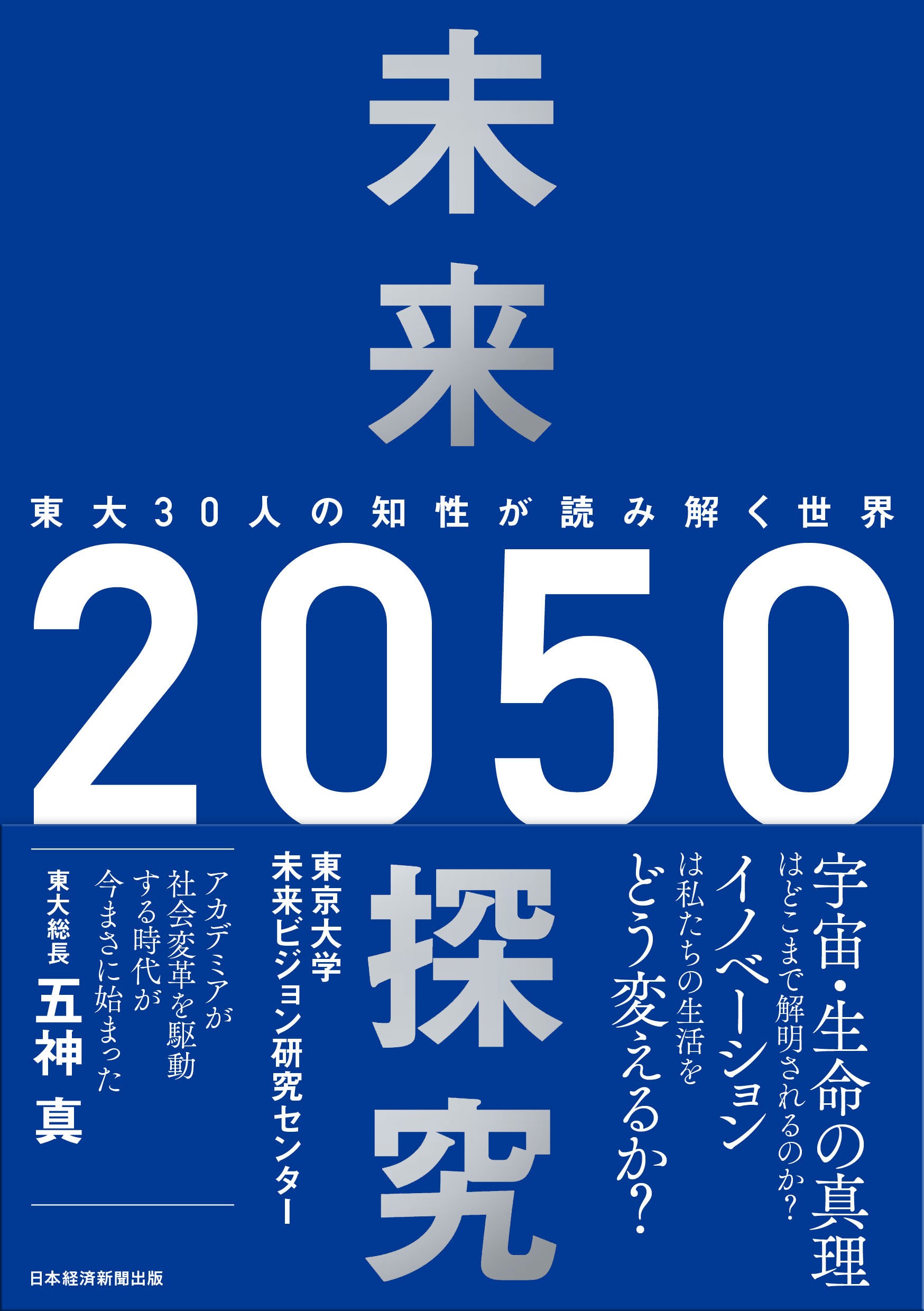培養肉とは、動物の個体からではなく、細胞を体外で組織培養することによって得られた肉のことで、家畜を肥育するのと比べて地球環境への負荷が低いことや、畜産のように広い土地を必要とせず、厳密な衛生管理が可能などの利点があるため、従来の食肉に替わるものとして期待されている。近年、世界中で「培養肉」の研究が行われており、ウシの筋細胞を集めて作ったハンバーガーやトリの細胞を用いたチキンナゲットなどが発表されてきたが、これらは、ランダムに並んだ筋肉の細胞を集めた、いわゆるミンチ肉のような組織であった。筆者らのグループでは、肉本来の食感を持つステーキ肉を培養肉で実現する目標に向け、筋組織の立体構造を体外で作製する研究に取り組んでいる。2019年に初めて筋線維が一方向に揃ったサイコロステーキ状の培養肉を発表した。また、2022年3月には、大学の倫理審査専門委員会から承認を得て、国内の大学で初めて試食することができた。
培養肉に関するプレス発表や取材を受けるたびに、「興味があるので、話を聞かせてくれないか」、「背景がわかる本はないか」とご要望をいただいた。これまでに専門書や解説記事などは多く執筆してきたが、一般の方が、手軽に読める書物をだせないかと考えていたところ、共同研究者の日比野愛子先生から、岩波書店の猿山様のご紹介をいただき、日比野先生と共著で本書を執筆することとなった。培養肉研究の背景、先端技術とこれからの課題は竹内が、社会受容性など含めた今後に関しては日比野先生が、できるだけわかりやすく書くことに専念した。
気候変動に加え、コロナ禍、ウクライナ危機など、激動の世界の中で、食糧の安全保障は一層重要な課題となっている。培養肉は、植物肉や昆虫食などに並び、課題解決のための一つの選択肢にすぎないが、牛肉に限らず、豚、鳥、魚、エビなど多彩な肉を、それぞれの体調や好みに合わせて地産地消で作ることができる究極のクラフトミートとなり得る。一方、新規の技術であり、直ちに社会に受け入れられるものではない。技術面に加えて、社会に受容される新たな食文化の醸成、どの製品でも安心して食べられる規制づくりなど、まだまだ課題は山積みである。培養肉という新しい技術が食文化として根付くためには、社会の価値観に合わせて、慎重に進めていくべきと考えている。本書をきっかけとして、この分野の研究や産業に興味をもち、参画したいという人が増えることを期待している。
(紹介文執筆者: 情報理工学系研究科 教授 竹内 昌治 / 2024)
本の目次
第1章 なぜ今、培養肉なのか?
第2章 培養肉のつくり方
第3章 培養肉への期待と不安
第4章 立ちはだかるハードルの数々
おわりに
関連情報
http://www.hybrid.t.u-tokyo.ac.jp/culturedmeat/
日清食品HDとの共同研究「研究室からステーキ肉をつくる。」
https://www.nissin.com/jp/sustainability/feature/cultured-meat/
最初に試食したときの様子の報告
『ついに食べた!』~未来の肉「培養肉」の今~ (NHK 2022年4月20日)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220420/k10013590031000.html
書評:
短評 (『月刊クーヨン』 2023年4月号)
関連記事:
東大・竹内教授ら、培養肉に「血管を通す」ことに成功――再生医療への応用にも期待 (日経バイオテク 2023年9月11日)
https://bio.nikkeibp.co.jp/atcl/news/p1/23/09/06/11055/
家畜を育てなくても肉が食べられるってホント? (東京大学広報室 2023年5月30日)
https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/features/z1304_00230.html
培養肉研究の現在地と未来図 (5) ゲノム編集技術も培養肉へ展開可能!課題は社会受容性――これからの培養肉研究と社会受容性の問題 (テンミニッツTV 2023年2月7日)
https://10mtv.jp/pc/content/detail.php?movie_id=4783
培養肉研究の現在地と未来図 (4) 培養肉が社会で受け入れられるための「3つの課題」――「本物の肉」再現への課題 (テンミニッツTV 2023年1月31日)
https://10mtv.jp/pc/content/detail.php?movie_id=4782
培養肉研究の現在地と未来図 (3) 3800万円の培養肉バーガー…技術革新で大幅コストダウン――培養肉開発の方法 (テンミニッツTV 2023年1月24日)
https://10mtv.jp/pc/content/detail.php?movie_id=4781
培養肉研究の現在地と未来図 (2) 食糧不足だけではない、「第3の肉」登場への4つの背景――培養肉需要の背景 (テンミニッツTV 2023年1月17日)
https://10mtv.jp/pc/content/detail.php?movie_id=4780
培養肉研究の現在地と未来図 (1) 食肉3.0時代に突入、「培養肉」研究の今に迫る――フェイクミート市場とリアルミート研究 (テンミニッツTV 2023年1月10日)
https://10mtv.jp/pc/content/detail.php?movie_id=4779
楽しく悩んで、食の未来を変える~「培養肉」研究の最前線~ (Science Portal 2019年10月24日)
https://scienceportal.jst.go.jp/gateway/sciencewindow/20191024_w01/
実用化が見えてきた「培養肉」は未来の食卓を変える存在になり得るか?――東京大学大学院 情報理工学系研究科知能機械情報学専攻 教授 竹内昌治【後編】 (EMIRA 2019年6月29日)
https://emira-t.jp/ace/10931/
“牛肉は研究室で”作られる! 「培養肉」研究の第一人者に食の未来を聞いた――東京大学大学院 情報理工学系研究科知能機械情報学専攻 教授 竹内昌治【前編】 (EMIRA 2019年6月28日)
https://emira-t.jp/ace/10917/
インタビュー:
【取材】第一人者が語る培養肉の「今」と「これから」 (日本細胞農業協会 2023年1月25日)
https://cellagri.org/articles/2023-01-25-23-19_%E3%80%90%E5%8F%96%E6%9D%90%E3%80%91%E7%AC%AC%E4%B8%80%E4%BA%BA%E8%80%85%E3%81%8C%E8%AA%9E%E3%82%8B%E5%9F%B9%E9%A4%8A%E8%82%89%E3%81%AE%E3%80%8C%E4%BB%8A%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%80%8C%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%8B%E3%82%89%E3%80%8D
「培養肉」はどんな味、工学研究者が挑む次の時代のおいしさ――東京大学 大学院 情報理工学系研究科 教授 竹内昌治氏 (日経クロステック 2022年8月9日)
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00134/080800321/
竹内 昌治 ― 培養肉の開発 (東京大学 / The University of Tokyo|YouTube 2021年3月2日)
https://www.youtube.com/watch?v=lLon4_f48qY
対談:
堀江貴文×竹内昌治 「培養肉」に 「ひも状組織」【東大生産研・竹内昌治氏が語る “細胞でのモノ作り”とは?】 (ZEROICHI 2021年12月23日)
https://zeroichi.media/with/1755
イベント:
第186回「培養肉」を食べる未来 (U-Talk|東京大学 2023年9月)
https://fukutake.iii.u-tokyo.ac.jp/utalk/2023/10/13/08.html



 書籍検索
書籍検索