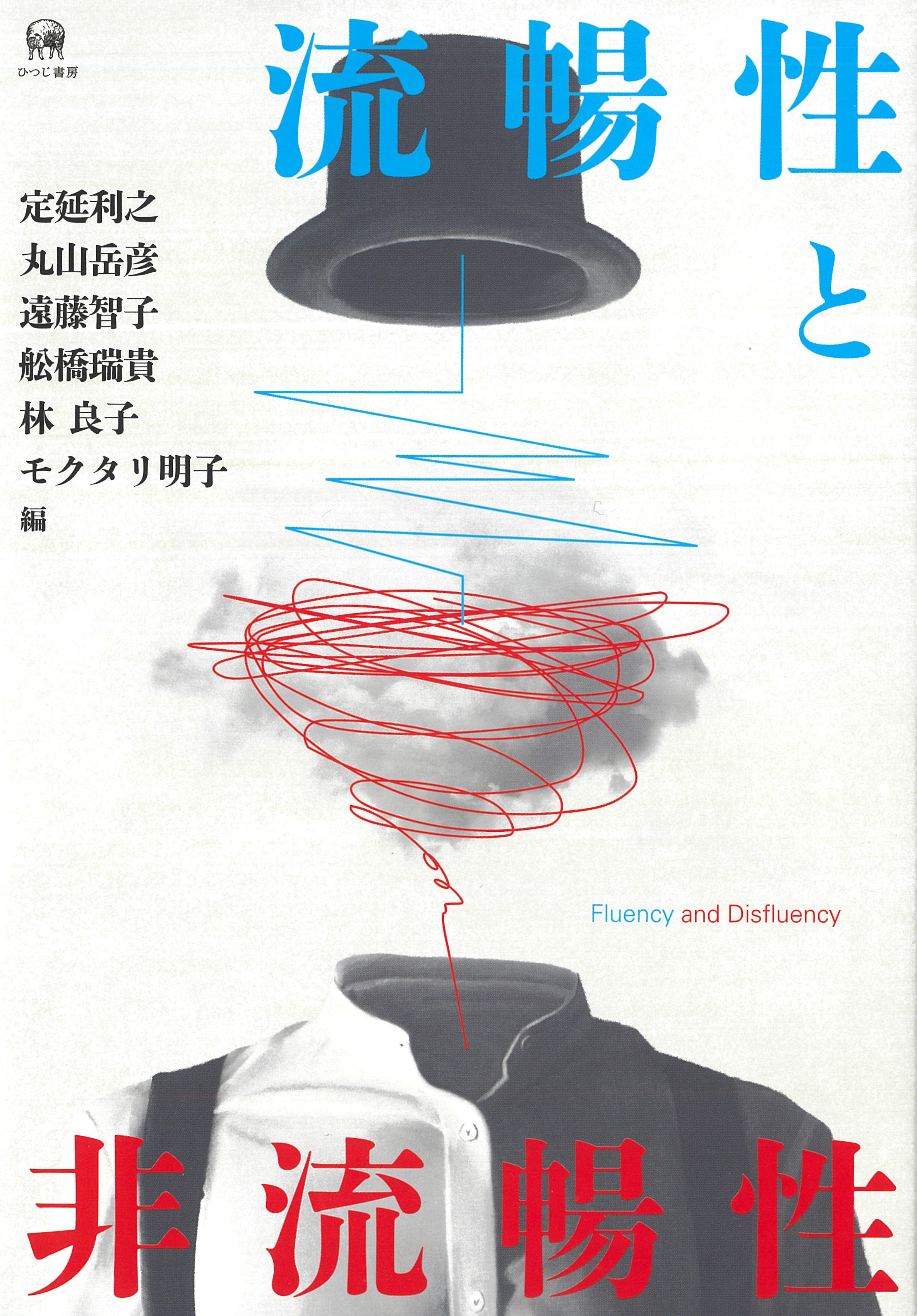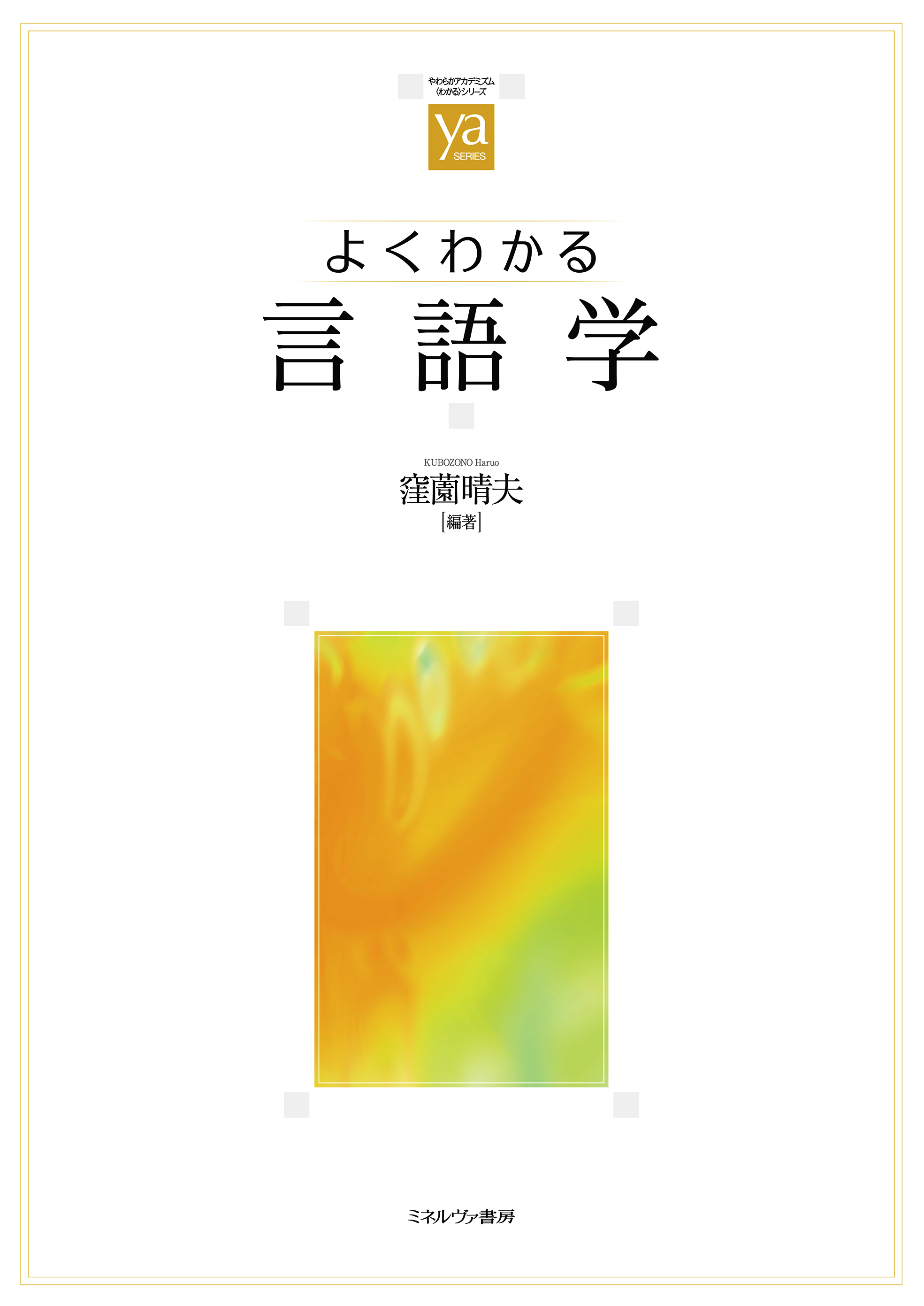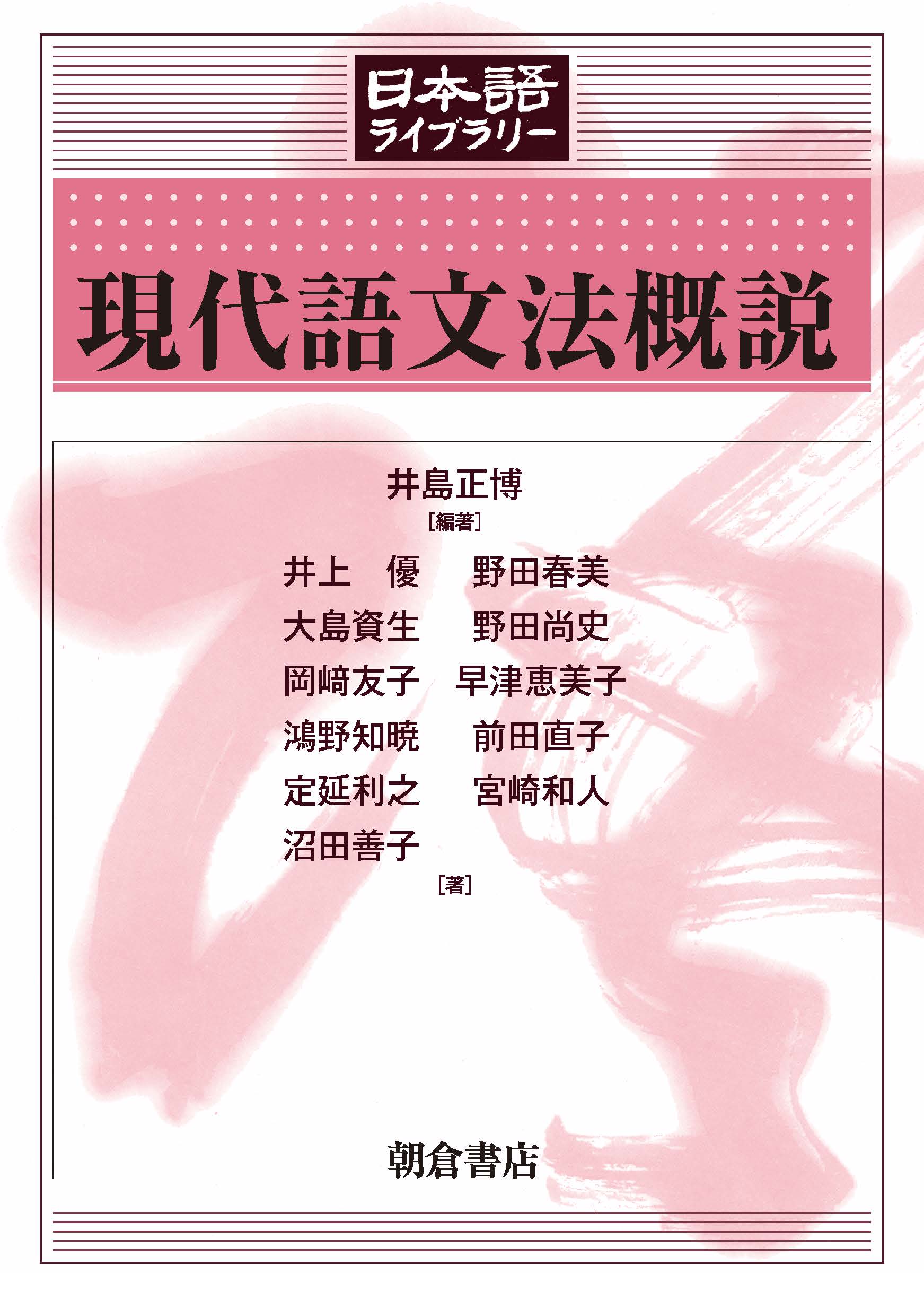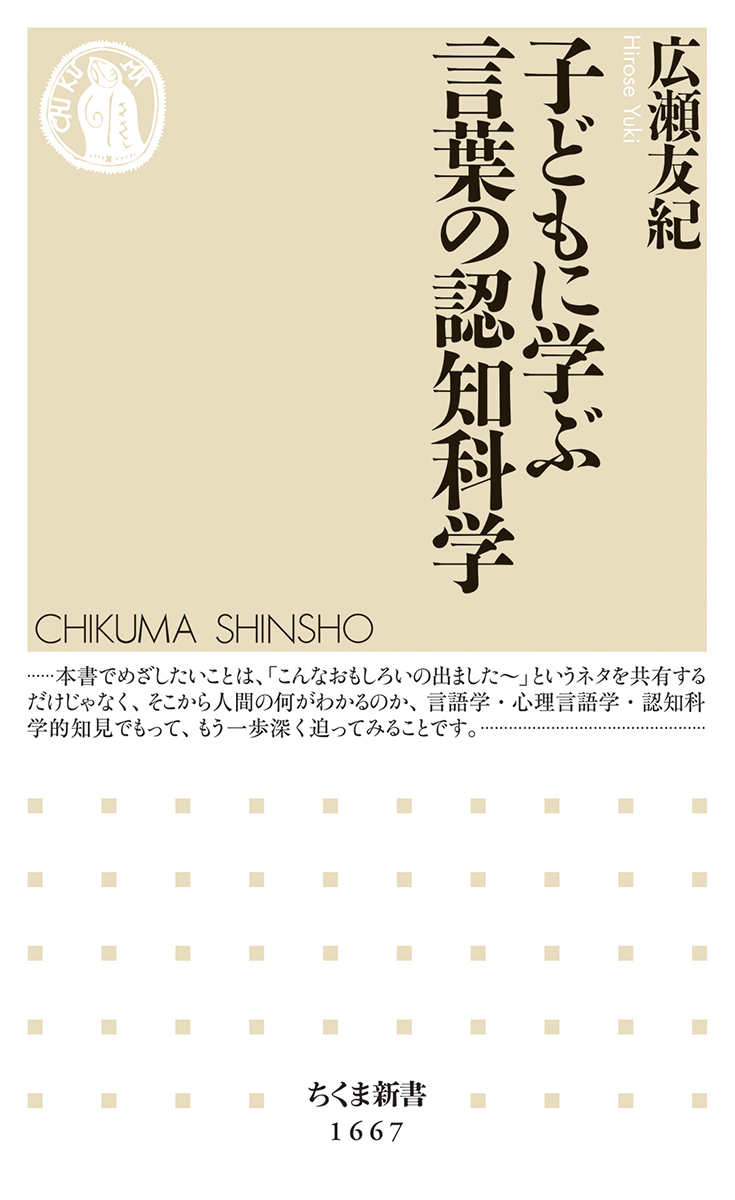言葉が人間の個人的および社会的活動にとって決定的な重要性をもつことは疑いようがないが、我々が言葉について考えるとき、しばしばそれは抽象化され理想化されたものとなる。そのような言葉はたしかに言葉のありうる形であり、論理関係や命題を表すためのいわば純粋な言語形式なのかもしれないが、我々が普段使う言葉とは大きく異なっている。実際に使われる言葉は、つっかえたり、のばされたり、言い換えられたり、時には途中で放棄されたりと、スムースとはいえないいびつで淀んだ形をしているのだ。本書はそのような言語の非流暢性に正面から取り組むとてもめずらしい取り組みである。
本書は第1部:総論、第2部:記述言語学、第3部:コーパス言語学、第4部:会話分析、第5部:言語教育、第6部:言語障害、第7部:非流暢性の獲得、という7部構成である。それぞれの部には2編から7編の論文が収録されており、本全体では25本の論文を読むことができる。第2部以降は本書の基となる科研費プロジェクト「非流暢性な発話パターンに関する学際的・実証的研究」(代表:定延利之 (京都大学)) を構成する各班と対応する。2020年より始まったこのプロジェクトは、各班がそれぞれ独自に活動しつつ、シンポジウムや学術誌の特集号では各班の班長が一同に会して研究発表を行うことで、言葉の非流暢性という問題に対する理解を様々な角度から深めてきた。
筆者が班長を務める会話分析班の論文で扱った現象をいくつか紹介しよう。たとえば、「うん」と言って肯定するような場面で、「う~ん」という引き伸ばされた形で発話を産出したら、そこではどのようなことが起きるのだろうか。日本語において、フィラー (「えーと」や「あのー」等、言いよどむ時に発される実質的な意味の薄い要素) としての「う~ん」と肯定応答詞としての「うん」の境界が実は曖昧であることが、会話に参加する人々にとって便利な資源として活用されているということが、実際のデータを会話分析の手法で詳細に分析すると見えてくる (第4部第1章)。また、同じくフィラー的な要素として、日本語会話では「なに」「なんだろう」「なんだっけ」「なんていうの」等の自問発話がしばしば用いられる。そのような場合の韻律的特徴や身体の動きは、個々の自問発話により傾向が異なることが観察された。さらに、話し手と聞き手の間にある相対的な知識状態と語る権利への志向が、自問発話への応答の有無と深く関わることもわかった (第4部第4章)。
言葉が非流暢であるということは、言われてみれば当たり前のことのように思えるかもしれないが、実は言葉にとって非常に本質的な重要性をもつ。様々なアプローチで非流暢性に取り組んできたこのプロジェクトの成果は、まだ出発点にすぎず、今後も研究は続いていく。始まったばかりの非流暢性研究を、この本を通じて是非知ってほしい。
(紹介文執筆者: 総合文化研究科・教養学部 准教授 遠藤 智子 / 2024)
本の目次
第1部 総論
第1章 発話の (非) 流暢性への総合的なアプローチ
定延利之
第2部 記述言語学からみた (非) 流暢性
第2部のねらいと論文紹介
定延利之
第1章 (非) 流暢性と現場性
定延利之
第2章 コーパスと談話から見た接続表現の共起と (非) 流暢性
アンドレイ ベケシュ、ボル ホドシチェク、仁科喜久子、阿辺川武
第3部 コーパス言語学からみた (非) 流暢性
第3部のねらいと論文紹介
丸山岳彦
第1章 「通時音声コーパス」とフィラーの経年変化
丸山岳彦
第2章 言い直し表現のアノテーション
―その基準と方法論の検討―
吉田奈央、丸山岳彦
第3章 語句の選択誤りを伴う言い直し表現の細分化
吉田奈央
第4章 L2日本語話者の自己モニタリング
―「漸次的な発話産出」に焦点を置いて―
井畑萌
第4部 会話分析からみた (非) 流暢性
第4部のねらいと論文紹介
遠藤智子
第1章 「うん」と「う~ん」のはざま
―相互行為の資源としての非流暢性―
早野薫
第2章 文節末延伸の韻律的バリエーションとその相互行為上の帰結
横森大輔
第3章 サービス場面における依頼発話にみられる非流暢性と優先組織
黒嶋智美
第4章 自問発話の応答要求性
遠藤智子
第5部 言語教育からみた (非) 流暢性
第5部のねらいと論文紹介
舩橋瑞貴
第1章 日本語学習者の自問発話
小西円
第2章 自問発話の音調の多様性と習得
―「何というか」を手がかりに―
須藤潤
第3章 口頭発表におけるフィラー
―口頭発表指導への応用を視野に入れて―
舩橋瑞貴
第4章 非流暢な母語話者と割り込めない学習者
―電話会話における期待に沿えない回答への学習者の対応―
平田未季
第5章 合意形成場面における非流暢性
―日本語母語話者と日本語学習者の発話を比較して―
宮永愛子
第6章 日常談話における「ちょっと」の多義性と非流暢性
鹿嶋恵、西村史子
第7章 初級日本語テキストにおける「ちょっと」の出現状況
西村史子、鹿嶋恵
第6部 言語障害からみた (非) 流暢性
第6部のねらいと論文紹介
林良子
第1章 運動障害性構音障害におけるリズム異常の印象
―子音の歪み、発話明瞭度との関係―
難波文恵
第2章 中国語を母語とする日本語学習者と母語話者を対象とする非流暢性発話フィラーの音声分析
李歆玥、石井カルロス寿憲、傅昌鋥、林良子
第3章 発話のしにくさの自覚と調音運動の非流暢性
北村達也、能田由紀子、吐師道子
第4章 言いよどみの音声生理学的特徴に関する一考察
林良子、孫静
第5章 多様な話者の非流暢性を連続体として捉える試み
林良子
第7部 (非) 流暢性の獲得
第7部のねらいと論文紹介
定延利之
第1章 幼児のことばの非流暢
―E児データによるケーススタディー―
友定賢治
第2章 非流暢な音声合成に向けて
モクタリ明子、ニック キャンベル、ラム タイ フック、定延利之
付録 非流暢性の目録
定延利之、丸山岳彦、遠藤智子、舩橋瑞貴、林良子
あとがき
索引
執筆者紹介
関連情報
https://www.speech-data.jp/kaken_hiryu/index.html
インタビュー:
「「非流暢に話す」とは? 京都大学・定延先生に“非流暢性”の 研究とその先にあるものを聞いた。」 (ほとんど0円大学 2023年11月28日)
https://hotozero.com/knowledge/kyotouniv_hiryucho/
座談会:
NEW「Disfluencies We Live With」 (主催: 科研費基盤研究S「非流暢な発話パターンに関する学際的・実証的研究」 2025年3月30日)
https://docs.google.com/forms/d/1Jw581caftT-Sphsi7_I2KMSmMLmAV-9NrrlOxu4hMC0/viewform?edit_requested=true
シンポジウム:
「コーパス日本語学の現在」 (東アジア国際言語学会第12回大会 2025年2月22日)
「非流暢性への多角的アプローチ―言語に埋め込まれた亜コード―」 (主催: 科研費基盤研究S「非流暢な発話パターンに関する学際的・実証的研究」 2023年3月26日)
https://www.speech-data.jp/kaken_hiryu/images/20230326_poster.pdf
パネルディスカッション:
「非流暢で自然な日本語」 (日本語プロフィシェンシー研究学会10周年記念シンポジウム 2021年6月26日)
ワークショップ:
“Methodology of Japanese Corpus Linguistics” (ユライ・ドブリラ大学プーラ 2025年2月5日)
https://www.senshu-u.ac.jp/news/nid00024800.html
特別ワークショップ「発話の非流暢性への学際的アプローチ」 (関西言語学会第48回大会 2023年6月10日)
“Workshop on Spoken Language: Czech and Japanese” (プラハ・カレル大学 2023年5月4日~5日)
「日本語音声コミュニケーションにおける非流暢性をめぐって」 (日本音声学会第35回全国大会 2021年9月26日)
「日本語教育と『非流暢性』―その言語的な実現と相互行為上の役割に注目して―」 (第45回社会言語科学会研究大会 2021年3月13日)



 書籍検索
書籍検索