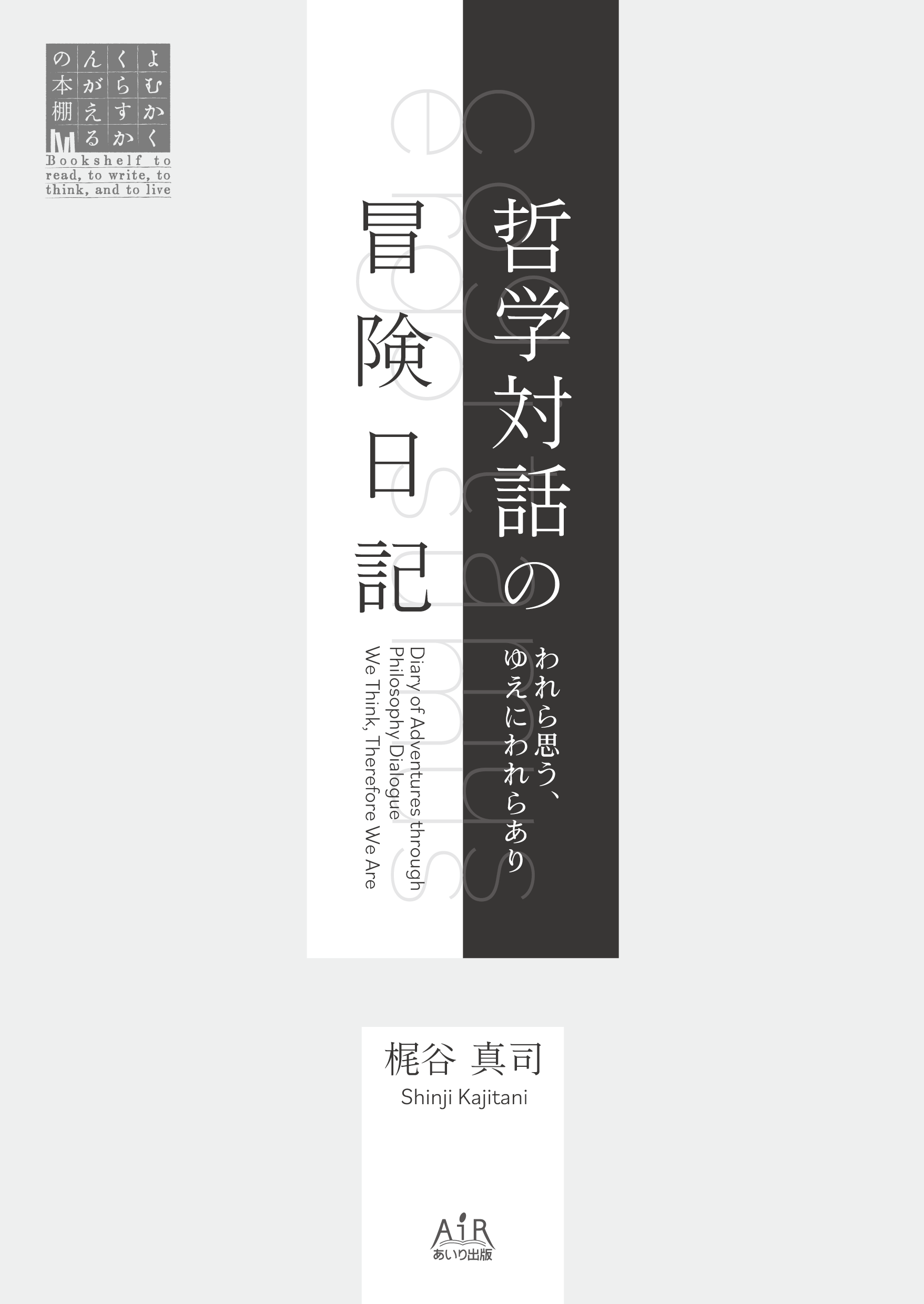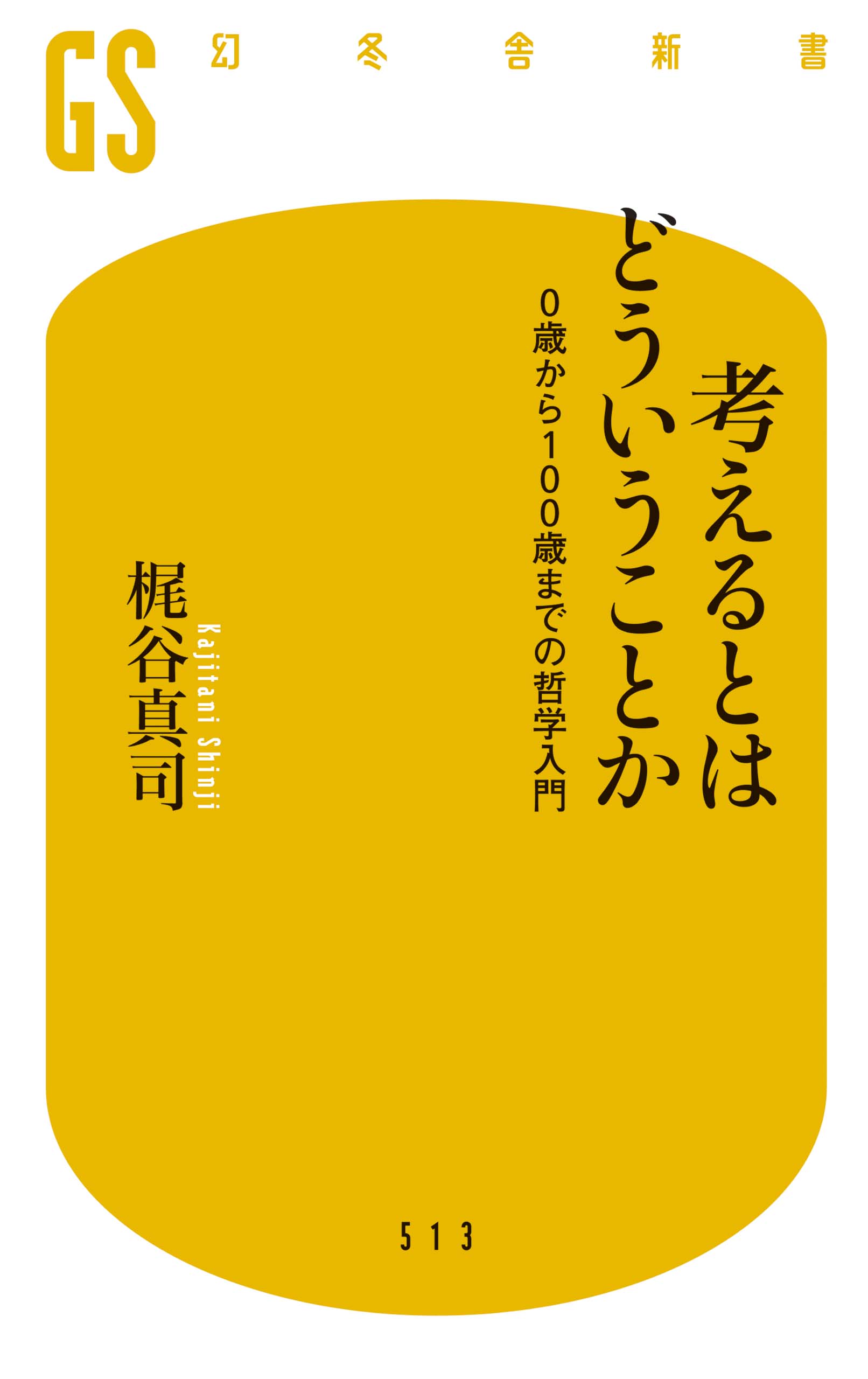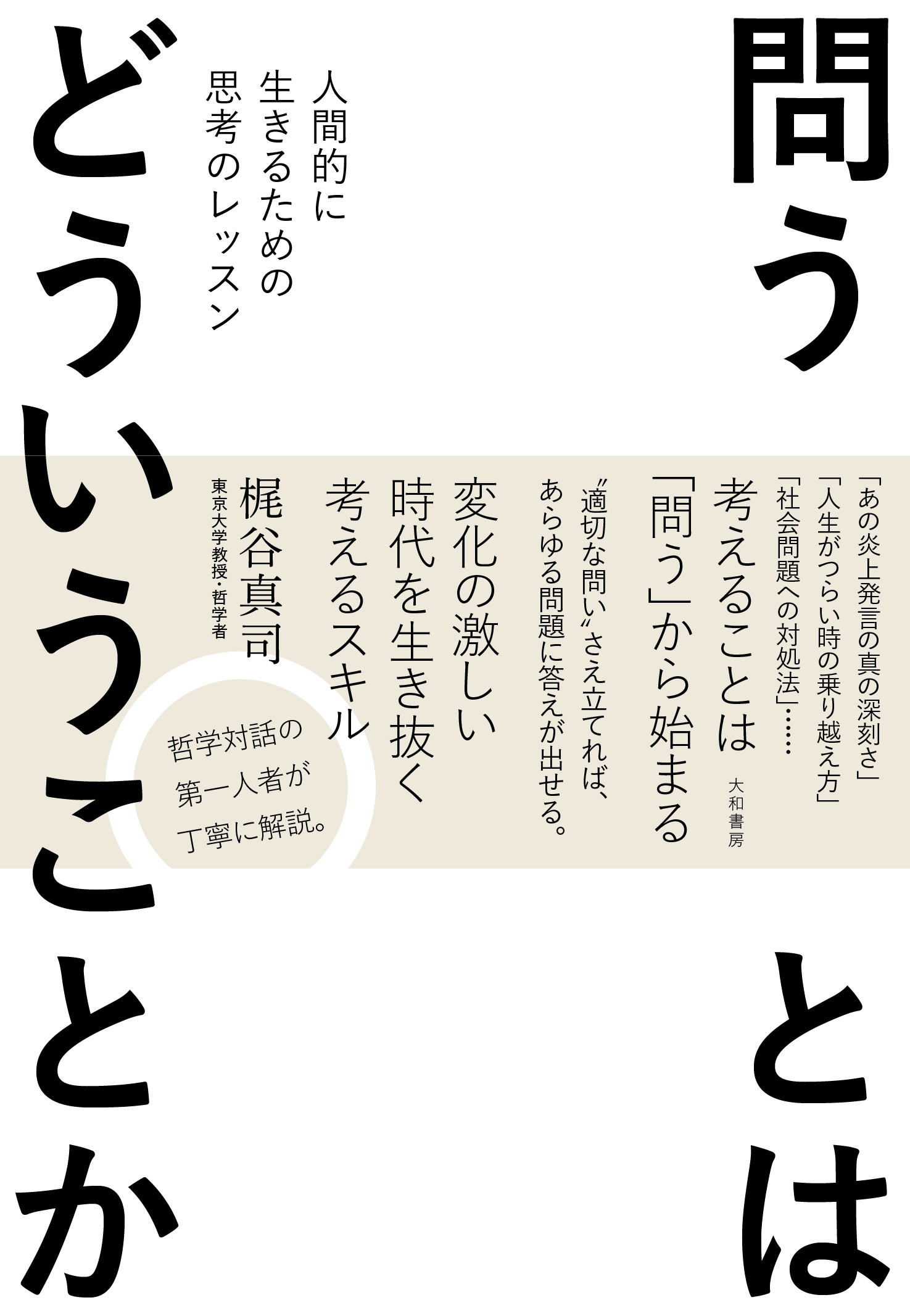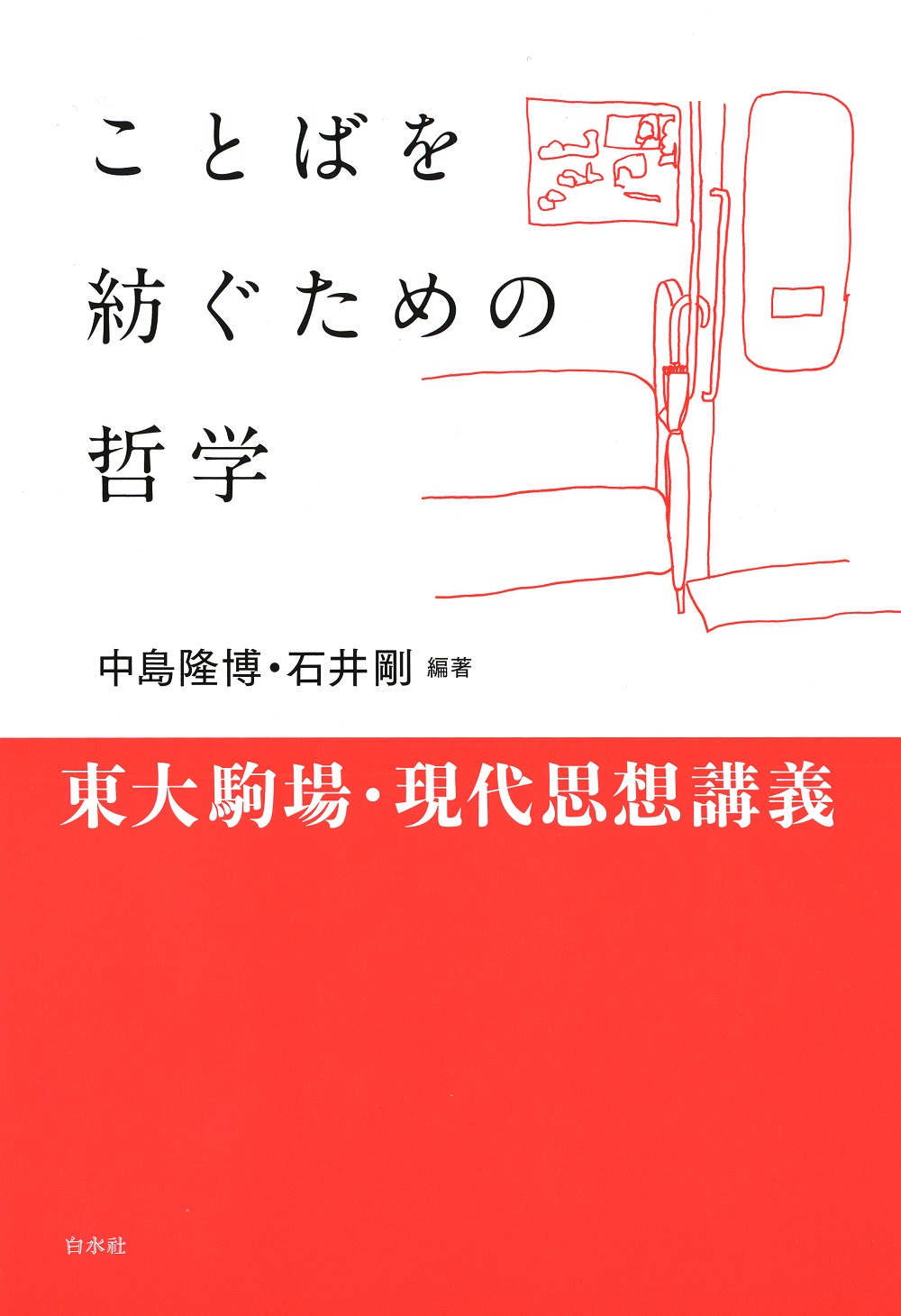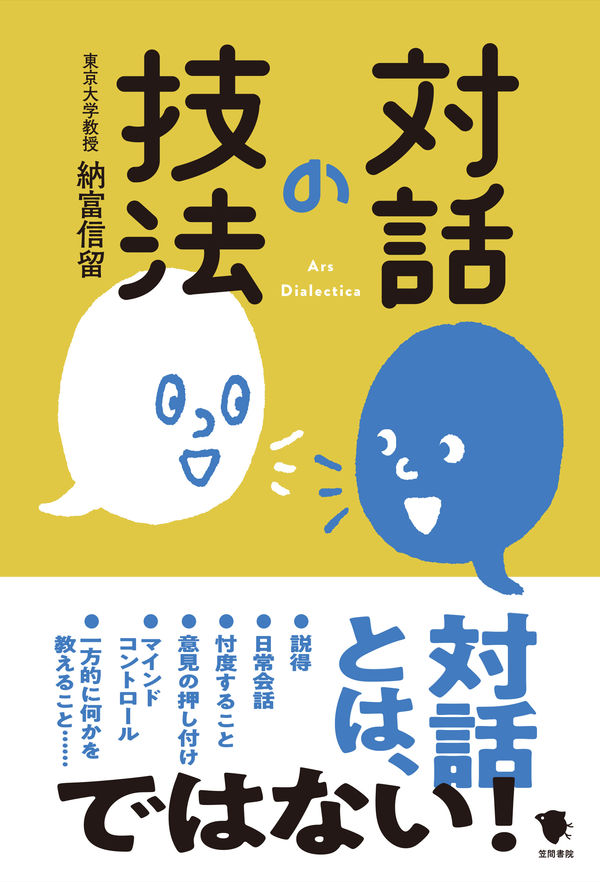駒場キャンパスには、「共生のための国際哲学研究センター」(University of Tokyo Center for Philosophy: UTCP) がある。私はそこに2012年から関わっている。事情もよく分からないうちに連れてこられ、どうやらその時点でなぜか次期センター長になることになっていた。有無を言わさぬ決定に観念した私は、半分は自分の備忘録として、半分は立場上の責任としてブログ報告を書くことにした。それが今でも続く「邂逅の記録」である。
もともと書籍として刊行される予定などなく書き綴ってきたものだが、全部読んで私に本として出版することを提案してくれた人が現れた。私が以前、京都の総合地球環境学研究所で3年ほどプロジェクトをもっていた時に知り合った寺田匡宏さんである。通読した彼が「これは梶谷さんが哲学対話をやってきた旅の記録のようだ」ということで、「冒険日記」というタイトルをつけてくれた。そのコンセプトに合わせて私が文章を選び、編集した。するとうまい具合に、時期的に4つのステージに分けることができた。
第1章「旅の始まり」では、哲学対話との出会い、Philosophy for Everyone (哲学をすべての人に) というプロジェクトに至る経緯について書いた。そこには一見無関係に思えるものが一つに収斂していく運命のようなものが見える。第2章「旅の出会い」では、哲学対話のイベントとして行った数々の試みについて書いた。「母」、「お金」、「ビジネス」、「宇宙」、「恋」など、哲学らしからぬテーマで、哲学とは無縁の人たちとコラボした。第3章「旅は道連れ」では、哲学対話とコミュニティの形成とのつながりから、広い意味でのデザインとの協働へと展開したプロジェクトについて書いた。そして第4章「ヴァーチャルな世界へ」では、コロナ禍の間、オンライン上で爆発的に広がった哲学対話について書き、そこで議論したことを詳細に記録していた。
哲学の研究者は、哲学対話のことを「井戸端会議」だの「素人談議」だの言って拒絶し、専門的な知識をもっていなければ哲学はできないと言う。そのような権威主義的な考え方をする人たちは世代に関わらずいて、言っていることもこの10年間まったく変わっていない。けれども私は、そういうヌルいことをやってきたわけではない。哲学対話によって、哲学の可能性を限界まで広げ、どこまでが哲学で、どこからが哲学でなくなるかを見極めようとしてきた。そして、デザインの知見を取り入れることで、多様な人たちが共同で思考を創り上げる「共創哲学」(inclusive philosophy) へと発展させることができた。それは、独我論へと通じるデカルトの「われ思う、われあり」(cogito ergo sum) に対して、その複数形の「われら思う、ゆえにわれらあり」 (cogitamus ergo sumus) を、思考による共同性の原理として打ち立てるものである。この哲学は、まさに「冒険」と呼ぶにふさわしくシリアスでスリリングであり、まだ道半ばでこれからも続いていくのである。
(紹介文執筆者: 総合文化研究科・教養学部 教授 梶谷 真司 / 2024)
本の目次
第1章 旅の始まり
出発点としての就活支援
自分と向き合い、自分の言葉を獲得する
漠然とした確信
考えること、書くこと、自由になること
問わないこと、考えないこと
学ぶことのない書く方法と考える方法
国際哲学オリンピックから哲学サマーキャンプへ
旅の寄港地 随想コラム1 国際哲学オリンピック(IPO)…哲学を通して世界中の人たちと仲間になる
P4C(Philosophy for Children)のインパクト
もう一つの P4C
プロジェクト「研究・教育の一般的方法としての哲学的思考」
哲学をすべての人に(Philosophy for Everyone)
旅の寄港地 随想コラム2 制度の先へ行く意志…西山雄二編『人文学と制度』への書評
第2章 旅の出会い
ワークショップ「哲学をすべての人に」報告(1)
ワークショップ「哲学をすべての人に」報告(2)
「研究」でない哲学~カフェフィロの松川絵里さんを迎えて
「母」をめぐる哲学対話(1)~なぜ「母」なのか?
「母」をめぐる哲学対話(2)~心地よい衝撃
「母」をめぐる哲学対話(3)~種を持ち帰る大切さ
哲学プラクティスの職業化
ビジネスと哲学
「哲学プラクティス週間」を終えて
「お金」をめぐる哲学対話(1)~人と人をつなぐもの
「お金」をめぐる哲学対話(2~哲学的テーマとしてのお金
「こまば哲学カフェ」を終えて
熊本での出張対話(1)~その始まり
熊本での出張対話(2)~いきなり熊本出張!
熊本での出張対話(3)~いよいよ本番!(南阿蘇編)
熊本での出張対話(4)~いよいよ本番!(上天草編)
ラーニングフルエイジング~生涯学び続ける場をつくる(1)
ラーニングフルエイジング~生涯学び続ける場をつくる(2)
ラーニングフルエイジング~地域社会における多世代交流と教育の役割(1)
ラーニングフルエイジング~地域社会における多世代交流と教育の役割(2)
第3章 旅は道連れ
ポッキーイベント~空虚にして充実した時間
問いのアバンチュール~新しい人たちとつながる試み
Knowledge Forest~本を通して知と人を結ぶ
旅の寄港地 随想コラム3 7 Days Book Cover Challenge
日常世界としてのルワンダ
音楽と想起のコミュニティ
映画と対話の出会い
文字を通して自らと向き合う
文を以て人を繋ぐ~「キセキの高校」を振り返る
「ために」から「ともに」へ~哲学対話と
語ることによる排除を乗り越える~書く哲学対話の試み
異物を取り込み、音楽を開放する~現代音楽と共創哲学の出会い
愛のために出会いの場をデザインする
障壁のある人生をどのように生きるのか?(1)
障壁のある人生をどのように生きるのか?(2)
旅の寄港地 随想コラム4 水俣で生きること、水俣へ行くこと
第4章 ヴァーチャルな世界へ
コロナの中の日常~誰もが思考と経験の当事者になる
ただ自分自身でいられる場を求めて~紫原明子さんとの対話
子育てと哲学対話~哲学カフェを運営する 人の母親との対話
哲学。をプロデュース!~新しい哲学の可能性を求めて
哲学対話とセックスは同じだ!~二村ヒトシさんとの対話
結婚の新しいカタチを求めて
未来のコミュニティをつくる~教育による地方創生の”たくらみ”
学校が変わるとき~内と外から見た教育改革の実践
哲学対話とコミュニティづくり~一緒に考えることでできるつながりとは?
共にいること、共に生きること、共に創ること(1)
共にいること、共に生きること、共に創ること(2)
共にいること、共に生きること、共に創ること(3)
旅の寄港地 随想コラム5 奇跡が自然に起こる場所…名古屋駅前の着ぐるみ街頭活動に1年以上通って
エピローグ いまだ旅の途上
あとがき
索引
英文要旨
関連情報
https://utcp.c.u-tokyo.ac.jp/
梶谷真司 邂逅の記録 blog (共生のための国際哲学研究センター (UTCP)
https://utcp.c.u-tokyo.ac.jp/blog/0018_kajitani_shinji/
著者インタビュー:
実践編:「哲学」研究 (1) (ジブンxジンブン 2024年8月8日)
https://jibunjinbun.com/self-study/practice/kajitani-philosophy1/
実践編:「哲学」研究 (2) (ジブンxジンブン 2024年8月22日)
https://jibunjinbun.com/self-study/practice/kajitani-philosophy2/
実践編:「哲学」研究 (3) (ジブンxジンブン 2024年9月5日)
https://jibunjinbun.com/self-study/practice/kajitani-philosophy3/
「共創する」哲学:梶谷真司教授インタビュー (東大新聞オンライン 2023年12月8日)
https://www.todaishimbun.org/philosophy_20231208/
賢人論: 高齢者との哲学対話で梶谷先生が見つけたこと (みんなの介護ホームページ 2023年9月1日)
https://www.minnanokaigo.com/news/special/shinjikajitani/
「人文知」を社会実装するNo.2 哲学対話が組織に起こす「小さな変革」 (電通報 2023年1月11日)
https://dentsu-ho.com/articles/8439
【梶谷真司さん】哲学対話の場でなにが起きているのか?(前編) (湯リイカ | YouTube 2022年3月6日)
https://www.youtube.com/watch?v=JhHs6GqfrNA
【梶谷真司さん】哲学対話の場でなにが起きているのか?(後編) (湯リイカ | YouTube 2022年3月6日)
https://www.youtube.com/watch?v=4lGulW66jYc
インクルーシヴな場を生み出す哲学対話とは何か
ダイバーシティ&インクルージョン研究 05 (東京大学ホームページ 2021年11月30日)
https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/features/diversityresearch05.html
メディア出演:
NHK視点・論点「“考える力”を育てる“哲学対話”」 (NHK 2020年3月31日)
https://www.nhk.jp/p/ts/Y5P47Z7YVW/episode/te/VKMJ4W7X3X/
イベント・講座:
市民提案型事業 講座づくり★まちチャレ『問い』『考える』ってどういうこと?
哲学対話入門講座「哲学対話の冒険」 (玉川学園コミュニティセンター 2024年12月14日)
哲学対話 (2年目) (長野上水内教育会館 2024年2月17日)
http://www.kminochi-edu.or.jp/wp/wp-content/uploads/2023/12/231219_01.pdf
企業における「哲学対話」の可能性とは?国際哲学研究センター「UTCPシンポジウム」レポート (FICC inc. ホームページ 2023年12月25日)
https://www.wantedly.com/companies/ficc/post_articles/879175
【丸の内みらいの学び場 with 幻冬舎】 梶谷真司「なぜ対話はすれ違うのか」 (株式会社幻冬舎、エコッツェリア協会 2023年1月11日)
https://www.ecozzeria.jp/events/special/mirai-manabiba3.html
「総合的な探究の時間」プログラム『哲学対話』が始まりました。 (宮崎県立宮崎東高等学校 2021年10月7日)
https://cms.miyazaki-c.ed.jp/6041/blogs/blog_entries/view/146/0fbffbe65b19f13df6d584c5f7e838bf?frame_id=101
ぷらっと文化祭「Art Platter」/《えほんとことばの森》 『哲学対話ワークショップ 問う・考える・語る・聞くを知る』 (穂の国とよはし芸術劇場PLAT 2021年9月19日)
https://www.toyohashi-at.jp/event/workshop.php?id=443
高1有志による「ゆるり哲学対話」 (開成中学校・高等学校 2015年10月7日)
https://kaiseigakuen.jp/diary/%E9%AB%98%EF%BC%91%E6%9C%89%E5%BF%97%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E3%80%8C%E3%82%86%E3%82%8B%E3%82%8A%E5%93%B2%E5%AD%A6%E5%AF%BE%E8%A9%B1%E3%80%8D/
U-Talk 第67回 哲学対話を体験する! (UTCP | 東京大学 情報学環・福武ホール 2013年10月12日)
https://fukutake.iii.u-tokyo.ac.jp/utalk/2013/10/12/23.html



 書籍検索
書籍検索