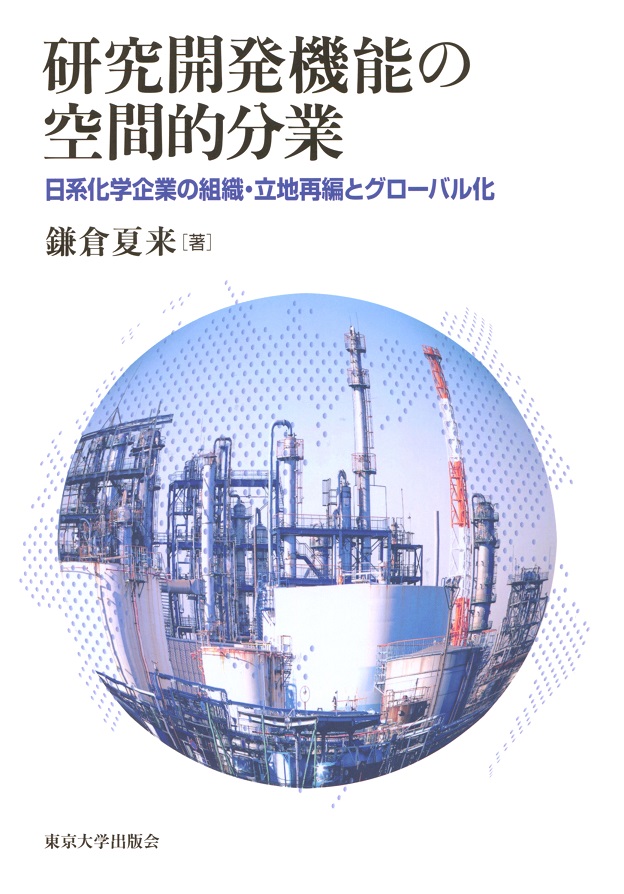工場の分布と機能の変遷から産業の立地固着性を分析 | 鎌倉夏来 | UTokyo 30s No.6
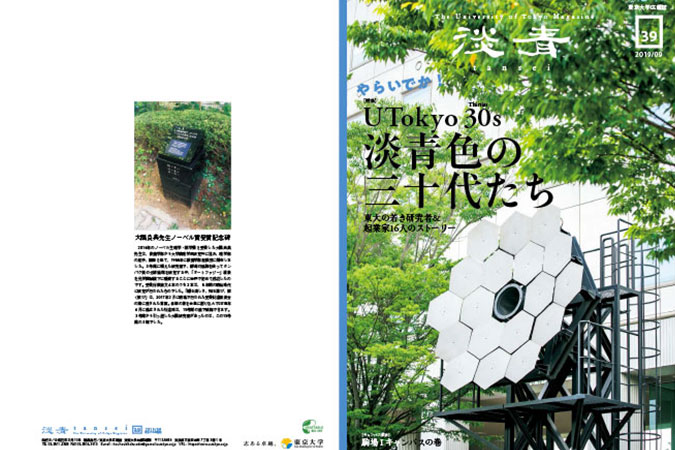
やらいでか!UTokyo サーティーズ
淡青色の若手研究者たち
約5800人いる東京大学の現役教員の中から、30代の元気な若手研究者を9人選びました。職名の内訳は、教授が1人、准教授が2人、特任准教授が1人、講師が1人、特任講師が1人、助教が3人です。彼/彼女らは日々どんな研究をしているのか、そして、どんな人となりを持っているのか。その一端を紹介します。(広報誌「淡青」39号より)
※2019年9月10日現在での30代を対象としています。
| 経済地理学 |
工場の分布と機能の変遷から産業の立地固着性を分析
 鎌倉夏来 鎌倉夏来KAMAKURA, Natsuki 総合文化研究科助教 |

さまざまな経済活動を、企業や人の位置する場所から分析する経済地理学。その中で、大企業の工場や研究開発機能の空間的な分布や変遷の研究を専門とするのが、中高生の頃から地図や地形図を見るのが大好きだったという鎌倉先生です。
「山奥の全然効率的でない場所に水田があったり、意外なところに工場を見つけると、なんでこんなところに水田があるんだろう、一体どう物流が機能しているんだろう、と面白くなってしまって」
地理学者になると決意して「決め打ちで」受験し入学した東大で門を叩いたのは人文地理学教室。卒論では、神奈川県にある東海道線沿線の工場用地の用途の変化を調べるため、10社以上の企業を訪ね歩きました。わかったのは、東京からの距離で土地の利用パターンが異なること。たとえば、東芝の工場跡地にラゾーナ川崎という商業施設が建設されたように、東京駅から15-35km未満にある地域ではマンションや商業施設に転換された割合が多く、それ以上離れると工場のまま変わらない割合が多かったのです。
「製造業は雇用主として地域を支えると同時に税金を払う事業体でもあり、工場が移転し跡地が住宅に変わると、人口増で社会福祉費用が増える一方、自治体の税収は減ります。工場が組織の中でどういう位置づけか、機能がどう変わってきたかを体系的に示すことによって、その企業が地元に残る可能性の程度や、自治体が打ち出すべき政策の方向性を示唆できればと思います」
プライベートでも工場夜景クルーズに参加するなど、工場を見るのが好きな先生がこれまでに調査で訪れた箇所は全国で300は下らないとか。今後は、師匠の松原宏教授が機構長を務める地域未来社会連携研究機構を通じ、北陸の工場研究にも取り組む予定です。
「北陸には、工作機械やマザーマシンといわれる、機械を作る機械の製造拠点が集積しています。その技術が地元の人材に依存しているのか、会社の持つ権利や知的財産に依拠しているのか。その違いによって、ある企業がその土地に固着しているか、そこでなければ持続できないのかどうかがわかってきます」
たとえば北陸の寒い気候が、室内でコツコツとモノづくりをする気質の人材を育みやすい、といったことがわかるかもしれません。
「環境ですべてが決まるという見方や県民性のようなものを誇張してはいけませんが、もしそういう人材が見つかりやすいという現実があるなら、数値で表すこともある程度はできます。産業の発展と立地固着性について分析を続けていくつもりです」
| Q & A | |
|---|---|
| 大学時代の思い出は? | 「部活一筋。卓球部女子の主将を務め、週6日練習していました」 |
| 師匠の松原先生はどんな人ですか? | 「楽しそうに研究し、どこでも誰にでも話しかけるのがすごい」 |
| オフには何を? 好きなテレビ番組は? | 「ジムで筋トレしたりバイクこいだり」「アメリカの“Seinfeld”」 |
| 大学に言いたいことは? | 「顔色の悪い研究者が多い。健康に暮らせるよう運動施設増を!」 |
| 鎌倉先生の著書 『研究開発機能の空間的分業』 (東京大学出版会/2018年2月刊/6600円+税) |