『今昔物語集』と言えば、多くの人がまず思い浮かべるのは芥川龍之介だろうか。非常に知名度の低かったこの作品を、一躍古典説話の代表作品へと押し上げた芥川は、『今昔』の秀逸な説話をモチーフに数多くの作品を残した。高校教科書の定番教材となった『羅生門』もその一つであるし、現在では古典教育の初期段階で、ほぼ全ての教科書が『今昔』の説話を取り上げている。
しかし、知名度の急速な上昇に反して、『今昔』の全体像は未だに深い謎に包まれている。そこには様々な要因がある。まず、この作品は院政期と呼ばれる十二世紀に執筆されたと思しいものの、未完成のまま死蔵され、あまり流布しなかった作品であること。また、そのために本格的な研究は明治以降に始まり、他の古典作品に比べて歴史が浅いこと。加えて、『今昔』自体が全三十一巻、累計千話を超える説話を収めた、日本文学史上最大の説話集であること。さらに、本作品には構成・配列の点で壮大な構想が窺われる一方で、そこかしこに多くの矛盾や撞着が見られること。このような様々な事情から、『今昔』全体を統一的に捉えることは非常に難しく、総合的な研究は難渋してきた。
そうした研究状況の中で、本書は〈各話と全体構造〉、〈編者の読者意識〉、〈作品の内部と外部〉といった複合的な視点を組み合わせることによって、『今昔』という作品の総合的解明と文学史的位置付けを試みた。この巨大で謎めいた作品を解明するには、一つの視点からの探求では到底足りないと考えたためである。
例えば、第一部は『今昔物語集』の内的世界を対象に、その生成や構造を追ったものだが、全体を通して、各話を関連資料と比較検証した成果に基づき、全体構造を考察するという手法をとっている。日本の古典説話の最も重要な要件は「伝承性」にある。一つ一つの説話は作者によって創作されるものではなく、必ず何かしらの話を受け継ぎ、”少々“手を加えて成立する。そして、『今昔』の場合、収録説話のほぼ全てが書かれた説話を書承したと考えられている。そこで、現時点で関連が指摘されている説話をできうる限り収集し、一話一話を『今昔』の説話と比較検証することで、編者が手を加えた痕跡を探し、その営為を全体の編纂行為と結びつけて考察した。
また、第二部では『今昔』の生成を多角的に考察することを目指し、周辺の作品を「史的圏域」として一定数扱った。近い時代の同類作品、隣接ジャンルの同時代作品、生成に関連する作品・資料を対象として考察した。作品内部への視点のみならず、外部からの視点を導入することによって、『今昔』世界の輪郭をより一層明確にし、この極めて特殊な説話集を日本文学史の中に位置付けることを目指したものである。
『今昔』の本格的研究は近代以降のものではあるが、質と量を兼備したこの作品が抱える不思議な魅力に引き寄せられるように、数多くの研究者が本作品に挑み続けてきた。それでも解き明かされない奥深さを持つ『今昔』の雄大な魅力を、本書を通して実感してもらえれば幸いである。
(紹介文執筆者: 川上 知里 / 2022年1月21日)
本の目次
一 『今昔物語集』概説
二 問題の所在と本書の目的
三 本書の構成
第一部 『今昔物語集』の世界
第一章 各話冒頭部の意義 ―構成と表現の連動性―
はじめに
一 事実性の強調と整合性の確保
二 構成・配列との連動
三 冒頭部と結語
四 二方向への欲求
おわりに
第二章 非仏法部の形成 ―巻十を基点として―
はじめに
一 巻十の話群構成
二 中国正史の存在と天竺部・本朝部
三 構成と表現の「本朝化」
おわりに
第三章 恐怖表現の意義 ―巻九の生成理由をめぐって―
はじめに
一 恐怖表現の実相I―正方向への影響力―
二 恐怖表現の実相II―内から作品を崩す力―
三 巻九「震旦付孝養」構成への影響
おわりに
第四章 歴史叙述からの解放 ―巻三十を手がかりに―
はじめに
一 仏教的観点の存在
二 仏教と恋との葛藤
三 巻三十の存在意義
おわりに
第五章 仏法と王法 ―巻三十一と王法仏法相依論―
はじめに
一 三国における仏法と王法
二 巻三十一の「仏法」
三 巻三十一の「王法」
おわりに
第六章 事実らしさへの執着 ―信憑性確保の手法と理由―
はじめに
一 仏法部における信憑性確保の手法
二 信憑性確保の理由と背景
三 非仏法部における信憑性確保の実態
おわりに
第七章 結語にみる読者意識(1)―主題と合致する結語の実態―
はじめに
一 結語の性質と研究史
二 一般読者 ―唱導的欲求―
三 編者内の〈読者〉―〈執筆者〉との応答―
四 編者内〈読者〉と〈執筆者〉の葛藤
おわりに
第八章 結語にみる読者意識(2)―逸脱する結語の生成―
はじめに
一 「君子危うきに近寄らず」型
二 仏法唱導型
三 日常的教訓型
おわりに
第二部 『今昔物語集』の史的圏域
第一章 『世継物語』論 ―説話化の営み―
はじめに
一 和歌から説話へ
二 物語類から説話へ
三 『世継物語』の生成
おわりに
第二章 『拾遺往生伝』論 ―歴史意識と文学意識―
はじめに
一 特徴と問題点
二 歴史意識 ―配列と国史受容―
三 表現へのこだわり ―文飾の排除と平明化―
四 説話内部への追求 ―為康の「説話化」―
おわりに
第三章 唱導資料と説話集 ―院政期の説話引用をめぐって―
はじめに
一 手控えに見る説話引用 ―『言泉集』『諸事表白』『草案集』「弁暁説草」『三国伝灯記』―
二 説法記録に見る説話引用 ―『法華百座聞書抄』『覚鑁聖人伝法会談義打聞集』―
おわりに
第四章 『打聞集』論 ―説話集としての可能性―
はじめに
一 原拠との距離
二 漢文体の出現と「云々」問題
三 作成意図と「打聞」
おわりに
第五章 金沢文庫本『仏教説話集』論 ―唱導資料の中の説話集―
はじめに
一 説話の引用形態の特徴
二 説話本文の特徴
三 唱導資料としての位置付け
第六章 『長谷寺験記』論 ―虚構の霊験記・歴史書―
はじめに
一 エピソードの挿入
二 長谷寺霊験譚への変容
三 霊験譚から長谷寺史へ
おわりに
終 章
一 『今昔物語集』の世界総論
二 『今昔物語集』の生成試論
関連情報
第二次第十七回 (通算二十九回) 関根賞 (関根賞運営委員会 2022年8月8日)
https://spc.hujibakama.com/
https://spc.hujibakama.com/doc/news_20220808.pdf
第4回 (2022年度) 説話文学会賞 (説話文学会 2022年6月26日)
http://www.setsuwa.org/
第1回東京大学而立賞受賞 (東京大学 2020年)
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/research/systems-data/n03_kankojosei.html
書評:
竹村信治 評 (『国語と国文学』通巻1186号 第99巻第9号、2022年9月)
https://www.meijishoin.co.jp/book/b605261.html
中根千絵 評 (『学芸国語国文学』第54号 2022年3月)
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/gkokugokokubun/-char/ja
松尾葦江 評 (中世文学漫歩 2021年5月7日)
https://mamedlit.hatenablog.com/entry/2021/05/07/175755
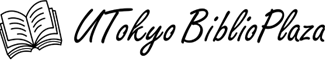



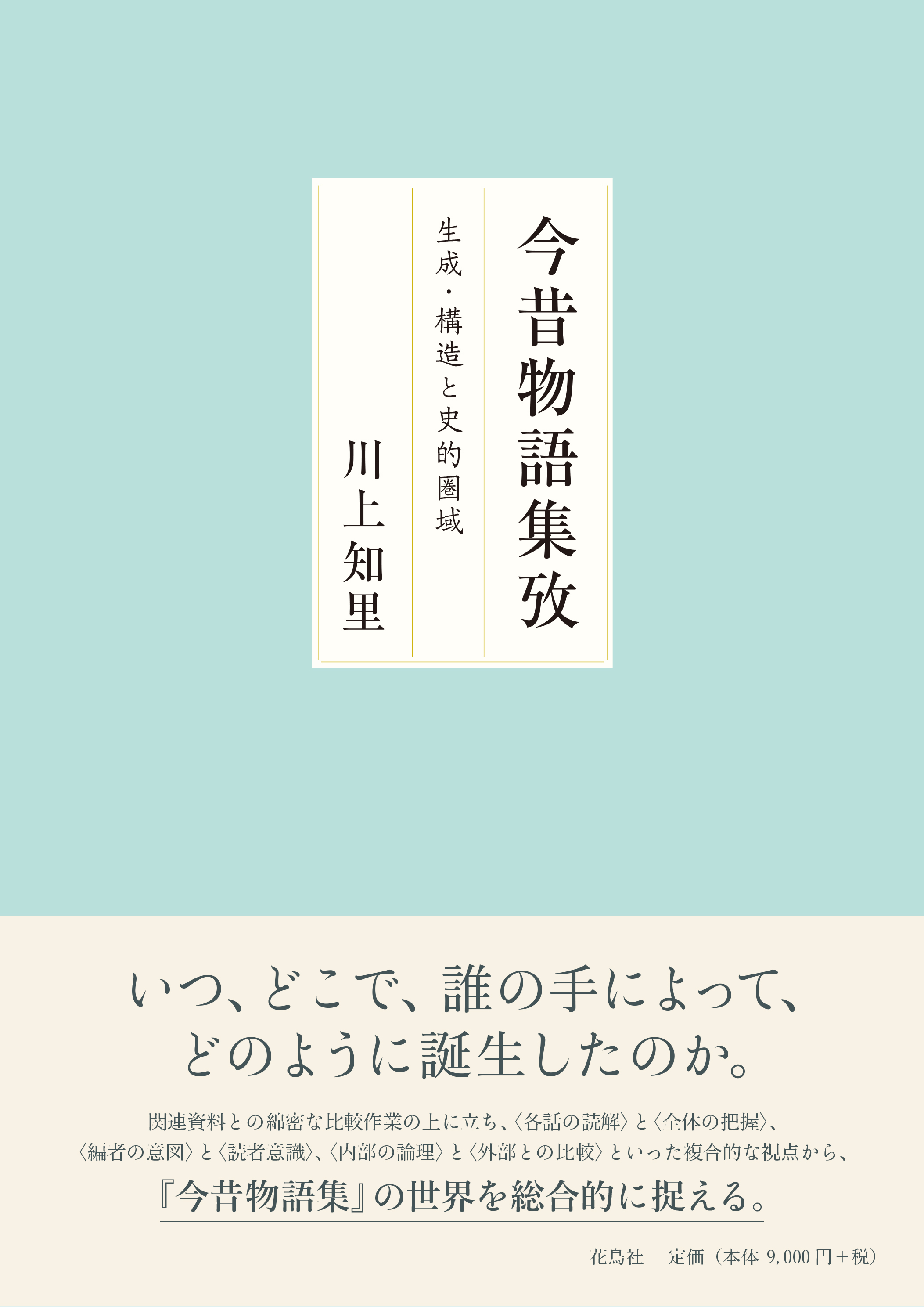
 eBook
eBook