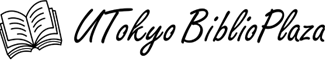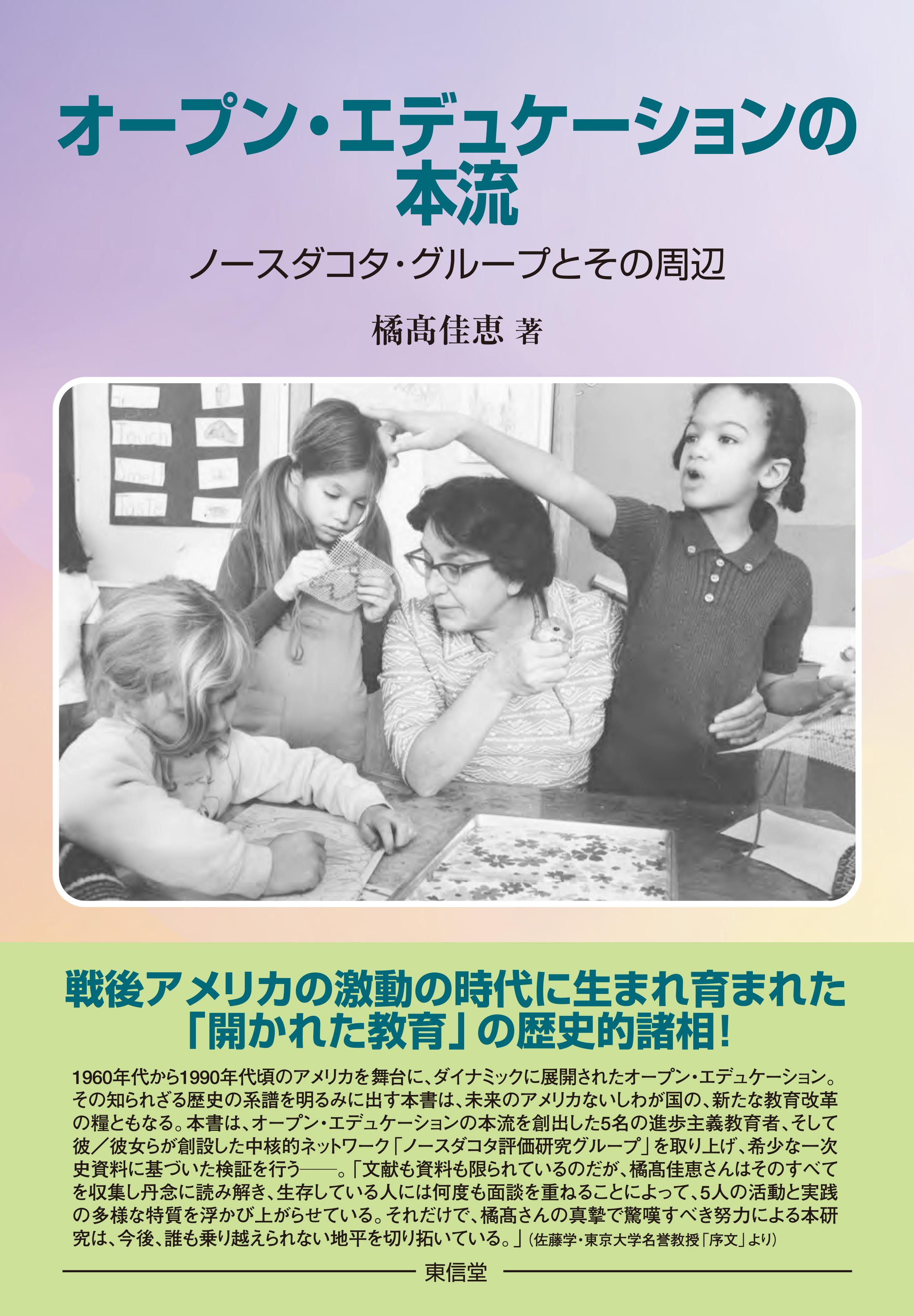
書籍名
オープン・エデュケーションの本流 ノースダコタ・グループとその周辺
判型など
230ページ、A5判、上製
言語
日本語
発行年月日
2023年3月
ISBN コード
978-4-7989-1810-5
出版社
東信堂
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
本書は、1960年代から1990年代のアメリカ合衆国において「オープン・エデュケーション」と呼ばれる教育の実践と理論が生まれ、展開し、挫折した過程を描き出している。
オープン・エデュケーションは、ジョン・デューイの進歩主義教育の伝統を継承する教育改革の系譜であり、世界の学校と教師に与えた影響は大きかった。しかしながら、誰がその中心的な担い手であり、彼らがいかなる役割を果たしたのかということについて、十分に解明されてはいなかった。本書は、オープン・エデュケーションの中心をなした人々を特定し、各々の実践と理論を明らかにした世界で最初の研究である。
本論では、まず1960年代から1990年代における進歩主義教育の盛衰を、アメリカの政治社会的動向を踏まえて辿る (第1章)。次いで、リリアン・ウェーバーを取り上げる。保育園教師としての経験を踏まえ、イギリスとアメリカの革新の伝統に学び、ニューヨーク市ハーレムにおいて公立学校改革と教師教育に尽力した彼女の実践とディスコースを明らかにする (第2章)。さらに、パトリシア・カリーニを取り上げる。子どもの作品と姿をとおし、一人ひとりが「特殊」であることを人の普遍性として示した彼女の実践と思想を明らかにする (第3章)。第4章では、ヴィト・ペロンとノースダコタ評価研究グループを取り上げる。1970年代初頭、急速に拡大していた標準テストの使用とそこに潜む人種差別のシステムに抵抗するため、進歩主義教育者のネットワークとして同グループが生まれ、発展していった経緯を、その中心をなしたペロンの活動とともに辿る。最後に、デボラ・マイヤーを取り上げる。社会主義と組合主義の姿勢に貫かれ、ニューヨーク市イーストハーレムにおいて公教育の再生を試みた彼女の実践と哲学を明らかにする (第5章)。さらに補論において、ノースダコタ・グループの現在を記す。
本書をとおし、オープン・エデュケーションの本流を導いた民主主義のヴィジョンが伝われば幸いである。中心的な担い手たちは、まさに「すべて」の子どもに探究的で創造的な学びを保障するために、公教育制度の変革を企図していた。そして一人ひとりの子どもの個性的な解放に、アメリカの文化革命も託されていた。本書の示す知性的かつ革新的なオープン・エデュケーションの歴史が、国境を越えて、公教育のヴィジョンを再構築する手がかりとなれば幸いである。
(紹介文執筆者: 橘髙 佳恵 / 2023年6月5日)
本の目次
はしがき
凡例
序章 主題と方法
第1章 1960年代から1990年代における進歩主義教育の展開
第2章 文化剥奪論を越えて――リリアン・ウェーバーの実践とディスコース
第3章 子どもの作品と姿に学ぶ――パトリシア・カリーニの教育思想
第4章 進歩主義教育者のネットワーク――ヴィト・ペロンとノースダコタ評価研究グループ
第5章 新たな公教育制度の試み――デボラ・マイヤーの学校設立
終章 結論と残された課題
補論 ノースダコタ・グループの現在
参考文献
あとがき
初出一覧
関連情報
第3回東京大学而立賞受賞 (東京大学 2022年)
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/research/systems-data/n03_kankojosei.html