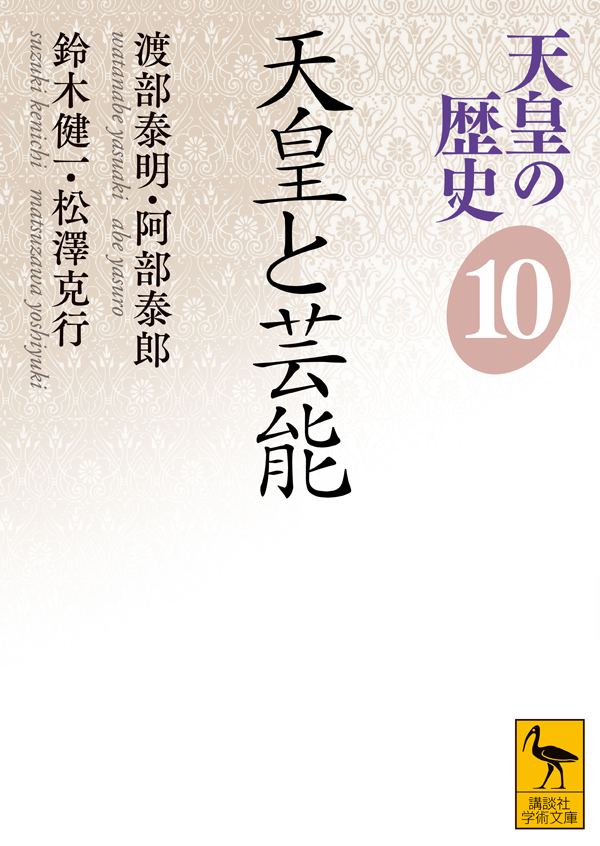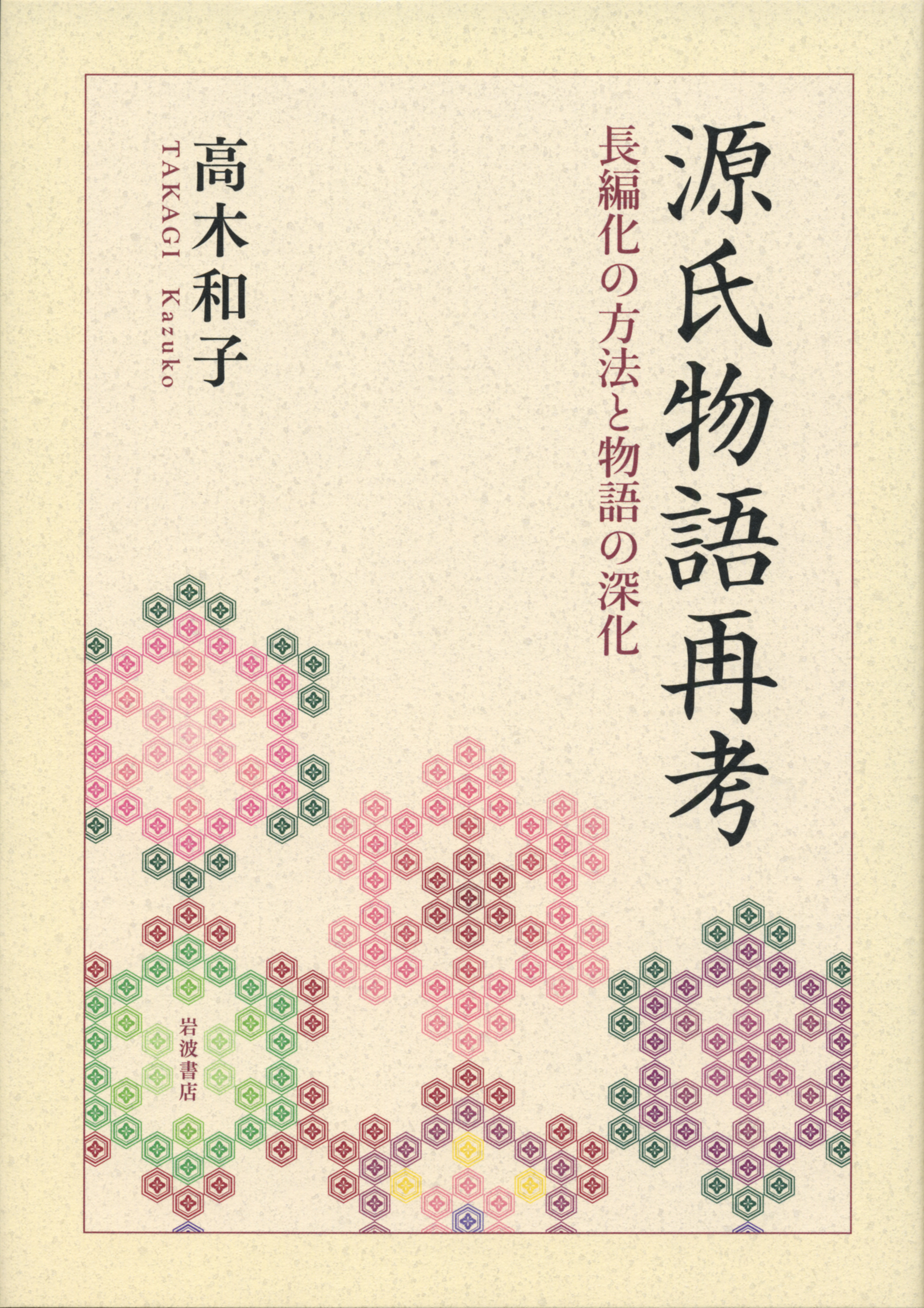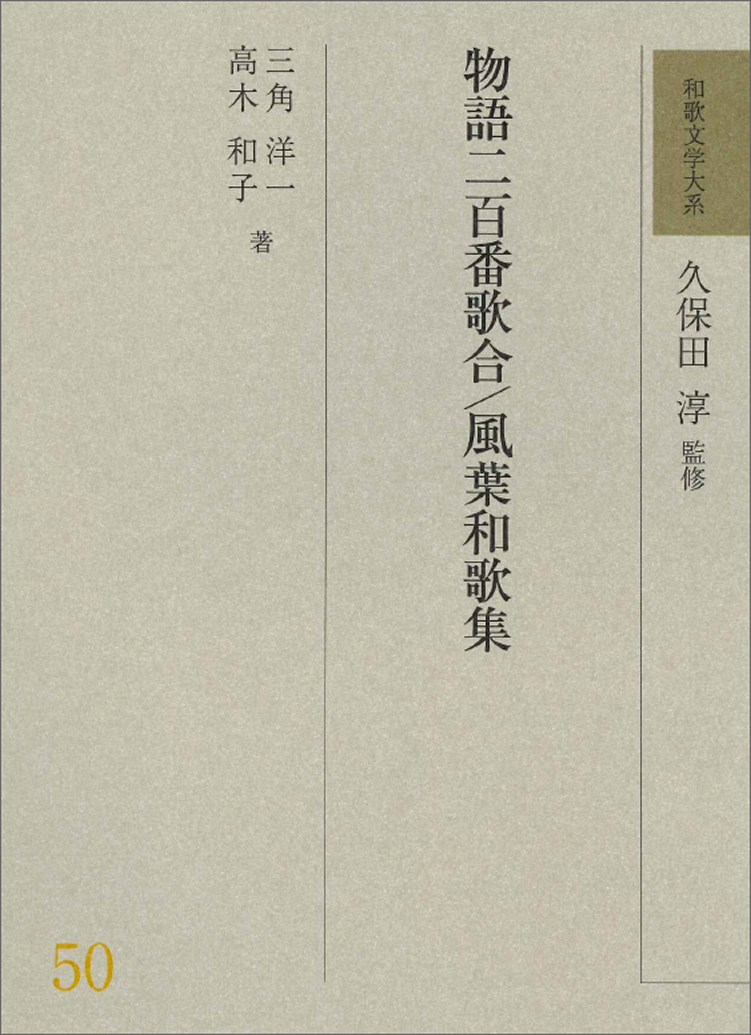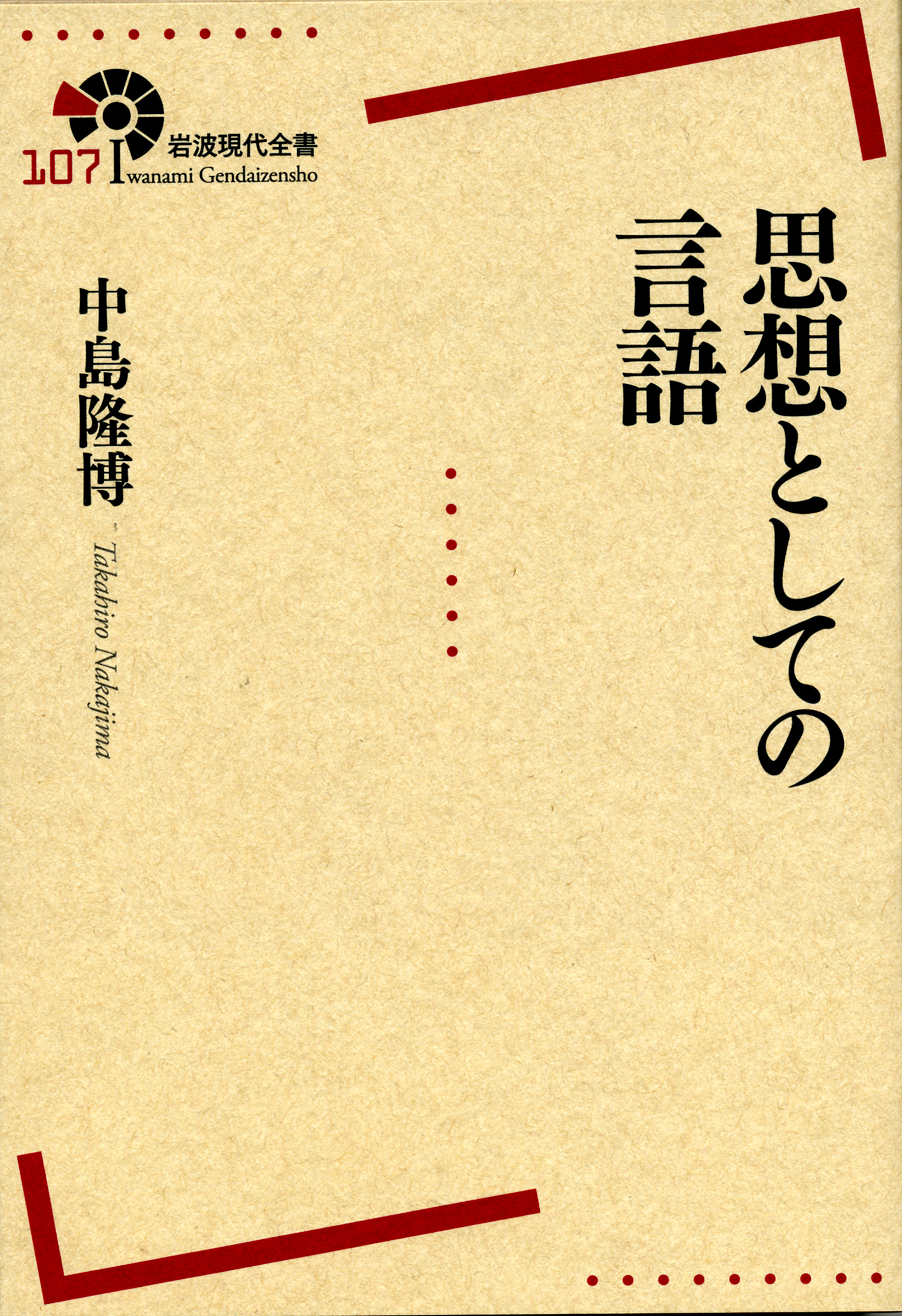三十一文字などとも呼ばれる、たった31音の言語表現にすぎない和歌が、なぜ日本の歴史を貫くほど長く続いたのか、というのが本書の問題意識である。古代貴族によって生み出され、様式を整えるまで形成された和歌が、中世以降もしきりと詠まれた。とすれば、まずは中世社会で和歌が重要な文芸として支えられていった経緯をさぐることが、その謎を明らかにする手立てとなるだろうと考えたのである。ただし、それを中世の歴史・社会的な構造や、思想的・精神史的な要因には求めなかった。あくまでも、和歌史を代表する優れた歌人が、和歌をどのように詠もうとしたのか、その際様式とどのように格闘したのか、その営みを支える方法をさぐり、その方法によってもたらされた作品の達成を分析することによって、中世の和歌史の動態を明らかにしようとした。
本書で論じた歌人のうち、主要な人物を取り上げて紹介しよう。まず平安時代からは、曾禰好忠・和泉式部・源経信に登場してもらった。「中世」なのになぜ平安時代の歌人? と疑問に思われるだろうが、古代の和歌に、すでに中世は胚胎していたのだ。彼らは、主体が分裂することさえいとわず、あらたな風景や抒情を開発していた。自分を不安定な立場に追い込むこともいとわず、新たな表現を追求していたのである。次に、源俊頼と西行らを対象とした。時代的には平安時代の終わり頃を生きた人たちだが、古代と中世の和歌の橋渡しとなった歌人である。そこに「縁語的思考」と私が名付けた、独特の様式意識が存在することを指摘した。「縁語的思考」とは、歌の詞が、相互に網の目のように結び付き、しかもそれが流動的・可変的である状態を指し示す概念で、歌人たちの創作の母胎を捉えたものである。本書の鍵となる概念といってよい。西行は個性的な和歌を詠んだ歌人として知られるけれども、やはり「縁語的思考」に基づいており、それによって、多くの人々に自分の言葉を届かせようと努力していたのであった。
次に藤原俊成と藤原定家の親子の和歌活動を扱った。本書の山場である。彼らは、それまでの表現の伝統をごっそりと受け継ぎつつ、まったく新たな和歌を生み出し、中世和歌の基本を形成したからである。その方法の核がとなったのが、「縁語的思考」であった。たとえば定家は、当然表すべき語をあえて表現しないことによって、縁語的思考を活性化し、大胆で深みのある表現を生み出した。その他、中世の和歌として、源実朝・兼好法師・頓阿・世阿弥・宗祇らを取り上げた。一例を挙げれば、兼好法師は随筆『徒然草』の作者だが、当時は歌人として知られていた、その和歌は、偶然の出会いを尊重するもので、実はその姿勢こそ、『徒然草』のテーマにつながっている、と論じた。
(紹介文執筆者: 人文社会系研究科・文学部 教授 渡部 泰明 / 2017)
本の目次
第一編 古代和歌における中世――風景と主体
第一章 曾禰好忠の和歌表現
第二章 和泉式部の歌の方法
第三章 源経信の風景表現
第二編 中世和歌の方法的始発――縁語的思考と演技
第一章 源俊頼の方法と『俊頼髄脳』
第二章 西行の「ことばのよせ」
第三章 西行の花の歌の対話性
第四章 藤原清輔にみる本歌取り形成前史
第三編 中世和歌の形成――藤原俊成と藤原定家
第一章 千載集の羇旅歌
第二章 藤原俊成の縁語的思考
第三章 『古来風躰抄』における『万葉集』の抄出
第四章 『源氏物語』と中世和歌
第五章 藤原定家の方法
第六章 藤原定家の縁語的思考
第四編 中世和歌の展開――歌人と創作意識
第一章 源実朝と音
第二章 源実朝と『万葉集』
第三章 頓阿論――題詠のポエジー
第四章 『徒然草』と兼好法師集
第五章 『西行物語』における鳥羽殿
第六章 「高砂」の和歌的世界
第七章 宗祇と古今伝授
終章 本居宣長と『新古今集』――近世からの照射



 書籍検索
書籍検索