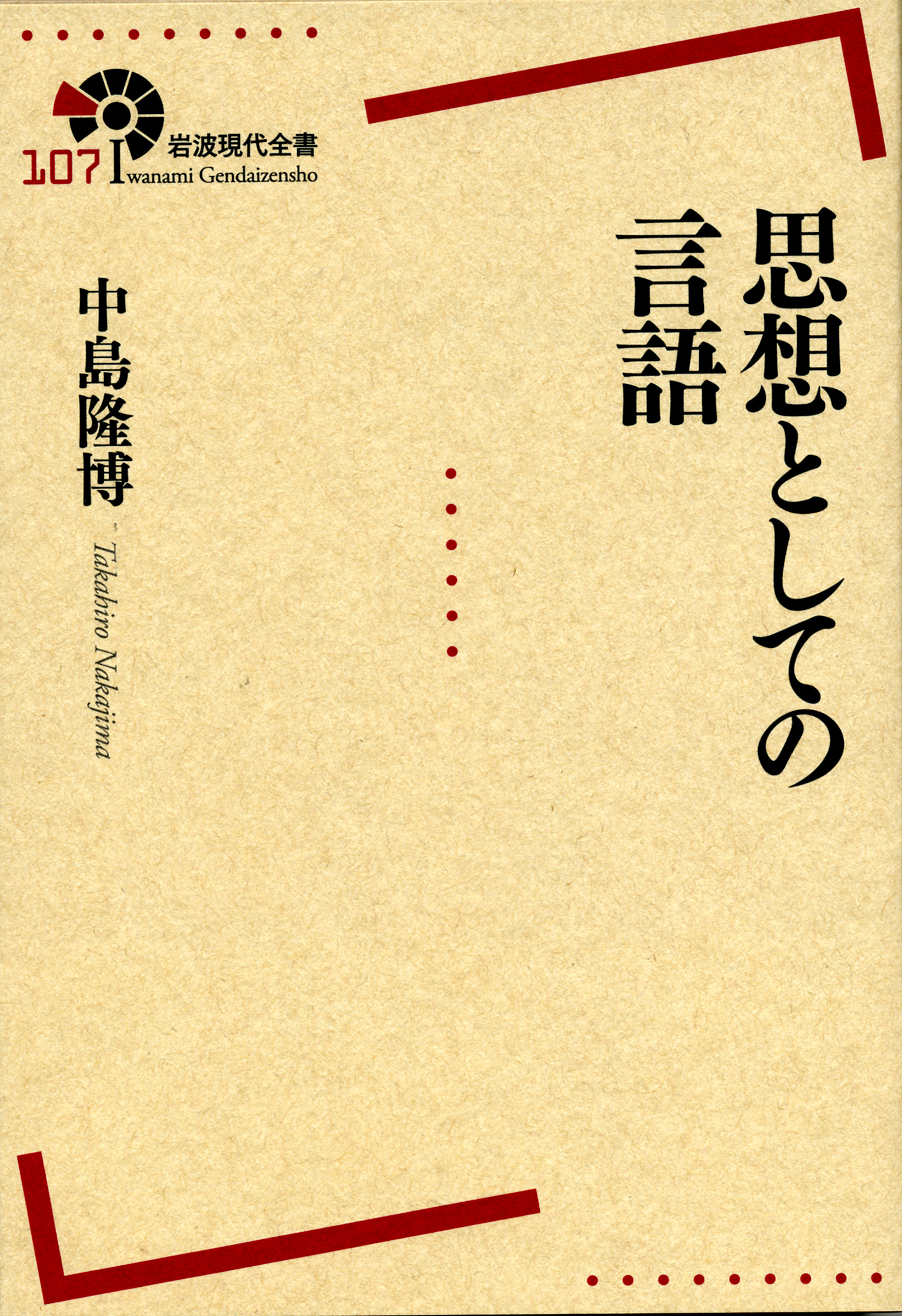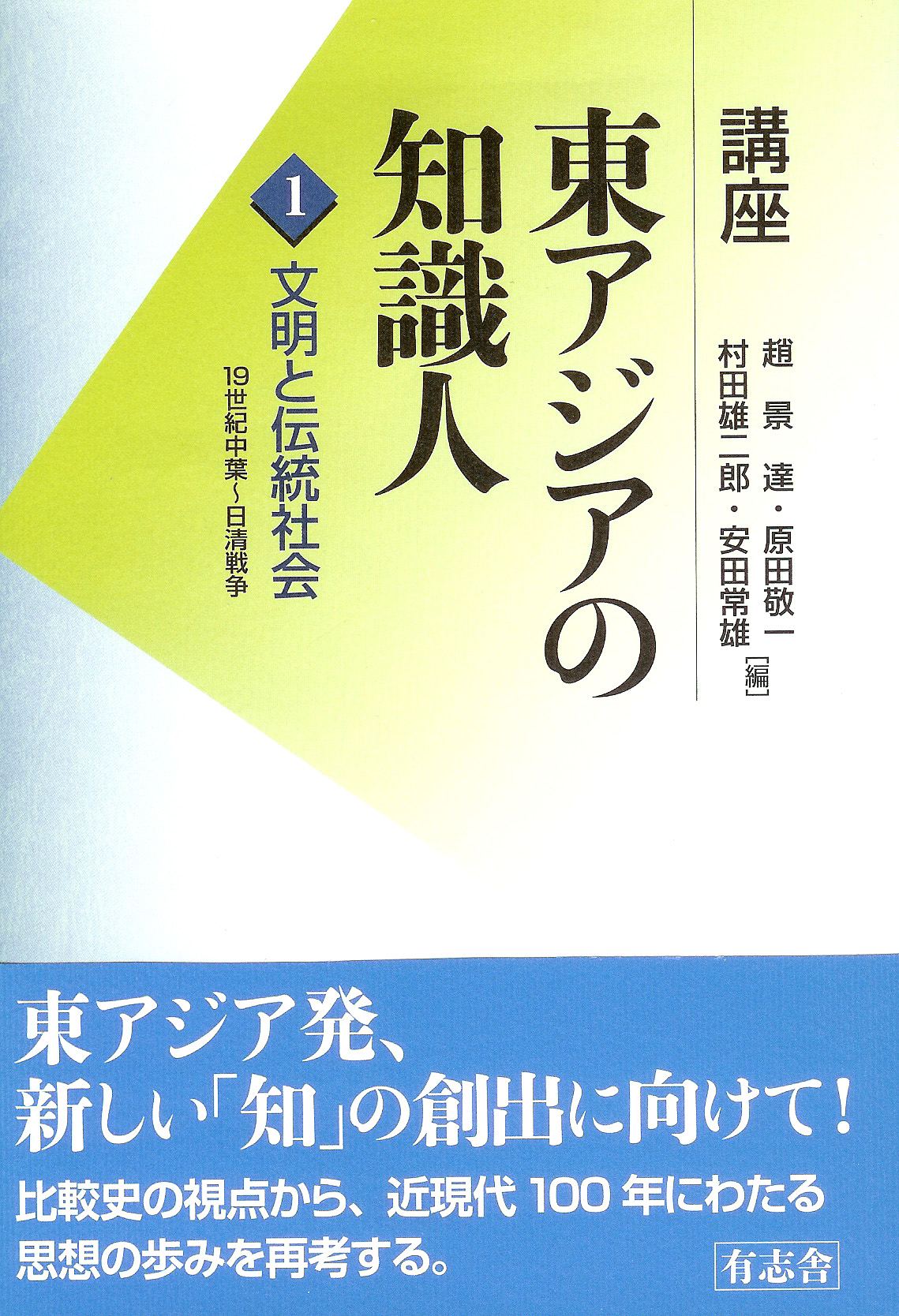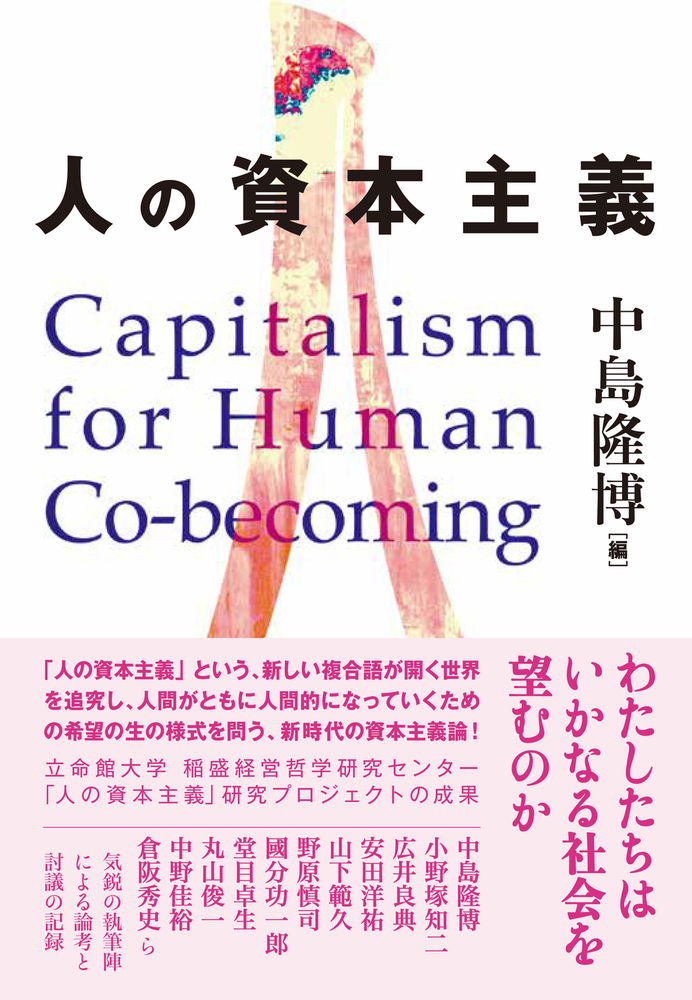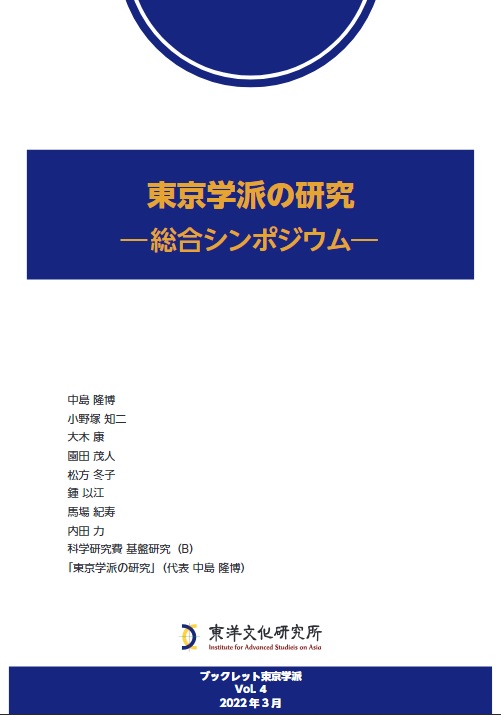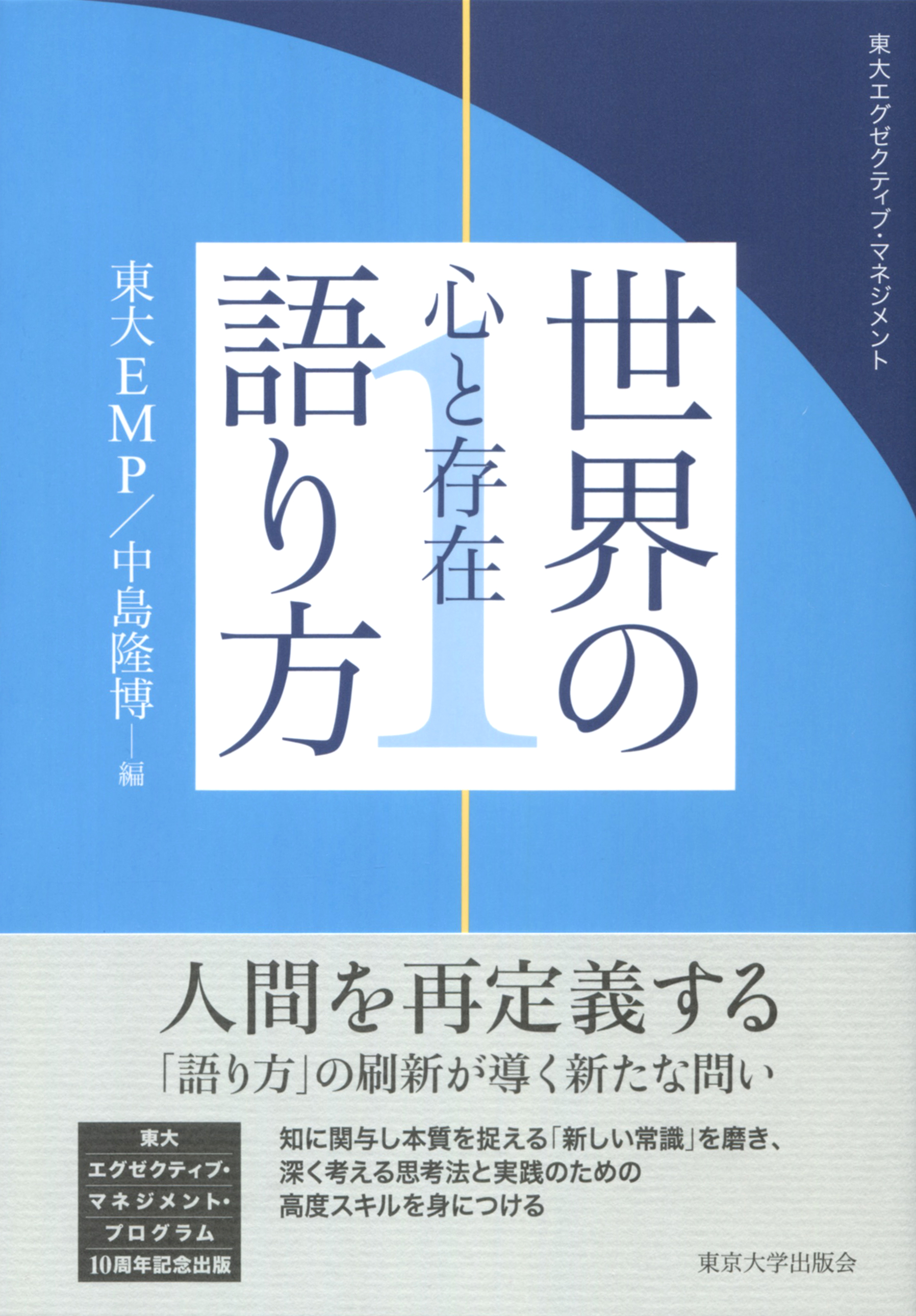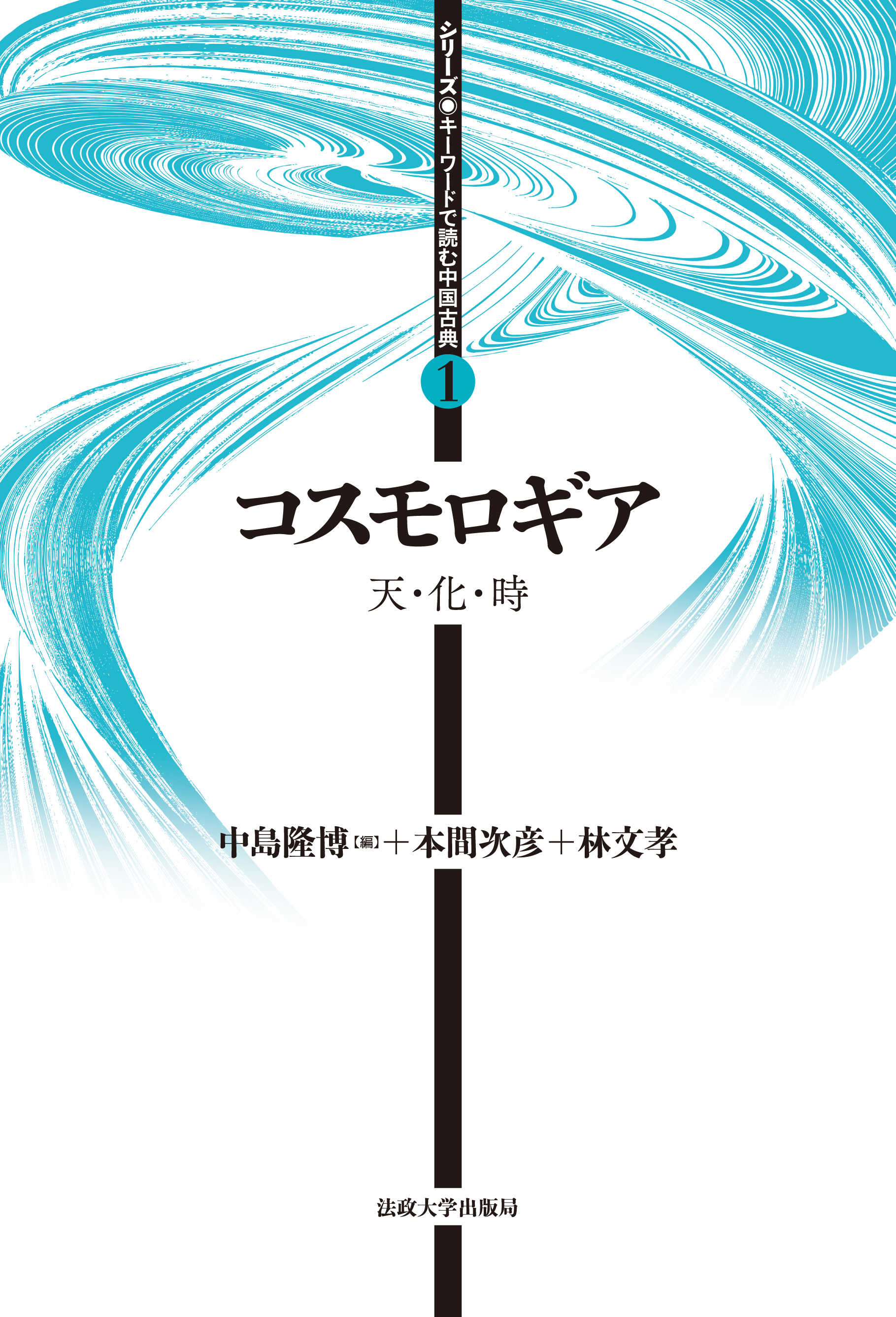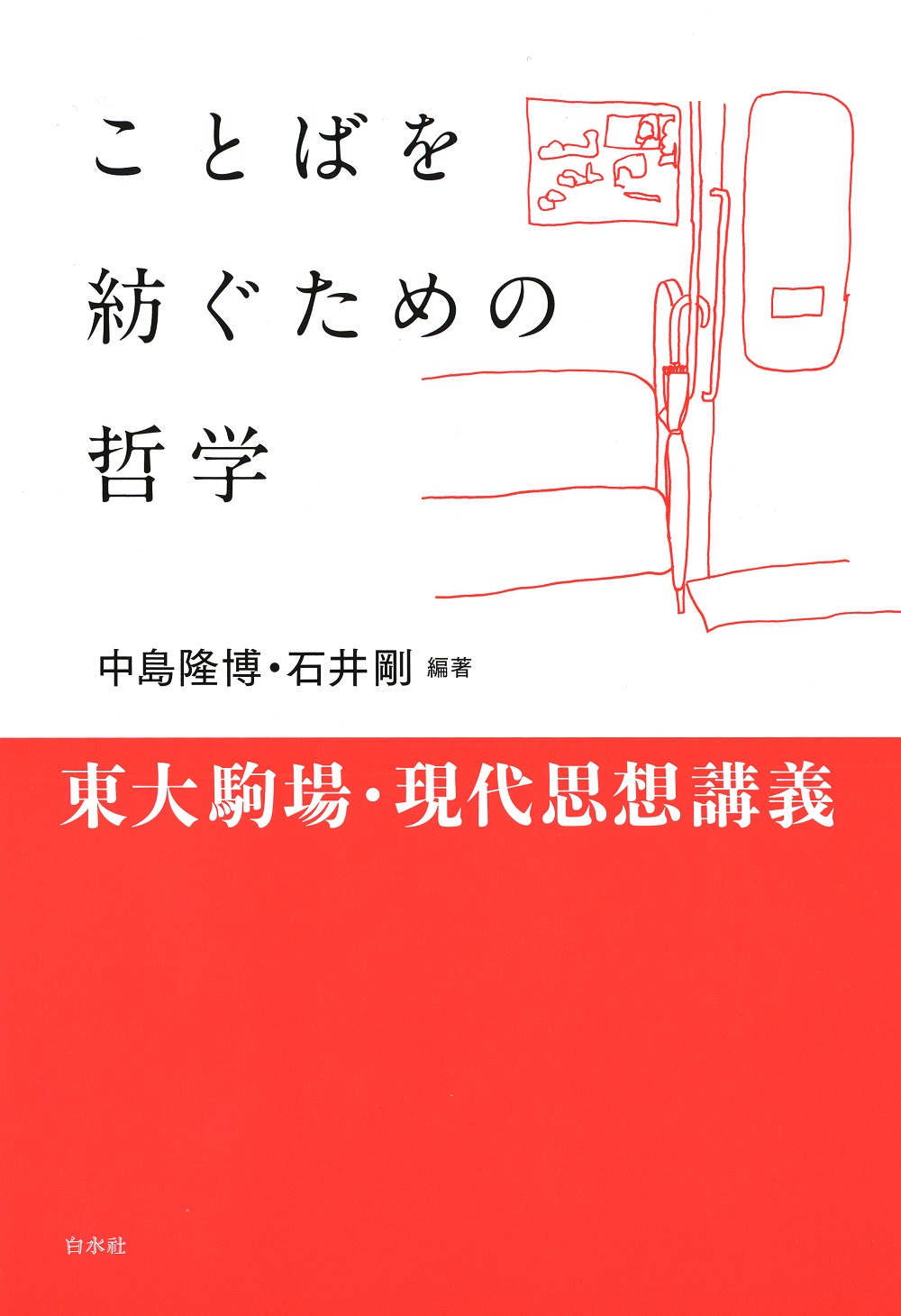本書が考えようとしたのは、道具としての言語ではなく、思想としての言語が、日本の思想史においてどのように展開したかである。
第一章で取り上げた空海の言語論は、その展開の方向性を大きく規定した。真言密教は、言語を鍛え直すことで、「今・ここ」という次元に直接秘密の次元を接続させて、衆生を救済する方途を示そうとした。言語は人間の言語を最初から超え出るものであった。
第二章では、『古今和歌集』の仮名序と真名序を取りあげ、その背景にある中国の詩論との比較を行った。紀貫之たちは、詩歌の起源にある秘密を、究極的には文であると考えた。そこには、空海が考えたような、言語と物そして心が織りなす入れ子状の構造や、言語が人間を超え出る可能性がやはり見出されたのである。
第三章では、本居宣長と夏目漱石を通じて、日本語が普遍にどう開かれていくのかを考えた。宣長は、中国という普遍に対抗して、日本的な趣味である「物のあわれを知る」を普遍化する道を取ったのに対して、漱石は、西洋的な普遍を前にして、関係概念としての「趣味」が普遍的でありうると考えることで、まったく新たに文学の基礎づけを行おうとした。そこから、文化本質主義に陥ることのない仕方で、しかし特殊を放棄せずに、普遍に開かれる可能性を探ったのである。
第四章では戸坂潤の翻訳と普遍について考えた。戸坂は、同時代人のベンヤミンによく似た仕方で、時間に刻みを入れ、それを時代として取り出し救済しようとする。そしてそれは、具体的な社会や具体的な歴史を離れてはありえないのだが、戸坂は時代が特異性を有したものとして結晶化すると同時に、「世界的に飜訳され得る」ことを要請していた。このことは、ファシズムへの抵抗としての言語の核心的なポイントであった。
第五章では、内村鑑三とその「日本的基督教」について考察した。これは漱石と同様の思考態度で、日本の経験を通じていかにより普遍的な普遍に開くことができるのかを考えたものである。その際、聖書という文が内村の思想としての言語を支えた。
第六章は、日本近代文学のなかで、「神樣」という関西に残るローカルな精神性/霊性とその近代における変貌を考えた。谷崎潤一郎、織田作之助、川端康成そして中上健次を見ていくと、近代のプロセスの中でローカルな精神性/霊性が毀損され、周縁化されていった傷跡が見て取れたのである。
第七章は、井筒俊彦が、儒教的な言語に対抗したとされる老荘思想を通じて、神秘の問題をどう考えていたのかを検討した。鈴木大拙とその日本的霊性という概念を継承しながら、井筒は神秘を、現実を超えたところに暗く潜むのではなく、現実の根底において働き、現実のただ中に立ち現れていると考えた。この空海的でもある議論を、井筒は老荘思想の読解において示したのである。
以上の考察を通じて本書が示したものは、言語経験(翻訳を含む)を通じて見いだされる救済や神秘の次元である。それは、わたしたちの生きているこの世界はそのままに、そこに垣間見られる別の次元における救済である。
(紹介文執筆者: 東洋文化研究所 教授 中島 隆博 / 2017)
本の目次
第一部 日本における思想としての言語――普遍に向かって
第一章 空海の言語思想
第二章 『古今和歌集』と詩の言語
第三章 本居宣長と夏目漱石の差異
第二部 近代における思想としての言語 (一) ――救済の場所
第四章 時代に切線を引くには――ヴァルター・ベンヤミン,竹内 好,戸坂 潤
第五章 日本的基督教と普遍――内村鑑三
第三部 近代における思想としての言語 (二) ――垣間見られる秘密
第六章 ローカルな精神性と近代――日本近代文学から
第七章 神秘をめぐって――井筒俊彦と老荘思想
結論にかえて
参考文献
注
あとがき



 書籍検索
書籍検索