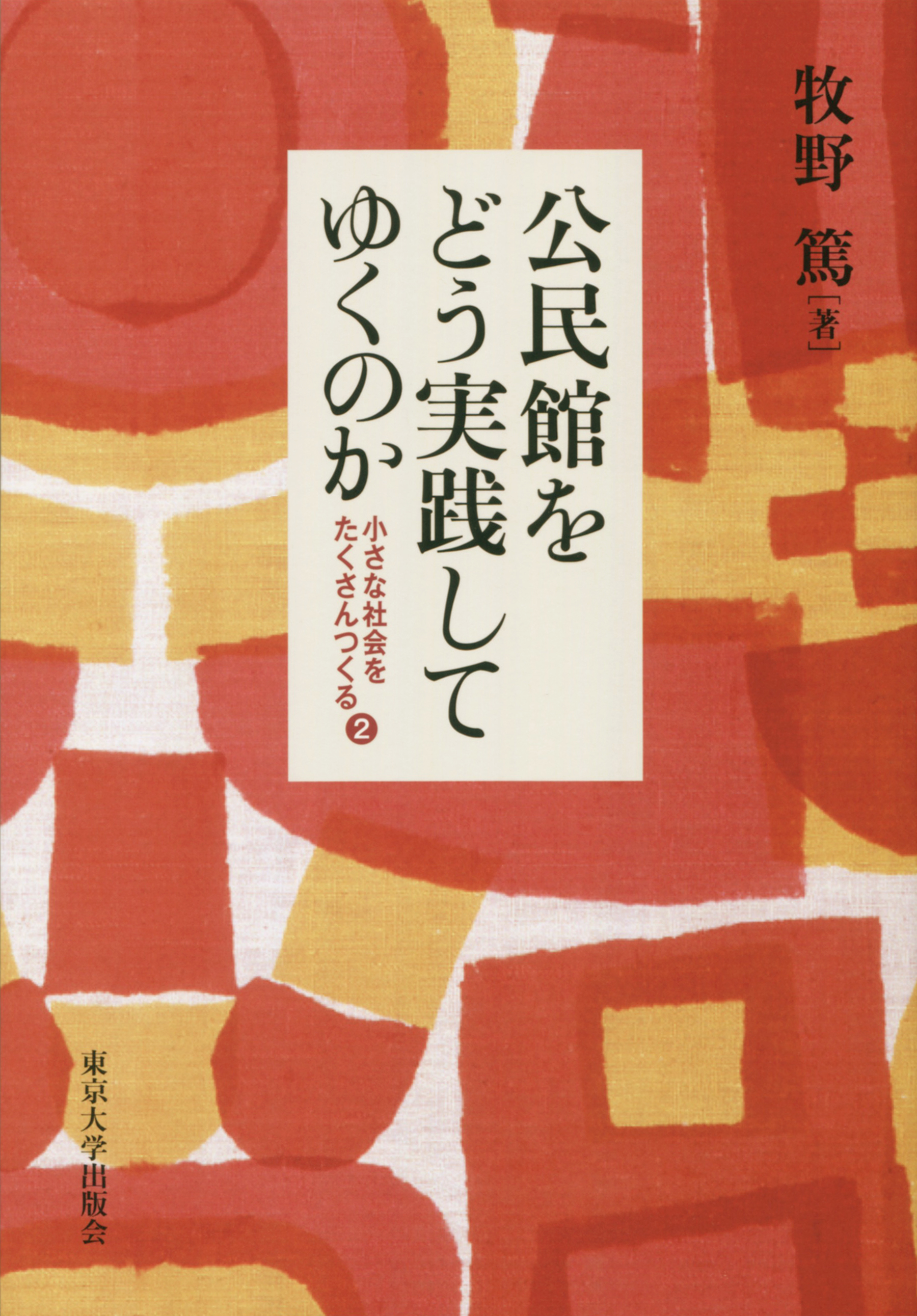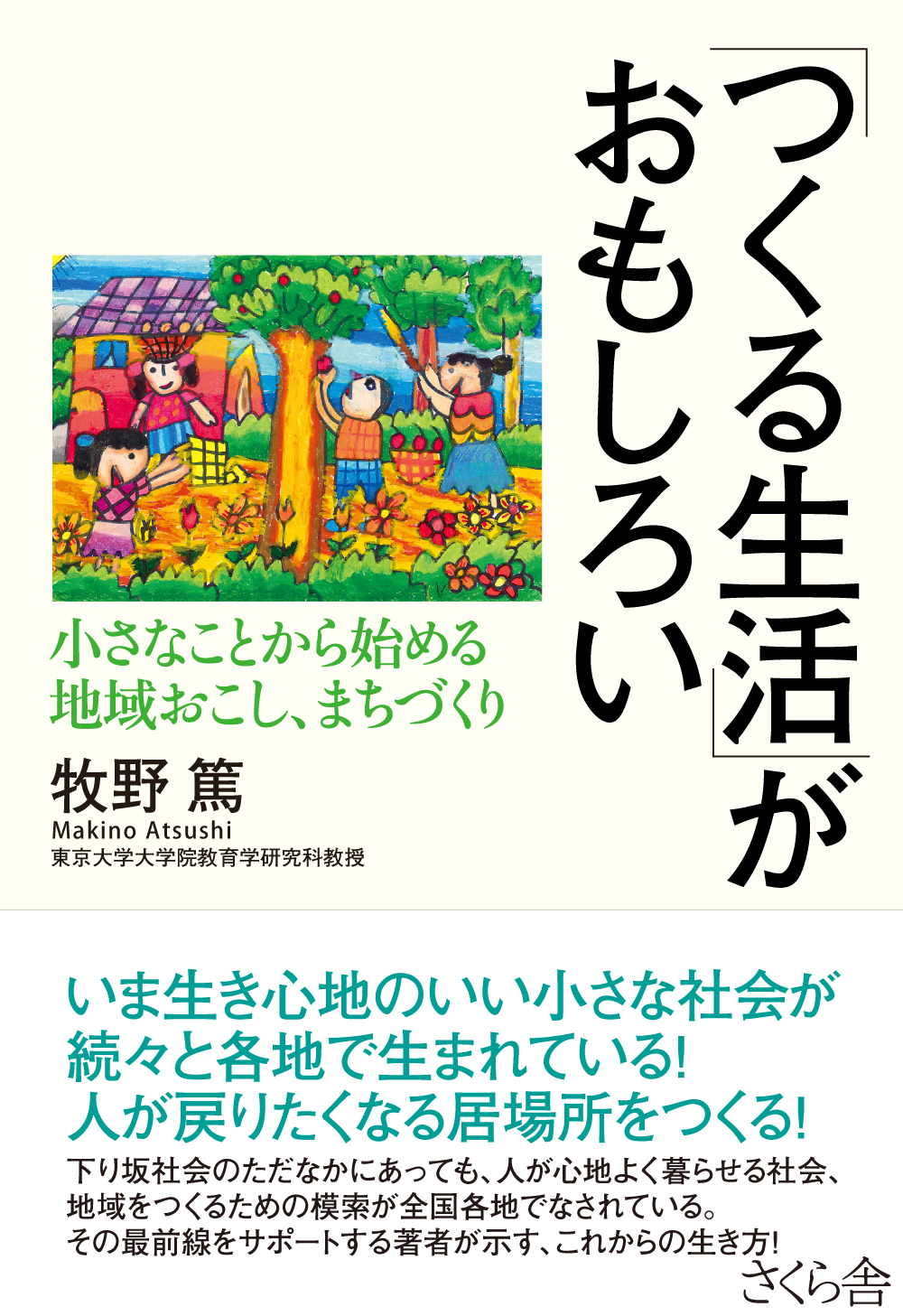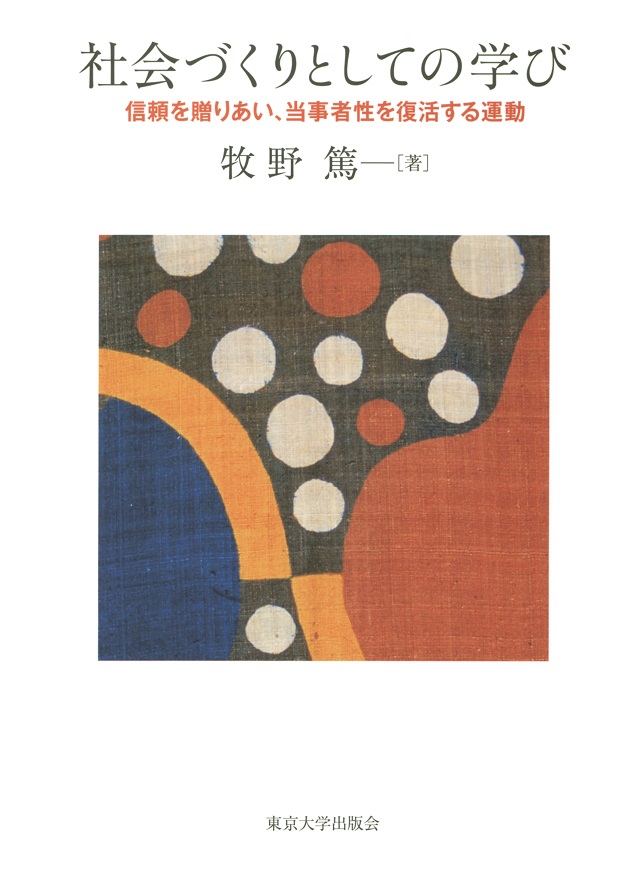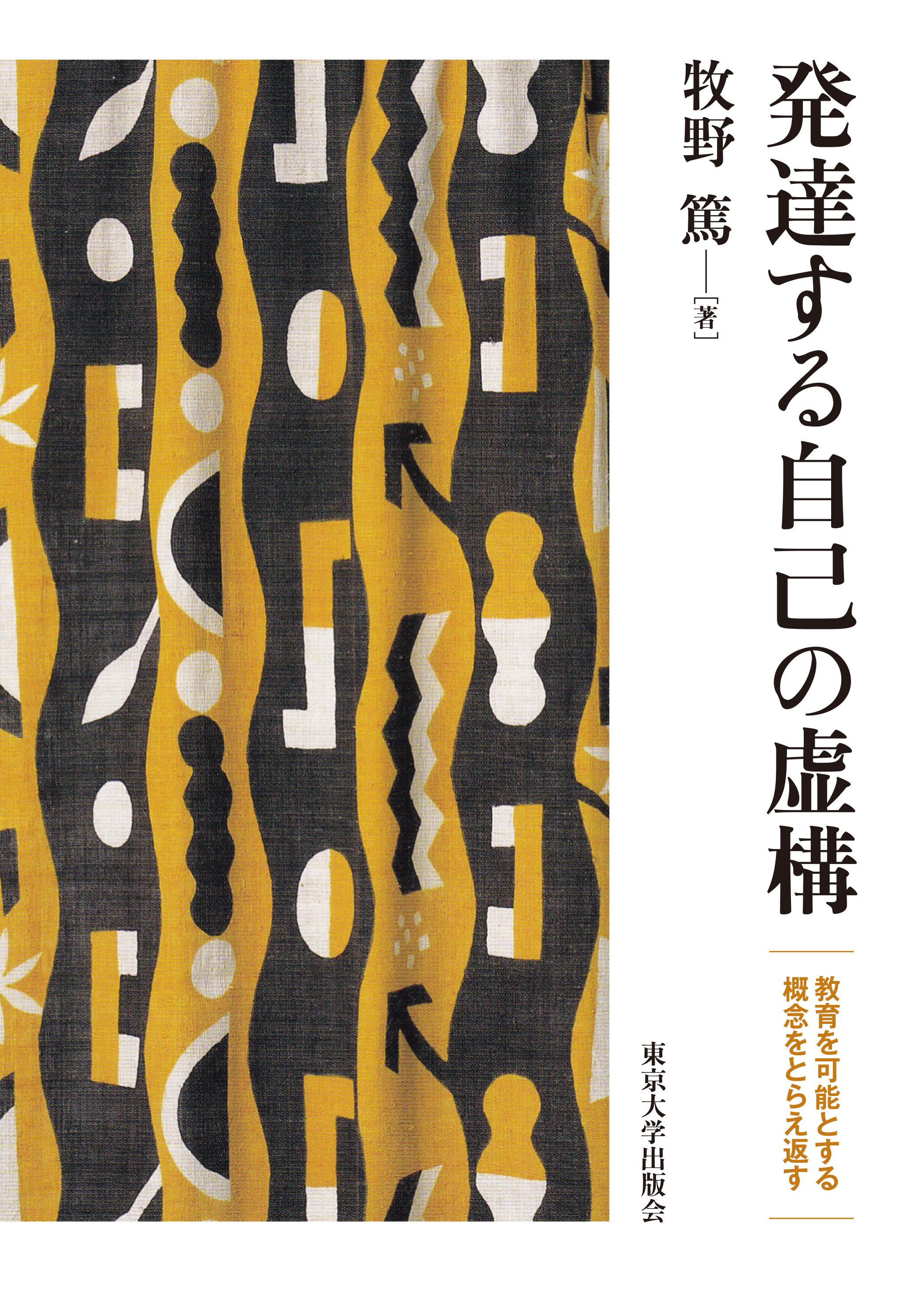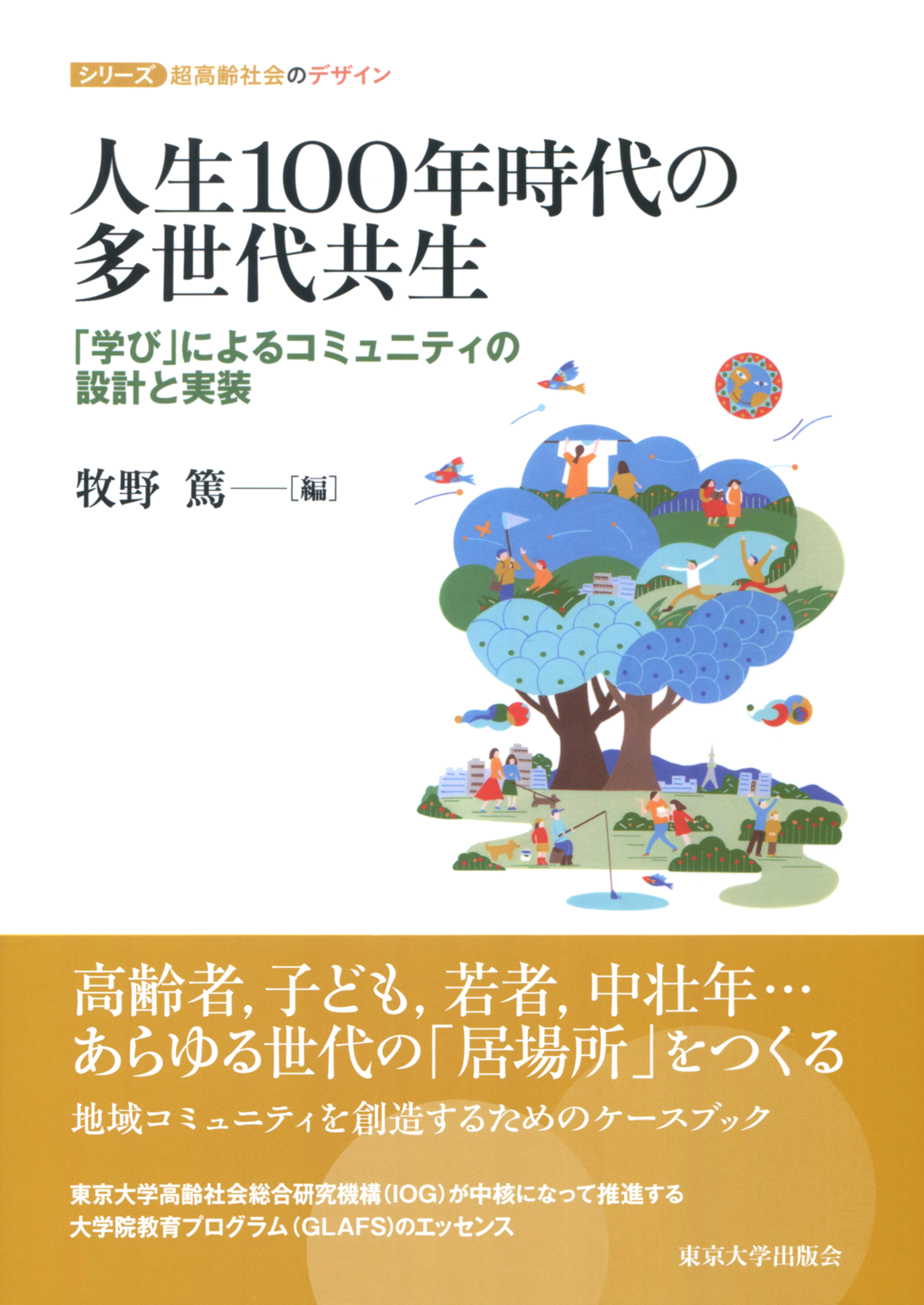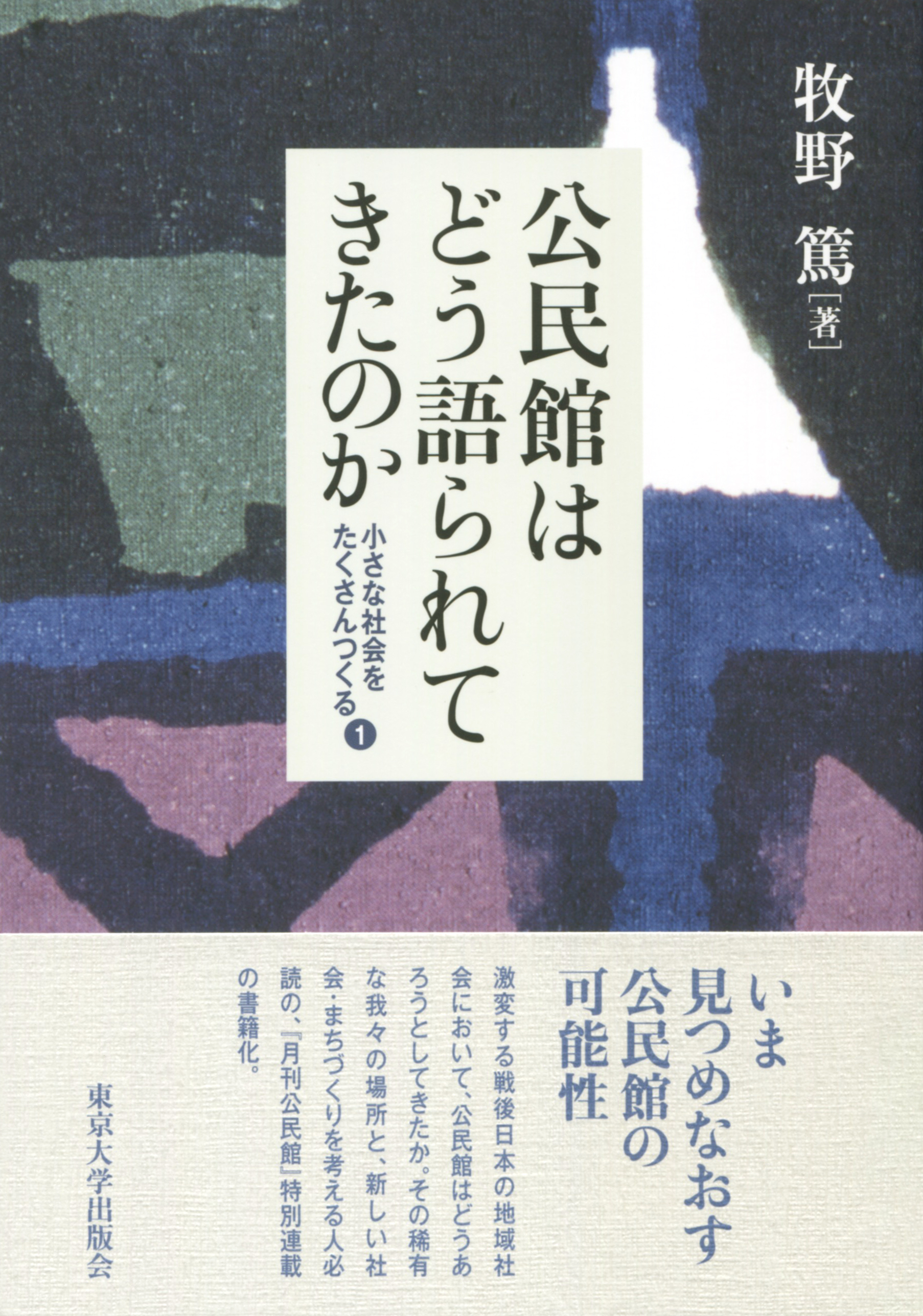
書籍名
公民館はどう語られてきたのか 小さな社会をたくさんつくる・1
判型など
296ページ、四六判
言語
日本語
発行年月日
2018年11月9日
ISBN コード
978-4-13-051343-2
出版社
東京大学出版会
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
日本の教育体系は大きく学校教育と社会教育の二つの制度から構成されており、公民館は、社会教育の実践を支える主要な施設として、住民によるいわば草の根の活動を支えてきた。その直接の構想は、1946年、いまだ日本が敗戦の混乱期にある中で提示され、平和で民主的な社会を生活の地平から実現しようとする人々の願いと努力に支えられて全国に施設の設置が進められた。現在でも、数は減ってきているとはいえ、1万5000館ほどの公民館 (基礎自治体が設置している公的な公民館) が置かれている。
本書の執筆過程で、私の胸に去来していたのは、公民館をめぐる言説が大きく展開するときはまた、社会教育が政治的に課題化されるときであり、社会教育が政治の関心事となるときは、この社会の構造が、人々の生活のレベルにおいて大きく変容し、人々の実存が毀損される危機が招かれているときだという歴史的な事実である。そして、今日でも、この状況は変わっていないように見える。
人工知能が多くの人々の仕事を奪う時代がすぐそこにやってきているといわれる。私たちはそのような社会の裏側にある事態にも目を向けなければならない。静かに潜行している子どもの貧困の蔓延に代表されるように、この社会には深い分断線が幾重にも走り、人々は自己責任の罠にとらわれて自己防衛的になり、他者に対する不寛容が広がり、この社会から信頼という文字が消えつつある。この社会では、自立をすることがまるで孤立することであるかのような感覚が広がり、人々は相互にいがみあいながら、行政への依存を深め、それをサービス化し、自治体行政機能の不全化を招くことになっている。自治体の団体自治の基盤である住民自治が、人々の孤立の深まりとともに瓦解しつつあるといってよい。
このような社会において、公民館が改めて社会基盤の整備のために政策の焦点となっている。そこでは、私たち一人ひとりの住民は、他者とは分割できない住民という集合的な存在として、この社会を担うことが求められる。その社会とは、過去のような、抽象的な国民である個体を基本とした分配と所有の社会、そしてそこで主体として位置づけられる普遍的な個人の完成が所与であり当為であるとして措かれる社会ではない。それは、むしろ他者との〈間〉に存在し、他者とは分割不可能な、それでいて個別具体的な日常生活を送る住民という集合的な存在を基本とした生成と変化の社会である。
このような社会と個人の存在の基盤を整備する仕組みの一つが公民館なのだといってもよい。それはまた、〈わたし〉が〈わたしたち〉という分割不可能な存在として「ある」ことのできる〈ちいさな社会〉から改めてこの社会のあり方を構想し直し、この社会の基盤を改めて確かなものへと鍛え上げていく、つまり住民自治を豊かに組み上げることにつながる。その基礎となるべき議論をとらえようとした。それが、本書である。
このような社会と個人のとらえ方の変化は、公民館をめぐる議論においても、さまざまに展開する言説の中に、あり得た過去として見出すことのできるものである。私たちは経験が通用しなくなる時代に生きている。しかし、過去に学びつつ、あり得た過去の声に耳を澄ませ、あり得る未来を構想することは可能なはずである。
(紹介文執筆者: 教育学研究科・教育学部 教授 牧野 篤 / 2019)
本の目次
第1章 私たちはどこにいるのか
第2章 戦後の公民館構想の特色
第3章 二つの「公民館のあるべき姿と今日的指標」の観点
第4章 自治公民館と「近代化」への志向性
第5章 歴史的イメージとしての公民館—寺中構想再考
第6章 高度経済成長と社会教育の外在・内在矛盾
第7章 生涯教育の時代と「第三次あるべき姿」
第8章 社会教育終焉論と生涯学習批判
第9章 住民自治と公民館
第10章 「自治」としての〈学び〉へ
結び 当事者になる場の新しい方向
あとがき
関連情報
田中里尚 評 (『図書新聞』3399号 2019年5月11日)
https://www.fujisan.co.jp/product/1281687685/b/1821479/
公民館は、どう「語られて」きたのか? (公民館プログラムのたね 2018年10月9日)
https://cs-wakasa.com/program/archives/4654
イベント:
「公民館的なもの」が今こそ地域に必要だ ―『公民館を再発明する』を著者・牧野篤先生と読む (本棚演算株式会社 2024年11月21日)
https://www.localknowledge.jp/2024/10/1744/



 書籍検索
書籍検索