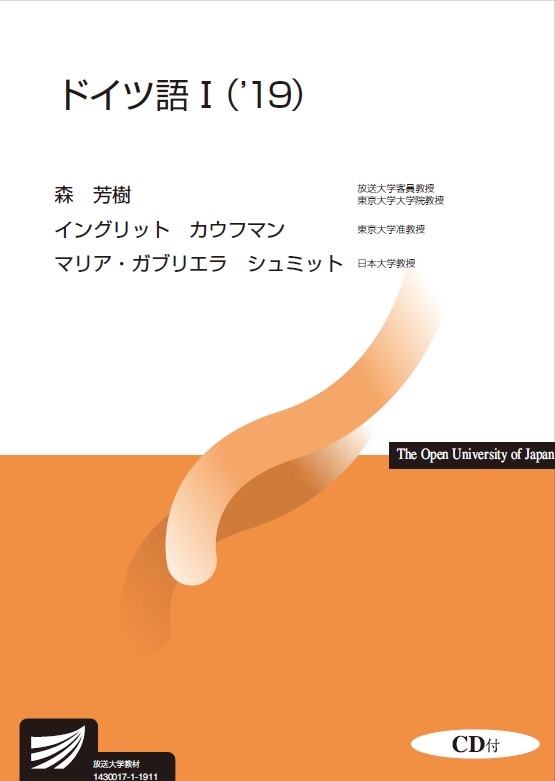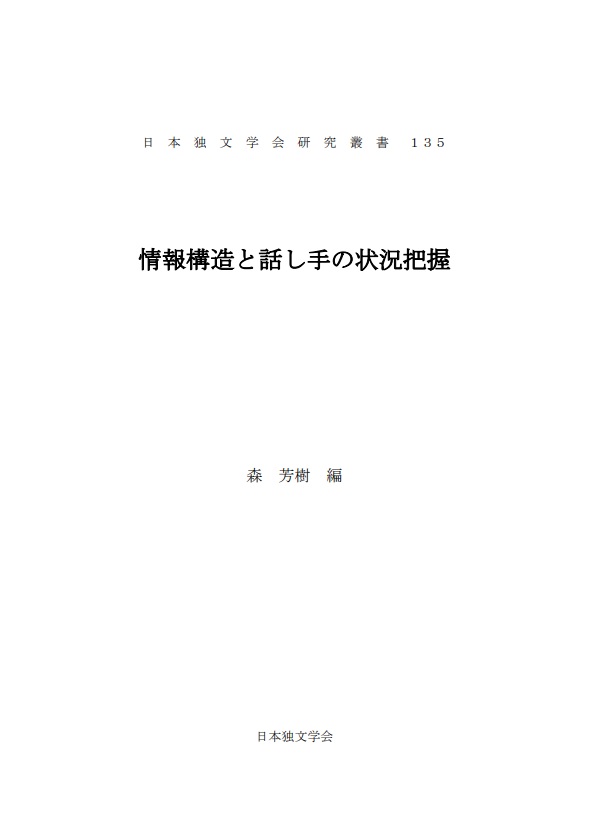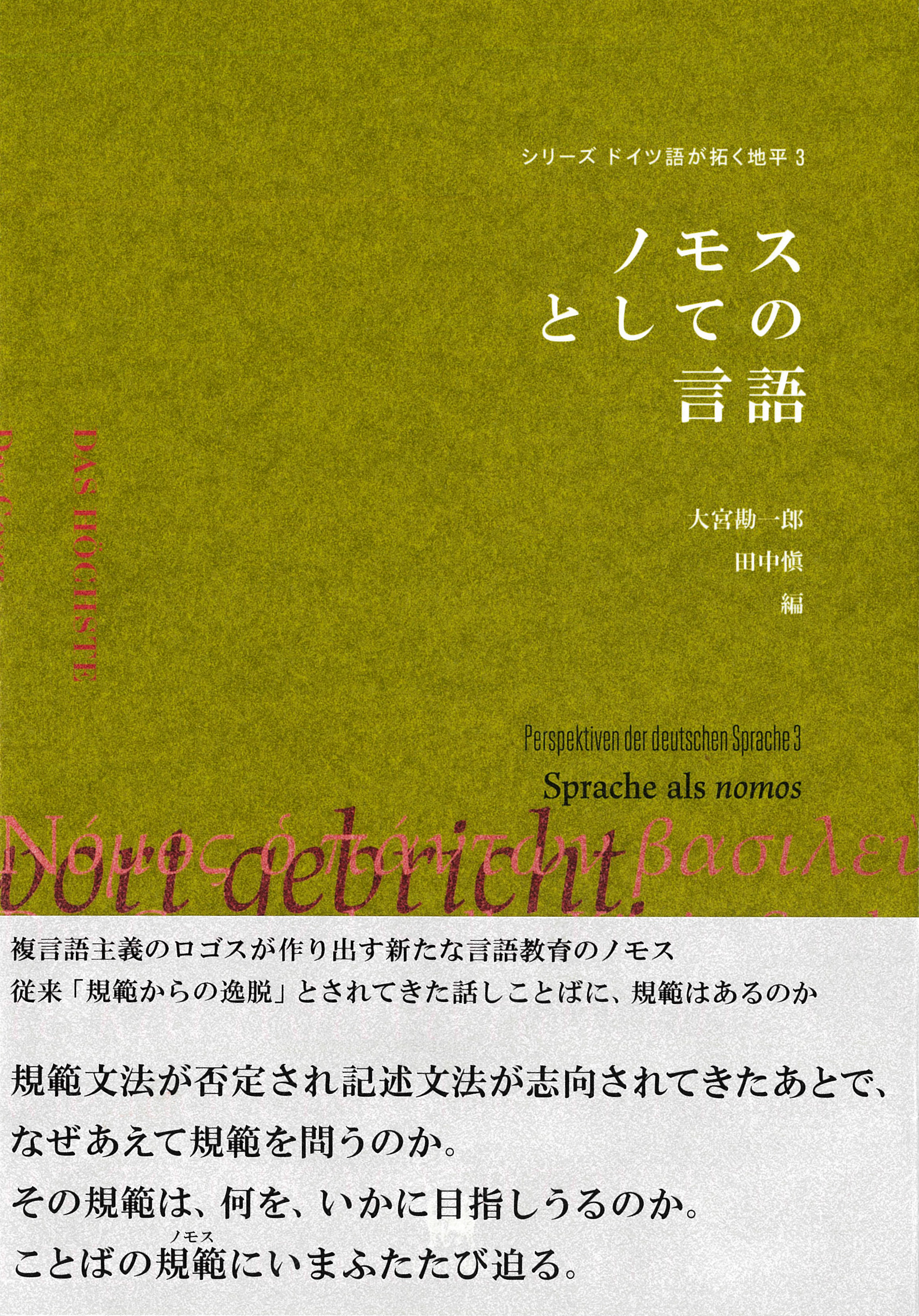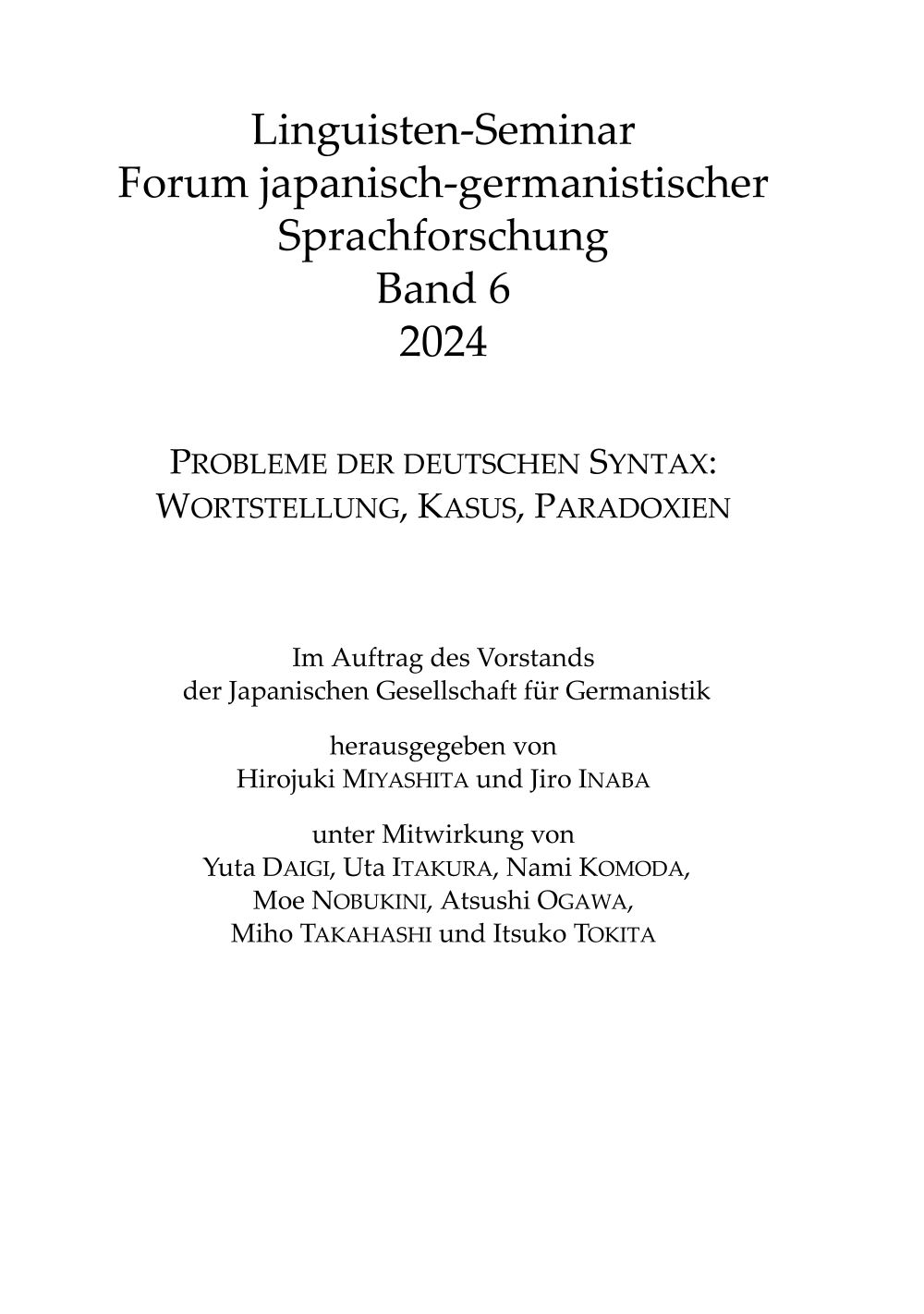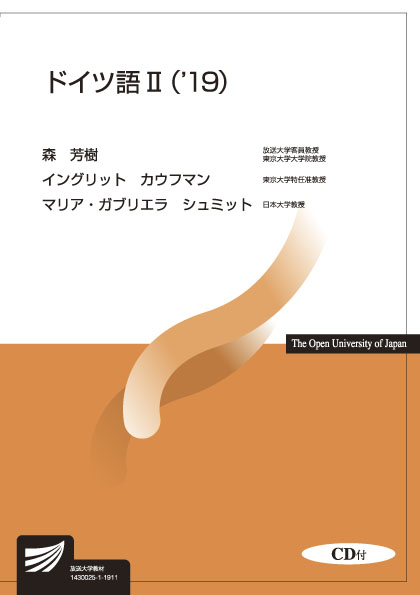
書籍名
ドイツ語II (’19)
判型など
368ページ、A5判、CD付
言語
日本語、ドイツ語
発行年月日
2019年
ISBN コード
978-4-595-31970-9
出版社
放送大学教育振興会
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
放送大学において2019年度から数年間使用される、テレビドイツ語のテキスト。ドイツ語Iの続編で、東京大学の1年生が必修ドイツ語で学ぶ内容の後半部分をより多面的に構成したものである。本書では、難しいことばにもトライできる足腰を鍛えるための文法の学習を進めながら、同時にことばの使い方を実用的に学ぶ工夫がなされている。ヨーロッパにおける言語教育だけでなく、世界におけるヨーロッパ言語の言語教育、さらに日本語など他言語の言語教育にもしだいに多大な影響を与えているヨーロッパ言語共通参照枠 (CEFR) を強く意識して作成された本書だが、その枠組みに囚われたというわけでもない。参照枠の受容はさまざまであり、状況と文脈に合わせてさまざまであるべきだとも思う。
「学校文法」は常に、実際に進められている言語の記述と理論の簡略版でしかないが、本書では、ドイツ語に関する「学校文法」に新たなアイデアを多く取り入れた。ドイツ語が他の言語からいかに違うのかという観点より、他の言語と似ている側面がここかしこに見てとることができるという観点を強調することで、新しく学ぶドイツ語に、まるでどこかで見たことがあるような気持ちになって取り組んでもらえることが重要だと考えたからだ。また語彙も、共通参照枠に準拠したゲーテ・インスティテュートのランク付けを参照しながら、初学者が学んでほしいものを明示している。
このドイツ語IIでは、英語に慣れ親しんだ読者やそもそも新しい言語を学ぶ学習者にはいつも難しい文の組み立て方と語順の話で全体をサンドイッチして、語の組み立てと文の構築というこれまでの文法に委ねられた役割だけでなく、組み立てた文をどのような場面、どのような行為の中で使うかという実際的な問いにも寄与している文法の役割も強調した。ことばの能力には、文法能力を中核にしながらも、ことばを使ってどのようなパフォーマンスをするか、自分の置かれている状況をどのように把握するかといった言語使用、言語認知の能力も含まれているのだ。さらに、さまざまな文体のテキストを配し、ドイツ語のさまざまな使い方に慣れ親しんでもらえるよう工夫した。
また、大学や仕事、介護といった日本にもある日常から始めて、祝祭日や共同生活の習慣、絵画や音楽などの芸術、環境問題や役所、そしてベルリンの戦後史、ドイツの憲法と憲法裁判所といった話題も含めて、ドイツを多面的に紹介するような構成を心がけた。ドイツの法学者による原文、ドイツのシンガー・ソングライターに特別許可をもらった歌詞の訳も含まれている。ドイツ・ヨーロッパの地域研究の出発点になってくれれば幸いである。
本書はテレビという放送教材との融合を考えて作られたテキストであり、さまざまなスキットと練習を盛り込んであり、実際にことばを使うパフォーマンスにつながるように設計されている。とくにスキットは、家族の構成員がそれぞれドイツでするであろう体験を組み合わせて、社会的に多様な日常場面の提示に努めた。この本だけではなく、アニメを多用したスキット、そこに登場する本学の先生や学生の声を聞きながら放送教材も楽しんでもらえれば幸いである。
(紹介文執筆者: 総合文化研究科・教養学部 教授 森 芳樹 / 2021)
本の目次
2.過去への遡行:体験の語りと手紙 旅行
3.過去からの語り メルヒェン
4.比較と順序づけ 交通路
5.人や物のより正確な描写 フランクフルト ・アム・マイン
6.文から作る名詞 ことわざ
7.非現実を用いた間接的な表現 願いと望み
8.不定詞副文を用いた禁止と規定 計画と秩序
9.複文の中での時間と因果の関連 芸術
10.行為の担い手の言及の回避 標準ドイツ語と方言
11.人伝の話 報告
12.口語文につける陰影 感情の表出
13.複合と派生:新しい語を作る 書き言葉
14.複雑な動詞構成 余暇と祭り
15.復習とまとめ 戦後史



 書籍検索
書籍検索