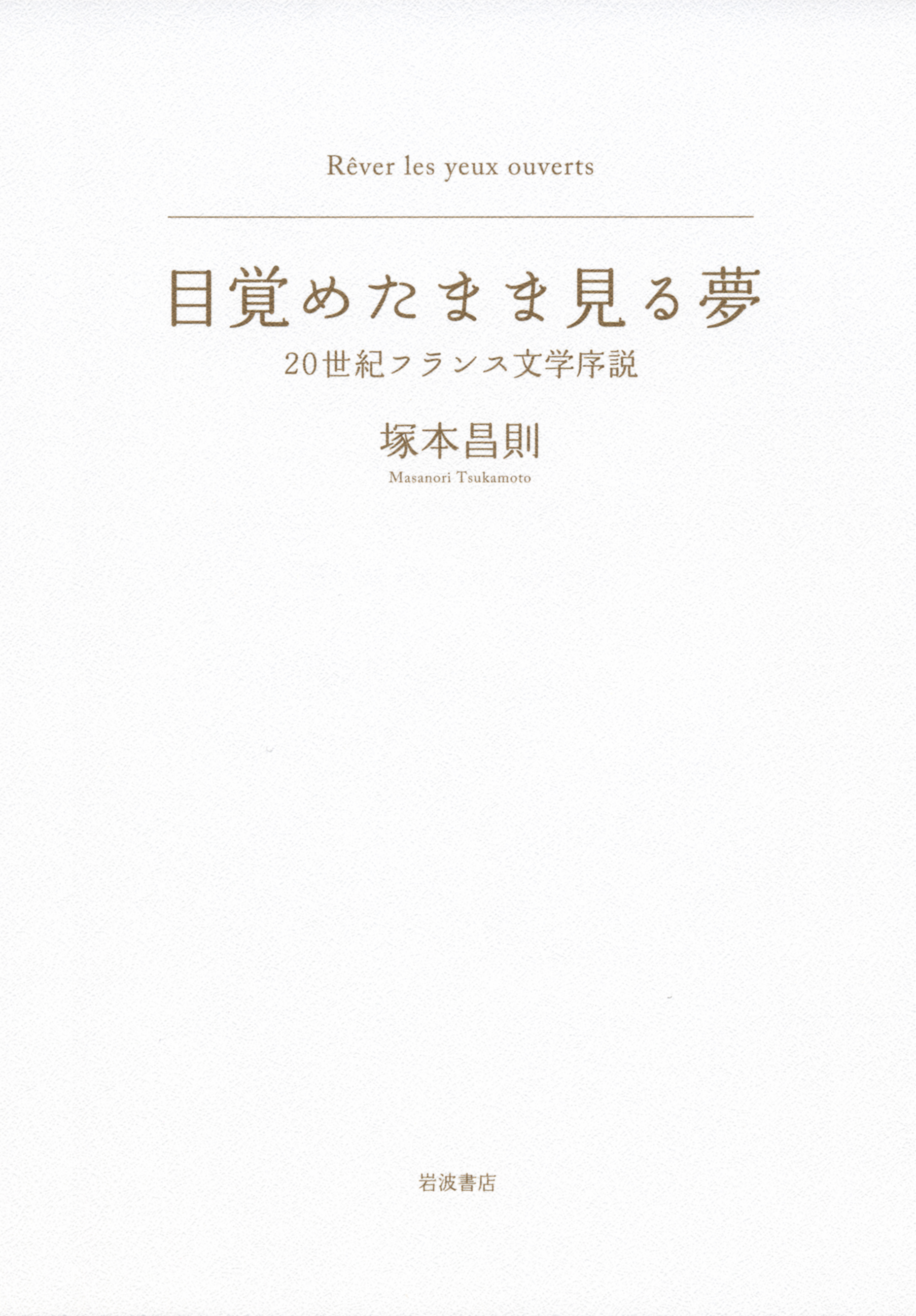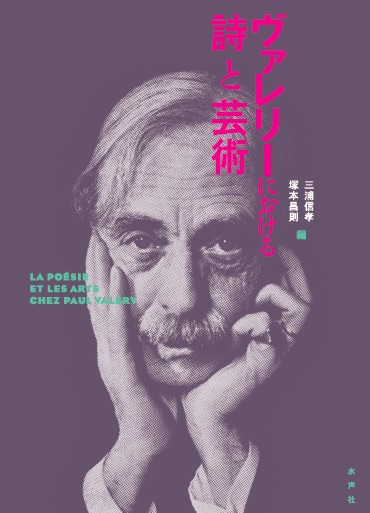小説のなかで、活字のかたわらに印刷された写真に出会うことがある。白い光沢紙にプリントされた写真とは異なり、紙の質も悪く、人目を引くような見事な作品というわけでもない写真。言葉のかたわらに写真が挿入された文学作品は、いったいいつ頃から作られるようになったのだろうか。
写真史をひもといてみると、一八三九年、写真が発明されてすぐに、写真文学が成立したわけではないことが分かる。写真創成期、文学作品に写真を取りいれようとする試みが数多くなされたが、そのほとんどが立ち消えになった。当時は写真を光沢紙に印刷する必要があり、膨大な費用がかかったためである。例えば、ヴィクトル・ユゴーは一八五三~五五年、ジャージー島での亡命生活を、写真と文章からなる本にしようとしたが、実現しなかった。
この状況が変わったのは、一八九〇年代、シミリグラヴュールという、文字と写真を同じページに安価に印刷する技術が発明されて以降のことである。この技術を使って、世紀末から二十世紀初頭にかけて、写真文学作品が続々と出版された。しかし、現在も読み継がれているのは、ほぼローデンバック『死の都ブリュージュ』(一八九二)一作のみである。これが写真文学を考えるうえで、最初の大きな謎となっている。どうしてこの作品だけが残され、他の写真文学は消えてしまったのだろうか。
当時の写真文学では、本に挿入されるのはほとんどが登場人物を演じるモデルの写真だった。どうやらここに問題があったらしい。というのも、ローデンバックはブリュージュの絵葉書を使い、できる限り人間の姿が写されていない風景写真だけを意図的に選んだからである。肖像写真には、言葉による芸術作品と折りあいをつけるのが難しい部分があるのだろうか。その難しさの正体は何なのだろうか。言葉によって喚起されるイメージと、写真イメージの二つがたがいに補いあい、一体となって想像力を駆りたてるとき、そこにはどのような想像空間が広がっているのだろうか。
このような疑問を抱いて、その後の写真文学作品を読み解いてゆくと、作家たちが実に多彩な写真の使用法を編みだしていることが見えてくる。アンドレ・ブルトンは『ナジャ』(一九二八、六三)に、ナジャと呼ばれる女性の両眼の部分だけを四つ重ねたコラージュ作品を収録している。谷崎潤一郎は『吉野葛』(一九三一、三七)に、架空の登場人物の祖母の書いた手紙の写真を掲げた。写真は、かつてそこにいた人物や物をあるがままに見せるものと普通は考えられている。しかし、虚実皮膜のうちに繰り広げられる文学作品において、中心となる人物をそのまま写真で見せることはきわめて難しいことなのだ。見えない中心を意図的に隠したり、別の角度から見せたりすることで、初めて写真は生き生きとしたものとなるかのようだ。
写真文学について考えることは、結局、言葉によって生みだされるイメージと、写真というイメージのそれぞれの特質を考察し、その二つがどのように関係し得るのかを探ることに帰着する。言葉によって喚起されるイメージには、眼で見て確かめられる形がそなわっていない。だが、言葉のうちで何かが語られていることを読者が感じ、その感触を追いつづけるとき、そこにはある明確なイメージが思いうかんでいる。それに対して、写真は、視覚的イメージそのものであり、見るべきものは目の前に、否定しようのない形で顕わにされているかにみえる。だが、写真文学において、写真が深く作品世界に関わってくるとき、そこには見えないものにこそ真実が宿っているように思えてくる。写真に写らないものとは、その写真が写されてから流れた膨大な時の厚みであり、その歴史の中で人々がたどった苦難の歩みに他ならない。
言葉と写真という異質な媒体に生気が吹きこまれるとき、そこでは何が起こっているのか。写真文学の重要作品を読みときながら、じっくり考えてみたい。
(紹介文執筆者: 人文社会系研究科・文学部 教授 塚本 昌則 / 2025)
本の目次
序 章 写真文学とは何か
1. 小説の危機と写真文学の誕生
2. 顔の物語
3. 言葉のイメージと写真イメージの交点──風景としての人間
4. 顔の消滅、顔の出現──写真文学の世界へ
第I部 顔、風景、ドキュメント──写真の中の見えないもの
第1章 風景写真の使用法
──ジョルジュ・ローデンバック『死の都ブリュージュ』(一八九二)
1. 無人の街路──風景写真の使用法
2. 写真都市ブリュージュ
3. 絵葉書とは何か
4. 出現のモチーフ
第2章 肖像写真の使用法
──アンドレ・ブルトン『ナジャ』(一九二八、一九六三)
1. 肖像写真の使用法I──ヒロインの顔を示さないこと
2. 「取り乱した証人」
3. 肖像写真の使用法II──男たちの写真
4. 風景写真の使用法──凡庸さの外観、敷居としての写真
第3章 ドキュメント写真の使用法
──谷崎潤一郎『吉野葛』(一九三一、一九三七)
1. 「初音の鼓」──『吉野葛』における写真の使用法
2. 虚構の手紙の写真
3. 備忘録の写真──W.G.ゼーバルト「アンブロース・アーデルヴァルト」をめぐって
4. 写真は実物に似ているのか
第II部 空白のスクリーン、不在の写真
第4章 戦争の記憶、空白のスクリーン
──ジョルジュ・ペレック『Wあるいは子供の頃の思い出』(一九七五)、パトリック・モディアノ『ドラ・ブリュデール』(一九九七)
1. 子供の写真──空白の部屋(ペレック『Wあるいは子供の頃の思い出』I)
2. 偽りの記憶──批評的自伝(ペレック『Wあるいは子供の頃の思い出』II)
3. 透かし模様のスクリーン(モディアノ『ドラ・ブリュデール』I)
4. ドラの顔(モディアノ『ドラ・ブリュデール』II)
第5章 不在の写真
──マルグリット・デュラス『愛人』(一九八四)、アニー・エルノー『娘の回想』(二〇一六)
1. 「絶対の写真」──行為としての写真(『愛人』I)
2. 「絶望の写真」──イメージの場所(『愛人』II)
3. 撮られなかった写真──エルノーの場合(『娘の回想』)
4. 写真が作りだす現実(アニー・エルノー/マルク・マリー『写真の使用法』)
第6章 記憶の想起と写真
──W. G. ゼーバルト『アウステルリッツ』(二〇〇一)
1. 迷子の写真──主人公の肖像写真
2. リヴァプール・ストリート駅の情景──見えない写真
3. 『アウステルリッツ』と『失われた時を求めて』──見出された時と写真の使用法
4. 母親の肖像
第III部 日常生活と写真
第7章 日常礼讃──現在をめぐって
──ロラン・バルト『ロラン・バルトによるロラン・バルト』(一九七五)
1. 伝記素──私的な生活
2. 写真と俳句
3. 「存在の増幅器」としての写真──ジル・モラ/クロード・ノリ『写真宣言』(一九八二)
4. 肖像写真に写らないもの



 書籍検索
書籍検索