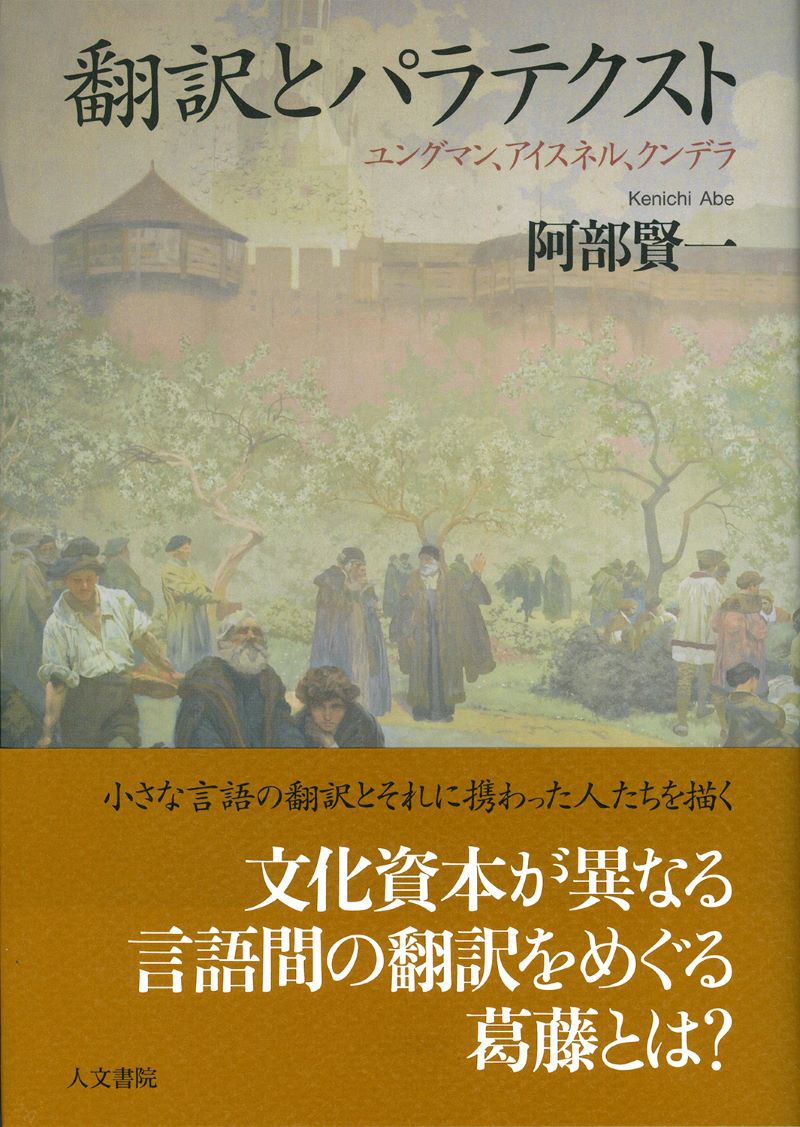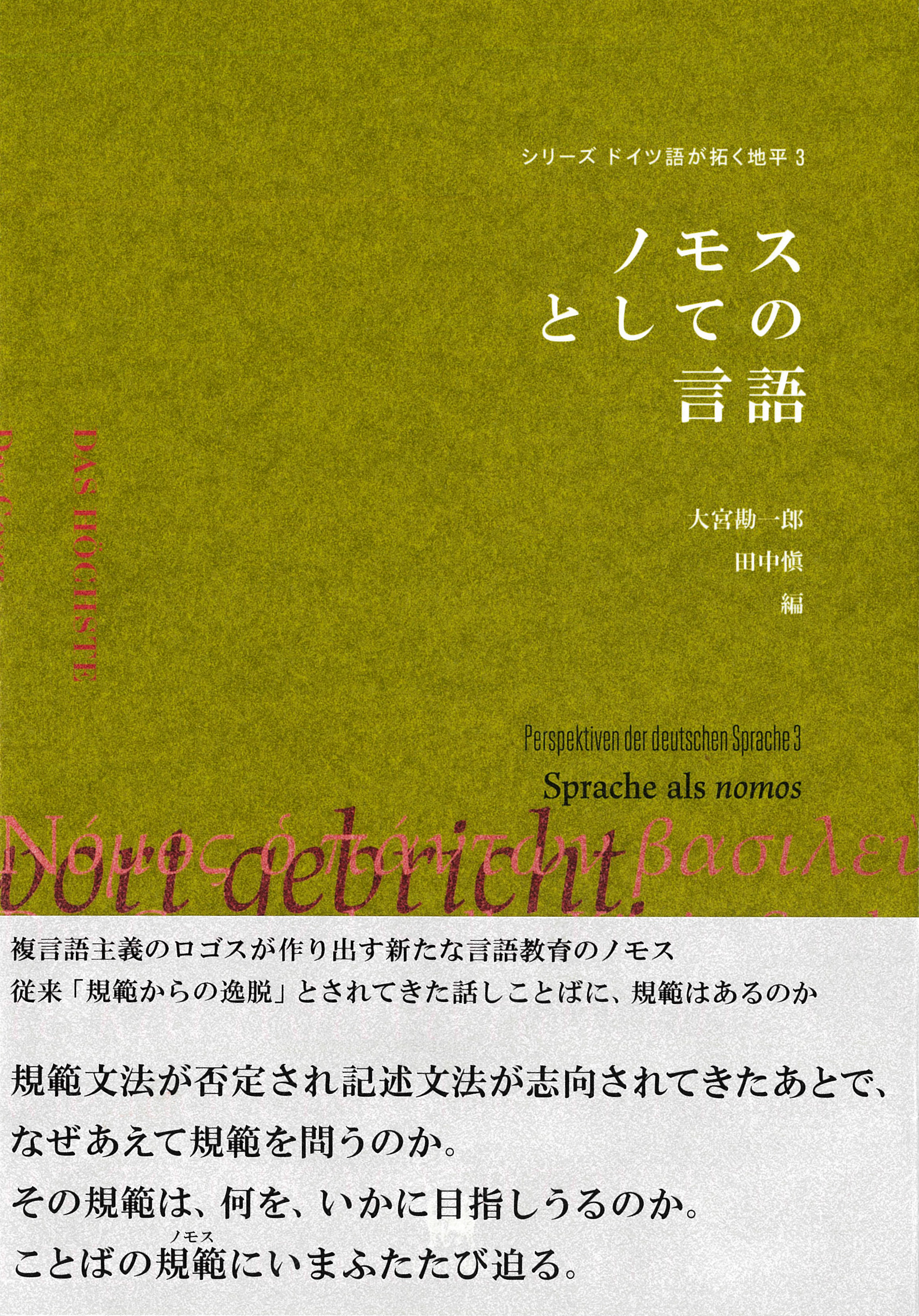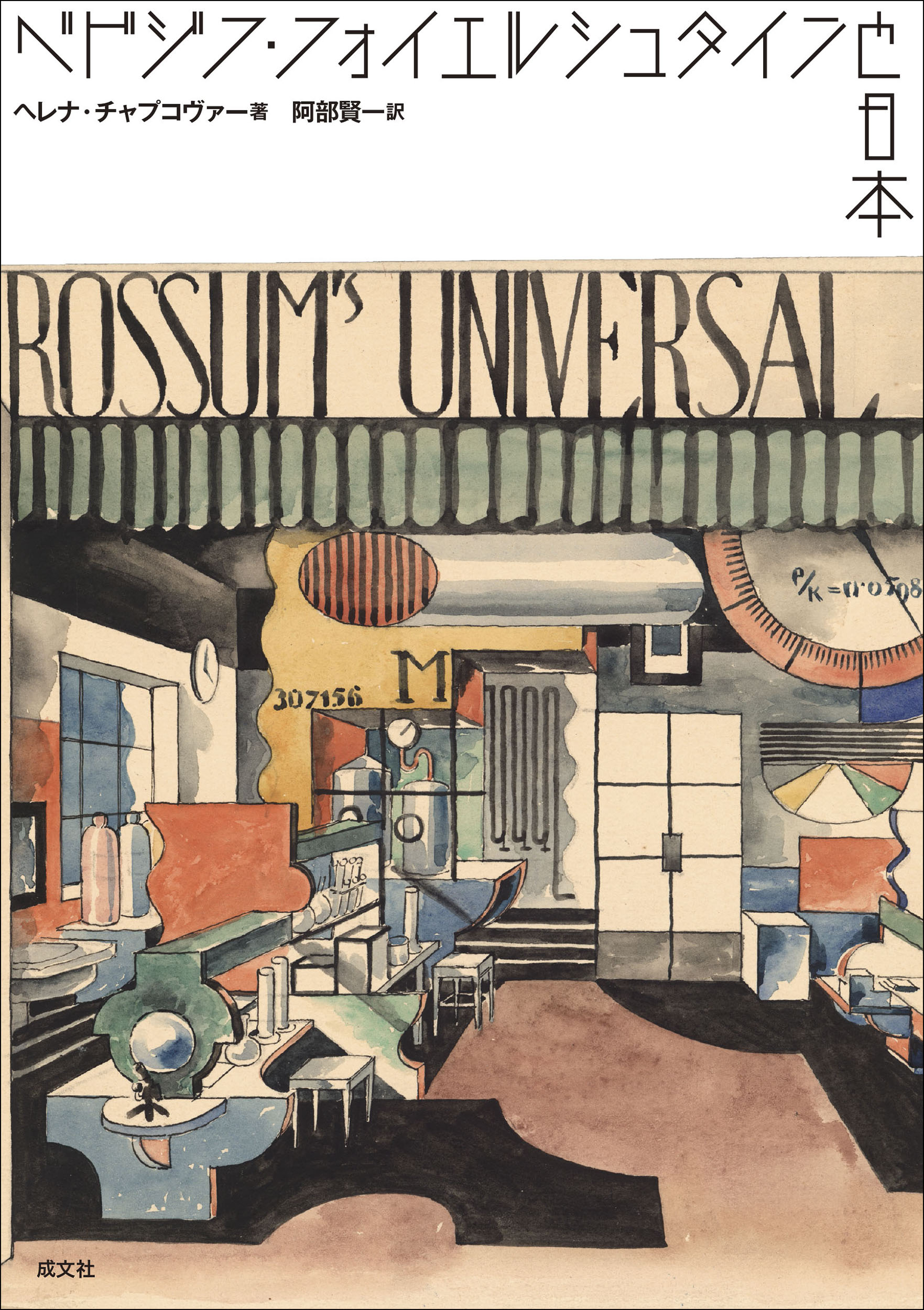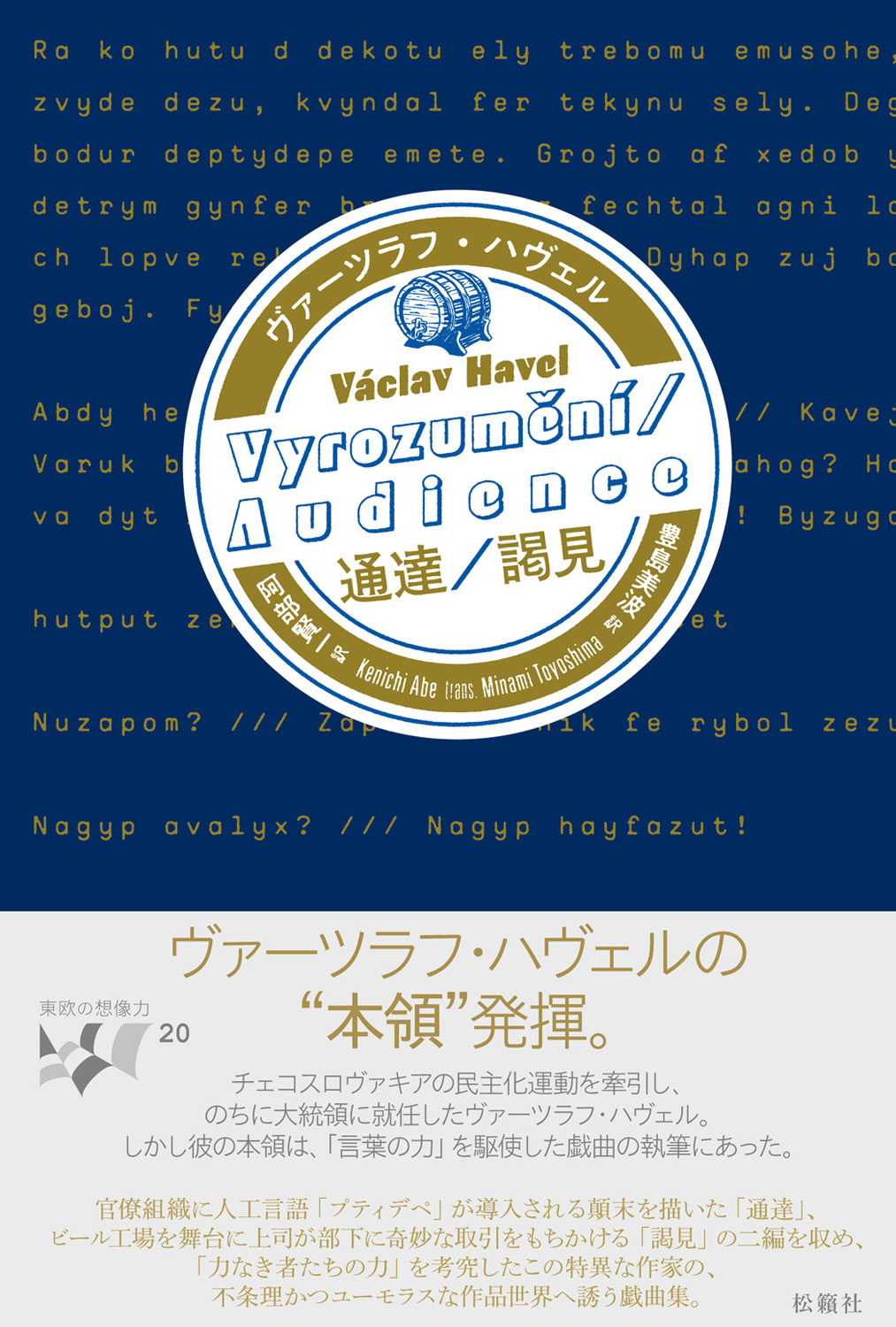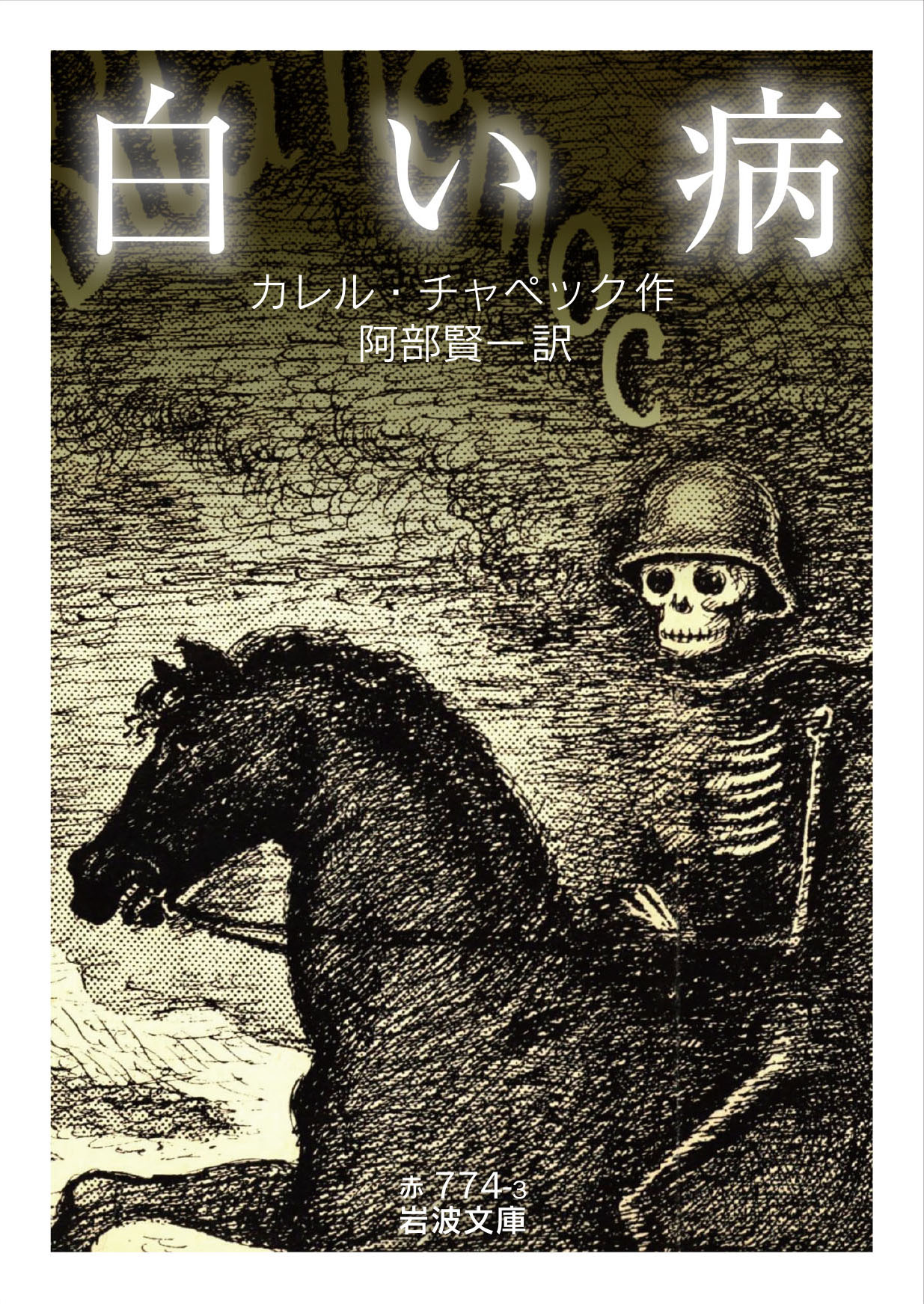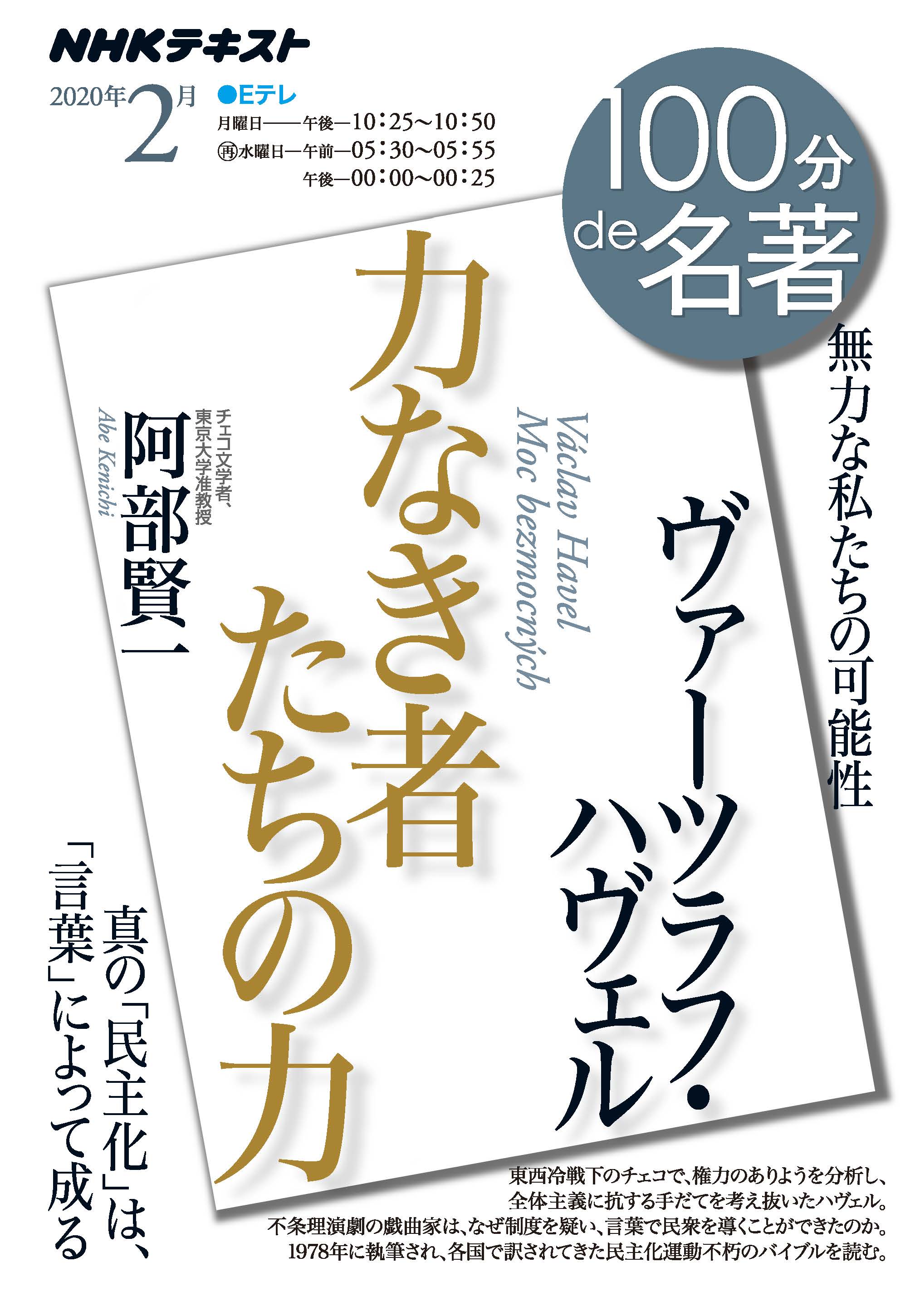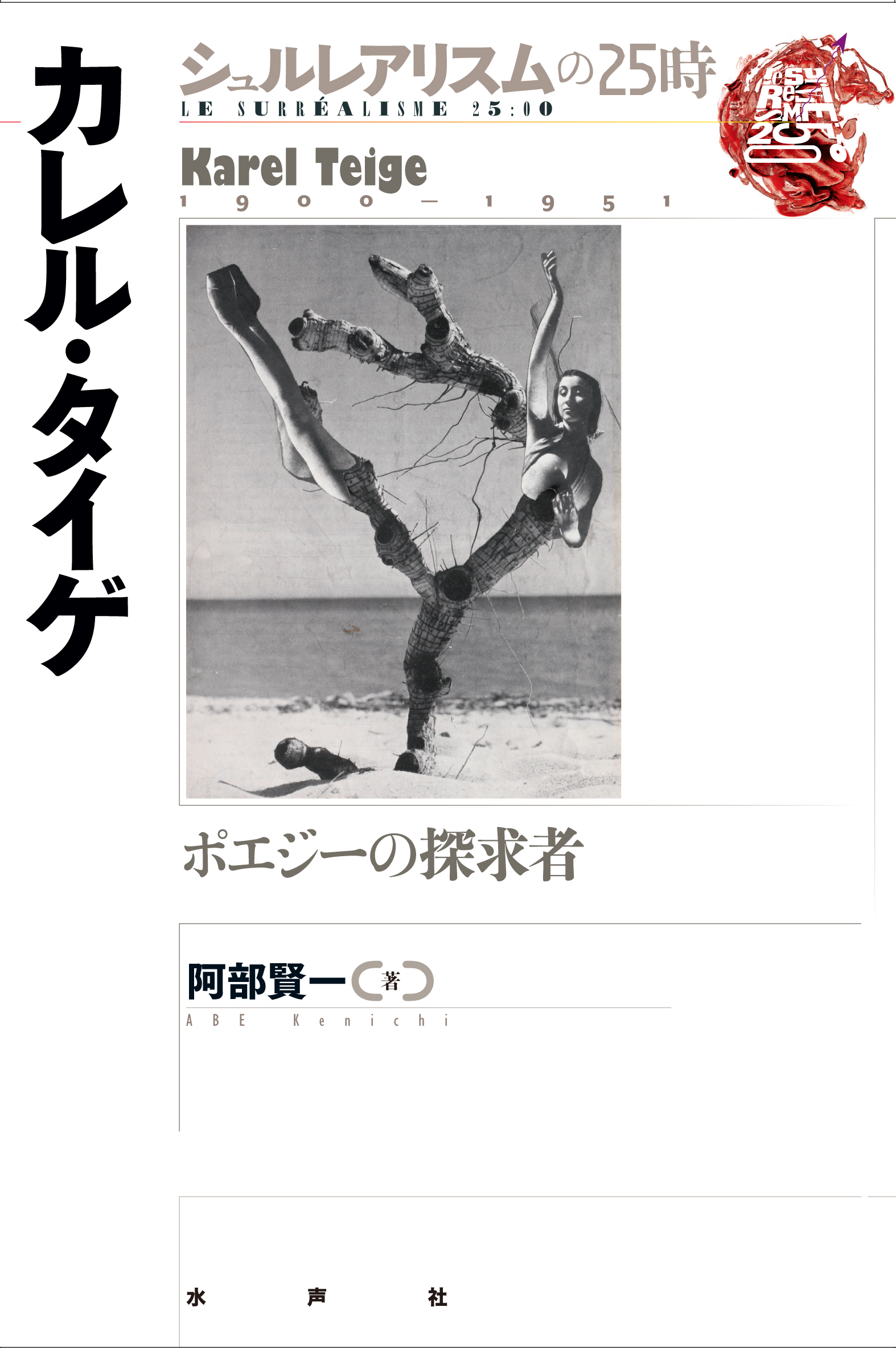図書館の本には番号が付されており、「文学」であれば、9から始まる三桁の数字が上段に記されている。日本十進分類法では、「日本文学」が910、「中国文学」が920、「英米文学」が930という数字が割り当てられているが、言語毎の分類は無限に続くわけではなく、990は「その他の諸言語文学」とされている。同時に気がつくのは、990番台の書棚の面積は他の文学に比べると圧倒的に小さいことである。文学のこのような「小ささ」は、どのような性格を持っているのだろうか。そのような「小さい」文学が翻訳される時、どのような障壁があり、翻訳者はどのようにして障壁を克服しているのだろうか。本書の出発点にあったのは、そのような問いである。
具体的に検討されるのは、ボヘミアにおけるチェコ語の言語文化である。19世紀初頭、ボヘミアでは、ドイツ語が、行政、教育、文化面での主たる言語であった。チェコ系住民は、チェコ語での表現の場を広げていくべき、様々な活動を展開する。というのも、チェコ語の文化資本は、ドイツ語のそれに比べると、圧倒的に小さいものだったからである。それゆえ、ヨゼフ・ユングマン (1773-1847) は、翻訳を通して語彙を増やし、辞書や文例集を編纂して、チェコ語の表現可能性を拡張したのである。
第一次世界大戦を経て独立国家となったチェコスロヴァキアでは、チェコ語とドイツ語の言論空間が交錯していた。その際、両言語の媒介者として活躍したのが、翻訳家パヴェル・アイスネル (1889-1958) であった。チェコ文学をドイツ語圏に紹介し、かつ、ドイツ文学をチェコの読者に紹介する際、彼が積極的に行ったのは、序文、解説、注などの様々なパラテクストを活用することである。ユダヤ系の出自を有するアイスネルはまさに翻訳に自らの居場所を見つけ出したかのように、カフカなど、数多くの翻訳を手がける。
20世紀後半、冷戦下のチェコにおいて、翻訳がまた別の機能を有することとなる。チェコ語の小説家ミラン・クンデラは、1975年以降フランスに移住し、チェコ語の原書を読む読書数が激減したことを痛感し、チェコ語原文と同等の価値をフランス語訳に認める。しかしながら、ビロード革命後に公刊されたチェコ語版では、フランス語訳にはない「著者あとがき」というパラテクストが付され、翻訳版とは異なる小説家の見解が提示されていた。
このように、本書は、文化資本、パラテクストという観点からボヘミアにおける翻訳を検討したものであり、複数言語に跨るチェコ文学史の一部を記述し、かつ、「小さい言語」特有の翻訳の諸問題を検討したものである。
(紹介文執筆者: 人文社会系研究科・文学部 教授 阿部 賢一 / 2024)
本の目次
第I部 ヨゼフ・ユングマン
第1章 十九世紀初頭のチェコ語
第2章 『言語芸術』
第3章 『アタラ』の翻訳
第4章 辞書
第5章 翻訳の機能
第II部 パウル・アイスナー/パヴェル・アイスネル
第1章 言語のはざまで
第2章 アンソロジー
第3章 「共生」に関する言説
第4章 ユダヤ性について
第5章 翻訳をめぐる言葉
第III部 ミラン・クンデラ
第1章 翻訳者クンデラ
第2章 翻訳されなかった作品
第3章 「小文学」を翻訳する
第4章 「真正版」という概念、あるいは小説の変容
第5章 翻訳される作品、あるいは「大いなる帰還」
参考文献
結びに
索引
関連情報
第76回読売文学賞 (評論・伝記賞) (読売新聞社 2025年2月1日)
https://store.kinokuniya.co.jp/event/1738732394/
著者インタビュー:
[読売文学賞の人びと]受賞者に聞く<2>「小さな言語」翻訳巡る葛藤…評論・伝記賞 「翻訳とパラテクスト ユングマン、アイスネル、クンデラ」 阿部賢一さん (本よみうり堂 2025年2月4日)
https://www.yomiuri.co.jp/culture/book/articles/20250203-OYT8T50177/
書評:
豊島美波 評 (『れにくさ : 現代文芸論研究室論集』第15号 p.148-152 2025年3月31日)
石川達夫 (専修大学) 評 (『スラヴ学論集』28巻p.105-115 2025年3月31日)
https://doi.org/10.69264/jsssll.28.0_105
鴻野わか菜 評「新刊紹介」 (表象文化論学会『REPRE』vol.52 2024年10月5日)
https://www.repre.org/repre/vol52/books/sole-author/1/
安永愛 評 (『図書新聞』3650号 2024年8月3日)
https://toshoshimbun.com/product__detail?item=1721891005104x498514336961789950
沼野充義 評「小言語が生き 発展した過程」 (『日本経済新聞』 2024年6月1日)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD0336C0T00C24A5000000/
鴻巣友季子 評「今週の本棚」 (『毎日新聞』 2024年5月11日)
https://allreviews.jp/review/6860
https://mainichi.jp/articles/20240511/ddm/015/070/029000c



 書籍検索
書籍検索