大河ドラマ「いだてん」に登場した、日本のオリンピックを支えた東京大学の人々|オリパラと東大。
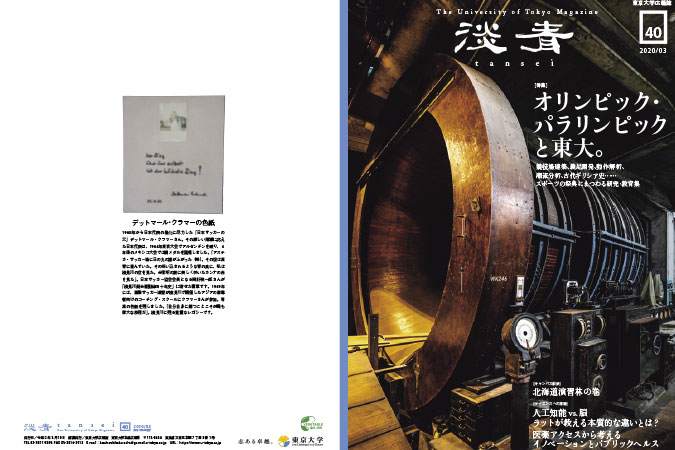
~スポーツの祭典にまつわる研究・教育とレガシー
半世紀超の時を経て再び東京で行われるオリンピック・パラリンピックには、ホームを同じくする東京大学も少なからず関わっています。世界のスポーツ祭典における東京大学の貢献を知れば、オリパラのロゴの青はしだいに淡青色に見えてくる!?
日本のオリンピックを支えた東京大学の人々
ストックホルム大会から東京大会までの52年間を、金栗四三、田畑政治という2人の主人公をリレーする形式で描いたNHK大河ドラマ「いだてん~東京オリムピック噺」。ここには東大に縁のある人々も多数描かれていました。観た人も観なかった人も、本人を演じた俳優さんの顔を想像しながらその功績に触れるのが「最高じゃんね~!」、です。
※敬称略
嘉納治五郎

文学部を卒業後、第一高等中学校(旧制一高)の校長などを経て東京高等師範学校(現・筑波大学)の校長を務めていた嘉納は、「柔道」を確立して世界に広めた功績を知ったクーベルタン男爵の求めに応じ、アジア初のIOC委員に。平和を標榜する大会の精神に惹かれ、日本の初参加に向けて奮闘した努力はストックホルム大会で結実。2人の陸上選手が出場した日本は国際スポーツ界に仲間入りしました。次は日本開催をと夢見た嘉納は神宮外苑競技場を建設。欧米だけで開かれてきた大会を極東で行う意義を精力的に説いてまわり、1936年のIOC総会で東京開催決定を手繰り寄せました。嘉納の死を機に1940年東京大会は幻となりますが、志は後輩たちに引き継がれました。
岸清一

法科大学時代は漕艇選手として活躍し、「東京帝国大学漕艇部五十年史」に第三回競漕大会優勝法科大学選手として写真が載る岸は、卒業後は国際的弁護士として活動。嘉納が創設した大日本体育協会(現・日本スポーツ協会)に当初から関わり、主に協会の財政面を整備して、理想に傾きがちな嘉納を現実的に支えました。1921年には第2代会長に就任。1924年には日本人2人目のIOC委員となり、1932年のIOC総会で1940年東京大会の招致計画を発表しました。1933年に亡くなりましたが、岸の寄附金をもとに建てられた岸記念体育会館は日本スポーツ界の総本山に。国立競技場の隣に移転したビルの前には、嘉納やクーベルタンとともに岸の銅像も設置されています。
武田千代三郎

漕艇部五十年史の記念写真に岸とともに写っている武田は、法科大学在学中にフレデリック・ストレンジの薫陶を受けてスポーツに親しみました。秋田県知事、青森県知事などを経て、1913年に大日本体育協会副会長となり、岸とともに協会の財政立て直しに貢献。1917年には「駅伝」の名付け親となっています。
牛塚虎太郎

法科大学を卒業後、岩手県知事、群馬県知事などを経て1933年に第15代東京市長となり、先代の永田秀次郎市長が進めた招致活動を継承。東京開催に反対するバイエ・ラトゥールIOC会長が来日した際に熱心に歓待し、開催決定の報を聞いて「多年の宿望を達成した」と語ったことを当時の朝日新聞が伝えています。
杉村陽太郎

法科大学を卒業後、外務省に入省。駐フランス大使館勤務、国際連盟事務次長などを経て1933年にIOC委員に。当時、1940年大会に向けた東京のライバルはイタリア。同じ柔道家として尊敬する嘉納の願いを受けた杉村はムッソリーニ首相に直談判し、副島道正が病を押して辞退の約束を得る機会を演出しました。
津島壽一

法科大学を卒業後、大蔵省に入省。戦後の外債処理に尽力し、2度の大蔵大臣を経験。東龍太郎の後の日本体育協会会長となり、東京オリンピック組織委員会会長に就任しました。しかし、1962年アジア競技大会の際の対応に批判が集まり、責任を取る形で辞任。後任は工科大学出身の安川第五郎に託されました。
東龍太郎

医者一家に生まれ、医科大学在学中は漕艇部で活躍した「東龍さん」。卒業後は母校で教授を務め、スポーツ医学の草分け的存在となりました。助教授だった1928年には東京帝国大学運動会の設立許可願を後に総長となる長與又郎教授とともに提出し、1936年には「運動会報」に漕艇部50年記念祝賀会の原稿を執筆しています。その活動は学内にとどまらず、1947年には日本体育協会会長に就任。1950年からはIOC委員も長らく務め、オリンピック誘致に尽力しました。1953年には茨城大学学長に就任。1959年に東京開催が決まると、オリンピックの成功に燃える田畑の熱意に押される形で東京都知事に。2期8年を務め、アジア初のオリンピックを成功に導きました。
田畑政治

法学部を卒業後、朝日新聞の政治部記者となった田畑。二・二六事件の記事などで実力を示す一方、注力したのは水泳指導者としての活動でした。浜松生まれで少年時代から水泳に親しんだものの、胃腸炎を患い、医師から言われて選手を諦めた過去があったのです。松沢一鶴とともに水泳の連盟を立ち上げ、アムステルダム大会に選手を派遣。ロサンゼルス大会では競泳の総監督として現地を指揮し、水泳ニッポンの名を轟かせるとともに五輪の素晴らしさを体感しました。ヘルシンキ、メルボルンと日本選手団の団長を務めた後、東京大会の組織委員会事務総長として現場を牽引。不本意な辞任を余儀なくされても大会のために尽くした「ミスター・オリンピック」です。
丹下健三

工学部を卒業後、母校の教授、建築家として活躍。1964東京大会の競泳とバスケットボールの会場として設計した国立代々木競技場で国内外に大きなインパクトを与え、大会後にはIOCから特別功労者として表彰されました。その作風の一端は本郷キャンパスの本部棟と第二本部棟でも確認できます。
辰野保
建築家の辰野金吾を父に持つ辰野。法学部時代は陸上部で活躍し、砲丸投げとハンマー投げで当時の日本記録を樹立しました。卒業後は弁護士として活動。1920アントワープ大会では監督として選手団に同行。世界の競技力の高さを実感し、海外事情を研究する必要性を訴えました。
松沢一鶴
理学部時代に水泳選手として活躍し、ロサンゼルス大会、ベルリン大会では監督を務めた松沢。後には式典演出でも優れた才能を発揮し、1964東京大会の閉会式では選手入場を各国が入り乱れて行う新方式を採用。この「東京式」は好評となり、その後の定番となりました。
平沢和重
法学部を卒業後、外務省に入省し、外交官として米国で活躍。横浜行きの船内で嘉納と出会い、その最期を看取りました。後にメディアに転じ、NHKの解説委員としてTVの顔に。当初は招致に反対でしたが、東や岩田の依頼を受けてIOC総会で演説し東京開催の流れを決定づけました。
岩田幸彰
法学部時代はヨット部で活躍。自身のオリンピック出場は叶いませんでしたが、メルボルン大会にはヨット競技視察員として参加。1957年に日本オリンピック委員会に加わり、田畑の右腕として東京大会に貢献。IOC総会で招致演説を行うなど、1972札幌大会招致でも活躍しました。
※岸・武田・東の写真は「東京帝国大学漕艇部五十年史」、杉村・田畑の写真は卒業アルバムより(ともに文書館所蔵)
「いだてん」には登場しない、オリンピックを支えた東大人
オリンピックを支えた東大人はもちろん「いだてん」で描かれた人だけではありません。そのほんの一端を紹介します。
●高山英華/工学部卒。工学部教授。近代都市計画学のパイオニア。学生時代はア式蹴球部で活躍し、ベルリン大会代表に選ばれながら盲腸で辞退した経験も。1964東京大会では、オリンピック施設特別委員会の副委員長として駒沢会場案を立案。
●加藤橘夫/文学部卒。教養学部教授。科学的トレーニングを導入する意義を説き、日本体育協会にスポーツ科学委員会を設置。1964東京大会に際して開催した「世界スポーツ科学会議」はその後のオリンピックの定例に。
●黒田善雄/医学部卒。教養学部教授。1964東京大会に向けて創設された日本体育協会スポーツ科学研究所の所長に就任。後には日本アンチ・ドーピング機構の会長となり、IOCクーベルタン賞を受賞。
●加藤隆/高山英華研究室の大学院生として学びながら組織委員会事務局の臨時職員として施設計画を担当。当時の経験をもとに『伝説:オリンピック東京大会施設づくり裏物語』(東京建築塾)を2018年に上梓。漕艇部OB。






