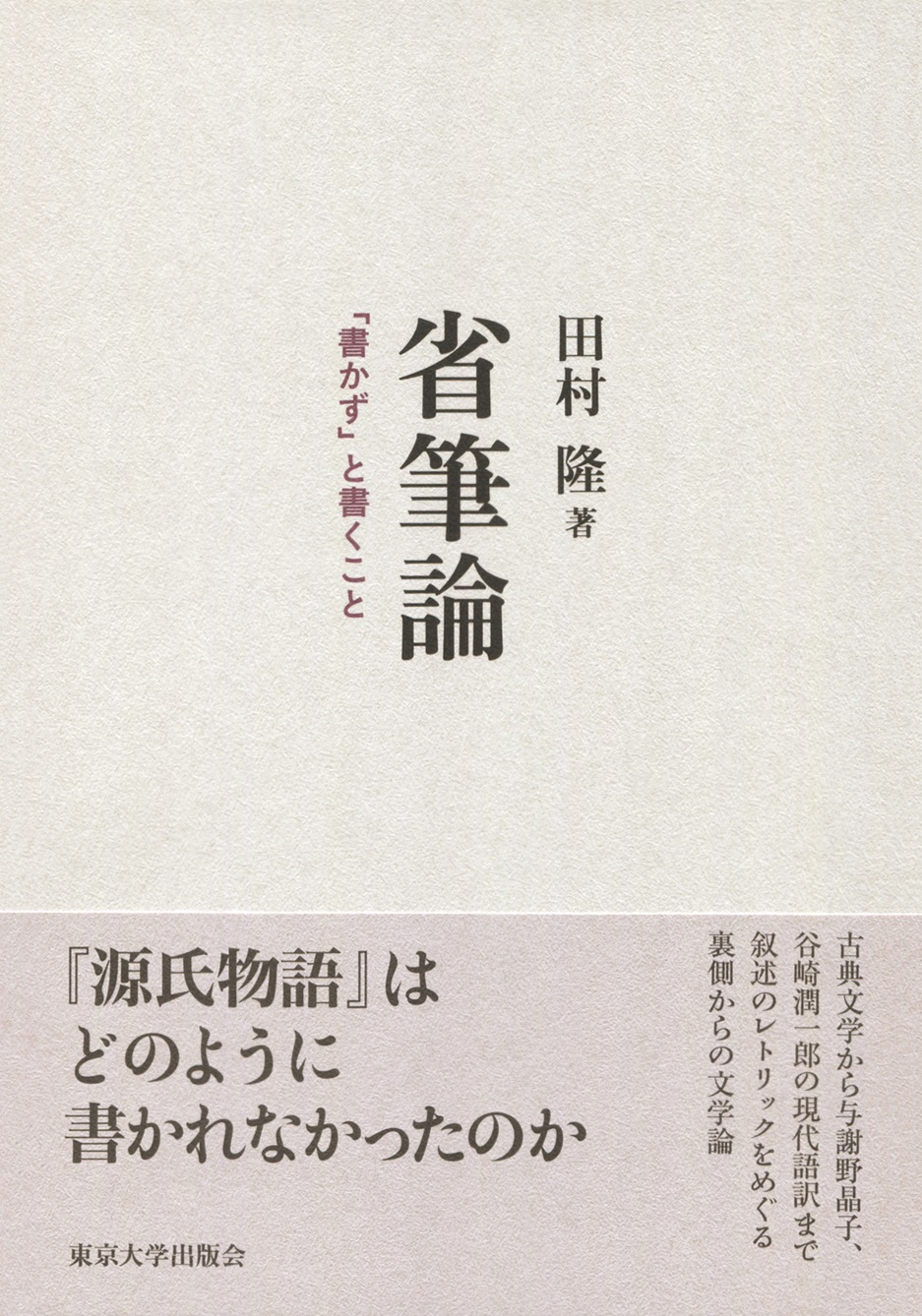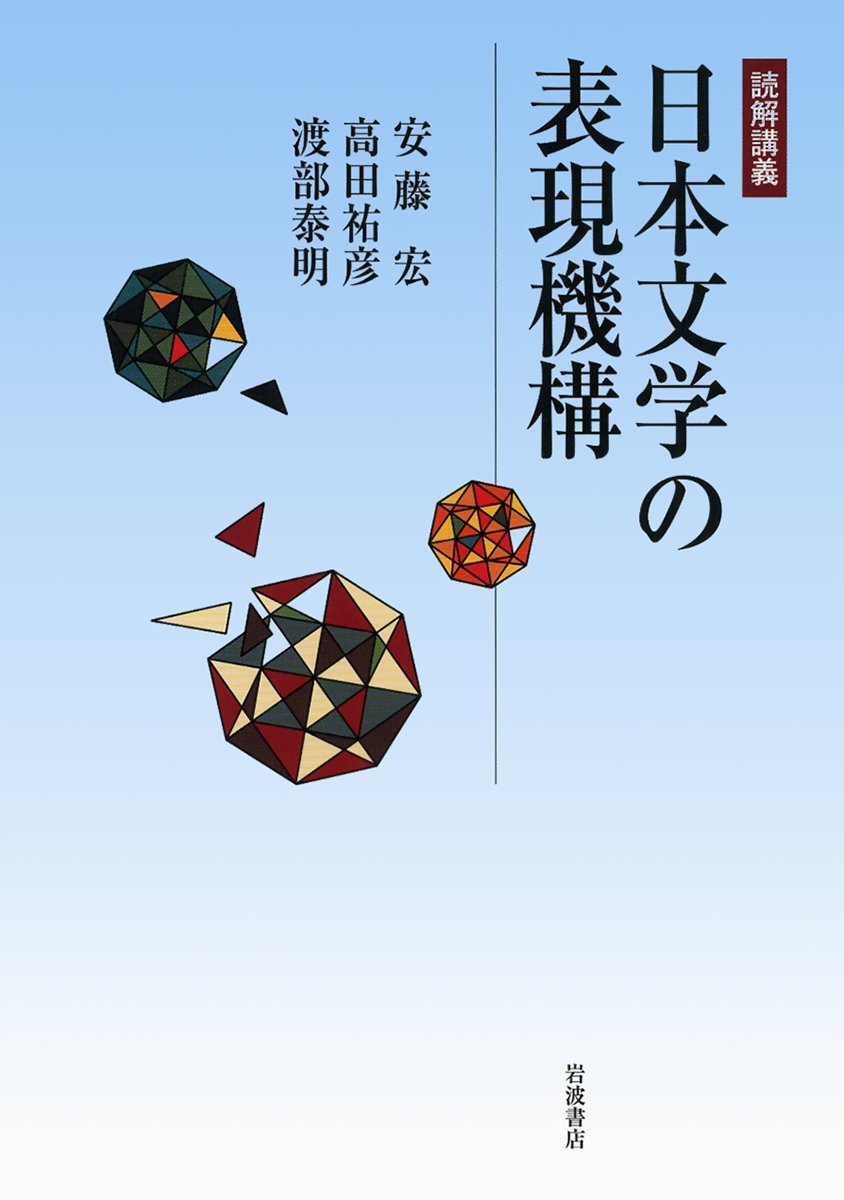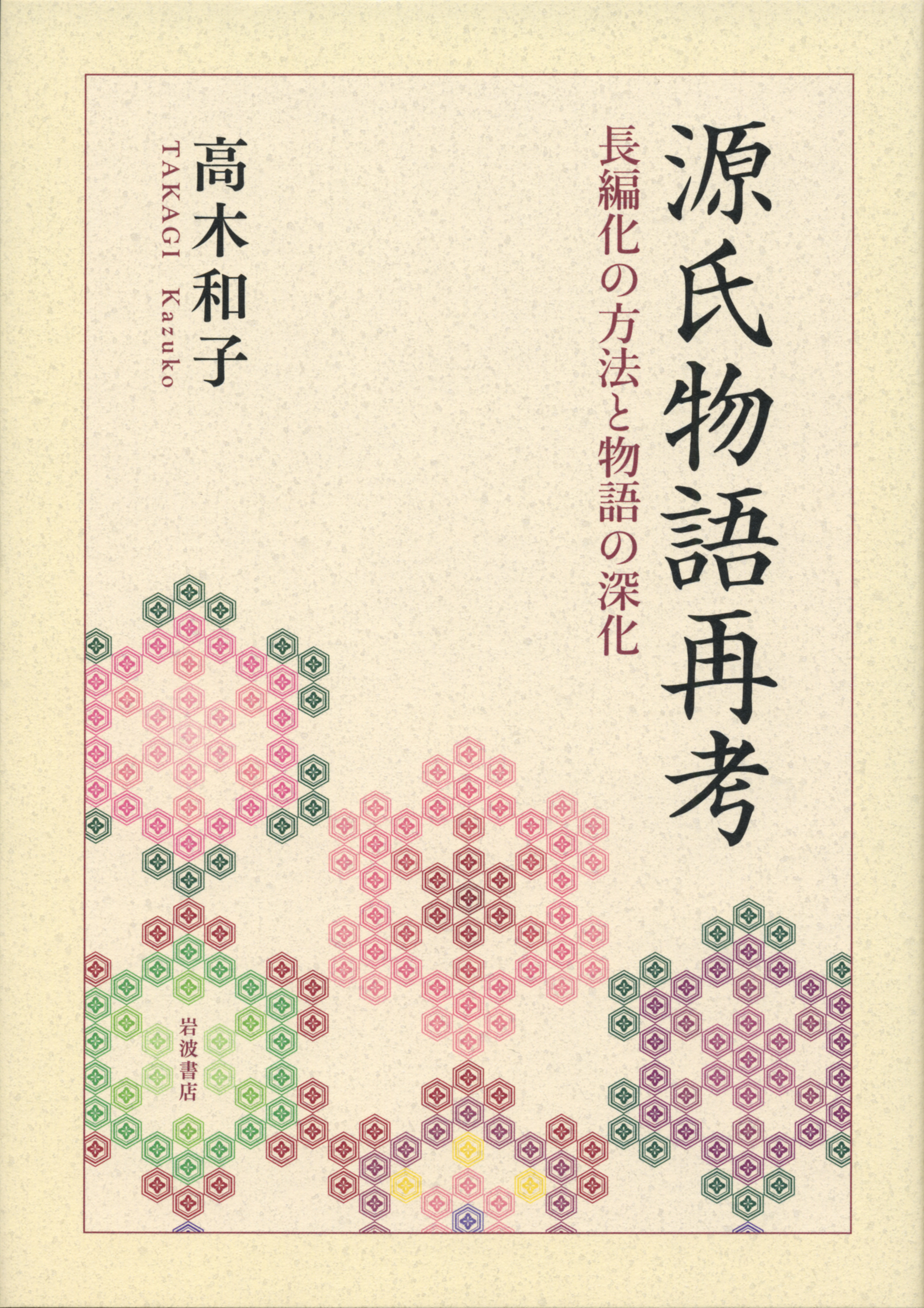本書は、書かないということの研究である。『源氏物語』を中心に、「省筆」(しょうひつ) について論じた。
私達は文章を書くとき、書くことと書かないことを選択している。読者として読む文章もまた、作者によるその選択を経たものである。本書で注目したのは、書かれていないという事態にも二種類あって、ただ書かれていない場合と、書かれていないことがわかるように書かれている場合がある、という点である。
省略を明示することは書物の外でも行われていて、たとえば卒業証書や学位記の読み上げでしばしば「以下同文」という言葉が聞かれるが、その「以下同文」には二人目以降の全文読み上げを省略することと、実際はそこにきちんと文面があることの表明という二つの意図が含まれている。
『源氏物語』には「書かれなかった事」が多い。藤壺との一度目の密通も「宮もあさましかりしを思し出づるだに」と朧気に記されるのみだし、光源氏の死も匂宮巻冒頭で「光隠れたまひにし後」とあることで示される。浮舟のその後も描かれることなく物語は終わる。
そして、『源氏物語』にも書かないことを宣言する例が散見される。それが副題に掲げた「「書かず」と書くこと」で、たとえば、若菜上巻に「院の御前に、浅香の懸盤に御鉢など、昔にかはりてまゐるを、人々涙おし拭ひたまふ。あはれなる筋のことどもあれど、うるさければ書かず。」という一節がある。朱雀院の出家をめぐる「あはれなる筋のことども」が、「うるさければ書かず」の言辞のもとに退けられる。ただ書かないのではなく、いわば「書かず」と書いているのである。
一、二例であれば気にもなるまいが、物語中、実に64例に及ぶ省筆の辞を目にし、それらは一体なぜ必要なのかという素朴な問いが生じた。省筆の断り書きは、筆を省くことのみが役割であるなら実は無用のものである。この場面で「書かれなかった事」は無論「無かった事」ではない。そう考えれば、「うるさければ書かず」とは端的に言えば、「あった」事を顕在化させる書き方と言える。
それゆえに、わざわざ書き記す省筆の表現には種々の工夫が凝らされた。「いますこし問はず語りもせまほしけれど、いと頭いたううるさくものうければなむ、いままたもついであらむをりに、思ひ出でてなむ聞こゆべきとぞ」(蓬生) という例などは、省筆の理由を頭痛としたものである。
このような事例を集めて考えながら、『源氏物語』はどのように“書かれなかった”のかという問題に取り組んだ。省筆を叙法として捉え、その役割や効果を考察することで、物語の舞台裏を探ってみたいという関心から本書は成っている。
(紹介文執筆者: 総合文化研究科・教養学部 准教授 田村 隆 / 2017)
本の目次
「書かず」と書くこと
第I部
省筆論
夕顔以前の省筆
貫之が諫め
卑下の叙法
「ようなさにとどめつ」考
「思ひやるべし」考
与謝野晶子訳『紫式部日記』私見
省筆の訳出
「御返りなし」考
第II部
施錠考
村雨の軒端
硯瓶の水
いとやむごとなききはにはあらぬが
「涙」の表記
玉葛の旧跡
関連情報
『省筆論』田村隆 著 / 読売新聞社編集委員 尾崎真理子 評 (読売新聞朝刊 2017年10月8日)
http://www.yomiuri.co.jp/life/book/review/20171010-OYT8T50050.html
田村隆『省筆論』東京大学出版会 / 中川照将 評 (「図書新聞」第3331号 2017年12月16日)
(会員記事)
http://toshoshimbun.jp/books_newspaper/week_description.php?shinbunno=3331&syosekino=11005



 書籍検索
書籍検索