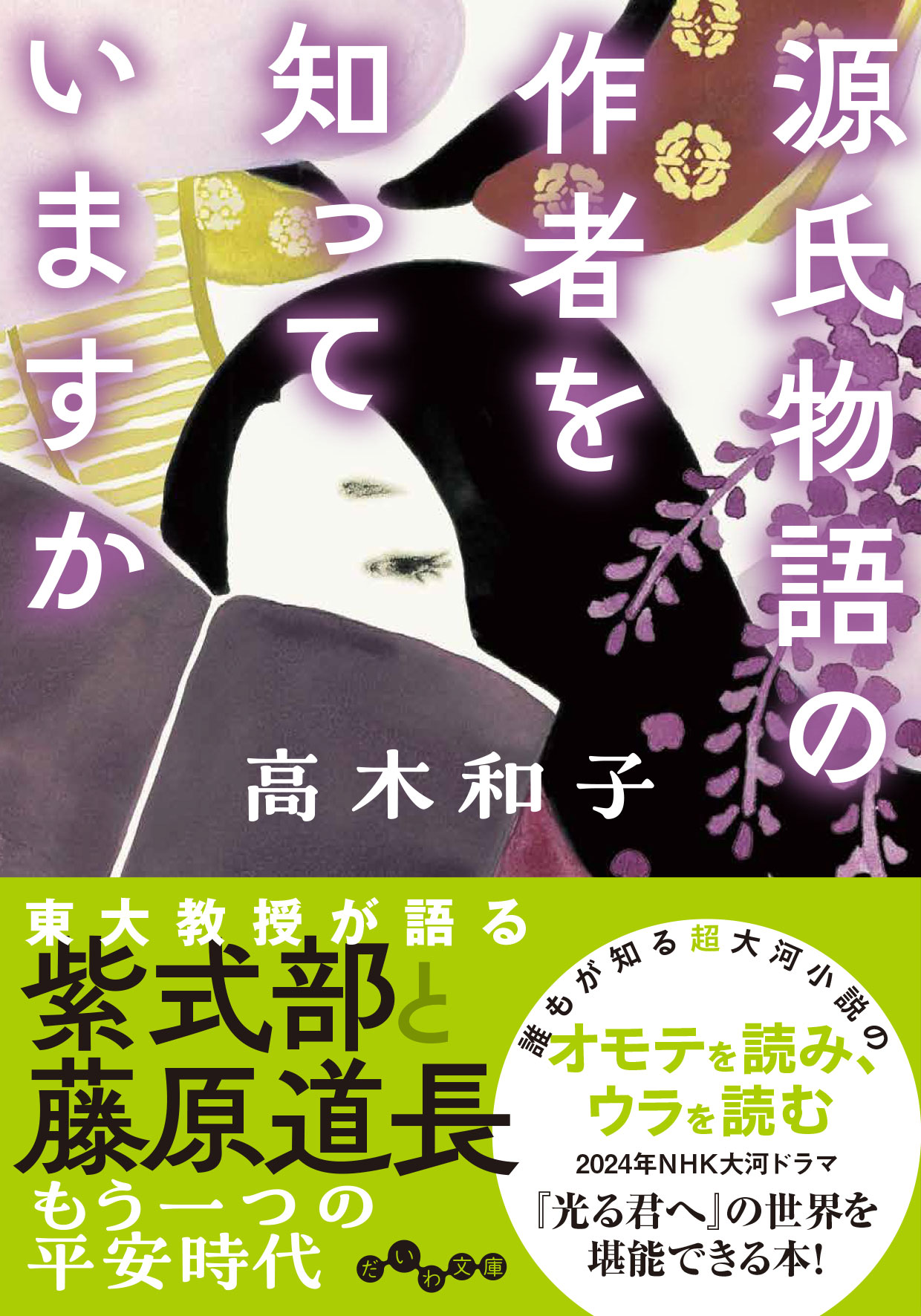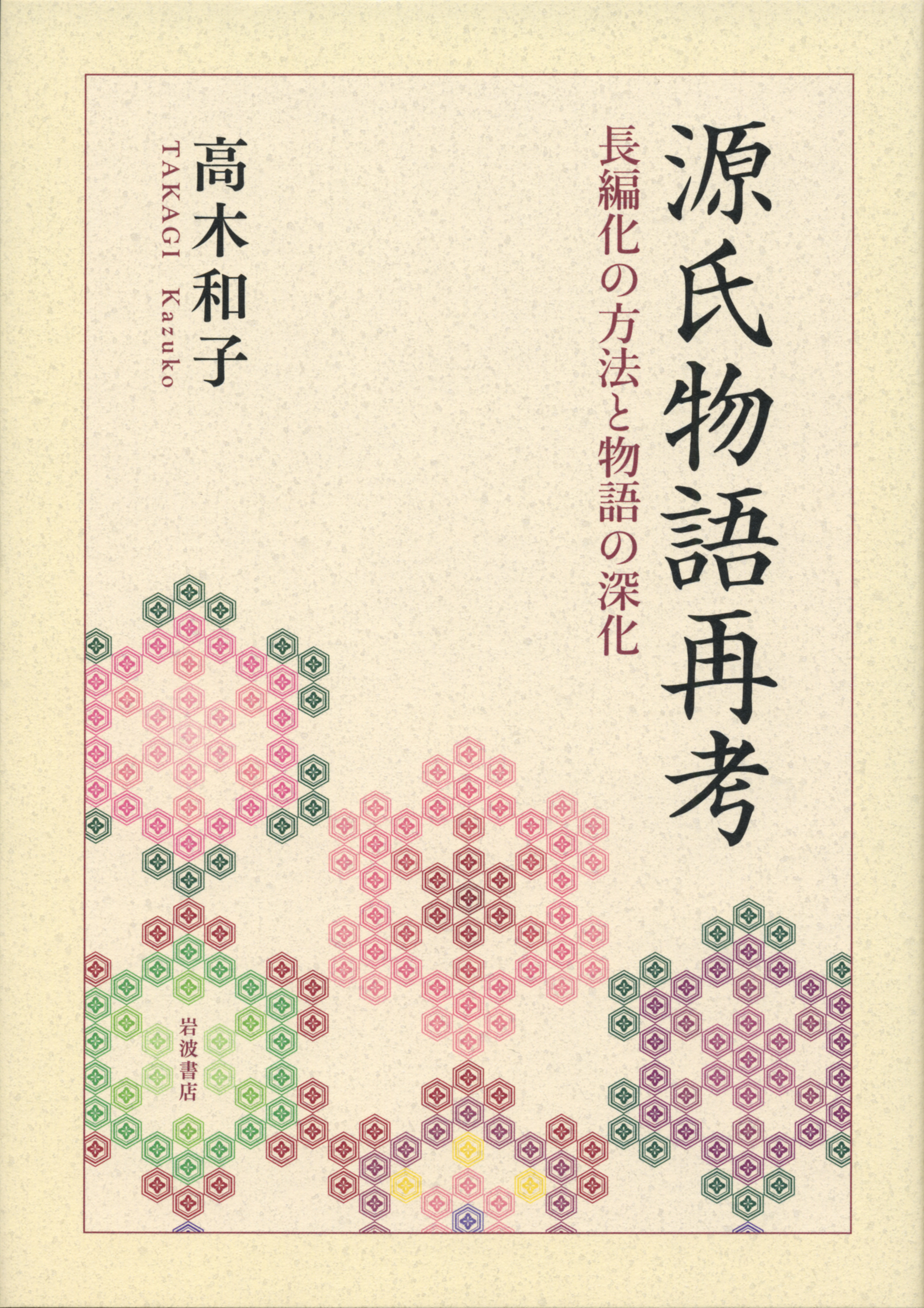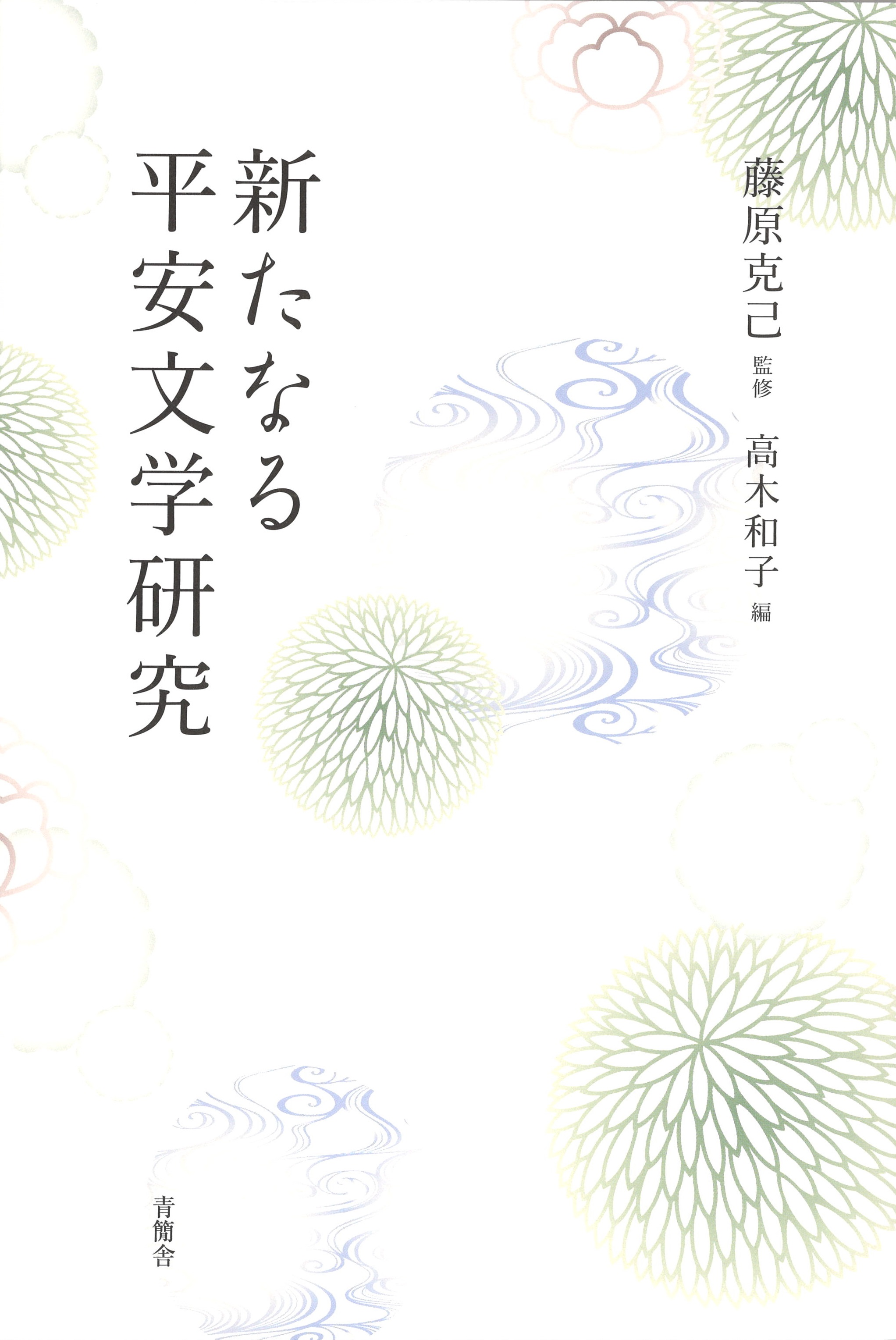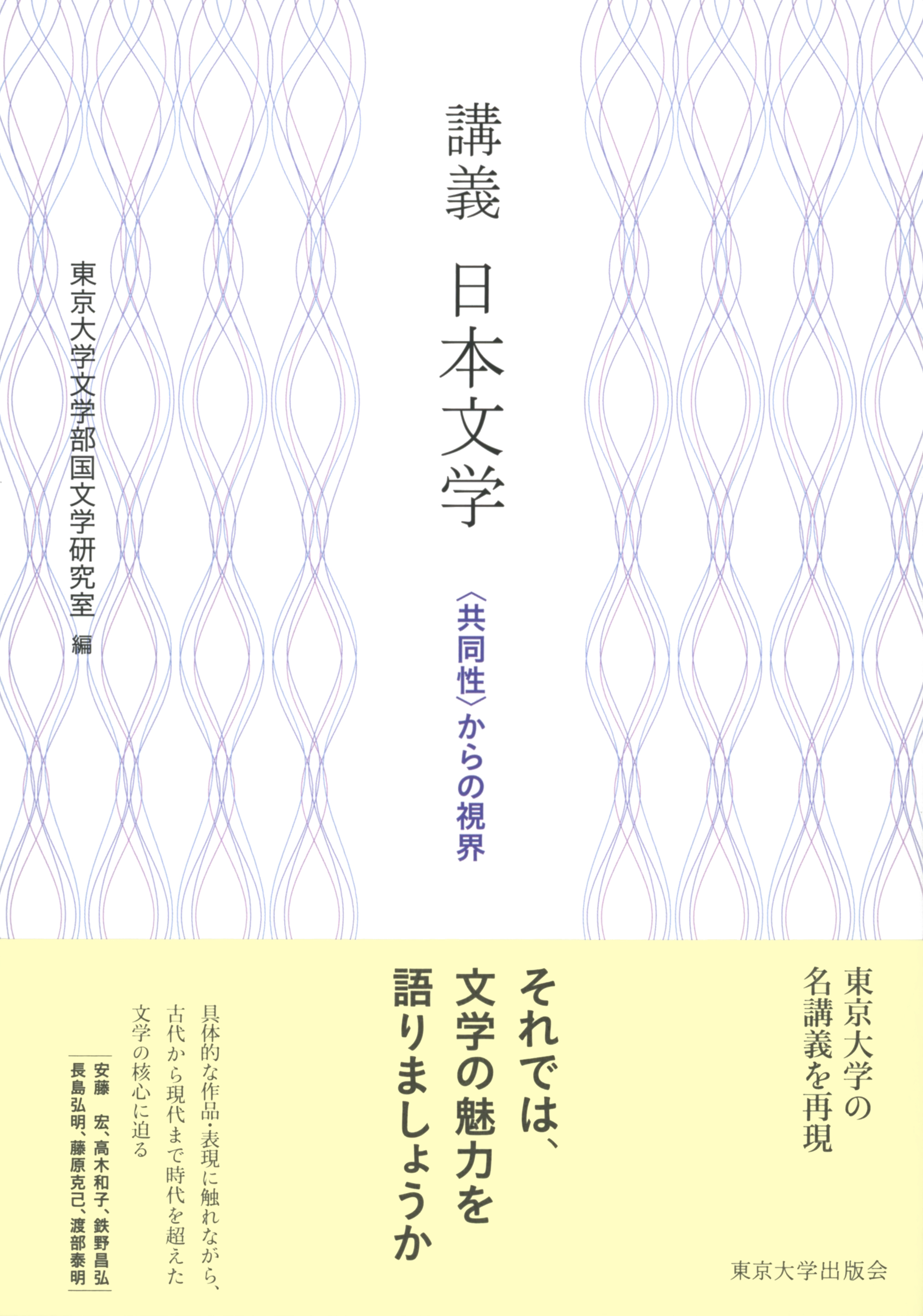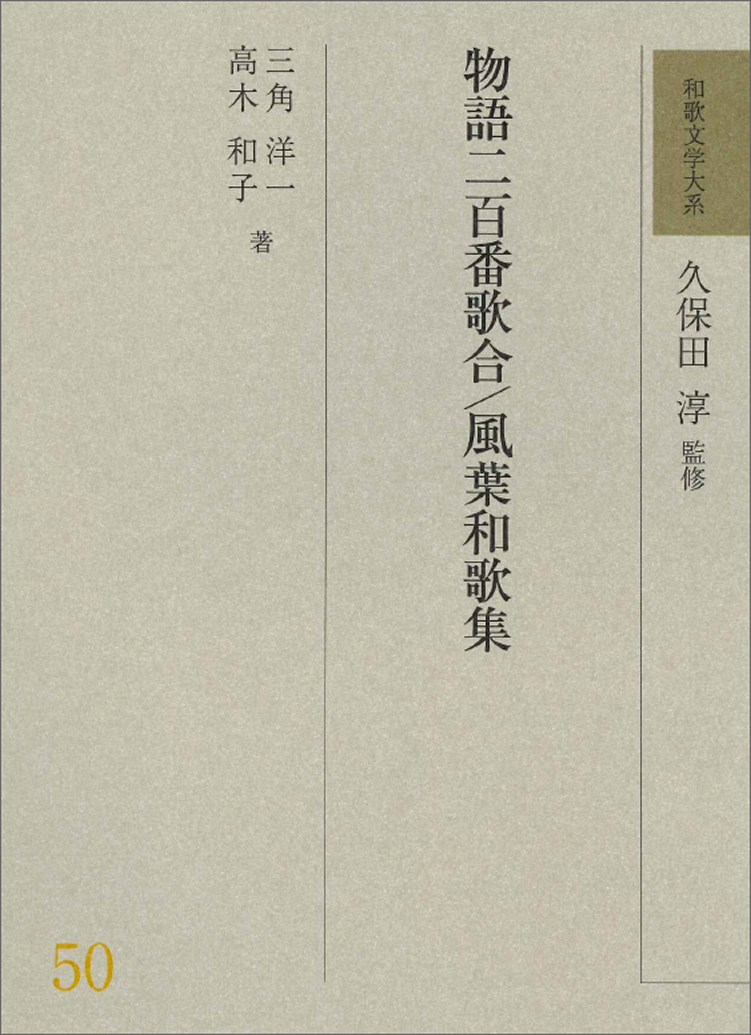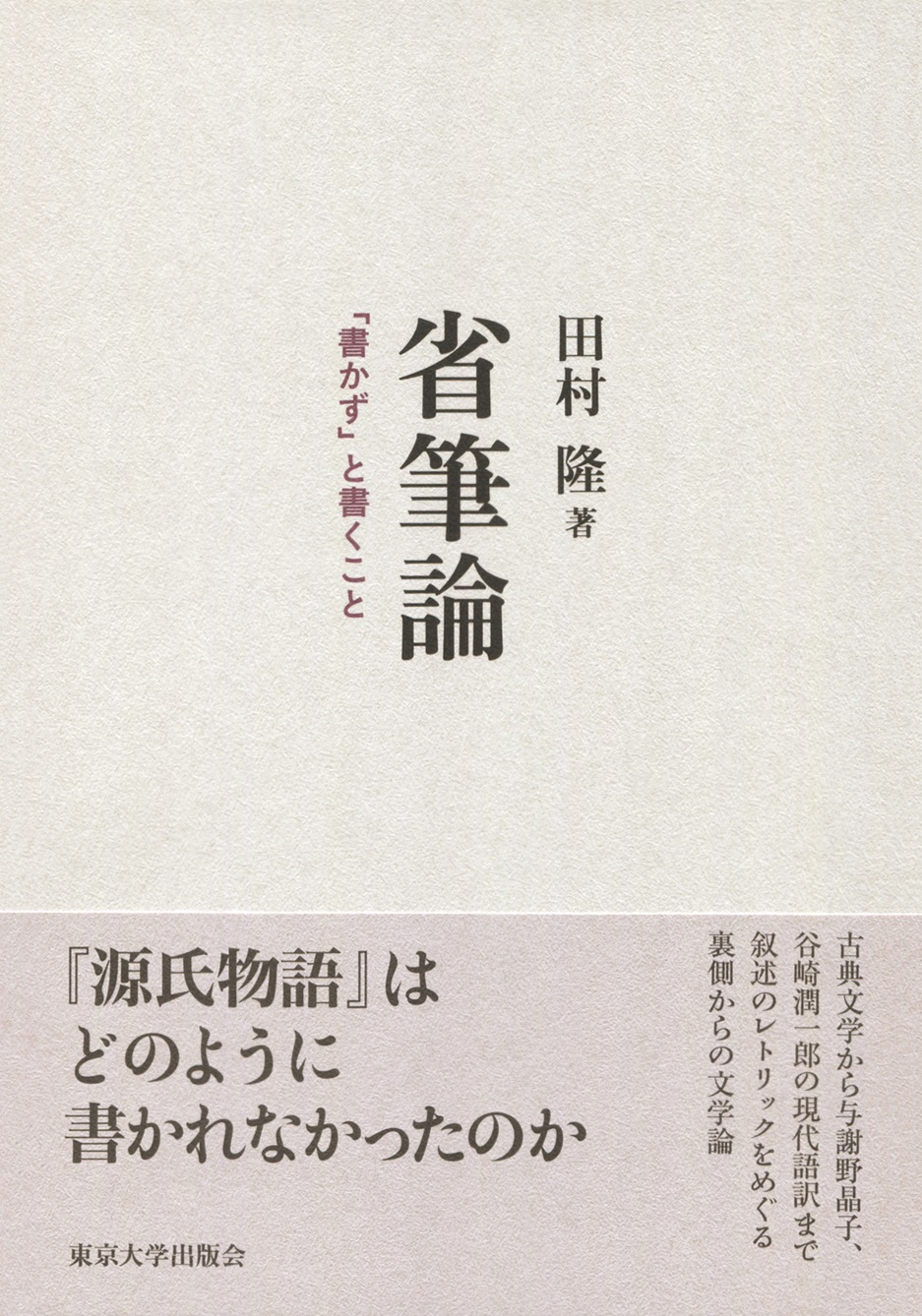本書は、『源氏物語』についての入門書であり、概説書である。『源氏物語』は、その成立間もなくから和歌の詠作のために研究され、後の物語の規範とされてきた。物語全体は長大であるため、ダイジェスト本や梗概本も早くから作られ、より簡便に作中世界を理解する機運も生まれた。作中の名場面は、絵画や工芸、能や歌舞伎等の素材になるなど、今日に至るまでの約千年の間、多様な次元で研究され享受され愛好されてきた。その背景には、権力の頂点を目指す後代の為政者たちが、光源氏の栄達にあやかろうと、『源氏物語』の継承に参与した事情もある。
二〇世紀初頭、イギリスのブルームズベリー・グループに関係の深いアーサー・ウェーリーの英訳によって、世界に紹介された。十一世紀初頭の日本で、これほど繊細で卓越した風景描写と心理描写に満ち溢れた近代的な長編が、しかも女性によって書かれたことが驚嘆され、プルーストの『失われた時を求めて』と比較されるなど、日本を代表する文学として世界的な評価を得た。
『源氏物語』は、骨格としては光源氏の恋愛遍歴の物語の体裁だが、より多面的に、人間社会の普遍的な問題を網羅的に取り込んだ、重厚な物語である。恋の脈絡はもとより、親子、主従、友情、闘争、老いなど、多様な人間関係や人生の局面における心の機微に分け入り、政治、歴史、社会といった多岐にわたる関心に応える物語となっている。きわめて洗練された美文と和歌によって書かれているために、いささか難解ながらも含蓄に富んだ豊穣な世界である。
今日も、『源氏物語』についての研究論文は常時、年間数百本に及び、日本文学研究の中でも突出した研究業績が創出される巨大研究分野である。高校や大学等での学習や研究にとどまらず、一般社会においても、教養としての『源氏物語』への関心は尽きることがなく、全巻講読に挑戦する公開講座や読書会の場は、各地で多数開催されている。
入門書や概説書の類いもすでに数多く刊行されている中で、本書は、物語の進展や表現に即して、丹念に五十四帖の内部世界を辿るところに特徴がある。単に筋立てを辿って紹介するだけでなく、要所要所で、研究上通説化している論点をふんだんに盛り込み、また時には筆者自身の独自な見解を織り交ぜながら、一般読者にも理解できるように心がけた。『源氏物語』を新たに知りたい人、長年講読を続けている愛読者、研究に関心のある大学生や大学院生等、それぞれにとって何らかの刺激になるはずである。
新書の一冊としてはやや情報量が多く、最初から最後までを読了するのは、少し苦労するかもしれない。好きな巻、好きなエピソードのある箇所から読み始めてもよいし、いま関心のある問題を調べるためのいわば事典の代わりにしてもよい。いかようにでも活用していただければ、まことに幸いである。
(紹介文執筆者: 人文社会系研究科・文学部 教授 高木 和子 / 2022)
本の目次
I 誕生から青春
一 両親の悲恋と美しき若君――桐壺 (きりつぼ) 巻
二 色好みの主人公――帚木 (ははきぎ)・空蟬 (うつせみ)・夕顔 (ゆうがお )巻
三 憧れの人とゆかりの少女――若紫 (わかむらさき)・末摘花 (すえつむはな) 巻
四 不義の子の誕生――紅葉賀 (もみじのが)・花宴 (はなのえん) 巻
II 試練と復帰
一 御代替わりの後――葵 (あおい)・賢木 (さかき)・花散里 (はなちるさと) 巻
二 不遇の時代――須磨 (すま)・明石 (あかし) 巻
三 待つ者と離反する者――澪標 (みおつくし)・蓬生 (よもぎう)・関屋 (せきや) 巻
四 権勢基盤の確立――絵合 (えあわせ)・松風 (まつかぜ)・薄雲 (うすぐも)・朝顔 (あさがお) 巻
III 栄華の達成
一 幼馴染の恋――少女 (おとめ) 巻
二 新たなる女主人公――玉鬘 (たまかずら)・初音 (はつね)・胡蝶 (こちょう) 巻
三 翻弄される人々――蛍 (ほたる)・常夏 (とこなつ)・篝火 (かがりび) 巻
四 玉鬘との別れ――野分 (のわき)・行幸 (みゆき)・藤袴 (ふじばかま)・真木柱 (まきばしら) 巻
五 六条院の栄華――梅枝 (うめがえ)・藤裏葉 (ふじのうらば) 巻
IV 憂愁の晩年
一 若い妻の出現――若菜上 (わかなのじょう)・若菜下 (わかなのげ) 巻
二 柏木の煩悶と死――柏木 (かしわぎ)・横笛 (よこぶえ)・鈴虫 (すずむし) 巻
三 まめ人の恋の悲喜劇――夕霧 (ゆうぎり) 巻
四 紫上の死と哀傷――御法 (みのり)・幻 (まぼろし) 巻
V 次世代の人々
一 光源氏没後の人々――匂兵部卿 (におうひょうぶきょう)・紅梅 (こうばい)・竹河 (たけかわ) 巻
二 八宮の姫君たち――橋姫 (はしひめ)・椎本 (しいがもと)・総角 (あげまき) 巻
三 中の君へ、そして浮舟へ――早蕨 (さわらび)・宿木 (やどりぎ)・東屋 (あずまや) 巻
四 薫と匂宮、揺れる浮舟――浮舟 (うきふね)・蜻蛉 (かげろう) 巻
五 浮舟の出家――手習 (てならい)・夢浮橋 (ゆめのうきはし) 巻
おわりに
参考文献
主要人物紹介
系 図
年 立
関連情報
常設講座「源氏物語を読む 原文をゆっくり、じっくり、とっくり」 (毎日文化センター 第二火曜 [開催中])
https://www.maibun.co.jp/wp/archives/course/35986
「源氏物語を読む」(講師: 高木和子) (オンライン [主催: 毎日文化センター] 2021年10月24日)
https://mainichi.jp/articles/20211012/ddl/k27/040/365000c
連続講座「世界の物語を旅する」第2回「源氏物語を読む」(講師: 高木和子) (オンライン [主催: 一般財団法人出版文化産業振興財団] 2021年7月10日)
https://www.jpic.or.jp/topics/2021/05/26/145201.html
関連記事:
高木和子「瀬戸内寂聴訳『源氏物語』の生成」 (『ユリイカ』2022年3月臨時増刊号 総特集「瀬戸内寂聴」)
http://www.seidosha.co.jp/book/index.php?id=3657
特集「源氏物語を読む」(高木和子・鈴木宏子編集) 高木和子「類話の累積に見る源氏物語の成立と方法」 (『日本文学研究ジャーナル』第17号 2021年3月)
http://www.kotenlibrary.com/journal/
シンポジウム:
《源氏物語を〈読む〉――研究の現在》高木和子「源氏物語における〈無常〉について」 (『中古文学』第110号 2022年11月30日)
https://chukobungakukai.org/backnumber.html



 書籍検索
書籍検索


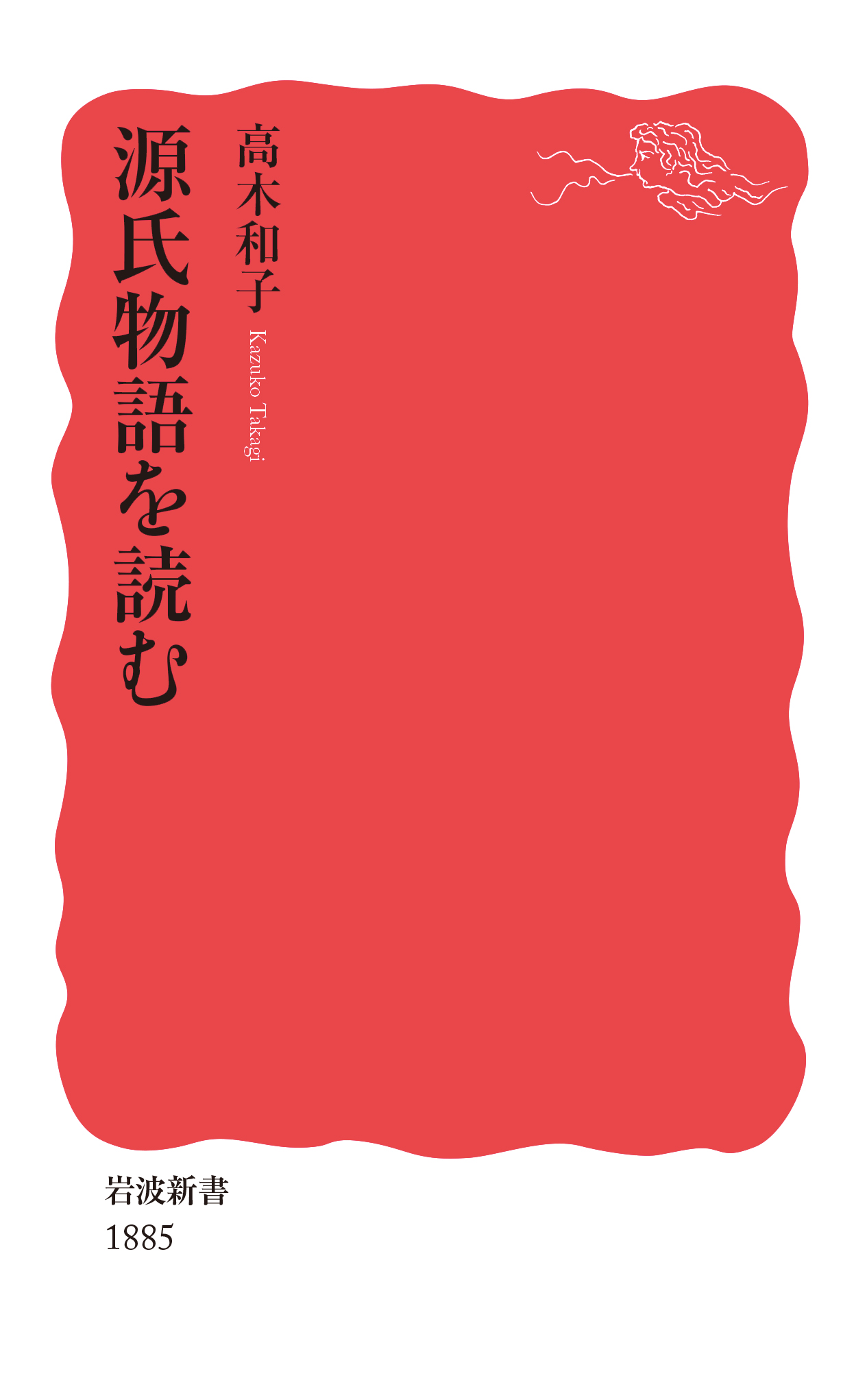
 eBook
eBook