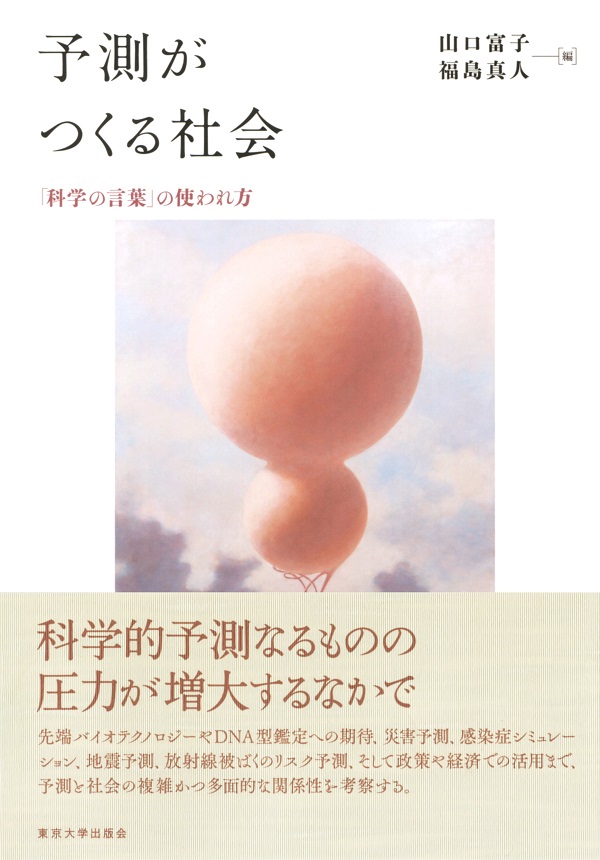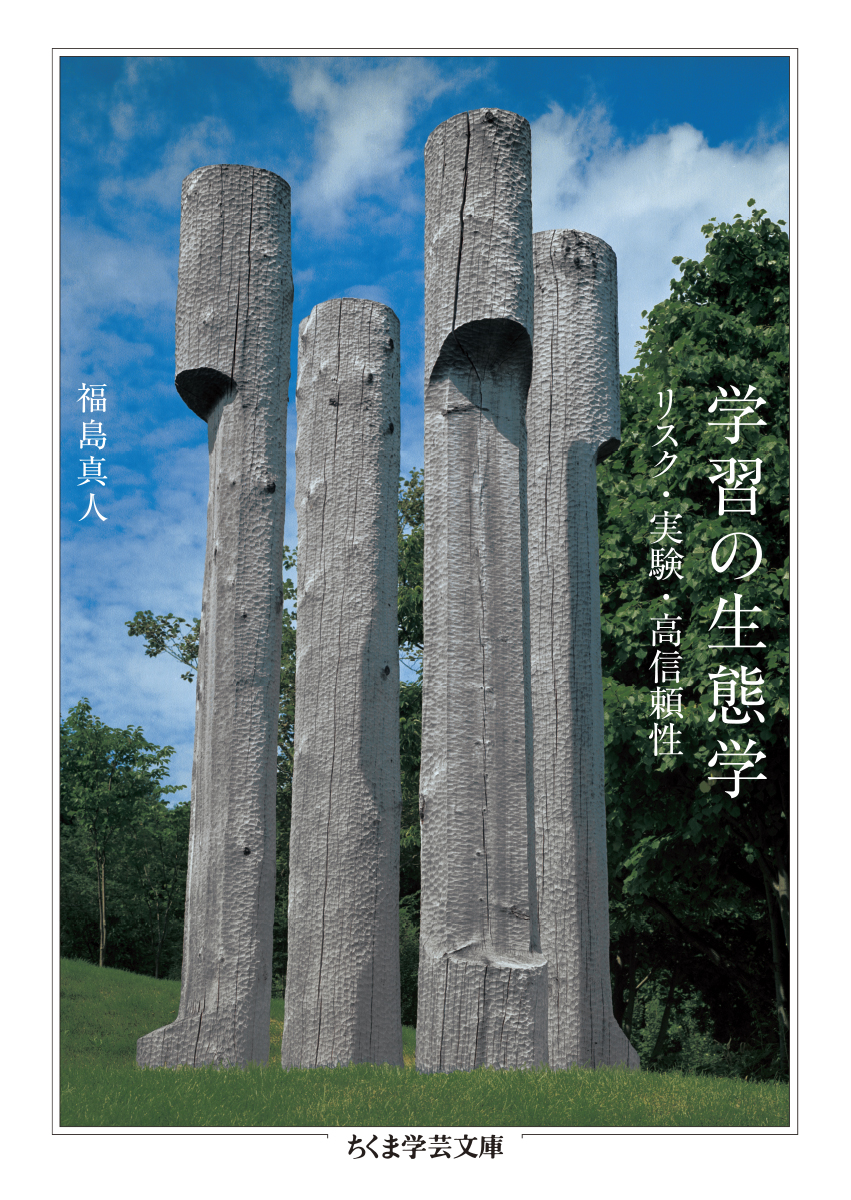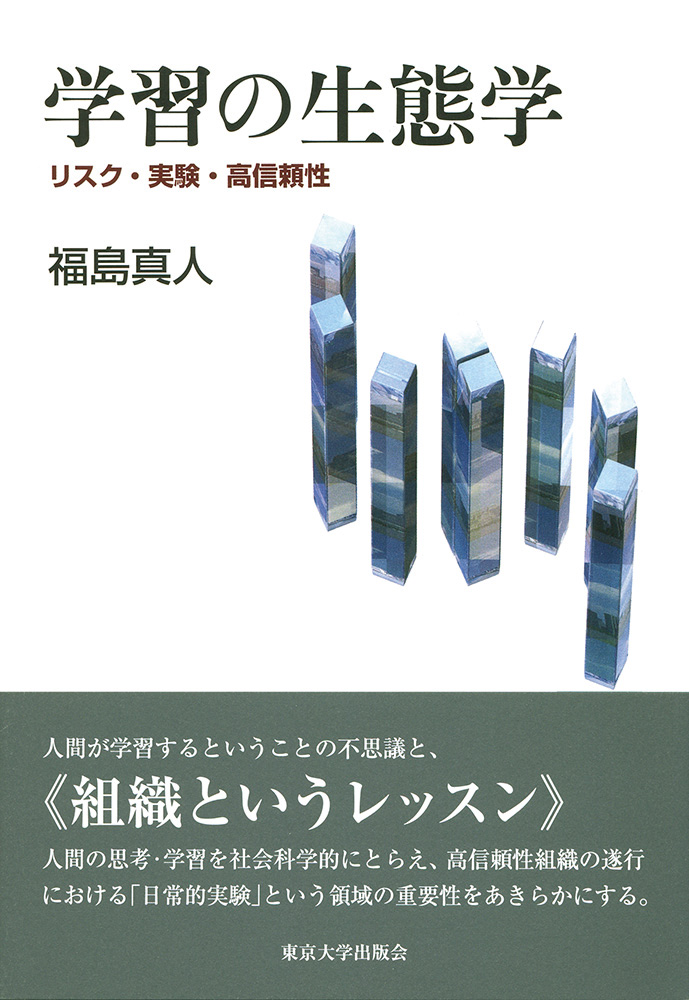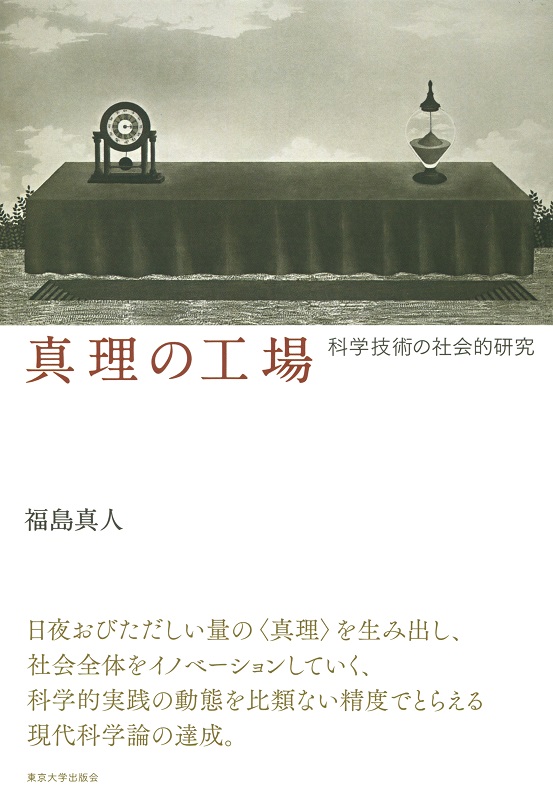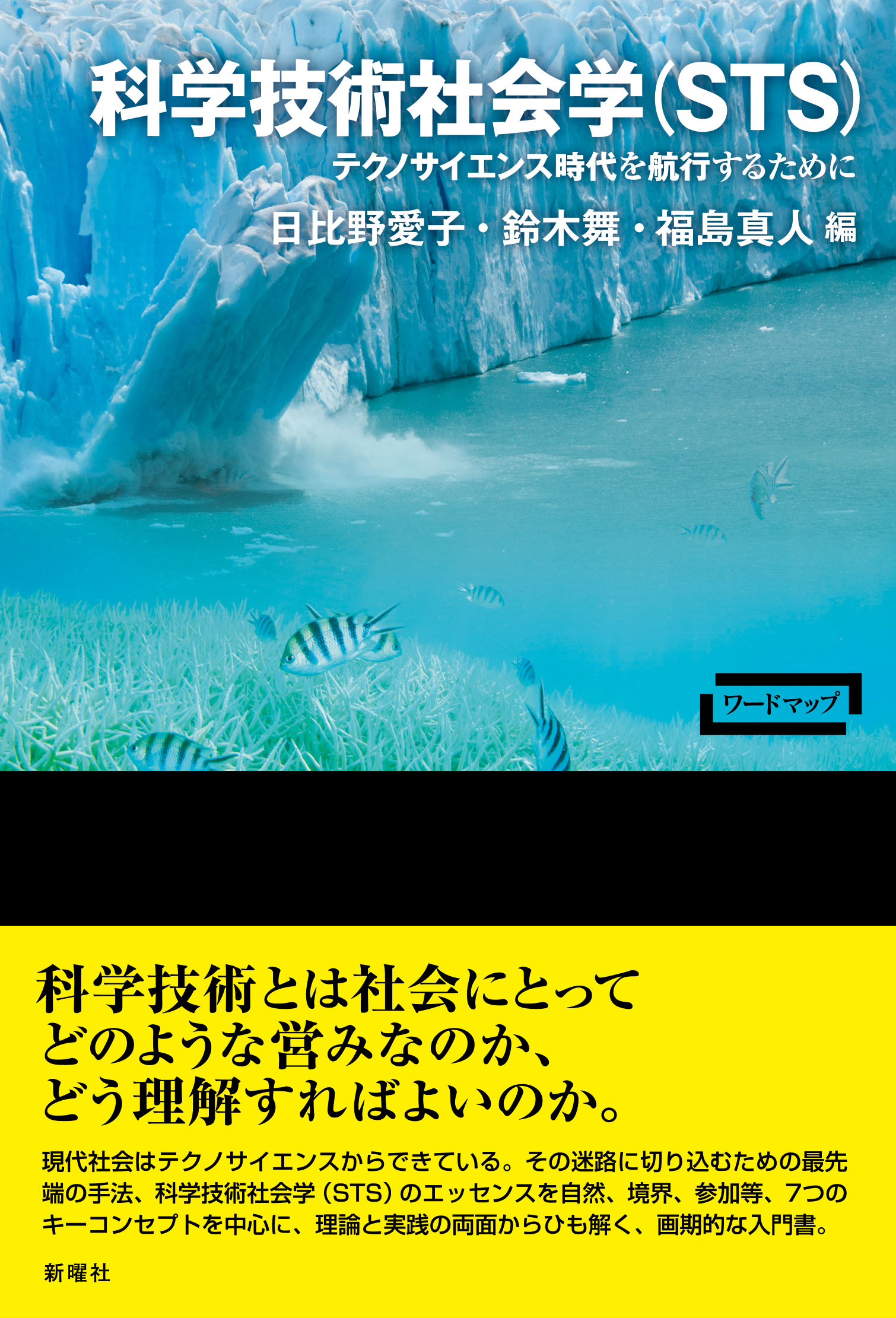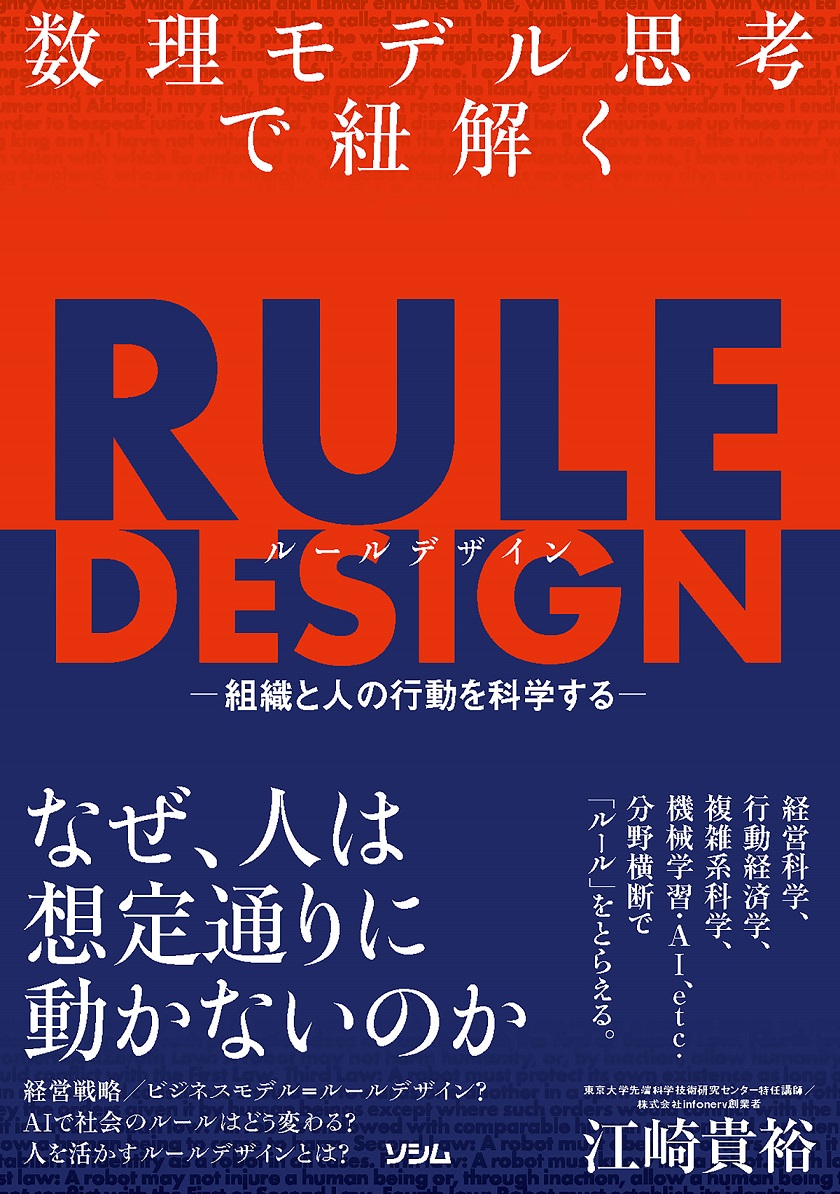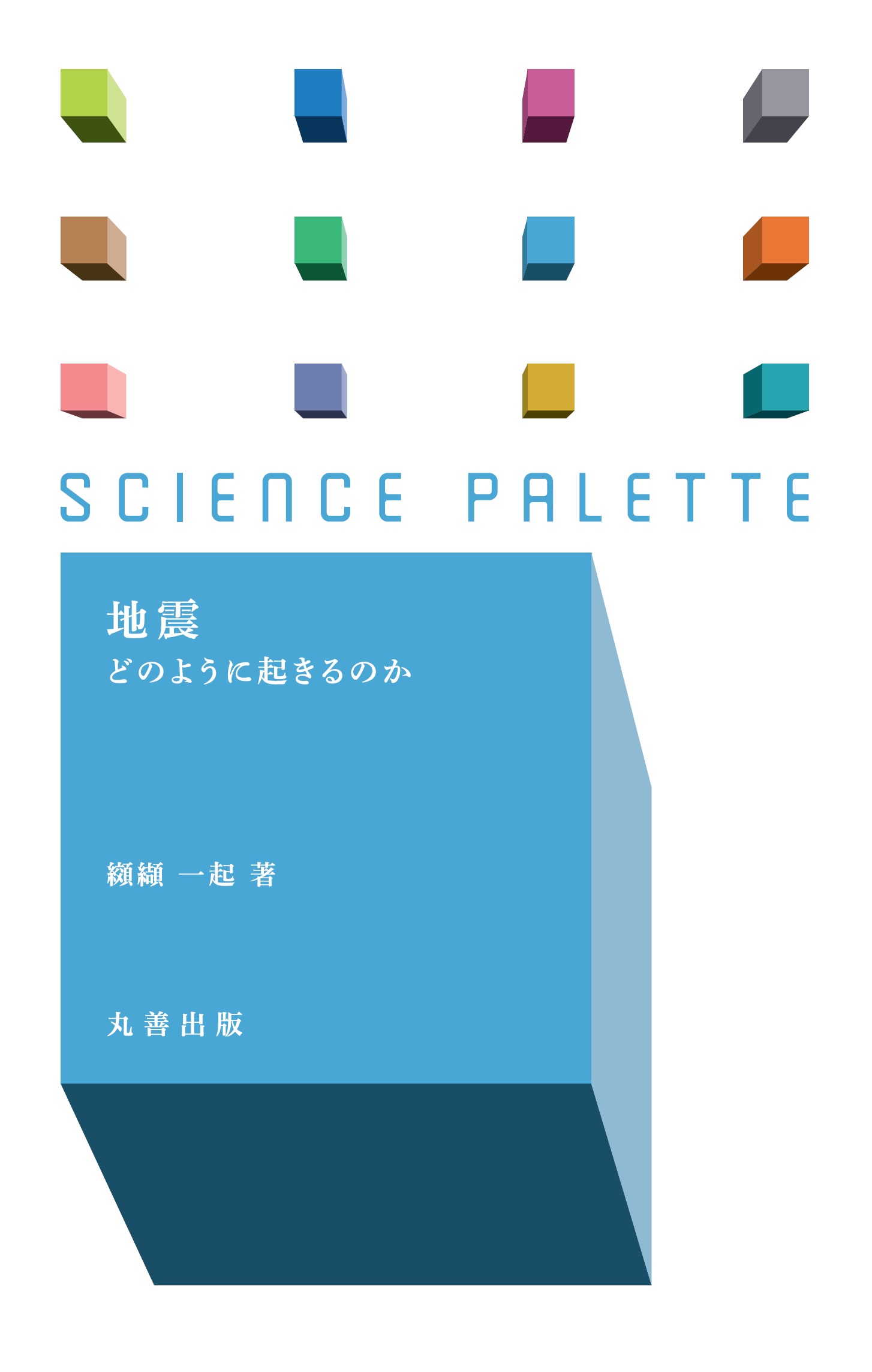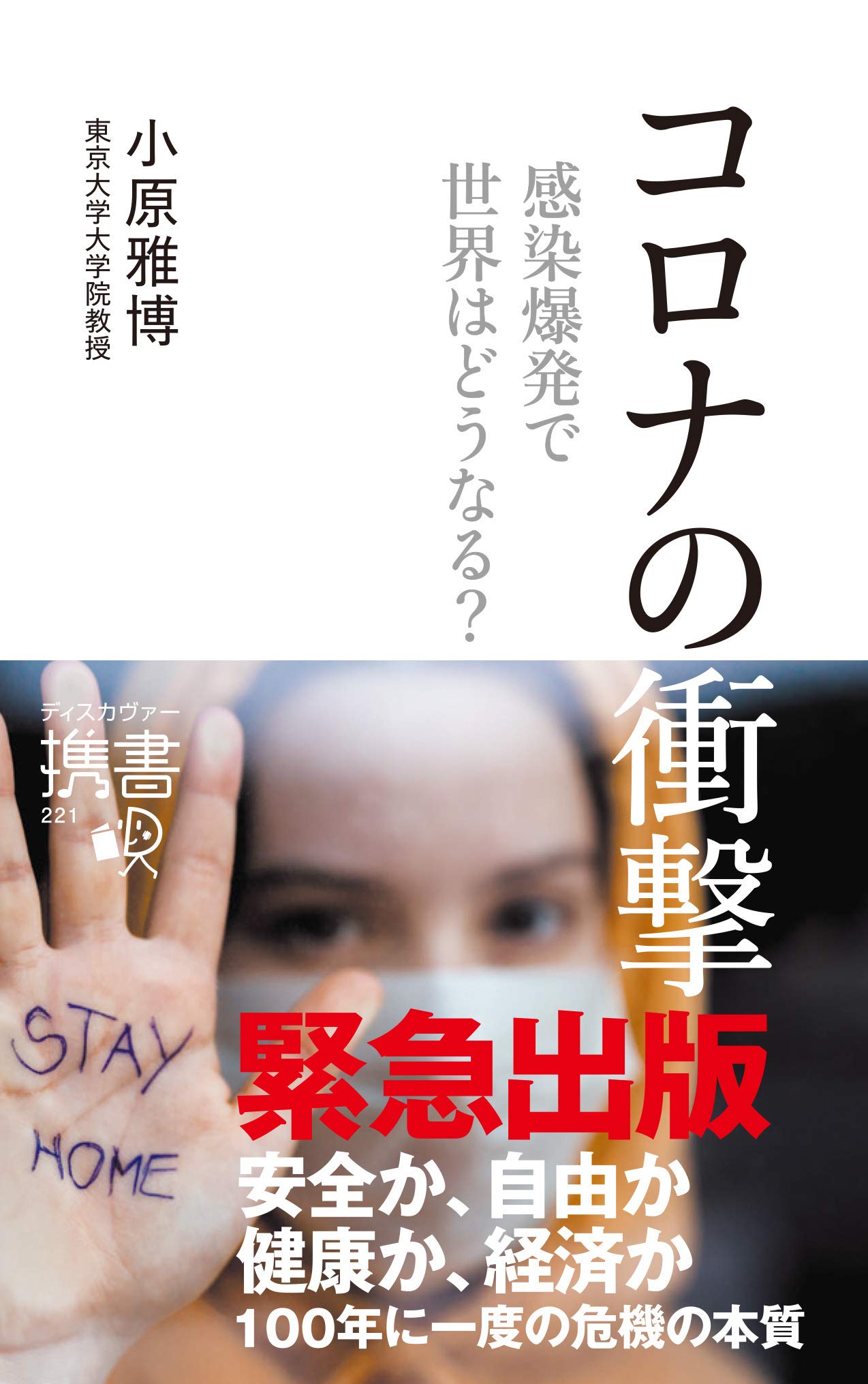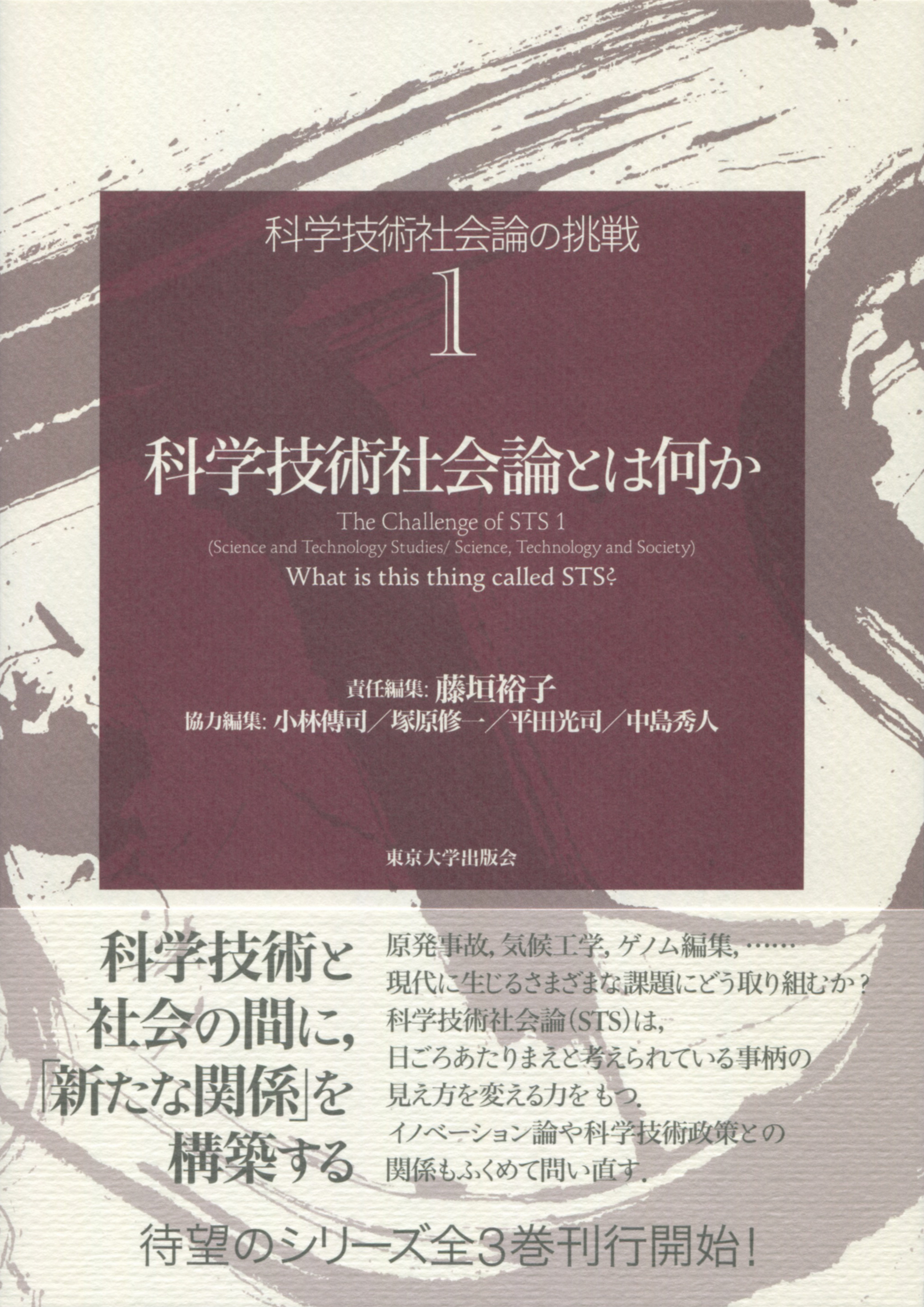現在、我々の周辺には、未来についての多くの (科学的) 予測が氾濫している。その内容は、気候や人口、経済や技術の将来等多岐にわたり、またAIが人間を超える日も近い (シンギュラリティ) といった物騒なものもある。これらの予測の言葉は様々な形で我々自体の思考を縛り、そこで描かれた世界像によって我々が右往左往しているというのが現状である。
しかしこうした予測は、いくつかの前提に基づく仮説に過ぎず、その前提を変えれば、異なる結果が出ることも、その製作者はよく知っている。問題はこうした予測はしばしば科学的な言語で語られるため、そこで描かれる未来が決定論的なものと一般に考えられがちだという点である。こうした予測の言語は、「言葉」としてその製作者が考える以上の働きを持つことが普通であり、それがめぐりめぐって、社会の構成に大きな影響を与える場合も少なくないのである。ある場合には、それは「発話行為」(語ることによって何かをなす) という語用論的な働きといえる場合もあるし、また別の場合には、自己実現的予言、つまり予言をすることで、社会がそれに反応し、結果的にそれが現実化していく、という働きともみなすことができる。
本書の目的は、現在我々の周辺に満ち溢れる様々な予測の言語を取り上げて、その分野ごとにそうした言葉がどのように設定され、それがめぐりめぐって社会にどう影響をあたえるかを比較研究したものである。たとえば、新規技術の世界では、しばしばその技術の将来について、技術予測の名のもとに、その薔薇色の可能性をうたう言葉が使われる。「この新しい技術によって、○○や××といった問題が解決され云々」、という形でその可能性が称揚されるが、現実には必ずしもそうならないケースも多い。こうした言葉は、「科学技術の社会的研究」の分野では「期待」の言語と呼ばれ、そのダイナミズムは詳しく分析されている。詳細は本書を参照してほしいが、未知の未来に対して、その新技術の可能性をアピールするためには、こうした期待の言語による一種の盛り上げは必須である。しかし現実にはものごとは思ったようにはいかないから、期待は失望に替わり、逆風が吹き始める。研究開発をするということは、期待の言語によって、こうした情動的なアップダウンを制御する必要があるのである (第1章)。 他方、例えば経済予測のように、当初その役割が純粋に予測と考えられていたものが、後にそれが持つ発話行為としての特徴に政策担当者が気がつきはじめ、そうした目的を含んだものとして予測を発表するようになっていくようなケースもある (第10章)。
このように、予測という形で未来を語る言葉は、それが「言葉」であるという性質そのものによって、社会を形成する力をもつ。その力の可能性と危険を、様々な領域の専門家と共同して検討したのが本書である。
(紹介文執筆者: 総合文化研究科・教養学部 教授 福島 真人 / 2019)
本の目次
1 過去を想像する
2 未来を創造する
3 結論――未来へのリテラシー
I 未来を語る――期待の社会学
第2章 未来の語りが導くイノベーション――先端バイオテクノロジーへの期待 (山口富子)
1 未来への期待
2 イノベーションへの期待
3 ゲノム編集技術への期待の高まり
4 期待の高まりのメカニズム
5 結論――誰による期待か/誰による予測か
第3章 未来をつくる法システム――DNA型鑑定への期待と失望 (鈴木 舞)
1 期待と社会
2 DNA型鑑定への期待と失望――アメリカの事例
3 DNA型鑑定への期待と失望――日本の事例
4 期待・失望・実践の背景
5 結論――法システムによる予測
第4章 防災における「予測」の不思議なふるまい (矢守克也)
1 「予測」が外れることをねらう
2 「予測」を既成事実化し先取りする
3 「予測」を言葉にしつつ実現してしまう
4 結論――「予測」の不思議なふるまい
II 未来のエコロジー――予測モデルの動態
第5章 感染症シミュレーションにみるモデルの生態学 (日比野愛子)
1 モデルの基盤
2 感染症のモデルをつくる
3 強力な武器同士の協力?――感染症介入政策に数理モデルが活用された事例
4 数理モデルのエコロジー
5 結論――予測モデルの感染前夜
第6章 語りと予測の生む複雑さ (橋本 敬)
1 複雑さの起源――「作用するもの」と「作用されるもの」の分離不可能性
2 「語り」の作用を複雑系科学から読み解く
3 ミクロとマクロの相互作用の構成論的検討
4 結論――複雑系科学からみた予測
第7章 過去に基づく未来予測の課題――確率論的地震動予測地図 (鈴木 舞・纐纈一起)
1 地震を予測すること
2 確率論的地震動予測地図をめぐる論争
3 予測の検証をめぐるダイナミズム
4 結論――地震に関する予測の課題
III 未来をつくる――予測モデルと政策
第8章 政策のための予測を俯瞰する (奥和田久美)
1 予測と目的
2 政策のための予測活動
3 予測活動を行う主体とスタイル
4 予測すべき対象
5 政策的意図を持った将来予測の特徴
結論――変化への感度と対応力
第9章 規制科学を支える予測モデル――放射線被ばくと化学物質のリスク予測 (村上道夫)
1 リスクの予測
2 自由主義とパターナリズム
3 リスクと安全
4 リスクと基準値
結論――新しい形の基準値
第10章 予測と政策のハイブリッド――日本の経済計画における予測モデルと投資誘導 (ソン・ジュンウ)
1 経済予測の二面性
2 経済計画の「基本問題」――予測のズレ
3 「誘導」――予測の新しい問題
4 計量経済モデルの「整合性」――誘導の新しい手法
結論――未来記述と発話行為が交わるところ
関連情報
シノドス 「遙かなる未来を語ること」 (SYNODOS 2019年6月26日)
https://synodos.jp/society/22693
個人的紹介ブログ 「予測がつくる社会」 (福島真人研究室 2019年3月3日)
https://ssu-ast.weebly.com/125021252512464/6627985
書評:
橋本毅彦 評 <本の棚>山口富子・福島真人編『予測がつくる社会 ─「科学の言葉」の使われ方』 (『東京大学教養学部報』第610号 2019年6月3日)
http://www.c.u-tokyo.ac.jp/info/about/booklet-gazette/bulletin/610/open/610-2-03.html



 書籍検索
書籍検索