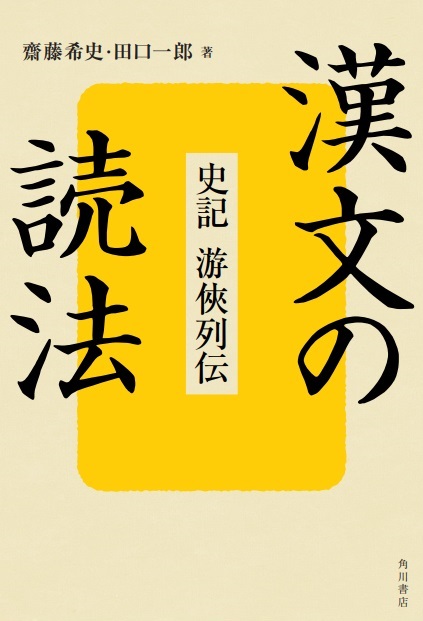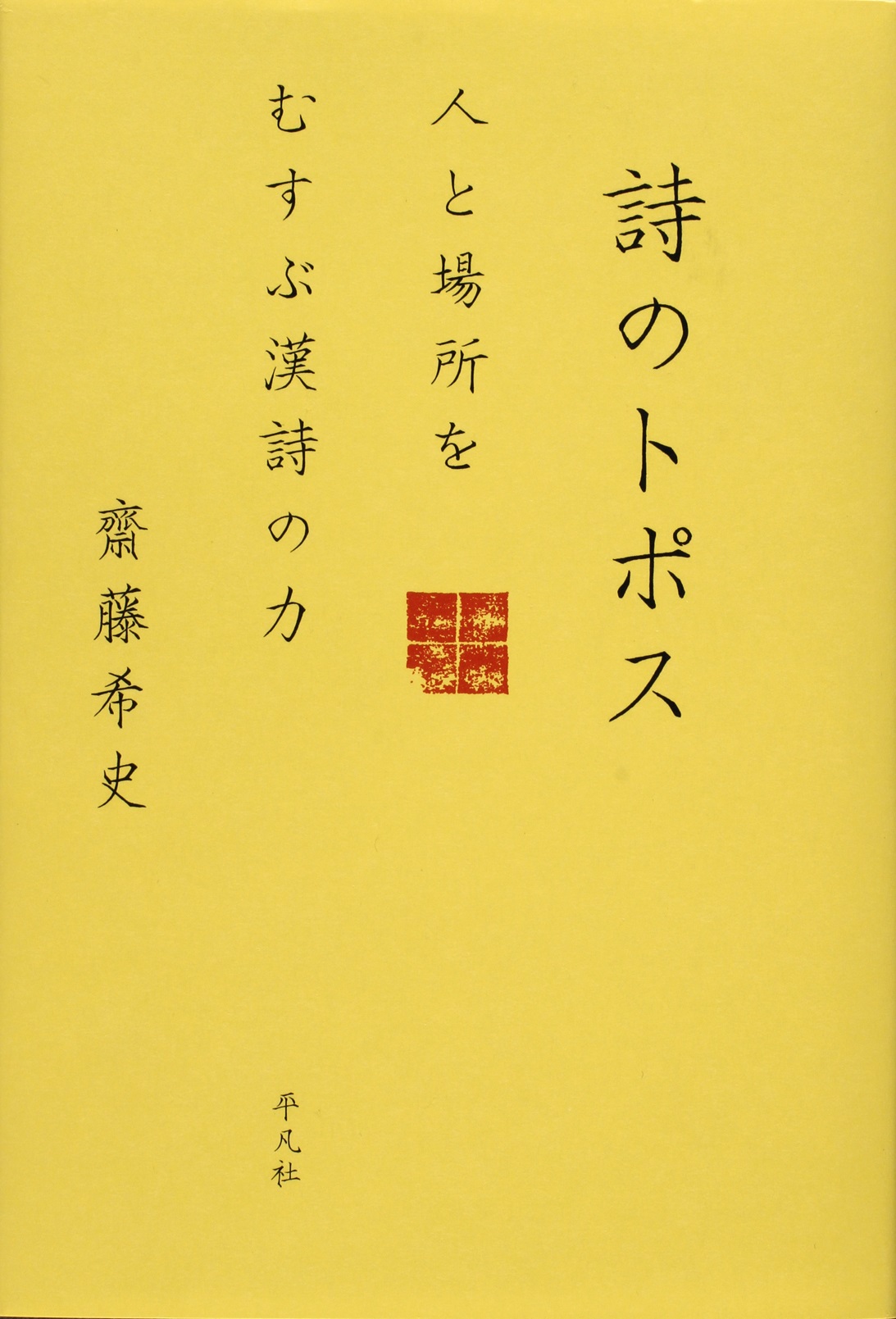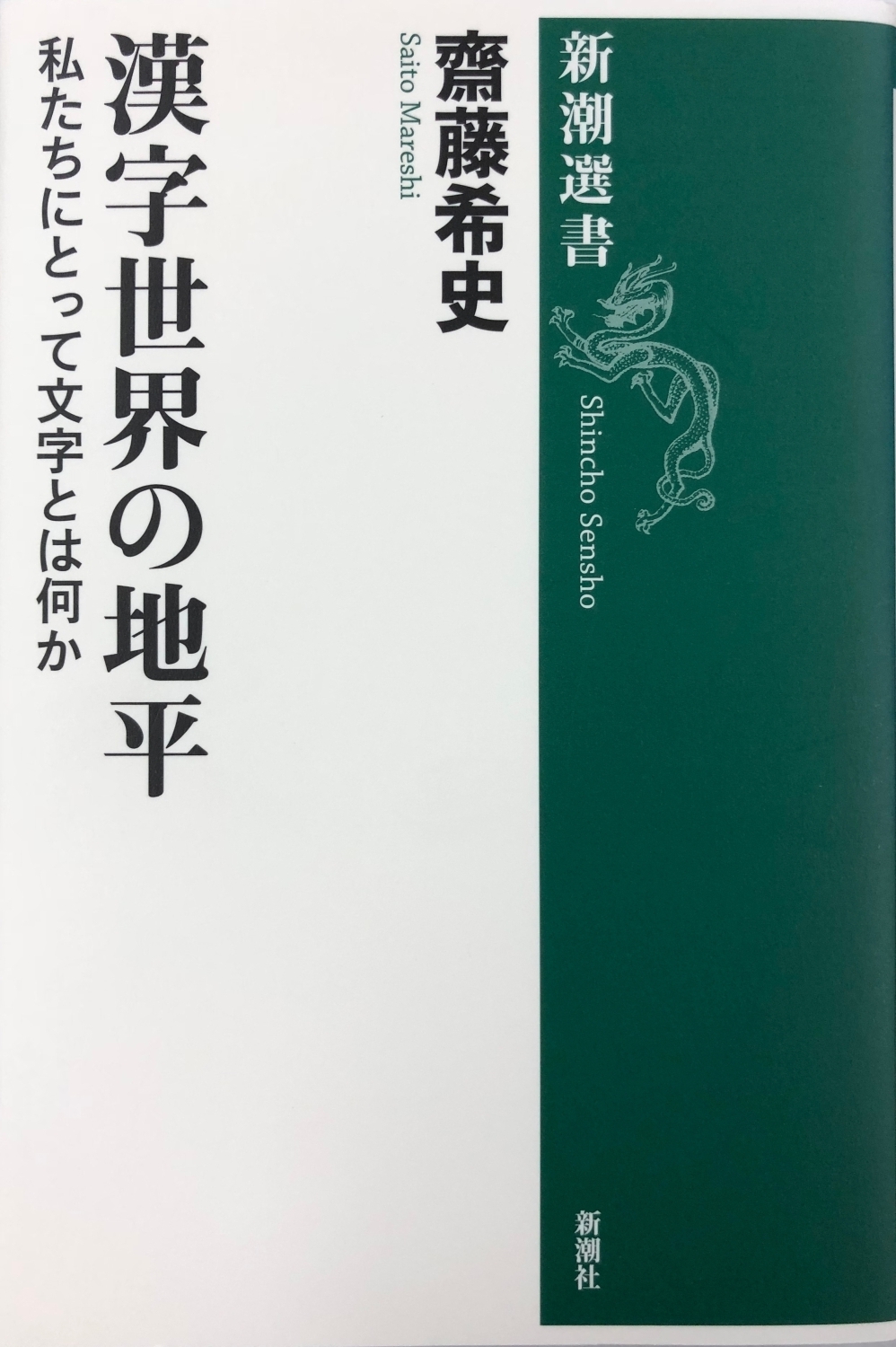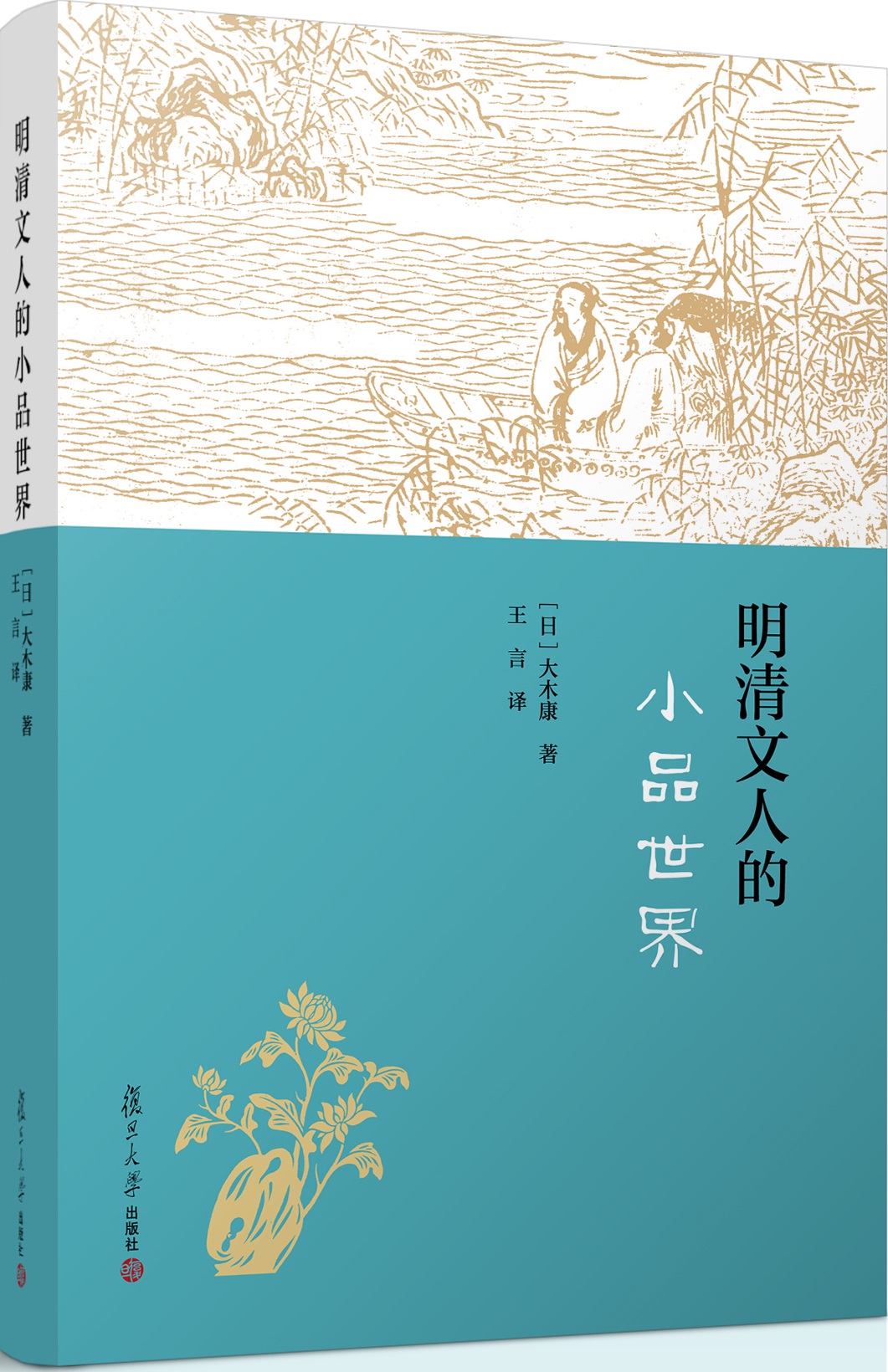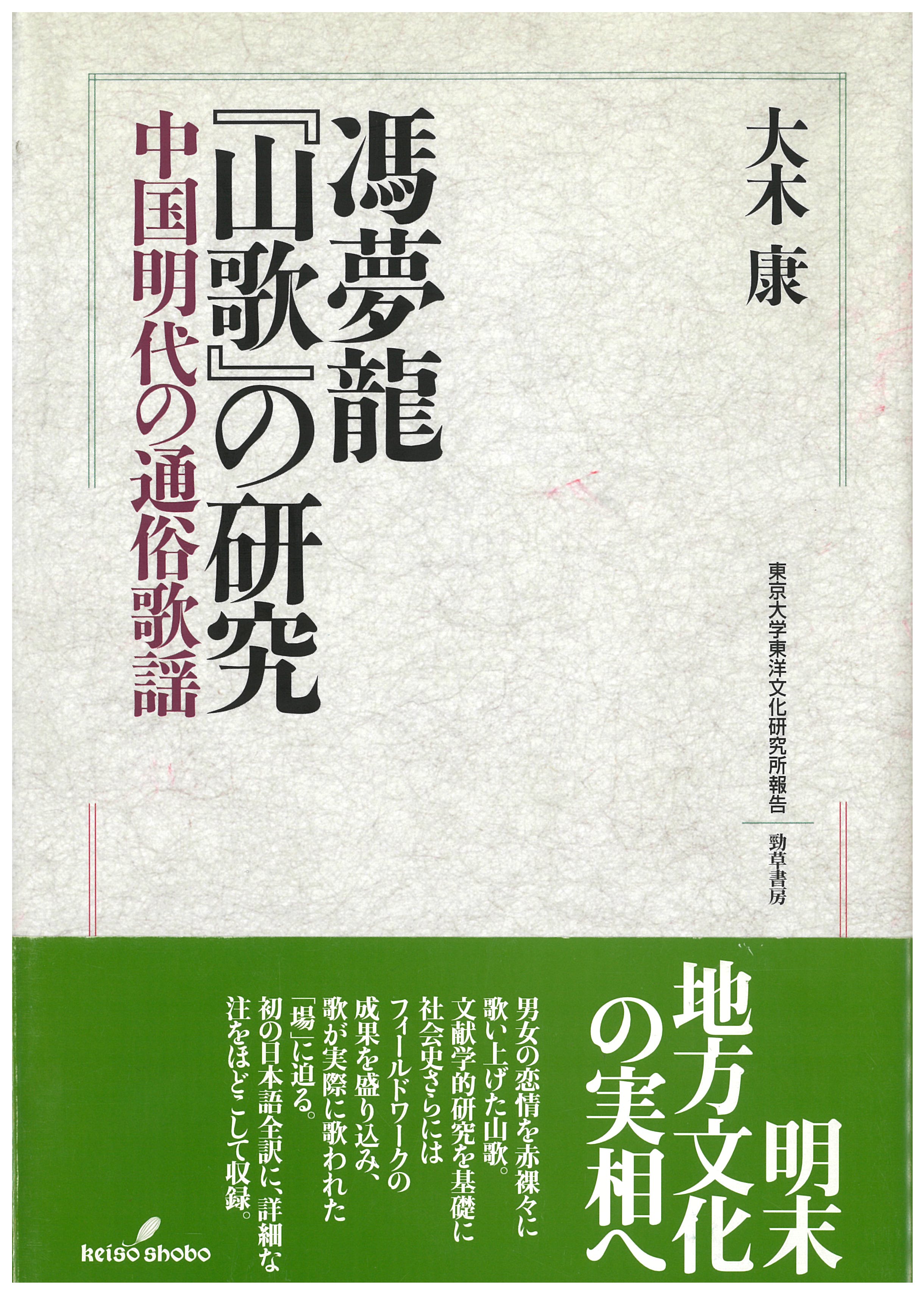東京大学出版会の月刊雑誌『UP』には、本学の教員などによる学術的エッセイとでも称すべき連載が並んでいる。それぞれの専門をふまえながら専門外の読者も視野に入れ、論文とは異なる自由さで書かれた文章である。この本は、そうした連載のうちの一つ (少なくとも形式的には) の「漢文ノート」をまとめたもので、書籍化にあたって副題を加え、文章を内容によって四季に配列しなおした。書名の「漢文」は、中国古典文学とそれにかかわって生まれた東アジアの文学を指し、副題で用いた「文学」はさらに広く、書くことによる表現全般を含む。私たちにとってそうした「文学」はどのような意味をもつのか。副題の案を検討しながら気づいたのは、季節や日常に沿って書かれたこれらの文章が、時には専門の論文よりも、その問いに近づこうとしていることだった。
「春」の章の末尾に「悼亡」と題する文章がある。「悼亡」は、文字通りには人の死を悼むことだが、中国文学では妻の死を悼む作を言い、晋の潘岳に始まる。この文章ではおもに宋の梅堯臣のそれを取りあげ、潘岳にも言及した。そしてじつは私が初めて書いた論文、つまり卒業論文は、その潘岳の「悼亡詩」の修辞について分析したものだった。潘岳以前に、亡くなった友人の妻になりかわって夫の死を嘆く詩や賦があり、「悼亡詩」の表現がそれを引き継いでいること、そうした修辞の踏襲は、繰り返し妻の死を悼んで三首に及んだ「悼亡詩」の構造とも通じていることなどを論じて、詩における悲哀のリアリティがどこから生まれるのかを検討した。あくまでテクスト論的な分析である。そもそも、潘岳の悲哀いかばかりか、では論文にならない。
「漢文ノート」の連載に「悼亡」の回を書いたのは、話題に窮してとうとう卒論まで引っ張りだしてきたというわけではない。いや、ある意味ではそうだったのかもしれない。その時の私には他に書くことが思いつかなかったのである。掲載は二〇一一年六月。東日本大震災で多くの人が家族や友人を亡くしたことがまだ記憶にもならないころだった。手もちのことばがどれも陳腐に感じられたとき、かつて論じた詩が浮んできた。
いま思えば、授業や論文とは違ったやりかたで十年以上にわたって続けた「漢文ノート」の連載は、私にとってことばや文章の価値はどこにあるか、それを繰り返し考えさせるトレーニングだった。ついでに言えば、自分でいささかの工夫を加えながら作成した巻末索引は、そのトレーニングにつきあってくれた人物や書物のリストとなっている。問いが生まれる場所の地図でもある。この本を手にとる機会があったら、ぜひ索引にもお目通しいただきたく思う。
(紹介文執筆者: 人文社会系研究科・文学部 教授 齋藤 希史 / 2024)
本の目次
【春】
霞を食らう/ともに詩を言う/双剣/年年歳歳/走馬看花/悼亡
【夏】
瓜の涙/斗酒なお辞せず/口福/帰省/スクナシジン/友をえらばば
【秋】
満目黄雲/蟬の声/菊花の精/隠者の琴/読書の秋/起承転結
【冬】
書斎の夢/郎君独寂寞/二人組/詩のかたち/杜甫詩注/漢詩人
関連情報
佐藤浩一 評 (図書新聞 2022年5月28日号)
https://www.fujisan.co.jp/product/1281687685/b/2255395/
加藤徹 評 (日本経済新聞 2021年12月18日)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD0851O0Y1A201C2000000/
書籍紹介:
(著者に会いたい) 齋藤希史さん「漢文ノート」インタビュー 豊かさは日々のことばに (朝日新聞 2021年12月18日)
https://book.asahi.com/article/14506049



 書籍検索
書籍検索



 eBook
eBook