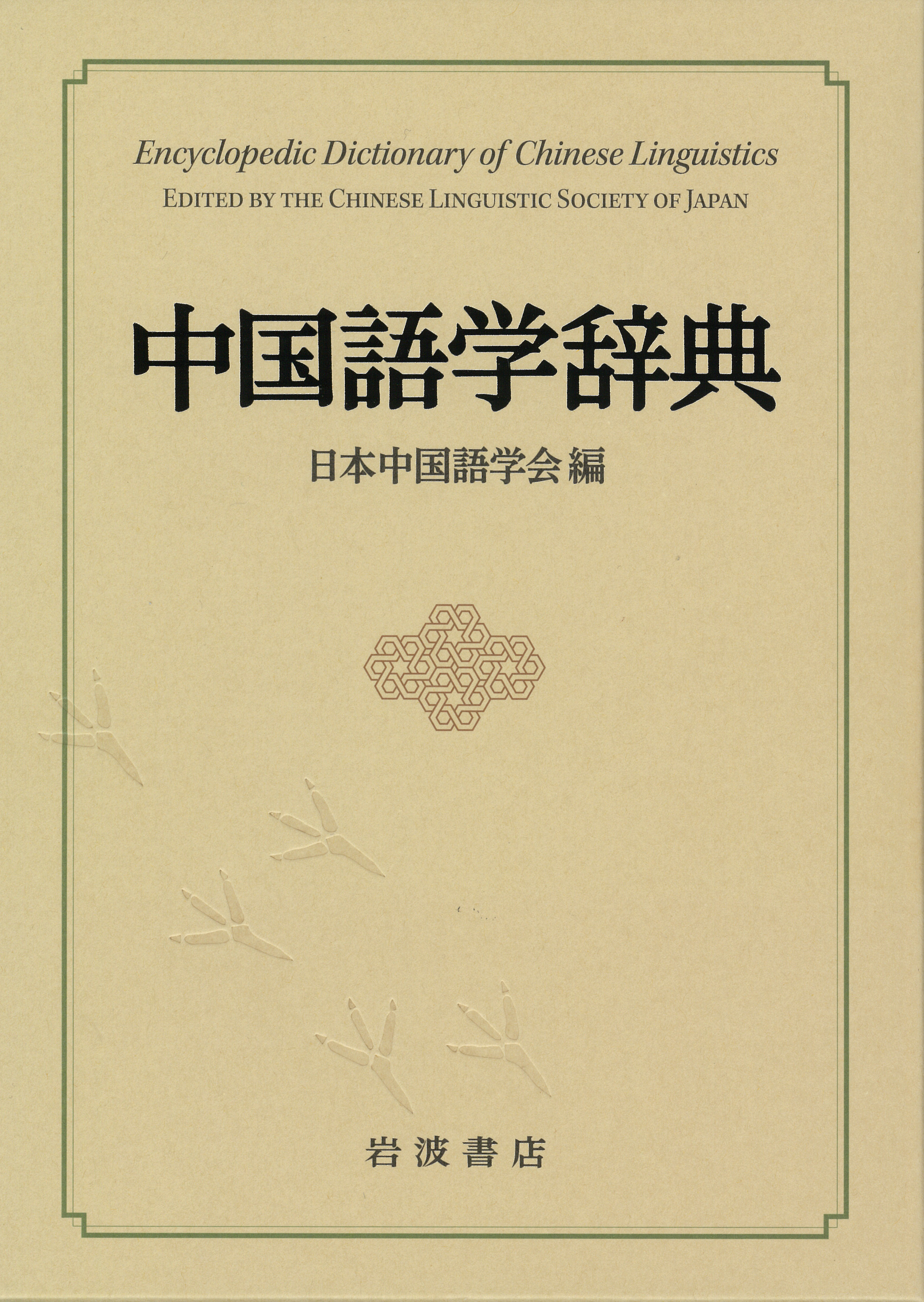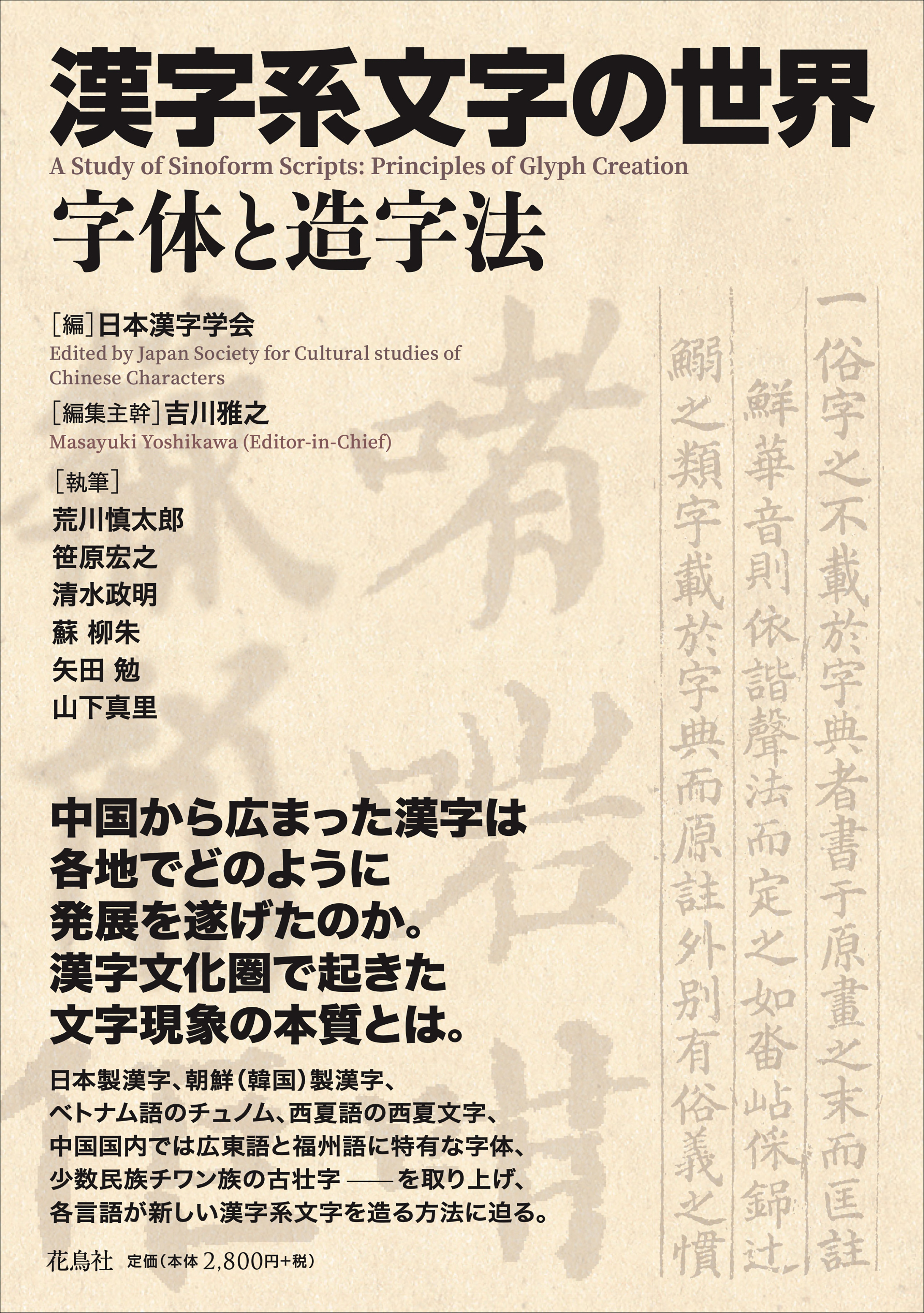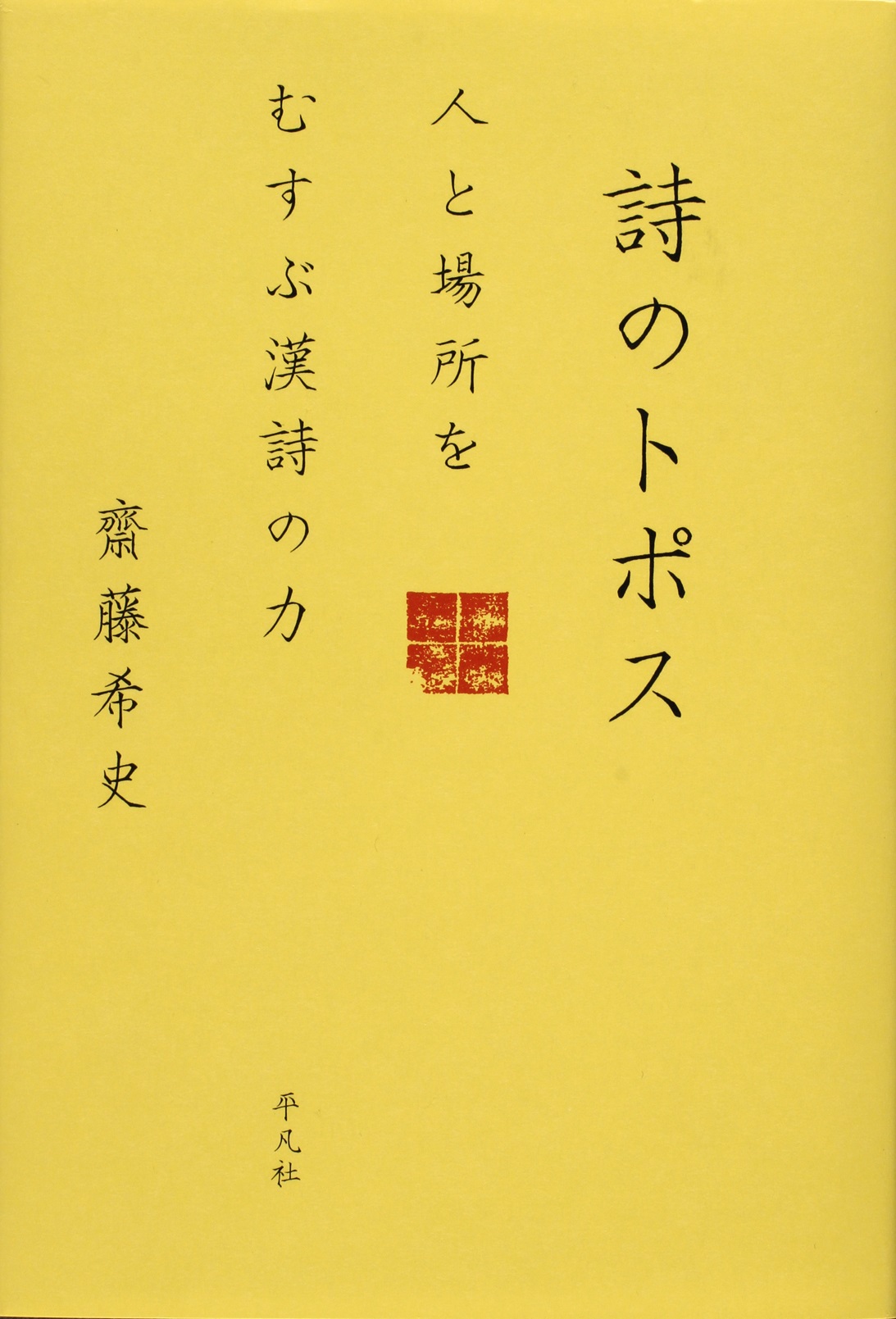「私たちにとって文字とは何か」という副題として示した問いが、この本で考えたかったことです。書名は「漢字世界の地平」ですし、内容も日本そして東アジア地域の文字と言語を対象にしていますから、「文字」と言っても漢字のことではないかと言われてしまうかもしれません。たしかに叙述の軸は漢字です。漢字がどのように生まれ、どのように流通し、そしてそれぞれの地域──とりわけ日本の文字と音声へとどのように展開したのか。この本で論じられるのはそうしたことがらです。「文字とは何か」とは少し広げすぎかもしれません。
とはいえ、やはりこの本の根底には、「文字とは何か」という問いがあります。いまの私たちは文字に依存する社会に住んでいます。基本的に文字が読み書きできることが前提となっています。けれどもそれはホモ・サピエンスの歴史においては、ごく新しいことです。文字を使用しない社会もかつては少なくありませんでした。言語と文字とはセットで語られがちですが、文字は言語よりもずっと遅れて獲得されたものです。文字は人間に何をもたらし、人間は文字によってどのような世界を作ったのか。この本では、漢字を切り口にして、それを考えました。ですから、副題の「私たち」は、漢字を使う私たちであると同時に、より広く、文字を使う私たちでもあります。
その問いを根底において、この本は甲骨文字から近代日本の文体まで、できるだけ個別の事例に即しつつ、文字と言語がどのような関係をもちうるのかを明らかにしようとしました。漢字が流通した圏域は、日本では漢字文化圏と呼ばれることがままありますが、この本ではそうした用語を採用していません。文化圏論は、他との対比によって成立しますから、おのずと地域の固有性を強調しがちです。また、その文化圏内における共通性も強調しがちです。そうでなければ「文化圏」とは呼びにくいでしょう。しかしこの本は、そうした立場からは距離を置きます。むしろ、漢字が流通したことによって生じた文字と言語との関係のダイナミズムに焦点を合わせました。
もう一つ、日本では漢字について語る言説が古くから(それこそ「漢字伝来」から)存在し、しばしば漢字を外来のものとして位置づけようとする議論が行なわれてきましたが、この本はそうした「他者としての漢字」論からも距離を置きます。「他者としての漢字」論は、「他者としての中国」を前提としています。外来の漢字を日本のものとして活用した、という議論も、思考の枠組みとしては同じことです。しかし問題は、それが中国で生まれたかどうかではなく、それが文字であることなのです。外来性や他者性があるとするなら、そこです。「私たちにとって文字とは何か」という問いは、そこにつながります。
文化論ではなく文字論として語ること。それによって得られる新たな視界を、みなさんと共有したく思います。
(紹介文執筆者: 人文社会系研究科・文学部 教授 齋藤 希史 / 2018)
本の目次
漢字の祖先/金文の位置/文字の帝国/拡大する漢字圏
第二章 言と文の距離──和語という仮構
もたらされる文字/和習への意識/ハングルとパスパ文字/仮名の世界
第三章 文字を読み上げる──訓読の音声
訓読の否定/『論語』のリズム/書物の到来/『古事記』と『日本書紀』
第四章 眼と耳と文──頼山陽の新たな文体
近世の素読/『日本外史』の位置/眼と耳の二重性
第五章 新しい世界のことば──漢字文の近代
翻訳の時代/漢文脈の再編/訓読体から国民文体へ
終 章 文化論を超えて
関連情報
平川祐弘 (東京大名誉教授) 評 「中華はどう受容されたか」(『東京新聞』2014年6月29日)
品田悦一 評 「漢字、この未知なるもの」(『波』2014年6月号)
https://www.shinchosha.co.jp/book/603750/#b_review
学会時評:金沢英之 (北海道大学准教授) 評 「上代」2014.1-2014.6(『リポート笠間』57)
http://kasamashoin.jp/2014/10/2014120146.html
学会時評:堀川貴司 (慶應義塾大学附属研究所斯道文庫教授) 評 「日本漢文学」」2011-2014.7(『リポート笠間』57)
http://kasamashoin.jp/2014/10/201120147.html



 書籍検索
書籍検索