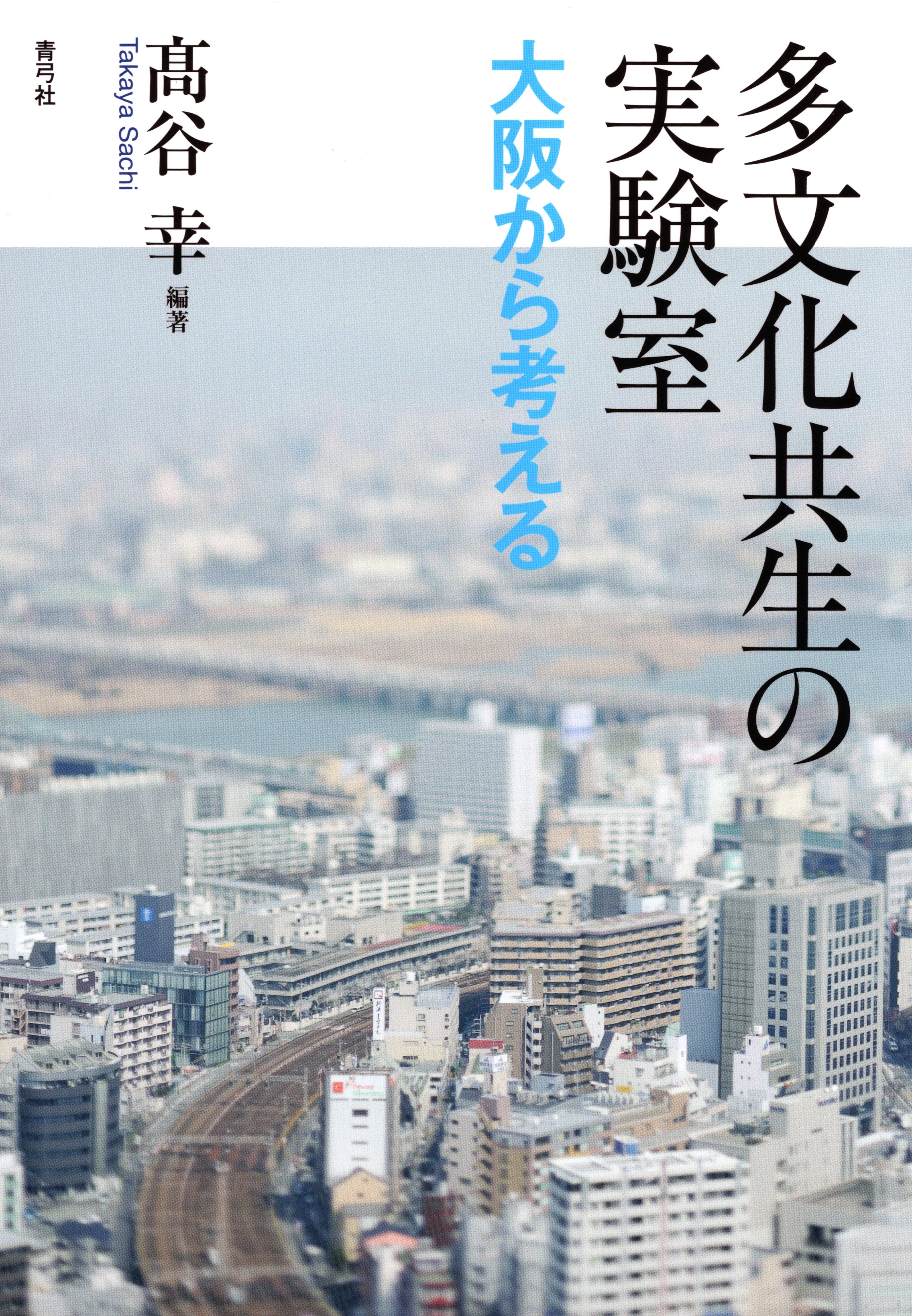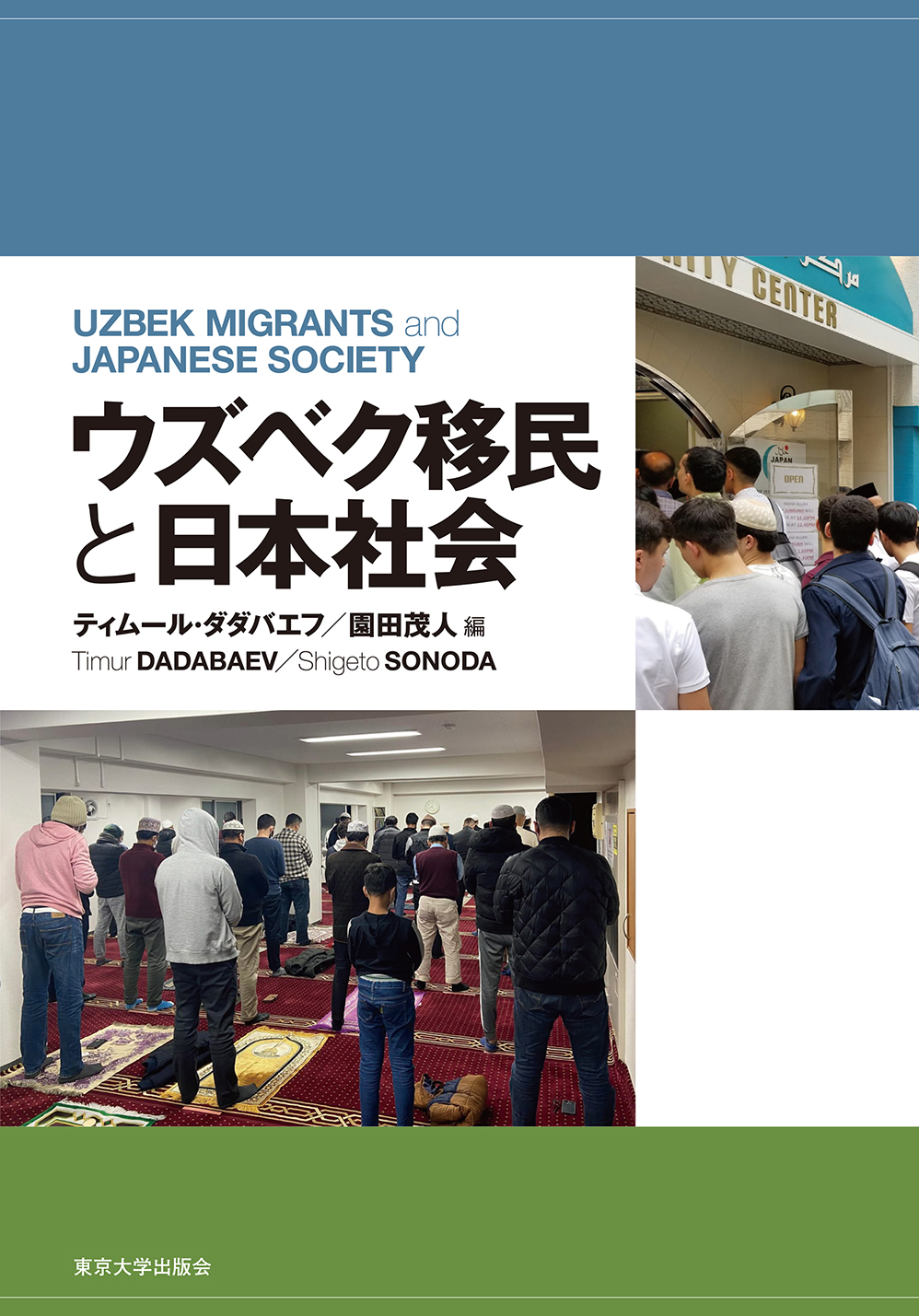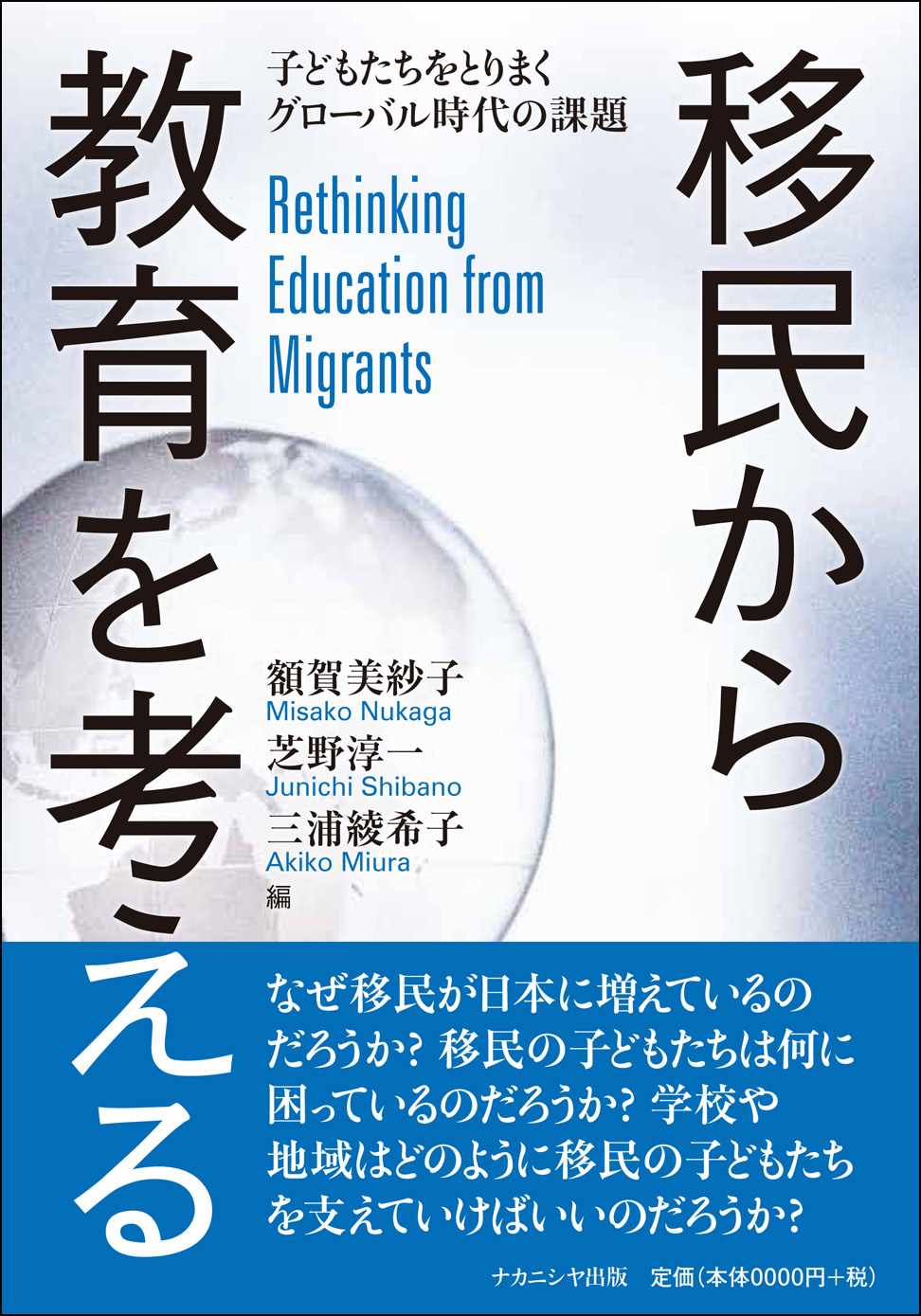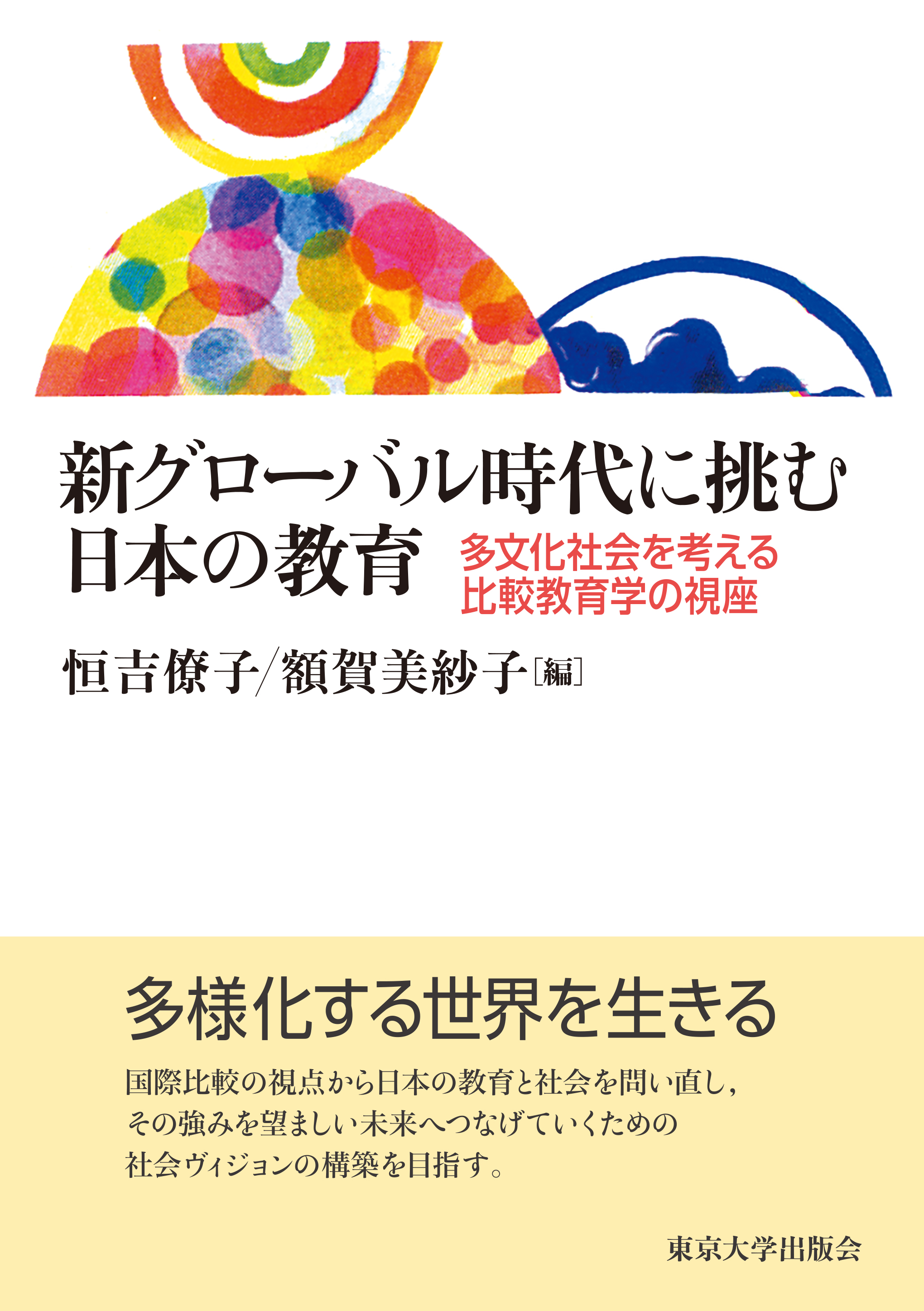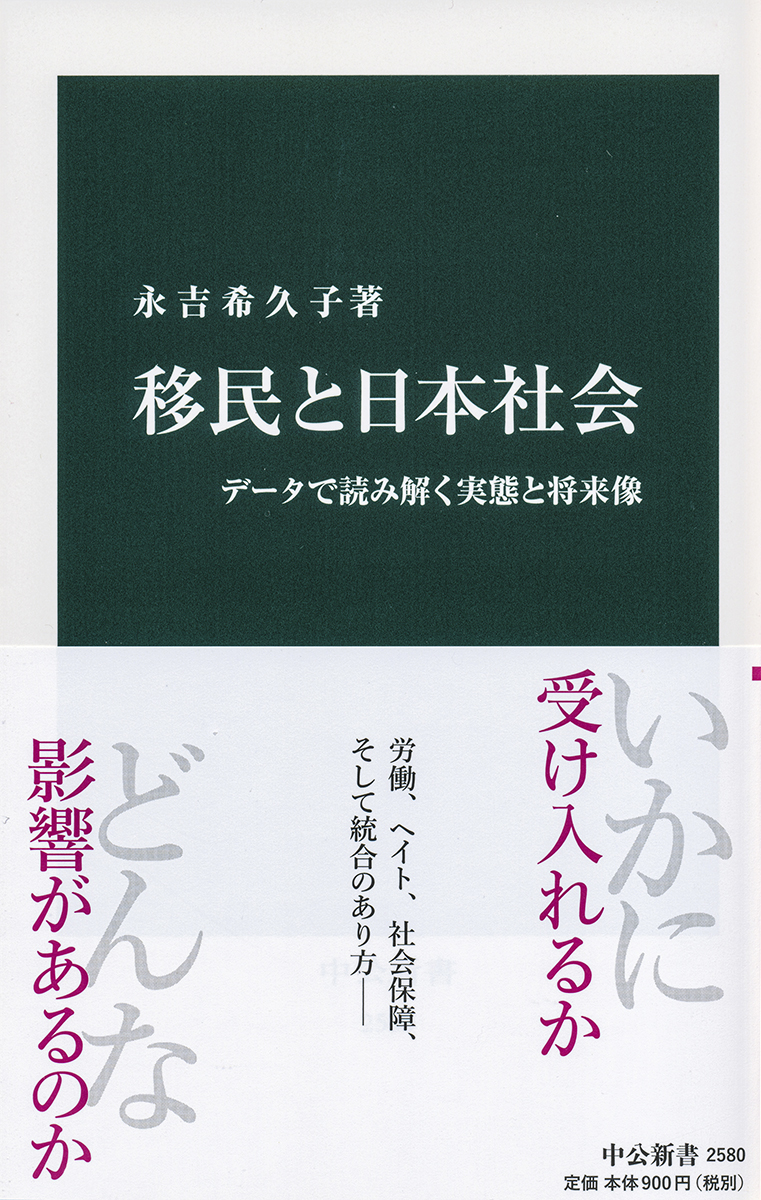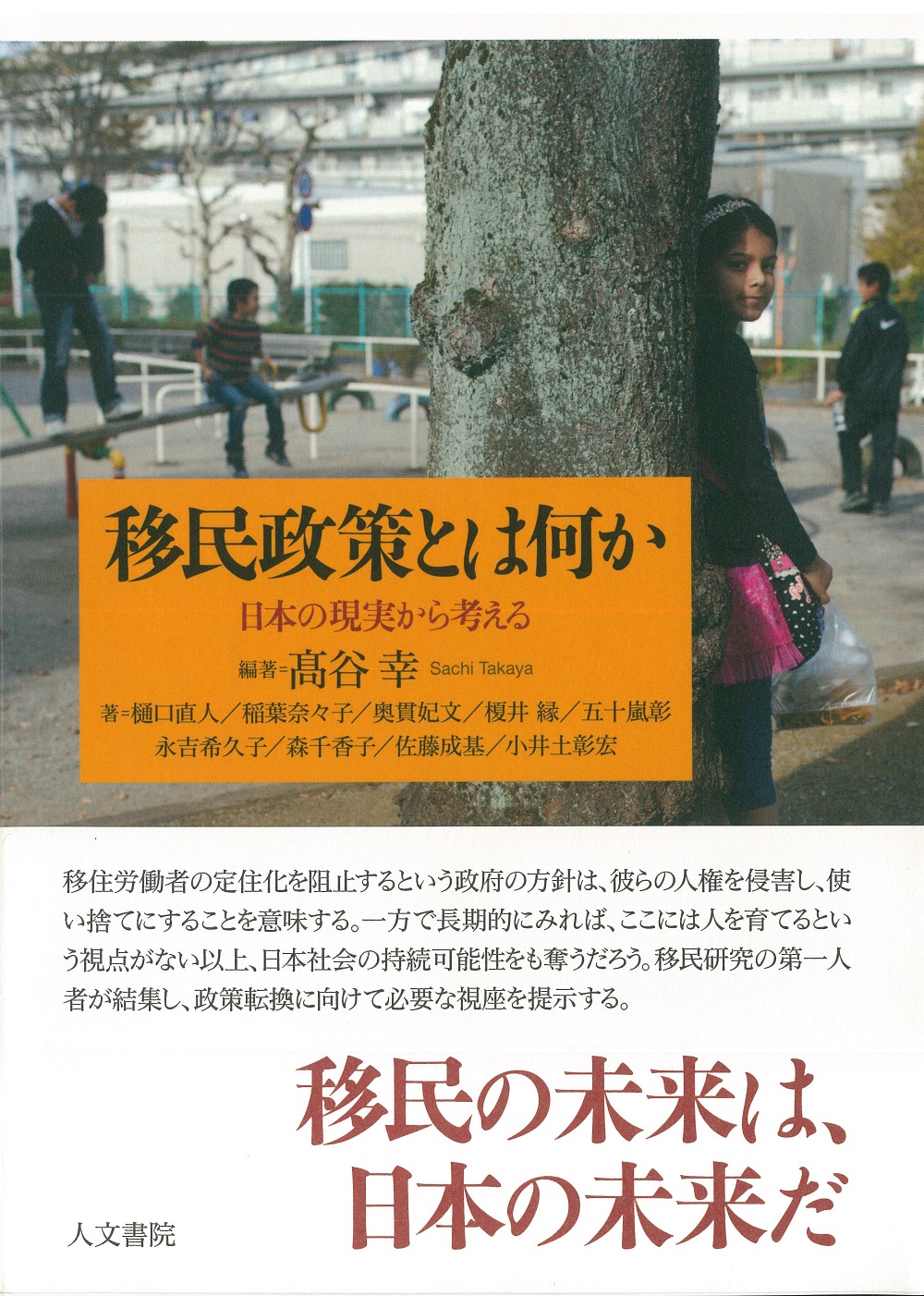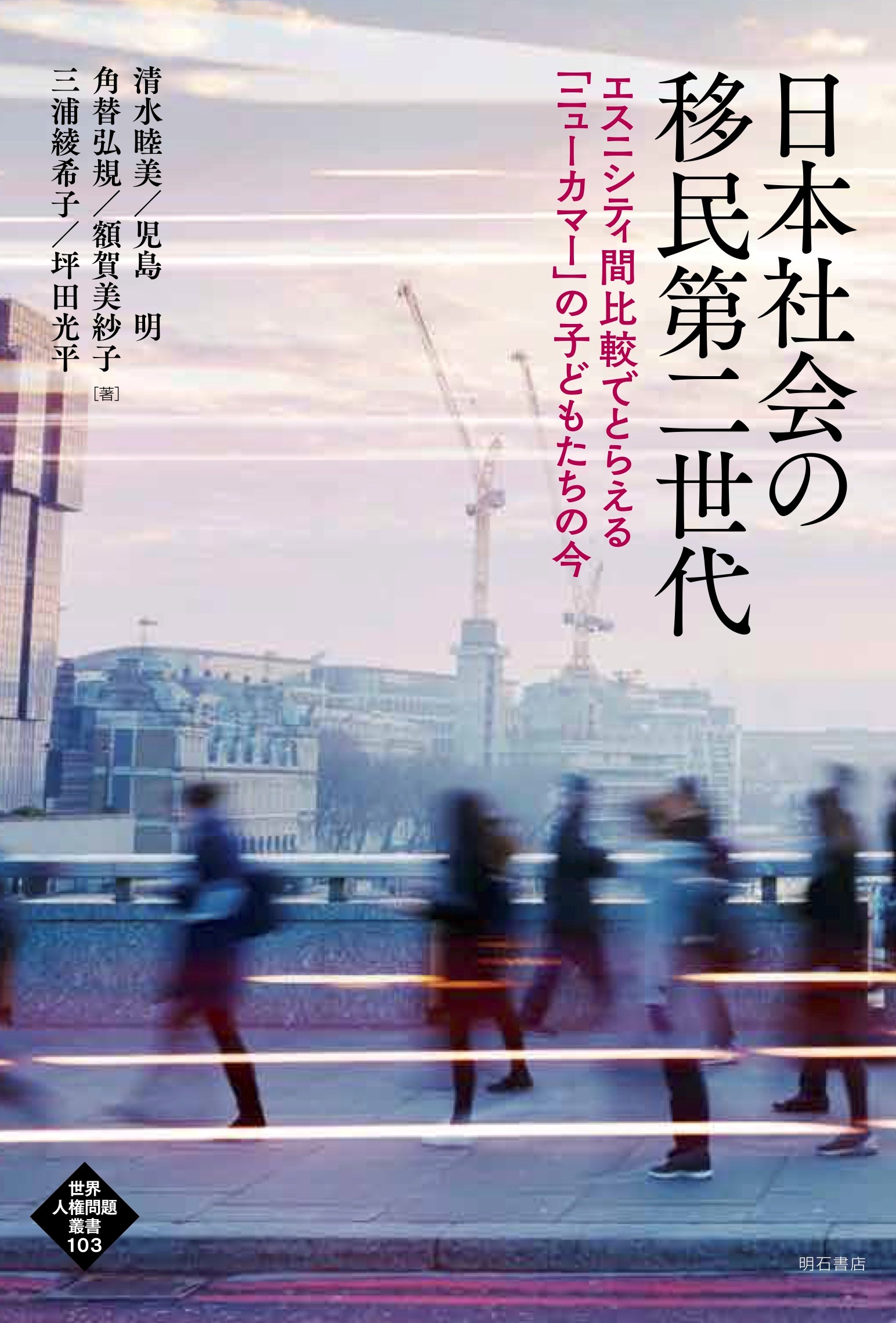
書籍名
世界人権問題叢書 103 日本社会の移民第二世代 エスニシティ間比較でとらえる「ニューカマー」の子どもたちの今
判型など
704ページ、四六判
言語
日本語
発行年月日
2021年7月25日
ISBN コード
9784750352282
出版社
明石書店
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
日本社会には今「移民第二世代」の若者たちが多く存在している。移民第二世代とは、片方または両方の親が外国生まれで、本人は受け入れ国に生まれ育った者を指す。かれらは出身国と受け入れ国それぞれの言語や文化のはざまに置かれ、多くの場合、移民に対する差別や偏見のまなざしの中でアイデンティティと生き方を模索していく。移民第二世代の経験に注目することによって、かれらを受け入れる国が多様な人種・民族に対してどこまで寛容であり、公正な社会を実現しているかが明らかになる。同化主義のもとで国内の民族的多様性を不可視化してきた日本でも近年は外国人労働者を積極的に受け入れはじめ、その子どもである移民第二世代の教育とキャリアの保障が政策的な課題として注目されつつある。
では、移民第二世代の若者たちは、日本社会でどのような経験をし、その過程はどのような地位達成に結びついているのか。本書は構想から8年の歳月をかけて、ベトナム、カンボジア、中国、ブラジル、ペルー、フィリピン出身の移民第二世代170名へのインタビューを積み重ね、かれらの語りをもとに上記の問いに答えることを試みた。明らかになったのは、移民第二世代のアイデンティティ、学業達成、キャリアが複数の社会的要因によって分岐し、多様化していることだ。移民第二世代は一枚岩の集団ではない。親の収入や学歴、出身国、学校で受ける偏見や差別、友人関係のありかたや市民団体からの支援の程度によって、第二世代の間には異なるエスニック・アイデンティティが形成され、学業達成の違いとなって現れる。
本書ではエスニック・アイデンティティを4類型に分けたが、親子関係と学業達成が良好であったのは、日本と出身国の文化を両方とも獲得し、場面によって使い分けられるハイブリッド志向の若者たちである。こうしたバイリンガル・バイカルチュラルな若者たちに特徴的なのは、多文化的仲間集団や移民支援を行う市民団体、親を介した出身国との繋がりが強かったり、学校で移民背景を積極的に認めてもらう経験を有していたりする点である。
つまり、トランスナショナルで文化的多様性に寛容な生活空間に育った者ほど、ハイブリッド志向になりやすく、進学やキャリアの活路がさまざまに開けている。問題はそうした環境を享受することが日本では容易ではないということだ。アメリカのような移民大国と異なり、資源の多い移民コミュニティは未発達で、市民団体の数も地域的な偏りがある。学校は同化主義的な価値観が強く、文化的差異は貶められがちだ。日本社会で学業達成するための資源を手に入れつつ、出身国の言語や文化を維持してハイブリッドな生き方をする機会は、制度的に保障されていない。
本書には移民第二世代の生々しい語りが多く収められているので、関心のある読者はそこだけを拾って読んでいただくのでもいい。移民第二世代の若者たちが日本で経験する生きづらさに目を向けることで、多様性を包摂する社会には何が求められているのか、日本にはどのような変化が必要なのかを考えるきっかけとしてほしい。
(紹介文執筆者: 教育学研究科・教育学部 教授 額賀 美紗子 / 2023)
本の目次
序章 移民第二世代研究を考える[清水睦美]
序‐1 教育学研究におけるニューカマー研究
序‐2 ニューカマー研究から「移民と教育」研究へ
序‐3 本書の目的と構成
序‐4 調査内容と対象者
コラム 本書が対象とするエスニックグループの概要
第I部 移民第二世代のエスニック・アイデンティティ
第1章 イントロダクション――多様化する移民第二世代のエスニック・アイデンティティ[額賀美紗子]
1‐1 移民第二世代の日本社会への適応
1‐2 移民第二世代のエスニック・アイデンティティの類型
1‐3 本調査における移民第二世代のアイデンティティの全体像
1‐4 エスニック・アイデンティティ分岐の過程と要因――エスニック集団間の比較から
1‐5 小括――日本社会における移民第二世代の分節的同化
第2章 想像のエスニシティ――ベトナム系・カンボジア系のエスニック・アイデンティティ[清水睦美]
2‐1 はじめに
2‐2 インドシナ難民(親世代)の日本への社会移動
2‐3 第二世代のエスニック・アイデンティティ
2‐4 小括――エスニック・アイデンティティの分岐要因
第3章 親族コミュニティとの狭間で――中国帰国者三世のエスニック・アイデンティティ[坪田光平]
3‐1 はじめに
3‐2 中国帰国者家族と永住帰国政策
3‐3 親族コミュニティとの関係のなかで
3‐4 小括――中国系移民第二世代の適応過程と準拠集団の重要性
第4章 「帰国の物語」のもとでの模索――ブラジル系のエスニック・アイデンティティ[児島 明]
4‐1 はじめに
4‐2 調査の対象と方法
4‐3 ブラジル系第一世代の移動の特徴
4‐4 ブラジル系第二世代のエスニック・アイデンティティ
4‐5 エスニック・アイデンティティの分岐要因
4‐6 小括――エスニック・コミュニティへの帰属と「帰国の物語」の受容
第5章 日系という表明の消失――ペルー系のエスニック・アイデンティティ[角替弘規]
5‐1 はじめに
5‐2 ペルー系移民第一世代の移動の特徴
5‐3 ペルー系第二世代のエスニック・アイデンティティ
5‐4 エスニック・アイデンティティの分岐要因
5‐5 小括――「日系人」と表明しないことの背景
第6章 二国の狭間で揺れ動く――フィリピン系のエスニック・アイデンティティ[額賀美紗子・三浦綾希子]
6‐1 はじめに
6‐2 フィリピン系第二世代が育つ家族の構造と編入様式
6‐3 第二世代のエスニック・アイデンティティ形成と学業達成
6‐4 アイデンティティ分岐を促す構造的要因――若者たちのネットワークと家族の資本
6‐5 小括――多様なアクターを含むハイブリッドな文化空間がもつ意義
第II部 移民第二世代の学校経験
第7章 イントロダクション――生きられた経験としての排除[児島 明]
7‐1 移民第二世代と日本の学校文化
7‐2 排除のとらえ方
7‐3 知見のまとめ
7‐4 小括――移民第二世代が学校における排除に抗する道筋
第8章 同化のなかの疎外感――ベトナム系・カンボジア系の学校経験[清水睦美]
8‐1 はじめに
8‐2 子世代の不安定さ
8‐3 いじめ経験の語り
8‐4 いじめ経験におけるヴァルネラビリティ
8‐5 いじめの様相に違いをもたらす要因
8‐6 小括――学校と家族の間をどう埋められるのか
第9章 困難経験の異同と階層性――中国系の学校経験[坪田光平]
9‐1 はじめに
9‐2 中国系移民第二世代における困難経験
9‐3 困難経験の形成過程
9‐4 困難経験の克服の方途
9‐5 小括――中国系移民家族の理解に向けて
第10章 同化/差異化によるいじめの回避とその陥穽――ブラジル系の学校経験[児島 明]
10‐1 はじめに
10‐2 ブラジル系第二世代のいじめの諸相――三つの事例
10‐3 いじめはどのように生じるのか
10‐4 いじめによる困難に影響を及ぼす要因
10‐5 小括――ブラジル系第二世代にいじめ回避戦略を強いる学校の構造的要因
第11章 個人化した対処と自発的周辺化の背景――ペルー系の学校経験[角替弘規]
11‐1 問題設定
11‐2 ペルー系第二世代のいじめ経験
11‐3 個人化するいじめへの対処
11‐4 自発的周辺化
11‐5 エスニック・コミュニティとの距離、孤立した家族
11‐6 小括――いじめ経験をめぐる別の可能性
第12章 疎外感の形成と克服の方途――フィリピン系の学校経験[三浦綾希子・額賀美紗子]
12‐1 問題設定
12‐2 フィリピン系第二世代が直面する困難経験――疎外感の形成過程
12‐3 疎外感を克服する道筋
12‐4 小括――差異を認めあう学校づくりと多様な居場所の確保
第III部 移民第二世代のジェンダー
第13章 イントロダクション――出身国のジェンダー規範の世代間継承[坪田光平]
13‐1 出身国のジェンダー規範と移民家族への影響
13‐2 出身国のジェンダー規範からの解放と本章の課題
13‐3 出身国のジェンダー規範継承をめぐる親子関係の様相
13‐4 小括――三つのエスニック集団間比較
第14章 親子の協和的関係の維持――「働き者」に向かうベトナム系第二世代の女性たち[清水睦美]
14‐1 親子の協和的関係を保持する女性たち――儒教の影響
14‐2 役割逆転への向きあい方――母親の権威保持の様相
14‐3 小括――ジェンダー規範の継承のゆく先としての「働き者」
第15章 農村家族の教育期待と第二世代の進路形成――中国系の女性たち[坪田光平]
15‐1 中国系移民家族におけるジェンダーと階層
15‐2 第二世代女性の進路形成――ジェンダー規範の継承をめぐる三つの世代間関係
15‐3 小括――移民第二世代女性のエンパワーメントに向けて
第16章 ジェンダー規範の世代間再構築――フィリピン系の女性たち[額賀美紗子]
16‐1 フィリピン人女性に課された「トランスナショナルな家族ケア」
16‐2 親子間のエスニック文化継承とジェンダー規範の再構築――三つのパターン
16‐3 小括――エスニシティとジェンダーの交差性
第IV部 移民第二世代のトランスナショナリズム
第17章 イントロダクション――トランスナショナルな社会空間の世代間継承[三浦綾希子]
17‐1 はじめに
17‐2 第一世代のトランスナショナリズム
17‐3 トランスナショナルな社会空間の世代間継承
17‐4 トランスナショナルな社会空間の世代間継承の分岐を促す要因
第18章 構築される社会空間――ベトナム系第二世代のトランスナショナリズム[清水睦美]
18‐1 「難民」としての親世代のトランスナショナリズム
18‐2 子世代のトランスナショナル実践
18‐3 小括――子世代のトランスナショナル実践に影響を及ぼす要因
第19章 国境を越えるキャリア志向――中国系のトランスナショナリズム[坪田光平]
19‐1 トランスナショナルな家族の教育戦略
19‐2 中国系移民家族におけるトランスナショナルな教育戦略
19‐3 中国系移民第二世代のキャリア志向
19‐4 小括――若者たちのキャリア志向を支えるもの
第20章 国を越える家族関係の創造――フィリピン系のトランスナショナリズム[三浦綾希子]
20‐1 トランスナショナルな家族で育つフィリピン系第二世代
20‐2 第一世代によるトランスナショナルな社会空間の形成
20‐3 第二世代のトランスナショナリズム
20‐4 トランスナショナルな社会空間の世代間継承の分岐要因
終章 移民親子の文化変容が照らし出す日本の教育課題[児島 明]
終‐1 移民親子の文化変容
終‐2 エスニック集団間比較――ハイブリッド志向型アイデンティティの形成過程に注目して
終‐3 学校における「つながり」形成の意味
補章 量的データからみた移民第二世代
補‐1 問題設定[角替弘規]
補‐2 親子の衝突[坪田光平]
補‐3 言語獲得[清水睦美]
補‐4 学校経験[角替弘規]
補‐5 大学進学[額賀美紗子]
補‐6 職業観[児島 明]
補‐7 第二世代の海外就労志向[三浦綾希子]
移民第二世代インタビューリスト
参考文献
索引
執筆者紹介
関連情報
越智康詞 評 (『教育社会学研究』第111集 2023年1月24日)
https://www.toyokan.co.jp/products/5047
榎井縁 評 (『異文化間教育』第56号 2022年8月)
https://www.intercultural.jp/journal/backnumber/#n056
佐藤郡衛 (明治大学特任教授) 評 (『教育学研究』第89巻第2号 2022年6月)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/kyoiku/89/2/89_316/_pdf
高谷幸 評「「ニューカマー」と呼ばれてきた在日移民の編入過程を多角的に明らかに――移民第二世代の日本社会での経験をエスニシティ比較によって捉えた本格的な調査研究」 (『図書新聞』第3526号 2022年1月15日)
http://www.toshoshimbun.com/books_newspaper/shinbun_list.php?shinbunno=3526
是川夕 評「「ニューカマー研究」から「移民研究」へ ―移民第二世代の社会適応の分かれ目はどこにあるのか?」 (じんぶん堂 2021年9月15日)
https://book.asahi.com/jinbun/article/14435727
書籍紹介:
伊吹唯 (『移民研究年報』第28号 2022年6月)
https://imingakkai.jp/.assets/review28.pdf
共著者記事:
政治プレミア: 清水睦美 (日本女子大学教授)「日本に「移民第二世代」の居場所はあるか 「ニューカマー」の子どもたち」 (毎日新聞 2023年5月5日)
https://mainichi.jp/premier/politics/articles/20230427/pol/00m/010/011000c
講演会:
Nissan Seminar: How do Japanese public high schools respond to immigrant students? Challenges of diversity and educational equity in Tokyo (オックスフォード大学 2023年5月12日)
https://www.nissan.ox.ac.uk/event/nissan-seminar-how-do-japanese-public-high-schools-respond-to-immigrant-students-challenges-of
現代日本研究センター ブックトークシリーズ: The Second Generation Immigrants in Japan: Cross-Ethnic Comparison of ‘Newcomer’ Children Today (東京大学 2023年1月13日)
https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/events/z0707_00017.html



 書籍検索
書籍検索


 eBook
eBook