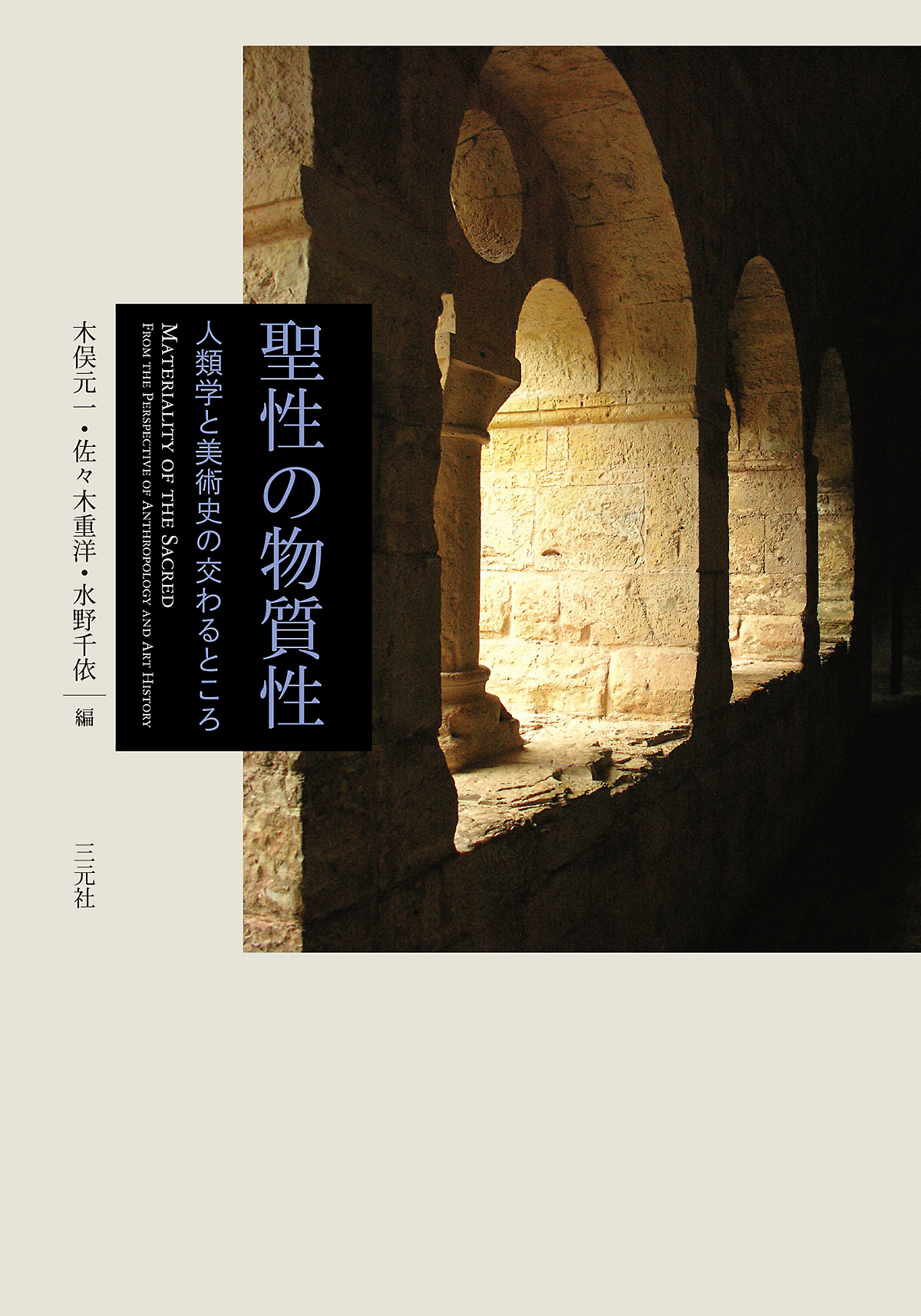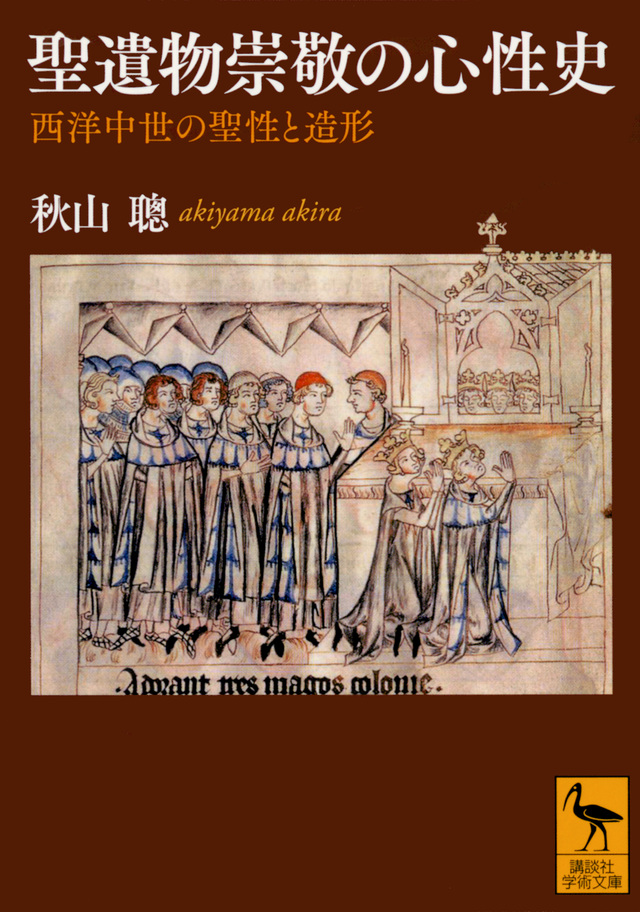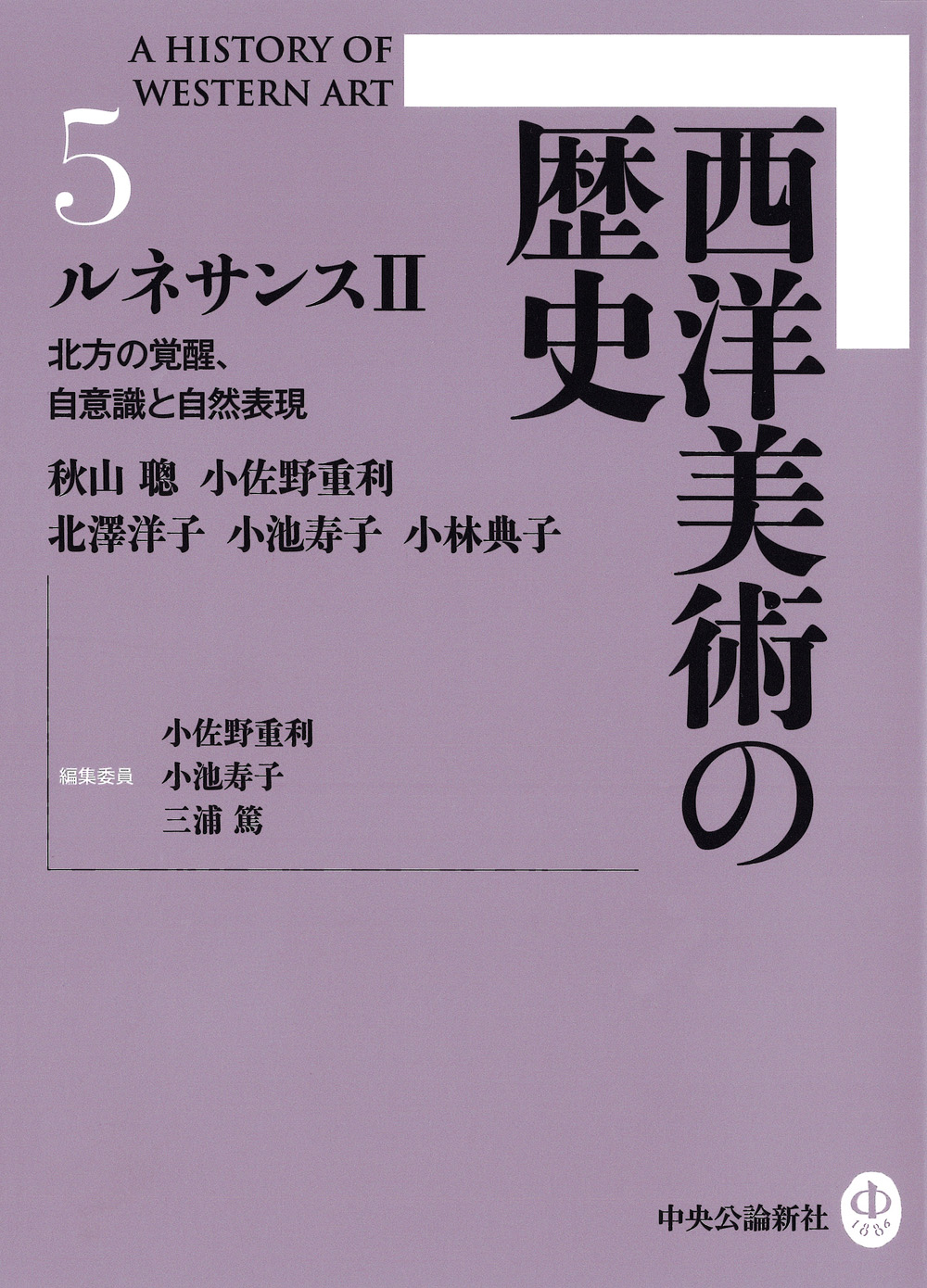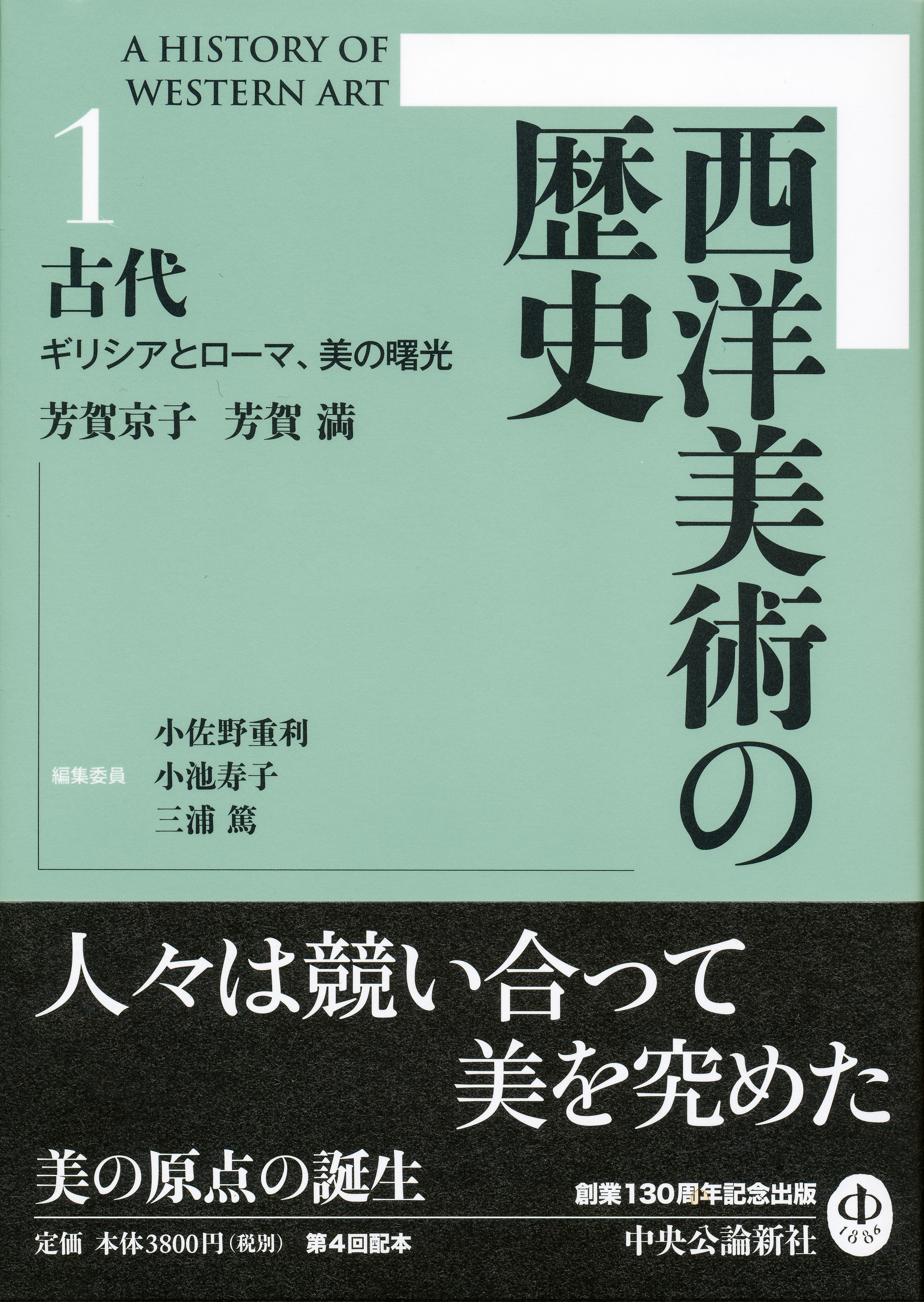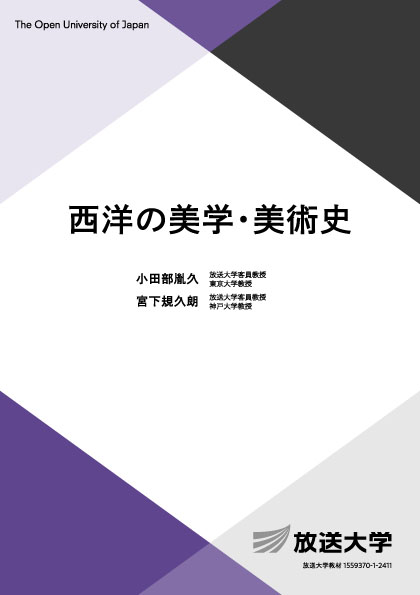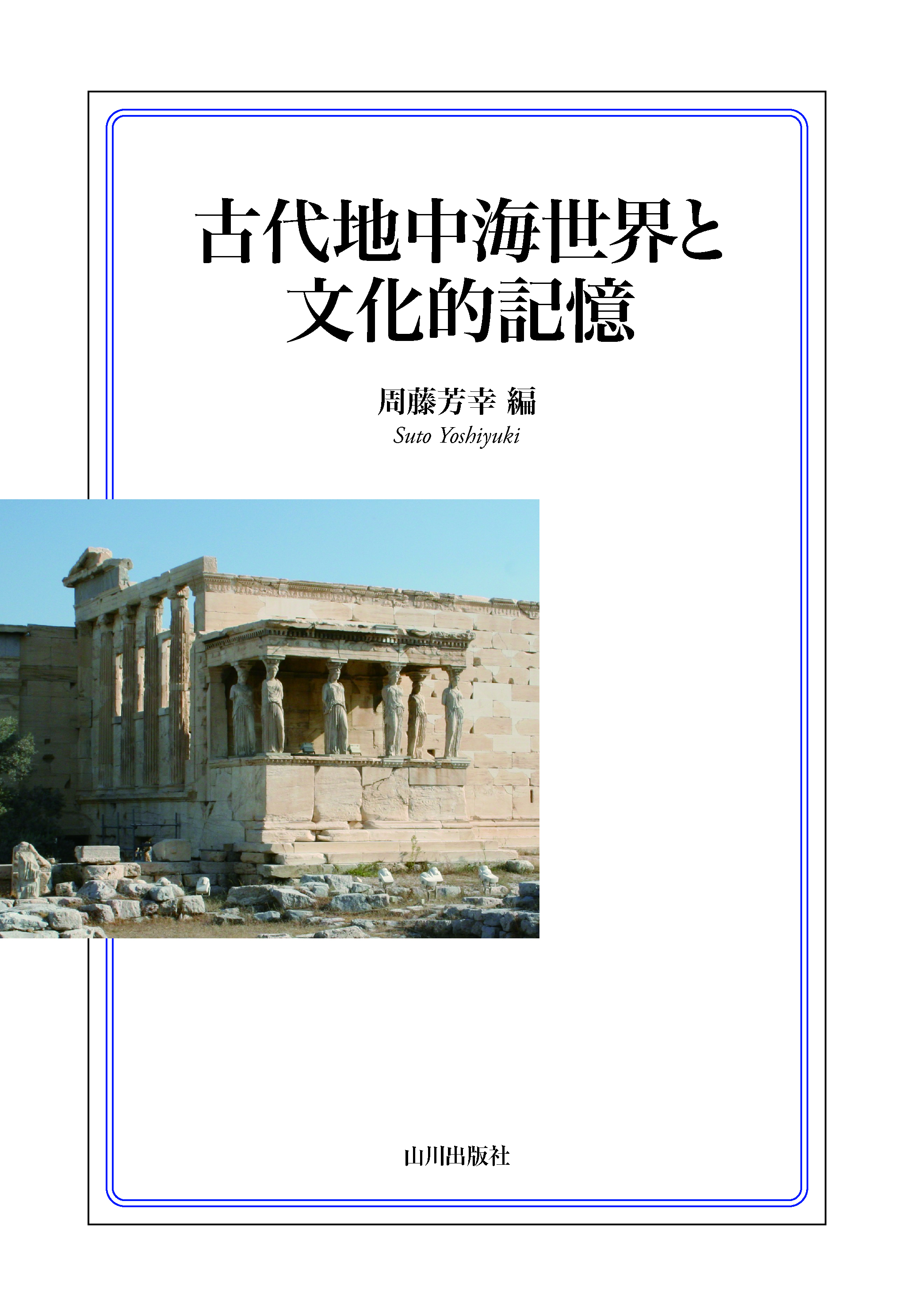ここ数十年、美術史学と人類学は相互理解 (あるいは相互批判) を続けながら、密接に関わり合ってきた。美術史界でそれを牽引したひとりが、2023年1月に亡くなったハンス・ベルティングである。彼が『美術史の終焉?』を上梓したのは1983年だから、もう40年前のことになる (邦訳は1991年)。刺激的なタイトルは、造形物のなかで「美術品」と呼ばれるものだけを研究の対象とし、その様式発展や図像解釈にばかり傾注する従来の美術史学に疑問を投げかけるものだった。彼はもとは西洋中世美術の研究者なのだが、宗教美術を扱うなかで、絵画や彫刻といったいわゆる「美術品」よりも広範な「イメージ」に向き合い、それが有するさまざまな「力」やメディア性を考察した。これは同時代の人間の生活全体を研究対象とする、文化人類学の手法を援用したものだった (『イメージ人類学』、原著2001年、邦訳は2014年)。
同じ頃、文化人類学の領域でも「アート」が積極的に取り上げられるようになる。この場合の「アート」は西洋的な意味での「芸術」や「美術品」ではなく、それぞれの民族文化のなかで生み出されたモノ、物質性をそなえた造形物を指す。アルフレッド・ジェルは、遺作『アートとエージェンシー』(1998年、未邦訳) のなかで「アート」が周囲に及ぼす力を「エージェンシー」と呼び、アートと人とその周辺がどのような関係にあるのかを分析した。
ジェル以降、美術史学と文化人類学にまたがる分野横断的な研究はますます盛んになった。美術史の側では、ベルティングに限らず、キリスト教美術の研究者がとりわけこの試みに熱心だった。キリスト教は神の物質性を否定しながらも、聖なるイメージを物質的なものとして表現し、礼拝せずにはいられなかった。だから彼らにとって、本書のタイトルにもなっている「聖性の物質性」はひときわ切実で、避けることのできない重要な問題なのである。
本書のベースとなっているのは、西洋中世美術史を専門とする木俣元一氏を研究代表者とする共同研究「キリスト教美術」におけるイメージの意味と物質性: 新たな図像学の構想に向けて」(科学研究費基盤研究B、2019~2023年度) である。しかし本書にはこの研究の分担者のほかに、キリスト教美術以外を専門とする15人の研究者が加わっている (かくいう紹介者も、書籍の段階で加わったひとりである)。第I部の2本の基調論文のほか、5つのサブ・テーマに分類された23本の論考は、「聖性と物質性」というメイン・テーマとゆるやかに結びついている。もし第I部から読み進めるのが難しければ、まずはサブ・テーマのどれかを選び、そのなかの論文すべてに目を通してみてはどうだろう。地球上のまったく別の地域や時代で、人間がモノに対してどのような感覚を抱くのか、それを研究者としてどのように分析するのか、新鮮な驚きがあるのではないだろうか。それこそが、分野・領域横断型研究の醍醐味なのである。
(紹介文執筆者: 人文社会系研究科・文学部 教授 芳賀 京子 / 2023)
本の目次
第I部 基調論文
基調論文1 「物質性」から広がる人類学研究の地平 佐々木重洋
基調論文2 生命体と非生命体とのあわい──美術史研究における「物質性」の射程 水野千依
第II部 経験・思考・想像力
誘惑の美学──イヌイト・アートにみる「生き方としての芸術」の可能性 大村敬一
継起する自己/イメージ──ナイル系牧畜社会における牛、紙、神性 橋本栄莉
モノを介したアナロジーの思考──オゴテメリとグリオールによる神話の釈義を事例として 中尾世治
イメージと規律=訓練──ティム・インゴルド批判 出口 顯
至聖所のカーテンとストラスブール大聖堂南袖廊──タイポロジーにおける物質性 木俣元一
第III部 人格・エージェンシー・生動性
夢ないし幻視における像の生動性についての比較美術史的考察 秋山 聰
長谷寺本尊十一面観音像の秘仏化と開帳 奥 健夫
ロココ絵画に描かれた彫像の生動性──信仰から愛好の対象へ 杉山奈生子
分配される人格/結晶する人格──像の人格化をめぐる文化横断的比較 水野千依
第IV部 聖性・奇跡・交渉
《アルテミス・エフェシア》──偶像に宿る聖性の継承と分与 芳賀京子
ネーデルラントにおける奇跡像と奉納像──中世から現代へ 杉山美耶子
トリエント公会議以後のフランスにおける聖画像論と美術──「キリストの顔」をめぐって 栗田秀法
金沢市真成寺の鬼子母神像 森 雅秀
バリ・ヒンドゥー教における「異界」との交流──可視化される神と物質性 廣田 緑
第V部 空間・環境・設え
キリスト教礼拝空間における典礼設備の物質性と象徴性 奈良澤由美
後期ビザンティンの聖堂における光の演出と聖性──イェラーキ (ギリシャ) の聖ヨアンニス・クリソストモス聖堂 樋口 諒
不可視の神との対話のメディウムとしての祭壇画──ジョヴァンニ・ベッリーニ作《ディレッティ祭壇画》を事例として 須網美由紀
神秘体験と日本建築──懸造・熊野詣の建築的仕掛け 松﨑照明
第VI部 儀礼・パフォーマンス・演出
〈集まり〉としての憑依──アフロブラジリアン宗教における人間・モノ・憑依霊 古谷嘉章
色彩における物質性と聖性──イヴ・クラインの芸術実践における聖別と涜神のあわい 松井裕美
神格との相互交渉と物質性──中動態的協働としての「神人和合」 佐々木重洋
あとがき
人名索引 I
事項索引 IV
関連情報
https://toshoshimbun.com/news_detail?article=1704210976957x200840609570013060
稲賀繁美 評 「五感では不可触な領域との接触を、いかに物質のうちに定位するか? 木俣元一・佐々木重洋・水野千依編『聖性の物質性――人類学と美術史の交わるところ』(三元社)を、Alfred Gell,Art and Agency, An Anthropological Theory(Oxford University Press, 1998)ほかと交差させて読む」 (『図書新聞』No. 3567 2022年11月12日)
https://toshoshimbun.com/news_detail?article=1704210980755x590613974592522100
余瑋 「書籍紹介」 (『民具マンスリー』第55巻7号 2022年10月)
https://www.i-repository.net/il/meta_pub/G0000723jmmonthly_153788
「ART BOOKS 新刊案内」(サン・アート) (『月刊美術』No.561 2022年6月)
https://www.gekkanbijutsu.co.jp/backnumber/2206/
「今月の読みたい本!」 (TOKYO ART BEAT 2022年4月1日)
https://www.tokyoartbeat.com/articles/-/books-2022-04-01



 書籍検索
書籍検索