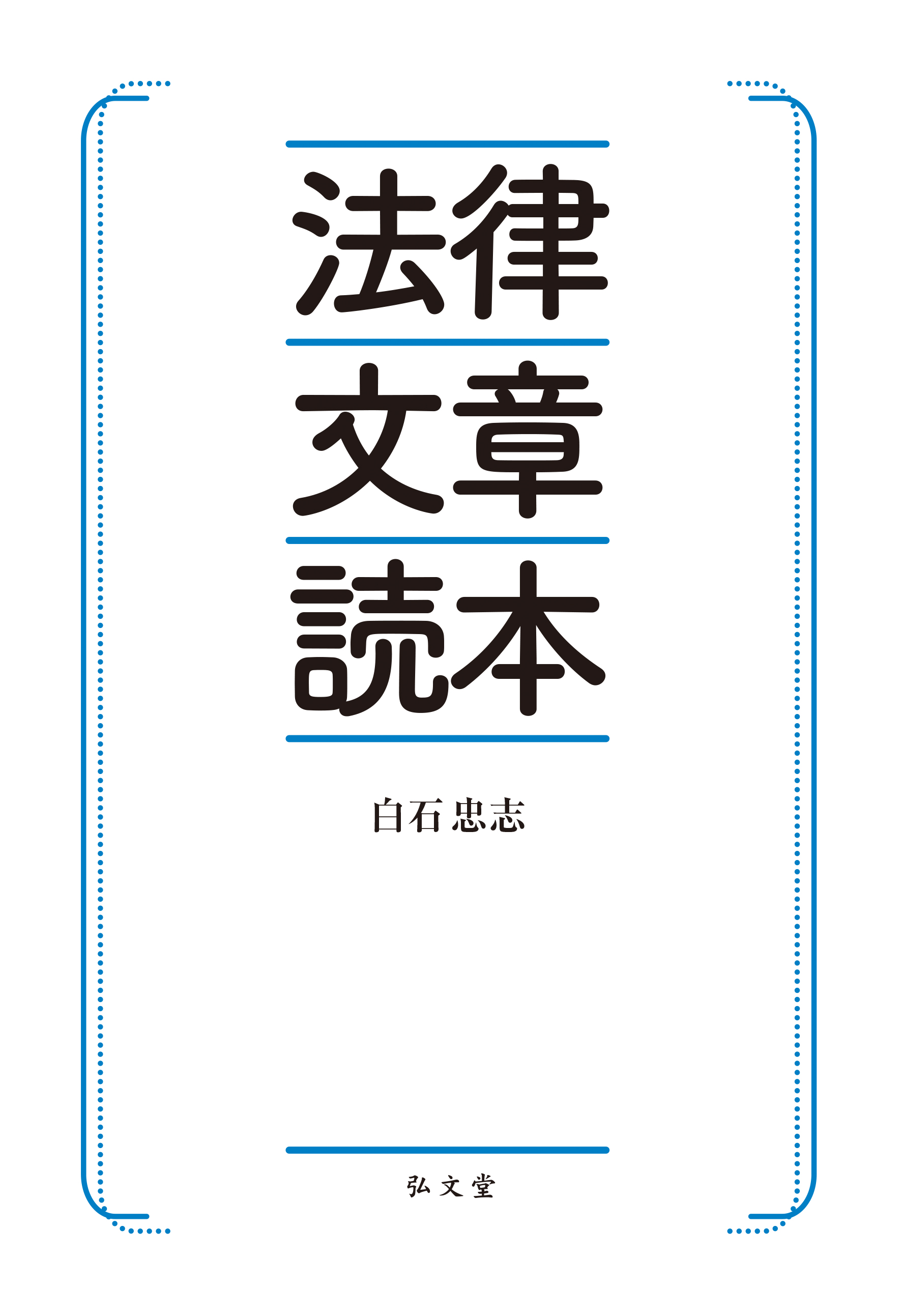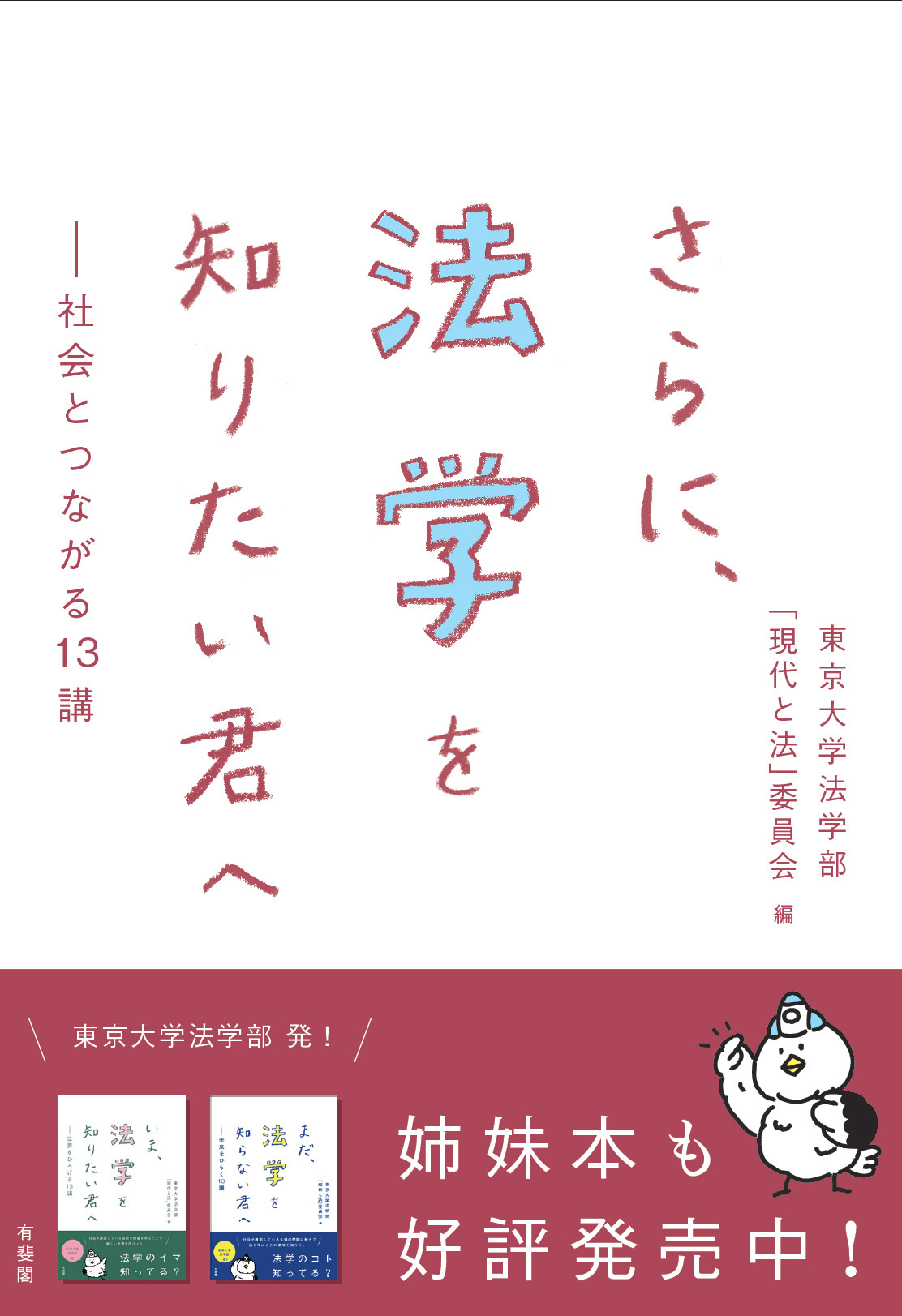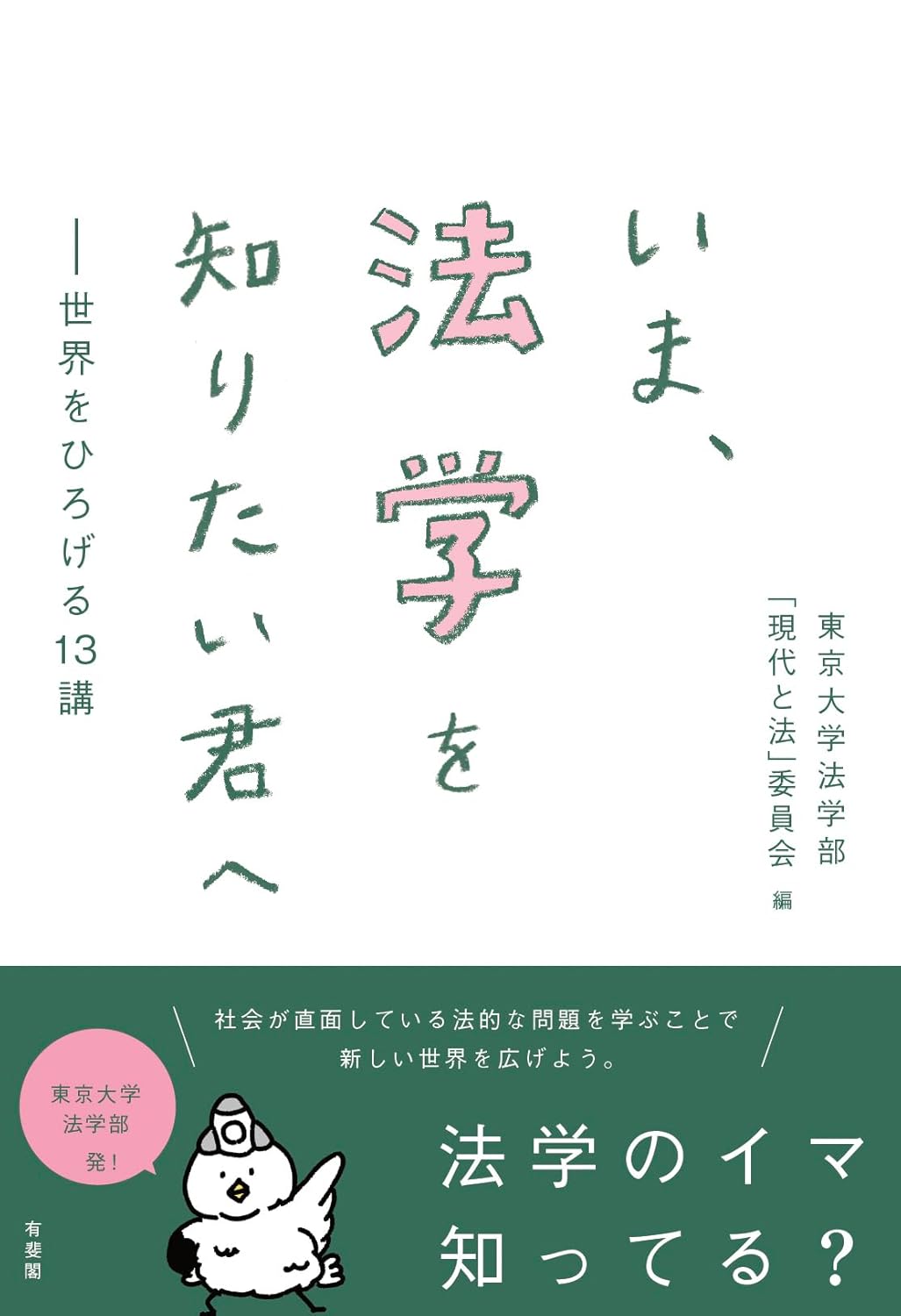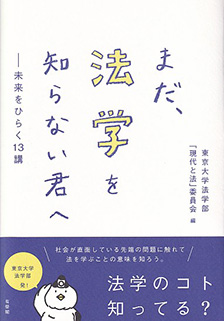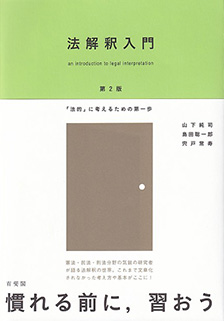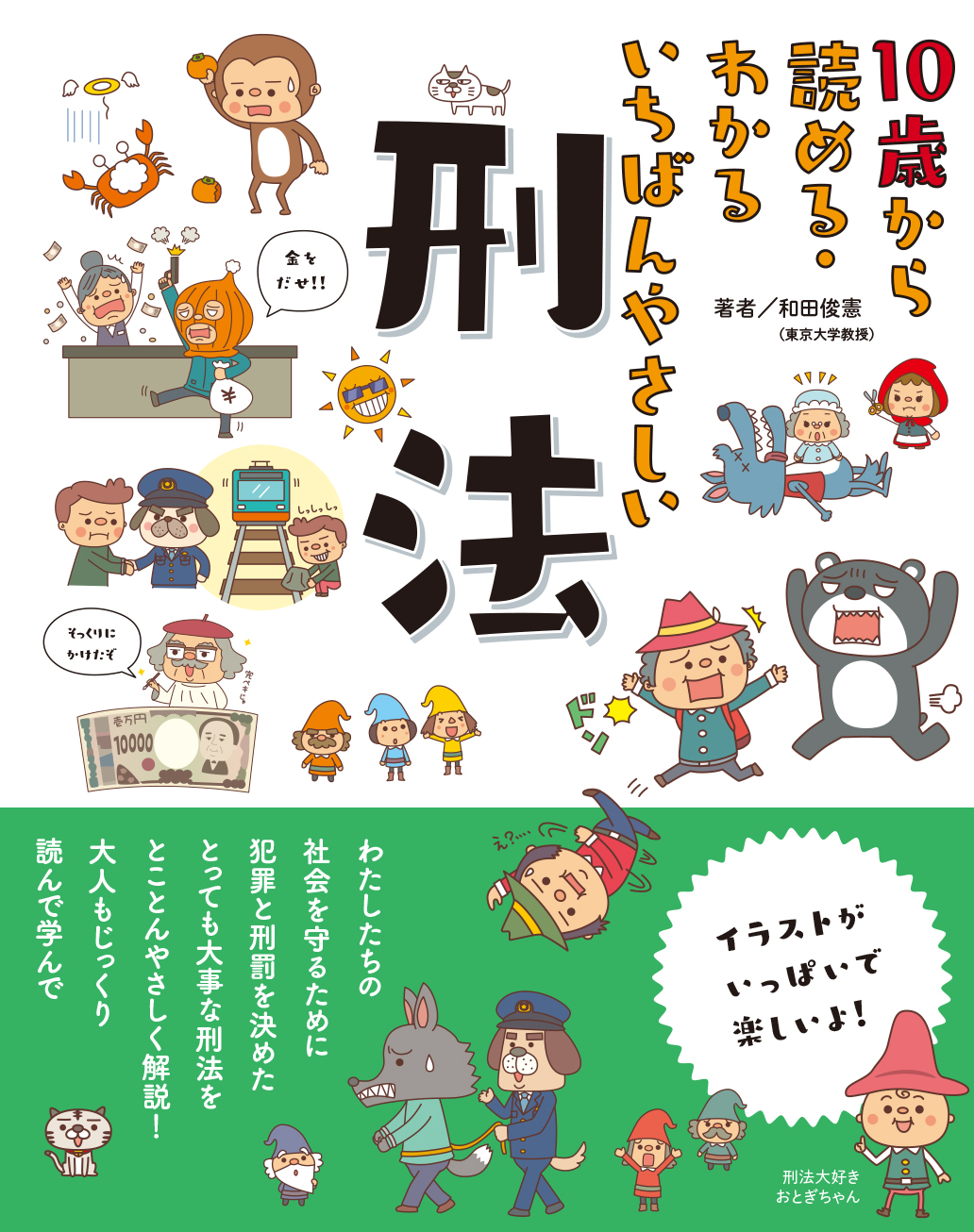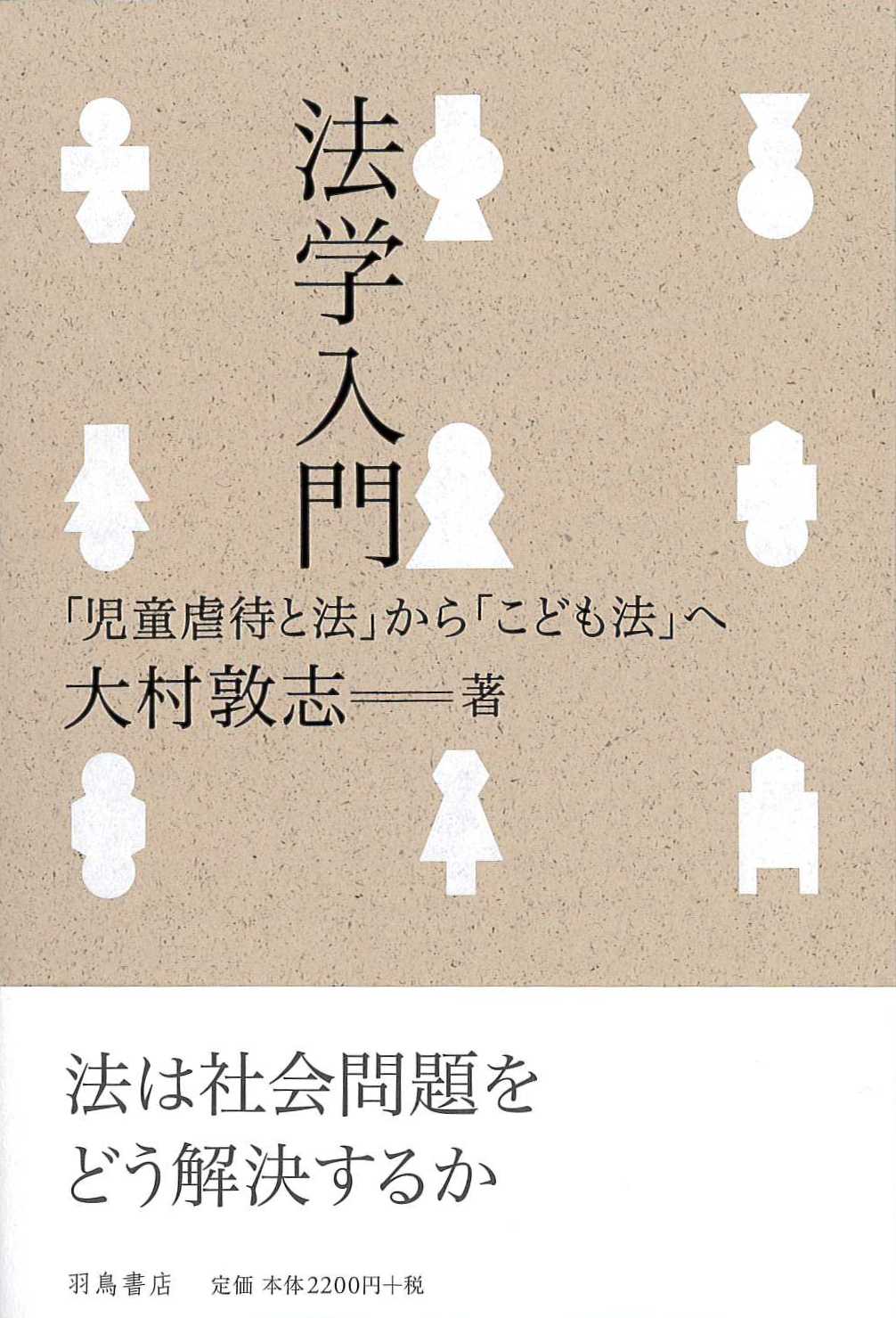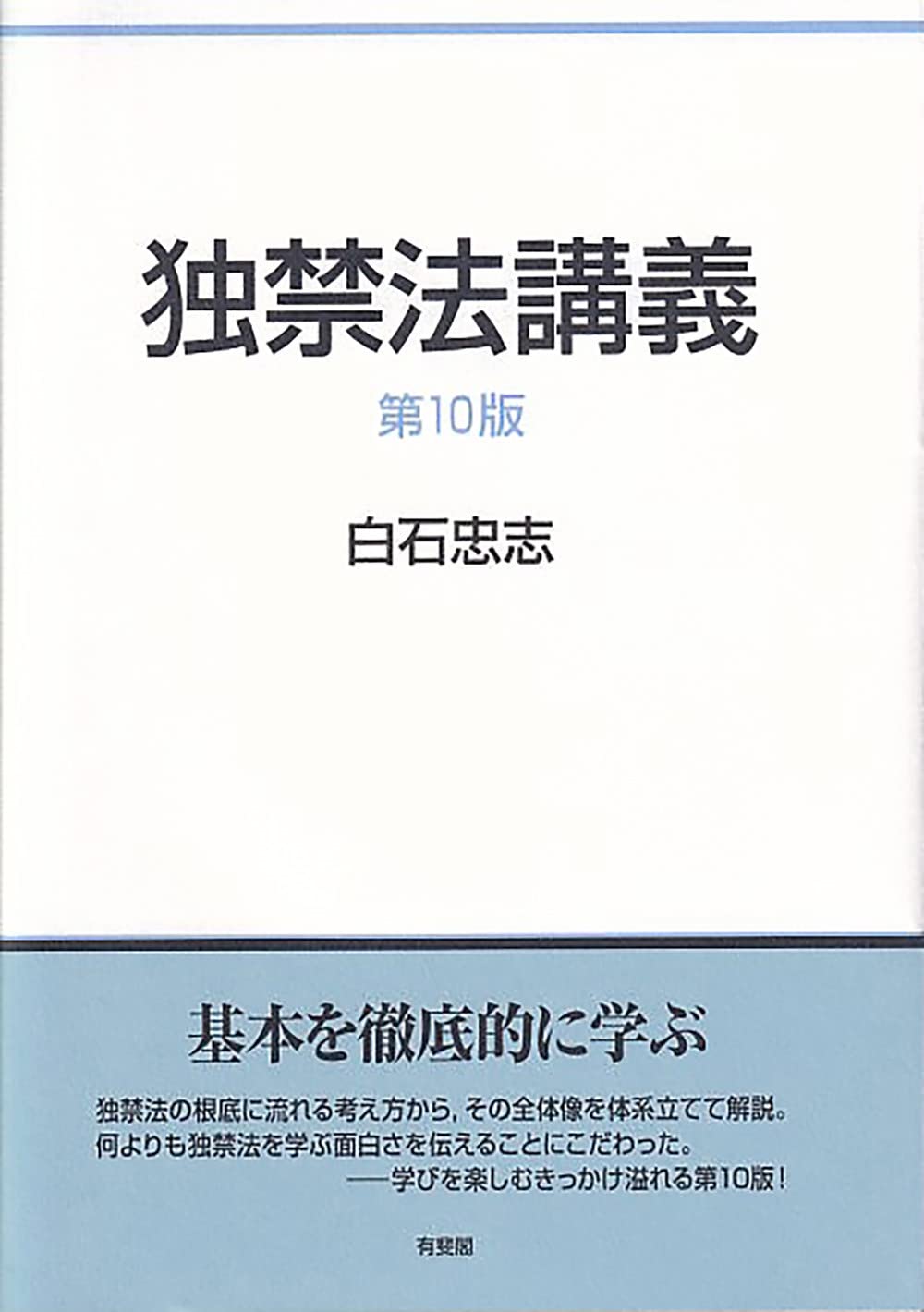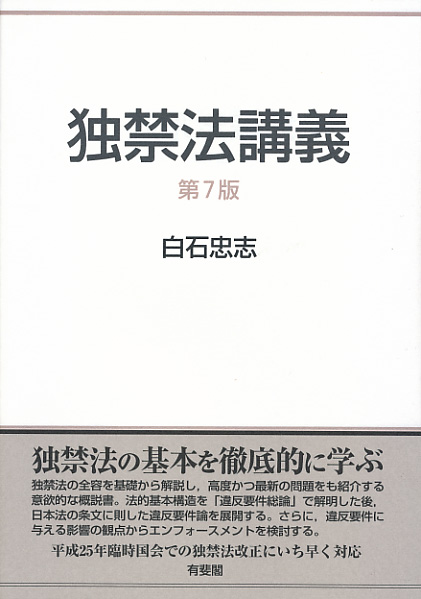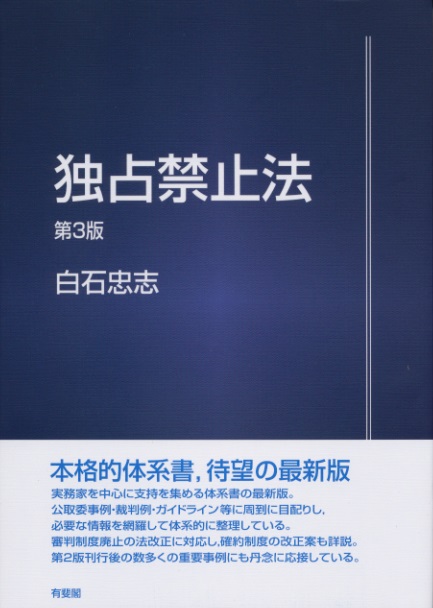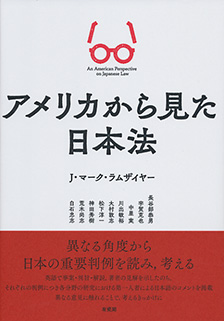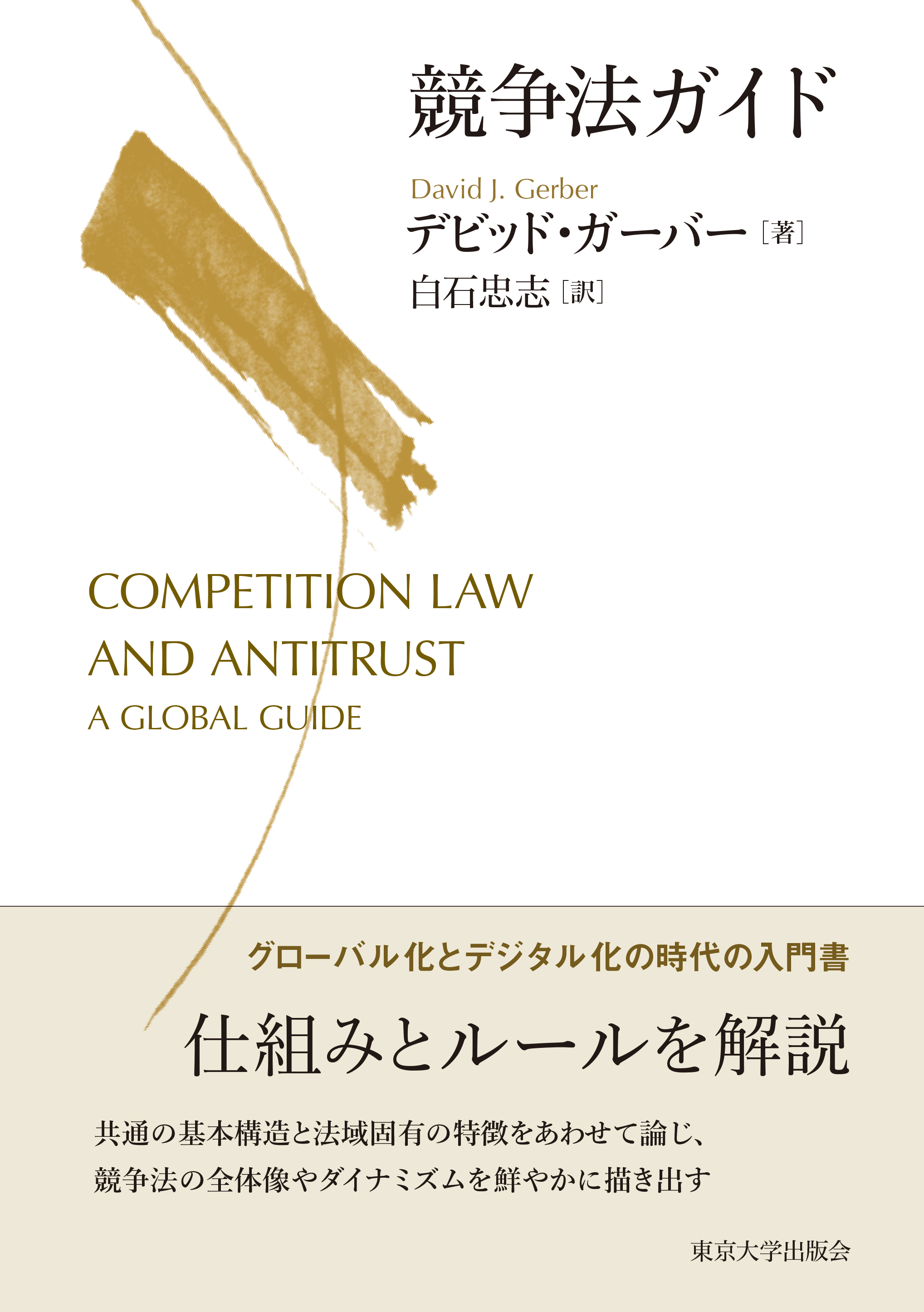本書は、法的な内容を含む文章が読み手に向けて正確に分かりやすく伝わるようにするためのヒントを、まとめたものである。法的な内容を含む文章としては、法令、行政文書、裁判文書、契約書などだけでなく、それらを解説する文章、民間企業を含めた一般社会における意思伝達の手段となる文章、法学の試験答案やレポートなどに期待される文章、なども想定している。
本書では、そのような文章を「法律文章」と呼んでいる。
本書の特徴を挙げると、次のようになるであろう。
・ 条文の読み方や扱い方の基本を解説した。
・ 公用文の標準的なルールを解説した。
・ 法律文章を書く際の私個人の心掛けを紹介した。
法律文章を正確で分かりやすいものとすることは、複雑化した現代における必須の課題である。頭脳・労力・時間は、不正確な文章や難解な文章を読み解くために使うのではなく、有益なことに振り向けるべきではないか。そうであるとすると、正確で分かりやすい文章を書く技法は、社会にとっての必須のインフラとなるはずである。世界は複雑であり、人間の持ち時間は少ない。
条文の読み方や扱い方、公用文の標準的なルールは、法学を学ぶにあたっての初歩的で基本的な前提であるはずであるが、これまで、それを系統立てて教える仕組みはほとんど存在しなかった。日本の法学教育では、そうした基本を教える構えが十分でない。そしてそれは、日本の法学教育の構造にも原因があるのではないかと思われる。日本の法学教育の構造といっても、私が考えているのは難しいことではない。既に存在する制度や条文の解釈と適用が中心となっており、条文を書いて、制度を作り、改める、という営みが、思考回路から抜け落ちがちではないか、ということである。したがって、体系的に教える用意がなく、不確かな見よう見まねが伝承される傾向がある。
法学を学ぼうとする学生は、既に存在する制度や条文の解釈と適用だけでなく、制度を作り条文を更地から書くことも、学びたいはずである。たしかに、作った制度や条文がどのように解釈され適用されていくかの相場観がなければ、適切な制度や条文を作ることはできない。しかし、解釈と適用ばかりでは、法学に対する期待に応えることはできないし、法学の魅力を磨くこともできないのではないか。
本書は、そのようなことも考えながら書いた。
(紹介文執筆者: 法学政治学研究科・法学部 教授 白石 忠志 / 2024)
本の目次
1 本書について
2 正確で分かりやすい文章
3 「公用文作成の考え方」について
4 本書の構成
第1章 入門
1 条・項・号
2 条・項・号をめぐる基本の続き
3 古い用語・表記について
4 基本的なルール
5 基本的な法律用語
6 入門を終えて
第2章 文書
1 文書を作成する際の基本的な考え方
2 正確で分かりやすい文章
3 文体
4 構成
5 字下げ (インデント)
6 文書全体の分量
第3章 文
1 外国語であると考えることについて
2 公用文考え方が掲げる留意点
3 一文を短く?
4 箇条書
5 主語を明示し、それに述語を対応させる
6 どこまで係るのかを明らかにする
7 単語の切れ目を明瞭にする
8 前後・上下・左右などを不用意に入れ替えない
9 読点の打ち方
第4章 用語
1 造語について
2 専門用語
3 外来語
4 紛らわしい言葉に留意する
5 用語に関するその他の留意事項
6 知っておくと便利な法律用語
第5章 表記
1 漢字の使い方
2 送り仮名の付け方
3 外来語の表記
4 数字の表記
5 符号の使い方
6 表記に関するその他の原則
おわりに
1 条文の読み方や扱い方に関すること
2 公用文に関すること
3 私個人の心掛けに関すること
関連情報
柴田堅太郎 評 (『ビジネス法務』 2024年9月号)
https://www.chuokeizai.co.jp/bjh/archive/detail_010872.html
岡本隆司 評「無味乾燥 万人のルール」 (『読売新聞』 2024年8月4日朝刊)
https://www.yomiuri.co.jp/culture/book/reviews/20240805-OYT8T50021/
田辺治 評 (『公正取引』885号 p. 81 2024年7月)
https://www.koutori-kyokai.or.jp/pages/258/
書籍紹介:
沖野眞已【巻頭言】マルをつけよう運動 (『法学教室』No.527 2024年7月26日)
https://www.yuhikaku.co.jp/hougaku/detail/021339
関連イベント:
伝わる法律文章の秘訣ってなんだろう?『法律文章読本』出版記念鼎談 白石忠志×興津征雄×横田明美 (ジュンク堂書店池袋本店 2024年8月6日)



 書籍検索
書籍検索