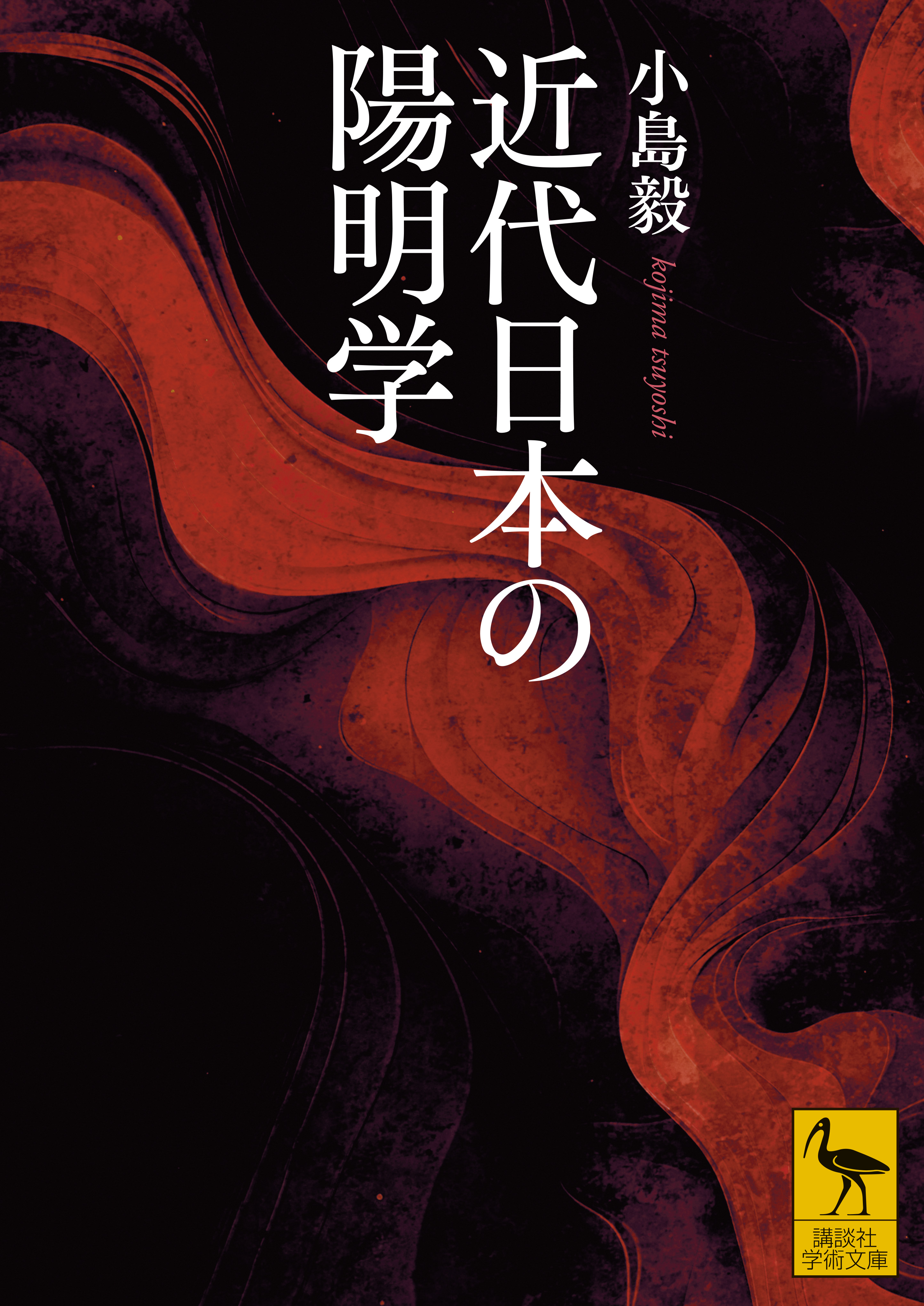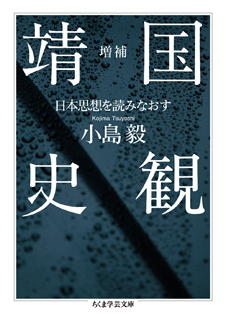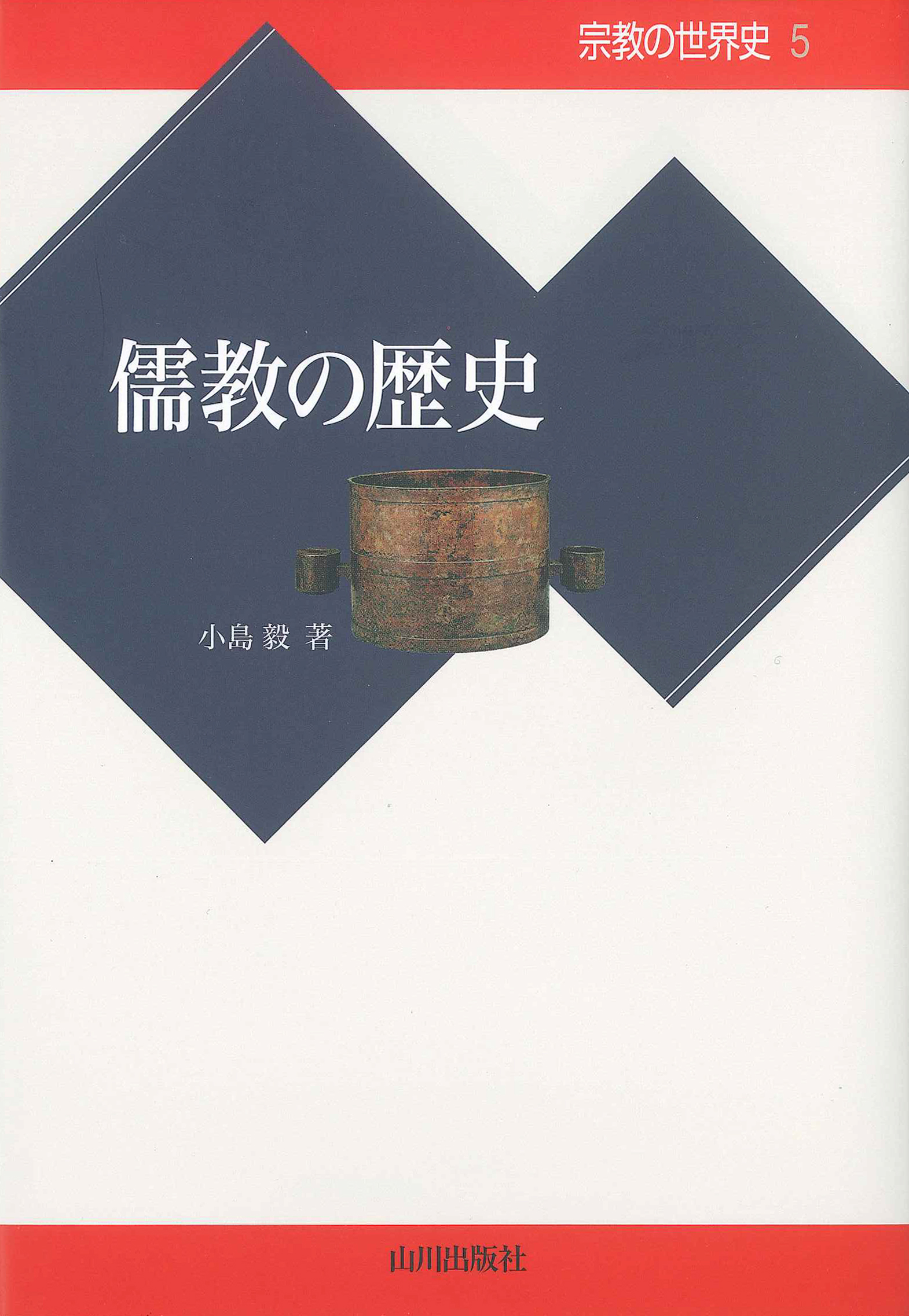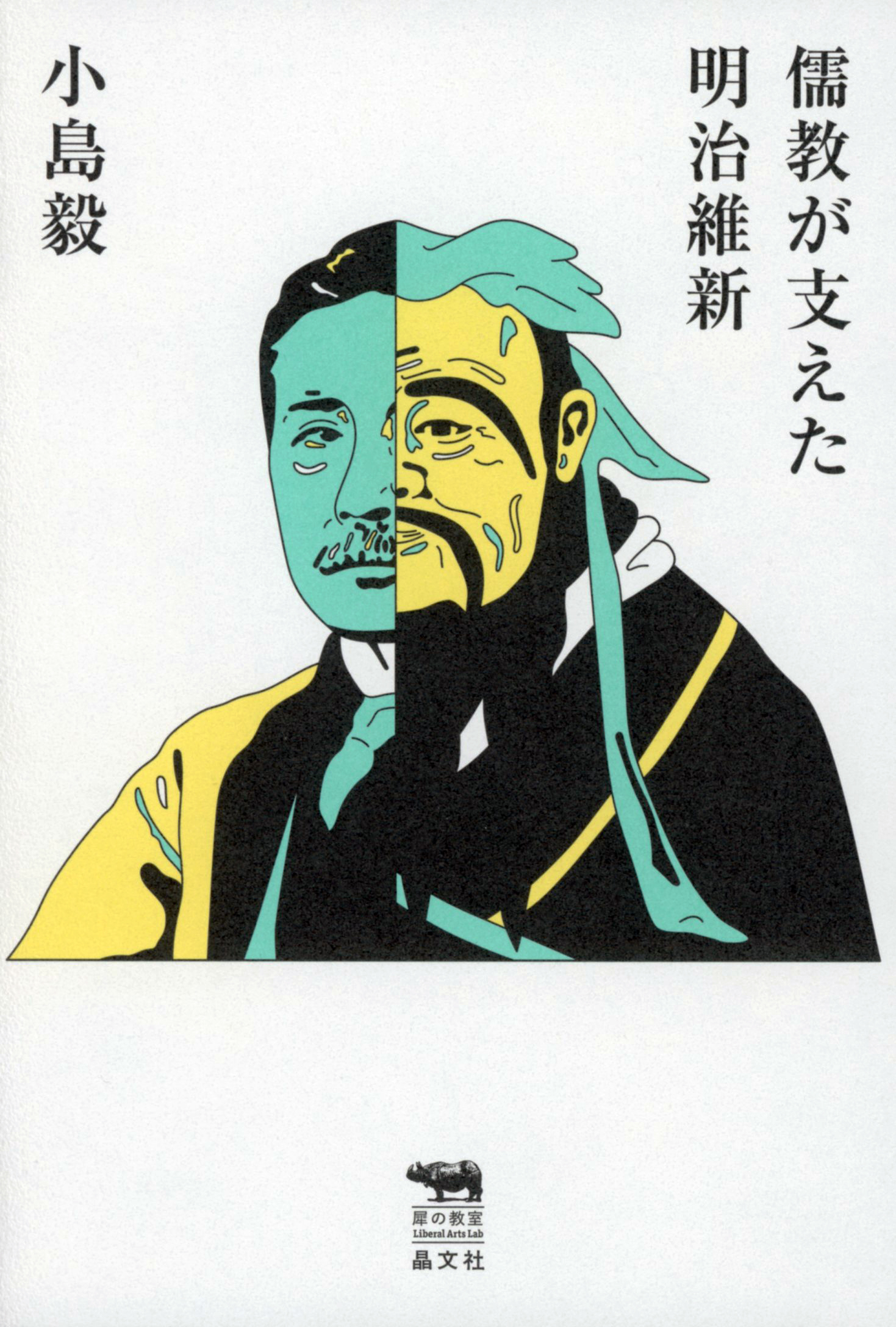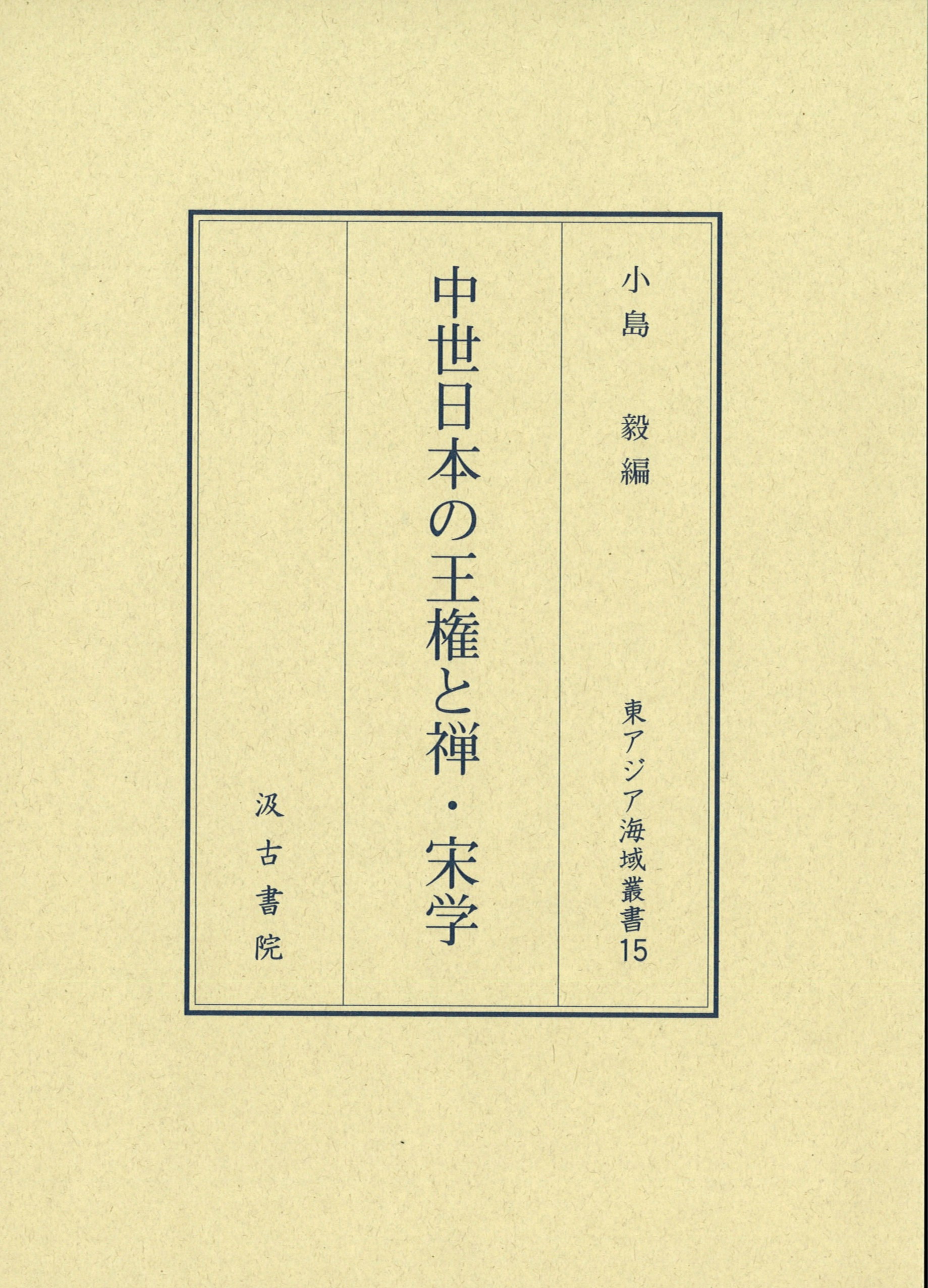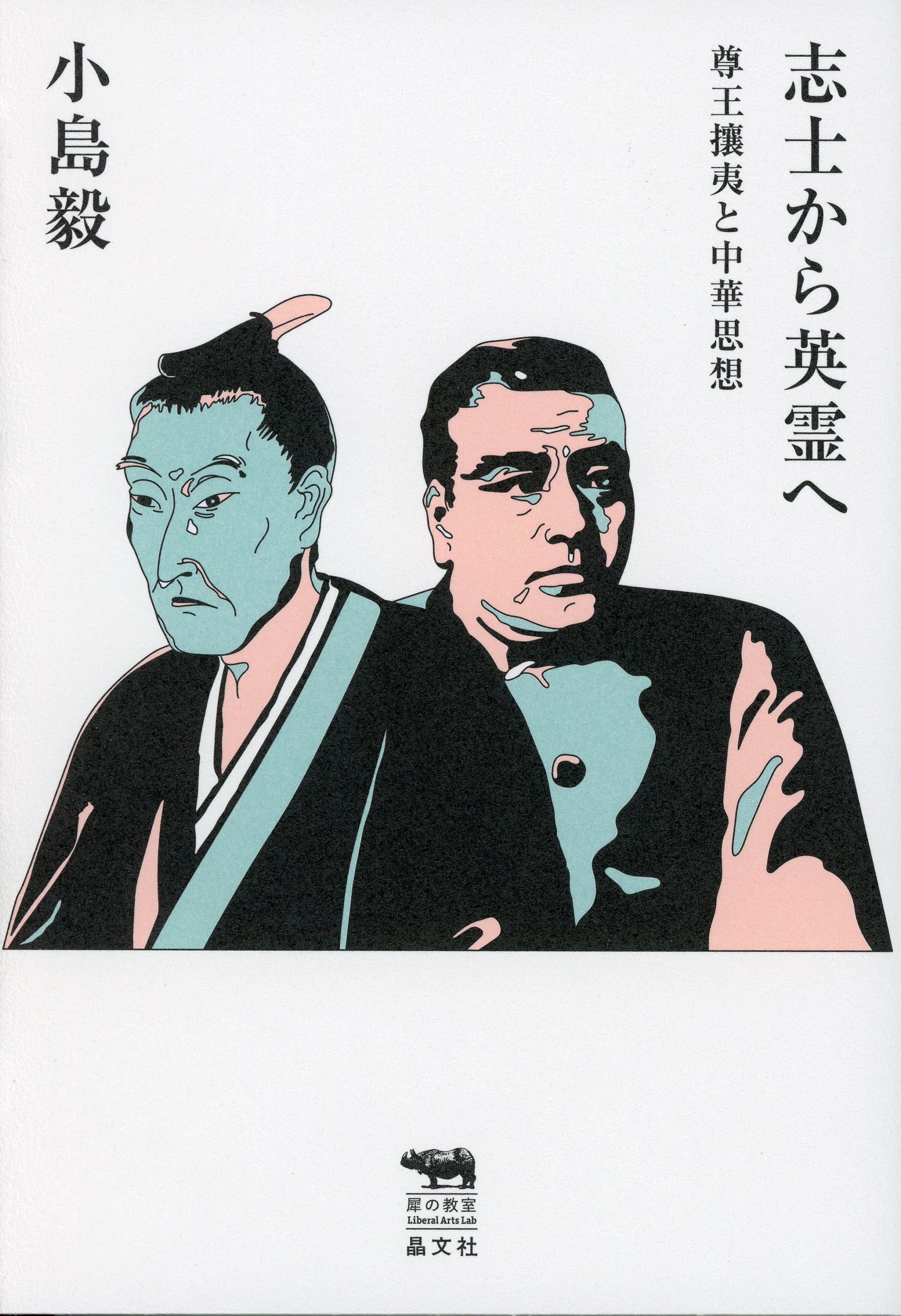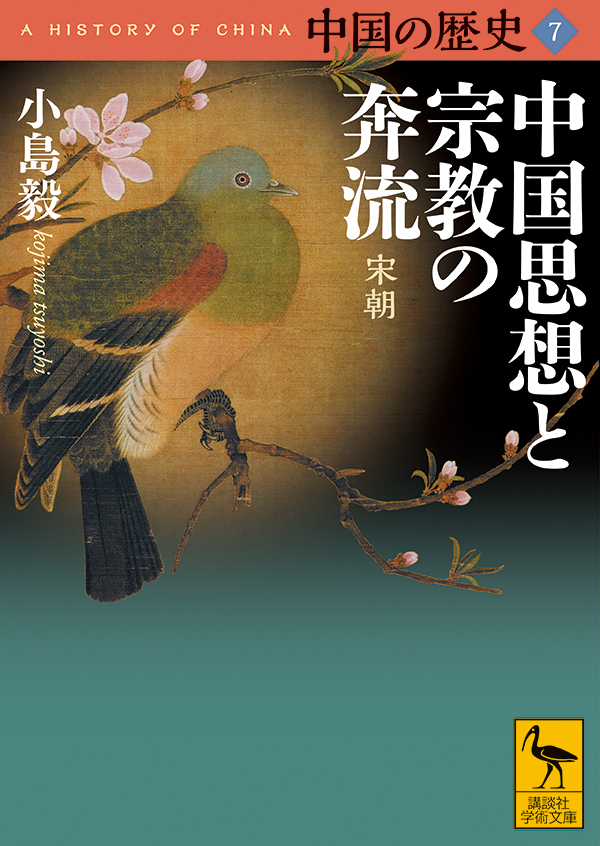陽明学は儒学の一流派として中国の思想家王守仁 (陽明は彼の雅号) が16世紀初めに提唱したもので、それ以前に主流派だった朱子学を批判したとされている。やがて日本にもその書物が伝来し、17世紀の中江藤樹とその弟子熊沢蕃山は教科書的には陽明学者に分類されている。
本書は1837年に大塩平八郎 (中斎) が大坂で武装蜂起した事件に始まり、1970年に三島由紀夫が東京で割腹自殺を遂げるまで、近代日本で陽明学的な感性を具えていた思想家・運動家たちをずらりと紹介し、その功罪を論じたものである。
従来の研究は陽明学者とされる人たちの伝記と著述内容の紹介に概ね終始していた。それに対して本書では彼らがどのように「陽明学的」なのか、そしてそれはなぜなのかを、各人の時代背景や生まれ育った環境に即して論じ、「朱子学的」な考え方に彼らが納得しなかった共通項を探る試みをしている。「朱子学は性即理、陽明学は心即理」とだけ暗記している人たちに、陽明学の魅力と危うさを理解してもらいたいという動機から執筆した。陽明学の思想内容については拙著『朱子学と陽明学』(現在はちくま学芸文庫で刊行) を参照されたい。
本書はもともと2006年に講談社選書メチエの1冊として刊行された。執筆時には小泉純一郎首相が在任中で、靖国神社参拝問題を巡って中国との外交関係が微妙になっており、本書に続けて書いた拙著『靖国史観』 (UTokyo BiblioPlazaに掲載) と同じく靖国礼賛派の心性を歴史的に説明する意図があった。それから約20年、東アジアの国家間の力関係は大きく変化しているが、日本が19世紀後半から20世紀前半にかけて為した所業について彼我の歴史認識は今も大きく食い違ったままである。
「文庫版あとがき」に記したように、本書は韓国語訳が出版されたのに対して、中華人民共和国での訳出刊行の計画は内容に差し障りがあるということらしく中止された。この20年、著者は問題関心を「日本的陽明学の危うさの指摘」から「東アジアにおける自由・自律の問題」へと移してきた。この文庫版にはこのような観点から、原著刊行後に著した陽明学関連の文章のうち4篇を「増補」として収載している。その最後に渋沢栄一についての論考がある。渋沢は青年時代には本書の主役たちと同じくディオニュソス的だったけれど、明治になってからは日本経済を近代化するため見事にアポロン的な役割を果たした。今年 (2024年) から1万円札の顔となったのを記念して、読者に彼の自由論を知ってもらおうと本書に入れている。「前任者」の福澤諭吉が終生一貫してアポロン的であり (=彼は尊攘派志士にはならず、また上野での彰義隊と新政府軍との戦闘当日にも慶應義塾を休校にしなかった)、それゆえか丸山眞男のお気に入りの思想家だったことなど思い合わせて読んでもらいたい。
(紹介文執筆者: 人文社会系研究科・文学部 教授 小島 毅 / 2024)
本の目次
プロローグ―靖国「参観」の記
エピソードI 大塩中斎―やむにやまれぬ反乱者
1 「乱」と呼ばれて
2 陽明学ゆえの蜂起?
3 知己頼山陽
エピソードII 国体論の誕生―水戸から長州へ
1 藤田三代の功罪
2 『大日本史』の編集方針
3 自己陶酔する吉田松陰
エピソードIII 御一新のあと―敗者たちの陽明学
1 陽明学を宮中に入れた男
2 陽明学を普遍化させた男
3 陽明学をキリスト教にした男
エピソードIV 帝国を支えるもの―カント・武士道・陽明学
1 明治のカント漬け
2 武士道の顕彰
3 陽明学の復権
4 白い陽明学、赤い陽明学
エピソードV 日本精神―観念の暴走
1 ある国家社会主義者のこと
2 西洋思想で説く東洋の革命
3 碩学か幇間か
エピソードVI 闘う女、散る男―水戸の残照
1 水戸の血と死への美学
2 「青山菊栄」の戦後
3 「その日」まで
4 その日
5 アポロンが演じたディオニュソス
6 それから
エピローグ
増補
I 近代における朱子学・陽明学
II 亘理章三郎と西田幾多郎の陽明学発掘作業
III 中江兆民の自由論
IV 渋沢栄一の自由論
主要参考文献
あとがき
主要登場人物略伝
本書関連年表
索引



 書籍検索
書籍検索