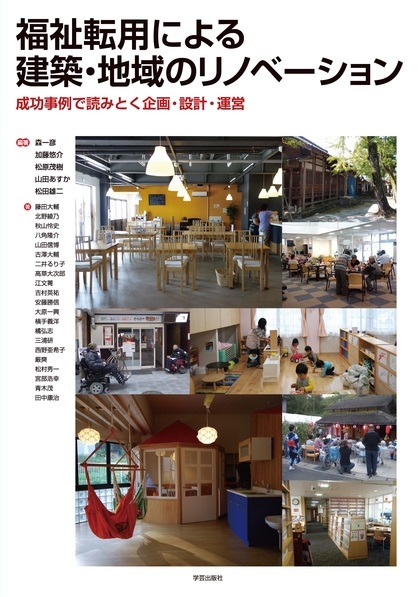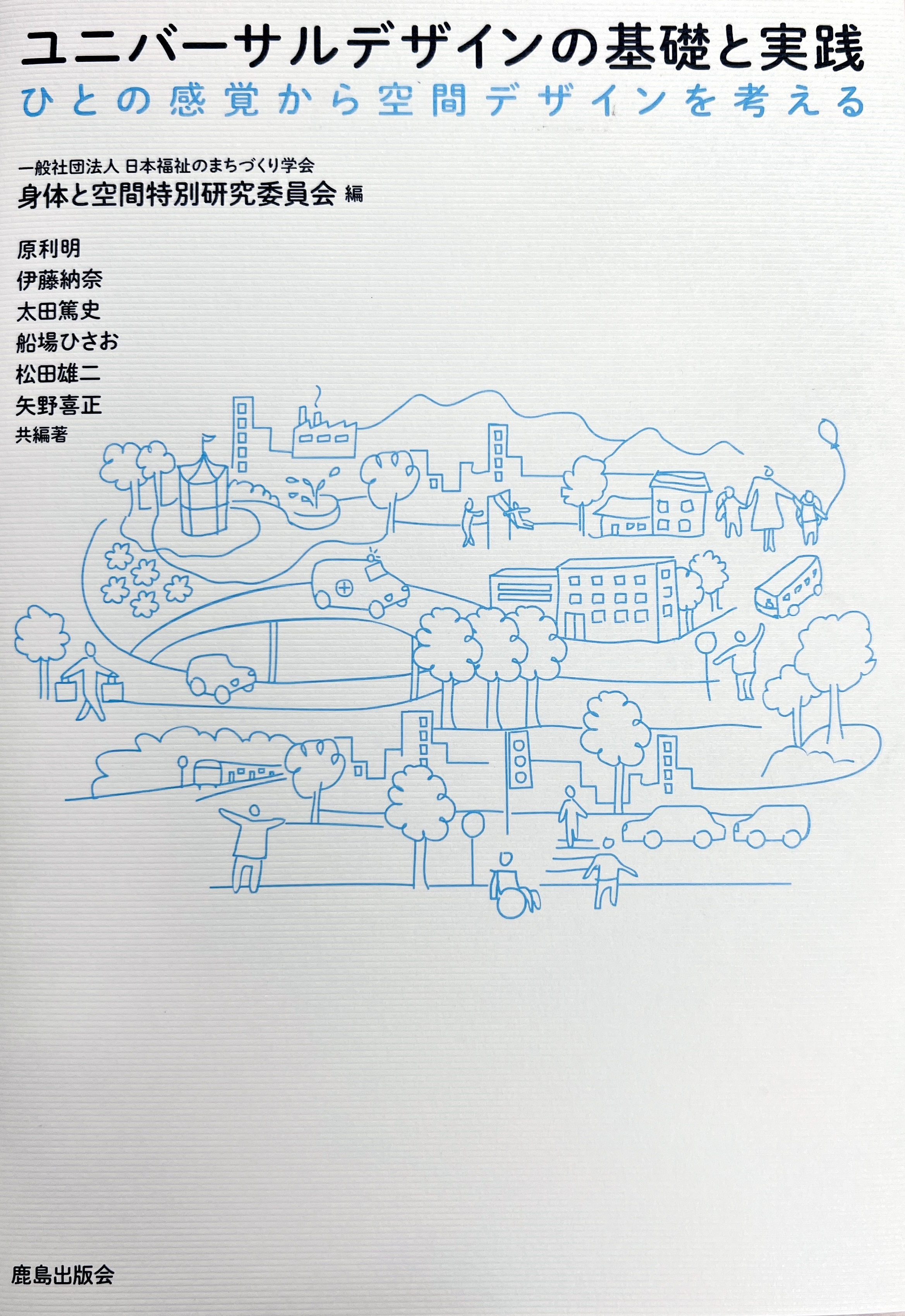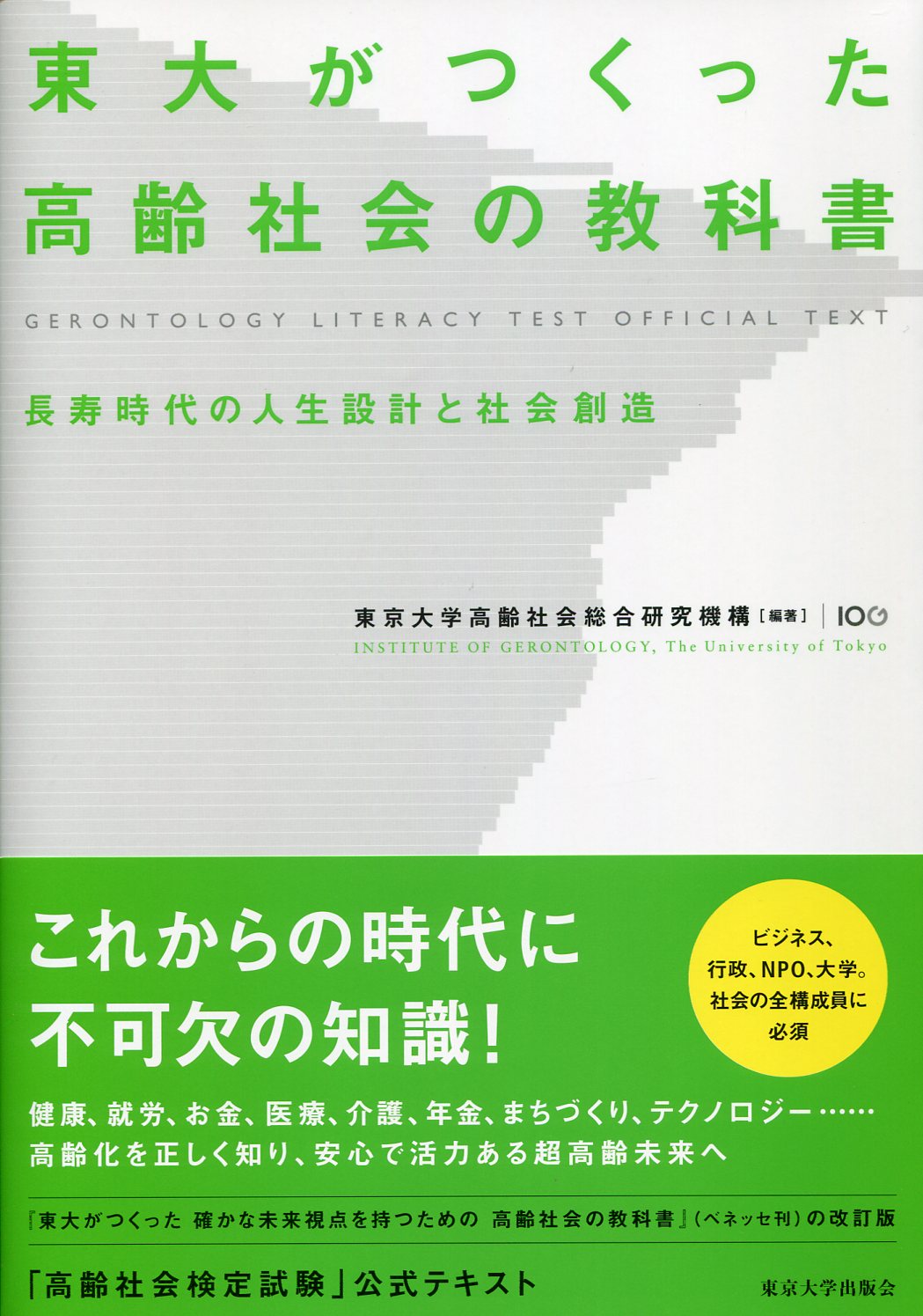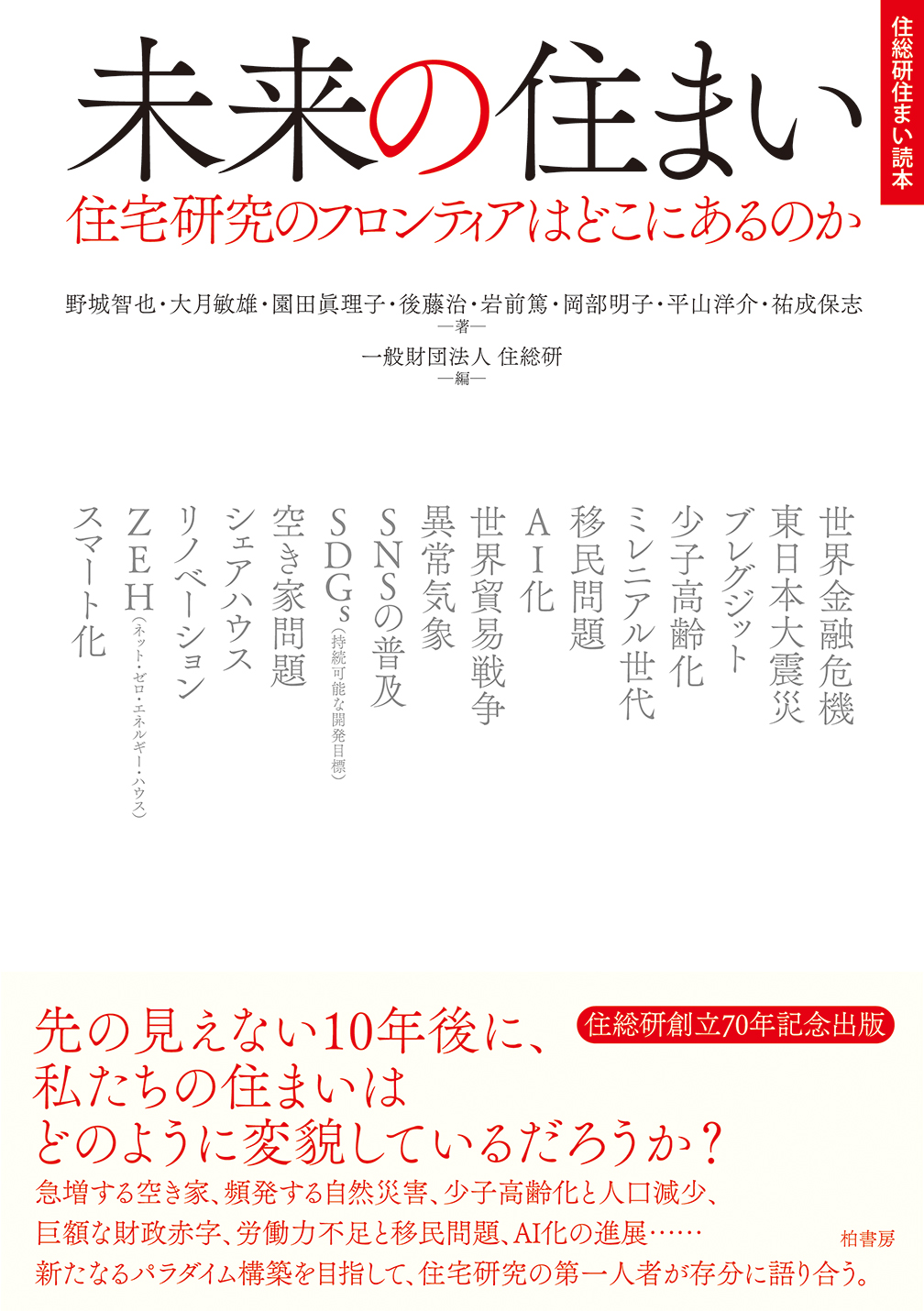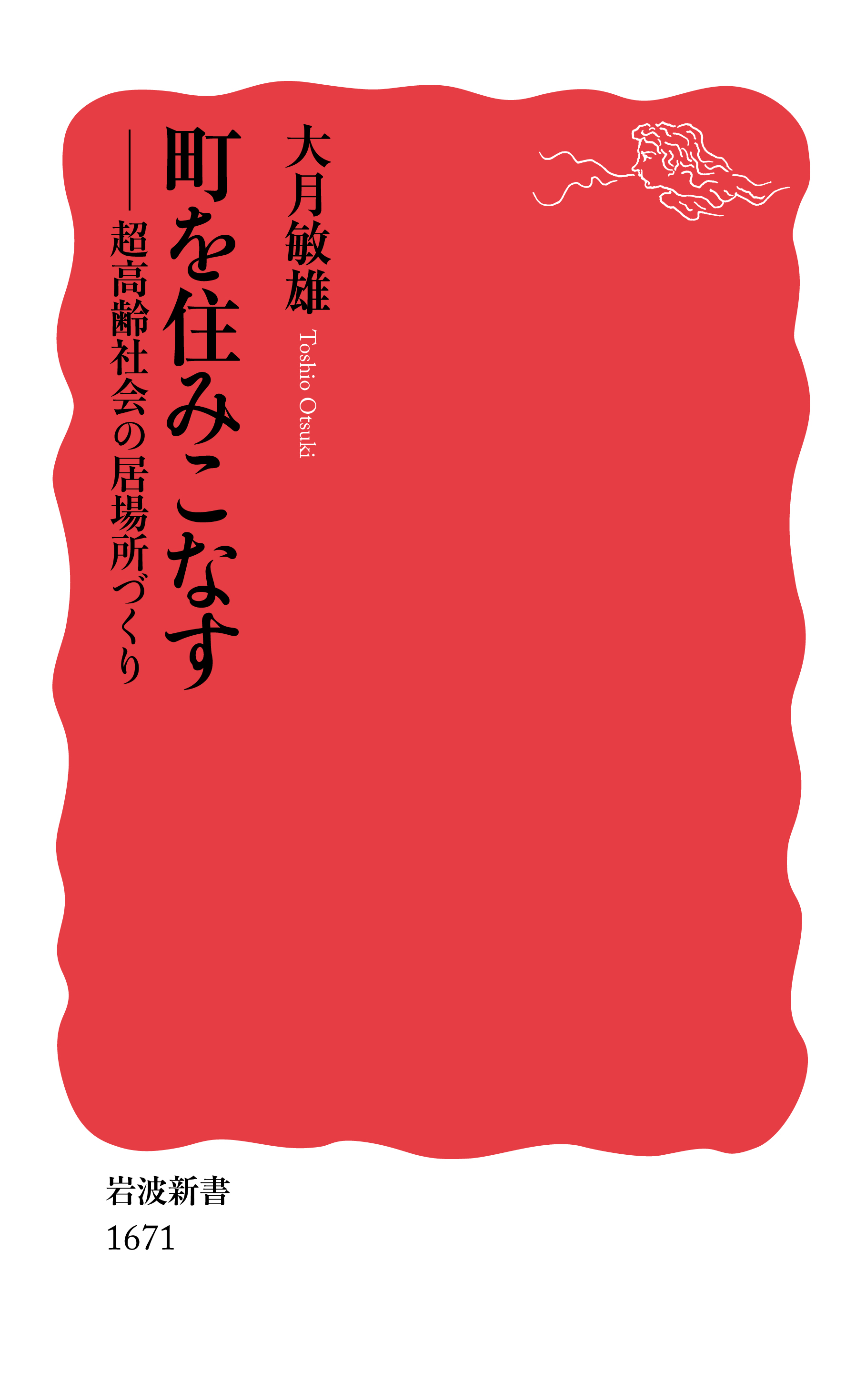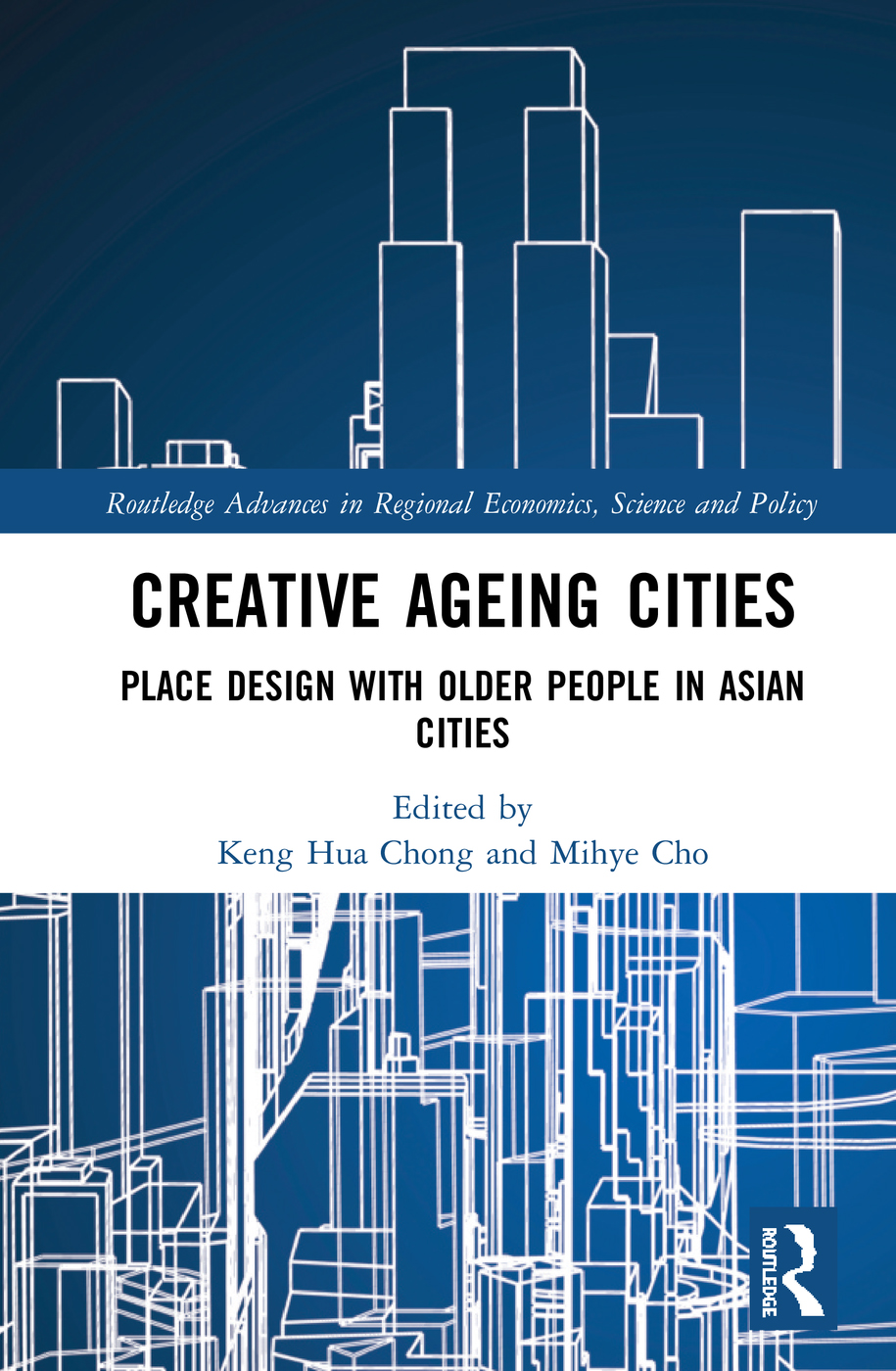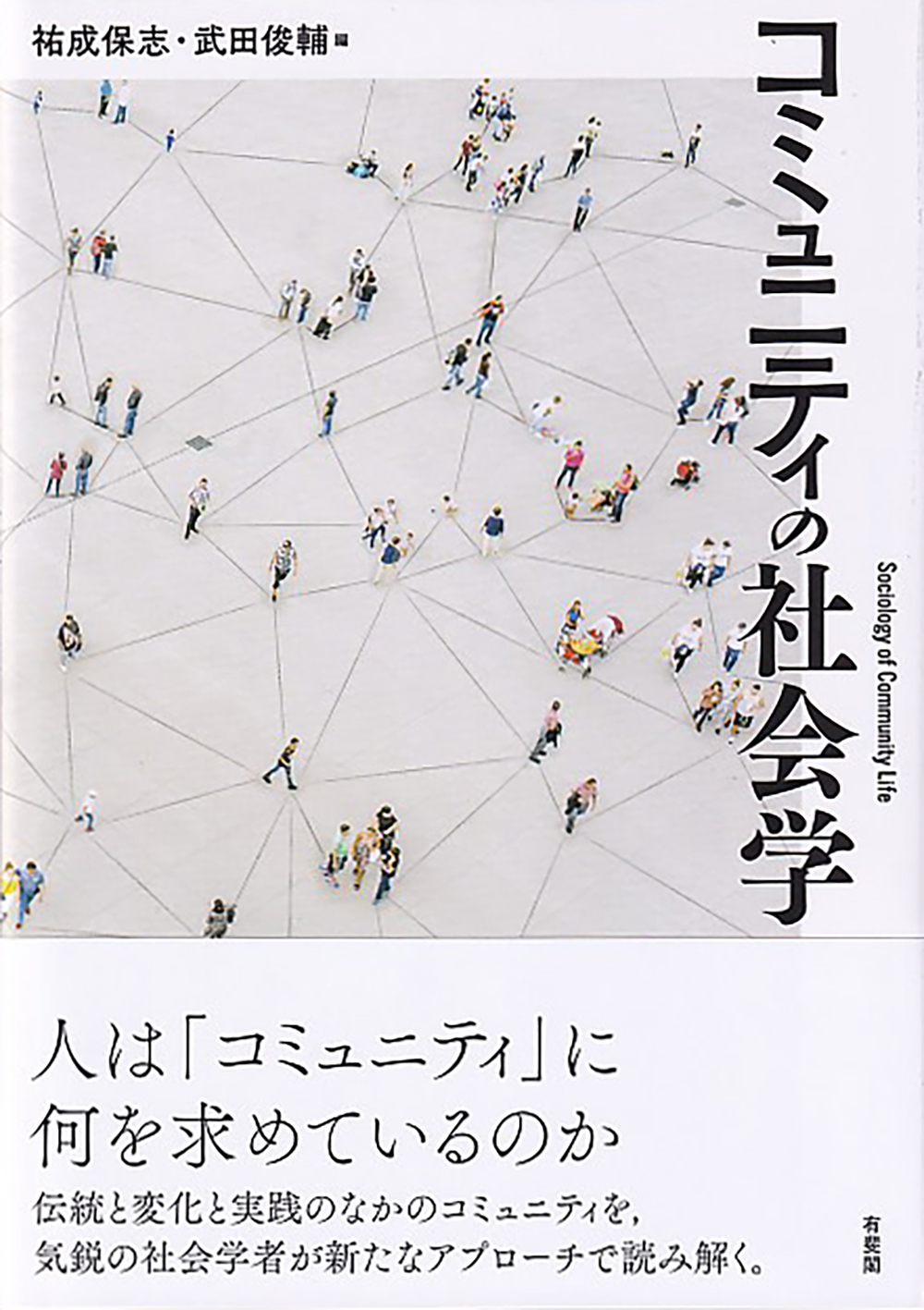書籍名
地域とつながる高齢者・障がい者の住まい 計画と設計 35の事例
判型など
172ページ、B5変版
言語
日本語
発行年月日
2024年9月15日
ISBN コード
9784761533045
出版社
学芸出版社
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
高齢になって、あるいは自分や家族が障害を持ったときに、どのようにして住み慣れた場所に住み続けることができるのだろうか。このような問いは、「普通」に過ごしている場合は頭に思い浮かぶこともないだろうが、いざ自分や家族がそのような状況に置かれた場合、決定的に重要であるとともに、簡単には答えが見つからない問いでもある。なぜ簡単に答えが見つからないのかというと、高齢や障害の状況はひとによって様々であり、それに対応した住まいやサービス、支援のあり方も様々で、簡単には答えが定まらないからに他ならない。
本書は、そのような状況を背景として、少しでも現在考え得る住まいやサービスの選択肢、そして地域を誰でも住みやすくするための試みを示すべく、日本建築学会に置かれた「高齢者・障がい者等居住小委員会」のメンバーを中心として、建築や福祉、都市計画、居住政策などに関わる専門家が知見を持ち寄り、わかりやすく、かつ具体的に、住まいや地域のあり方を示した書籍である。本書籍の包含する分野の広がりを反映して、執筆者は31人にものぼることとなった。
本書は5つの章で構成される。第1章の「高齢者や障がい者の住まい・暮らしを支える」では、高齢者や障がい者の住まいに関わる心身の状況を説明した上で、住まいの選択肢や関係する法令、利用できるサービスなどをわかりやすくまとめている。第2章の「事例から読み解く高齢者の住まい」では、高齢期に備えた住宅改修やニーズに併せた調整が可能な順応型住宅、あるいはサービス付き高齢者向け賃貸住宅のような住まいが紹介されるとともに、認知症に求められる住環境や見守り支援機器の活用事例なども示されている。第3章の「事例から読み解く障がい者の住まい」では、成長によって変化する住要求に対応した住宅改修や公営住宅改修による車椅子使用者用の住戸、強度行動障害に対応したグループホームや発達障がい児 (者) の住まいにおける工夫など、これまでほとんど情報がまとめられなかったマイノリティーの生活環境について、示されている。第4章の「人と人のつながりを生む地域の実践」では、自治体やNPO、民間企業、教育機関、あるいはそれらの連携によって、地域に住民や外部の人々の繋がりを生む事例が紹介されている。最後の第5章「高齢者や障がい者の住まいの制度と相談窓口」では、高齢者・障がい者を対象とした住宅改修を支援する制度や住まいの相談窓口について、紹介された。
以上のように、本書は建築と福祉に関わる内容を専門家でなくても概要が理解できるようにすることで、両方の分野の関係者がお互いの分野についての知識を得られるものであり、かつ実際に困りごとを抱えた高齢者や障害者とその家族が、地域で暮らし続けるためのなんらかのヒントをえら得ることも意図している。本書が、住まいの問題に直面した多くの当事者にとって、役立つものとなることを祈っている。
(紹介文執筆者: 多様性包摂共創センター 副センター長、バリアフリー推進オフィス オフィス長、工学系研究科 准教授 松田 雄二 / 2025)
本の目次
第1章 高齢者や障がい者の住まい・暮らしを支える
1-1 地域共生社会と住まい
1) 地域共生社会とノーマライゼーション(岡部真智子)
2) 外出して人・地域・社会とつながる(西野亜希子)
1-2 高齢者のからだと住まい
1) 高齢期の心身機能の特徴と住まい(鈴木健太郎)
2) 高齢期の住まい手の変化に応じた住まい・住まい方の選択肢(西野亜希子)
3) 毎日の生活で用いる移動方法と住まい(橋本美芽)
1-3 障がい者のからだと住まい
1) 障がいによる心身機能の特徴と住まい(鈴木健太郎)
2) 地域で暮らす障がい者・障がい児の住まい(西野亜希子)
1-4 地域で暮らす高齢者・障がい者を支える仕組み
1) 地域で暮らすとは(岡部真智子)
2) 在宅生活を支える福祉サービス(岡部真智子)
3) 地域で交流やつながりをつくる(岡部真智子)
4) 外出を支える移動環境(稲垣具志)
第2章 事例から読み解く高齢者の住まい
2-1 高齢者の住まい(西野亜希子)
2-2 アクティブな生活から介護予防まで
1)生涯夫婦で自立して本音の暮らしができる家
―バリアフリーで将来の変化を受容し地域の人を招ける新築住宅(西野亜希子、三浦貴大)
2)住宅を改修して高齢期に備える(雜賀 香)
3)高齢期の移住とライフステージによる変化(番場美恵子)
4)サービス付き高齢者向け住宅(阪東美智子)
5)住まい方を工夫しながら住み続ける集合住宅(南 一誠)
2-3 介護が必要になったら
1)片麻痺で車いすを利用する高齢者向け新築住宅(原 和男)
2)車いすで暮らせるように1階店舗を住宅改修(西野亜希子)
3)認知症に求められる住環境と自宅での環境整備(大島千帆)
4)天井設置型の見守りセンサの活用事例
―見守りセンサにより介護職員と利用者の距離感を適切に保つ(三浦貴大)
5)可搬設置型の見守りセンサの活用事例
―見守りセンサにより介護職員・利用者の負担を軽減する(三浦貴大)
6)介護施設の新しい姿を示す木造・分棟型の計画
―ケアタウン小牧 特別養護老人ホーム幸の郷(石井 敏)
7)物理的環境が認知症を支えることを実証
―認知症高齢者グループホーム こもれびの家(石井 敏)
コラム 災害後の高齢者の仮住まい(冨安 亮輔)
第3章 事例から読み解く障がい者の住まい
3-1 障がい者の住まい(西野亜希子)
3-2 肢体不自由者の住まい
1)バリアフリーはストレスフリー―車いすユーザーが住むマンションのリノベーション(吉田紗栄子)
2)子どもの成長で変化する住要求に対応した住宅改修(西野 亜希子)
3)障がいのある子どもの成長を促す住環境整備―家族にも配慮した段階的な改修(植田瑞昌)
4)身体障がいのある人々が集まって住む―重度身体障がい者グループホーム(松田雄二)
5)既存公営住宅改修による車いす使用者用住戸の整備(室崎千重)
3-3 視覚障がい者の就労施設
1)視覚障がい者の就労施設における環境の工夫―五感活用で過ごしやすい自立の場(三浦貴大、西野亜希子、吉田紗栄子)
3-4 精神障がい者・知的障がい者の住まい
1)精神障がいの人々が集まって住むグループホーム(大島千帆)
2)強度行動障がいを持つ人々のためのグループホーム(松田雄二)
3-5 発達障がい者の住まい
1)発達障がい児(者)の住まいの工夫(西村 顕)
第4章 人と人のつながりを生む地域の実践
4-1地域でつくるつながり(西野亜希子)
4-2 地域の支え合い
1)自助・互助による住民が主役のまちづくり―神奈川県・横浜若葉台団地(佐藤由美)
2)地域交流のまちづくり―横浜市寿地区(阪東美智子)
4-3 通いの場づくり
1)小学校区ごとの小規模多機能型居宅介護施設の整備―大牟田市(金 炅敏)
2)学生が運営に参画するコミュニティ拠点(室崎千重)
4-4 多世代交流
1)共用空間を活用し多世代で支えあって暮らす―千葉県・シティア(曽根里子)
2)大学生が支え、支えられる団地の暮らし―兵庫県明舞団地(糟谷佐紀)
3)協働する住まい―コレクティブハウスかんかん森(大橋寿美子)
4)“ごちゃまぜ”で暮らす―Share金沢(神吉優美)
4-5 住民参加
1)住民主体のサービスづくり―沖縄県・波照間島(神吉優美)
4-6 多様な活動とサービス
1)地域居住を多様な世代・サービスで支える―神奈川県・認定NPO法人ぐるーぷ藤(西野亜希子)
2)多様な制度外サービスを提供―もちもちの木(岡部真智子)
3)団地再生事業における居住者の交流の場づくり―柏市・豊四季台団地(笈田幹弘、李 潤貞、田中紀之、西野 亜希子)
コラム 制度外ケア付き福祉仮設住宅「あがらいん」(児玉善郎)
第5章 高齢者や障がい者の住まいの制度と相談窓口
5-1 介護保険制度における住宅改修費給付制度(岡部真智子)
5-2 障がい者向けの住宅改修支援制度(蓑輪裕子)
5-3 高齢者や障がい者の住まいの相談窓口(佐藤由美)
5-4 居住継続支援における多職種連携(鈴木 晃)
おわりに
「知っておきたい用語・解説」索引
関連情報
松田 雄二 — バリアのない建築へ (東京大学 | YouTube 2020年2月28日)
https://www.youtube.com/watch?v=2J7vvfBPJZU
関連情報:
2025年日本建築学会賞 (論文) 受賞
障害者の生活環境に関する一連の研究 (一般社団法人日本建築学会 2025年)
https://www.aij.or.jp/2025/2025prize.html
書籍紹介:
(『コミュニティケア』 2025年2月)
https://www.jnapc.co.jp/products/detail/4261
(『ケアマネジャー』 2025年1月)
https://www.chuohoki.co.jp/site/g/g80586L76/



 書籍検索
書籍検索