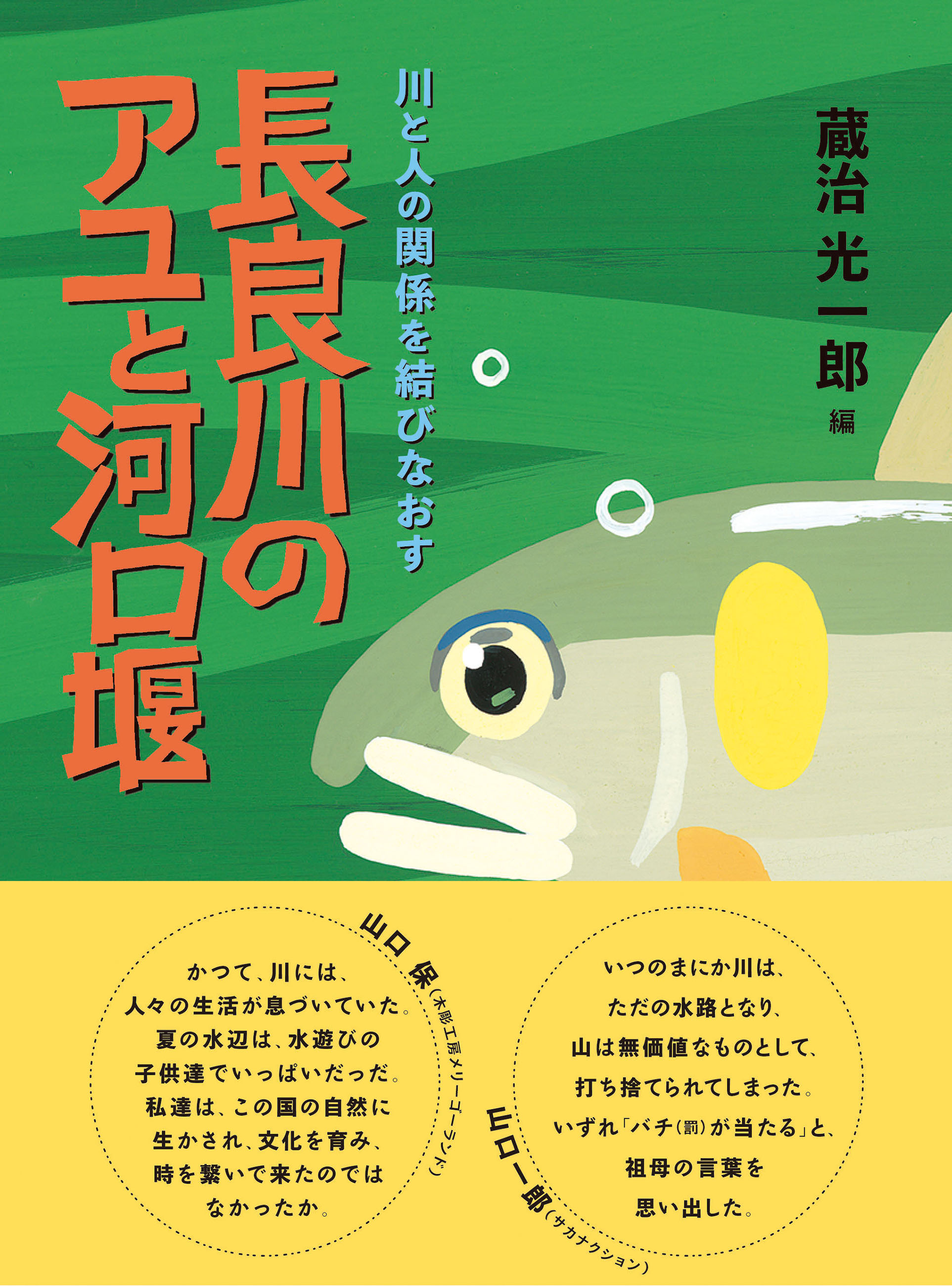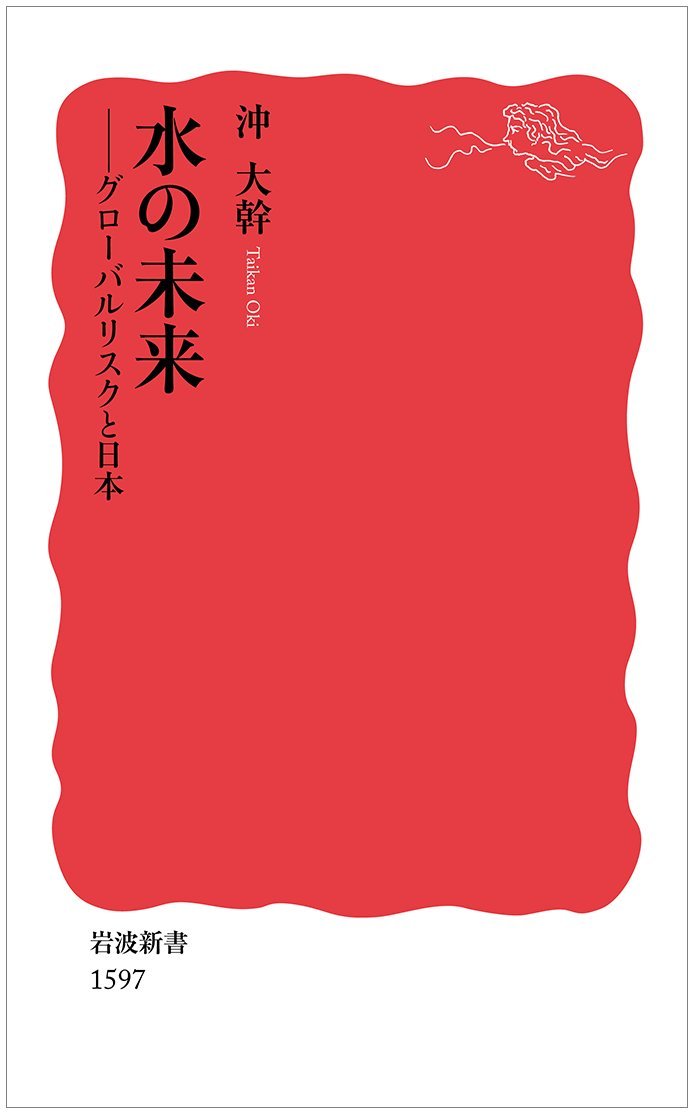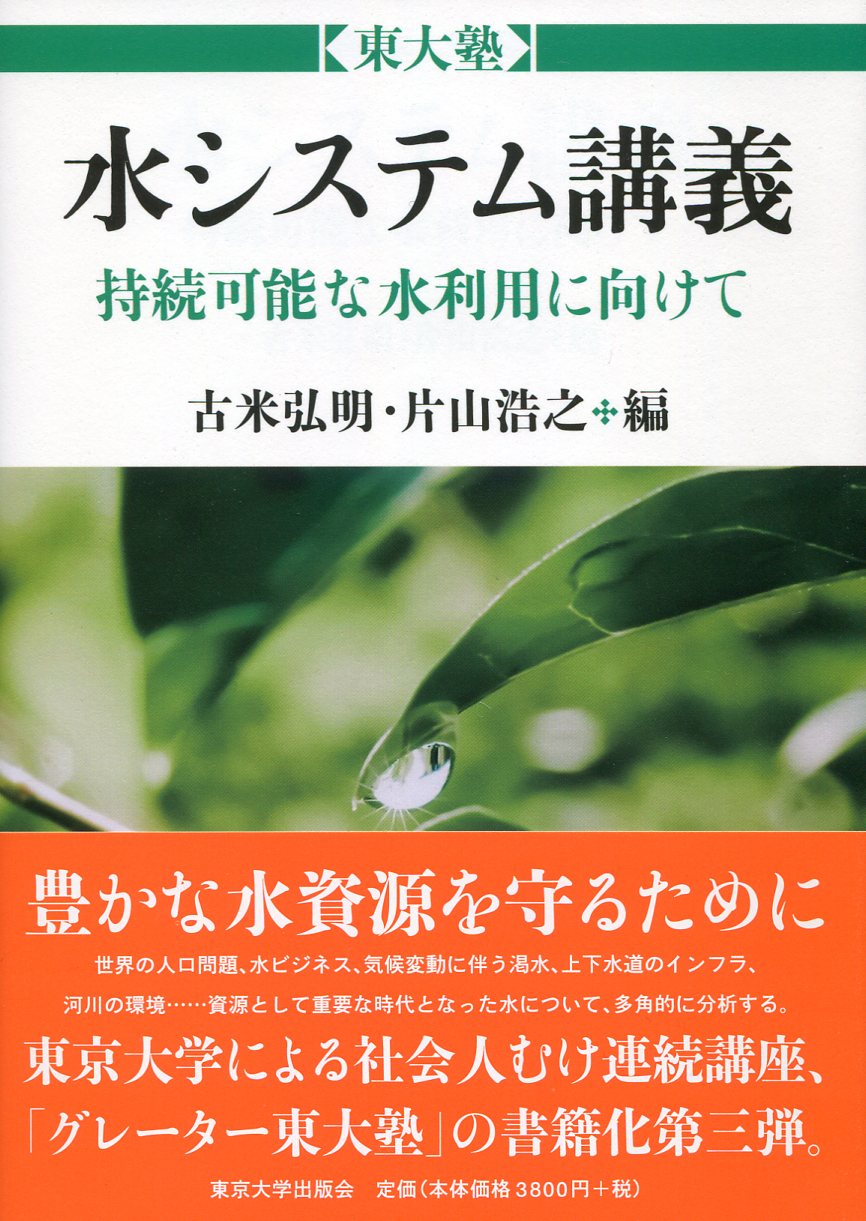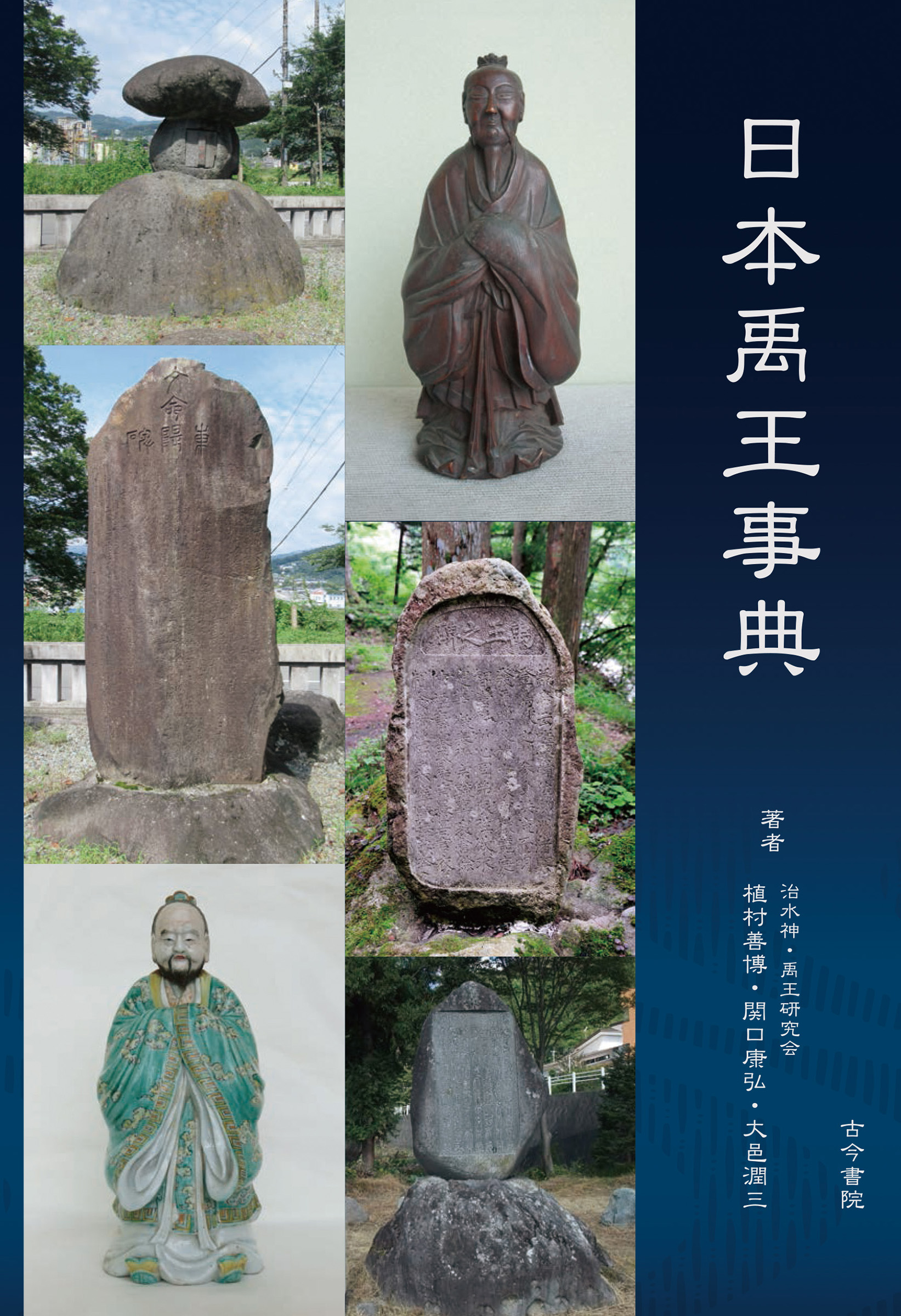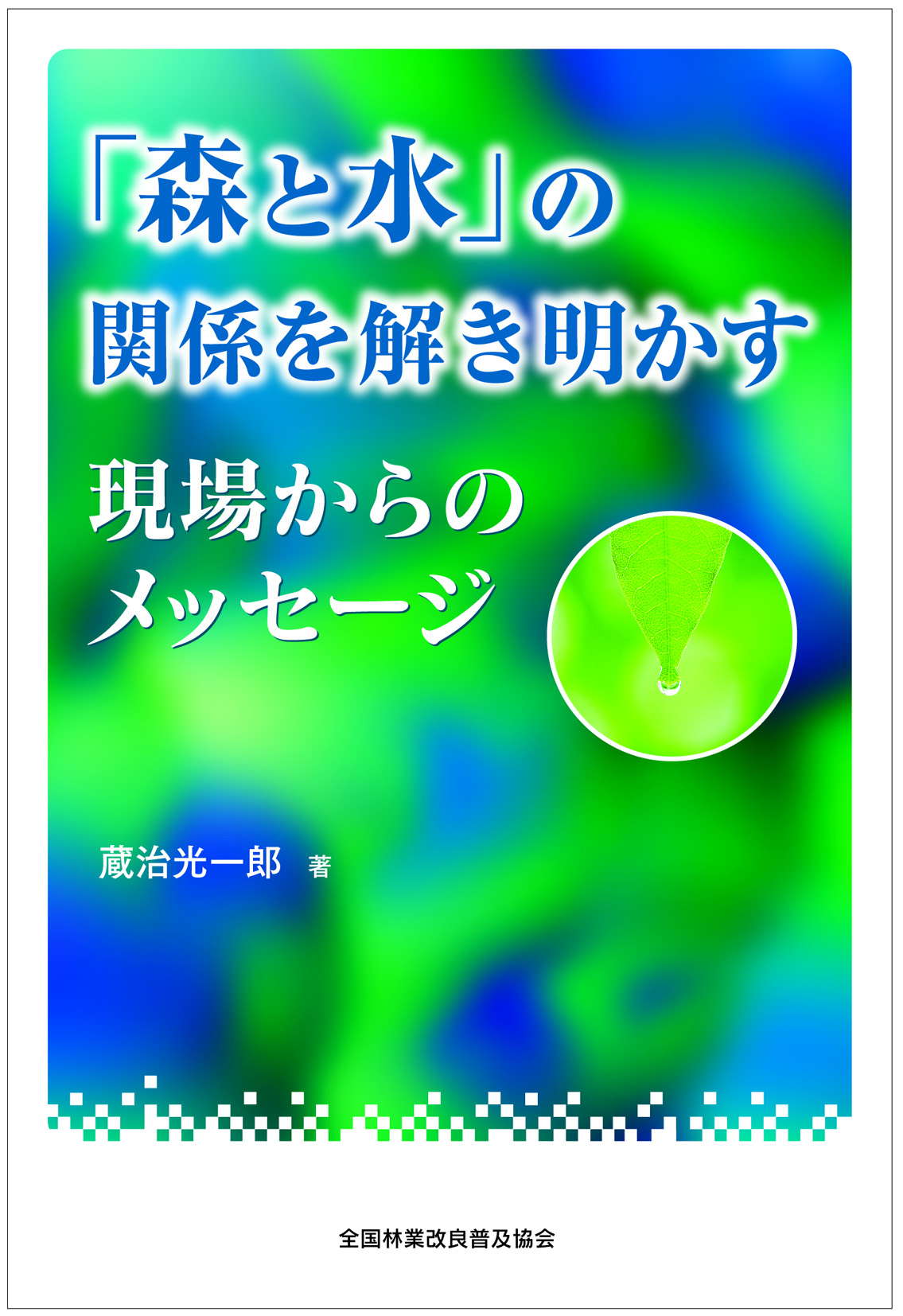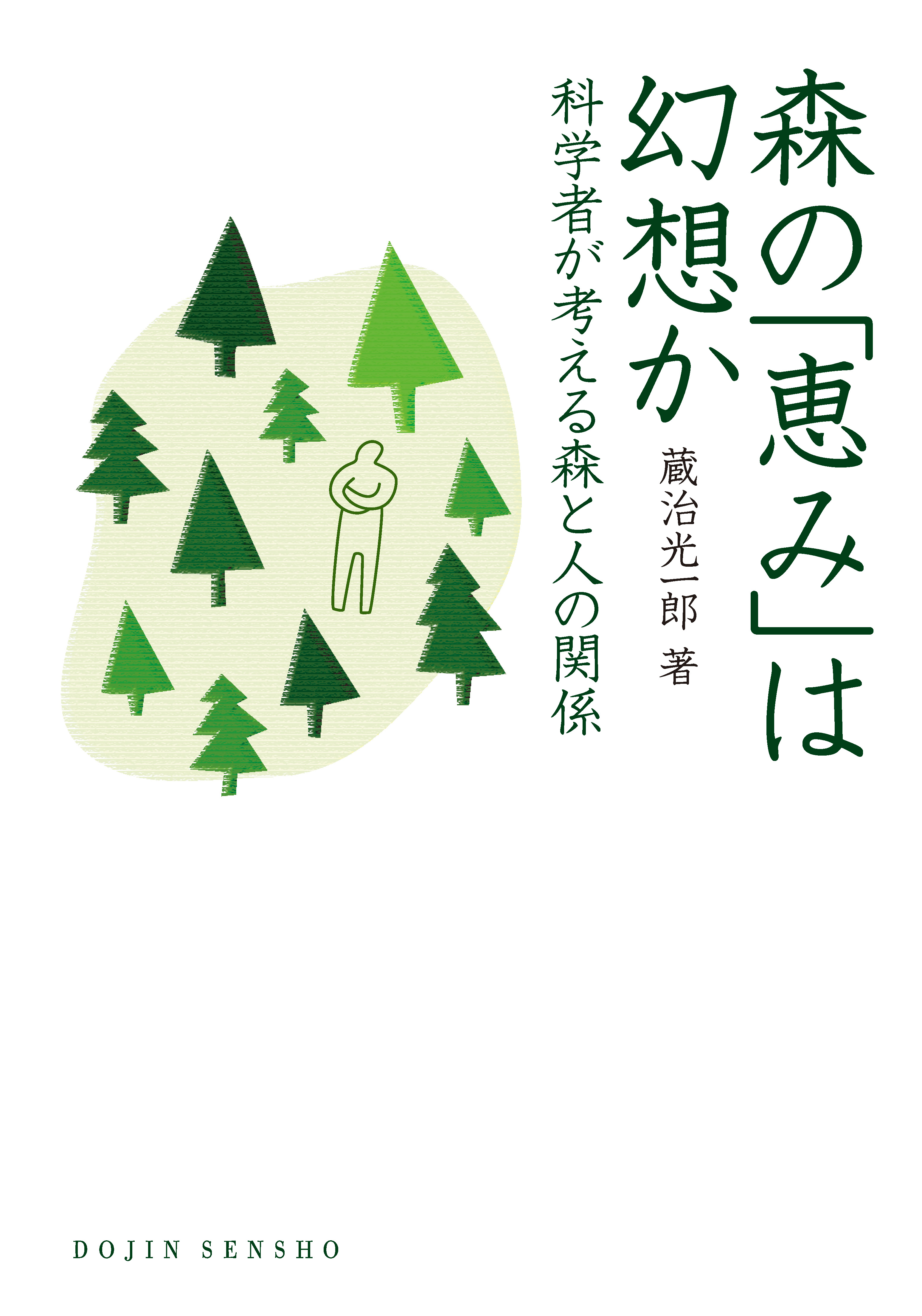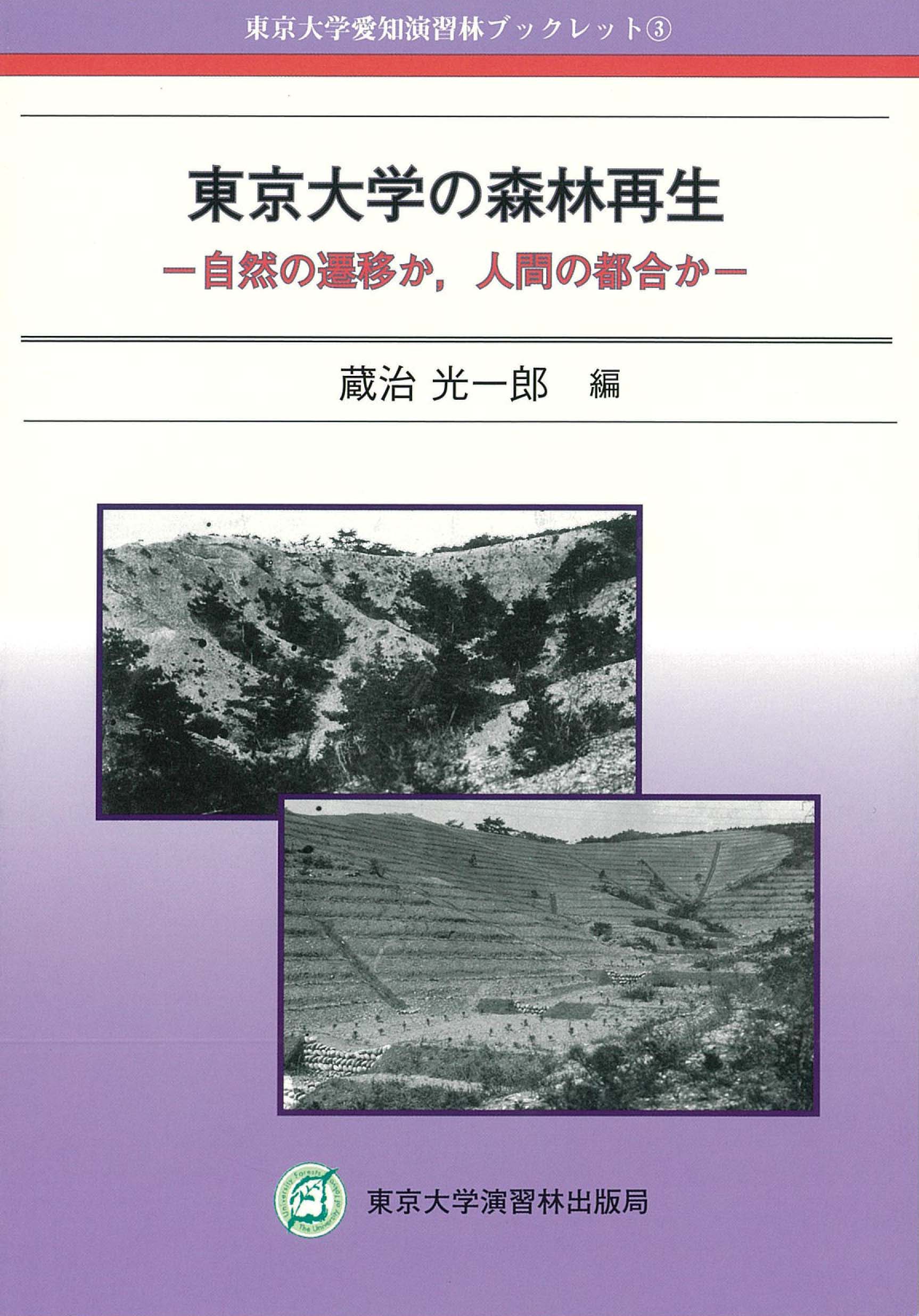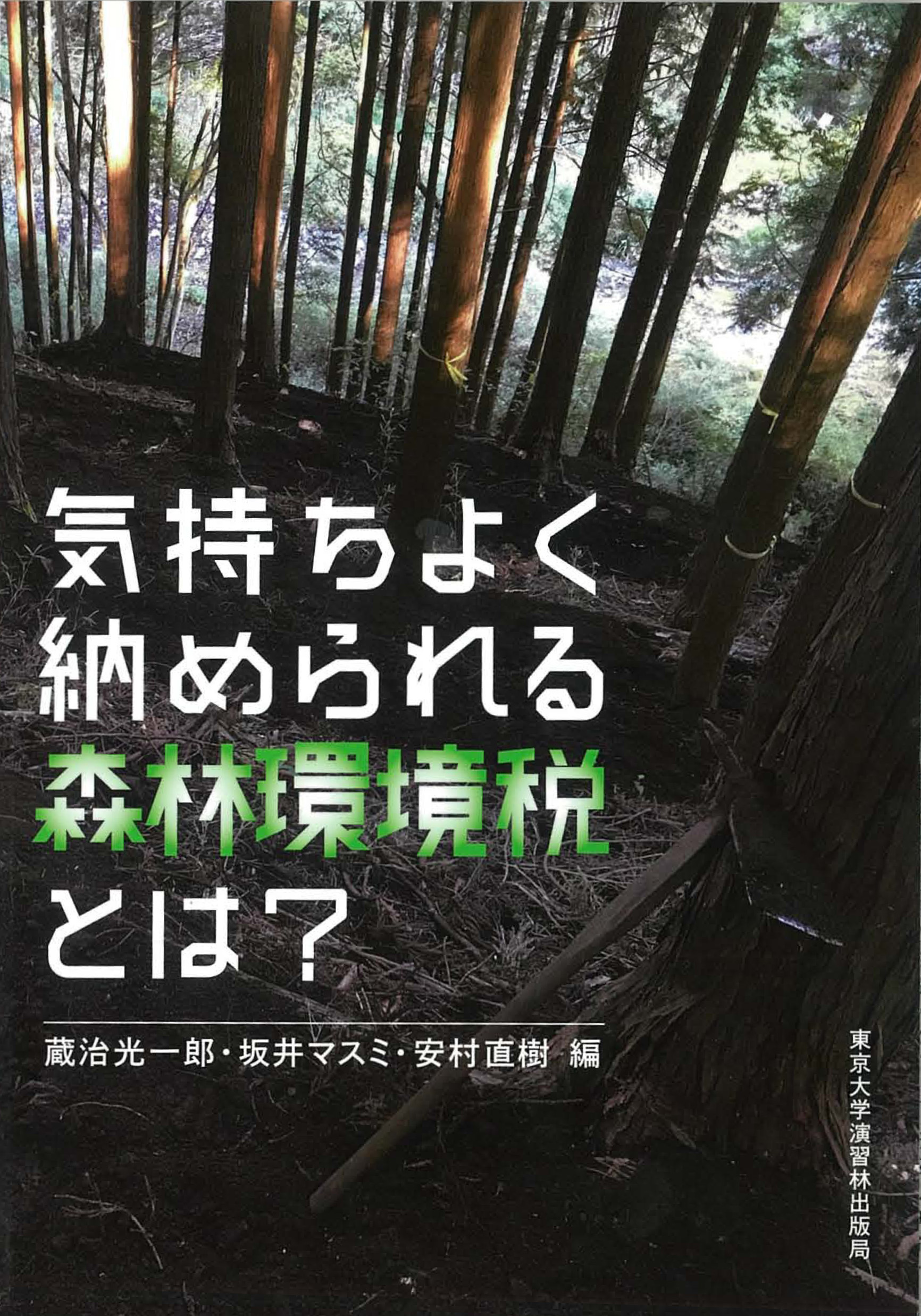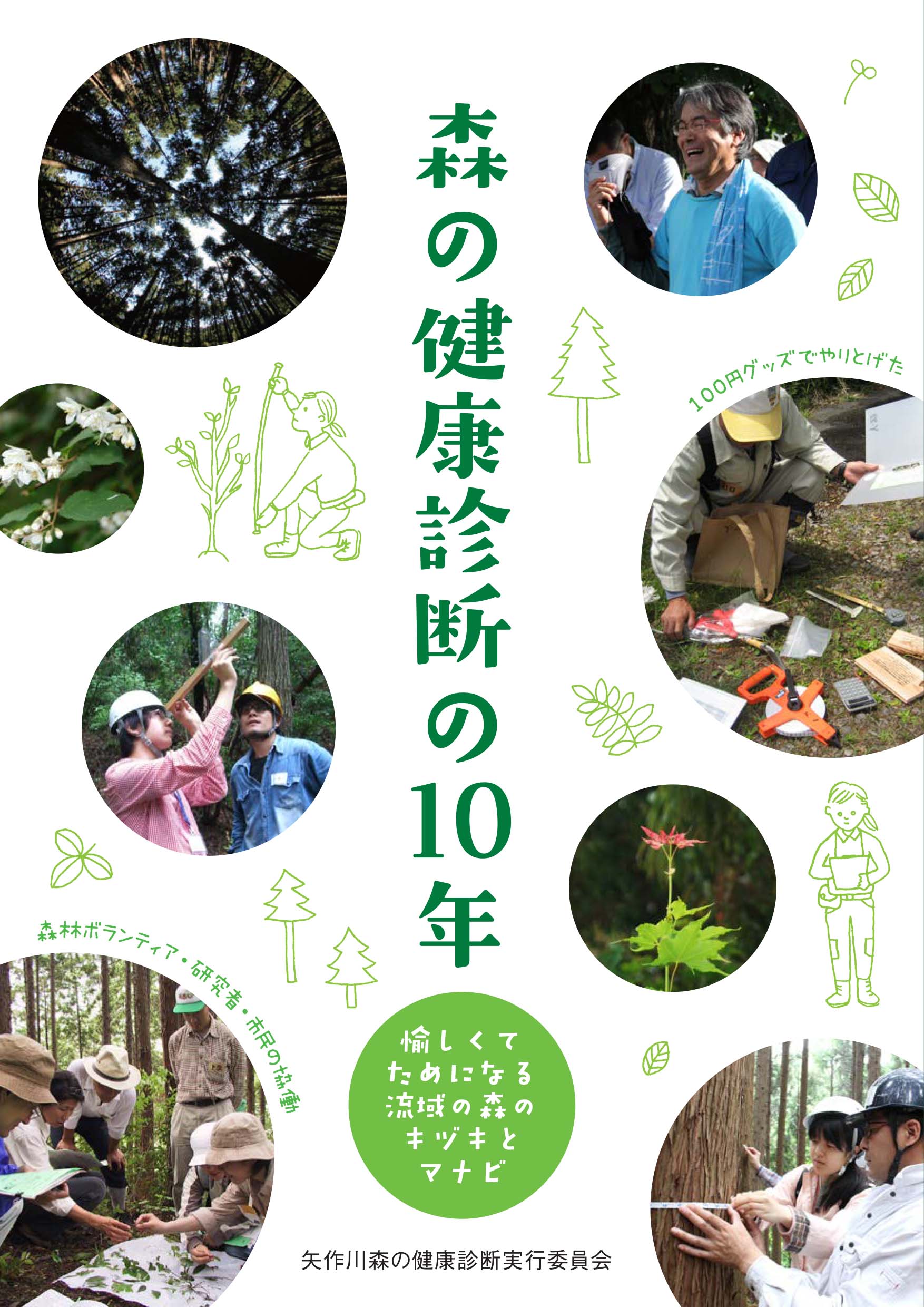書籍名
未来を拓く人文・社会科学 5 水をめぐるガバナンス 日本、アジア、中東、ヨーロッパの現場から
判型など
224ページ、四六判、並製
言語
日本語
発行年月日
2008年1月31日
ISBN コード
978-4-88713-808-7
出版社
東信堂
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
近年、環境問題の中でも特に水をめぐる問題が、地球温暖化と並んでクローズアップされるようになってきた。水が少なすぎて困る水不足、多すぎて困る水災害の両方が話題に上っている。
水はもともと、人類にとって都合のよい形で存在していたわけではない。人類は、その長い歴史の中で、水が少なすぎる、多すぎる、雨季乾季がはっきりしている、といった「与えられた条件」と折り合いをつけながら生きてきた。水不足に対しては、ため池のような小規模の水貯留のための施設を作り渇水に備えた。水災害に対しては、水に決して浸からない高台に居を構え、低地にはわざと水をあふれさせ、農地として利用した。水不足、水災害を巡る争いは絶えず、合意形成、調停や裁定が繰り返され、地域の秩序 (ローカル・ガバナンス) が形成されていった。
ところが近年、大規模な土木工事ができるようになると、様相は一変した。大規模な水貯留施設が山の奥深くに建設され、目の前の川が枯れても、水を遠くから引いてくることができるようになった。水があふれないように堤防やダムを築き、洪水の脅威を軽減することに成功した。これまでしょっちゅう水に浸かっていた土地が、一見、安全そうに見えるようになり、さまざまな形で利用されはじめ、それを守るためにさらに水害防御対策をせざるを得なくなるという「いたちごっこ」が始まった。水争いは沈静化に向かい、水に対する人々の関心は希薄化していった。
しかし、どんなに科学技術が進歩しようとも、時として多すぎる、または少なすぎるという「水の本質」を完全に制御することはできない。近年の流域閉塞やアラル海の縮小、河川環境の悪化、洪水やハリケーンの被害は、水をめぐる問題に対する科学技術に偏重した対応に対して、警告を発しているかのように見える。
本書は、現代社会で顕在化している水をめぐる諸問題の具体的な事例を取り上げ、その解決には科学技術に加えて水の新しい秩序 (ガバナンス) の形成が不可欠であることを示す。日本でも世界でも水害、河口閉塞、濁水、水没補償、国際河川における二国間、多国間の理解調整などの「水をめぐる深刻な問題」があることを、フィールド研究者の視点から紹介し、その解決に向けて新しい水のガバナンスを確立しようとする努力がどのように行われてきて、今、何が必要とされているのかを示す。
国連ミレニアム開発目標でも重点的に取り上げられている水問題は、地球温暖化とともに、二十一世紀の地球に課せられた最も重要な環境問題の一つである。日本では水問題に関心が高まっているとは必ずしもいえない。しかし経済のグローバル化に伴い、世界の水危機は食糧や資源の調達コストをひきあげる要因となりうる。国内の問題に限っても、日本はもともと自然災害の多い国であり、いつ大きな水災害や水不足に襲われないとも限らない。日本人は決して水問題に無関心ではいられないはずである。本書をきっかけとして、世界と日本の水問題への関心が高まることを願っている。
(紹介文執筆者: 農学生命科学研究科・農学部 教授 蔵治 光一郎 / 2019)
本の目次
第2章 川の流域とガバナンス(1)武庫川での実践――総合的な計画づくりへの挑戦 (中川芳江)
第3章 川と流域のガバナンス(2)「物部川方式」を考える――流域連携の新しい可能性 (川中麻衣)
第4章 川と流域のガバナンスと法制度――総合性と国家責任から見た武庫川と物部川 (松本充郎)
第5章 ダム建設と水没移転のガバナンス――開発に求められる新たな価値とは、コラム 国際化したダム問題 (武貞稔彦)
コラム 国際化したダム問題 (藤倉 良)
第6章 国際河川のガバナンス(1)中東――ユーフラテス川をめぐる紛争、その対立点と協調の可能性 (遠藤崇浩)
第7章 国際河川のガバナンス(2)アジア――メコン川流域をめぐる紛争と交渉 (大西香世)
第8章 国際河川のガバナンス(3)ヨーロッパ――ドナウ川とダム問題、環境政策と水政治学 (村上雅博)
第9章 水のローカル・ガバナンスとグローバル・ガバナンス (中山幹康)



 書籍検索
書籍検索