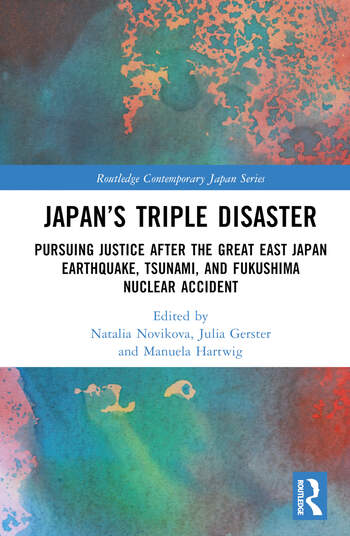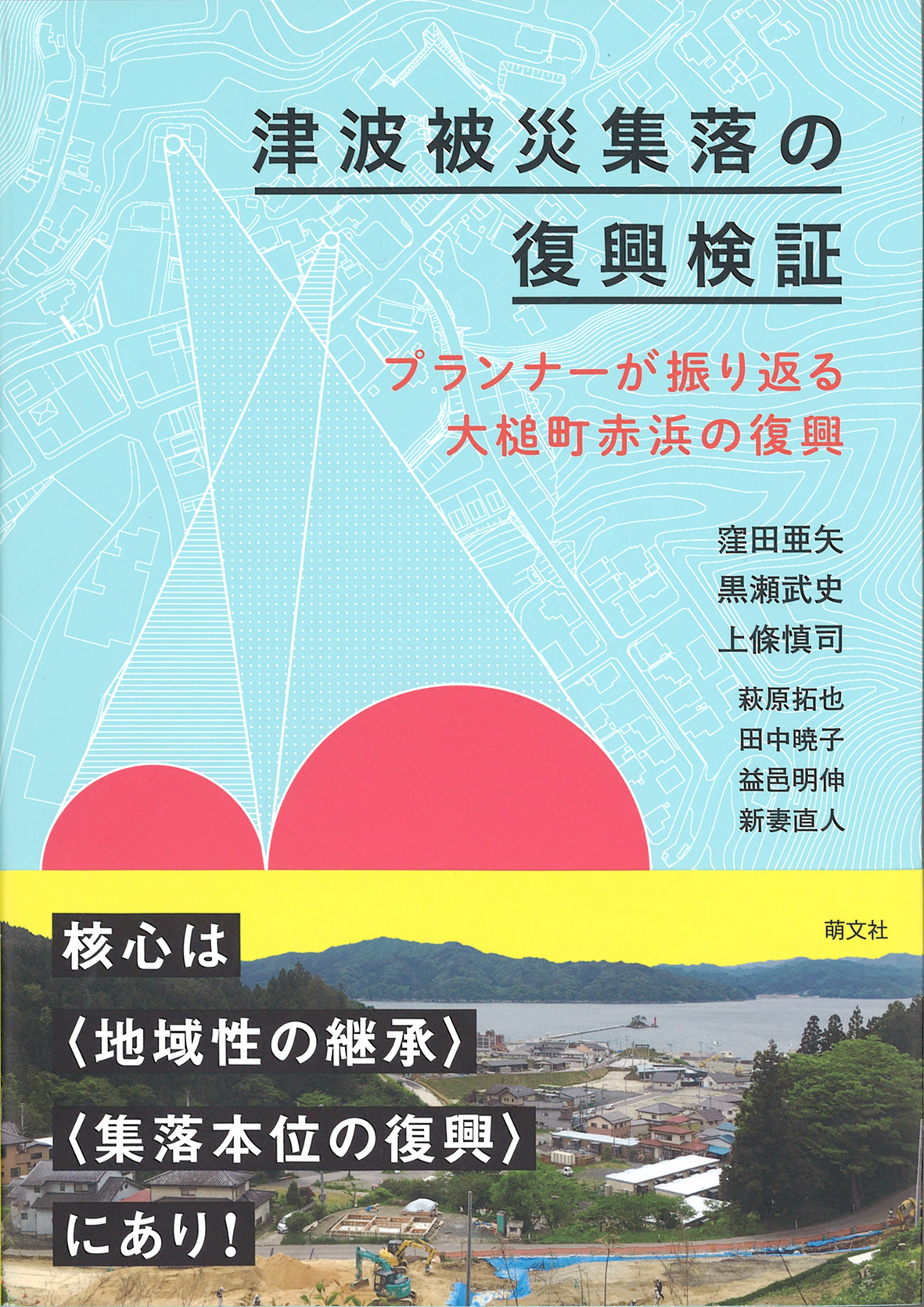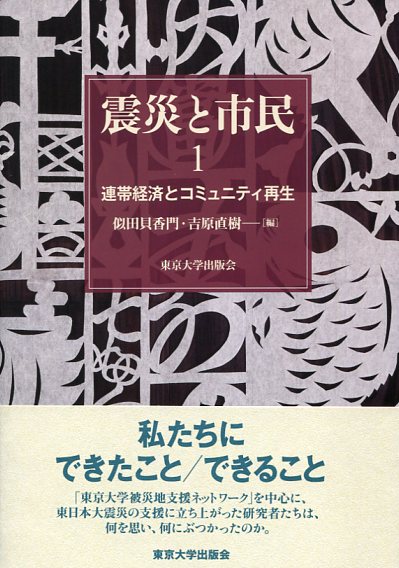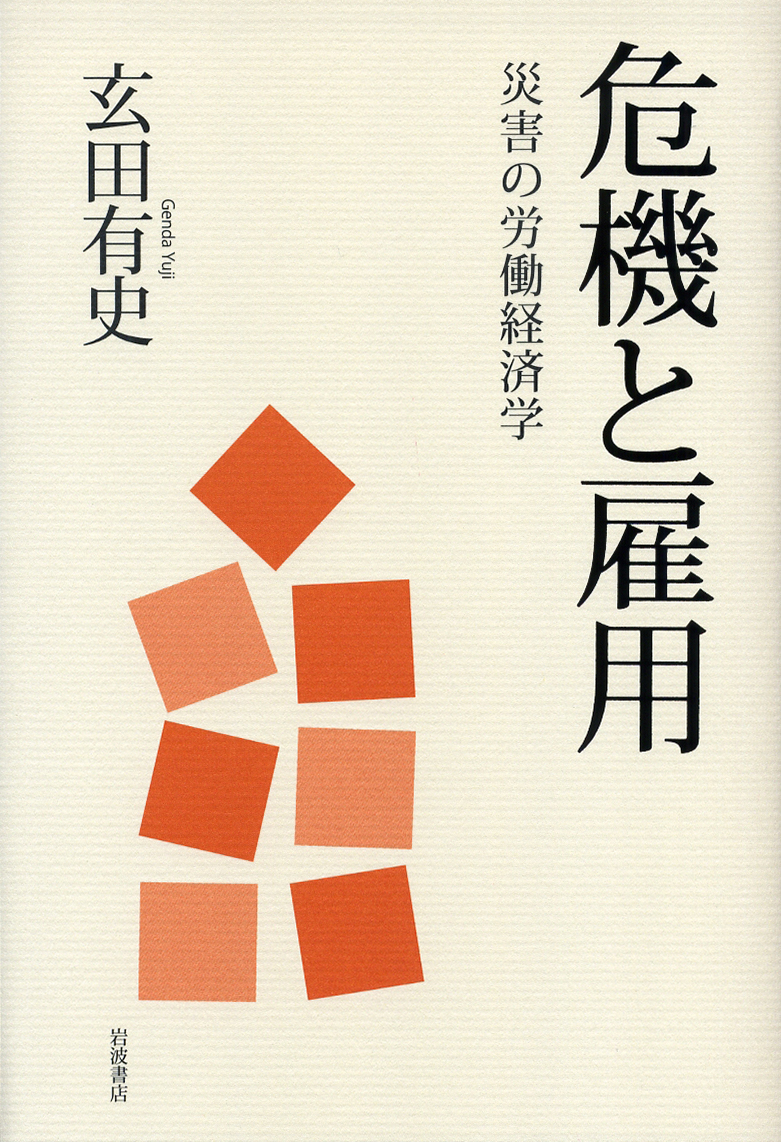書籍名
震災復興の公共人類学 福島原発事故被災者と津波被災者との協働
判型など
304ページ、A5判
言語
日本語
発行年月日
2019年1月31日
ISBN コード
978-4-13-056118-1
出版社
東京大学出版社
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
貧困や災害といった苦境に立たされた時、人は試される。苦境に立たされた人がどのように英知を集め、相互に助け合って乗り越えるかについて、当事者の視座で考察することを、本書では特に取り組んできた。私が専門とする文化人類学では、フィールドワークを行い民族誌を書くことが仕事とされるが、本書では、フィールドは2011年3月11日に発生した東日本大震災後の東北地方を中心とする社会であり、書き上がった成果は協働の民族誌となった。
文化人類学におけるフィールドワークでは、従来までは人類学者が単独で参与観察を行い、フィールドにいる人たちが織りなす生活文化を言葉を尽くして描写することが徹底されてきた。そこで取り上げられるテーマは様々で、人類学者が特権的にテーマを選び、彼/彼女自身の言葉でフィールド世界を描き出すことが許されてきた。貧困や災害についても、これまでは人類学者自身がフィールドで見てきたことを、諸理論や分析枠組みに基づき、ある一般化された実体像に落とし込むことが行われてきた。
しかしながら、苦境に立たされた人たちを、ただ観察し描写することはなかなか困難である。そうした人々を理解しようとするのであれば、一緒に苦境に抗い、闘うことのほうが寄り添う人間の在り方として自然なのではないか。そうすることで、人類学者は客観的な立場を少し失い、記録だけでは済まない状況に追い込まれるという犠牲を払うかもしれないが、現場で何が問題となっているのかという点により深く向き合えるし、困難なフィールドでも記録をしながら行動をし、現場に少しでも資する貢献をもたらす可能性も見出すことができるのである。
東日本大震災以後、私は学生や友人を連れて訪れながら、主に福島原発事故被災者の声に耳を傾け、人々が向き合っている問題がどのような過程で、解決され、苦境が少し良くなっていくかを見てきた。見るだけではなくて、時には一緒に考えて行動を起こしてきた。そのようにしてしまったのは、自然な成り行きであるし、徐々に人々に笑顔が戻る様子を見ることが、ともに寄り添う人間として、とてもうれしかったからである。さらに、こうした過程を記録に残すことが、先の学びを次の苦境を乗り越えるときのために活かす、ことにもつながる。残すのであれば、できるだけ当事者の視座から見えていることを鮮やかに残す。おそらく本書に論考を寄せた執筆者全員がそのような思いであったと信じている。
さて、綺麗過ぎるとも思えるこうしたフィールドとの付き合い方から生まれた協働の民族誌はどのような学術的意味合いがあるのだろうか。現場の人たちも巻き込んで、協働の民族誌のテキストを紡ぐ作業はこれまでも多くの先達が試みてきた作業で、賛否両論がある。客観性に欠ける、あるいは学術的水準が保証できない、そうしたリスクの一方で、当事者たちの視座を動態的に描き出している可能性が残されている。
(紹介文執筆者: 総合文化研究科・教養学部 准教授 関谷 雄一 / 2019)
本の目次
I 震災復興の映像アーカイブ化
第1章 灰色地帯を生き抜けること――「つくば映像アーカイブ」から考える (箭内 匡)
第2章 避難者のセーフティネット作りから映像アーカイブ制作への発展 (武田直樹)
第3章 『立場ごとの正義』――自主避難者の視点から映像を撮る (田部文厚)
第4章 災害に抗する市民の協働 (関谷雄一)
II 福島第一原発事故被災者に寄りそう実践の試み
第5章 原発事故避難者受け入れ自治体の経験
――ソーシャル・キャピタルを活用した災害に強いまちづくりを目指して (辻内琢也・滝澤 柚・岩垣穂大 / 研究協力: 佐藤純俊)
第6章 当事者が語る――一人の強制避難者が経験した福島第一原発事故 (トム ギル・庄司正彦)
第7章 まなび旅・福島――公共ツーリズムの実践 (山下晋司)
III 津波被災地の生活再建の現場から
第8章 現在から過去へ,そして未来へ――「復興」への手探りの協働 (木村周平・西風雅史)
第9章 津波被災後の稲作農業と復興における在来知の役割 (高倉浩樹)
第10章 震災とデス・ワーク――葬儀業による死後措置プロセス支援の展開 (田中大介)
関連情報
<本の棚> 森山 工 (東京大学教授・文化人類学) 評 (東京大学教養学部報 611号 2019年7月1日)
http://www.c.u-tokyo.ac.jp/info/about/booklet-gazette/bulletin/611/open/611-02-2.html



 書籍検索
書籍検索