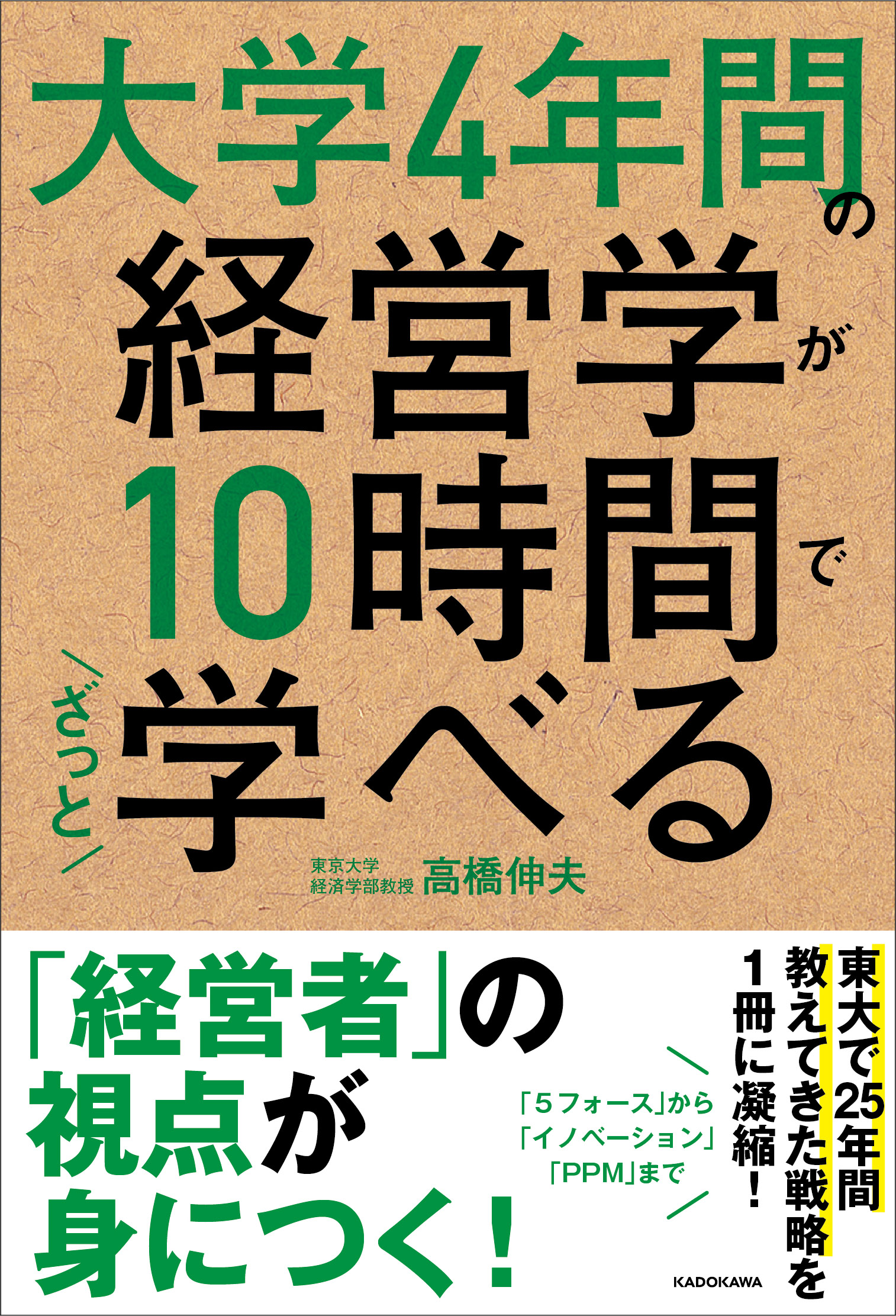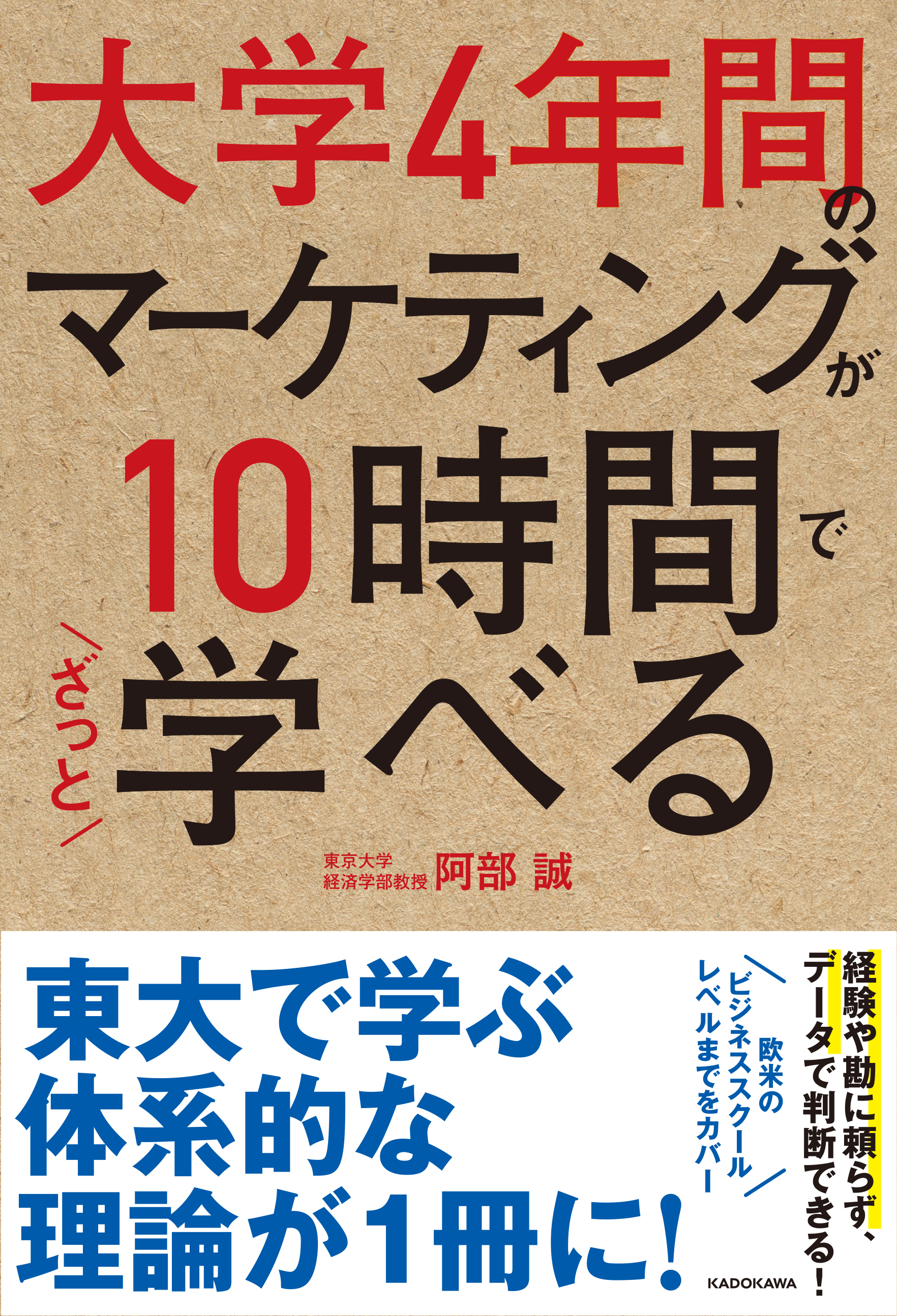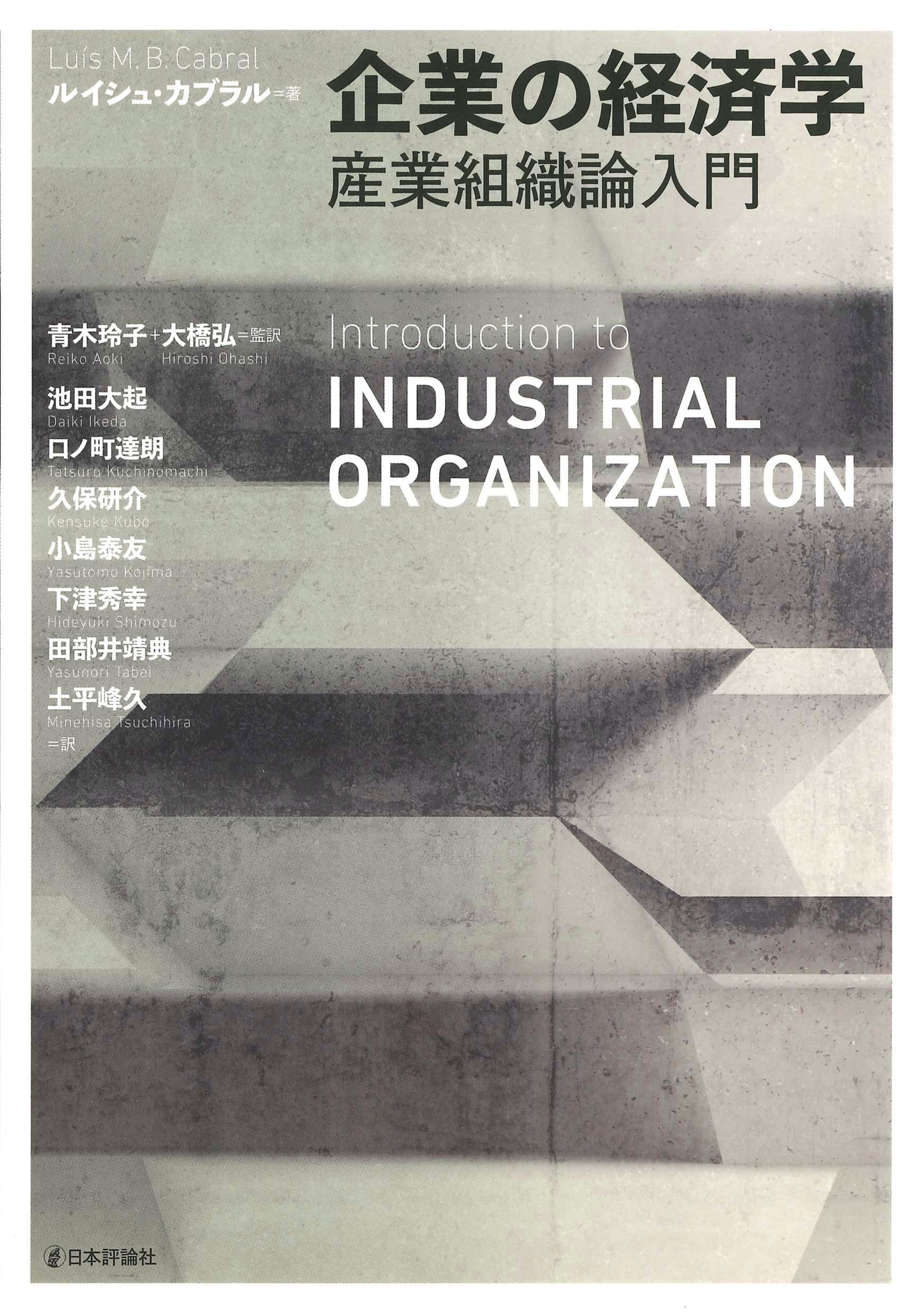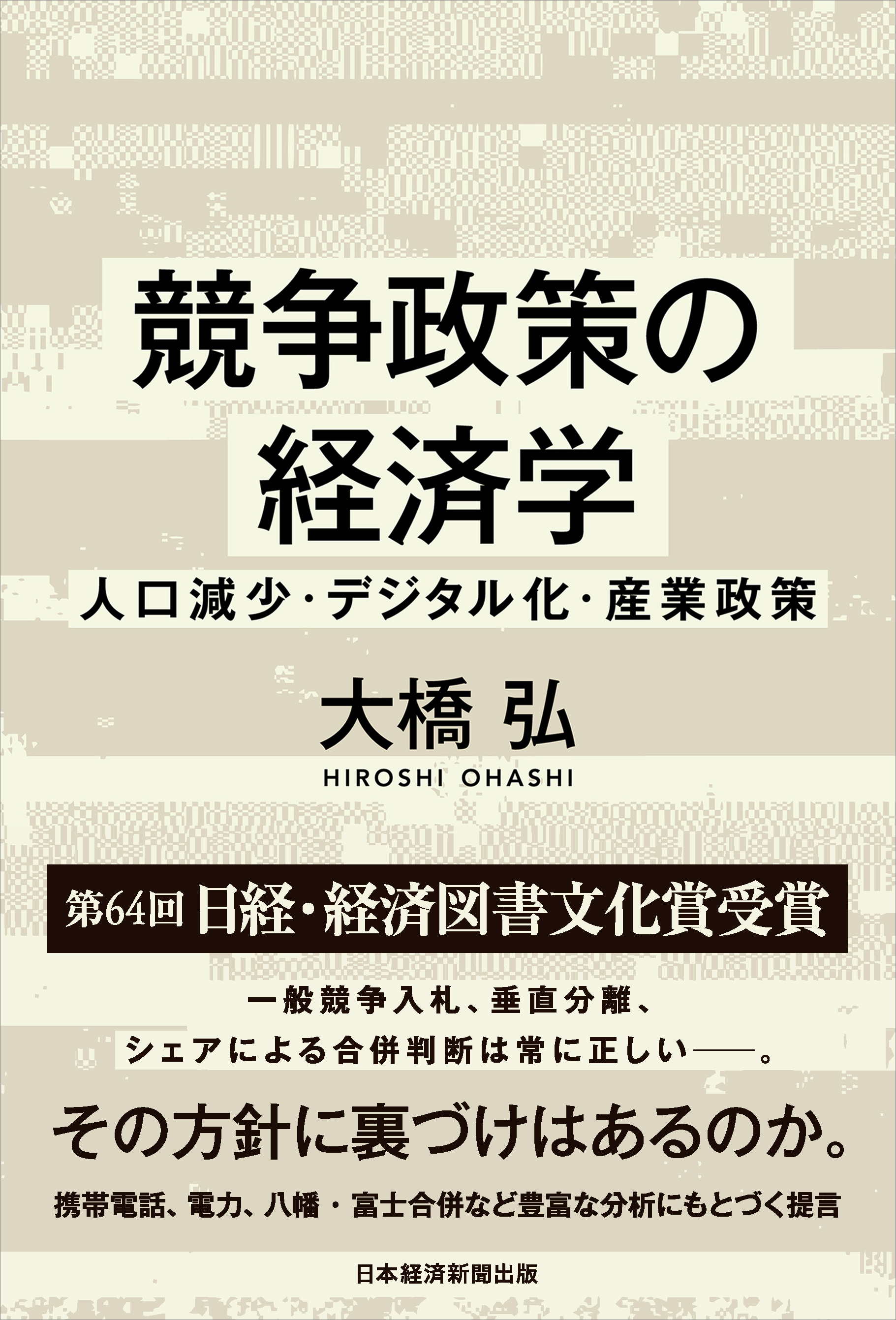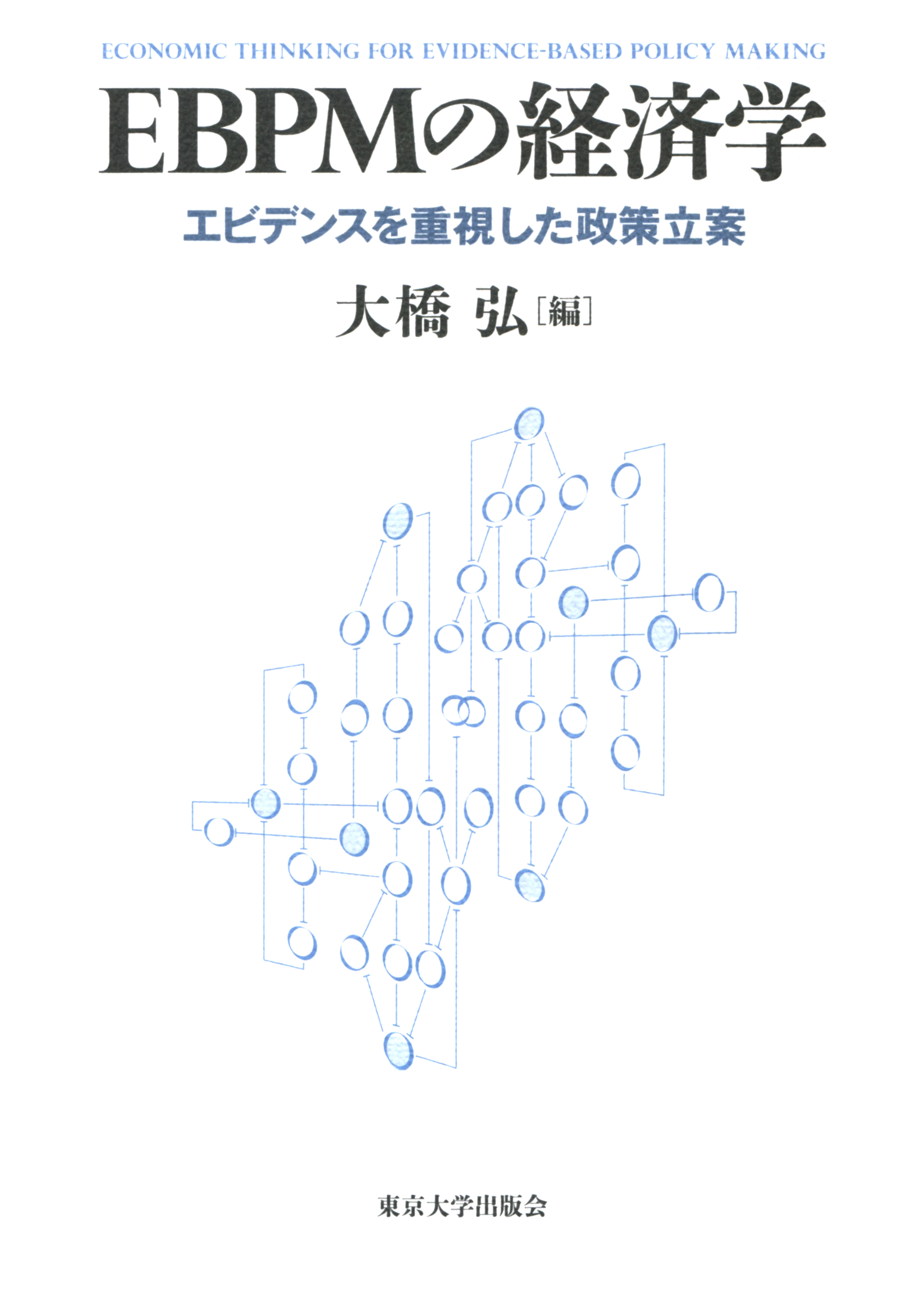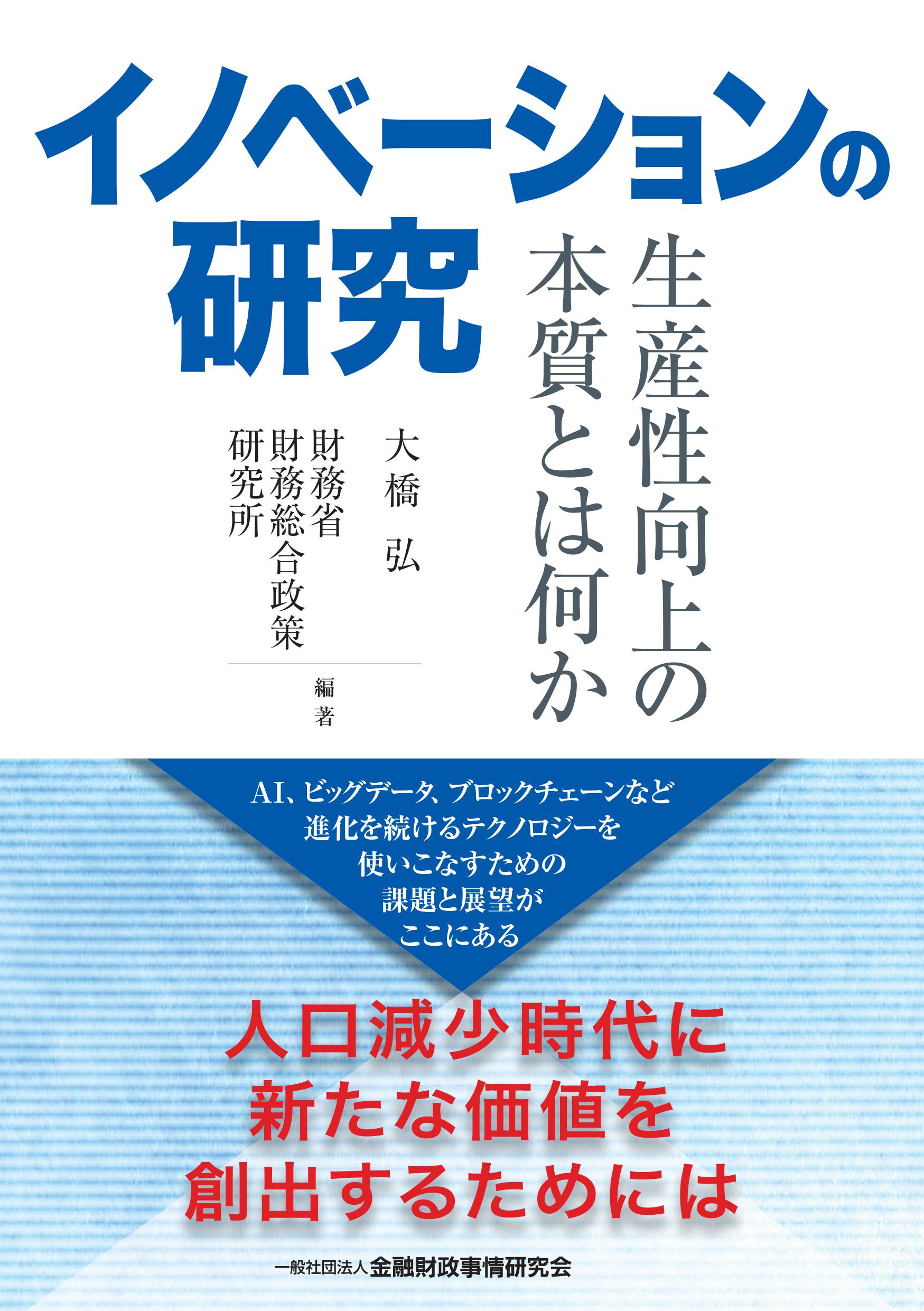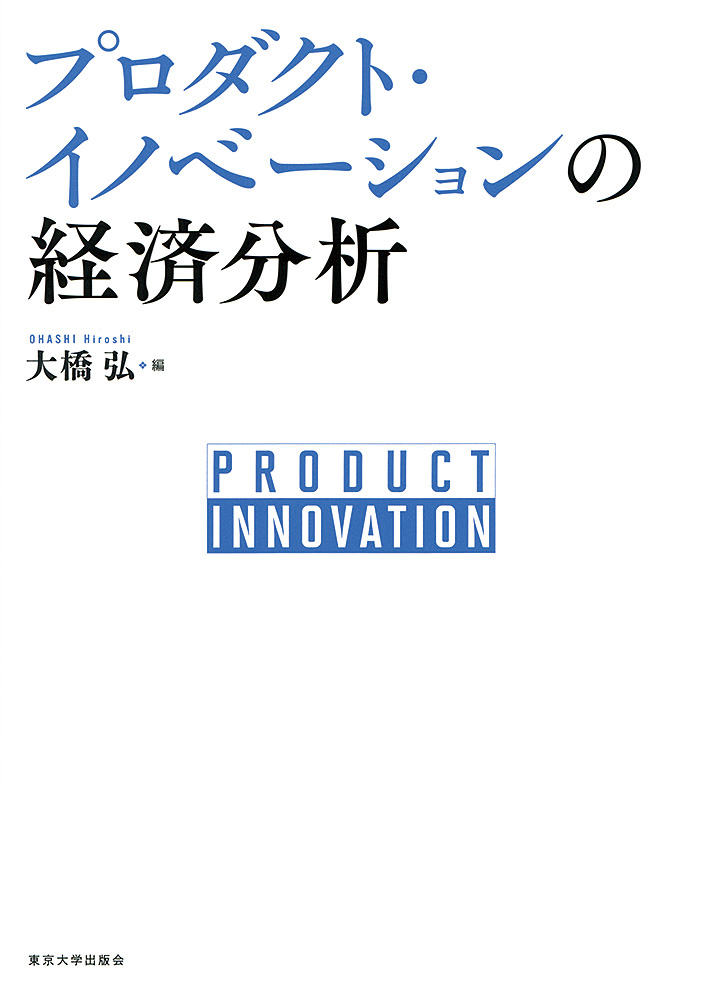書籍名
大学4年間の経済学が10時間でざっと学べる・実戦編
判型など
240ページ、四六判
言語
日本語
発行年月日
2023年3月16日
ISBN コード
9784046060747
出版社
KADOKAWA
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
本書は経済学を現代が抱える経済社会の課題に対してどう応用されるか、理解を深めることを目的にした入門書です。経済学の入門書は数多くあり、読者のニーズに合わせて経済学を身近に学ぶ機会は増えており、経済学を通じて経済社会の理解を深める切り口も多くあります。よく目にするのは、ビジネスやマーケティング、経営といった分野になるでしょう。こうした経済学の様々な「実戦先」のなかで、本書では経済政策を取り上げることにしました。
なぜ経済政策なのでしょうか。経済活動における経済政策の与える影響が、新型コロナウィルスの感染拡大した時期を境に、大きくなってきているからです。新型コロナウィルス感染拡大による移動制約によって、経済社会活動が分断され、持続化給付金を初めとする経済政策が経済活動の継続に大きな役割を果たしたこともさることながら、地域を中心に人口減少と高齢化が深刻化するなかで、地域活性化をしつつ、いかに地域の活動をコンパクト化・ネットワーク化していくのか、老朽化するインフラをどのように群として地域や施設でまとめて保守修繕していくのか、経済政策のあり様が重要になっています。
脱炭素やカーボンニュートラル (2050年までに温室効果ガスの排出を実質としてゼロとすること) も、一企業の努力では達成することは困難です。炭素税や排出量取引をさらに強化させながら、企業の研究開発活動やイノベーションをカーボンニュートラルに向けて進める必要があります。また経済安全保障における政策も、トランプ政権下における米中技術覇権競争を発端として、いまや日本が経済原則で作り上げてきたサプライチェーンを大きく変貌させるまでに至っています。
経済政策に共通するのは、政策を行うことのメリットとデメリットを比較衡量しつつ、判断を迫られるという点にあります。この政策を行うメリットとデメリットは、まだ生まれていない将来世代も含めて、世代によって異なっていますし、また地域によっても異なっています。このように多様な時間軸と多数の利害関係者がいるときに、あるべき経済政策を考えるときに寄って立つべき道しるべとして、経済学の論理構成が役に立ちます。本書が経済政策を使って、経済学を「実戦」する意図がここにあります。
本書の執筆を通じて、経済学と経済政策との違いを意識しました。経済学は概して普遍的で、その根本理論は古くから変わりませんが、多くの経済政策は、経済社会の現実の動きや、そこから生じる新たな課題に対応せざるを得ないという点で、「鮮度」が重要で、逆にいうと、「劣化」の速度も著しいということがあります。本書では、できるだけ「消費期限」が長く、しかし経済学の知見が必要とされる分野を取り上げて章立ててみています。
多くの政策分野を扱いましたが、そうした分野が異なっても、経済学というレンズを通すと、背景に共通する考え方が見えてきます。本書を入り口に、経済学を「実戦」的に使いながら、経済政策を学ぶことの面白さを少しでも感じてもらえると嬉しいです。
(紹介文執筆者: 公共政策大学院 / 経済学研究科・経済学部 教授 / 副学長 大橋 弘 / 2024)
本の目次
1章 経済政策の基礎
2章 経済政策の手法
■第2部 マクロ経済政策
3章 戦後経済政策の変遷
4章 最近の経済財政政策
5章 国際経済
■第3部 ミクロ経済政策
6章 労働・教育政策
7章 成長につながる再分配政策
8章 規模の経済性とインフラ政策
9章 外部性/公共財と地球温暖化対策
10章 情報の非対称性と医療政策
11章 競争政策
■おわりに



 書籍検索
書籍検索