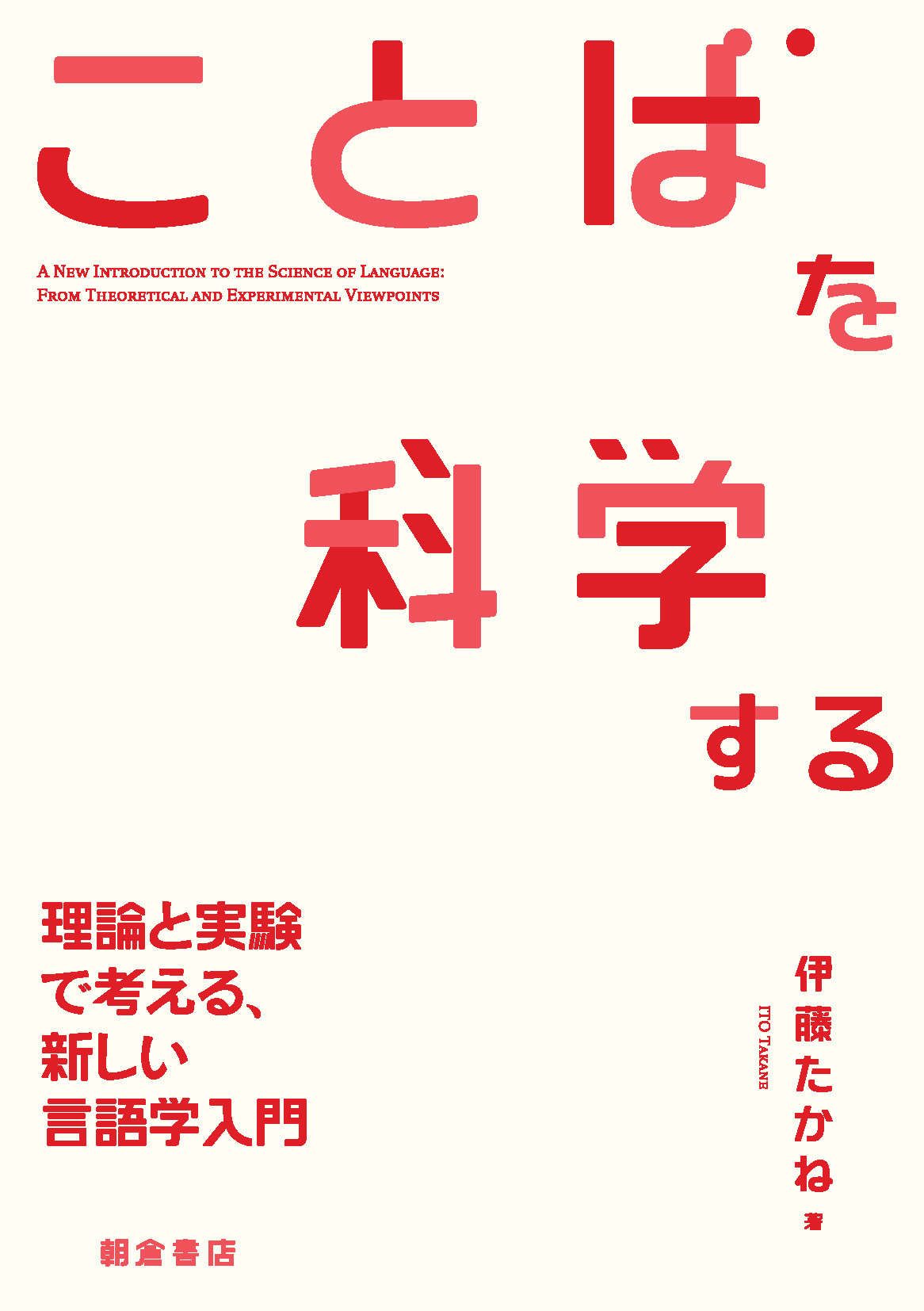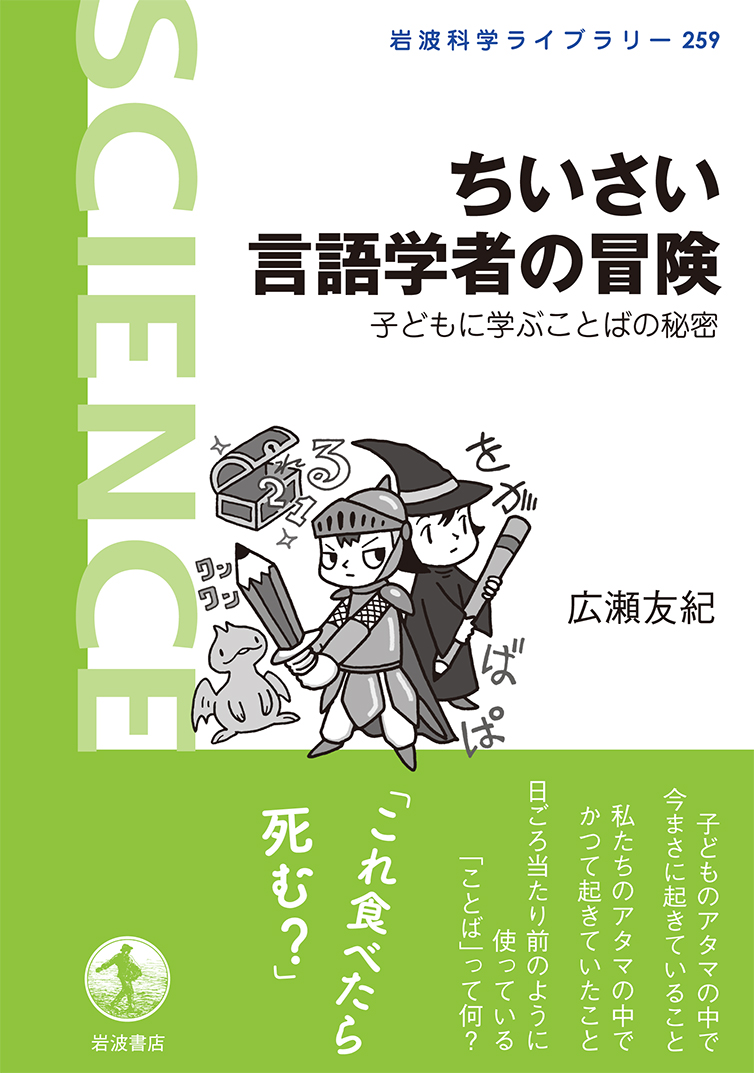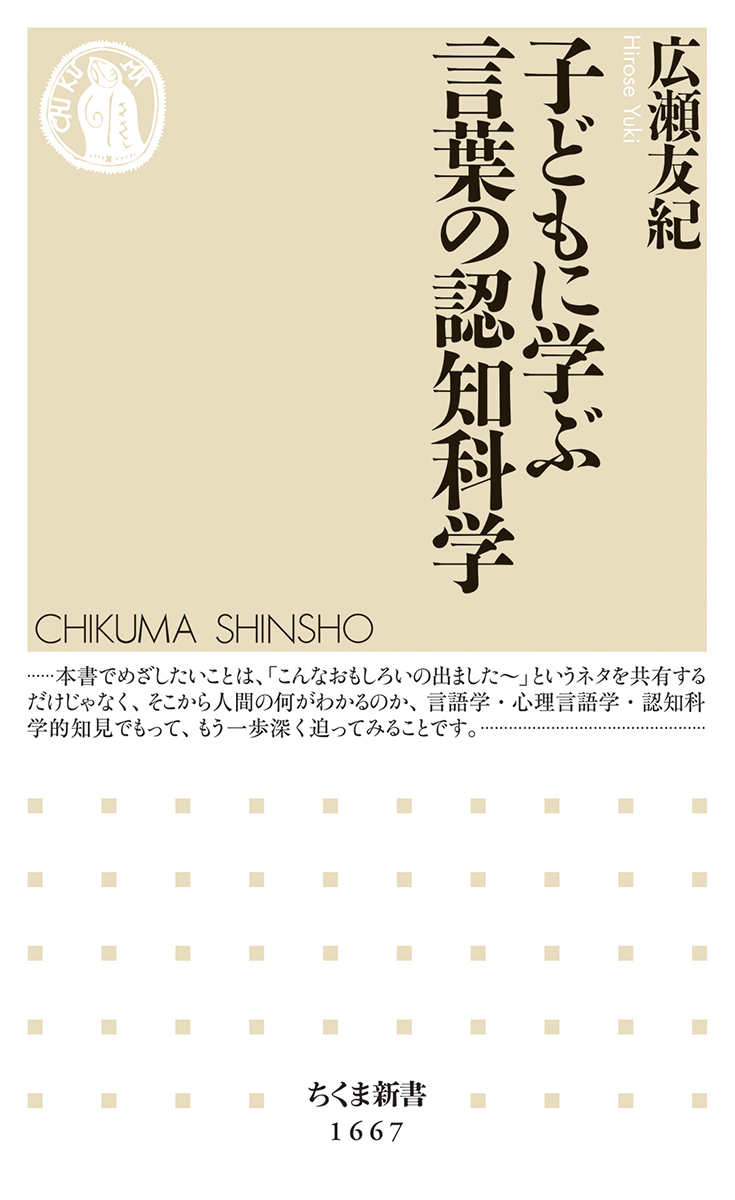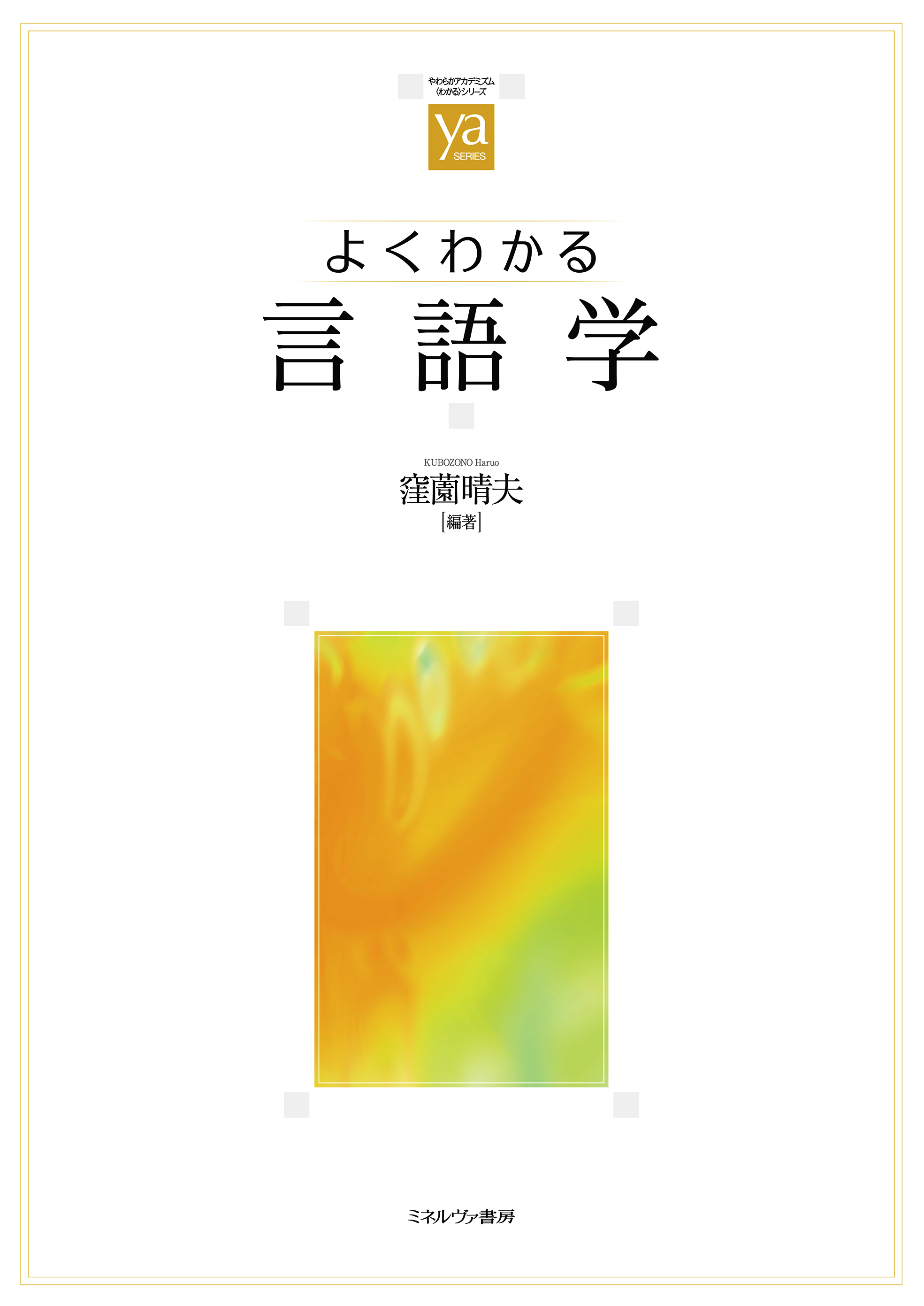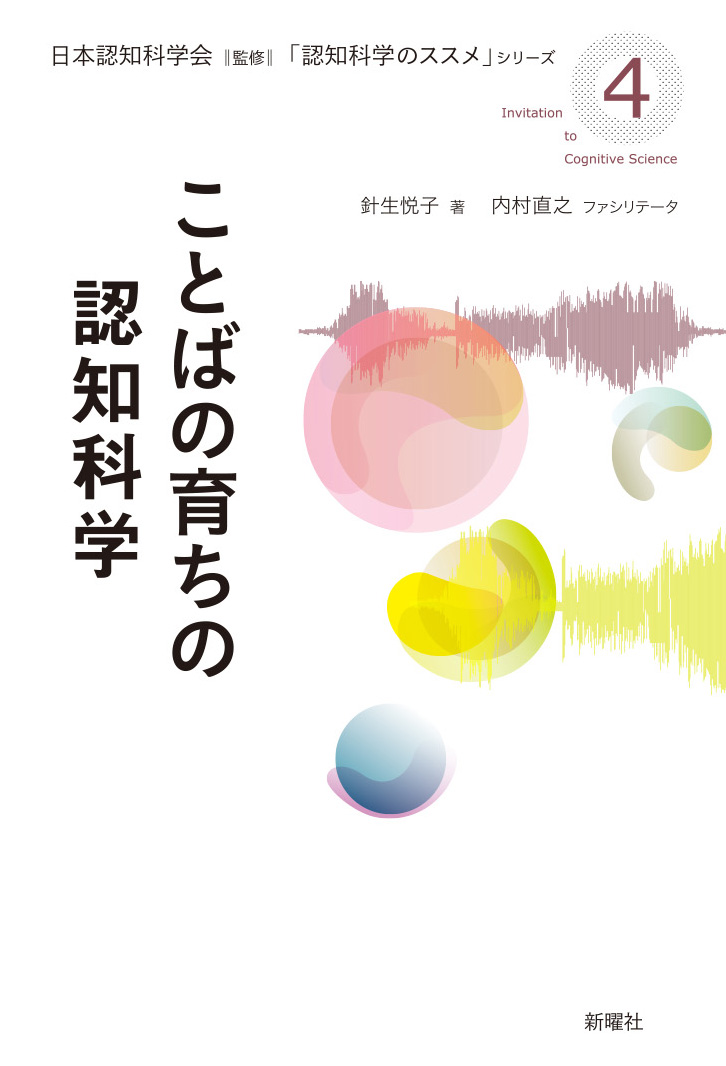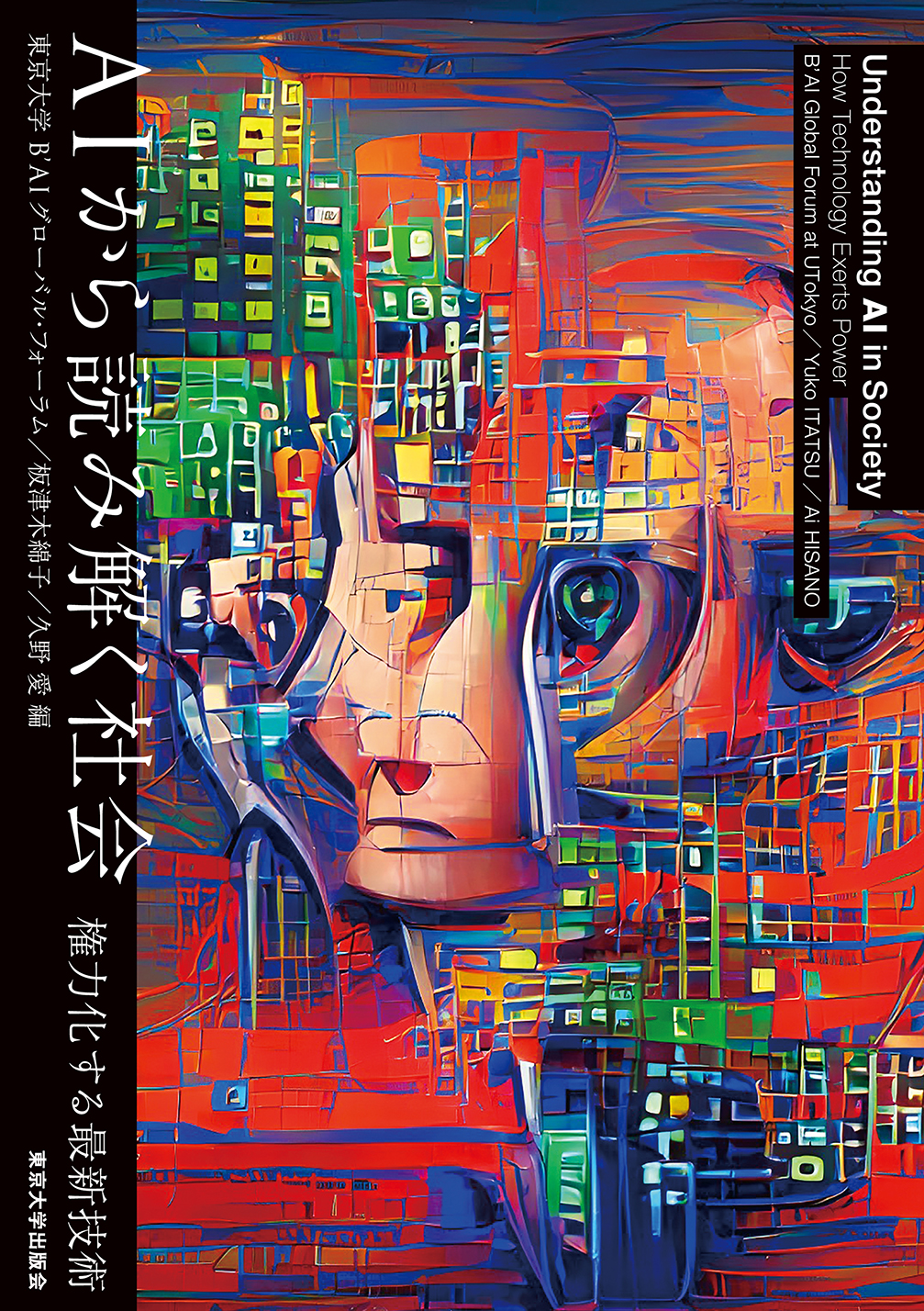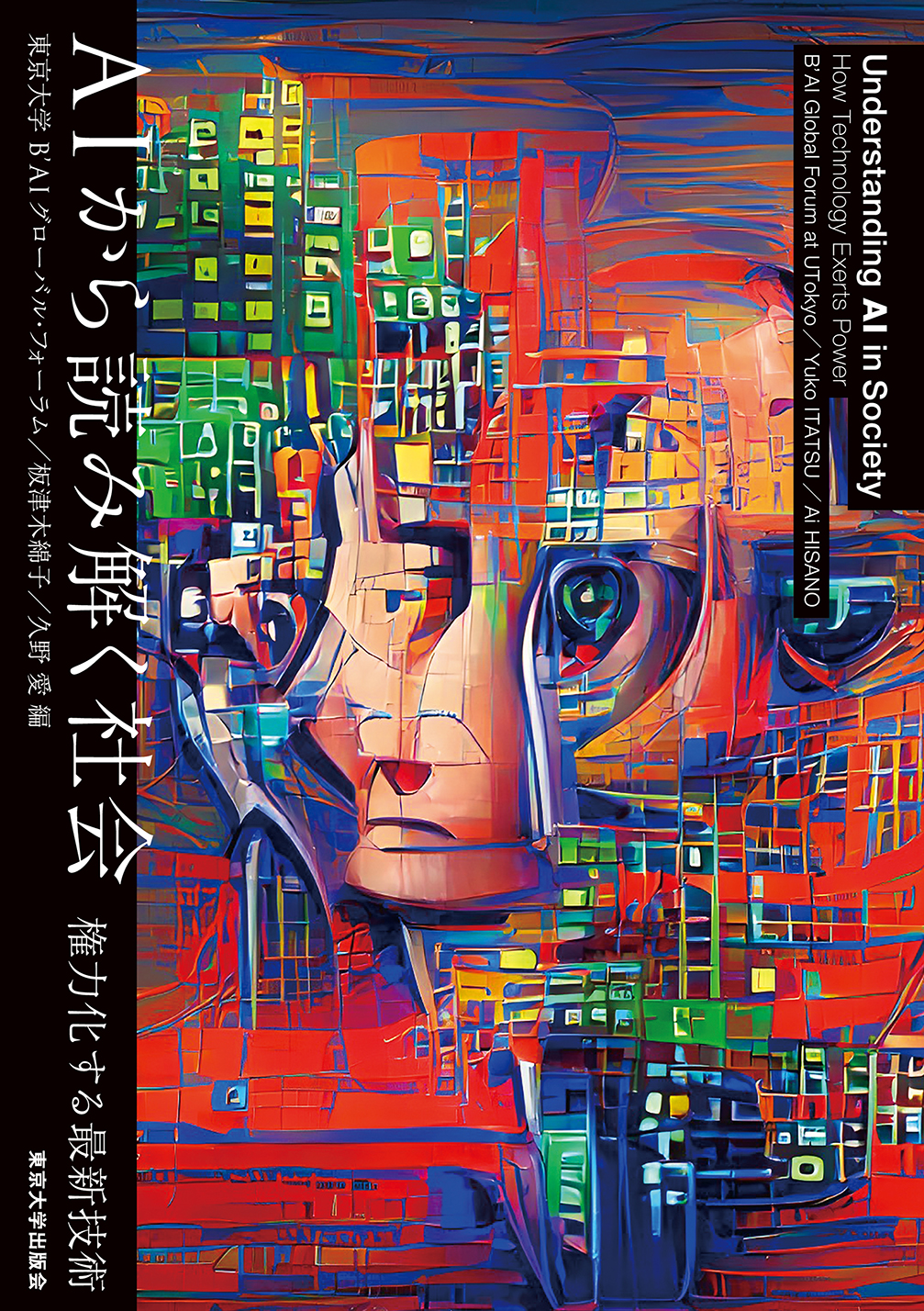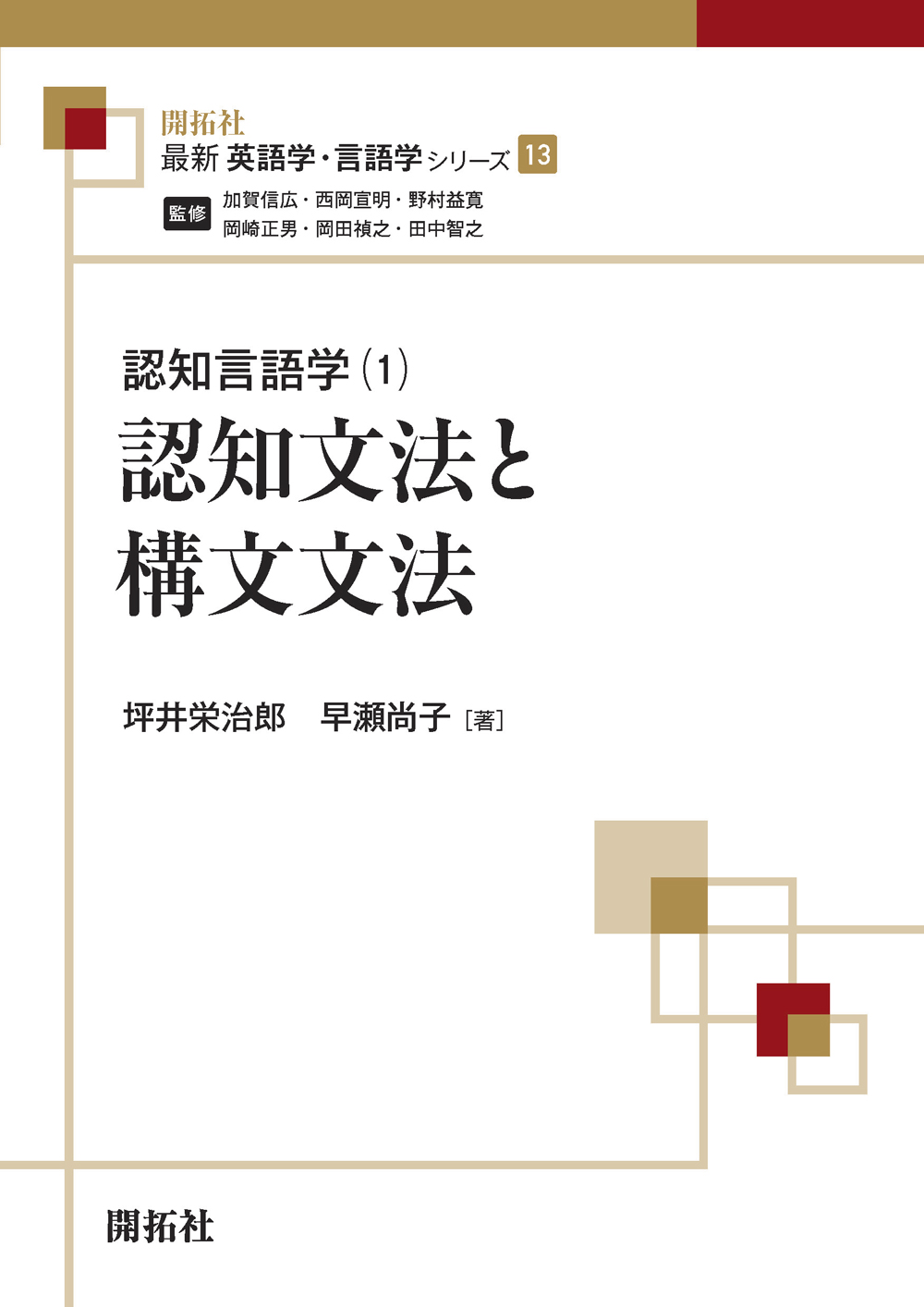「1日おきに電話する」としたら2日に1回なのに、「24時間おき」になると毎日1回になるのはなぜだろう。東京方言 (いわゆる共通語) で、「長野」は人名でも地名でも同じアクセント (音の高低) なのに、「長野氏」と「長野市」では違ってしまうのはなぜだろう。このような、ごく日常的な言語使用にまつわる<不思議>について、私たちの頭の中で無意識のうちにどのような処理がなされているのだろうか、という側面から読者が (できれば周りの人を巻き込んで) 考える機会を提供したい、というのが本書の狙いである。そのため、本書の特色の一つとして、上記の様な<不思議>にまつわる問いを【Q】という形であちこちに散りばめた。楽しみながらじっくり考えてみてほしいと思っている。もう一つの特徴は、各章で実験的な検証を紹介していること。理論言語学を専門にしながら実験的な検証の面白さに目を開かれた自分の経験を、少しでも共有したいと考えてのことである。言語学の入門書は多く出版されているものの、本書はこの二つの特徴によって新しいタイプのテキストになっていると言える。
母音や子音という「音」から始まって、「語」、「文」、「言語の使用」という順序で、小さな単位からより大きな単位へ考察を進める点では伝統的な言語学入門のありかたを踏襲しているが、本書は入門レベルで必要な知識を網羅する形の教科書にはなっていない。<不思議>だな、と思えることを深掘りすると目から鱗が落ちるような分析ができる場合があること、さらにそのような分析の妥当性を実験という形で検証することが可能な場合もあること、そのような分析の楽しさを読者自身が考えながら実体験してもらうことを最優先に考えて、学ぶべき知識の網羅性は必ずしも目指さなかったのである。
このように、「正統的」とは言えない入門書なのだが、これには駒場 (東京大学教養学部) の1-2年生向け授業という出自が関係している。文系・理系を問わず、さまざまな専門課程に進んでいく学生を対象に、リベラルアーツ科目として言語学の初歩を教える際にどこに重点を置くか、という試行錯誤の中でこのスタイルに行き着いた。ことばの使用の<不思議>というのは、すなわち人間の<不思議>である。脳の活動のうち意識されるものはごくわずか、という知識はあっても、知的活動の根幹にある言語の使用は、自分が意識的にコントロールしていると思っていないだろうか。日常的なことばの使用の背後に、意識されない心・脳のどのような働きがあるかに気付かされるたくさんの体験をすることで、自分 (=人間) とは何か、考え直す機会としてほしい。これだけのことを無意識のうちにやりこなしている自分 (=人間) って、すごい、という思いを読者と共有できたら、著者冥利に尽きる。
(紹介文執筆者: 多様性包摂共創センター 特任教授 / 名誉教授 伊藤 たかね / 2024)
本の目次
第1章 ことばを操る─「気づいていない」のに「知っている」とは?
1.1 無意識に駆使される知の体系─母語の体系を私たちは「知って」いるか?
1.2 方言や言語変化をどう捉えるか─正しい用法?優れた言語?
1.3 科学としての文法研究─記述文法と規範文法
1.4 母語の獲得─子どもの規則体系の構築
第2章 ことばを理論的に科学する─仮説を立てて検証するとは?
2.1 仮説を立てる─反証可能な仮説とは
2.2 仮説を検証する─「水が蒸発をする」と言えないのはなぜ?
2.3 通言語的な仮説─主要部の位置
第3章 心と脳の働きを調べる─実験研究のための手法
3.1 心の働きを調べる
3.2 脳の働きを調べる
Part2 音の文法
第4章 音の異同の認知─音素・異音とその処理
4.1 音素と異音─同じ音?違う音?
4.2 言語間の相違─外国語の音の聞き分けと発音
4.3 乳児の音素の獲得─弁別できる音が減っていく?
4.4 音素の産出と認知─周囲の音の影響
第5章 「語」の中の音─日本語のアクセントと連濁
5.1 日本語のアクセント─「花」と「鼻」はどう違う?
5.2 連濁─カバの子どもは「子ガバ」再訪
Part3 語の文法
第6章 同一語の語形変化─屈折と二重メカニズム
6.1 英語の屈折─計算している?記憶している?
6.2 二重メカニズムモデル─記憶も計算も両方必要
6.3 記憶と計算─脳科学からのアプローチ
第7章 語から別の語を作る─複雑語の構造と処理
7.1 複雑語の内部構造
7.2 複雑語の処理
第8章 語の意味と構文─動詞の意味分解
8.1 2種類の他動詞─「たたく」と「開ける」はどう違う?
8.2 構文交替と動詞の意味─「ゴミを散らかす/部屋を散らかす」
Part4 文の文法
第9章 文の階層構造と二階建ての文─日本語の使役文を中心に
9.1 埋め込み構造─その文は何階建て?
9.2 日本語の使役─「乗せる」と「乗らせる」はどう違う?
第10章 名詞句の移動─受身文の構造と処理
10.1 英語の受身文
10.2 日本語の受身文
第11章 節境界を越えた関係─疑問文の構造を中心に
11.1 英語の疑問文
11.2 日本語における島の制約─疑問文とかきまぜ
Part5 ことばの使用の文法
第12章 話し手と聞き手の関係─相手はどこにいる?相手はどう思っている?
12.1 直示表現─「来る」とcomeは同じ?
12.2 話し手と聞き手の想定─眠くない?/眠くないの?
第13章 世界知識と意味─名詞の特質構造
13.1 名詞の意味構造と修飾関係の解釈
13.2 名詞の意味からコトの意味を引き出す
まとめに代えて
第14章 言語の普遍性と多様性─手話から迫る
14.1 手話とは─視覚を用いる自然言語
14.2 手話の特性
14.3 手話言語の処理
14.4 手話から考える言語の普遍性と多様性
参考文献
索引
関連情報
新刊紹介 (『日本語の研究』第20巻3号, pp.119 2024年12月)
https://www.jpling.gr.jp/kenkyu/syokai/
亘理陽一 (中京大学国際学部言語文化学科教授) 評 (中京大学 亘理研究室ver.3.0ホームページ 2024年3月6日)
https://www.watariyoichi.net/2024/03/06/books170/
書籍紹介:
じんぶん堂4周年記念ブックフェア「探訪! 知のワンダーランド」
朝倉書店「おすすめの一冊」 (じんぶん堂小冊子p.05 2024年3月1日)
https://book.asahi.com/book/jinbun/pdf/%E3%80%90%E5%B0%8F%E5%86%8A%E5%AD%90%E3%80%91%E3%81%98%E3%82%93%E3%81%B6%E3%82%93%E5%A0%824%E5%91%A8%E5%B9%B4%E8%A8%98%E5%BF%B5%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A2.pdf



 書籍検索
書籍検索