ロシアのウクライナ侵攻の背景を読み解く

ロシアがウクライナに侵攻してから約1か月。ロシア軍による攻撃が続き、民間人の被害が広がっています。ロシアが軍事侵攻に踏み切った背景に何があるのか。これまでの二国間関係、プーチン大統領の「ネオナチ」発言などについて、歴史社会学の観点からロシア・ユダヤ史やナショナリズム論などを研究し、教養学部でロシア・ウクライナ関係についても講じてきた鶴見太郎准教授に話を聞きました。

© Oleksli / Adobe stock
―― これまでのウクライナとロシアとの関係について教えてください。
ウクライナとロシアとの関係は、必ずしも全貌が明らかではないキエフ・ルーシ(9~13世紀、ロシア人とウクライナ人、ベラルーシ人の共通の起源とされる)の時代を別にすると、ロシア帝国の時代にさかのぼります。
現在のウクライナの大部分はそれまでポーランド・リトアニア王国の領域でしたが、東部地域は17世紀にロシアの支配下に入ります。18世紀末のポーランド分割の際には、中部地域がエカテリーナ2世治世のロシアに、西部はハプスブルク家のオーストリアに併合されました。南下政策を進めるロシアは、オスマン帝国からクリミア半島も獲得します。それらロシア帝国に組み込まれた地域は政府主導で開発が推進され、東部では工業化が進み、鉄鋼業などが発展していきました。ソ連が成立すると、ウクライナはその一共和国となり、西部地域も組み込んで現在の国境が確定しました。
今でもウクライナの西部は農業が中心で、東部は工業が盛んです。私たちのヨーロッパのイメージでは、西に行くほど豊かという印象があると思いますが、ウクライナの場合は東のほうが稼ぎ頭で、かつロシアとの結びつきが強い。言語も、東部はロシア語の通用度がかなり高く、本来ロシアに対して心情的には親和的でした。ウクライナ全体としても、2014年のロシアによるクリミア併合までは、決して敵対的ではありませんでした。調査によって変動はありますが、NATO加盟に関して前向きな国民も、2014年以前はせいぜい3割程度でした。
経済においてもロシアとの関係は非常に重要で、独立以来、2014年を転機に依存度が低下するまで輸出入ではロシアがずっと1位。ロシア資本もかなり入っています。ウクライナの1人当たりのGDPはロシアの3分の1にすぎず、あえてロシアと敵対する動機をウクライナは持たないわけです。
一方でアイデンティティに関しては、1991年の独立以来、「ウクライナ」という単位で考える人が増えています。ソ連では血縁に基づく民族の意識がアイデンティティの基礎になっていて、ウクライナの人口の2割前後を占めるロシア人は必ずしもウクライナ人意識を持っていませんでしたが、独立後のウクライナでは、特に若い世代で、どの国で生まれたかがアイデンティティの重要な要素になってきました。1990年代の調査でも、東部のロシア系住民であってもウクライナ人としての意識を持っていて、西部とあまり変わらないことがわかっています。2014年以降、ウクライナのロシア系住民のあいだで、むしろウクライナ人としての意識を強めている人が増えているという調査結果もあります。社会の実情は、キエフ・ルーシの時代にさかのぼって同民族であることを強調するプーチン大統領の理解とは、かなり乖離しています。


クリミア併合が決定づけた親EU路線
―― ウクライナがEU寄りになった背景は何でしょうか?
1991年の独立後、ウクライナでは親ロシア派と親EU派が交互に政権交代してきました。2004年には「オレンジ革命」という民主革命で親EU派の大統領が誕生し、それに対しロシアはウクライナ向けの天然ガス供給を止めるなどして圧力をかけました。

すると、ロシアと不仲になるのはやはりよくないということで、次はロシア寄りのヤヌコビッチが当選した。そういうジグザグを続けていたので、ロシアからすると何かの拍子にEU寄りになるのではないかという警戒心を常に持っていました。
はたせるかな、2014年のユーロマイダン革命と呼ばれる政変でヤヌコビッチが政権を追われ、ウクライナは一気にEU寄りに傾きました。そこで危機感を持ったロシアが介入し、強引にクリミアを併合したため、ウクライナとの関係は後戻りできないほどに傷ついてしまった。このときを境に、NATO加盟に前向きな国民も年々少しずつ増えてきました。EUの経済的魅力がもともとあったにしても、まさにロシアの行動やあり方を見て、ウクライナ人は最終的にEU寄りになっていったといえます。
大統領選でも、それまではロシア寄りとEU寄りの一騎打ちになる傾向が強かったのですが、2014年以降の選挙では、親EUであることは大前提になりました。その意味では、2019年の大統領選は初めて国内問題がもっぱら争点になった選挙といえ、ウクライナ国内の汚職克服などへの期待から現大統領のゼレンスキーが当選しました。
チェチェン紛争の経験と「強いロシア」
―― プーチン大統領はなぜ侵攻に踏み切ったのでしょうか。
ストレートに言うと、ウクライナをロシア側につけるため、ということに尽きると思います。NATO東方拡大に危機感を持ったとか、ソ連ないしロシア帝国の復活への野望はあるでしょうが、それが現実的にできると誤認したことも重要です。

© 2022 鶴見太郎
プーチン大統領のイメージにあったのは、恐らくチェチェン紛争です。ソ連崩壊後、ロシア連邦として組み込まれるはずだったチェチェン共和国が1991年に独立を宣言し、阻止しようとするロシアとのあいだで武力衝突に至りました。1994年に始まった1回目は制圧に失敗しましたが、2回目は1999年にプーチンが指揮を執ってから力でねじ伏せました。これによってチェチェンの姿勢が180度変わり、今では親プーチンのカディロフが首長です。力を行使すれば同じようなことがウクライナでもできる、ということを考えていたのではないでしょうか。
チェチェン人はムスリムですし、昔からロシアと折り合いが悪かったので抵抗が激しかったのですが、ウクライナ人はロシアを歓迎してくれるはず、とプーチンは本気で思い込んでいたのだろうと思います。
チェチェンは現在もロシア連邦の中で一番貧しい共和国の一つで、人口も100万くらい。しかし、ウクライナは人口も面積もその約40倍です。チェチェンでさえ第二次紛争の収束に10年くらいかかったので、チェチェン並みに抵抗があれば、とても数日のうちに制圧できるはずがない。恐らく、かなり甘い見込みで侵攻したのだと思います。
―― プーチン大統領が掲げる「強いロシア」はなぜ支持されてきたのでしょうか。
1991年のソ連崩壊後、90年代のロシアは経済的に非常に苦しく、西側の支援がどうしても必要でした。その支援は今から思えば失敗で、今日までいろいろな形で尾を引いています。一言でいうと、全部民営化して市場に任せてしまえばうまくいく、という発想でロシア経済の体制転換を進めたことです。今まで国営企業で上からの指令に従ってきた国民は、市場というものをどう泳げばいいか全く分からなかった。急に激流に突き落とされて溺れてしまったというのが実情です。その混乱に乗じて成り上がったのがオリガルヒ(新興財閥)で、社会は犯罪や汚職がはびこり、ゆがんでいきました。
プーチンが大統領に就任した2000年以降、たまたまエネルギーの価格が急上昇し、それによってロシアは10年間の困窮の時期を脱しました。プーチンは、この経済の好転を味方につけながら、「強い国家」の下で社会を立て直していくという像を示した。10年間の苦しい時期を経たロシア人からすると、「強い国家」が秩序を回復してくれるという像はかなり説得力を持っていました。プーチンが陣頭に立った第二次チェチェン紛争に関しても、チェチェン側の猛反撃で泥沼化した第一次紛争で傷ついたプライドを取り戻す、という雰囲気があり、その強硬姿勢が国民に受けたと言えます。
西側との関係でも、ゴルバチョフが始めた冷戦終結は、ロシア人の感覚ではソ連が歩み寄って対等な関係で終結したものだったはずが、西側は自分たちの勝利として理解し、そこから認識のズレが始まっていたように思います。すでに東西ドイツ統一の時点からロシアの少なからぬ部分で不満が渦巻き始めており、事実ゴルバチョフはそれが要因の一つとなって軍にクーデターを起こされました。西側の支援があまり必要なくなったプーチン時代にその傾向が加速し、西側に対峙する意味でも「強いロシア」路線が支持されていきました。
プーチンが「非ナチ化」を主張する理由
―― プーチン大統領は侵攻を正当化する理由の一つとして「ナチ」という表現を使っています。
プーチンにとって、第二次世界大戦の記憶は、ロシア国内をまとめていく際のアイデンティティの核として非常に重要です。ソ連軍がナチスを打ち負かした、これによってソ連はもちろん世界が救われた、という意識を強く持っています。ソ連・ロシアは多民族国家ですが、それが一丸となってナチスに立ち向かったという記憶は、ロシアをまとめる上で重要な意味を持つのです。
ゼレンスキー大統領を「ナチス」や「ネオナチ」と呼ぶのは、ロシアだけでなく、世界のためにロシアが立ち向かうべき敵なんだ、というイメージを植え付けようとしているのだと思います。「ウクライナ人の多くは善良で本当はロシアと仲良くしたいが、少数の危険分子が彼らを惑わしているので、それを駆除する必要がある」という認識です。 ゼレンスキー大統領はユダヤ系で、先祖がホロコーストの犠牲になっているので、ナチスであるわけがないですが、ソ連・ロシアの文脈での「ナチス」は、ユダヤ人を虐殺したことではなく、ドイツの全体主義と軍国主義が世界に混迷と苦難をもたらした、ということがまずイメージされます。ゼレンスキーがユダヤ系だということはあまり気にしていないだろうと思います。
―― 国際社会への影響は?
すでに影響が現れているところでは、ドイツが軍備増強に舵を切りました。今後の成り行き次第でもありますが、ある程度軍事力の強化という流れになるのではないかと思います。
その一方で重要なのは、国際社会の1人1人がこれからどう行動していくかということだと思います。例えば、このような暴挙は国際社会がただではすませないということを、プーチンや、彼を支持する人たちにしっかり伝わるようにするということです。当面は経済制裁くらいしか手段がありませんが、これはロシアの次の行動を左右するだけではなく、例えば中国が今後どうするかという判断にも影響してくるはずです。同じようなことをすると経済的に大きな損をし、何も良いことがないと思わせられるかどうか、ということにかかっていると思います。 また、今回はソ連崩壊後の30年間で培われてきた被害妄想のようなものが効果を持ってしまったところがあります。そうした認識のズレを、ロシアに限らず、世界各地でどう解消していくかも、安全保障上の重要課題であることを物語っています。
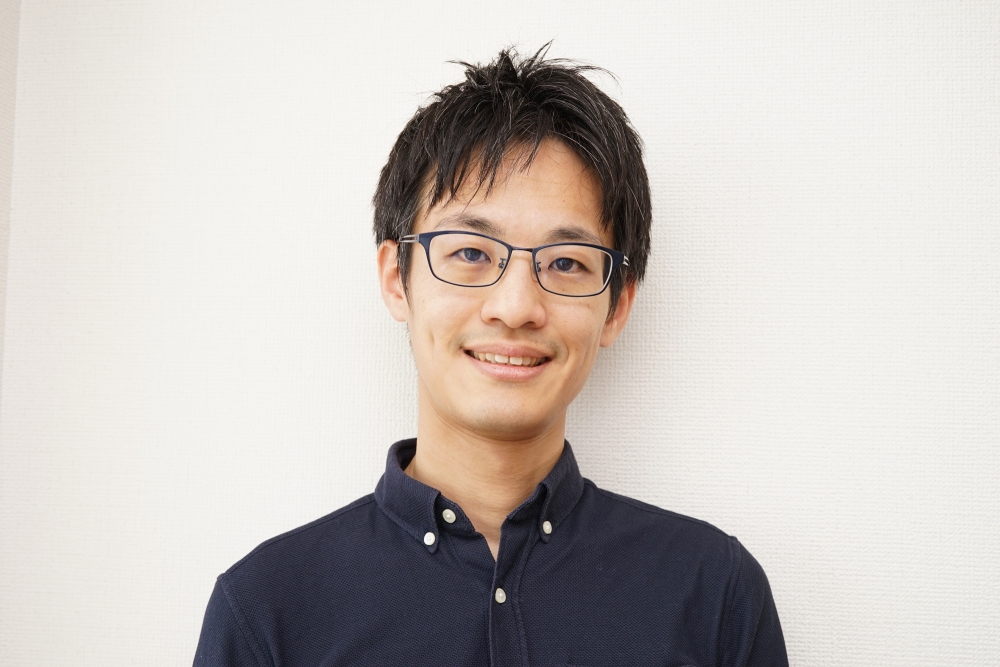
鶴見太郎
総合文化研究科准教授
東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻相関社会科学分野博士課程修了、博士(学術)。エルサレム・ヘブライ大学(日本学術振興会特別研究員として)、ニューヨーク大学(同海外特別研究員として)などにて研究。2016年より現職。著書に、第12回日本社会学会奨励賞を受賞した『ロシア・シオニズムの想像力』(2012年、東京大学出版会)、『イスラエルの起源』(2020年、講談社)など。







