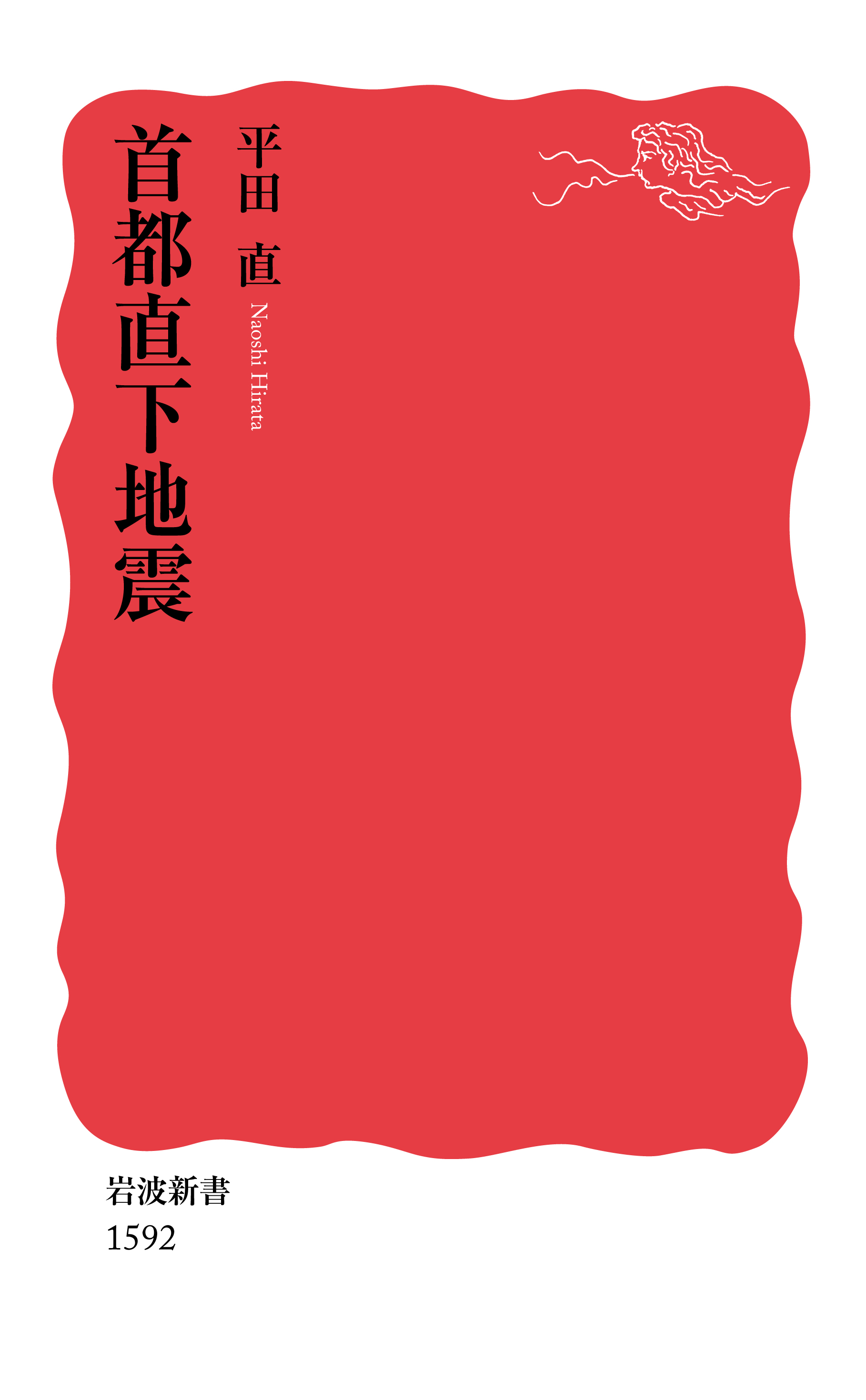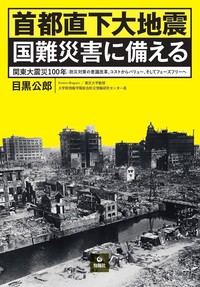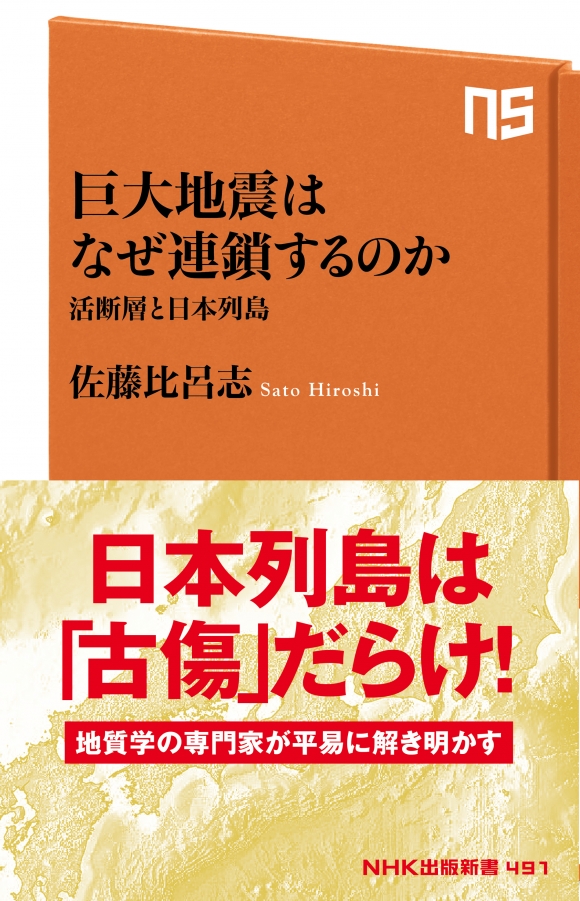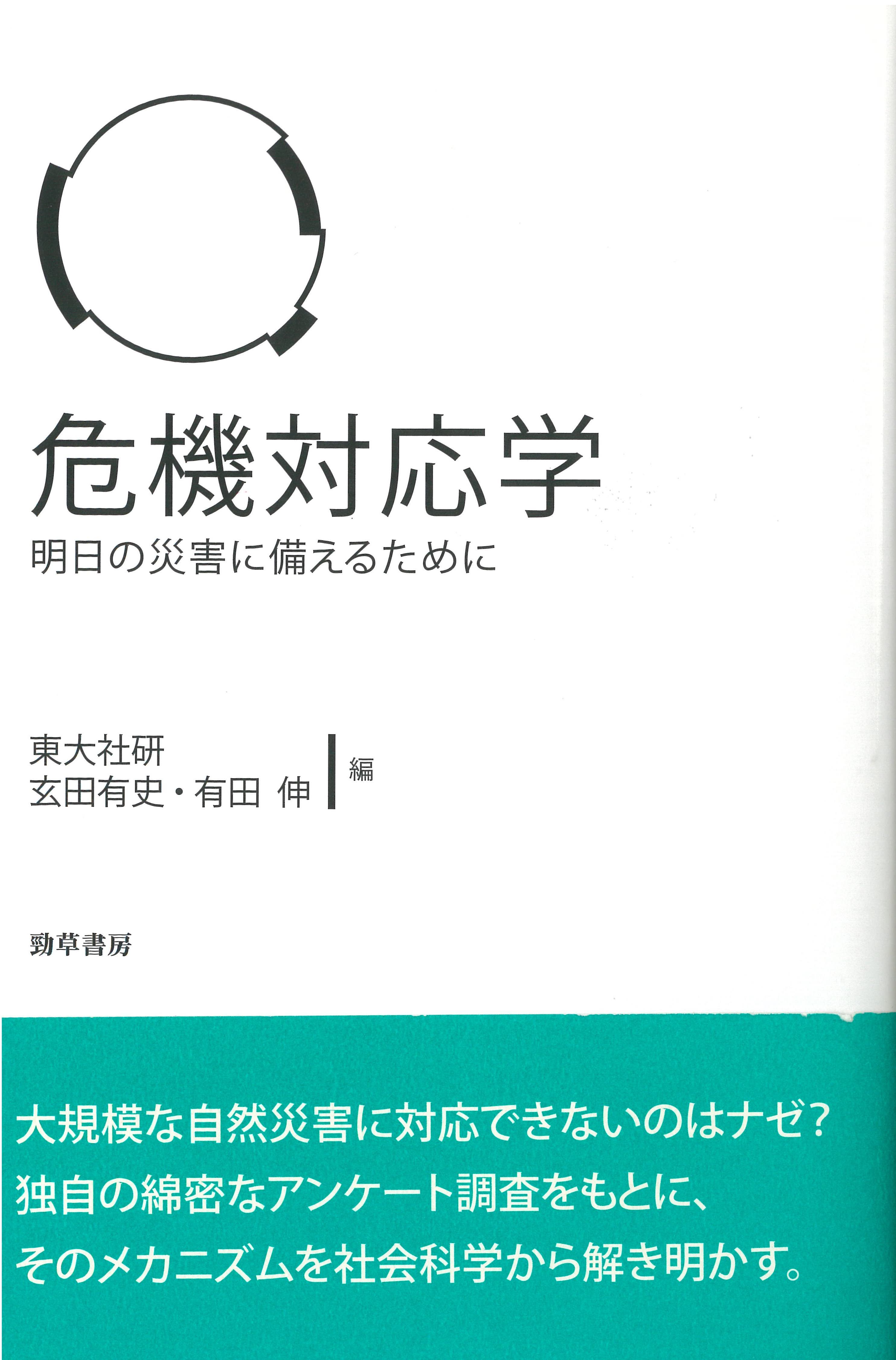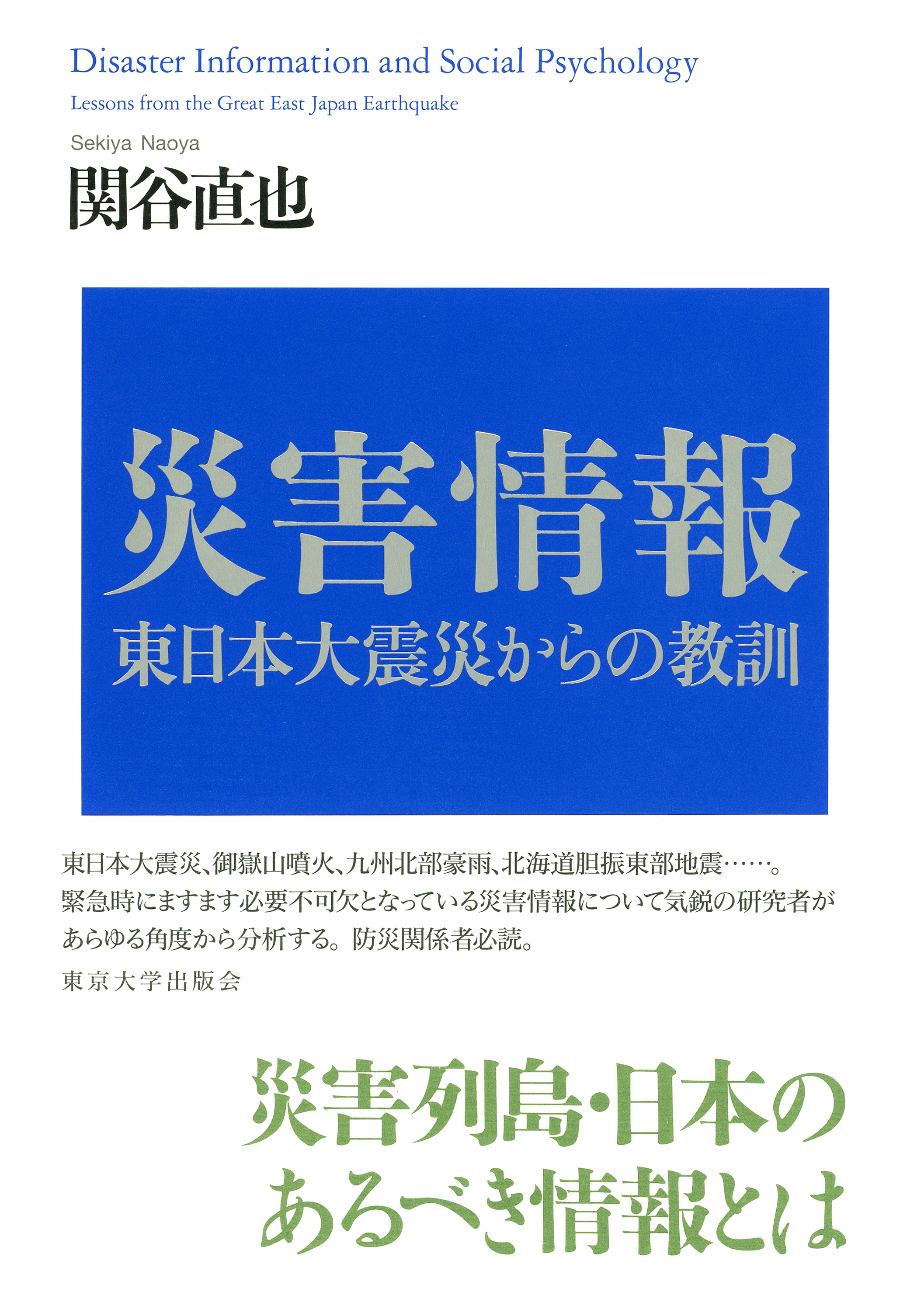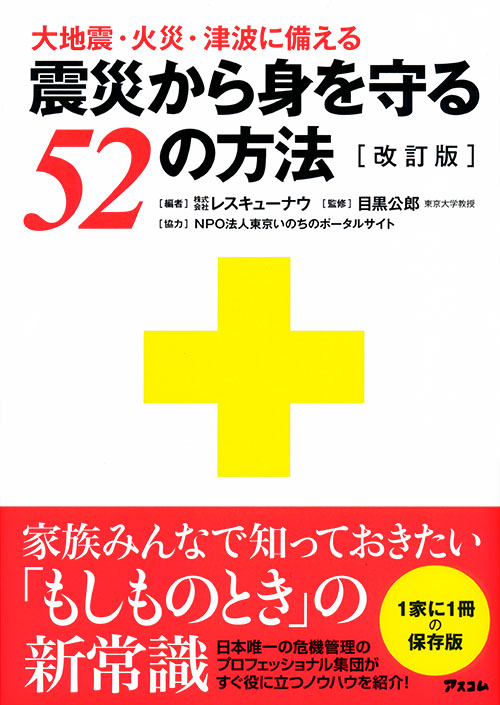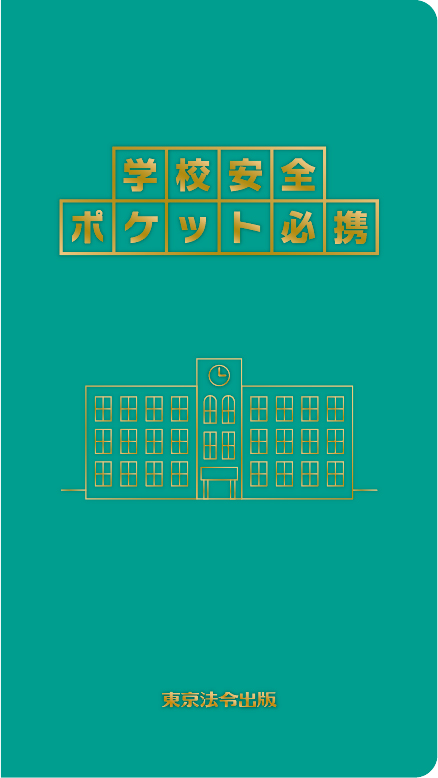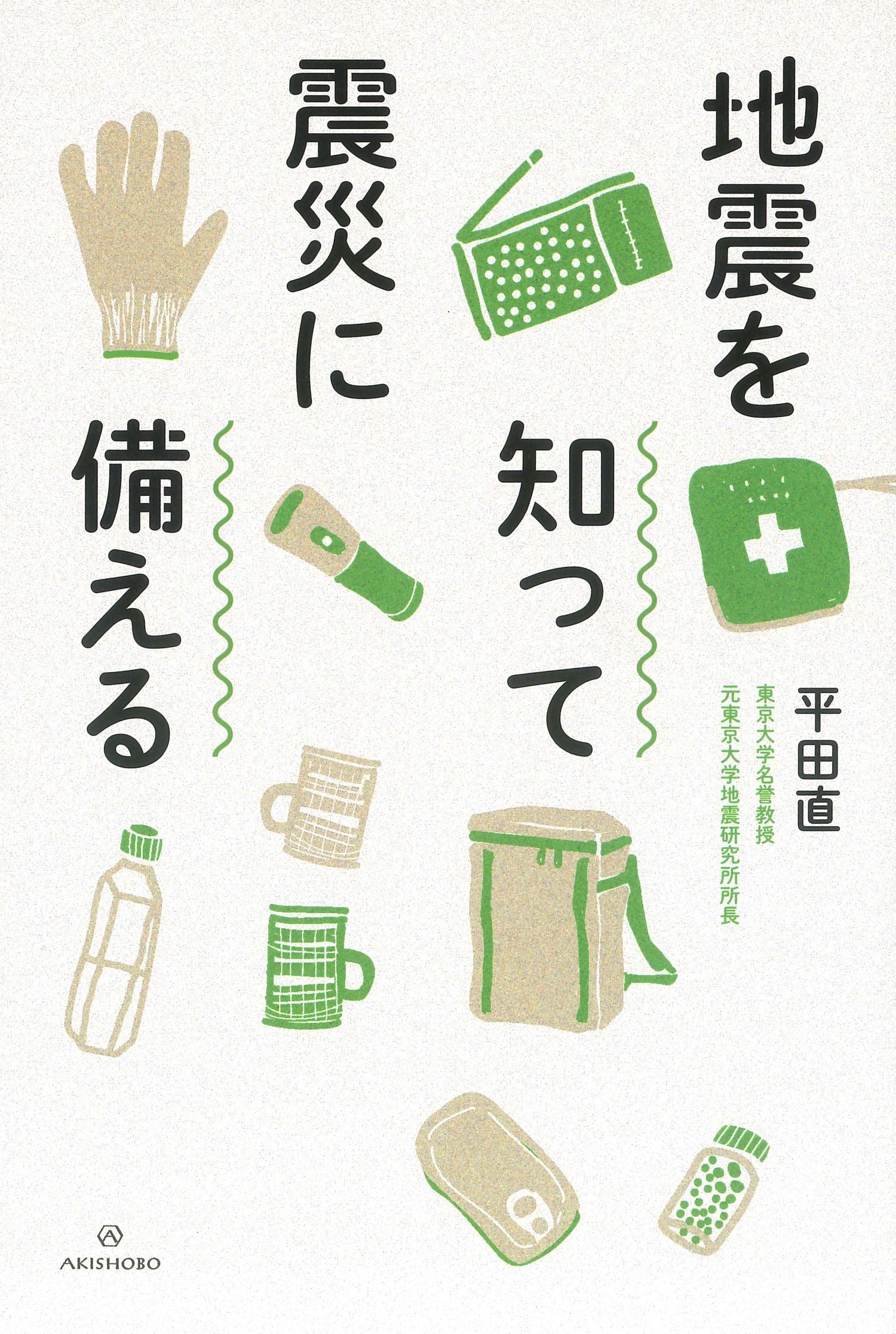
書籍名
地震を知って震災に備える
判型など
112ページ、四六判、並製
言語
日本語
発行年月日
2024年8月30日
ISBN コード
978-4-7505-1846-6
出版社
株式会社 亜紀書房
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
地震とは地下で岩石がずれるように破壊される物理現象である。地震が発生すると周辺に力が加わり、地震波が発生し、これが地表に到達すると地震動 (揺れ) として観測される。地震災害 (震災) とは、その物理現象によって社会が内在的に持つ弱点 (災害素因) によって生じる被害であり、社会・経済現象である。その意味で、正しく地震を知って、なぜ震災が起きるかを知ることは、災害に備えて被害を軽減するために不可欠である。
本書は、2部から構成され、1部、2部とも、インタビュー形式で書かれており、事前の予備知識がなくとも読むことができる。これまでに発生した地震の理学的な特徴と、震災が発生する社会の環境を解説し、理系の学生だけでなく、文系の学生にも読みやすい内容となっている。まず、第1部では、物理現象としての地震として、令和6年能登半島地震や、南海トラフ地震など、最近話題となった地震を取り上げる。日本ではなぜ地震が頻繁に起きるのかを、日本列島の成り立ちと現在の地学的な環境から説き起こして説明する。そのうえで、地震と震災の違いについて述べ、なぜ被害が大きくなったのか、将来も大きくなる可能性があるかを議論する。さらに、地震の発生確率の意味についても考え、震災を軽減するために備えるべきことは何かを議論する。日本は、太平洋プレートという地球上最大のプレートの西端に位置することで、多くの地震が発生する。同時に、日本列島はかつてアジア大陸の一部であったが、約1500万年前に日本海が拡大することで、現在の列島の位置になった。このことが日本列島内部には多くの弱面が存在する原因であり、現在多くの地震が発生する理由の一つとなっている。
第2部では、首都圏で発生する地震を話題にする。これまで、日本で経験した最悪の震災は1923年の関東大震災であり、今後も首都圏で大地震・大震災が発生する可能性がある。これらの地震・震災には、国や自治体から被害想定が公表されている。こうした地震被害想定は何のために、どのような根拠で出されているかを解説して、改めて震災への備えを考える。特に、首都圏などの大都市で震災にあった時にどのように生き延びるかを議論する。1923年の関東大震災では10万人以上が犠牲になった。その約87%が焼死である。当時と現在では都市の環境、特に建物の環境が大きく異なっている。しかし、現在の首都圏でも地震火災による被害が甚大であると考えられている。震災時にまず優先するべきことは人命を守ることである。この為には、まず揺れても壊れないように、建物を耐震化することである。地震火災は、倒壊した建物からの出火が重要な要素であり、耐震化は出火防止にも不可欠である。さらに、学校や職場で発災したときには、堅牢な建物にいるならばオフィスにとどまれ、無駄に動くなということが強調されている。発災時には鉄道などの公共交通が不通になる。そのため、道路は人と車で大渋滞となる。しかし、発災後72時間は、救命救急活動を優先する必要があるために、緊急車両以外は、道路を使わないようにすべきである。また、自宅の耐震性が確認されていれば自宅に留まり、避難所に行く必要は無い。しかし、耐震化されていても、電気・水道・ガスなどが途絶すれば、在宅生活は難しくなる。特に、都市で上下水道が使えなくなれば水洗トイレが使えなくなる。被災時に自宅で生活を続けるためには、水・非常食・常用薬の備蓄が不可欠である。
(紹介文執筆者: 地震研究所 名誉教授 平田 直 / 2025)
本の目次
1.地震を知って、震災に備える(聞き手・亜紀書房編集部)
◆日本ではなぜ地震が頻繁に起こるのか
◇日本列島と地震の関係
◆能登半島の地震とはどんな地震なのか
◇なぜ、被害が大きかったのか
◆地震の確率について考える
◇つねに準備をしておく
2.首都直下地震に備え、関東大震災に学ぶ(聞き手・森まゆみ)
◆地震予知はできるか
◇地震は続けて起こりやすい
◆国の防災体制
◇関東大震災といま
◆古き良き町とだけはいっていられない
◇東京都の防災計画
◆オフィスにとどまれ、無駄に動くな
◇避難所に行くのは家が壊れて住めない人だけ
◆避難場所と避難所は違う
◇いまそれぞれがすべきことは
おわりに
関連情報
書籍紹介:
福島隆史 (TBSテレビ報道局)「書籍紹介」 『日本災害情報学会』ニュースレターNo.99 2024年10月)
http://www.jasdis.gr.jp/_src/3016/n-letter99.pdf?v=1743655482332
ラジオ出演:
防災FRONT LINE「なぜ? 日本で地震が多いのか」 (Tokyo FM 防災FRONT LINE 2024年11月2日)
https://www.tfm.co.jp/bousai/index.php?itemid=203178&catid=1476
https://audee.jp/voice/show/92756
セミナー・講座:
NEW! 第140回(2025年春季)東京大学公開講座
平田 直「日本の震災と地震研究 -予測可能性―」 (東京大学 2025年6月14日)
https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/events/e_z0801_00022.html
https://sites.google.com/g.ecc.u-tokyo.ac.jp/publiclectures
住まいと生活を安全・安心に~木耐協オンラインセミナー【2025年第1回】
『地震災害への備え&悪質業者の現状と対策』
講演1) 「地震を知って震災に備える」 (日本木造住宅耐震補強事業者協同組合 2025年4月12日)
https://www.mokutaikyo.com/bousai/
「阪神・淡路大震災から30年を迎えて、改めに震災に備える」 (震災対策技術展 2025年2月6日)
https://www.shinsaiexpo.com/yokohama/2025s01/
特別講演「能登半島地震、日向灘地震を経験して首都圏で備えるべきこと」 (国土交通省国土技術政策総合研究所 2024年12月12日)
https://www.nilim.go.jp/lab/bcg/kisya/journal/kisya20241120.pdf
関連記事:
南海トラフ地震にどう備える 死者数32万人、経済被害は292兆円 (日経ビジネス 2025年4月1日)
https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00081/030500779/



 書籍検索
書籍検索