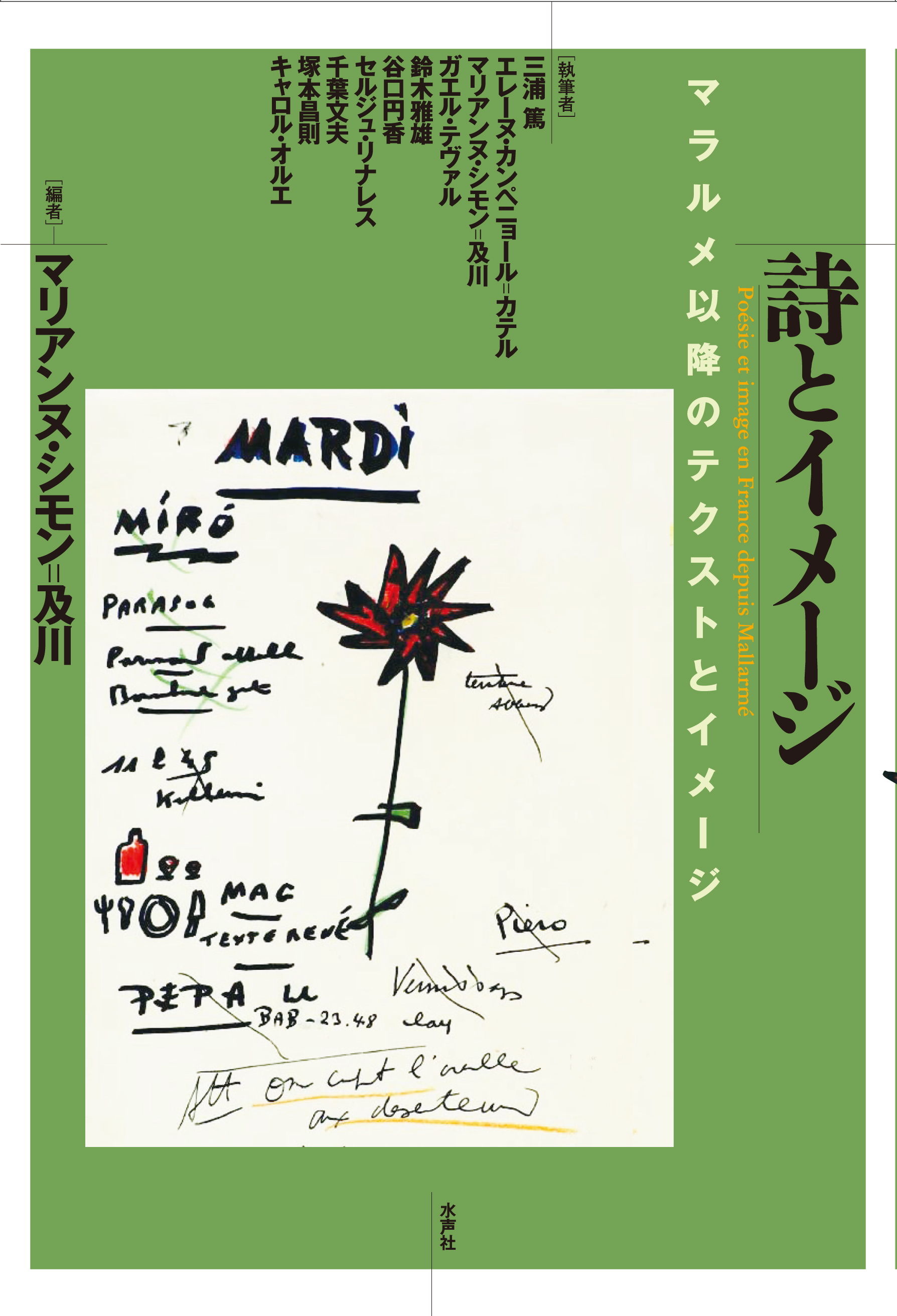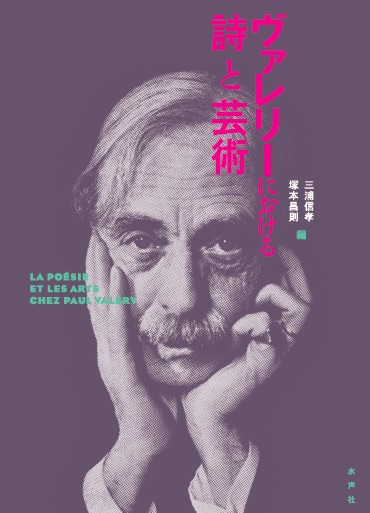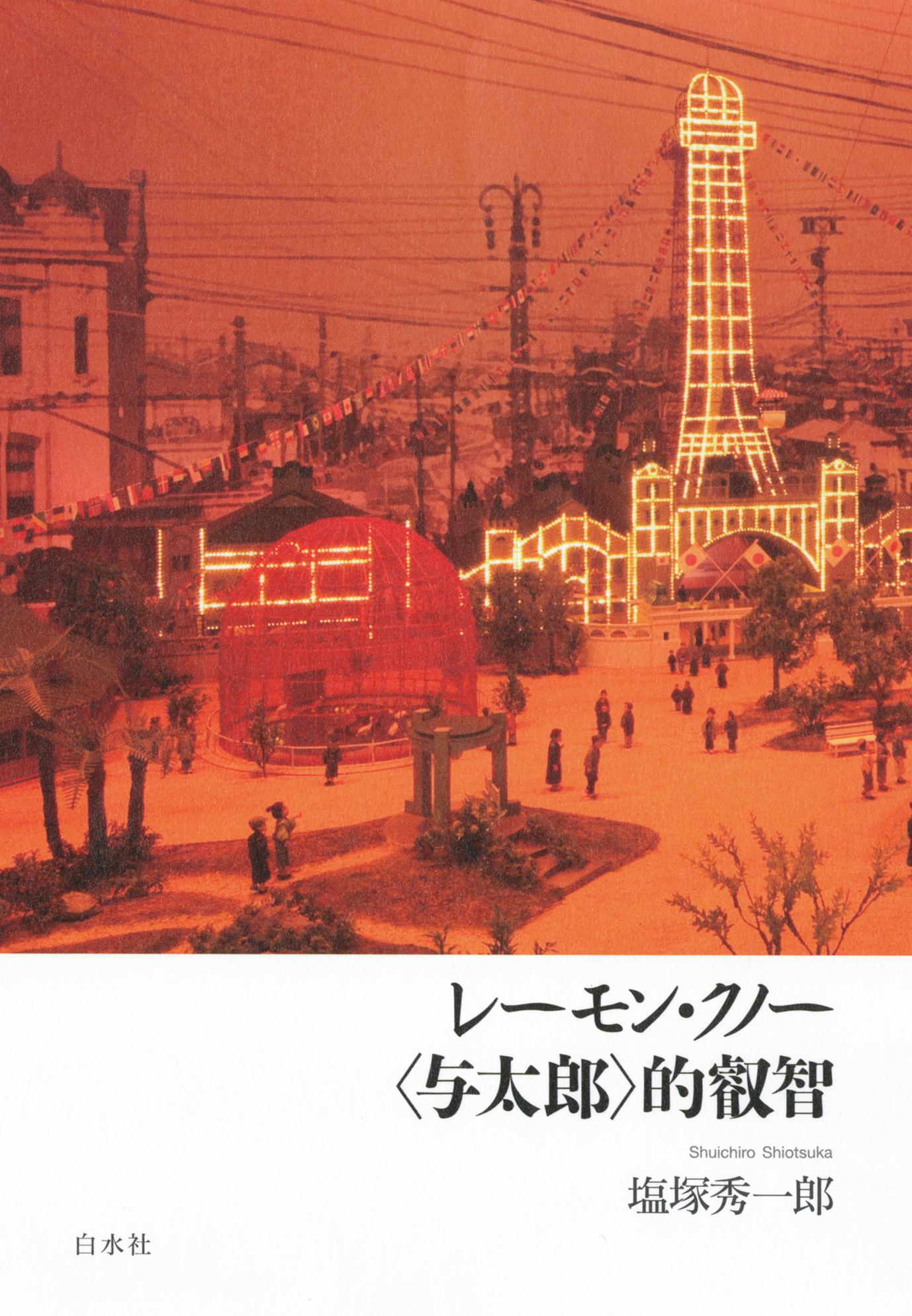西欧では、文学、特に詩と美術との関係は、広く古代から認められる。文学的な作品による美術品の描写、視覚美術から文学への借用、詩と美術とが同じ媒体の上に共存していることなどは、これらの関係の多様性を示している。
フランスの十九世紀は、詩とイメージとの関係が深められ、刷新された時代である。マラルメの果たした役割は本質的なものであった。マネの友人であったマラルメは、1874年に書いた有名な論文の中で、マネを擁護した。次いで彼は二つの重要な作品において (1875年の『鴉』と1876年の『牧神の午後』)、マネとの共作を実現し、1876年に制作された有名な『肖像画』のためにポーズをした。『骰子一擲』は、マラルメにとっても、視覚詩の歴史に於いても記念碑的な作品であった。絵画に関するテクストからイメージによって作られた詩まで、マラルメの詩作品は見る物と読む物の間に、多くの可能な関係を開拓した。彼の作品を我々の考察の出発点とすることは自然なことである。しかしマラルメ以降、詩とイメージとの関係は、変容を重ね続けて来た。書物の中のイメージは、挿絵以外の形態を持つようになった。イメージも絵画だけに限定されることなく、目に見えるあらゆる範囲に拡大して行き、タイポグラフィやページの白い空間にまで及んできた。
本書の第一部は、マラルメに関する内容である。三浦篤は、画家のマネの側から考察している。マラルメと詩の本との関係により限定して言及するエレーヌ・カンペニョール=カテルは、マラルメの詩作品が詩の本の大きな傾向を現代に至るまで、決定したと述べている。
第二部では、マリアンヌ・シモン=及川は、20世紀の詩人であるピエール・アルベール=ビローのケースを研究している。コラージュやフォトモンタージュやレディーメイドなどは現代でも詩人の創造性を養い続けている。ガエル・テヴァルはジャン=フランソワ・ボリーの作品を紹介している。
テクストとイメージの併存は、挿絵だけではない。第三部では鈴木雅雄が、ゲラシム・ルカのケースを研究し、谷口円香は、ロジェ・ド・ラ・フレネの遺稿と言う形で出版されたランボーの『イリュミナシオン』のための習作の分析をしている。
本書の第四部では、セルジュ・リナレスが指摘するように、ピカソは挿絵には危惧を持っていた。千葉文夫は、ピカソによるレリスの一連の肖像に関して、分析を行っている。
本書の最終章は絵を考える詩人、絵と遊ぶ詩人への考察である。塚本昌則はヴァレリーの写真に関する考察を分析している。キャロル・オルエが述べているように、ジャック・プレヴェールは最初に手に入れたイメージから、すっかり意味を変えたコラージュを制作している。
本書は、『絵を書く』(水声者、2012年) と同じく、日本学術振興会の2011年4月から2014年3月の支援による、研究プログラムの研究成果の発表である。
(紹介文執筆者: 人文社会系研究科・文学部 准教授 マリアンヌ・シモン=及川 / 2018)
本の目次
第I部 イメージの世界、詩の世界——本という媒体の変貌
三浦 篤 / マネとマラルメ――絵画と詩の共鳴
エレーヌ・カンペニョール=カテル / 書物の歌——詩集の変容
第II部 詩集の中のイメージ
マリアンヌ・シモン=及川 / ピエール・アルベール=ビロー――詩集に書かれたイメージ
ガエル・テヴァル / ジャン=フランソワ・ボリーの視覚詩における活字のコラージュと本のレディ・メイド
第III部 イメージを詩にする――挿絵の多様性
鈴木雅雄 / 読めないテクスト、見えない書物——ゲラシム・ルカの視覚的実験
谷口円香 / ランボーの『イリュミナシオン』とキュビスム――ロジェ・ド・ラ・フレネの「『イリュミナシオン』のための習作」について
第IV部 ピカソという巨人
セルジュ・リナレス / 詩の挿絵画家ピカソ
千葉文夫 / ミシェル・レリスの肖像
第V部 イメージを考える、イメージと遊ぶ詩人
塚本昌則 / ヴァレリーと写真
キャロル・オルエ / ジャック・プレヴェールと静止したイメージ
関連情報
千葉文夫 (ほか共著) マリアンヌ・シモン=及川(編著)『詩とイメージ マラルメ以降のテクストとイメージ』(REPRE vol.25, 2015年9月16日)
https://repre.org/repre/vol25/books/02/04.php



 書籍検索
書籍検索