社会とともに歩む東京大学
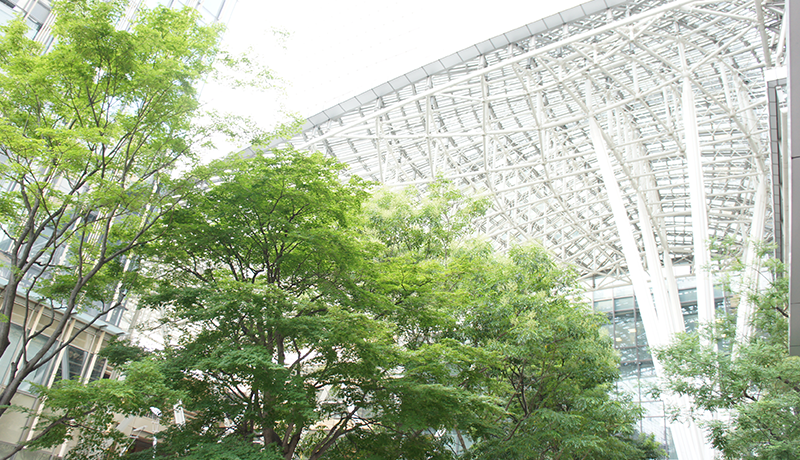
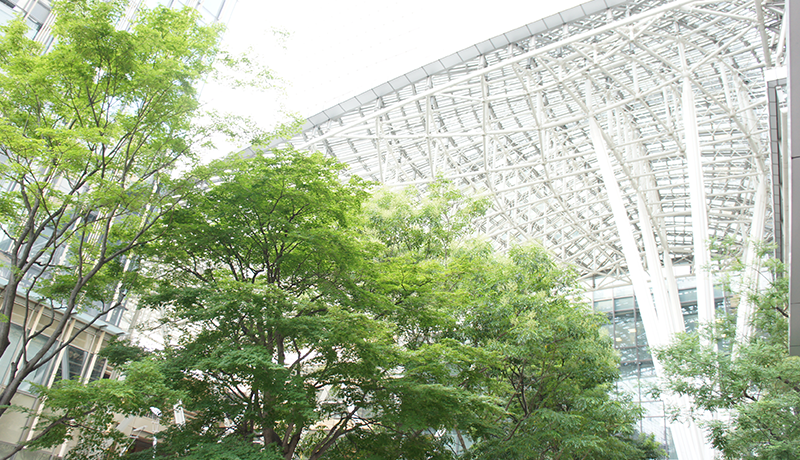
「社会とともに歩む東京大学」とは
近年の地球的な規模の危機は、それを解決する知の担い手である大学の社会的役割への期待を高めています。また、大学の使命の根幹である教育と研究の展開の上に、社会連携が大学の第三の使命として重要性を増してきました。
東京大学は、学問の自由と自律を基盤に、世界に向かって自らを開き、社会の過去・現在・未来に対して責任を持ちうる教育・研究活動を行いながら、大学と社会との双方向的な連携を推進することを基本理念としています。
大学が社会と関わりあう回路は無数にありますが、よりいっそう「社会に開かれた大学」として、大学から社会への研究成果の還元という一方向だけでなく、大学と社会が協働して課題を発見・共有し、新たな知とイノベーションを生み出す「知の共創」と呼ぶべき双方向の活動を推進するため、社会連携に関する基本方針を以下のとおり定めます。
- 「東京大学における社会連携に関する基本方針」 (PDFファイル: 95.1KB)
- 「社会とともに歩む東京大学」リーフレット版 (PDFファイル: 2.2MB)
- 「ソーシャルメディア運用方針」 (PDFファイル: 58.7KB)
1. 研究成果を社会に還元し、社会との「知の共創」を進めます。
21世紀社会においては、地球環境、エネルギー、少子高齢化といった課題が顕在化してきています。課題の解決には、大学と社会・企業での活動を双方向に連携させていくことが必要であり、大学と社会の「知の共創」と呼ぶべき活動を進めていく段階に来ています。本学では、平成16年度に設置された産学連携本部を中心に、「知の共創」の推進に向けた活動を推進し、大学と社会が共働して課題を発見・共有し、解決を図るための活動をさらに展開するため、今後も取組んで参ります。
また、本学には最先端の知が結集していますが、一方では社会の中にも種子は宝の山のようにあります。それらをネットワーク化して共に知識を創っていく新たな試みとして「知の共創プラットフォーム」や、各種寄付講座を設置・実践していきます。
【具体的な事業の例】
- 産学連携事業の推進(産学連携本部)

- 各種寄付講座の設置(研究推進部学術振興企画課)
- 持続可能な未来社会を創造するために、未来社会の諸課題に関する政策・社会提言ならびにそのための社会連携研究を行う(未来ビジョン研究センター)

- 初等中等教育の質の向上に寄与する活動(大学発教育支援コンソーシアム推進機構)

2. 教育、研究活動をわかりやすく、広く社会に伝えます。
本学では、社会連携と呼べる活動をすでに幅広く行っています。公開講座やアウトリーチ活動ばかりでなく、様々な集まりで企業や市民の方々と議論する機会や政策提言等を行う機会は少なくありません。
このような社会連携活動や本学の教育・研究活動をホームページや、一般公開等を通じて、社会に対して発信し、より身近なものとして理解していただけるように取組んでいきます。
【具体的な事業の例】
- 教育・研究活動の情報発信
- 「オープンキャンパス」や一般公開等の施設公開
- 情報通信技術等による公開授業の拡充 (大学総合教育研究センター)

- 「コミュニケーションセンター(UTCC)
 」、「伊藤国際学術研究センター(IIRC)」
」、「伊藤国際学術研究センター(IIRC)」 の運営
の運営
3. 卒業生、大学への理解者とのネットワークを育てます。
大学が教育を通じて有為の人材を育成することは、社会連携のもっとも重要な回路であり、本学が生み出した人材は、社会の多様な分野で活躍しています。こうした卒業生や大学の教育・研究活動に対する幅広い理解者との緊密なネットワークを形成していくことは、大学の活動に対する幅広い支援の基盤となるとともに、大学の知と社会の知の連環を活性化させる上でも重要な意味を持つことから、卒業生等との連携を推進していきます。
【具体的な事業の例】
- 「ホームカミングデイ」の開催

- 卒業生が参画する活動の実施
4. 広く社会に向けて教育活動を行います。
本学では、「東京大学エグゼクティブ・マネジメント・プログラム(東大EMP)」や「グレーター東大塾」といった社会人向けのプログラムを開講しております。また、どなたでも御参加いただける公開講座や各種講演会等の開催、小中高生を中心に出張授業等も行っております。今後も、社会に開かれた大学を目指し、これら教育の社会連携というべき活動を積極的に推進・展開していきます。
【具体的な事業の例】
- 社会人を積極的に受け入れる柔軟な教育システムの構築・運用
- 社会人向けのプログラムの開発・実施(「東京大学エグゼクティブ・マネジメント・プログラム(東大EMP)」
 、 公開講座
、 公開講座 、講演会、「グレーター東大塾」、履修証明プログラム等)
、講演会、「グレーター東大塾」、履修証明プログラム等) - 専門職大学院における教育の充実
5. 地域等とともに様々な活動を進めます。
本学では、キャンパスが所在する地域や広く関係自治体、国及び国際機関とも相互に緊密な連携をはかるとともに、学術研究、人材の育成及び地域社会の発展に寄与する諸活動を実施しています。
【具体的な事業の例】
- 本学が保有する資源を活用した地域貢献
- 自治体等の審議会・委員会への参画
- 地域等との連絡調整
6. 社会とともにあるために、東京大学基金を拡充していきます。
本学は日本を代表する大学として、いつの時代も真理を探求し、社会が解決を求める様々な課題にいち早く取り組み、人々の豊かな未来を築くための教育・研究に邁進していきます。そのための教育・研究活動及び社会連携活動等を長期に渡り推進していくためには、財政基盤の充実・強化は不可欠となります。
本学はそのために平成16年10月に「東京大学基金」を設置し、2027年に迎える本学創立150周年に向けて「UTokyo NEXT150」と称し、2026年度末までに残高200億円を目標として、ディベロップメントオフィスを中心に広く社会からのご理解とご支援をお願いしています。
【具体的な事業の例】
- 東京大学基金の充実

- 奨学制度の充実支援
- 研究者の研究活動支援
- キャンパス環境の整備支援




