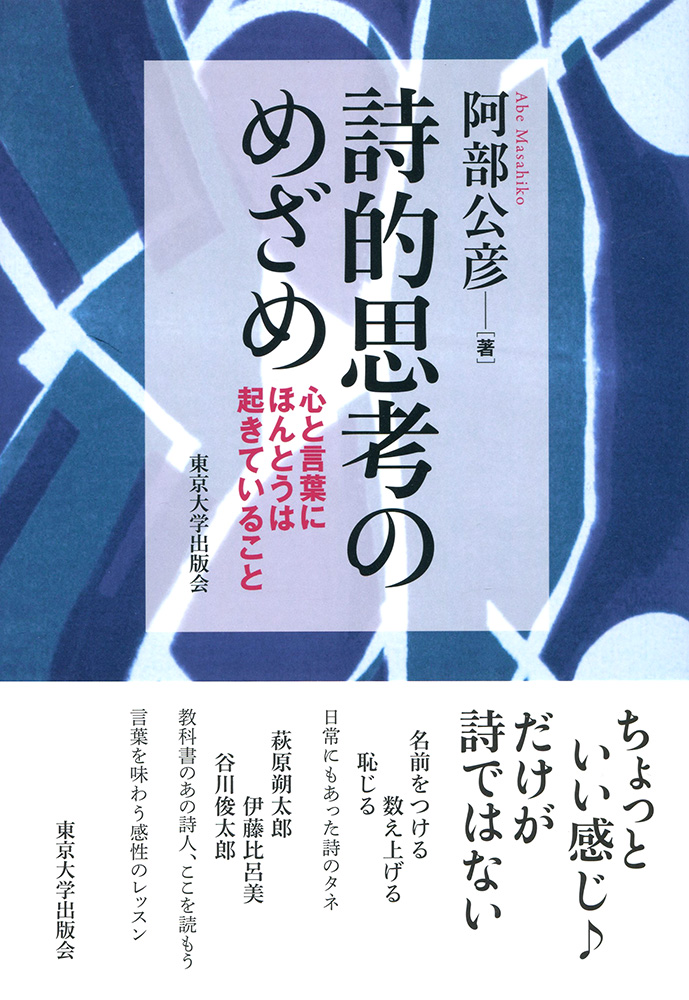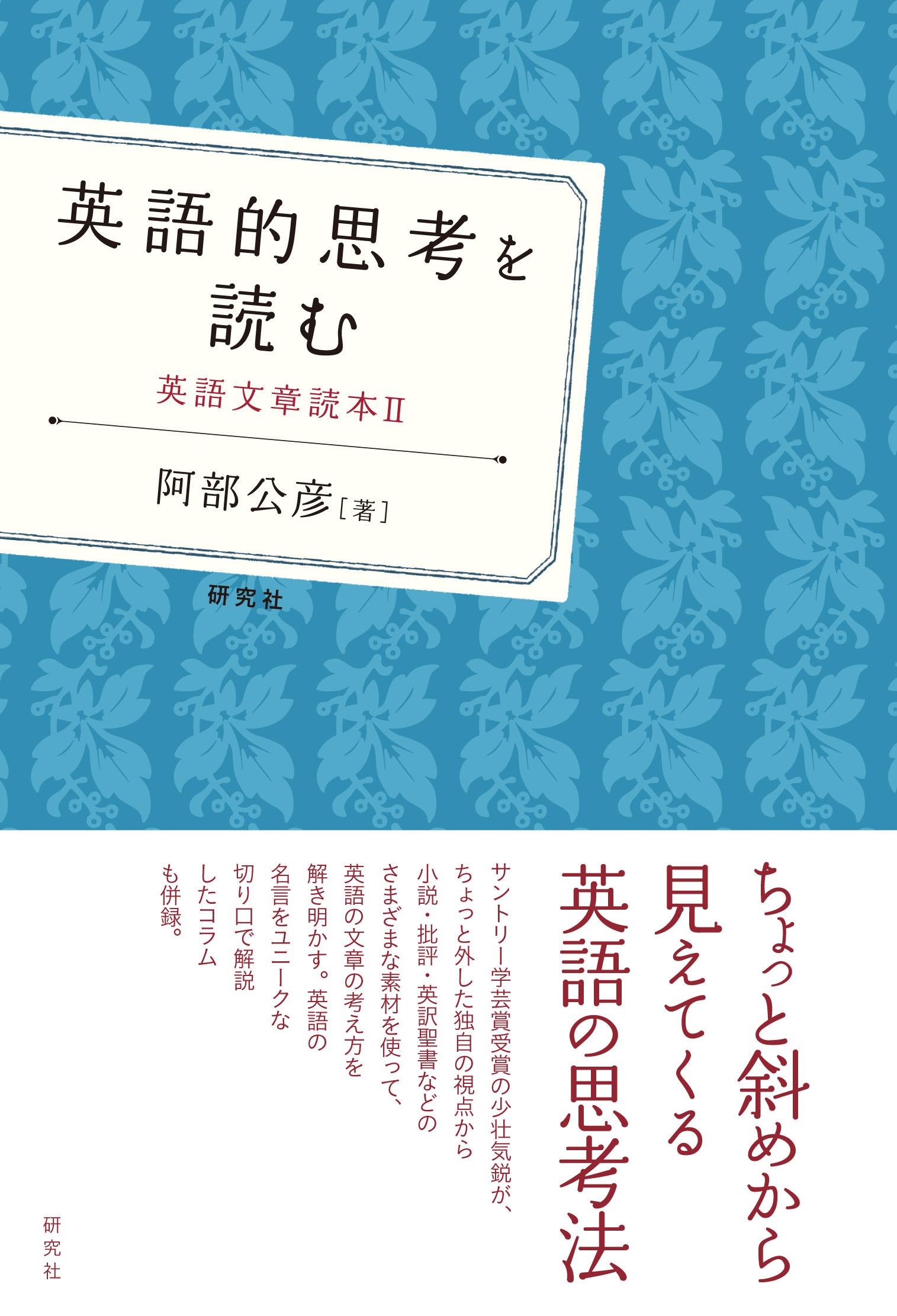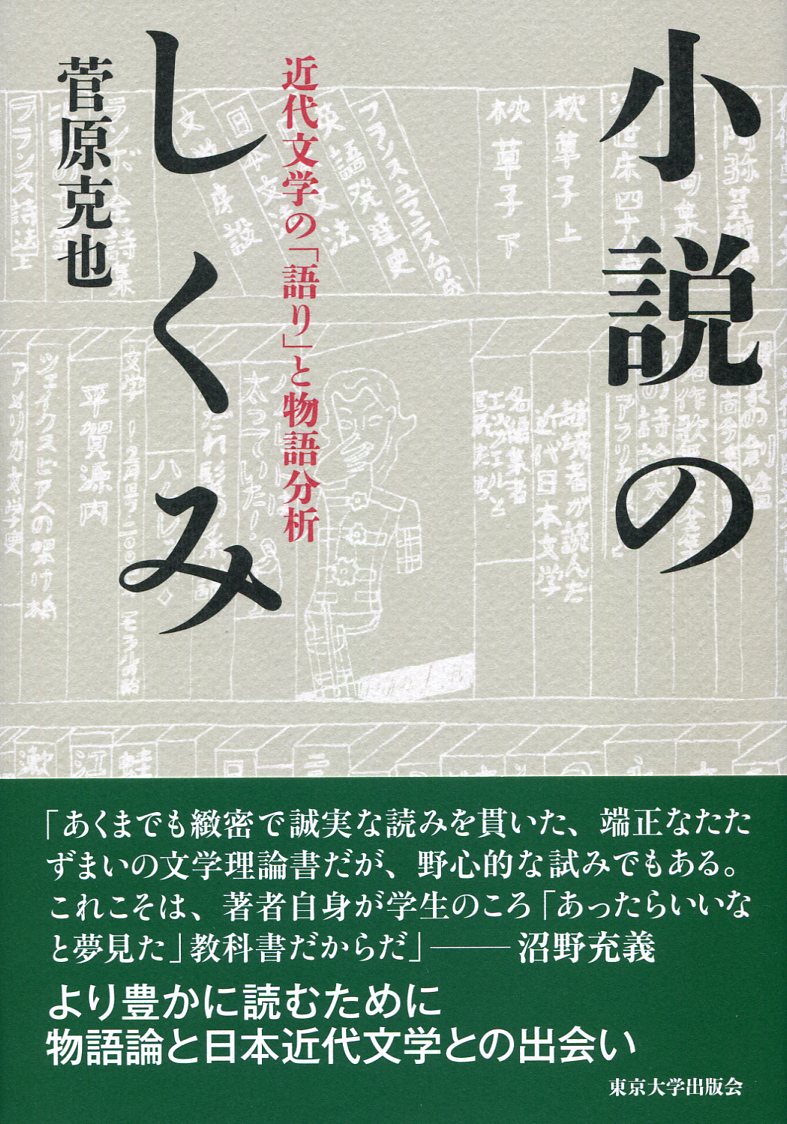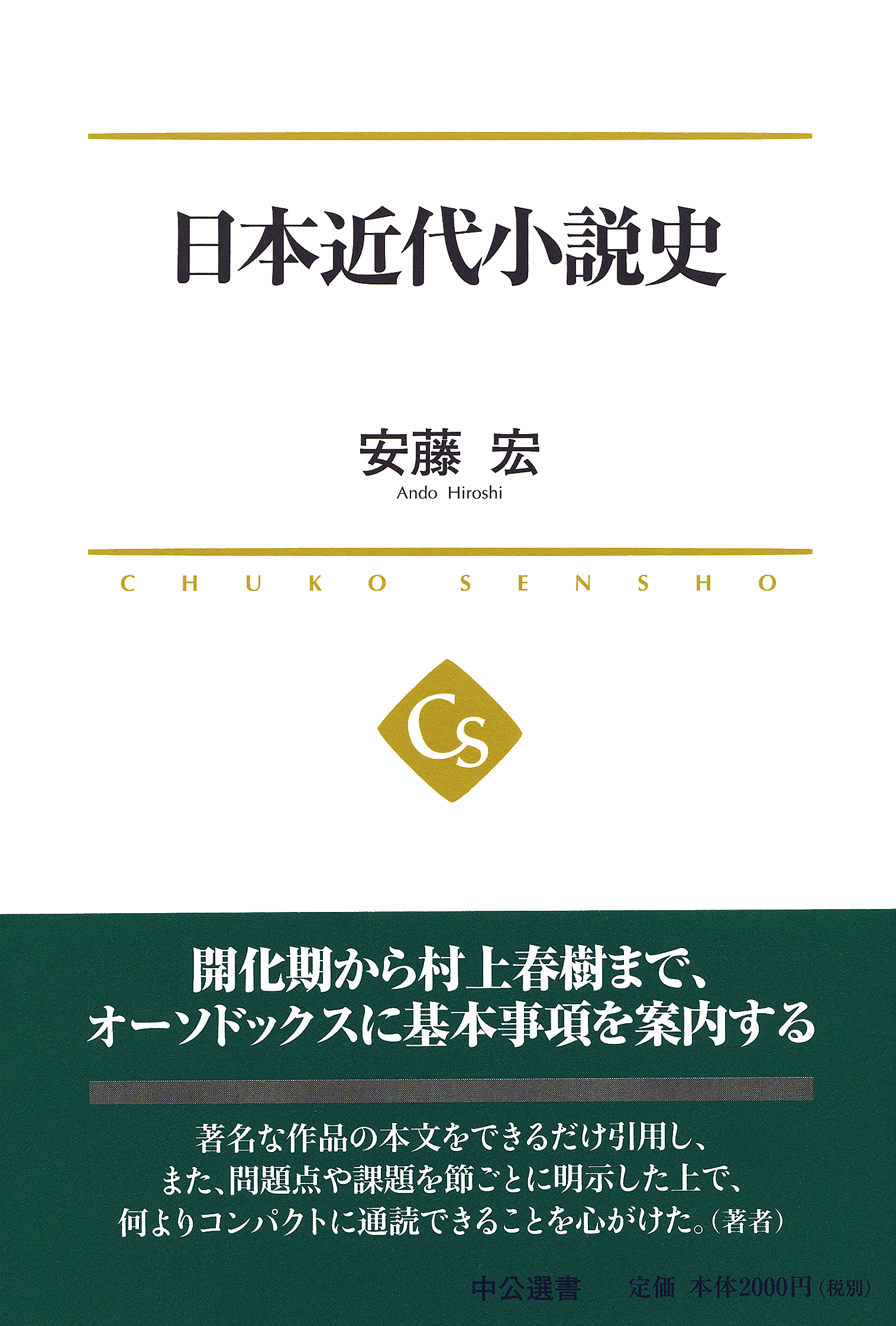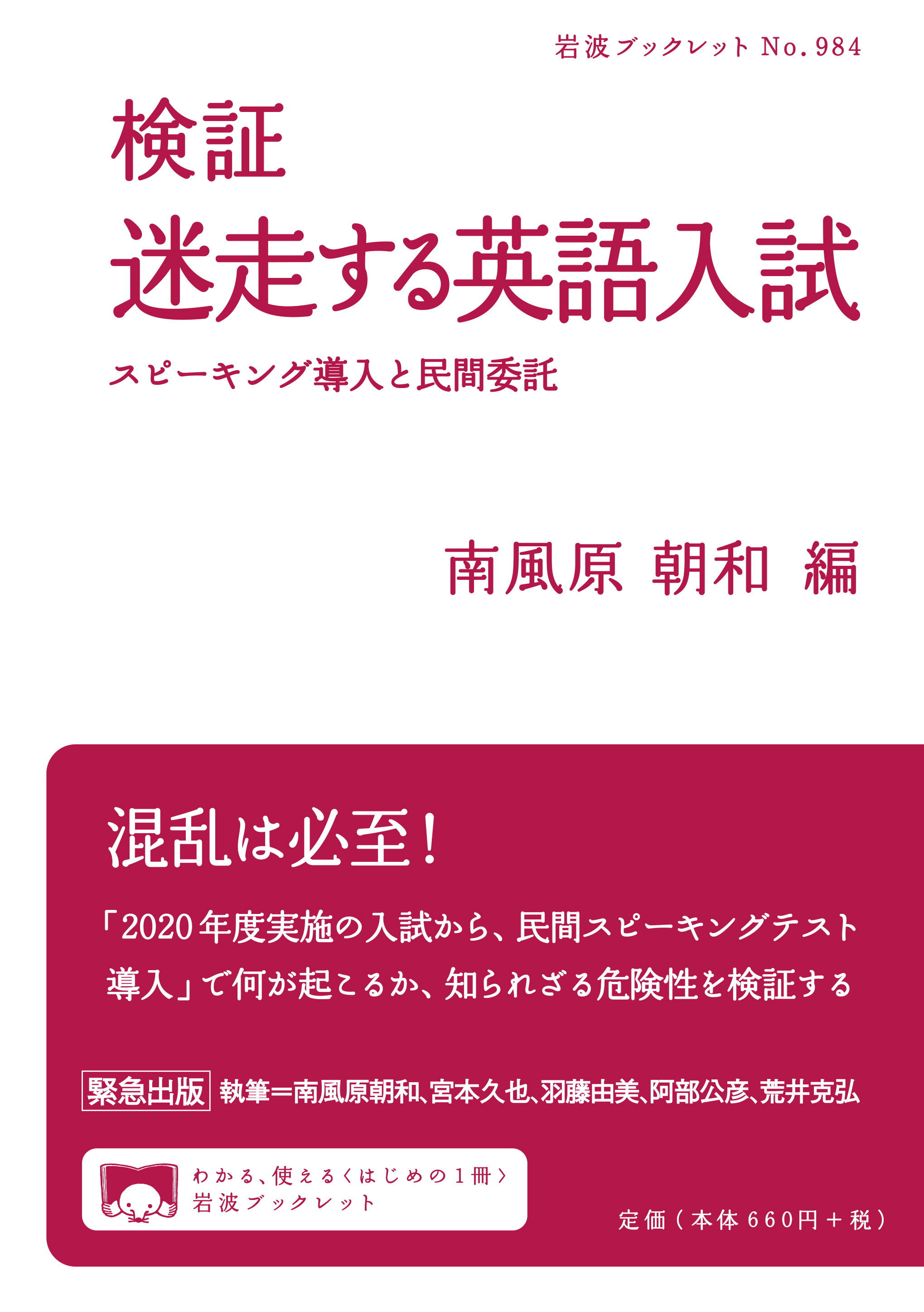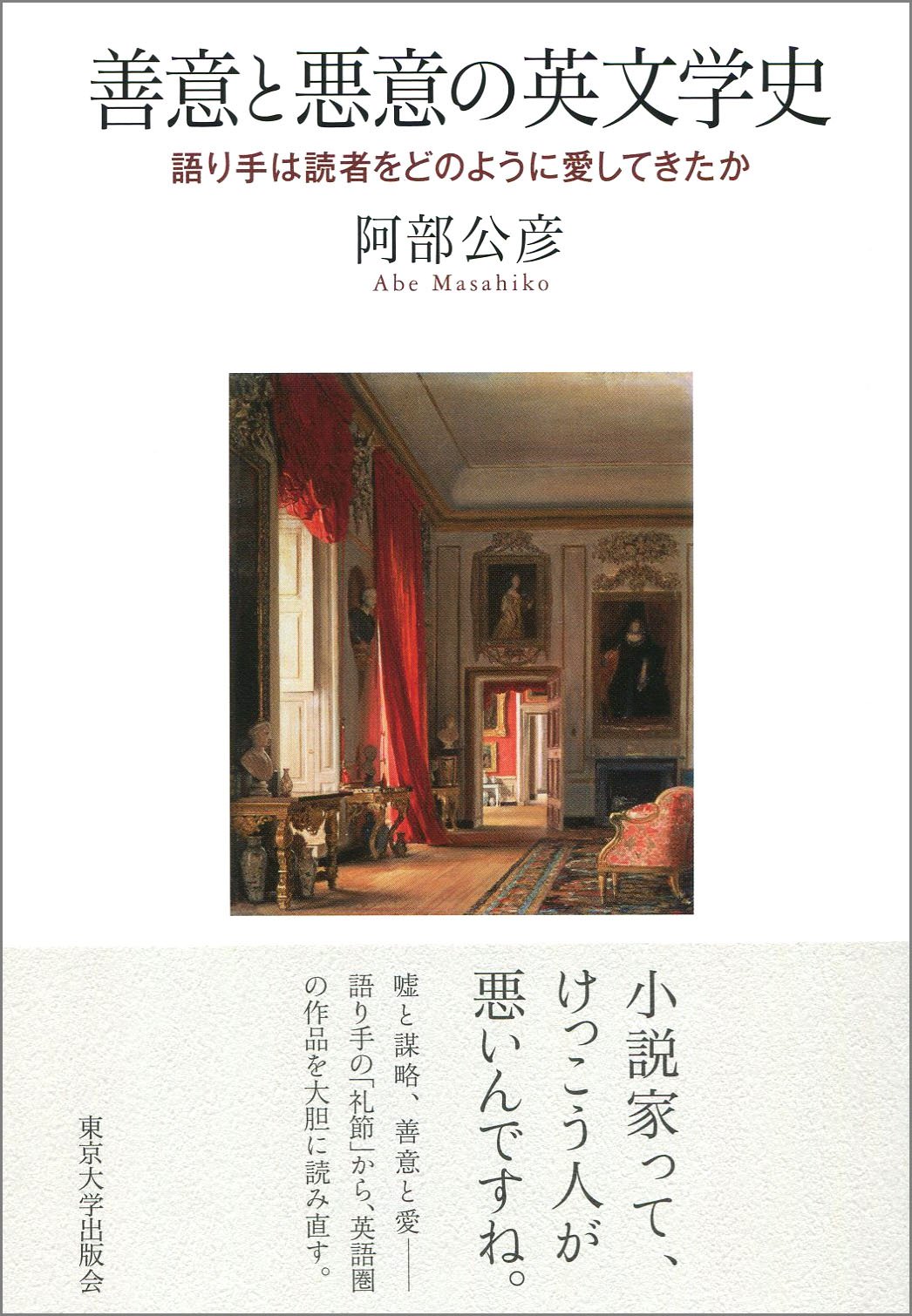
書籍名
善意と悪意の英文学史 語り手は読者をどのように愛してきたか
判型など
304ページ、四六判
言語
日本語
発行年月日
2015年9月15日
ISBN コード
978-4-13-080106-5
出版社
東京大学出版会
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
本書は、近代から現代にかけてのイギリス、アメリカ、アイルランドといった英語圏の国々で、「善意」がどのように表現され流通してきたかを、それぞれの時代を代表する文学作品を読むことを通して考察する。
近代小説は、異なる文化圏に属する人間が出会ったときに生ずるさまざまな葛藤を描き出すのを得意としてきた。ジェーン・オースティンやジョージ・エリオットの作品にも見られるように、英国小説の最大のテーマの一つは、階級を越えた恋愛や結婚だった。背景には、近代に入って社会と階級は流動化したことがある。移動手段やさまざまな「出会いの装置」も発達したのも大きい。おかげで中世や初期近代までなら結びつくはずがなかった「階級外」の人間同士が、近代に入り知り合う可能性が高まった。近代小説は、そうしたときにどのように人間関係がつくられるかを描き出してきた。アメリカの小説では、これにさらに「人種外」の人間の接触や結婚という問題が加わる。
これまでなら「枠外」の者として、知り合う可能性がなかった同士が接触を持つようになると――それが登場人物同士であろうと、語り手と登場人物という関係であろうと――お互いが警戒を解いて近づくためにさまざまな「善意」のシグナルが発せられる必要がある。人々はそれをきちんと見抜くこともあるが、読み過ごしたり、誤読したりすることも多い。ジェーン・オースティン『高慢と偏見』のエリザベスやナサニエル・ホーソーン『七破風の屋敷』の語り手は、まさにそうした”読みをめぐって格闘する人“として機能している。私たち読者もまた、彼らのそうした読解作業をともに読むことになる。
こうして出会いを数多く描いてきた小説作品だが、そもそも作品を読む際につねに「解釈」という手続きが必要になるという点で、小説というジャンルそのものがこの出会いのプロセスを具現しているとも言える。「出会う」という行為への参加者は、相手の意図を読み取り、また相手にも自分の意図を読み取らせながら距離を縮めていく。小説はそうした意図の読み合いを描出するだけではなく、小説そのものが意図を読み取らせたり、また読み取ったりする主体ともなるのである。
20世紀になると人々は次第に「善意」のジェスチャーに対して警戒的な態度をとるようになる。そして、むしろ「ぶっきらぼう」やときには「悪意」こそが、人と人とが接近するための有効なシグナルともなっていく。これは19世紀の作品とくらべて20世紀の作品で、読者に対する直接の語りかけが減り、どことなく作品の言葉に壁ができてみえたり、読みにくく感じられたりすることとも関係する。
作家や語り手は、時代に応じて読者や登場人物とのあいまいな距離感をときに縮めたり、ときに拡げたりしながら、近代人がたえず直面せざるをえない距離の不安定さを、まるごと作品として表現してきた。本書では、そうした戦略がどのように機能しているのかを詳しく見ることで、英文学史の新しい読み方を提案する。
(紹介文執筆者: 人文社会系研究科・文学部 准教授 阿部 公彦 / 2017)
本の目次
第1章 英会話の起源――デラ・キャーサ『ギャラティーオ』(1558)、クルタン『礼節の決まり』(1670)
第2章 女を嫌うという作法――『チェスタフィールド卿の手紙』(1774)
第3章 作家の不機嫌――ジェーン・オースティン『高慢と偏見』(1813)
第4章 イライラの共和国――ルイス・キャロル『不思議の国のアリス』(1865)
[インタールード1] 児童文学とですます調――江戸川乱歩『怪人二十面相』(1936-52)
II 「丁寧 (ポライトネス)」に潜むもの――17~19世紀の英・米
第5章 拘束の歓び――ウィリアム・シェイクスピア『ソネット集』(1609)
第6章 登場人物を気遣う――ナサニエル・ホーソーン『七破風の屋敷』(1851)
第7章 やさしさと抑圧――ジョージ・エリオット『サイラス・マーナー』(1861)
[インタールード2] 遠慮する詩人――宮沢賢治『銀河鉄道の夜』(1933)
III 「愛」の新しい作法――20世紀の英・米・アイルランド
第8章 性の教えと不作法――D・H・ロレンス『チャタレー夫人の恋人』(1928)
第9章 目を合わせない語り手――ウィリアム・フォークナー『アブサロム、アブサロム!』(1936)
第10章 冠婚葬祭小説の礼節――フランク・オコナー「花輪」(1955)、ウィリアム・トレヴァー「第三者」(1968)
第11章 無愛想の詩学――ウォレス・スティーヴンズ「岩」(1954)
関連情報
『英語教育』2016年3月号、p.96.
『週刊朝日』2015年12月4日号、p.70
『週刊読書人』2015年12月11日号, p.5
『図書新聞』2015年12月12日号
『北海道新聞』2015年12月20日朝刊



 書籍検索
書籍検索


 eBook
eBook