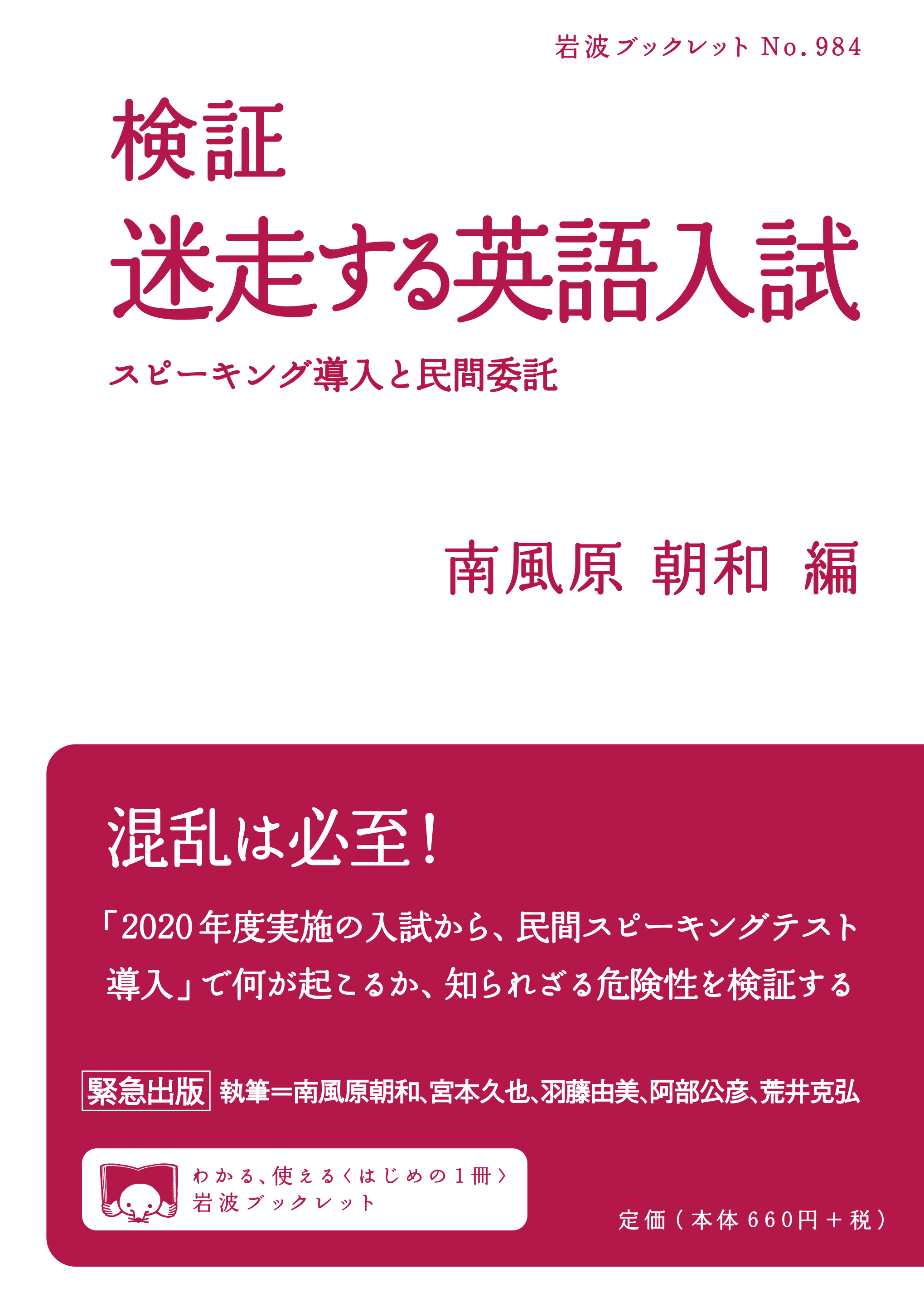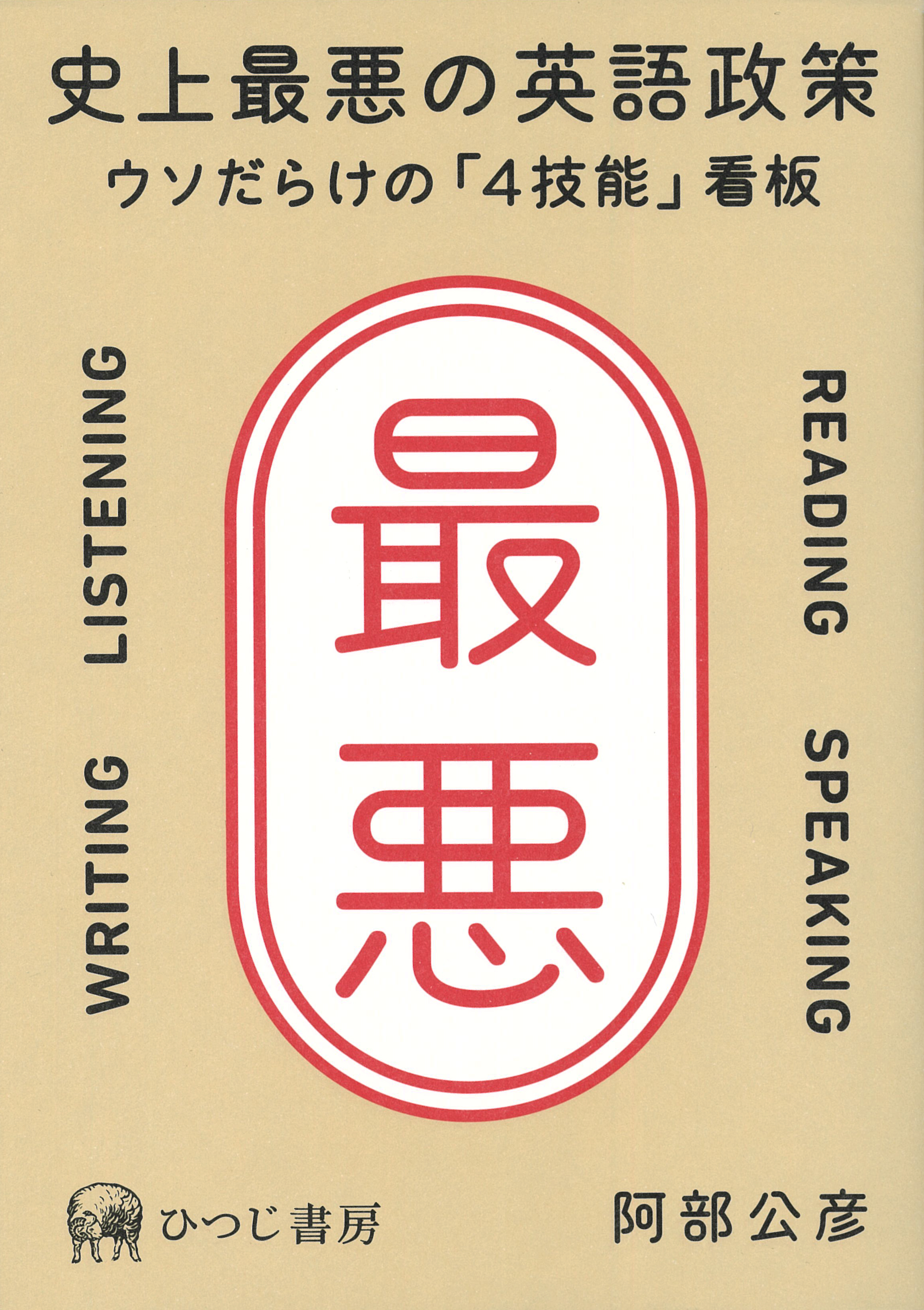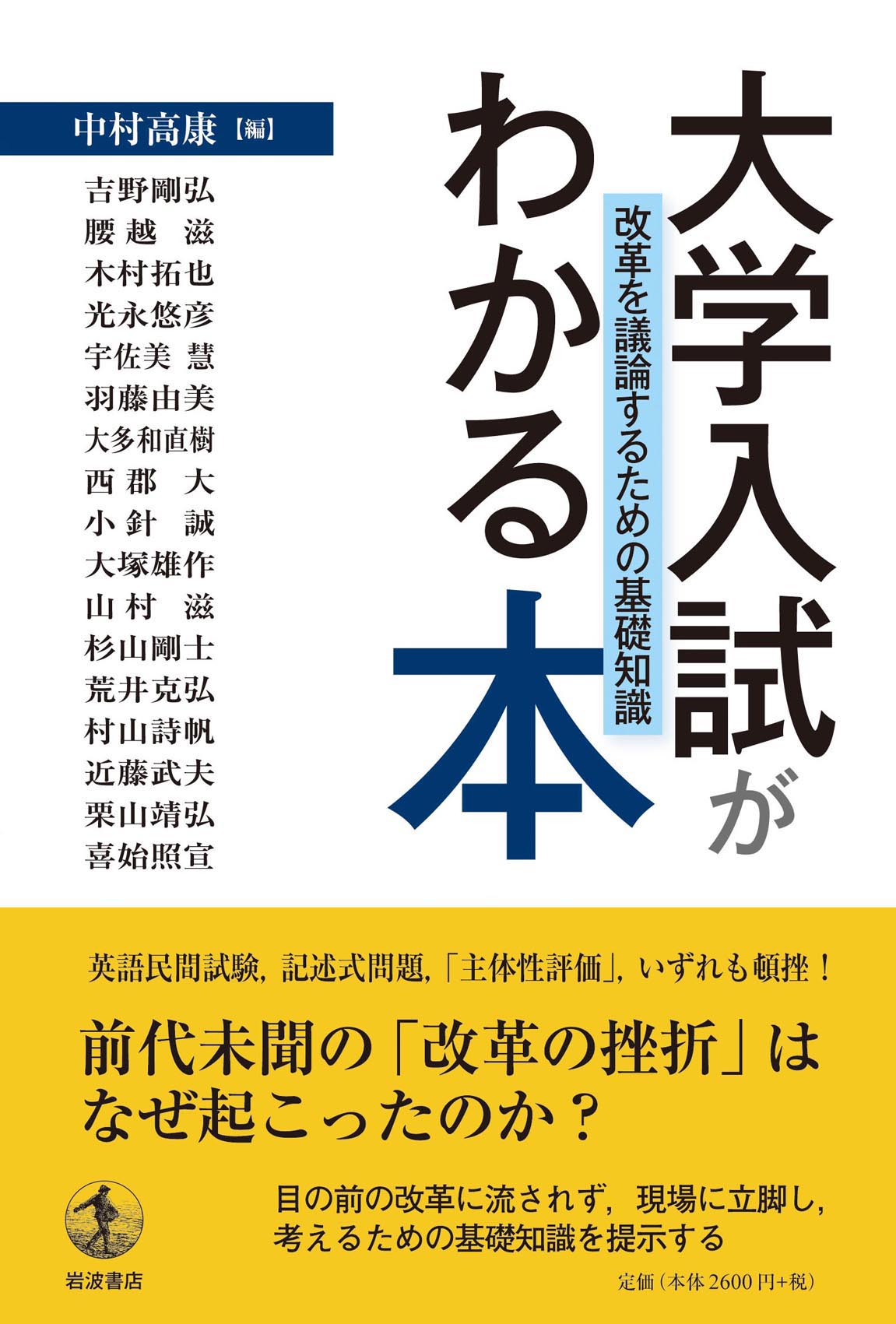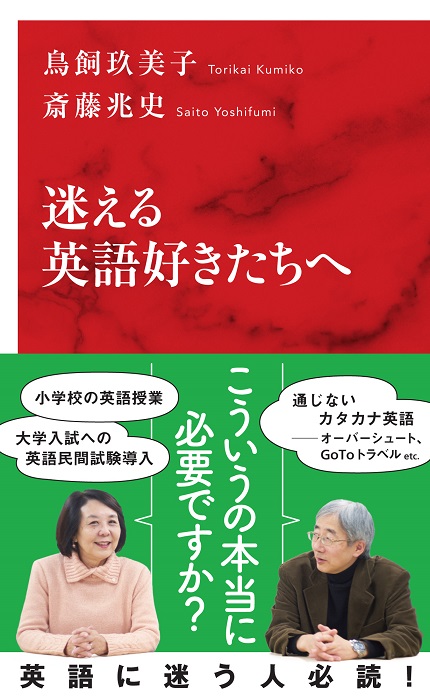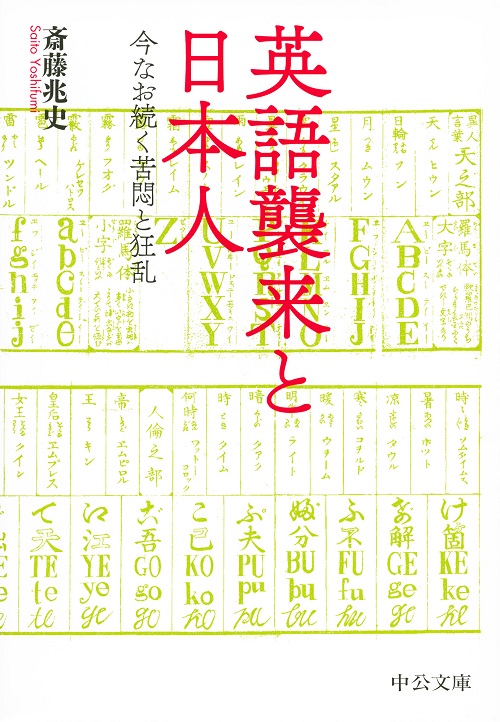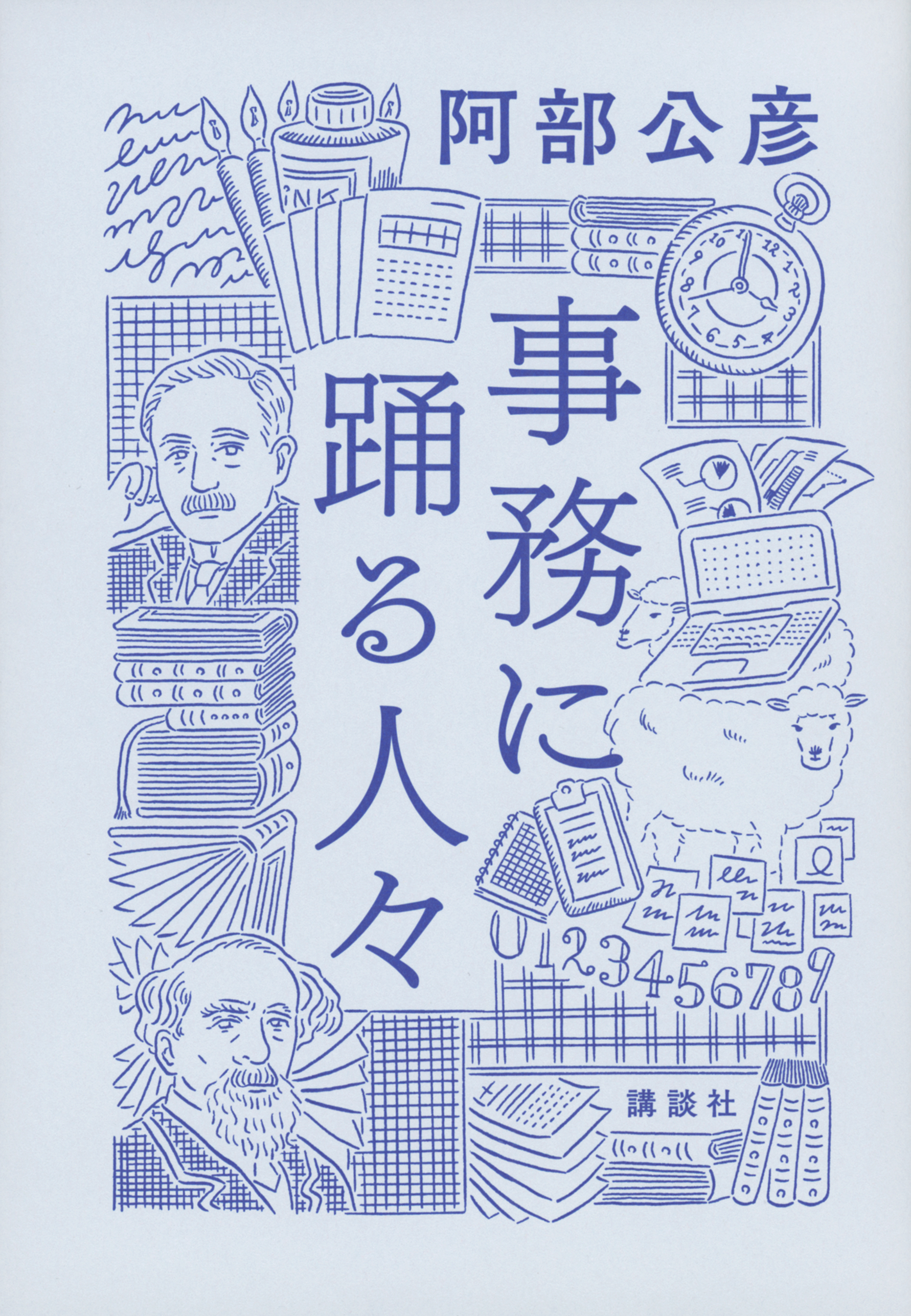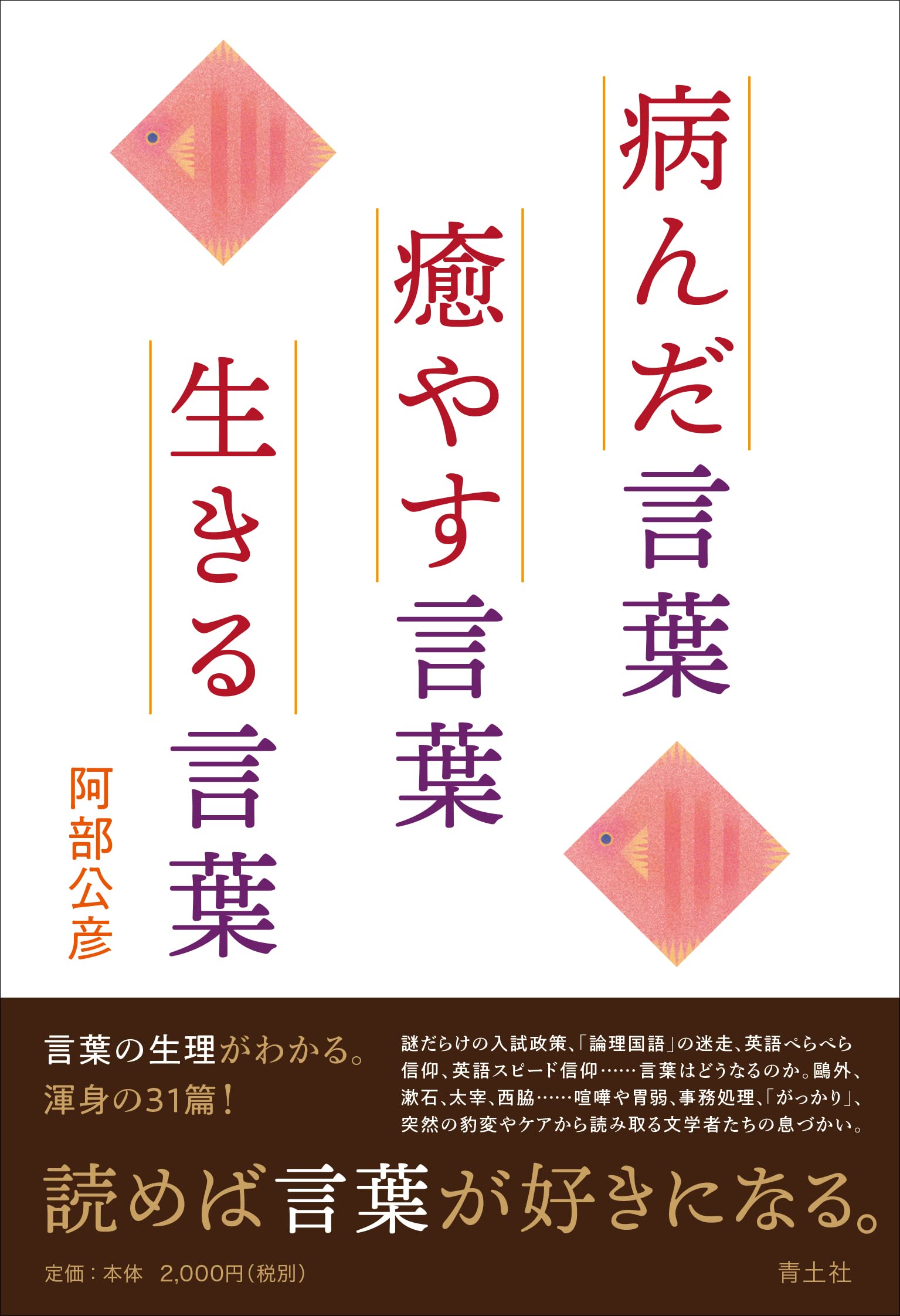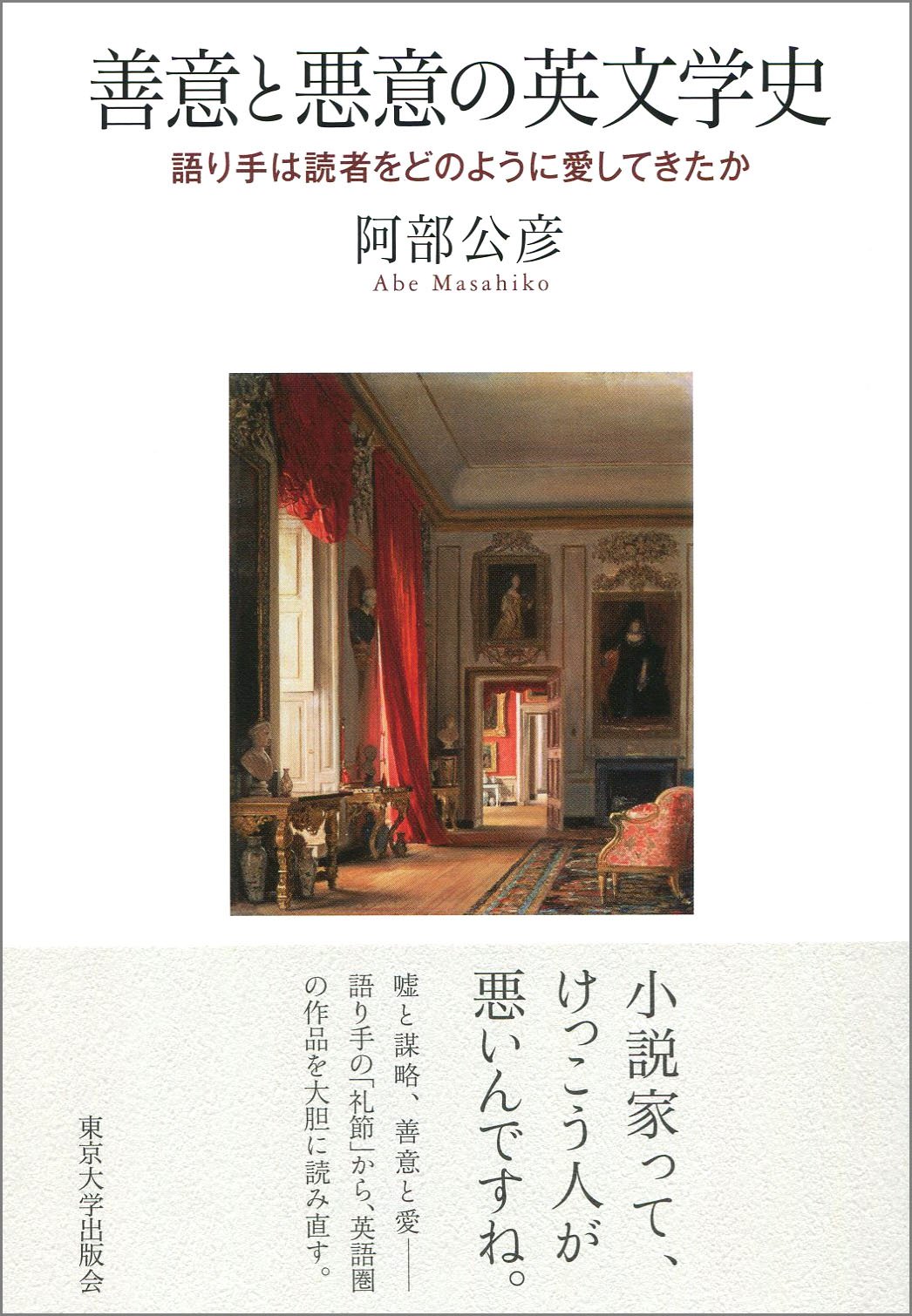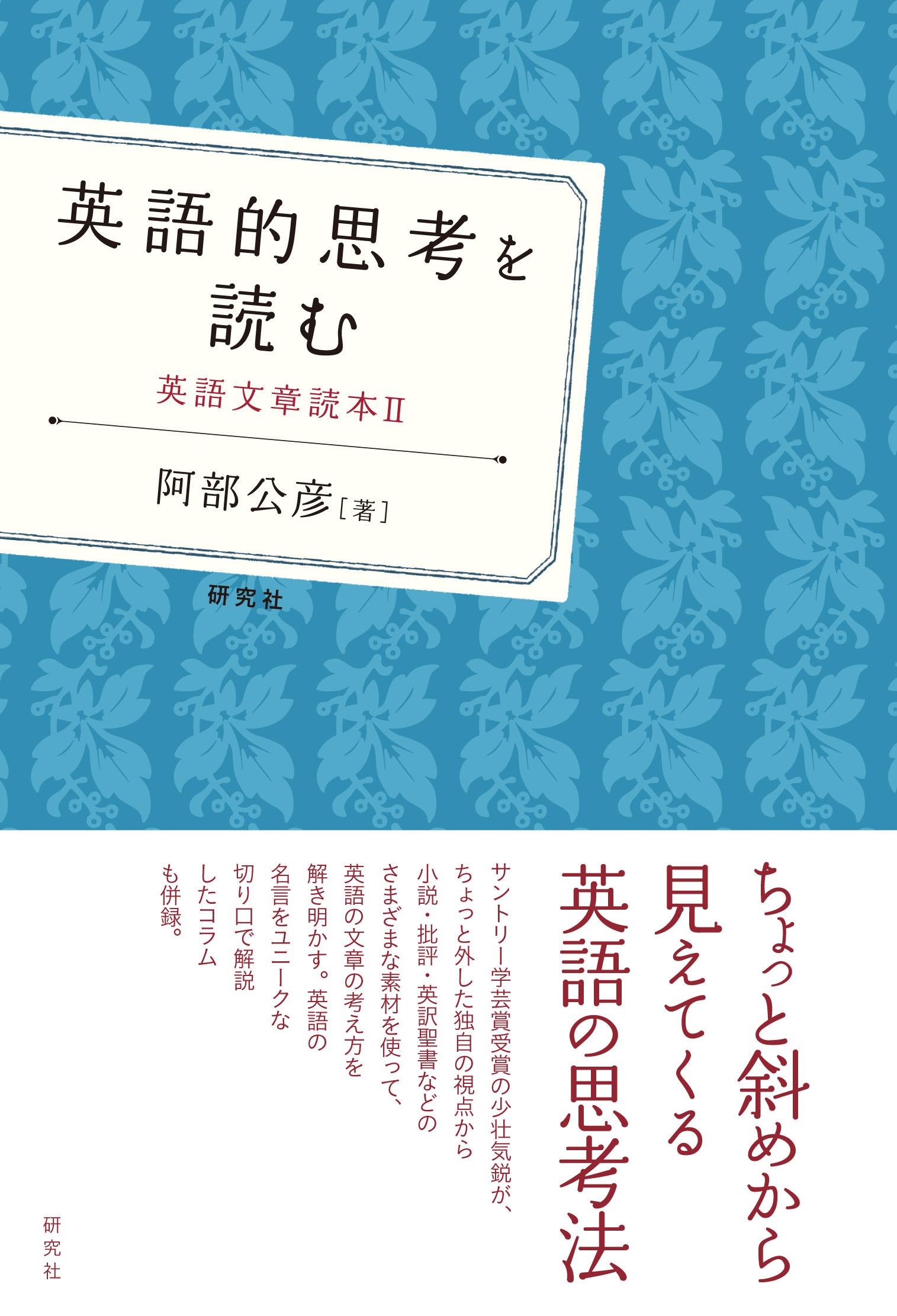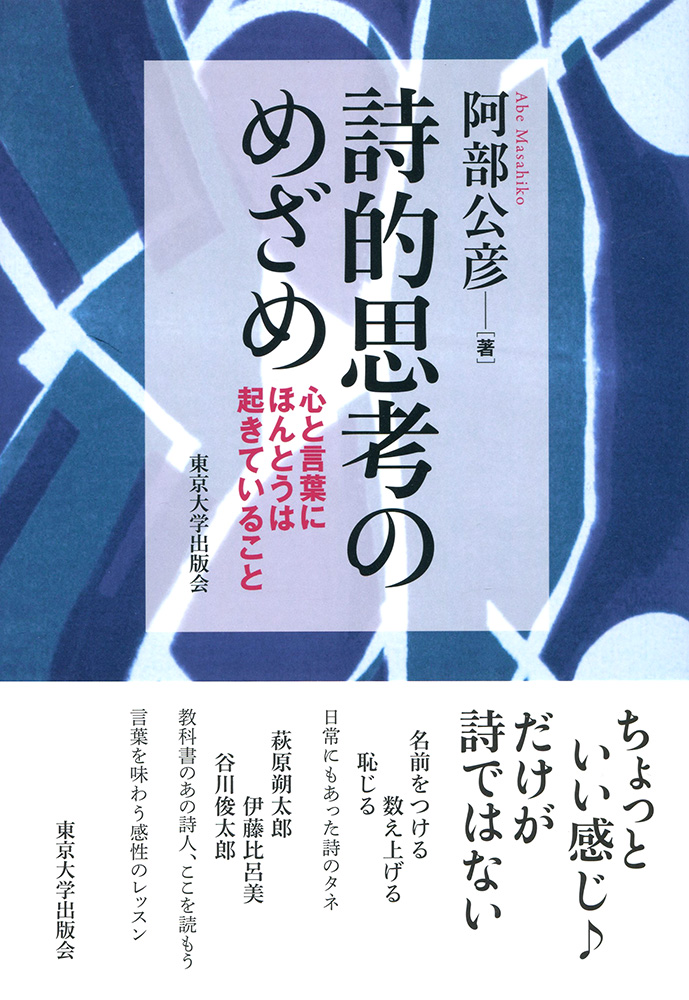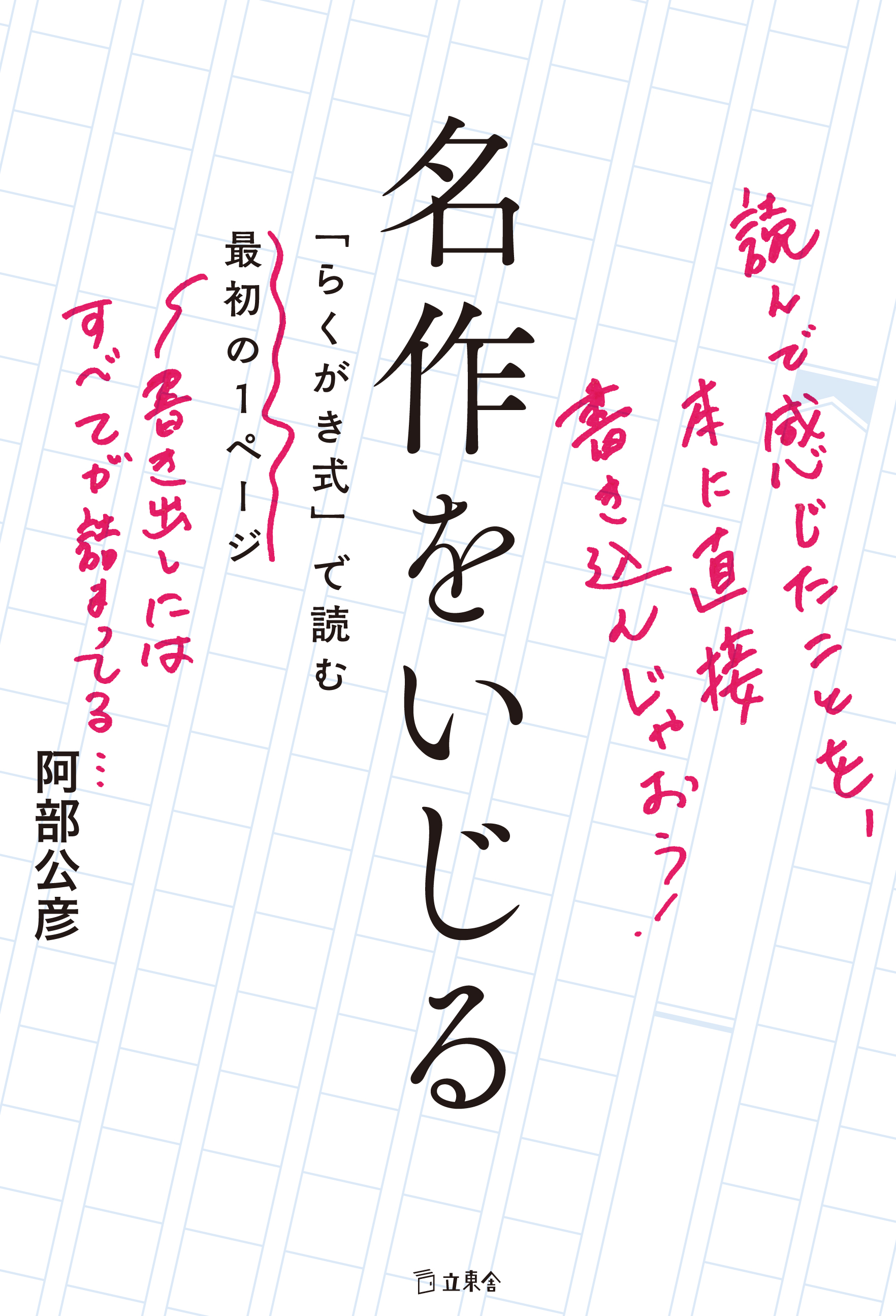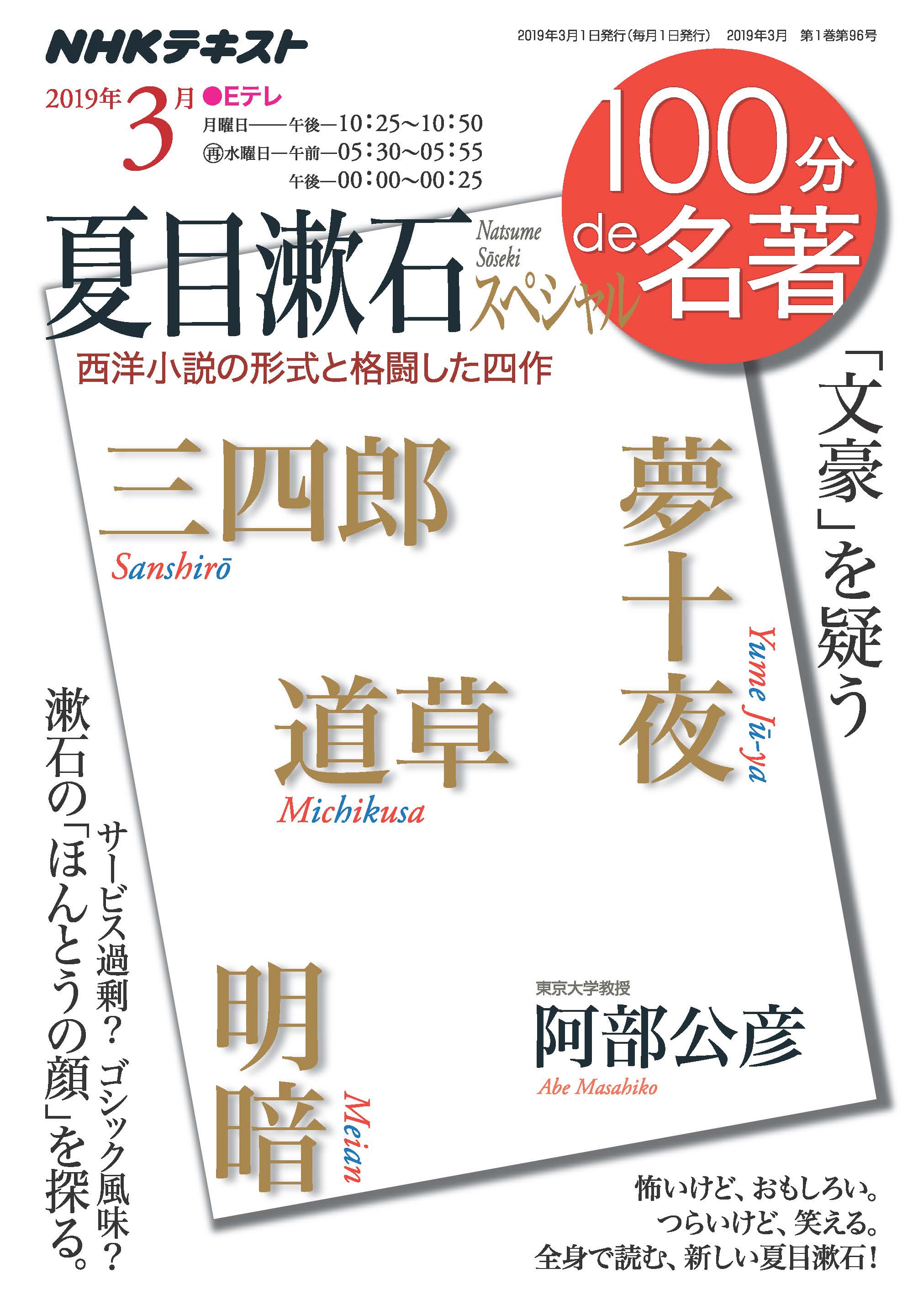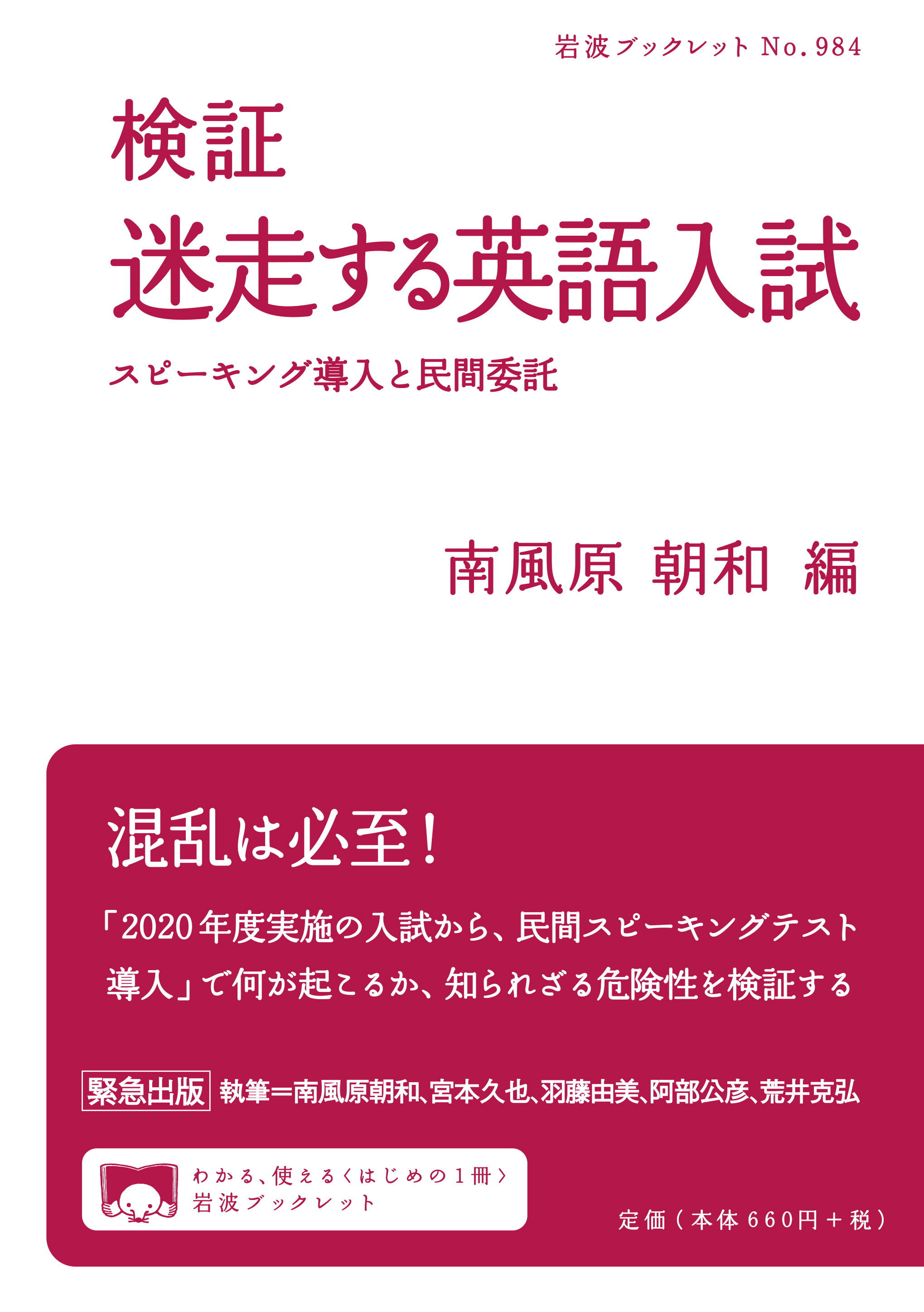
書籍名
岩波ブックレット No.984 検証 迷走する英語入試 スピーキング導入と民間委託
判型など
96ページ、A5判、並製
言語
日本語
発行年月日
2018年6月5日
ISBN コード
9784002709840
出版社
岩波書店
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
今、大学入試が大混乱に陥っています。この紹介文を執筆しているのは2019年8月末。民間試験導入を謳った新しい共通テストの開始が目前にせまっています。しかし、かねてから指摘されていた制度設計の杜撰さがここへきてぼろぼろとあきらかになり、制度は機能不全の様相を呈しつつあります。障害者への対応や、不正行為の処理など試験の仕様についても課題が山積。受験機会の不公平さ、受験生の金銭的負担の大きさ、業者が試験対策を主導することから発生する利益相反の疑惑、異なる試験の点数の比較の難しさなど、より大きな課題についてもまったく解決の目処は立っていません。
これに先立ち、参入予定だった業者の一つのTOEICは突然の撤退を表明。英検やGTECも試験日程や会場などを発表するのに手間取っています (2019年8月末現在)。今や業者の側も制度に対して懐疑的になりつつあるとの声が聞こえてきます。試験を利用する側の大学も、試験の運営が信頼性に欠け、入試には使えないとする判断をするところが次々に出てきました。
この政策を主導した政治家は、文科省を通し大学にさまざまな圧力をかけることで何とか「活用」という看板を維持させようとしているようですが、実質的に民間試験の配点を低く設定するなど、制度を骨抜きにすることで自己防衛しようとする大学が旧帝大を中心に増えています。
こうした混沌とした状況は制度の1期生にあたる高校二年生やその保護者の間に大きな不安と不満を引き起こし、全国高等学校長協会は混乱の収拾を求める異例の訴えを文科省に対して行いました。メディアも「産経新聞」「読売新聞」から「日本経済新聞」「毎日新聞」「朝日新聞」「東京新聞」「赤旗」まで、政治的スタンスにかかわらず一様にこの新テストの問題を指摘し、延期や中止を訴えています。
これだけの混乱を引き起こした以上、新制度は「きっと失敗する」ではなく、「もはや失敗した」と言っても過言ではないでしょう。
いったいなぜ、このようなことになったのでしょう。2018年6月に刊行された本書は早い段階から政策の「迷走」に対して警鐘をならし、さまざまな角度からの問題点を指摘しています。そこに提示された懸念の多くは、残念ながら現実のものとなりました。そういう意味では、今後のこの史上空前の「入試政策の混乱」を研究するためにも非常に役に立つ資料を提供していると言えます。
とはいえ、8月末現在、文科省はこの政策を強行実施する構えでいます。つまり、本書は現在進行形の、きわめてアクチュアルな問題と切り結ぶ、「ナマの声」として読んでいただけるものです。本書で示された基本的な情報や知見を踏まえれば、今後の大学入試をめぐる議論に加わる際にもおおいに役立つはずです。
以下、本書であげられた新しい英語入試の主な問題点を列挙します。
・民間試験のスピーキング対策に大きな時間をとられたら、高校で適切な基礎力の養成がはかれない。大学での学習に必要な能力も身につけられない。
・もともと診断テストとして使われている試験を、選抜入試に「流用」することから生まれる問題。
・目的や測定内容も異なる複数のテストの成績を比較することができるのか。
・50万人もの受験生に、一律に「しゃべる」テストを科すことへの懸念。事故や不正行為への対応も不十分。
・テストを変えれば、生徒の能力があがるという主張の根拠があまりに薄弱。
・採点には膨大な人 x 時間がかかるが、採点者はどうやって調達するのか。採点結果は、大学入試に求められる水準の信頼性があるのか。
・テストの練習は何度でもできるので、受験生の負担増や、大学受験の早期化、長期化をもたらす。
本書では多用なバックグランドを持つ執筆者が、それぞれの観点から議論を展開します。テスト理論を専門とする、元東京大学理事の南風原朝和氏は政府の会議にも参加してきた経験を生かし、政策決定の不透明さに切りこみます。全国高等学校長協会の元会長・宮本久也氏は高校生の置かれた状況を代弁、応用言語学を専門とし、長年スピーキングテストの開発をつづけてきた羽藤由美氏は、政策の非現実性を具体的に指摘します。元・大学入試センター副所長の荒井克弘氏は、高教育行政の構造的な問題をあきらかにします。なお、筆者阿部は英米文学が専門。すでに『史上最悪の英語政策』(ひつじ書房) でこの問題を扱いました。本書では、スピーキングテストの導入が必ずしも「話す力」の養成につながらないとの議論を展開します。
本書が、迷走 (暴走?) する英語入試「改革」の歯止めに役立つことを願っています。
(紹介文執筆者: 人文社会系研究科・文学部 教授 阿部 公彦 / 2019)
本の目次
第1章 英語入試改革の現状と共通テストのゆくえ (南風原朝和)
第2章 高校から見た英語入試改革の問題点 (宮本久也)
第3章 民間試験の何が問題なのか―CEFR対照表と試験選定の検証より (羽藤由美)
第4章 なぜスピーキング入試で、スピーキング力が落ちるのか (阿部公彦)
第5章 高大接続改革の迷走 (荒井克弘) 年表 入試改革全体と英語入試改革の流れ (南風原朝和)
年表 入試改革全体と英語入試改革の流れ (南風原朝和)
関連情報
https://www.ct.u-tokyo.ac.jp/news/20180210-symposium/
関連インタビュー:
大学入試共通テストの記述式問題、AIやPCが使えないことも断念の理由に (ITmedia 2019年12月23日)
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1912/23/news050.html
【大学最前線 この人に聞く】かくして英語民間試験・国数記述式問題導入は自滅した 南風原朝和・東大名誉教授 (上) (産経新聞 2019年12月19日)
https://www.sankei.com/life/news/191219/lif1912190008-n1.html
【大学最前線 この人に聞く】かくして英語民間試験・国数記述式問題導入は自滅した 南風原朝和・東大名誉教授 (下) (産経新聞 2019年12月20日)
https://www.sankei.com/life/news/191220/lif1912200004-n1.html
書評:
(ひもとく) 受験 公平こそが正当性の源泉 中村高康 (朝日新聞DIGITAL 2019年12月21日)
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191221000162.html
民間試験活用への反論の書 (日本教育新聞 2019年2月4日)
https://www.kyoiku-press.com/post-198773/
金曜J-CAST書評「2020年から大学入試にTOEFLやTOEIC、大丈夫なのか?」(BOOKウォッチ 2018年7月20日)
https://www.j-cast.com/bookwatch/2018/07/20007657.html
週刊ダイヤモンド 2018年10月27日号
学研・進学情報 2018年11月号
関連記事:
寺沢拓敬 (言語社会学者) 大臣の「身の丈」発言の炎上のせいで民間試験導入は「延期」になったのか? (Yahooニュース 2019年11月5日)
https://news.yahoo.co.jp/byline/terasawatakunori/20191105-00149683/
文部科学省、英語民間試験利用を24年度以降に延期 (東大新聞オンライン 2019年11月1日) http://www.todaishimbun.org/20191101english_exam/
寺沢拓敬 (言語社会学者) 英語四技能入試は改革の切り札か? (Yahooニュース 2019年7月13日)
https://news.yahoo.co.jp/byline/terasawatakunori/20190713-00134071/
紅野 謙介 (日本大学教授) <コミュ力不安> という病に憑かれた「センター試験改革」の危うさ (現代ビジネス 2018年12月18日)
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/58943



 書籍検索
書籍検索