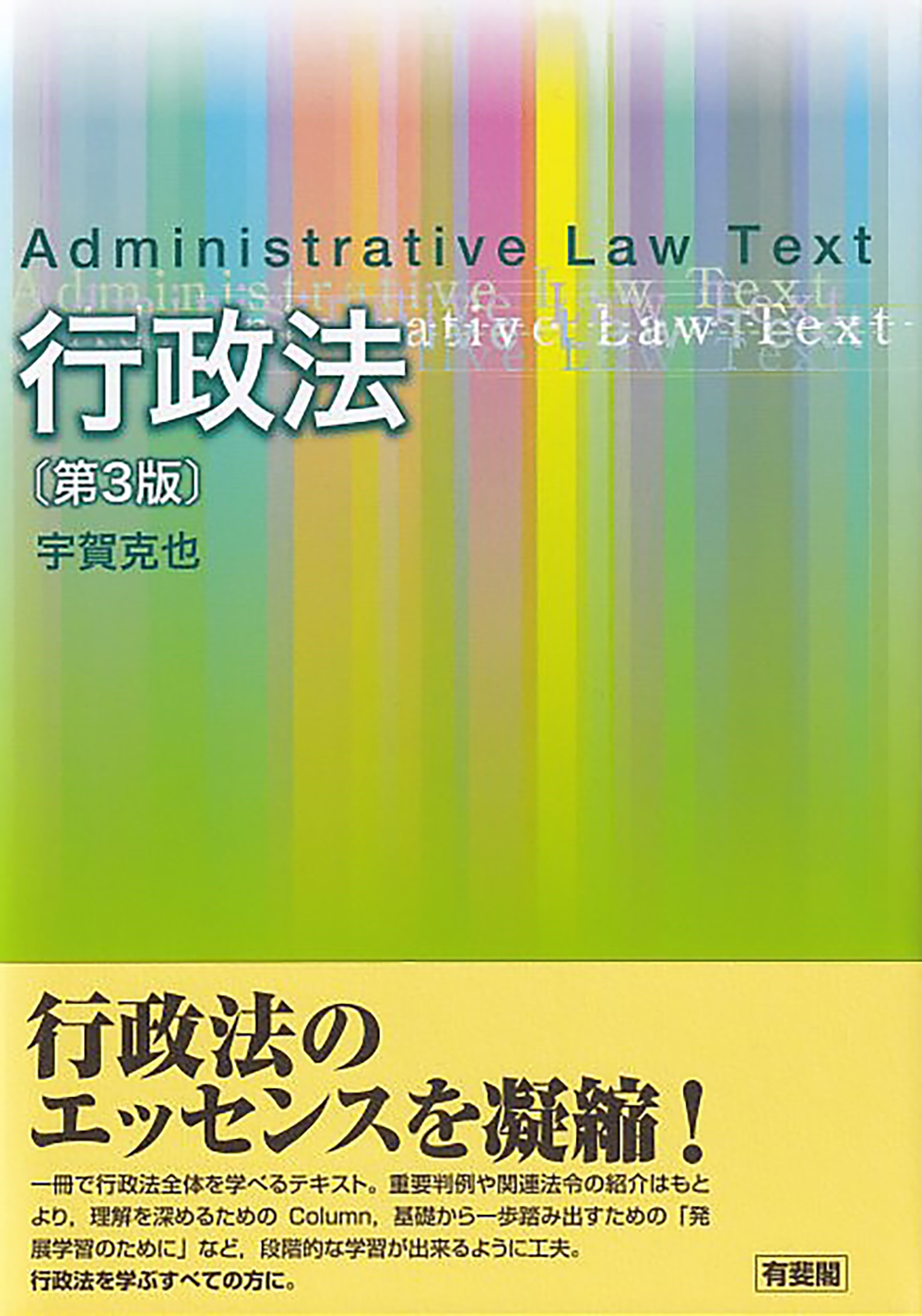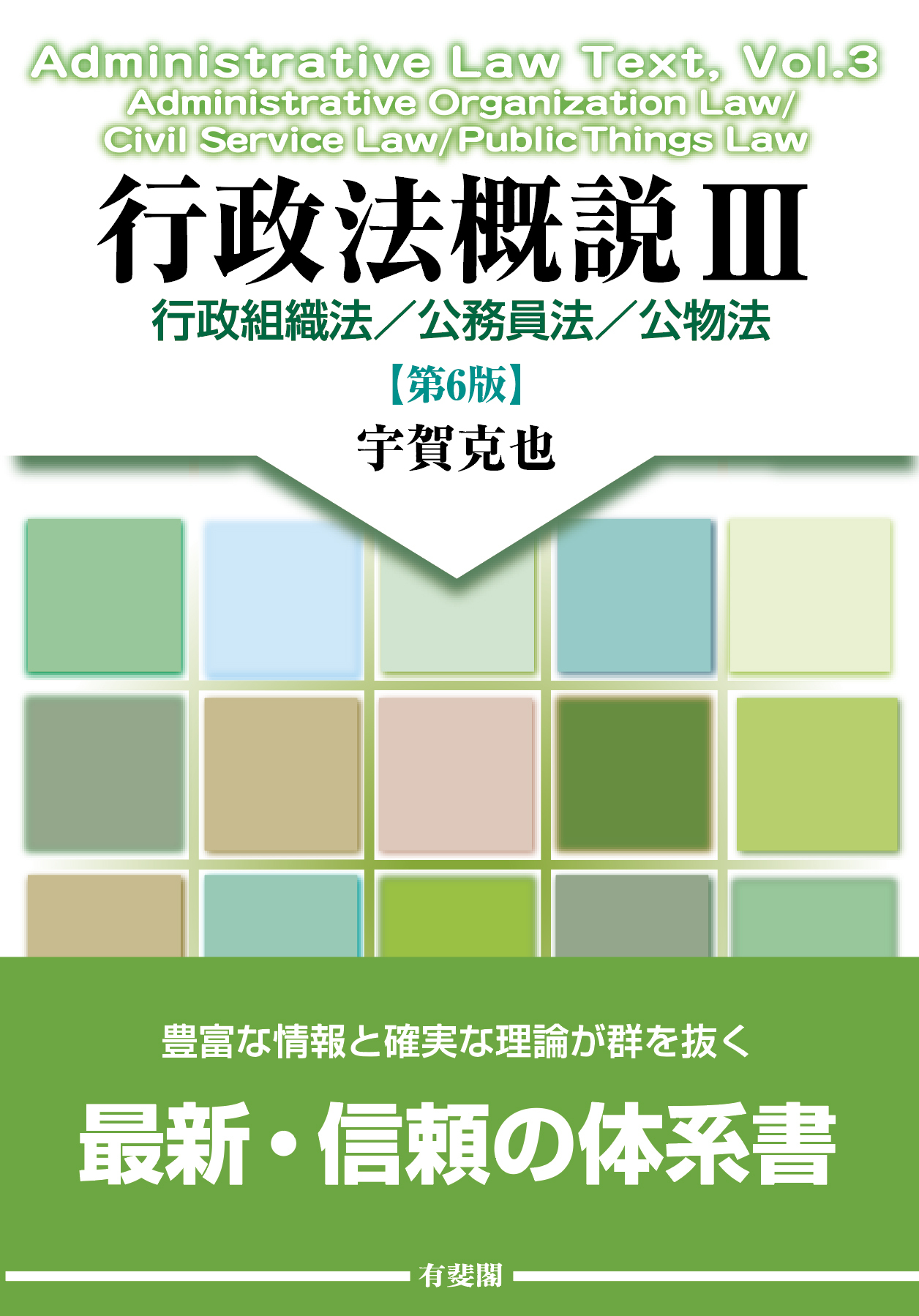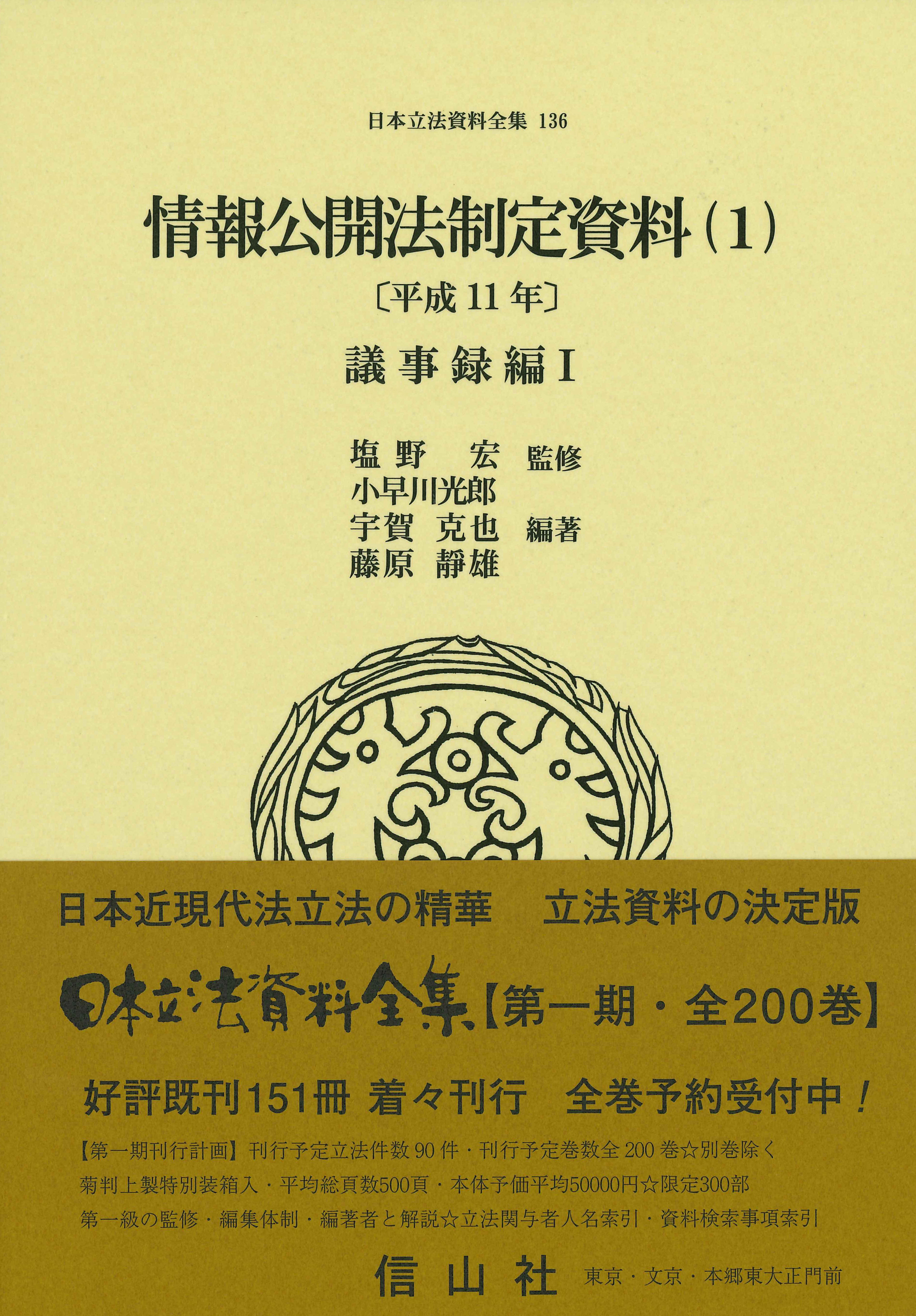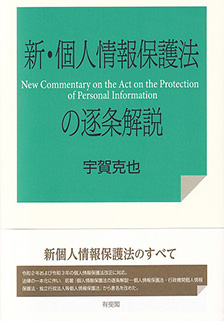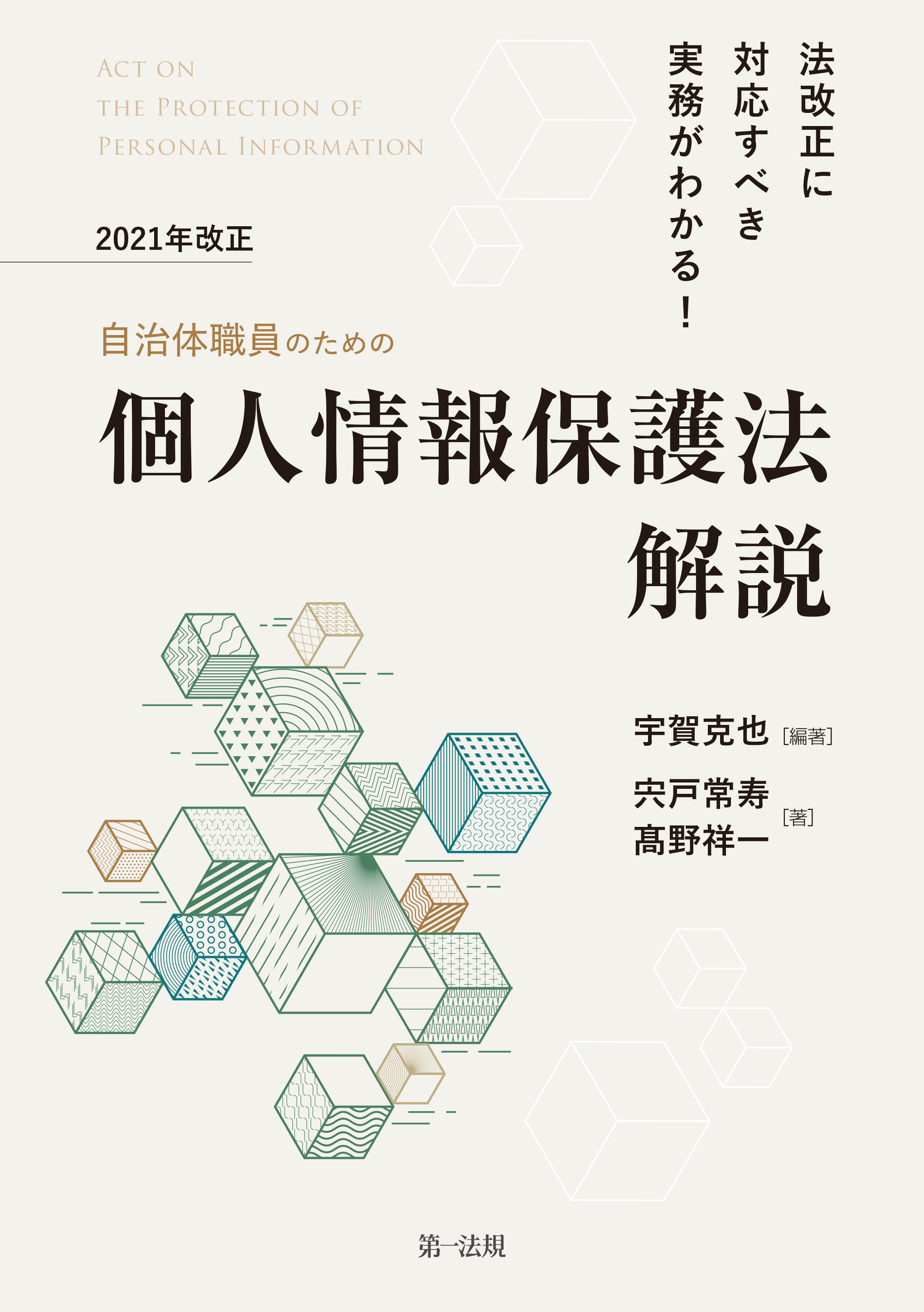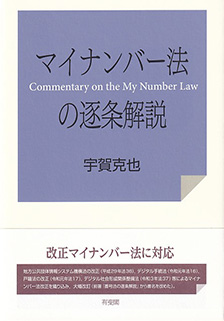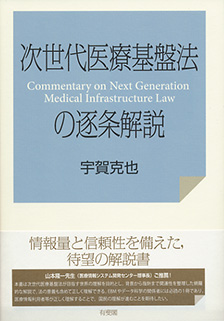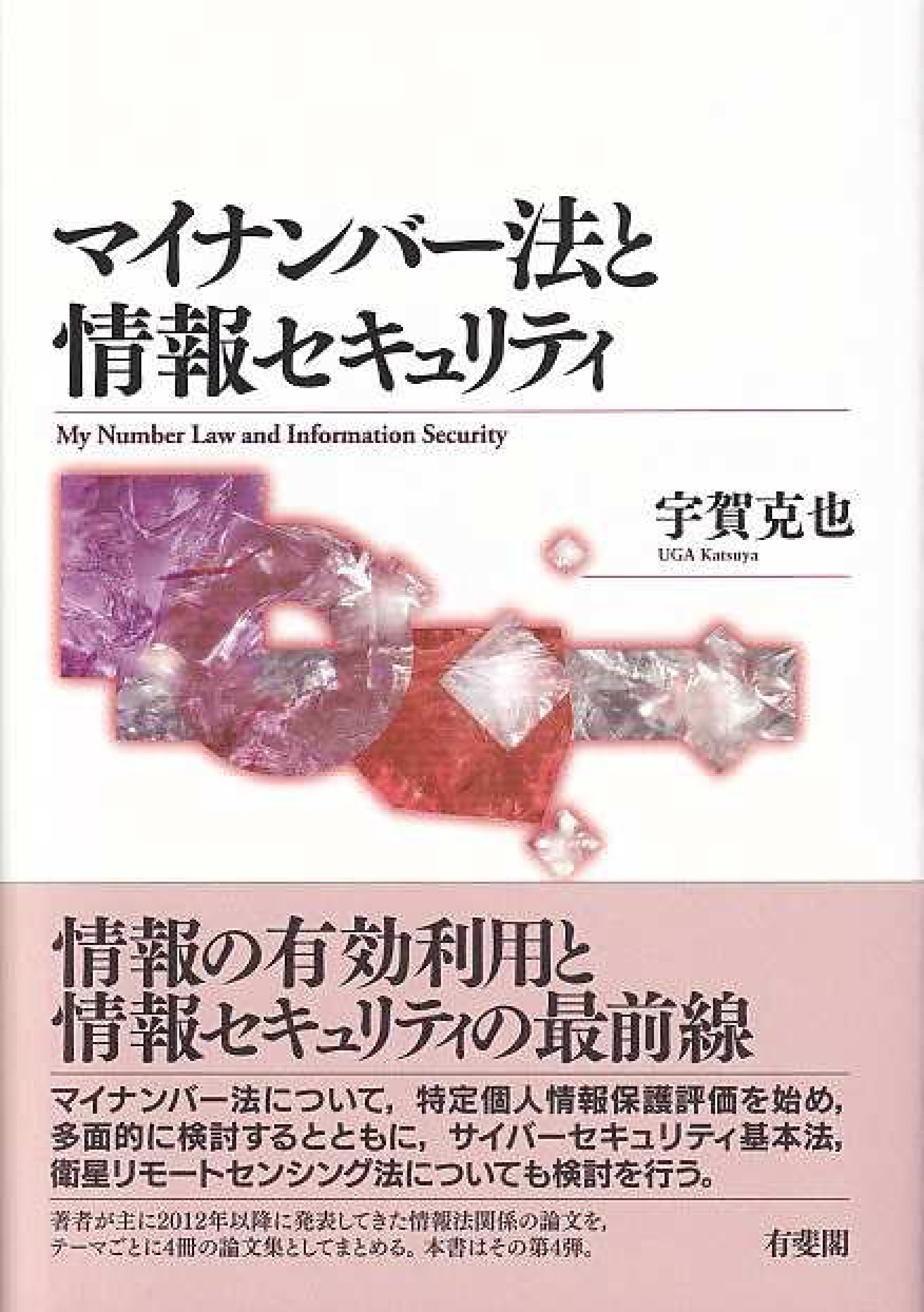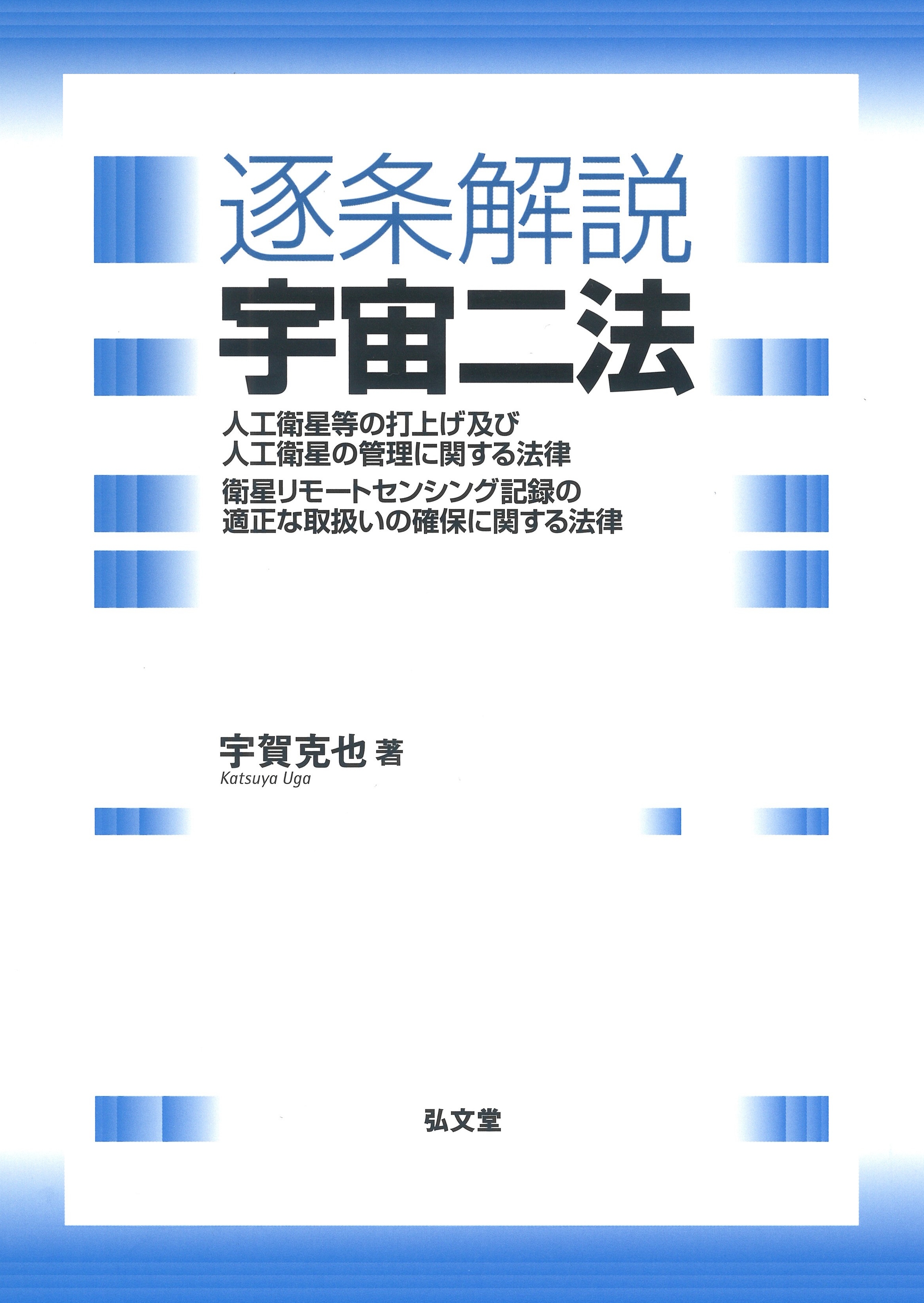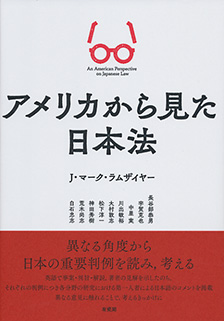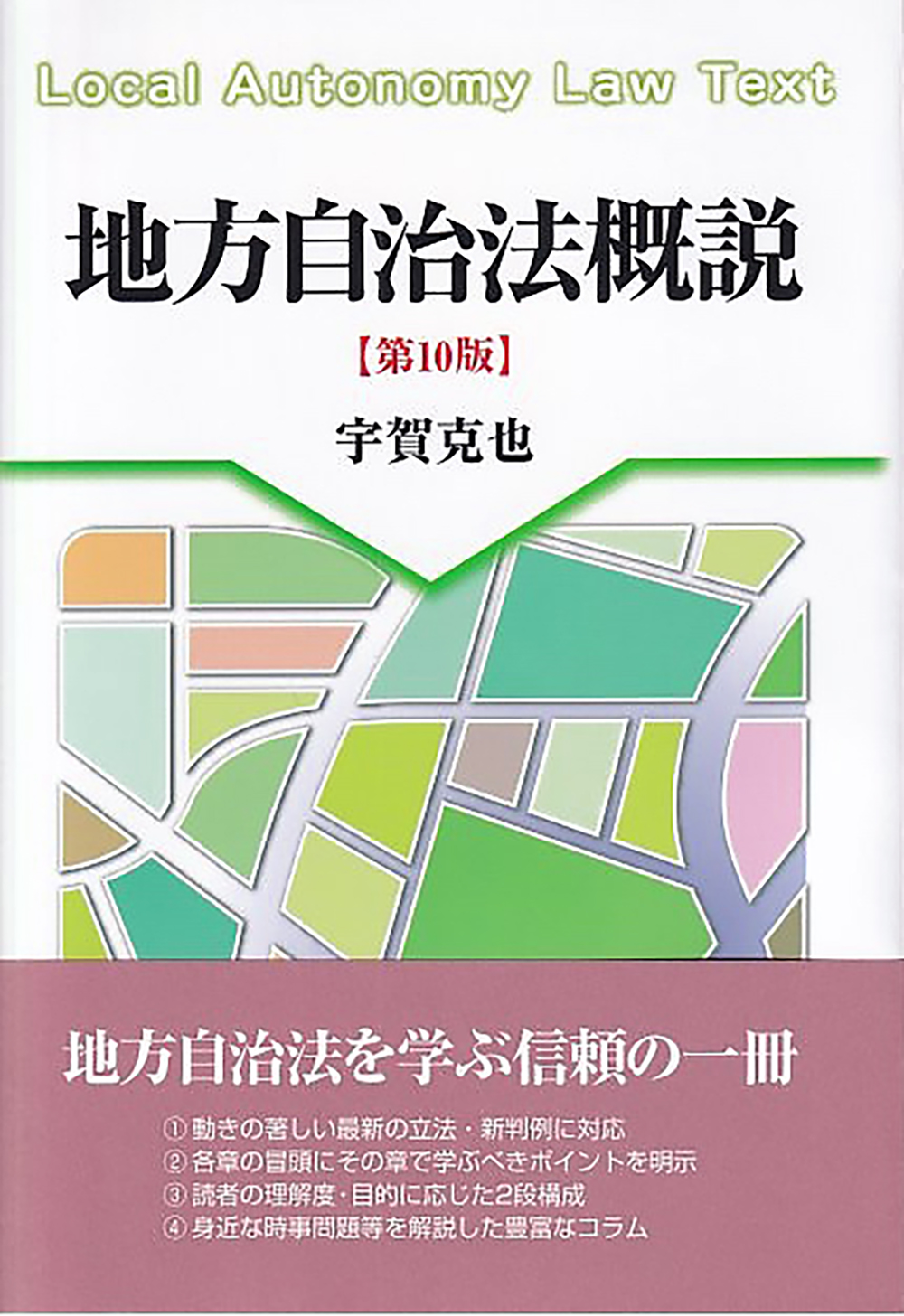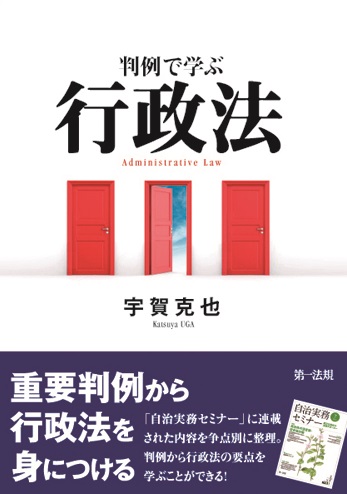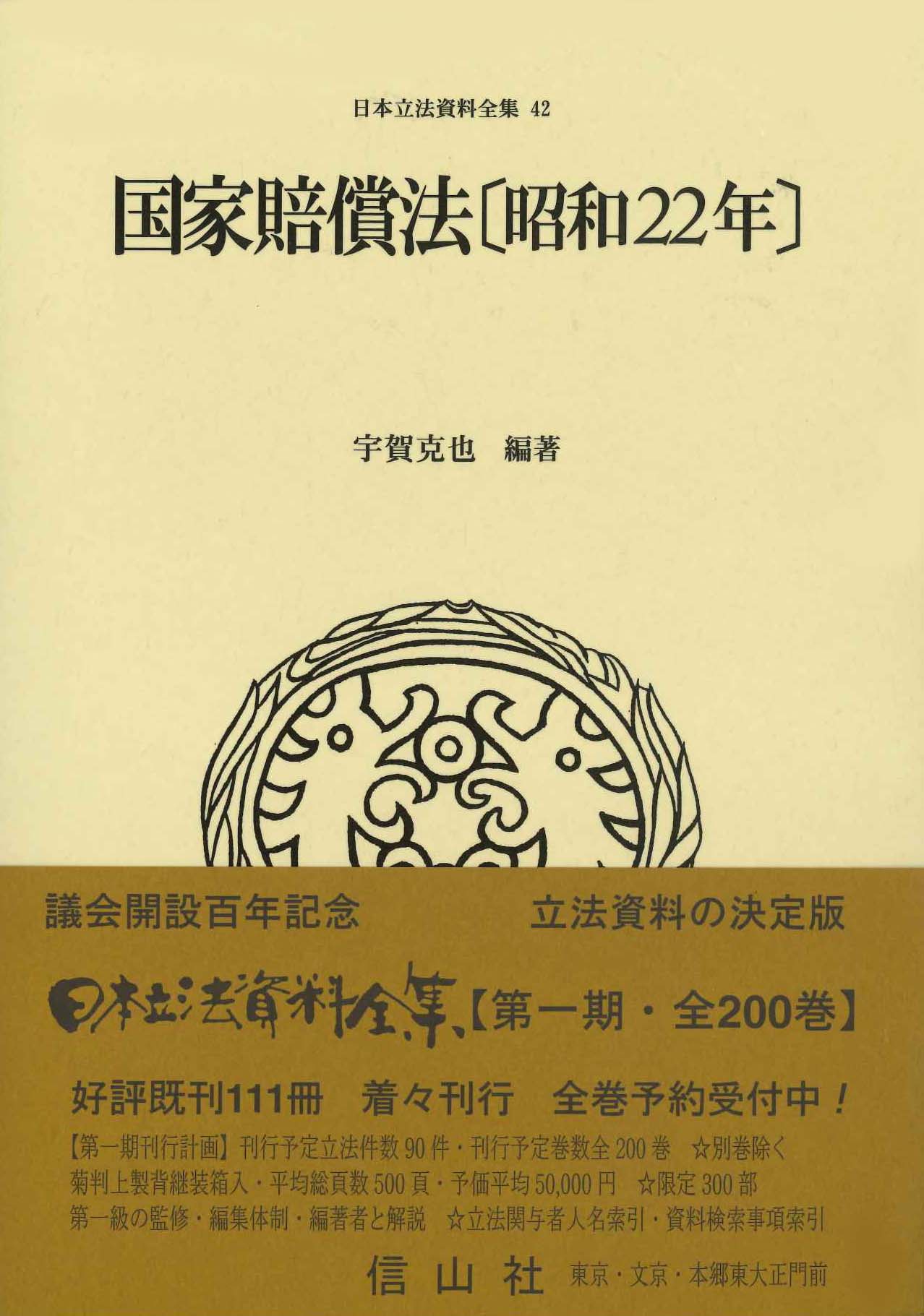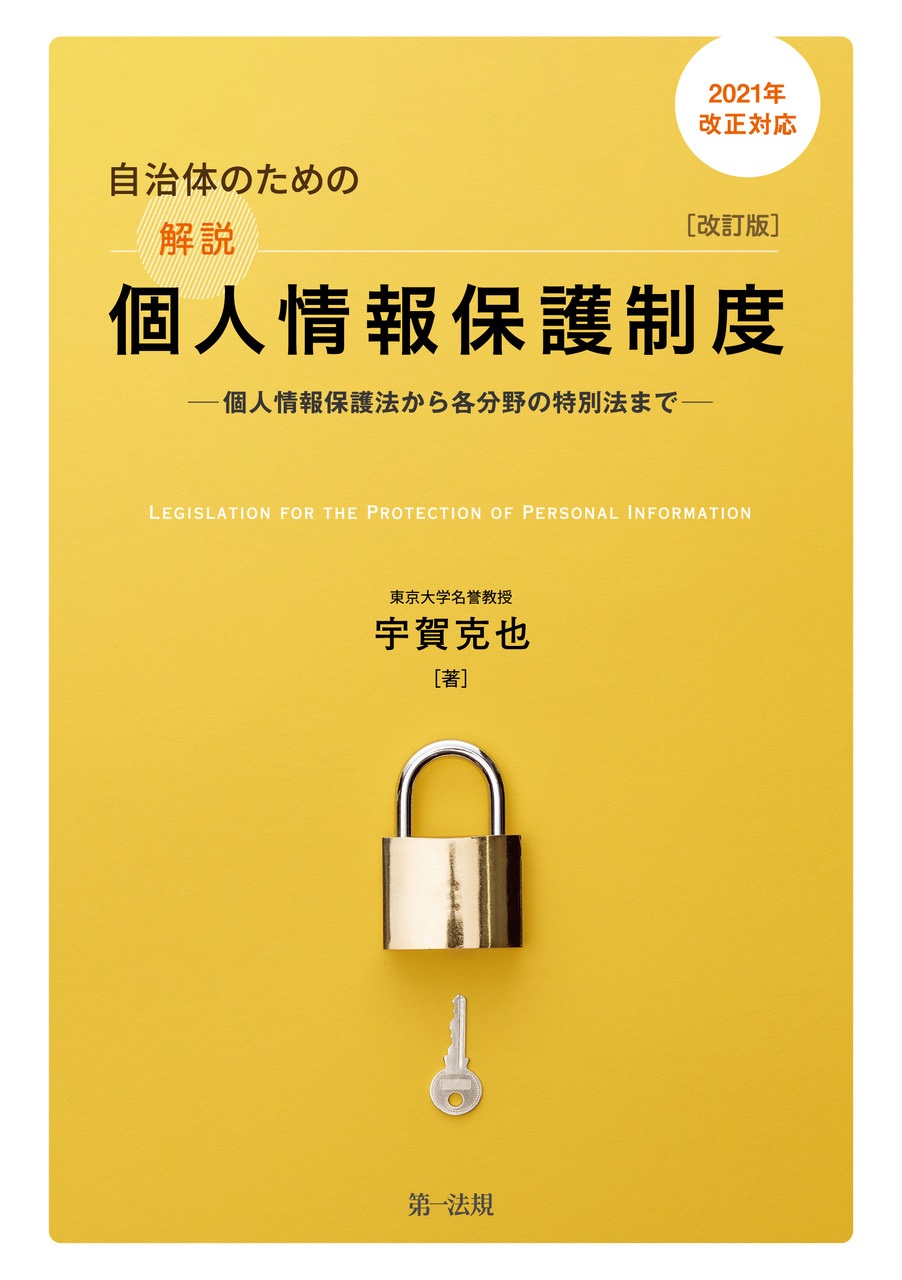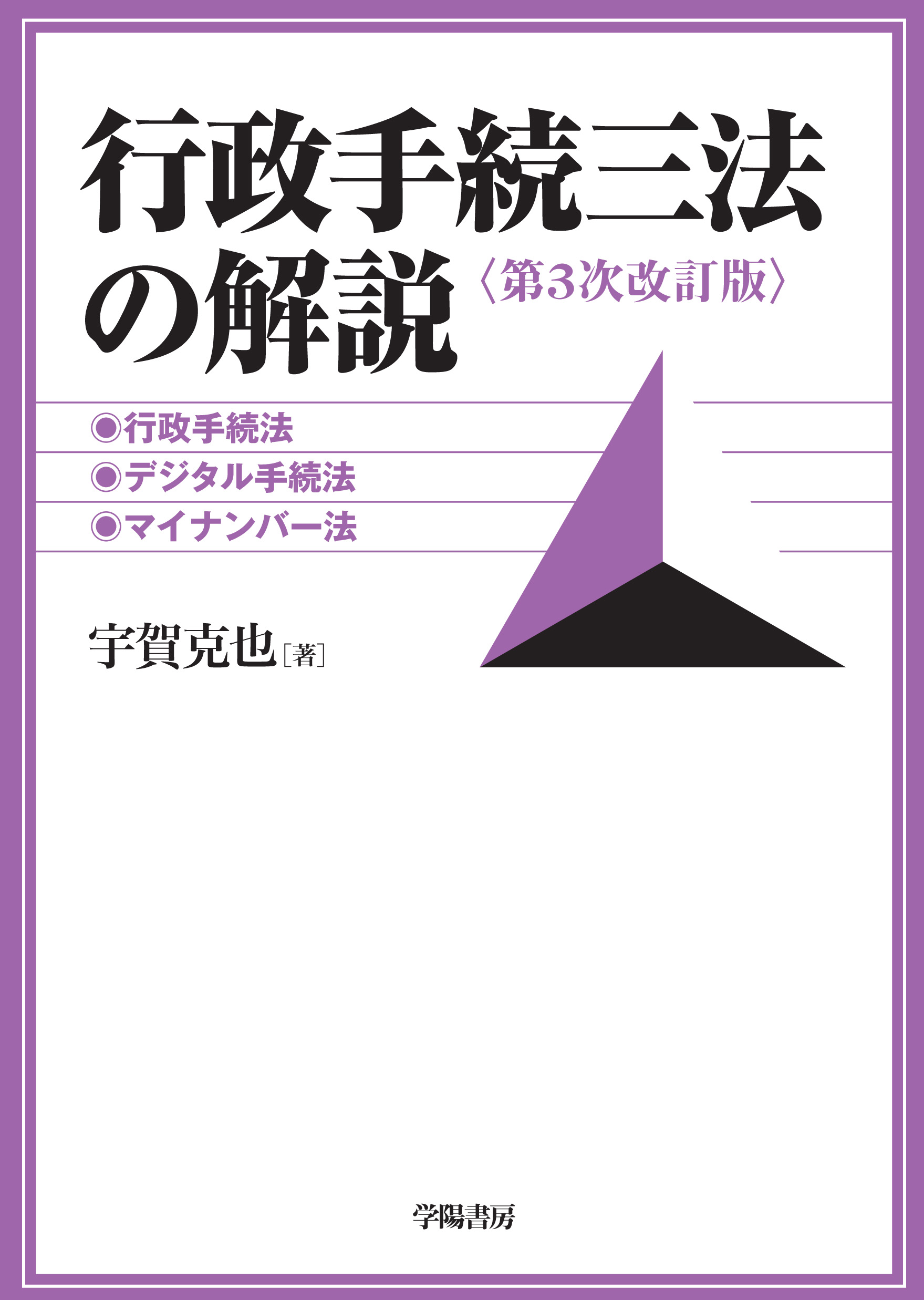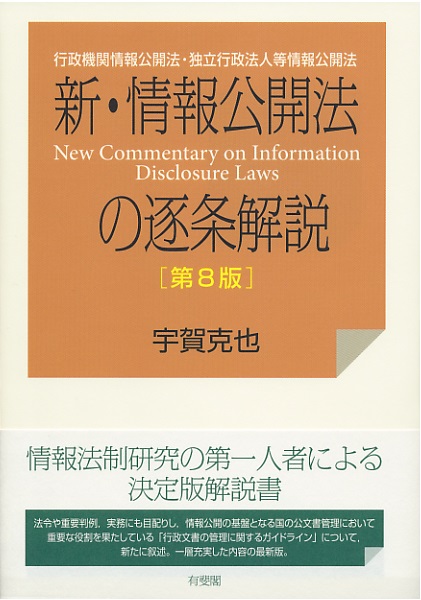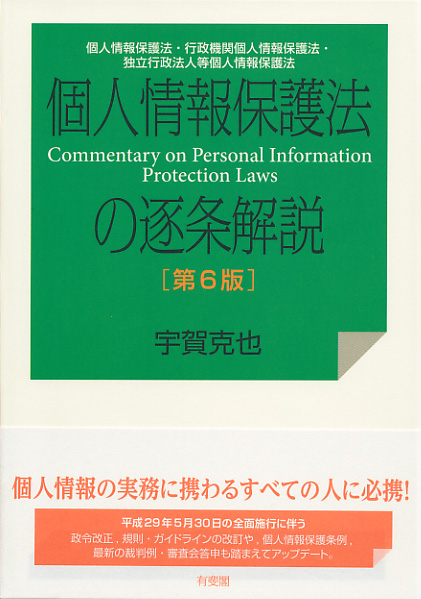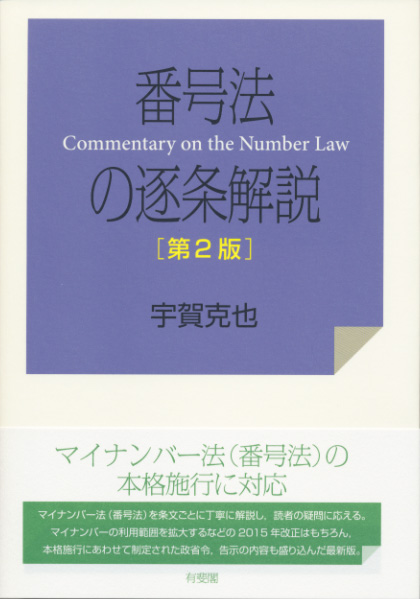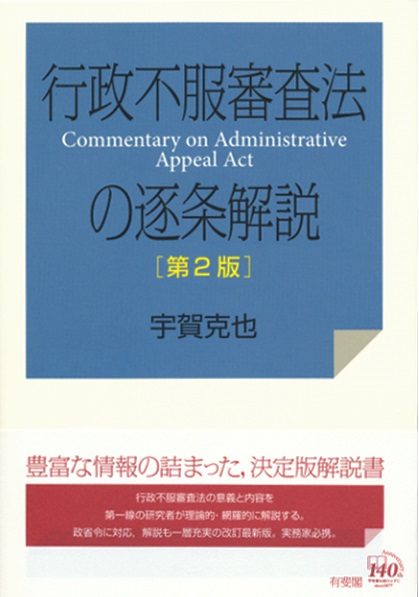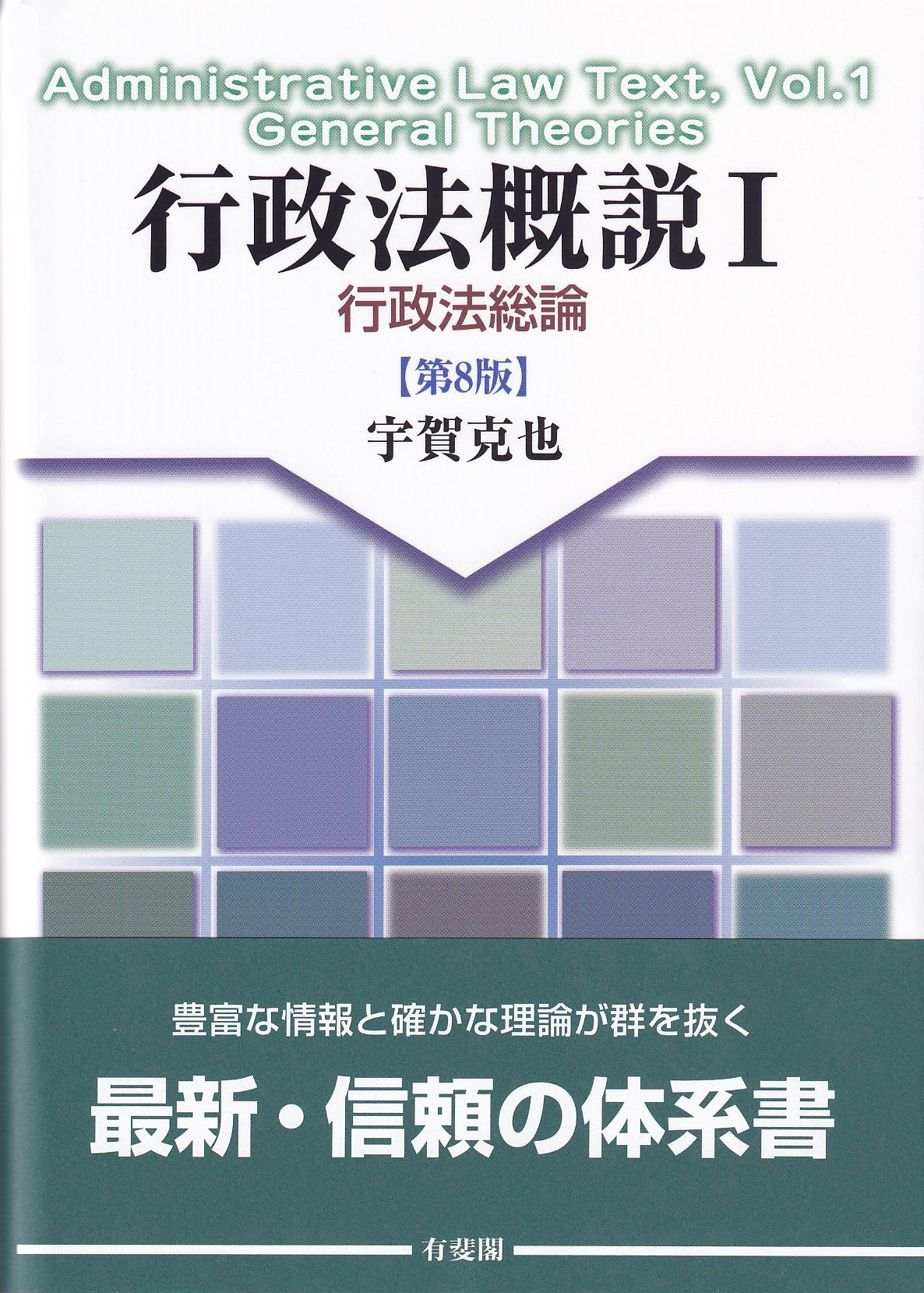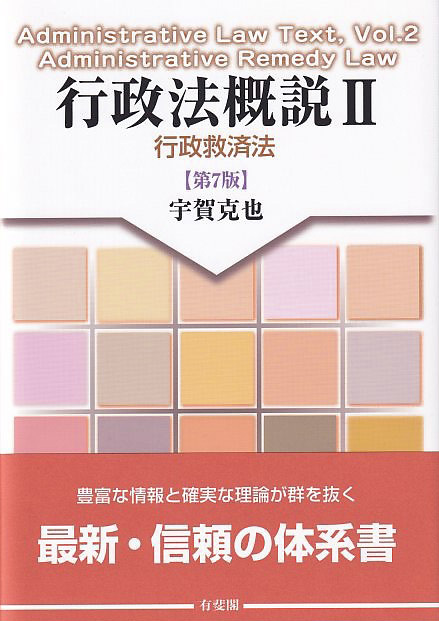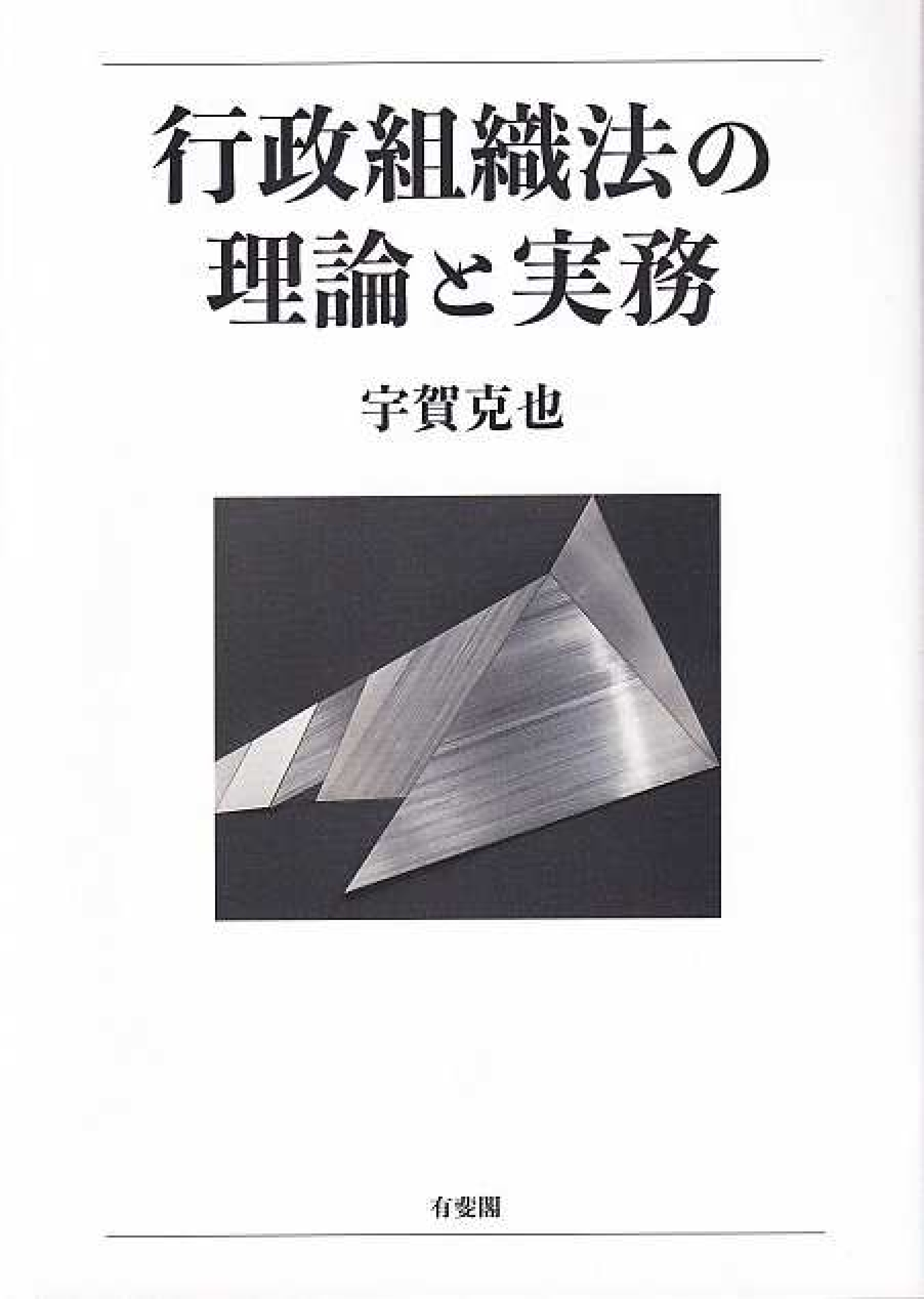
書籍名
行政組織法の理論と実務
判型など
404ページ、A5判、上製カバー付
言語
日本語、英語
発行年月日
2021年2月
ISBN コード
978-4-641-22799-6
出版社
有斐閣
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
行政組織法は、直接に国民の権利義務と関わらないことが多いため、一般的に関心が稀薄になりがちである。しかし、行政組織の在り方は、国民の権利義務に大きな影響を与えるのであり、行政法の重要な研究課題である。本書では、1998年に制定された中央省庁等改革基本法が、単なる省庁再編成にとどまるものではなく、行政改革基本法と称しうるものであり、行政組織法上、さらには行政法全体にとっても重要な論点を多数含むものであるため、その検討を最初に行っている。本書の大きな特色は、それまで、ほとんど研究の蓄積のなかったアメリカの政府関係法人について、その歴史的展開を含めて、詳細に分析し、わが国の特殊法人・独立行政法人との比較考察を行った点にある。そして、わが国では、特殊法人・独立行政法人は、行政の事務・事業のアウトソーシングによる行政のスリム化を目的として行われることが少なくないが、アメリカでは、法人化自体は、直ちにアウトソーシングと考えられているわけではなく、省の一部と位置付けられ、一般の行政機関と同じ規制を受けることが稀でないことを明らかにした。また、わが国では、行政機関に適用される予算・人事上の規制を外す手段として法人化が検討されることが稀でないが、アメリカでは、Performance Based Organizationやウェーバーという法人化を伴わない規制緩和の仕組みが導入されていることを明らかにし、わが国でも、重要なのは不合理な規制の緩和であって、法人化それ自体が目標とされるべきではないことを指摘している。本書では、ある省庁を設置するためには、それと同格の別の省庁を廃止するというスクラップ・アンド・ビルド原則によらずに、新たな庁が設置された稀有な例として、消費者庁と環境庁について、詳細な検討を行っている。消費者庁については、消費者の被害に関する情報の消費者庁による一元的な集約体制の確立と当該情報に基づく的確な法執行の確保を可能にすることを企図している点、縦割り行政の規制権限のすき間に落ちてしまい、規制ができない「すき間」事案に対処する立法を行った点等で、重要な意義を有することを指摘している。さらに、本書では、わが国の重要な事故調査機関である消費者安全調査委員会と運輸安全委員会についても検討を行い、調査・審議の公正中立性の確保、情報公開、行政調査と犯罪捜査の関係等について論じている。また、金融再生委員会について検討し、国務大臣が委員長となる大臣委員会の中に、国家公安委員会のように委員長が可否同数の場合の裁定権のみを有するものと、金融再生委員会のように、委員長が表決権も有するものがあることを初めて明らかにした。さらに、電気通信事業を例にして、基準認証制度と指定検査機関についての分析を行うともに、スクラップ・アンド・ビルド原則によらずに設置された特定個人情報保護委員会についても検討している。
(紹介文執筆者: 法学政治学研究科・法学部 名誉教授 宇賀 克也 / 2021)
本の目次
第2章 アメリカにおける政府関係法人の歴史的展開
第3章 アメリカの政府関係法人の法的考察
第4章 特殊法人と独立行政法人―アメリカの政府関係法人との比較考察
第5章 基準認証制度と指定検査機関
第6章 消費者庁関連3法の行政法上の意義と課題
第7章 地方消費者行政
第8章 消費者庁「事故調査機関の在り方に関する検討会」取りまとめ
第9章 消費者安全調査委員会
第10章 特定個人情報保護委員会
第11章 運輸安全委員会の現状と課題
第12章 金融再生委員会
第13章 日本の環境庁―その歴史と現在の課題
第14章 行政委員会
補論 書評三篇



 書籍検索
書籍検索


 eBook
eBook